( 前頁 / TOP ) web拍手
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 3章 interval 〜 渡来人 〜
( 前頁 / TOP )
道路から放たれた夏の熱気が、空気をじりじり焼いていた。道の向こうで陽炎が揺れる。タイヤの行き交うアスファルト、その上に引かれた横断歩道の白線が、正午過ぎの強い日差しを弾いている。
日比谷の交差点に立っていた。八車線の自動車道路を車が何台も行き過ぎる。タクシー、トラック、乗用車──。
赤信号の横断歩道。うだるような炎天下、歩道を歩く人影も疎らだ。こんな真夏の炎天下に、何故こんな所にいるのかといえば、遠野に呼び出されたからだった。夏休みも残すところあと数日となった今、つまるところ俺達は、提出課題を片付けるべく都内の図書館に出向いたのだ。この腐れ縁の友人遠野は面倒見が良く、成績も良い。道場の倅のこちらとは性格も成績も正反対だが、なんとはなしに気が合った。だが、暑い最中に渋々出向いてみたものの、目当ての図書館は休館していた。というより昨年からずっと改修工事中、開館予定は来年春──。とんだ徒労だ。
抜け目ない遠野にしては珍しいポカに、しばし二人して呆然とする。だが、このくそ暑い中、別の図書館を調べてまで移動しようという気には到底なれない。それなら映画でも見に行くか、と話はすぐにまとまった。だが、有楽町方面に出ようとしたところで、遠野が知り合いに出くわした。なら、お開きにするか、ということで引き上げることになったのだ。
公園の木陰を探して歩き、照り返しのきつい舗道に出る。木陰から炎天下に踏み出した途端、ひどい眩暈に襲われた。思わず太陽を振り仰ぎ、目が眩んで目を逸らす。目を焼かれて視界が奪われ、目頭を押さえた。信号待ちをしているのは自分だけ、他には誰の姿もない。続く不運に辟易しながら、向かいの信号に目をやった。
誰もいない横断歩道に、いつの間にか猫がいた。普通の大きさの白い猫。いや、白じゃない、銀色だ。滑らかに動く猫の毛並みが日差しを浴びて輝いている。車の流れは信号待ちで途切れていた。銀の猫は悠然と向こうの舗道へ歩いて行く。華奢な前脚をおもむろに止め、毛並みの肩越しに振り向いた。
猫はじっと凝視した。誘うような赤褐色の獣の瞳。何かを訴えかけるように。車が来ないからいいようなものの、道路の真ん中で停まっていたら、いつ轢かれるかと気が気じゃない。特別猫好きではないのだが、目の前で車に轢かれたりしたら、それはさすがに後味が悪い。右手交差点の左折車線では、車が数台停まっていた。信号が変われば、すぐにもやって来るだろう。車の途切れた道路の左右を見回して内心はらはらしていると、銀の猫は、ふい、と素気なく向こうを向いた。銀の尻尾をぴんと立て、再び悠然と歩き出す。暑さなどものともしない至極しなやかな足取りで。焼けるように熱いアスファルトの路面を、猫はどこへ行くのだろう──。
額の汗を腕で拭い、晴れ渡った空を恨みがましく仰ぐ。何とはなしに見返して、その光景に目を瞠った。
視界左から、波が穏やかに打ち寄せていた。どこかの浜辺の風景だ。無人の浜辺には日差しが照りつけ、水を含んだ柔らかな砂には足跡が点々とついている。猫は砂浜を歩いていた。だが、交差点の風景も依然としてそこにある。世界が二重写しになっている──。
目を擦って見直した。猫と砂浜は消えていた。何の変哲もない昼の交差点の風景が、目の前に気怠く広がっている。信号待ちの右手の車が交差点を左折して、何事もなく通り過ぎた。それに続いて何台も何台も。異変に気付いた。行き過ぎる輪郭がぶれている。走り去る残像が少し遅れて実体に追いつく。時間が微かにずれている──?
蝉声が耳に飛び込んだ。道の雑踏が耳に戻って、ふっと唐突に引き戻された。信号が青に変わっている。慌てて踏み出し、ためらった。何もない空間から暴走トラックが突如現れ、轟音を上げて通過するのではないか。今正に別世界を疾駆するそれに撥ね飛ばされてしまうのではないか──。
首を振って、奇妙な幻想を振り払った。途方もない妄想だ。そんな馬鹿げたことがある筈もない。息を吐いて歩道に踏み出す。足元の砂が微かに動いた。何故、アスファルトの上に砂がある? 一瞬違和感が掠めたが、特別気にも留めなかった。今にして思えば、それは警告だったかも知れない。五感が異変を察知して、必死で引き戻そうとした。ソッチニ、イッテハ、
──イケナイ。
何かに激しくぶつかった。いや、まともに弾き飛ばされた。見えない壁があったのだ。
轢かれた、と思った。暴走するトラックに。
潮の香りが微かにした。生臭い匂いも混じっている。
目を開けると、見知らぬ天井が視界に入った。田舎のじいちゃんの家にあるような木造の古そうな天井だ。どうやら自分は横になり、天井を見上げているようだ。
寝たまま視線を巡らせると、薄暗く狭い小屋だった。静かだ。誰もいない。風雨に曝された汚れた硝子が斜光を鈍く弾いている。絶え間なく聞こえる波の音。湿気を帯びた海辺の空気。畳敷きの閑散とした部屋──。混乱した。一体ここはどこなのだ。何故こんな所にいる。今の今まで日比谷の交差点にいた筈だ。
「……猫」
ひょい、と猫が戸口から顔を覗かせた。長い尻尾をピンと立て、じっと顔を見つめつつ、そろりそろりと壁伝いに入ってくる。ふと、交差点で見た銀の猫を思い出した。もしやと思い凝視したが、同じ猫かどうかは分からない。猫の毛皮は銀色には見えなかった。白い猫だ。それは窓の下で丸くなった。
のろのろ体を引き起こし、唖然と部屋を見回した。八畳ほどの和室だった。色褪せた土壁に木枠の時計がかけてある。生活感はあるものの、殺風景なほどに物がない。テレビさえ見当たらない。古そうな箪笥と使い込んだちゃぶ台、全体的に一昔前の古民家のような感じだ。上がり框の向こうは土間で、薄暗い中、祭の時に履くような薄い草履が端に寄せて置いてある。ふと気付いて確認すると、携帯の表示は圏外だった。
窓辺の猫が顔を上げた。それからすぐに足音がして、男が日に焼けた顔を覗かせる。顎ひげのある中年の男だ。短い髪でどことなく厳しい顔つき。やはり祭の時期なのか、筋肉質な痩せた体に青っぽい着物を羽織っている。どうやら、ここの住人らしく、どれどれ、というような無造作な足取りで、畳の室内に上がりこんでくる。
見知らぬ男は布団の横まで歩いてくると、着物の裾を無造作に割って、畳の上にあぐらをかいた。猫がおもむろに立ち上がり、男の元へと寄っていく。猫に顔をすり寄せられて、男はあぐらの膝に抱き上げた。猫の頭をぞんざいに撫でてやり、その目を返して気遣わしげに覗き込む。
「おう。気分はどうだ、兄ちゃん」
混乱しつつも、事情を一通り説明した。日比谷の交差点に立っていたこと。自分は都内の高校生で、今日は図書館に行こうとしたが、改修工事で館内に入れず、やむなくJRの駅に向かったこと──。男は猫の頭を撫でながら、口を挟まず聞いている。
奇妙に思った。地名がまるで通じない。"JR"も通じない。"高校生"さえ何のことやら判らないらしい。説明すればするほどに焦燥と混乱は深まった。一体何がどうなっている。何故、彼は知らないのだ。サッカーW杯では、日本はオランダに負けた筈だ。
ふと、違和感を覚えた。自分と同様、髪も目も黒いが、目の前の男はどこかが決定的に日本人ではない。日本人と、似た外見のアジア人とでは、何かが明らかに異なるように。それは内面から滲み出るものだった。"質"だとか"雰囲気"だとか、そういった類いの。
"異国"の二文字が脳裏を過ぎった。だが、言葉は確かに通じていた。男が話したのは日本語だ。文字も判かる。少なくとも壁の時計は不自由なく読めていた。文字盤に刻まれた12までの算用数字──。
懐手にして、じっと話を聞いていた男が、溜息混じりに身じろいだ。そいつは困ったな、などとどこか飄然と頭を掻く。思案するように眺めているが、やはり理解はできないようで半信半疑といった顔。だが、長く考えるでもなく、膝を叩いて立ち上がった。
「わかった。しばらく面倒みてやる」
男の小屋は町外れの、浜辺から少し入った林の中に建っていた。ここは漁港であるようだ。他国の荷も着くようで、町外れの桟橋には大型船舶も泊まっている。そして、町を貫く大通りを中心に、のどかな田舎町が広がっていた。ビルやマンションのような巨大建造物は一つもなく、大通りを中心として戸建ての民家が連なっている。バイクも車もコンビニもない。テレビも電話もレンジもない。
電柱のない町の通りはアスファルトではなく石畳で、連なる家々の白壁が日差しを明るく弾いている。なにか外国の観光地のような風景だった。こぢんまりとはしているが、それなりに栄えているようで、小綺麗に整った街並みだ。白壁が連なる建物群と青い海とのコントラストがエーゲ海辺りの島の風景を彷彿とさせる。
町の大通りには商店が連なり、看板があり、路地があり、酒場がある。人々の服装にも変わったところは取り立ててない。シャツにズボン、革靴、サンダル、日傘に帽子。
無我夢中で日々を過ごした。帰郷を渇望していたが、帰る術は見つからなかった。そうして一年が過ぎ、二年が過ぎ、三年が経ったところで諦めた。
男の職業は漁師だった。年の頃は三十過ぎで、妻子はいないようだった。自船を持ち、酒を呑み、いつも誰かしらが訪ねてくる。仕事が引ければ、賭場に出向いて博打を打つ。何も持たない居候に、男は生きる術として漁の技術を叩き込んだ。
毎日のように船を出し、陽に焼かれ、潮風に吹かれて釣り糸を垂らした。町に出て釣果を売り、食料を買い、酒を買った。新しい着物を買い、賭博をし、女を買った。この異国の通貨にも、いつの間にか慣れていた。
飯屋の窓向こうの大通りでは、薄灰色の石畳が日差しを眩しく弾いている。普段と変わらぬ昼下がり。あの日とよく似た夏の午後。通りを行き交う雑踏に、自分とよく似た背が歩いて行くのを見た気がする。
「……遠野?」
息を呑んで後を追いかけ、だが、すぐに足を止めた。そんな事がある筈もない。
あれから十年が経っていた。あの頃の姿のまま、遠野が高校生の姿形をしている筈がそもそもなかった。もっとも、現に自分が居る以上、自分と同じ渡来人がどこかにいたとしても不思議はない。帰郷の手がかりを探すべく商都カレリアへ出向いた折りに、奇妙なものを見つけていた。子供向きの絵本
『 ヘンゼルとグレーテル 』 著者は不明。
文化が明らかに流入していた。この自分とは又別の渡来人の存在を、それは明確に示唆していた。誰もが知る著名な童話をこちらに伝えた者がいる。
一部地方での畳や着物の定着は、そうした文化を持つ者がかつて渡来した事を示していた。日本語の使用については、かなり早い段階で何者かが紛れ込んだ事を示している。もっとも、どこかにいるであろう同胞を、夥しい人間の海から見出す事は不可能に近い。箪笥にしまい込んだままの携帯は、不思議なことに切れなかった。充電せぬまま長い歳月が過ぎたというのに。
助けられた際に名を訊かれ、有野恭平と名乗ったが、万事につけ大雑把な男の耳は、動揺でもつれた発音を「アルノ」と聞きとったようだった。男は名をオーサーといった。
*2010.08.08 第2部3章 了
![]()
( 前頁 / TOP )
web拍手
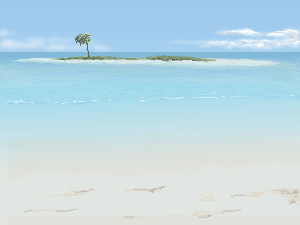
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》