☆ web拍手を送る ☆
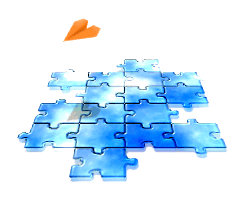
( TOP に戻る )
当作品は、下記ランキング に参加しております。 .
お気に召して頂けましたら、下記のリンクをクリックして、ご投票下さい。
地 平 の 果 て
ぼくはただ単純に、見てみたかっただけなんだ。キラキラ光る地平の果てを。
計画を打ち明けたケンちゃんは、変なのー、と馬鹿にして笑った。地平の果てなんて、あるわけないよ。だって、地球は丸いんだから。
ずっとまっすぐ歩いて行ったら、おんなじ場所に戻っちゃうんだよ。だって、地球は丸いんだから。
それでも、ぼくは見たかったんだ。そこがどんなふうに、なっているのか。どんな光で満ちているのか。
だから、ある晩、決行した。
用意は万端。前の晩までに色々揃えて、ナップザックには、おやつも入れた。
そうして、ぼくは家を出た。
ぼくは歩いた。ずんずん歩いた。
町角を二つ、曲がったところで、買い物かごを片手に下げたケンちゃんの所のおばちゃんに会った。
「あら、どこへ行くの?」
にっこり顔を覗き込むから、胸を張って、ぼくは答えた。
「ぼく、地平の果てを探しに行くんだ!」
すぐに家に連れ戻された。
大人はもう信用しない。
ケンちゃんの所のおばちゃんは、すぐに母さんに言いつけた。
お陰で、ぼくは母さんに、あれから、こっぴどく叱られたのだ。
だから、二度目の計画は慎重に立てた。
用意は万端。前の晩までに色々揃えて、ナップザックには、おやつも入れた。
そうして、ぼくは家を出た。
ぼくは歩いた。ずんずん歩いた。もちろん誰にも、絶対内緒で。
誰にも会わないように気をつけて、町角だって素早く曲がる。
町の眺めは、行けども行けども変わらない。家と、塀と、電信柱と。
「どこへ行くんだい、ぼうや」
ぼくは口をつぐんで振り返る。
抵抗しても無駄だった。よく見る制服のおじさんは、ぼくの町のおまわりさんだった。
交番の場所は、チェックした。
昼間はダメだ。誰かに会うから。
ぼくの町のおまわりさんは、すぐに母さんに言いつけた。
お陰で、ぼくは母さんに、あれからこっぴどく叱られたのだ。
だから、三度目の計画は慎重に立てた。
用意は万端。前の晩までに色々揃えて、ナップザックには、おやつも入れた。
そうして、ぼくは家を出た。みんなが眠った部屋の窓から。
ぼくは歩いた。ずんずん歩いた。もちろん誰にも、絶対内緒で。
誰にも会わないように気をつけて、町角だって素早く曲がる。交番だって、きちんと避ける。
二度目の時には、家と塀と電信柱がどこまでもどこまでも続くばかりで、道の先には何もなかった。
だから、今度はそっちと逆の、北の方向へ歩いているのだ。
しばらく歩くと、駅に出た。お年玉を持ってきたから、電車の切符はきちんと買えた。
ホームに出てから一番最初の赤い電車に飛び乗った。
途中で連れ戻されたりしないよう、大きな駅に着く度に、何度も電車を乗り換える。
遠く、遠く、どこまでも遠く。
線路の終点、地平の果てまで。
駅から出ると、紺色の夜空に星がきらきら瞬いていた。その下に真っ黒な山並みが津波みたいに広がっている。
誰もいないその駅は、黒く連なる山々と、広い田んぼに囲まれていた。空は、すっかり真っ暗だった。銀の星しか見えなくて、さすがにちょっと困ったけれど、後戻りは出来なかった。ここが終点、乗って来たのは終電だから。
駅の前は狭い広場になっていた。地面はレンガやコンクリじゃなくて、デコボコした土のまんまだ。改札の右側に、小さいメガホンみたいな傘のついた裸電球が立っていて、狭い駅前広場をちろちろ薄暗く照らしている。
駅前なのに暗かった。誰もいないし、駅ビルも、バス乗り場も、キヨスクもない。お店はみんな閉まってる。三軒だけしかないけれど。
右端のお店は、古い雨戸が締まっている。市営プールに置いてあるみたいな横長の古いベンチが置きっ放しになっているから、お土産屋さんなのかも知れない。隣に赤いポストがあって、その隣の、駅から出てまん前には、ガラス戸が締まった真っ暗な食堂。その隣のぼろっちいお店は何屋さんなんだか分からない。ぼくの田舎のおじいちゃんちみたいに、端っこが茶色く錆びた看板が斜めになってかかっているから、トイレットペーパーとかお米とかを売っている何でも屋さんなのかも知れない。その何でも屋さんの隣から、道が一本伸びていた。
ポケットからキャラメルを出して、誰もいない改札を出た。キャラメルを口に放り込み、月に照らされたジャリ道に向かう。
無人の寂しい駅を出て、ぼくは一人で歩いて行く。まっすぐまっすぐ歩いて行った。地平の果てへ行くのだから、途中で曲がっちゃいけないのだ。
田んぼの中の一本道には、駅にあったメガホンみたいな薄暗い電灯が、遠くぽつぽつ灯されていた。カエルがゲコゲコ鳴いている。道にもやっぱり、だあれもいない。
少し歩くと、古そうな家がぽつりぽつりと現れた。どの家にも庭がある。
「……どうしよう」
ぼくは困って立ち止まった。右の家の玄関横に、赤い屋根の犬小屋発見。でっかい犬がこっちを向いてうつ伏せている。寝ているみたいだ。ケンちゃんとこのと同じレトリバー。吠えると、ものすごく恐いんだ。
地面にそおっと両手をついた。横目で見ながら四つん這いで進む。できる限り遠回りして、地面の端っこをジリジリ進む。時間をかけて真ん前まで来た。あと、もうちょっとだ──。
犬がでっかいあくびをした。びくっとして動きを止める。犬はでっかい口を閉じ、揃えた前足に頭を載せた。ぐーすか眠り込んでいる。ぼくはそろそろ、そのまま前進。
「……ふー。やれやれ」
静かな犬小屋を振り向いて、ぼくはおでこの汗を拭く。ピンチはなんとか乗り切った。その先の家には犬小屋はない。
キャラメルを舐めながら、ずんずん進む。順調順調。道には、やっぱり、だあれもいない。
「……どうしよう」
ぼくは困って立ち止まった。道の前方に川を発見。そんなに大きくないけれど、橋はどこにもかかってない。
月の光に川面が光る。水はさらさら流れている。水は透明、流れはあんまり速くない。浅い水底に緑の小石がはっきり見えた。きっと足首くらいの深さだろう。ぼくは運動靴と靴下を脱いだ。
「……ふー。やれやれ」
静かに流れる光る川を振り向いて、ぼくはおでこの汗を拭く。ピンチはなんとか乗り切った。持ってきたタオルで足をふき、靴下をはいて運動靴をはく。
キャラメルを舐めながら、ずんずん進む。順調順調。道には、やっぱり、だあれもいない。
「……どうしよう」
ぼくは困って立ち止まった。手の平を上にして、空を見る。ぽつん、ぽつん、と手が濡れた。頭も、頬っぺも、洋服も。きらきらしていた星々が、いつの間にか灰色の雲に隠れている。
雨がじゃんじゃん降ってきた。どうしよう、傘なんか持ってない。キョロキョロすると、ジャリ道の先に森がある。ぼくは全力疾走した。
「……ふー。やれやれ」
ぽつんぽつんと電灯が灯る雨に煙る道を振り向いて、ぼくはおでこの汗を拭く。ピンチはなんとか乗り切った。森の中なら、雨で濡れない。森の葉っぱがでっかい傘だ。
キャラメルを舐めながら、ずんずん進む。順調順調。道には、やっぱり、だあれもいない。
森の中は暗かった。地面に立ち込める白い霧が、生き物みたいに、ゆっくりゆっくり動いていく。きょろきょろしながら、ぼくは進む。
「──わっ!」
困る暇もなかった。あっと気づいた時には転がっていた。枯葉まみれになりながら、ぼくは坂道をごろごろ転がる。
どっしん、とすごい音がした。ぼくは、いてて、と起き上がる。
「……おやまあ」
ガラリ、と音がして見上げると、白髪のおばあさんが立っていた。
ぼくは、坂道の下にある、おばあさんの家にいた。
おばあさんは暖かいタオルで、ぼくの顔を拭いてくれた。すりむいた膝小僧にもバンソウコウを貼ってくれた。
とっても優しかったけど、大人は誰も信用出来ない。だから、ぼくは言わなかった。「どこに行くの」と聞かれても。「おうちの人に来てもらおう」と電話番号をきかれても、「いやだ」としぶとく頑張った。時計の針は十二時だ。おばあさんは困った顔でぼくを見ている。
「おなか、すいてないかい?」
ぼくのおなかが、ぐー、と鳴った。おなかのヤツ、正直だ。
おばあさんと二人で三分待って、はふはふ言いながらカップメンをすすった。おばあさんは一人暮らしみたいだ。食べ終わったカップを下げると、どこかに電話して戻ってきた。
「そしたら、明日になったら帰ろうな」
断固いやだと頑張ったけど、おばあさんはしわの手で、ぼくの頭をゆっくりなでて、大きなマグカップを持ってきた。温かいミルクを飲んでたら、急に眠たくなってきた。今日はずいぶん歩いたもんな……。
気がつくと暗かった。重たいフトンがかかっている。首を伸ばして、そおっと部屋を見回すと、おばあさんは隅っこで、こんもりフトンを被っている。
ぼくはこっそりフトンを出た。あったかい毛布が気持ちよくて、本当はもっと寝ていたかったけど、朝になったら、おまわりさんが来てしまう。
リュックを持って、忍び足で部屋を出た。薄暗い居間を、そおっと、そおっと横切って、コタツの上にキャラメルを一つ。おばあさんにお礼。横に開く玄関の扉を、音がしないようにぴったり閉める。
夜の空には星がピカピカ、雨はすっかりやんでいた。おばあさんの家を出て、ぼくはずんずん歩いていく。渓谷の高い吊り橋を渡り、白いスズランの丘を越え──。
森は、ひんやりしていて薄暗かった。曲がりくねった一本道だ。きらきらきらきら、月の光が葉っぱから零れる。森の風がざわざわ騒ぐ。ほーほー、と鳴く鳥の声。草の匂い、土や風の濃い匂い。
「……でっかい木」
きっと、お父さんの両手でも抱えられない。大きな木はシンとして、なんだか吸い込まれてしまいそう。生きてるみたいな大きなその木を、ビクビク横目で通り過ぎた。
森が深くなって、急に目の前が真っ暗になった。ぼくは手探りで歩いていく。地面がどこかも分からない。もしかしたら、さっきのあの木、ぼくの後ろで暴れてないか──?
ガサリ、とどこかで音がした。
目をつぶって、全力で駆けた。ぼくが後ろを向いた途端、大きな木々が目を開けたんだ。葉っぱの枝がニョキニョキ伸びて、ぼくの背中を捕まえようとするんだ。太い根っこで追いかけてくるんだ。そうしてきっと食べられる。そうだ! きっと、そうなんだ!
目の前が、急に明るくなった。
冷たい空気が吹き付けてくる。ぼくは目を開けて立ち止まった。
……やった。
夜明けを迎えるその場所は、ひっそりとして静かだった。ぼくの他には、だあれもいない。やった。ぼくはやったんだ。
潮の香りに包まれて、ぼくは満足して倒木に座った。ほーらね、ちゃあんと、あるじゃないか。ぼくが見たかった地平の果てが。
どこまでも続く暗い浜に、波が打ち寄せ、白く砕ける。繰り返し繰り返し、いつまでも。
広くて青い大海原が、朝焼けに染まって輝いていた。
気が付いて目を開ければ、真上に真っ白な天井があった。胸には毛布がかかっている。
黒いソファーで、ぼくは寝ていた。ガタンゴトン、と聞こえてくるのは、さんざん乗った電車の音?
青い制服の男の人が明るい窓辺で笑っていた。隣には、あの白髪のおばあさん。後ろ向きの女の人がペコペコ頭を下げている。どこかで見たことある服だ。
四角い机と、電話と湯飲みと時刻表。駅長さんの部屋だった。ゲッソリやつれた母さんが泣きべそ顔でそこにいた。
冒険は二度としなかった。
地平の果ては見つけたし、母さんがたくさん泣くからだ。ぼくはそんなに親不孝じゃない。
ぼくは、ゆっくり大人になった。
高校を出て、大学を出て、ぼくは社会人になっていた。
ぼくは消防士になりたかった。本当はずっと憧れていた。人を助ける仕事がしたかった。
両親は驚いて反対した。そういう仕事は危険だわ。そりゃあ、立派なお仕事だとは思うけど──。
ぼくは地元の公務員になった。母さんはとても喜んだ。ぼくはそんなに親不孝じゃない。来る日も来る日も、書類相手の仕事ばかりだ。
最近、よく考える。
今、ここに座っているのは、ぼくでなくてもいいんじゃないか? 別の誰かでもいいんじゃないか?
ぼくしか出来ない仕事なら、ぼくが自分ですればいい。
他の誰かが出来るなら、他の誰かがすればいい。
窓を開け放った春の宵、ビールを飲みながら考えた。
エリート商社マンのケンちゃんは「馬鹿な真似はよせ」と言う。
彼女のマユミも眉をひそめて「そんなの、もったいない」と言う。何がそんなに不満なの。上司の覚えもめでたくて、友達もいて将来も安泰。どうしても、って言うんなら、あたし考え直すわよ──。
机の上には白い封筒。筆ペンで書き上げた表書きは「辞表」
この頃、見たいものがある。
この頃、考えることがある。
真っ暗な夜空から目を戻し、机の辞表に目を戻す。向かいにあったタンスの鏡に、ぼくの顔が映っていた。ぼくは不敵に笑ってみる。
初めて家出を企てた頃の、七つのぼくが、そこにいた。
☆ web拍手を送る ☆
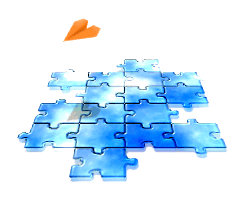
( TOP に戻る )
![]()
当作品は、下記ランキング に参加しております。 .
お気に召して頂けましたら、下記のリンクをクリックして、ご投票下さい。
![]() ネット小説ランキング に投票する .
ネット小説ランキング に投票する .
短編小説サイト 《 セカイのカタチ 》