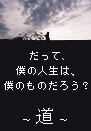僕の前に、道はない。
僕の後ろに、道はできる。
昔、そんなことを言ったのは、どこの詩人だったろう。
都会では、人の流れが道を作る。皆が進む方向へと、俺は流れに沿ってセカセカ歩く。人の行き交う混雑した道路。車の行き交う交差点。多くの者が進む方へと、俺も折れる。押し合いへし合い先を争うようにして、しばらく進むと、又、左右に道が現れる。当然だ。「時は金なり」をそのまま地でいく大都会。回りは全てライバルだ。他人に一歩でも先んじる為に、アクセスを重視する都会では、道は街中至る所に縦横無尽に張り巡らされているのだから。くたびれた革靴の下には陽に焼かれたアスファルト。陽炎がゆらゆら立ち昇っている。
昼時、高層ビルから吐き出された人の群れが、信号待ちで白線の前の歩道に溜まる。腕を持ち上げ、腕時計を見た。12時5分。周りは定食屋へと向かう"負け組"の群れ。しかし、いささかフライング気味だ。この連中は正午と同時にフロアを出て来た口だろう。高層階のエレベーター・ホールでは、一階へ向かうエレベーター待ちで混雑が始まっている頃合いだ。少しでも出遅れると、満員のエレベーターに目の前を何台も通過され、そうこうする内、人気の店には行列ができ、この暑い最中を長々と並ぶ羽目になる。第二波はそれを避け、だいたい12時半を回った頃に、冷房の利いたビルの中からブラブラと出て来る。
首尾良く地上に降り立ったダラけた人込みをやれやれと眺め、流れに紛れて歩きながら、俺は一人、駅へと向かう。昼休みを使って移動を終え、13:10 には先方に到着、13:30 から新企画のプレゼンを始めねばならない。昼飯は駅の立ち食い蕎麦屋で適当に済ませる。近年のリストラで就業人数が激減した今、食い物の選択で浮かれているような暇はない。裏を返せば、首を切られた奴の仕事は全て、居残った者達で分担して背負わねばならない。万事支障のないように。だが、全力を振り絞って十の仕事をこなしても、次には十二を要求され、それが達成出来れば今度は十五と、数値はどんどん吊り上がり、上からの要求は留まるところを知らない。
社運と生き残りを賭けた吸収合併の筈だった。だが、オフィスの雰囲気は重苦しく一変した。つい昨日まで商売敵だった輩と机を並べている、というのだから。どれほど笑顔で繕おうが、よそよそしさは拭えない。
目の前には、夏の陽に焼かれたアスファルトの道路。人込みの少し先には、くたびれたスーツの中年親父が額の汗を拭きながら、同僚と肩を叩き合って笑っている。商談が上手くいきでもしたのだろう。首から誇らしげに下げたIDカードは誰もが名を知る大商社のもの。顔は知らないが、同僚だ。だが、能力のある輩なら、とうに他社に移っている。こんな風通しの悪いギスギスした場所に未だ好き好んで留まっているような輩は、よほど愛社精神に溢れているか、そこにしか居場所のない奴だ。苦々しい思いで眺めるが、中年の親父は得意満面。あれでも本人にとっては順風満帆、上出来な部類の人生だろう。汗跡の浮き出たよれたワイシャツ、履き古した黒の革靴。俺より数年先を歩いている頭の禿げかけた中年親父、もうすぐ定年。数十年後の自分の後ろ姿を見るようだ。
「あれが俺の人生、か……」
毎日毎日こんな下らないことを繰り返して、俺は一生を終えるのか──。
信号待ちで晴れた空を仰いだ。キラリ、と何かが目を焼いた。首から下げたIDカード、そのプラチックが反射したのだ。オフィスは全館、入口でセキュリティ・チェックがかかっているから、これがないと締め出しを食らう。自分のフロアにさえ入れない。入館証を兼ねたIDカードは、俺が何者であるかを示してくれる軽くて確かな身の証。ポケットの中には会社から持たされたシンプルな携帯。いつでも連絡がつくように──。
息苦しさにネクタイを緩めた。肩で大きく息をつき、疲れた瞼を指の先で揉み解す。信号が青になった。今度は人の少ない方へと進んでみる。
ほっとした。人いきれから解放されて、人口密度が低くなり、肩が少しだけ軽くなる。足取りを緩めて、少しゆっくりと歩いた。
次の分かれ道も、その次も、俺は人の少ない方を選んだ。立ち止れば、たちまち小突かれる騒がしい雑踏、日常的な渋滞、吐き出される排気ガス、ひっきりなしのクラクション、交通整理の神経に障る鋭い警笛──。街の喧騒が遠ざかる。石のように凝っていた肩は進むにつれて軽くなり、引き摺るようだった足取りも、どんどんどんどん軽くなる。ああ、そうだ。何故、早くこうしなかったのだろう。自分の欲求に、素直に、忠実に。こんな生活、とうに嫌になっていた筈なのだ。

夏の夕暮れの気怠い風が、僕の頬を、ふわりと撫でた。首から下げたままになっていたIDカードにふと気付き、革の通勤鞄の中へとしまった。
路地を覆う生暖かい風は、やんわりと凪いでいた。この辺りは住宅地だ。店も、ネオンも、何もない。車も一台も通らない。隙なく犇いていた高層マンションでさえ、ここには一つも建っていない。あるのはただ、どこかで見たような暮れなずむ町の静かな光景。路地の右側には、灰色のブロック塀が道なりに連なり、左は二階建ての木造民家、何の変哲もない住宅地の光景だ。今しがた通り過ぎた小さな公園のシンプルな鉄柱の時計は、3時50分を指していた。
町角を曲がってきた子供が三人、僕の足元を通り過ぎた。赤と黒のランドセルを揺らし、楽しそうに笑いながら。
疲れを知らぬ小さなその背が、暮色に包まれた町の路地を駆けて行く。足を止め、振り向いた肩の向こうで、小突き合いながら、ブロック塀の町角を曲がって行った。学校が引けて家に帰るのだろう。彼らの体が半分透けたように見えたのは、立ち込め始めた蒼い帳のせいだろうか。薄闇立ち込める夕間暮れ、一日が終り、西に陽が傾くこの時刻、あらゆる境界が溶け出して世界の全てを曖昧にする。
目を前に戻して、歩き出した。
あの年頃の僕には、夢があった。僕は昆虫学者になりたかった。こんなサラリーマンになんか、なりたくなかった。毎日毎日ドブネズミ色のスーツを着て、朝から晩まで誰彼構わず媚を売り、恥も外聞もなく愛想笑いで頭を下げてペコペコペコペコ──。
だって、僕は、──僕の夢は、取引先にご機嫌伺いをしに行く事なんかじゃなかった筈だ。虫網を持って山中を駆け巡り、幻のヘラクレスをこの目で発見することだ。そう、誰よりも早く。なのに、人波に呑まれ背中を押されて歩く内、僕はいつしか僕自身を見失い、そして、今──。
ああ、僕は、いったい、いつの間に、自分の砦を明け渡してしまったのだろう。
じゃれ合う子らの無邪気なその背に、大切なものを思い出した気がした。それは長い間放置され、厚く埃を被って尚、輝きを失わぬ大切な宝。いや、捨てずに大切に守ってきたからこそ、内なる輝きを尚のこと増して。
そうだ。
僕の人生は、僕のものだろう?
他の誰のものでもない筈だ。親達のものでも、妻のものでも、ましてや部長のものなんかじゃない。毎晩、得意先を接待し、休みの日にまで会社に携帯で呼び出され日が暮れるまで休日出勤──うんざりだ。
それは忘れ果てていた"希望"だった。無味乾燥な時の流れに抗って、胸の内で一人密かに大切に温め続けていた僕自身。"それ"は魅惑的な光を放ち、以前にも増して黄金の輝きに満ちていた。
人影が少なくなるにつれ、通い慣れた道のような"懐かしさ"が増してきた。スーツの上着を脱いで腕にかけ、のんびり歩く。そう、僕も帰らなければならない。僕の "家" へ。
しばらく歩くと、晩飯の匂いが漂ってきた。どこの家だろう。コトコト煮付けた醤油の匂い。ブロック塀の庭先の向こう、開け放った縁側の向こうで、ステテコの背を向け畳に寝転がった主らしき男が、ビールを片手に野球の中継を眺めている。正方形の小さなテレビは、今時珍しい古い型だ。摘みは小皿に盛られた緑の枝豆。
僕は、道を辿る。
僕は、帰らなければならない。
向かいからやって来るセピア色にくすんだ時間が、軽やかに笑いさざめきながら、僕の背へと抜けていく。
チリン──と涼しげな音がした。
幾つもの風鈴をぶら下げた木造りの屋台が、夕陽に照らされた町角の向こうを左から右に横切って行く。辺りがこうも暗くなっては、今日はもう店仕舞いだろう。豆腐売りが物哀しいラッパを吹いて、人も疎らな夕暮れの町角を行き過ぎる。そうした景色の何れもが半分透けて見えるのは、この静かな夕間暮れのせいだろうか。
子供の頃から馴染みのブロック塀が延々と続いていた。木柱に括られた丸笠の電球、未舗装の路地、小石の転がる剥き出しの地面。道は、人生に似ている。そうだ。人生は"道"に似ている。
腕時計の針は 6時35分を指していた。習慣で時刻を確認し、我に返って苦笑いした。もう、どうでもいいことだ。
白ワイシャツを肘の辺りまで巻くり上げ、ふと足元を見た。無粋な黒い革靴だけが頑なに同化を拒んでいるようで、この懐かしい光景にそぐわない気がした。
歩みを止めることなく、僕は道を進む。浴衣(ゆかた)姿の女の子が二人、キャッキャと笑い戯れながら、向かいの道を横切った。高校生くらいだろうか。二人とも白い団扇で風を送り、一人が手に下げているのはビニール袋に入った橙(だいだい)色の一匹の琉金。ビニールの小さな水槽の中、長い尾ビレが、鮮やかな橙の衣が優雅に舞う。
風流なことだと見ていると、高く緩やかな笛の音が聞こえてきた。和太鼓の音が遠くから聞こえる。傍らの提灯がパッと点いた。それを合図とするかのように、頭上に吊るされた通りの提灯が、次々瞬く間に灯っていく。薄黄色の光の筋が道の両側を一直線に──いや、町中、縦横に延びていく。
「……なんだ? 注連縄(しめなわ)? この辺りは祭なのか」
薄暗くなって大分見分け難くなってはいたが、家々の前に白い紙垂(しで)の付いた縄が張り巡らされていた。そういえば、あれは、神域と外界とを隔てる結界のようなものなのだと、祖母から昔聞いたような覚えがある。
風があるのか、紙垂(しで)が揺れる。物悲しい調べの祭囃子が聞こえてくる。
道の端から、何かがひょっこり踊り出た。背を丸めた頬被りの男だ。とぼけた顔のひょっとこ面。黒々と書かれた「祭」の一文字を青半纏の背に背負い、白い股引、足袋姿。天に上げた両手をくねらせ、奇妙な足取りで練り歩きながら横切って行く。その後に、白地にトンボ柄の浴衣の男が下駄を鳴らしてブラブラ続いた。奇妙な奴だ。顔に狐の面を付けている。シゲシゲそれを眺めていると、ふと足を止め、振り向いた。小首を傾げた白い狐面の中、口角の上がった赤い口が鮮やかで、いやに目を引く。何故か嘲笑っているように思えて、不思議な気がした。
お囃子が遠く聞こえる。
陽は完全に落ち沈み、辺りは闇に包まれていた。今いる場所はうら寂しい路地だ。随分遠くまで来てしまった気がして、なんとはなしに後ろの闇を振り返り、なんとはなしに腕時計に目をやる。針は7時40分を指していた。そろそろ引き返した方が良いだろうか。
僕は一人ぼっちになっていた。僕が歩くこの道には、随分前から誰もいない。人通りの少ない方をわざわざ選んできたのだから、当然といえば当然なのだが、こうまで誰もいなくなってしまうと、なんだか少し──いや、
誰か、いた。
少し先に誰かいる。薄闇の先に目を凝らす。突っかけた下駄と、トンボ柄の浴衣姿。見覚えがあった。今しがた見かけた狐面の男だ。
ほっとして駆け寄った。ここが、いったいどこなのか、そして、帰り道を訊こうと思ったのだ。浴衣の先行者は下駄の足をふと止めて、ゆっくりこちらを振り向いた。宵闇で姿が見難いのか、顔の狐面に手をかける。切れかけた鈍い街灯の下、面をゆっくりと顔から外すと、「やあ」と親しげに手を上げた。
どこかで見たような顔だ。
乏しい街路灯が照らし出す相手の姿に目を凝らす。緩めたネクタイ、腕辺りまで捲くり上げた、くたびれた白ワイシャツ──。
"俺 "だった。
「やっと会えたな」
もう一人の " 俺 " が小首を傾げて気さくに笑う。「これからは、ずっと "こっち" にいるんだろ」
「──え?」
そう言われて、たじろいだ。気がつけば、僕は一人きり。辺りには人っ子一人いなかった。いや、周囲の全てが消え失せている。家も、色も、全ての音も──。僕はそいつと二人で立っていた。東西も、いや、上下さえも定かじゃないポッカリと真っ暗な空間に、
二人きりで。
──どうしたら、いい。
焦燥がこみ上げた。僕は "こいつ" を、どうしたら、いいんだ?
恐慌に震え上がった頭でマニュアルの全てを捲ってみるが、手強い顧客の篭絡方法は載っていても、こんな相手への対処法はない。これまで見聞きしてきた対人関係のノウハウ等々凡そ全ての手引書を頭から大至急引っ張り出すも、この相手をやり過ごす方策は、ただの一つも見つからない。
そうだ。どんな誤魔化しも利きはしない。相手は、こっちの手の内を隅から隅まで、裏の裏まで知り尽くしているのだ。対峙している相手は、他ならぬ "自分" なのだから。
「た、助けてくれ──!」
とっさに身を翻し、空気を掻くように踊り出た。足がもつれて転びそうになりながら、持てる全力で引き返す。空間の密度が異様に高い。ドロドロの重油の海を必死で泳いでいるように、体が前に進まない。膝が笑う。歯の根が合わない。後ろの影が猛烈なスピードで追い迫って来るような気がして、生きた心地もしやしない。そうだ。"あいつ" は真っ赤な口で哄笑しながら、空の端から端まで覆ってしまう黒く広大な腕(かいな)を広げ、頭上高くから覆い被さり、僕を頭からすっぽり呑み込んでしまうのだ。
"あれ" に囚われたら、お終いだ。
直感が全身を貫いた。"あれ" に囚われてしまったら、全てのものを失ってしまう──。
立ち上がった貪欲な闇が津波のように迫っていた。重油の海を掻く足が重い。絡め取られる訳にはいかなかった。"あれ" が僕から取り上げようとしている"それ"は、僕が望んで手に入れてきたものなのだ。他人を必死に押し退けて、この手で一つ一つ積み上げてきたものなのだ。失う訳にはいかなかった。
どんなに輝きを失っても。
早い脈を刻む耳元で、急を告げる警鐘が世界を揺るがすほどに鳴っていた。切迫した危機感が、萎え震える足を狂おしいほどに急き立てる。
両側の濃厚な闇に、巨大な時計が、ぽん、と唐突に浮かび上がった。いや、時計そのものではない。文字盤だ。異様な圧力に歪められ、グニャリとひん曲がった白い文字盤。それは無限に増殖し、濃厚な闇を埋め尽くす。
幾つもの巨大な文字盤が一斉にカチコチ、僕の両側で時を刻み始める。いや、回り方が逆だ。白い文字盤の上、時計の長針と短針が、狂った時間が、グルングルンと逆行している。絶望的な唸りを上げて回転し続ける時計の二針。それは瞬く間に速度を上げ、視認出来ない速さに達した。回転の負荷に耐え切れず煙を上げて次々焼き切れ、巨大な針が滅茶苦茶な軌道を描いて闇の中へと弾き飛ばされていく。
両目を見開き、息を喘がせ、今来た道を全力で辿る。軒を並べる縁日の屋台で、軒先に吊るされた裸電球が激しく一斉に揺れ靡いた。一面に並べられた狐の白面が抗議を示してガタガタ鳴った。逃げる僕を非難している。顔のない男達に担がれて金の飾りの神輿が練り歩き、浴衣姿の子供を従え煌びやかに飾った山車(だし)が往く。物悲しい笛の音が、調子の狂った祭囃子が、ビニール袋の橙の金魚が、何かを咀嚼しているかのような歪な渦を描く背後の真っ黒な空間に、捻くれ曲がりながら飛び去っていく。世界の全てが吸い込まれ、高密度に凝縮された闇の中へと消えていく。ランドセルの子供達が。ナイター中継に熱中しているステテコ姿のおやじの背が。古ぼけた民家のブロック塀が。──走れ、
走れ、
走れ、
走れ──!