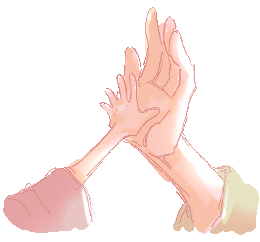
■ CROSS ROAD ディール急襲 第1部3章3話5
( 前頁 / TOP / 次頁 )
夕陽が照らす煉瓦の街路に、住人は寄り集まっていた。
誰もが黙りこくったまま、その場に立ちつくしている。子供が父の手を引いた。
「ねー、とうちゃん、かえろうよー。ぼく、もう、おなか、へったよ」
「……そうだな」
だが、そうは応えるものの、やはり立ち尽くしたまま動こうとしない。
誰もが解散する気になれずにいた。戦のさなかには、あれほど焦がれた我が家だというのに。戦いは、とうに終わったというのに。
「かえろうよ。かあさんも、かえってくるの、まってるよ。けんかは、もう、おわったんでしょう?」
父親は深く嘆息した。
「──ああ、終わったな。みんな、終わった。本当に、長い一日だった」
「なら、どうして、こわいお顔をしているの? お兄ちゃんたちも、いつもみたいに笑ってくれなかったし」
邪気なく問われ、父親はとっさに返事に窮す。隣にいた初老の男が、それを見て、子供に言い聞かせた。
「坊主。俺たちはな、人として、してはならないことをしてしまったんだよ」
「" してはならないこと " ー?」
きょとん、と子供はまたたいて、しげしげ首を傾げている。
「どうして、あやまらないのー?」
「──そりゃ、奴らが」
隣の男は口ごもった。困惑したように口をつぐむ。
街路にたたずむどの顔も、苦い顔で目をそらした。子供は不思議そうに見まわして、父親の服を引っぱった。
「ねーねー、お兄ちゃんたちさあ、すごく、しょんぼりしていたよ」
「──ああ。ああ、そうだな」
「ねー、どうして、だめなんだろうねー」
大人は渋面を見合わせた。理由は誰もが知っていた。そう、今しがた子供をなだめた派手な身形の遊民が、言葉の先をのみこんだ時、あの場の誰もが続けたろう。
『 だって、俺らは── 』
遊民だから。
誰からも蔑まれる遊民だから。
だから、きっと
── 受け入れては、もらえない。
それは、遊民ならば誰もが宿す、心にくすぶる忸怩たる想い。枷つきの不遇に対する矢も盾もたまらぬ苛立ち。
あの彼女の試みが、どれほど惨いものであったのか、この地を踏んでまだ間もない、あの若い新参者は知らない。安易で無謀な試みが、長らく諍う当事者の心にいかなる波紋を投げたのか、彼らに投げた呼びかけが、たやすく返事のできない類いの、だが、どれほど甘く、苦しい誘いだったのか。
包帯替わりのスカーフが、朱に染まって揺れていた。
西からの夕陽を浴びて、遊民はぞろぞろ引き揚げていく。血染めの衣装で足を引きずり歩く者、腕の負傷を押さえる者、半袖衣装の白い腕に、鮮血が滴り落ちていく。
ぽつり、と呟きが街路に落ちた。
「──あいつら、あんな薄着でよ、それでも戦ってくれたんだな。ろくに装備もない、あんな成りで」
自らの体を盾にして。街と人々を守るために。
砂埃舞いあがる戦時には、あでやかな舞台衣装がなめらかな動作を引きたてて、優美な剣舞を見るようだった。死と隣り合わせの戦場にあって、危なげなく剣を振るう堅実さが、身近にあった舞台衣装の色彩が、どれほど頼もしく感じられたか分からない。
今となっては、あでやかな衣装、それこそが仇だった。途方に暮れた哀愁を、それは殊更に際立たせ、彼我の間の絶対的な隔たりを嫌というほど突きつける。埋めがたい乖離を。街に住む者との立場の違いを。
そう、いつの頃からだったろう。それを信じて疑わなくなったのは。遊民たちの絶対的な下位を。彼らに対する己が優位を。
子供は誰でも、遊民たちが大好きだ。彼らは誰より高く飛び、誰より鮮やかに舞うことができる。彼らは誰より陽気に笑い、誰より美しく歌うことができる。彼らは祭を華やかに彩り、笑顔を振りまき、おどけて歩く。大きなあの手と手をつなぎ、華やかな帽子の長身を仰いで、街を練り歩くパレードを歩いた。日が西に暮れるまで。
そう、いつの頃からだったろう。そのゆるぎない彼らの地位が " 蔑まれて然るべき存在 " にまで転落してしまったのは。
子供の時分には、この子らと同じ疑問を誰もが抱いた。今、彼らがしたように、親に問いかけ続けたはずだった。ねじくれ曲がった理不尽さを。誰はばかることない無心さで。曇りのないまっすぐな瞳で。
そして、歴史はくり返す。
街の小さな住人は、今、再び " 声 " をあげる。いつか置き去りにした " あの声 " を、あたかも代弁するように。
──ねえ、 " どうして " ?
それは跳ねのけ続けた問いだった。
子供の澄んだその声は、疑心に固まった大人の胸に、真っ向から矛盾を突きつける。本当にそれでいいのか、と。己の行いは正しいのか、と。
父親は深く嘆息し、小さな頭に手を置いた。
「そうだな、坊主。お前の言う通りだ。──後で、奴らに謝りに行こう。うちでこさえた手土産もって」
「いく! ぼくもいく!」
きょとん、と仰いだ幼い顔が、みるみる明るく笑み崩れた。
懸念を投げかける者はいなかった。それに異論をさし挟む者も。親子を眺める人々の視線は、和やかで、穏やかで、あたたかい。胸のつかえが取れたかのように。
父親は、にっか、と笑い、子供の頭をこねくり回す。
「きっと、あいつら、びっくりするぞお? そうしたら、お前、馬の乗り方教えてもらえ。きっと上手に教えてくれる」
「うん! とうちゃん!」
「それから、あいつらに、こう言うんだ」
照れくさそうに少し笑う。
「" ここで一緒に暮らそう " って」
「許さんぞ!」
猛々しい叱責が、親子の会話を遮った。
フロックコートの一団が、つかつか大股でやってくる。取り巻きを連れたチェスター侯だ。戦後の街を見回っていたのか、まだ居残っていたらしい。
先頭に立ったチェスター侯は、人々が怪訝に目配せする中、親子に険しい目を向けた。
「何を馬鹿なことを言っておる! 勝手な真似は、私が許さん! あの使用人あがりが許しても、この私が許さんぞ! ああ、断じて許すものか! よもや忘れてはおるまいな。この北カレリアの土地土地を、代々治めてきたのが誰であるのか」
まなじりつりあげ、がなり立て、人々の顔を睥睨する。
「この際、とくと知らしめてやる。他の者も聞くがいい。ここは我がクレスト公家の領有地だ。お前らのものではない。まして、どこの馬の骨とも知れぬ小娘が自由にして良い道理はない。これだから、下賎の者は質が悪いのだ。高々平民あがりの分際で何を勘違いしたのか知らないが、図々しいことこの上ない。一体自分を何様だと──」
「やかましいっ!」
ぎょっと、チェスター侯は飛びあがった。今の罵声の出所を捜し、人々に視線をめぐらせる。
街路に立つ一同が、荒々しい視線を向けていた。ぐるりを囲むどの顔も、まなじり決して腹立たしげな面持ちだ。睨めつけるどの目にも、憎々しげな刺を含んでいる。
今にも詰め寄らんばかりの不穏さに、チェスター侯はたじろいだ。浅慮の口をふさぐついでに領家の威光を知らしめるつもりが、これでは逆に吊るしあげを食っているようではないか。
唖然としつつも、指を振る。「ど、どういうつもりだ! 誰に向かって口をきいていると──」
「あんたは黙ってろ!」
平服姿の八百屋の主が、地面に剣呑に唾を吐いた。
「あーあー、なんてえ様だよ、情けねえ。年端も行かぬこの子らの方が、よっぽど道理をわきまえているじゃねえかよ」
チェスター侯はうろたえた。領民が幾重にもとりかこみ、罵声を浴びせそうな勢いだ。後方にいた取り巻きが、平静を装い、踵を返した。そそくさ密かに離脱する。前方にいる残る四人も、警邏を呼ぼうというのだろう、おろおろ周囲を見まわしている。だが、領民の人垣に阻まれて、求める姿を見い出せない。
チェスター侯の取り巻きたちは、密かに顔を見合わせた。大声で助けを乞えば、救出されるかも知れないが、興国の功労者・騎士を祖に持つ由緒正しき貴族たるもの、公衆の面前で醜態などはさらせない。そんな無様な真似をしたなら、末代までの恥である。
領民たちが、公然と反旗をひるがえしていた。大人しく従順だった統治されるべき領民が。
予期せぬ反抗を目の当たりにして、チェスター侯はあわてふためき、じりじり町角に後ずさる。
「な、なんという無礼な! 誰に向かって口をきいていると思っている! お前らごとき下々などは、この私が一声かければ、たちどころに──」
「あんたが何をしてくれたってんだ!」
長身の雑貨屋の主が、たまりかねたように食ってかかった。あの子供の父親だ。カッとまなこを見開いて、貴族街を顎でさす。
「あの若い奥方が一人で矢面に立ってる時に、あんたは一体、どこにいた! 全部終わってから、もっともらしく出てきやがってよ! なあにが騎士だ、笑わせるな。街を守ったのは、あんたらじゃない。奥方様とあいつらだ!」
夕日が照らす煉瓦の路上、その先の、北の方角を眺めやる。そこには遊民が引き揚げた天幕群の一端が、鈍く西日を浴びている。雑貨屋の主は苦々しげに続けた。
「先代の始めた諍いが、どれほどのものだかは知らねえよ。だが、今を生きてるのは俺たちで、親父たちじゃねえからな。俺たちは俺たちのやり方で、したいようにさせてもらう」
「し、しかし──!」
辛うじて、チェスター侯が異議を唱えた。だが、声は甲高く裏返る。宿屋の主がぎょろりと眼をむき、濁声で話に割りこんだ。
「ああ、ああ、あんたら領家のもんが、どんだけ偉いか知らねえよ。だが、古い因縁なんぞに囚われていたら、いつまでたっても進めやしねえ。これじゃあ、なんにも変わりゃしねえ。こんな馬鹿らしいことはありゃしねえ! ああ、そうだ。あのメイドあがりの言う通りだ!」
「──だ、だが、あれは新参者の、たかだか領主の添え物で──」
「確かに!」
別の声が遮った。憮然と腕を組んだ、小太りの土産物屋だ。
「確かに新参者かも知れねえよ。小娘のじゃじゃ馬かも知れねえよ。ああ、あれには、ほとほと頭にきたぜ。あの小生意気な言い草ときたらよお。あのアマ、人の痛いところを遠慮なくポンポン突っつきやがる。まったく、とんだ奥方様もいたもんだぜ。だが、投げ出したりはしなかった。俺らを見捨てて自分だけ、逃げ隠れたりはしなかった。一度たりともだ! あんたに分かるか、その意味が。奥方様は俺らと一緒に戦ったんだ。戦が終わるまで、どこぞに隠れてたあんたら貴族と違ってな。あの人を悪く言うのはよしてくれ。あれはもう、立派に俺たちの仲間なんだ!」
チェスター侯は四方から刺すような視線を浴びせられ、忌々しげに舌打ちした。
「こんな真似をして、ただで済むと思うなよ。身の程を思い知らせてくれる。すぐにも牢に放り込んでくれるわ。精々覚悟することだな。──どきたまえ!」
胡乱に立ちふさがる人垣を、癇癪を起こしたように押しのけた。
呆然と聞いていた取り巻きが、我に返って、後を追う。フロックコートの一団が、西日に染まった貴族街へと、せかせか気忙しく去っていく。
「──けりが、ついたな」
ぽつり、と誰かがつぶやいた。
「ああ、終わった。これで全部」
人々は放心したように嘆息した。
どこか懐かしい煮炊きの香りが、夕焼けの街路に漂っていた。急速に降りはじめた青い帳が、北方の街を包みこもうとしている。
子供らは、ぽかん、と口を開け、目を丸くして大人たちを見ている。長身の雑貨屋が──あの子供の父親が、子供のつむじを振り向いた。
「腹が減ったな。──さてと帰るか。母ちゃんが待ってる」
「うん! とうちゃん!」
ぱっ、と子供が振り向いた。にっか、と笑う。
「とうちゃん、ものすごーくカッコよかったっ!」
「そ、そうか?」
日頃うだつの上がらぬ " とうちゃん "は、照れくさそうに頭を掻いた。我が子の頭に手を置いて、手をつないで歩き出す。
人々は引き揚げ始めた。ようやく奪い返した各々の家へ。
握り締めていた指先が、微かに震え続けていた。こらえ続けた緊張に、どの手の平も汗ばんでいる。
領家の意向に盾突くなど、およそ考えられないことだった。曲がりなりにも武器を持ち、戦った昼の昂揚が、未だ抜け切れずに残っていたのかもしれない。無論、この後ただでは済むまい。貴族に無礼を働いたのだ。領主がこの地に戻ってくれば、なんらかの処罰は下るだろう。人々がこれまで従順の仮面を被ってきたのは、領家の偉業に心酔してのことではない。手ひどい報復を恐れてのことだ。あの侯爵の剣幕では、どんな仕打ちが待っているのか、それを思えば、気分も重い。
だが、心は軽く、晴れ渡っている。沈みゆく夕日を眺めて、「それでも、いい」と誰もが思った。
ノースカレリアの街が暮れてゆく。
せわしない一日が終わりを告げて、夕日が建物の向こうに輝いている。
長い長い一日が、ようやく幕を下ろそうとしていた。柔らかな萌芽を懐に抱いて。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》