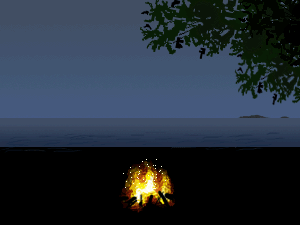
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部3章 6話9
( 前頁 / TOP / 次頁 )
あの言葉を聞いた途端、足が一歩も動かなくなった。
「いいか。勝手にここを動くなよ」
黒梢ざわめく大木の下、背を屈め、言い聞かせるようにして覗き込む瞳。深い深い、黒い瞳。見つめられると喉が詰まって、何の反論も出てこなくなる。何の気なしに放たれた呪が、手を、足を、全身を、やんわり捉えて放さない。
踵を返して歩み去るその背を、見ていることしか出来なかった。何故、そんなことが起こるのだろう。吸い込まれそうなあの眼だろうか。安心出来るあの声だろうか。全身を縛り付ける不思議な呪。
あんなことがあったのに、ケネルは、普段と変わらなかった。二人の首長も副長も、あんなに心配してくれたのに。慰め、気遣い、世話を焼いてくれた。一見、冷淡にさえ見えるあの副長に至っては、問答無用で叩きのめすなどという凄まじい暴挙まで働いてくれた。なのに、ケネルは──。
ケネルが来れば、もっと懲らしめてくれると思っていた。粗暴で野放図な副長以上に、不埒な輩を叱ってくれると信じていた。なのに、彼の口から出てきた言葉は、
『 ……なるほどな 』
普段と何ら変わらぬ受け答え。それぞれの立ち位置で一同が遠巻きにして取り囲む中、暗い地面に膝をつき、こちらの顔を見ていたケネルが、ゆっくり立ち上がったあの刹那、こちらだけを見ていた関心が、立ち上がるにつれて削ぎ落とされ、群れへと逸れたのがはっきり分かった。
自分でも驚く程に傷ついた。ケネルは、終始淡々としていた。無様に引き裂かれた衣服を見てさえ少し驚いた顔をしただけで、激昂して狼藉者を追求するでも、相応の制裁を加えるでもない。淡々とした態度は、普段と何ら変わらない。周囲とやりとりするケネルの顔は、いつもの平然としたものだ。知っているくせに。酷い目に遭わせた犯人が、すぐ目の前にいることを。なのに、眉の一つも動かさない。
ケネルは、何もしてくれない。口を塞がれ出口を失くした濁流が、荒んだ胸で猛り狂う。満たされぬ想いの正体は、憤懣というより悲しみだ。そして、軽い喪失感。確かにケネルは、いつも、さりげなく気遣ってくれる。こっちが知らない気付かぬ時には、そっと優しく扱ってくれる。でも、本当は、
「……ケネルは、あたしのこと心配じゃないの?」
連れて来られる道すがら、思い余って訊いていた。連絡を受けてキャンプから急行したのだろうか、いつもより少しだけ汗臭いケネルは、前を見たまま、少し苛立ったように応えた。
「──心配しない筈がないだろう」
そして、ふと気づいたように、憮然と言葉を付け足した。「突然いなくなっちまうんだからな」
虚しさが胸を支配した。
──あたしのことなんて、どうでもいいの?
込み上げる焦燥とやりきれなさに、息さえ苦しい。歯がゆかった。悔しかった。やっつけて欲しい。とっちめて欲しい。もっと優しく慰めて欲しい。確かに彼は、身内でも友達でも何でもない。成り行きで居合わただけの赤の他人だ。心配してくれ、と強要は出来ない。どう思おうが、本人の自由だ。無関心でも責められない。それは、十分わかっている。でも、それでも、ケネルは他の皆とは違うのだ。誰より心配しなければ駄目だ。どんなに些細なことでさえ、ケネルだけは怒ってくれなければ駄目なのだ。──分からない。何故そんなにも、ケネルに対して、理不尽な苛立ちを抱いてしまうのか。
ケネルの最後の付け足しは、どこか言い訳がましく等閑(なおざり)に聞こえた。
黄色く尖った丸い弓が、深く広い紺空に小さく遠く輝いていた。
黒梢に覆われた樹の上は、代わり映えなく静かなものだ。寝巻きのブーツの足元は、夜に塗り潰された黒い野草で埋まっている。こちらもやはり真っ暗だから、何があるのかよく見えない。辺りは一面、夜の木立で、見上げても見上げても黒いばかりで暗くって、枝なんだか葉っぱなんだか分からない。何度目になるか分からぬ溜息をつき、静まり返った樹の上を仰いだ。
「あんたねー! いい加減そこから降りて来なさいよねー」
エレーンは、むぅー、と膨れて、お願いする。だが、高い頭上の樹の上で一人不貞寝を決め込んだテキは、
「やなこった」
「──んもうー!」
ケネルに往(い)なされた野良猫が、すっかり拗(す)ねて、木の上によじ登ってしまったのだ。さっきから、こうして待ってもいるが、どうあっても降りて来ない。やる気なく伸ばした野戦服の脚と黒い編み上げ靴の先っぽが、黒梢の先に見え隠れするだけだ。爪先立って目を凝らし、エレーンは、ぴょんぴょん跳ねてみる。反応のなさに思い余って、大木の周りをグルグル回り、──と不貞腐ったあの顔が、梢の先に垣間見える絶好のポジションを発見。早速、そこまで後戻りした。
「なによ、拗ねちゃってさあ! 子供みたい!」
ちゃんと相手に聞こえるように呆れた溜息をついてやり、両手を腰に押し当てる。だが、すっかり拗ねちまった野良猫は、
「なんとでも言え」
相当ぶんむくれているようである。そして、一方エレーンも、負けず劣らず、ぶんむくれていたのであった。知れたこと。ケネルに置いてけぼりを食わされたからである。
ケネルは、こんなに広い暗がりの中でも、難なくファレスを見つけ出した。通りかかった部下達に「おい、副長を見なかったか」と二言三言尋ねただけで。幾つか得られた目撃情報から、相手が通った道筋の目処をつけると、ケネルは、迷うことなく歩き出した。雑木林の切れ目を突っ切り、確かな足取りで藪に分け入り、そして、木立の中を闊歩すること数分後には、潜伏していた大木に容易く辿り着いていた。エレーンは、ケネルの小脇に引っ抱えられ問答無用で連行されつつ、手際の良さに舌を巻いた。予め場所を知らされてでもいなければ、見い出すことさえ困難だろうに。高い樹の上で不貞寝をしていたのだから。あんな所まで、いったいどうやって上ったんだか、かの野良猫の潜伏場所は、優に三階分くらいの高さはある。そう、あんなにも高い樹の上なのだ。
腕を組み、不満に口を尖らせて、夜風にサワサワ梢を晒す、黒くて暗い樹を仰ぐ。
「ねー、いつまで、そこにいる気なのー? いじけてないで降りといでー!」
頬に手の平でメガホンを作って、エレーンは、声を張り上げる。度重なるつれない返事に、いささか自棄気味な呼びかけである。
「るっせーな。用があるなら、上がって来い」
「──あんたねー!? そんなの無理に決まってるでしょー!?」
エレーンは、ぷりぷり言い返す。どんだけ高いと思っているのだ!?
梢から垣間見える野良猫は、器用に寝そべって、知らんぷりを決め込んでいる。エレーンは、そわそわ焦れ始めた。
「ねー! 女男ってばあ! ねーってば、ねーっ!」
黒く染まった周囲を見回し、拳を握ってジタバタ足踏み。必殺「だだっ子」作戦である。
「……まったく、お前はうっせーな」
辟易したような声がした。高木の梢がガサリと鳴る。寝返りをうったらしい。あんなに高い樹の上だというのに、よくも落ちてこないもの、あたかも平坦な地上でダラダラしているかのような無造作ぶりだ。胸の前で手を握り、黒く塗り潰された周囲の木立を、エレーンは、おろおろ見回した。
「だって、──だって、一人じゃ恐いもん」
黒く覆われた梢の先で、ふと、ファレスが振り向いた。寝そべった体をそろそろ起こして、根元の様子をさりげなく観察。エレーンは、指の先をいじくりながら、ぶちぶち口を尖らせる。
「さっきだってさあ、靴に黒いもんがササ──ッて、すっごい勢いで飛び出して来て! あれって、思うに、ちっちゃい蛇とかトカゲとか? きっと、この辺りって、なんかああいうのがウジャウジャいっぱい──」
はっと唐突に飛び上がり、体をよじって後ろを覗く。( まさか変なのくっ付いてないでしょうねー!? )と己の長いスカートを今更ながらジロジロ点検、「んもう! やんっ!」と口を尖らせ、寝巻きの裾をバタバタむきになって叩いている。と、ギョッと顔を強張らせた。「──あ! さっきのアレ、もしかして黒虫だったり──!?」
シカと我が身を掻き抱き、エレーンは、あわあわ絶叫寸前、いや、
「いぃやあぁぁぁー! 早くぅー! 早くぅー! 女男! 早くぅー!」
実際、紛れもなく絶叫した。一方、そろりそろりと降下準備をしていたファレスは、
「……ぜってえ降りねえ」
元いた位置にそそくさ戻る。エレーンは、拳を握って振り仰いだ。
「んもー! 何よそれえー! か弱い女性が困ってるのに助けてやろうとか思わないの!? それでも男!? 薄情! 横暴! エゴイスト!」
そわそわ辺りを見回して エレーンは、焦れて唇を噛む。あんなに高い樹の上にいたら、もしもの時に、間に合わないではないか──!
そう、テキの動きは滅法速い。アレがカサカサカサ──と出没してから、よいしょと幹にへばり付き、暗い足場を確かめながら、えっちらおっちら降りて来たんじゃ、そんなの、完璧、間に合わない! 因みに「もしもの場合」とは、他でもない、宿敵黒虫がカサ……と出現した時である。だが、暗い樹上でゴソゴソしていた野良猫は、
「なんとでも言え」
又もダラリと寝そべって、プラプラ手なんか振っている。やる気なし。降りて来る気はなさそうだ。エレーンは、むむぅ……と拳を握る。実に頼りがいのないヤツである。
肌寒い夜風が駆け抜けて、黒い木立がサラサラ鳴った。周囲に人影は全くなくて、エレーンは、そわそわ足元を見回す。そうして、しばし、辺りをウロウロしていたが、
「ねー……ねえーっ! どういうことよー、さっきのあれはー」
ふと、立ち止まり、ふい、と顔を振り上げた。
「──あー? " あれ " ってのは何のことだよ。まったく、お前の話は要領を得ねえな。身勝手この上ねえとは、このこった」
阿吽(あうん)の呼吸で話が通じず、エレーンは、「だーかーらー!」と口の先を尖らせる。そもそも、コイツにだけは言われたくない。そして、そもそも、今日のダラけた野良猫は、話に参加しようとの気概と努力と意気込みに欠ける。エレーンは、焦れた。
「もーっ! アドのことだってば! なんで、あの人のお父さんを」
「──お前、その話、誰から聞いた」
返答に詰まった間があった。困惑したような反問だ。エレーンは、しれっ、とバラしてやった。
「バパさんが言ってた」
さっき矢面に立たされたお返しである。
「──ち! あんのお喋りジジイが余計なことを!」
忌々しげに舌打ちし、ファレスは、辟易とした渋い声だ。その話をするのは気が進まないらしい。だが、奥方様は、こうと決めたら、たいそう、しつこい。
「ねーねーなんでー? なんでアドがあの人のお父さんのこと──ねーねー女男! ねーってばあっ!」
夜空を仰いで、力の限りに問い質す。答えを聞くまで口をつぐまない所存である。暇だし。
一方、樹上に潜伏中の野良猫ファレスは、応用の利かない樹の上に居場所を定めた事が仇となり、全くどこへも逃げられない。こうなると、集中砲火もいいところである。そもそも、この奥方様は、彼に対して遠慮という言葉を知らない。
「──あ、わかった! 戦争の時とかでしょ!」
一人で騒いでいたエレーンが、合点したように手を打った。「ねー! そうでしょ。そうなんでしょ。事故かなんかで誤って──」
「いや、あのおっさんは、明らかな殺意をもって、バリーの親父を手にかけた」
「……え?」
パチクリ眼(まなこ)を瞬いて、エレーンは、唖然と口をつぐんだ。
「それも、幼いあいつの目の前でな」
思わぬ答えだ。ファレスは、意外にも、ぶっきらぼうに言葉を付け足す。話す気になったようだ。喚かれ続けて、あっさり観念したらしい。もしくは、彼らの暗黙の堤防を、我が身を挺してまで死守してやるのが、早々に面倒になったのか。何れにせよ、かったるそうな溜息混じりで続けた。
「──こいつには、ちょっとばかり、込みいった事情がある。それでも聞くかよ」
梢が夜風にさわさわ騒いで、不意に静寂が訪れた。紺空を背景にした黒梢で、ぽっと小さく火が灯る。煙草に点火したらしい。
長い話になりそうだ。薄く煙が立ち昇った。
「知っての通りシャンバールでは、西のシャンバール帝国と、東のモンデスワール都市同盟とが、長らく国を二分して争っている。ある時、俺達は同盟からの依頼を受けて、同盟領の、とある辺境の村を襲撃した。二十人足らずの集落だ。敵兵が村人に化けて潜伏している──同盟からは、そう聞いていた。そいつを叩いて拠点を潰すのが、こっちの請け負った役割だ。たいした抵抗があるでもなく、村はあっけなく陥落した。あまりの手応えのなさを不審に思い、片っぱしから家捜ししたが、だが、あるのは農具ばかりで、弓矢一本出てきやしねえ」
「え? それって、まさか──!?」
「ああ、その "まさか " だ。蓋を開けてみりゃ何のことはない、全部ただの村人だった。つまるところ俺達は、同盟の連中に嵌められて、戦とは無関係なド素人の民間人をまんまと虐殺しちまったって寸法だ。だが、話が違うと気付いた時には後の祭だ。その時、現場に出向いていたのが、あのおっさんの部隊でな」
「アドの?」
気がかりな名前が不意に出てきて、エレーンは、ハッと目を凝らす。暗い樹の上で、ファレスは、続ける。
「事が終わって、おっさんは慌てた。で、瓦礫の中から生き残りのガキを捜し出し、傍に置いて手ずから育てた。実の息子も同然に。そいつがバリーだ」
──" バリー " ?
あの……?
「あ、……でも、なんでアドは、その時、その子のことを──?」
「生き残り、即ち生き証人だ。そんな者がいると知れりゃあ、同盟は即刻口封じにかかる。口を割られたら、全てがフイだ」
「──まだ子供よ!?」
「関係ねえだろ年なんざ。口さえきけりゃあ、用は足りるぜ」
ファレスは、かったるそうに片付ける。エレーンは、愕然と口をつぐんだ。確かに、生き残りの存在を同盟の側が知ったなら、口を塞ごうとするだろう。だからこそアドルファスは、群れに子供を匿ったのだ。そして、連れて来た子供を《
遊民 》として育てた。同盟の目からひた隠しにして。
「……アドは引け目があるから、あの人のことを。──え、でも、それじゃあ、」
はっと気付いて、エレーンは、暗い樹上を見返した。「それじゃあ、あの人は──!」
「ああ、バリーは生粋のシャンバール人だ」
「──シャンバール、人?」
カレリアは大きな都市だが、シャンバール人など裕福な商人くらいしか見かけない。隣国は内戦続きで、かの国からの入国は厳しい。
「シャンバール人……あの人が……?」
エレーンは、唖然と言葉を呑む。今のファレスの話によれば、彼らは同盟側に加担して、帝国の戦力と戦っているらしい。戦国の大きなうねりの中で、同盟の村で生まれたバリーは、故郷の盟主に見捨てられた──いや、積極的に攻撃されたのだ。敵方の侵略から本来庇護すべき同盟に。つまり、バリーは、自分の故郷に裏切られたことになる。でも、それなら──
嫌な燻りが、胸を焼いた。その現実が心に重く引っ掛かる。成人した今になっても、バリーは、アドルファスの元にいて、同盟を利するべく戦っている。ならばバリーは、己を襲撃した他ならぬ同盟を守る為に、体を張っていることになりはしないか。親を殺した仇敵を守る盾として 。
「……自分を裏切った国なのに」
何かがほろ苦くわだかまった。その上手く飲み込めない一端が、絶句の口から零れ出た。
「なのに、あの人はそんなにまでして、……今もアド達と一緒になって……」
──戦っている?
やりきれない。皮肉な現実が割り切れない。
一人残された子供には、生き延びる場は、恐らくそこにしかなかったろう。救いの手を差し伸べた相手が憎き敵将であったとしても。同盟が虐殺を命じたその瞬間から、故郷に居場所は、既にない。
「……どうして、」
同盟のやり口に、腹が立つ。知らず、唇がわなないた。
「どうして、そんな惨(むご)い事が出来るの!? 善悪の区別もつかないの!? どうして、そんな──!」
おぞましさに息が詰まる。なじる声が激昂に震えた。ひどい。苦しい。
──許せない!
「さあな。大方、戦意高揚が目的ってとこだろ。現にあの後同盟は、あれを帝国の仕業として喧伝し、随所に燻っていた反戦気分を一掃することに成功したからな」
思わぬ話に、耳を疑った。
「そんな事の為に、なんの落ち度もない人達を!? どうして、そんな──!」
ファレスは当然のように推測するが、そんな解釈は呑み込めない。だが、それに続くファレスの言葉は、更に信じられないものだった。
「戦を食い物にする輩ってのは、どこの国にもいるって話だ。厭戦気分が蔓延すると、お偉いさんには都合が悪い。稼ぎがめっきり減っちまうからな」
「か、 稼ぎって何──!?」
エレーンは、驚いて振り仰ぐ。
「見返りがなけりゃ、誰もそんなものには手を出さねえよ。戦をするには、経費も手間も莫大にかかるからな」
「──だって味方よ!? その人達を支持していたのよ!? なのに、慕ってくれる人達を無差別に虐殺するなんて!」
「国土を牛耳る連中にとっちゃ、帝国であろうが同盟であろうが、どっちがくたばろうが大差ない。シャンバールの国土はデカい。西の隅に在る帝国が、広大な国土を東の端まで須らく掌握する日が来るなんざ、上の方は誰も考えちゃいねえ。つまり、てめえと周囲が安泰ならば、どっちがどうなろうが痛くも痒くもねえって話だ。もっとも、そいつらのホラ話を間に受けて旗振り役が出て来るってんだから、大衆ってのは分からない。そいつらの私腹をわざわざ肥やしてやる為に、てめえの命さえ差し出してやろうってんだから恐れ入る。──まったく、いい面の皮だぜ」
「──そんな! 必死で戦っている人達のことをそんな風に!」
愕然と、エレーンは、戦慄する。
「人の命を、いったい、なんだと思っているの!」
「どれほど義憤に駆られて突進しようが、連中にとっちゃ只の駒だ。てめえの世界とは何ら関わりのない──いや、そもそも、てめえと同じ "人"
として認識してさえいねえだろうさ」
「そ、んな……!」
エレーンは、唖然と反論を呑んだ。ファレスの辛辣な認識は、見知った世界とは、あまりにも違う。これまで漠然と抱いてきた、崇高な理想に燃える指導者像とは、それらはかけ離れて過ぎていて、とっさに反駁さえも叶わない。
信じられない思いだった。だが、どれほど詰ろうが、ファレスは引かない。己が手にした真実を、ただ相手に伝えんが為に、説いて聞かせているように。
紺空に、紫煙が立ち昇っていた。風は凪ぎ、大木の梢は、ひっそり静まり返っている。これまで抱いていた認識が、引っ繰り返され、混乱し、混沌のままで停止した。けれど、錯綜する条理の果てに、硬く死んだ核がある。目に焼きついて離れぬ光景。白黒に褪色した煉瓦の道端、折り重なった屍の、軍服の放つ青だけが、色鮮やかに目を焼いた。
「……他人を散々煽っておいて、散々殺し合いをさせておいて……そんなに戦争がしたいなら、」
声が、零れた。ノースカレリアの終戦の街。虚空を掻いたままの動かぬ指。どれほどの無念がそこにあったか──。
噴悶に、目の前の木立が朱に染まった。立ち尽くす全身から、血の気が一気に引いていく。拳を強く握り締めた。
「そんなに戦争したいなら、自分達だけで、やればいい!」
ファレスの口調は、素気ない。
「そういう奴らとそいつの身内は、間違っても前線なんかには出て来やしねえよ。危ねえからな」
「──そんなの卑怯よ!」
「現実だ」
ピシャリと、抗議が撥ね退けられた。
一筋薄く、紫煙が揺れた。淡々としたファレスの声が、静かな黒梢から降って来る。
「そいつが戦の常識だ。戦をしたがる輩ってのは、往々にして自分らだけは安全な場所に居るもんだ」
怯んだ拳を胸で握って、エレーンは、力なく、祈る思いで首を振る。「……そんな筈、ない……国を治める人達が、みんながみんな、そんなに卑劣な人達ばかりじゃ……」
「──まったく、お前はめでてえな。隣の国の戦争が、いつまでも終結しねえのは何故だと思う」
はっと、梢に顔を上げた。静かな声が先を続ける。
「殺し合いなんぞ、本来誰も望みはしない。なのに何故か、いつまで経っても終りやしねえ。満場一致の当然過ぎる認識が歪(いびつ)に捻じ曲げられる時、そこには必ず故意がある」
「……故意? わざと、ってこと?──誰がそんなことを!?」
「無論、下っ端風情の意図じゃない。それなりの権力を持つヤツだ。全体を動かせる程度には影響力がなけりゃ、元より話にならねえからな。筋書きを書いたヤツは中央にいる。それで得する奴こそが、一連の作為の台風の目、全てを牛耳る元謀だ」
暗い夜空に、紫煙が揺蕩う。ファレスは、殺伐とした話にキリをつけるように、押し殺した皮肉な口調を、少しだけ、さばけたものへと改めた。
「お前の嫁いだクレストなんぞは" 骨肉相食む "の最たるもんだぜ。ああいう場所に身を置くなら──金持ちとつるんで生きるなら、頭の隅にでも入れておけ。権威の集中する中枢は、食えねえ業師の巣窟だ」
ふと、ファレスが身じろいだ。
はっと我に返り、エレーンも、話にのめり込んだ意識を戻す。ファレスは、右手の暗がりを眺めていた。何かに耳を澄ますように。
高い樹上を仰いだ視線を、そちらの方へと振り向けた。暗い木立の向こうから、騒がしい気配が伝わってくる。遠く微かに聞こえたそれは、次第次第に大きくなって、
「な、何かしら……」
暗がりの先で藪が鳴った。ガサガサ、ガサガサ……徐々に近付いて来るようだ。
エレーンは、当惑した。誰だろう? こんな外れの物寂しい場所に。もしや、昼に遭遇した賊とかじゃ──? いや、ここには、今さっき襲われたようなとんでもない輩もいる。何れにしても、あんなに高い所にいたら、何かあっても間に合わないではないか──!
降って湧いた慌しさに、微かな不安が入り混じる。今日は、碌な目に遭ってない。非難混じりに樹の上を仰いだ。いや、振り向こうとして身じろいだ刹那、どこかの木立が激しく鳴った。いや、"どこか
"じゃない。
至近距離だ。
振り向く間もなく、飛び掛ってきた。
突き飛ばされて、つんのめる。バサリ──と何かが覆い被さる。何が起きたか分からない。
……何か、いる!?
真後ろだ。
押し潰すように圧し掛かる体重。荒く獰猛な獣の気配。生き物の体温と息遣いを感じる。既に " それ " に捕まっていた。とんでもない速さだ。たった今まで何の気配もなかったのに。
立ち上がった前脚で体を掴まれているようだ。人間並みの体格からして、かなり大型であるらしい。少なくとも可愛らしい子兎や野鼠の類いなどでは、あり得ない。
足が震えた。戦慄が駆け抜け、総毛立つ。知らぬ間に首をすくめて目を瞑っていた。そういや、さっき、熊がどうこう言っていた。なら、この辺りは出没地帯なのに違いない。そう、常々ケネルも言っていた。
──夜の木立は、獣がいっぱい。
全身、恐怖に凍り付く。恐慌をきたした頭は、もう何も考えられない。鋭い爪で薙ぎ払われたら、脆い人間などは一撃でお陀仏。顔の半分くらいは軽く失くなっているだろう。
グッと、硬く瞼を瞑る。ここで会ったが百年目!
──咬まれる!?
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》