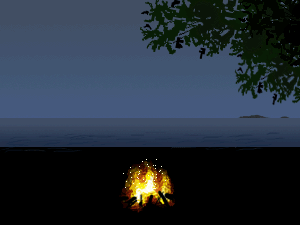
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部3章 6話13
( 前頁 / TOP / 次頁 )
犇き、たむろする野戦服の賑わいを、眺めるともなしに眺めやる。隣にいるのは、ツルツル頭のセレスタン。街で見かける若者のように、遠目はヒョロリとしているが、近くで見れば、ご多分にもれず、体躯は敏捷そうに引き締まっている。個性的な風貌で、ともすれば恐い人に見えがちなこの彼も、言動は存外飄々としていて、話しかければ意外にも、きちんと真面目に応えてくれる。態度は親切で礼儀正しい。どこぞの横柄な野良猫みたいに、うざったそうに舌打ちしないし、デコピンなんか間違ってもしないし、ケネルみたいに聞こえない振りして無視したり、荷物みたいにぞんざいに扱ったりとか絶対にしない。そう、こちらの扱いは丁寧だ。慎重で節度があり、配慮がある。ちゃんと
"女の子" として留意してくれる。ラジカルで排他的な一見鋭い見た目に反して目下の面倒見も良いようで、伺いを立てられたり、逆に指示を出したりしている姿も時折見かける。そもそも、彼に限らずファレスがコーディネートしたタンポポ隊の面々は、何れも信望はあるようで、周囲から一目置かれている感がある。彼らが常々自称している「精鋭隊」との看板に嘘偽りはないらしい。てっきり冗談なのかと思っていたが。
セレスタンは、片足に体重を預け、ズボンのポケットに両手を突っ込み、ただただ隣に立っている。もぞもぞ足を踏み替えたり、禿頭の首を回してみたり──。そろり、と、それを窺って、エレーンは、なんとなく謝った。
「わ、悪いわねえ、足止めしちゃって」
雑談に入るべく、まずは軽く社交辞令。二人っきりの不慣れな状態が照れ臭く、とりあえず、えへへ……とお愛想笑い。セレスタンが身じろいで、銀星瞬く夜空を眺めた。「──いいっすよ別に」
(え゛?)
意外にも、ぶっきらぼうな反応だ。ビジネスライクというかドライというか……。いつもは、あんなに気さくなのに。予想外に出鼻を挫かれ、エレーンは、面食らってたじろいだ。
「う、うん! あ、でもね、あの──っ!」
彼は、ただただ立っている。若干楽めの"休め"の姿勢で。
「……あ、……あ、あの、……」
しかし、努力するも取っ掛かりなし。会話終了。もしや、機嫌でも損ねたのだろうか。野良猫が「ハゲ」とか言ったから。
エレーンは、気まずく俯いた。視界の端に写り込むのは、上着を羽織っていないセレスタンのアーミーグリーンのくたびれたTシャツ。胴を締める黒の太い革ベルト。ズボンのポケットから突き出た褐色に焼けた骨太の腕。筋肉の付いた見慣れぬ腕。黒くてゴツい腕時計。はっきり言って、話題はない。となると──?
密かに気合を入れ直し、深呼吸して振り向いた。
「め、珍しいよね、そういう頭って」
同行者達の髪型は、わりと長めのザンバラ頭が多い。本人達が不精な結果か、床屋へ行ってる暇がないのか、はたまた趣味かは不明だが。
「──いや、禿げてる訳じゃねえっすから」
セレスタンは、訊きもしないのに言い訳した。「これはね、わざと剃ってんの」
「あ、そうなんだ?」
エレーンは、軽い驚きと共に訊き返す。( あたし、"バケ"なんて一言も言ってないしぃ? )と心中で要らぬ反論を返しつつ。そして、マジマジ彼を見た。「好みなの? そういうの」
セレスタンは、上着の懐を弄りながら、ボチボチ応えた。
「……あー、仕事中にさ、命取りになるんだわ。髪の毛長いと、引っ張られたりして」
小型の箱を軽く振り、煙草を一本、揺すり出す。エレーンは、むっ? と見咎めた。何を隠そう禁酒禁煙の侘しい身の上。自分だけが飲めない上に、他人の喫煙を指を咥えて見ているなんて、あまりに切ないものがある。
「へえ、そういうもん?」
つつがなく応えを返しつつ、さりげなく箱を引ったくった。だが、
「そういうもんなの」
上背のあるセレスタンは、節くれ立った長い指で、ひょい、と上から摘み上げ、難なく箱を取り戻す。禿頭を少し傾けて、咥えた煙草に点火する。小指に嵌めたシルバー・リングが炎の揺らぎにきらめいた。ハードな幅広のアーマー・リング 。年季が入って黒ずんでいる。不精に見えて、意外とお洒落だ。そう、彼らの大抵は身奇麗だ。いつも、こざっぱりした成りをしている。もちろん中には、無精髭を生やしただらしない輩もいるにはいるが。
セレスタンは、マッチを振り消し、ふぅー、と旨そうに紫煙を吐いた。こちらにすれば丁々発止の阻止行動も、詮ない悪戯としてやり過ごしたようで、別段気にした風もない。
立ち昇る煙が揺蕩って、夜気に吸い込まれるようにして拡散していく。沿道の件の一角は、酒を取りに行く者達で、相も変わらず賑わっている。
暇に明かして隣のセレスタンとボチボチ話した。だが、どうしても会話は途切れがちだ。皆と一緒にいる時は、ハツラツと気さくなこの彼も、特別饒舌なのでもないらしい。時折足を踏み替えては、意味なく夜空を見上げてみたり、日没後で暗いというのに、ズボンのポケットから黒いサングラスを取り出して、気もそぞろにかけてみて、当然のことだが、すぐに外してソワソワポケットに捻じ込んでみたり──。
( ……なにしてんの? )
エレーンは、ぽかん、と見物した。一人奇妙な行動を繰り返しつつも、セレスタンは、隣に並んで突っ立っている。二人きりにされたこの状態が気まずいのか、早くもこちらを持て余しているのか、どうにも居心地が悪そうだ。だが、ファレスに番を言い付けられて、どこへも行く事が出来ずにいる。
「あ、あのっ!──せ、せれすたん、て、頭の形、わりと、いいよねっ!」
気合を入れて、なんとか話題を振ってみる。言い慣れない名前が言い難い。けれど、セレスタンは、
「そ、そお……?」
所在なさげに足を踏み替え、煙草を挟んだ指先で、褒められた禿頭を掻くばかり。そうして立ち込める空疎な静寂──。辺りは十分に賑わしいのだが。
思わぬところで、奇妙な緊張を強いられる。なんかギクシャク、気詰まりだ。次なる話の取っ掛かりを求めて、隣の様子をこっそり窺う。
「あ!──そ、そのリングもカッコいいよねっ! せ、せれすたんって、すっごい、おしゃれ〜!」
ふと、セレスタンが顔を上げた時だった。
「見ろよ、奥方様だぜ〜?」
喧騒が、不意に近付いた。
「──へ〜? どらどら?」
質の悪い揶揄の気配に、そろり、と、そちらを振り向けば、赤い顔の二人組が、足を止めてこちらを見ていた。右の男が隣に訊く。「でも、なんで、こんな所に奥方様がいんの?」
「知るかよ俺が」
彼らは、どちらも首を捻って、釈然としない面持ちだ。左の男が案の定、へらへら笑って呼びかけてきた。
「どーしたのー? 奥方様〜? 一人寝が寂しくて遊びに来たのお〜ん?──なーんつってなあ?」
後の言葉で隣の男に笑いかけ、口笛で茶化して囃し立ててくる。随分酔っているらしい。数人が足を止めて振り向いた。別の男が訝るようにジロジロ眺めて行き過ぎる。不躾な野次。無遠慮な視線。四方から突き刺さる不審と冷やかしと値踏みの視線──。エレーンは、気まずく縮こまった。彼らに悪意はないのだろうが、見世物にされているようで居たたまれない。そもそも場違いなのだ、こんな所は。客を物色する商売女がウロウロ練り歩くこんな場は──。
ずい、と立ち塞がったセレスタンが、シッシ、と手を振り、「てめーら、あっち行け!」と、にやけた野次馬を追い払った。それに曖昧な笑みを返しつつ、ファレスが消えた沿道をソワソワやきもき眺めやる。これまでは、薄暗い夜道で大勢の中に紛れていたから、こんなに注目されなかったのに。──いや、上背のあるファレスが上からすっぽり被さっていたから、大して目立たずに済んでいたのだ。例えこちらに気付いたとしても、皆、見て見ぬ振りで行き過ぎて行った。あんな風に露骨にからかう者など、一人としていなかった──
爆音が不意に轟いた。
( ななな何事っ!? )
考え事をしていたエレーンは、ビクリと肩を震わせた。胸を押さえてドキドキしながら見回せば、丸太の組まれたかがり火で、景気良く火花が散っている。パチパチ弾ける色とりどりの閃光、あれは──。
唖然と口を開けて、突っ立った。
「は、花火まで、やるんだ……?」
なんか宴会っぽいとは思っていたが、あんな小道具まで用意しているとは。それにしても、すこぶるデタラメな閃光だ。種類も何もお構いなしに、炎に放り込んでいるらしい。周囲にいる野戦服達は、歓声を上げ、ゲラゲラ楽しそうに笑っている。うろついていた足を止め、腕を組んで見物する者、横目で眺めて行き過ぎる者。どの顔も、いやに物珍しげだ。しかし、本来、花火などというものは、一つずつ点火しては「まあ、きれい」などと周囲と言い合い、ほのぼのしみじみ楽しむ娯楽。あんなぞんざいな使い方をしたら、花火が勿体なくないか? わざわざ用意をしたんだろうに。
「ん?……はな……び……?」
エレーンは、ひくり、と頬を引きつらせた。心当たりがある。そして、嫌な予感がする。慌てて探せば、案の定、
「──あーっ!? アレって、もしかして、あたしのじゃ!?」
そう、見覚えのある大きな袋が、彼らの足元に転がっているではないか。しかもチャック全開で、ぱっくり口開けた袋の中身は、恐らく既にすっからかん。そこにあるのは、クタッとへたった無残な残骸。──と、又も凄まじい爆音が。見れば、今度は、夜空に派手な打ち上げ花火だ。あまりの仕打ちに、エレーンは、わなわな打ち震えた。
「あ、あたしの花火があ〜!」
ジタバタ指差し訴える。あの手恐いケネルから、嘘泣きしてまで死守したというのに。これでは、まるまる叱られ損。夜空の煌びやかな華を眺めて、セレスタンがぽっかり紫煙を吐いた。「こいつは運が悪かったな」
「──んもおっ! せっかく、あたしが持ってきたのにぃっ!?」
半泣きである。残念である。とっても楽しみにしてたんである。けれど、セレスタンは、
「諦めな。奴らに目ぇつけられたら、どうしようもねえよ。あいつら " あっち " の方もプロだから」
あっさり肩をすくめるばかり。そして、ワイのワイのやってる沿道を、顎の先で意味ありげにしゃくってみせる。あの賑わいの先にいるのは、件の物資配給部隊──て、あれの仕業かチョビ髭軍団!?
……どういう生業なのだ!? あの連中!?
被害を訴えるも取り合ってもらえず、エレーンは、「う゛〜!?」と唸ってイジイジべそかく。さすがに不憫と思ったか、セレスタンが慰めるように提案した。「まー、副長にでも言って、おんなじのを買ってもらうんだな」
エレーンは、むー、と膨れて、やさぐれた。もちろんである。当然である。絶対、弁償してもらおう、と心に決める。
断固、決めた。
そうこうしている間にも、色とりどりの華やかな花火が、ぞんざいに打ち上げられていく。それを見やってエレーンは、唇を噛み締め、気落ちの溜息をそっと零した。
「……どうかした?」
遠慮がちな声がした。ふと我に返ってそちらを見やれば、軽く背を屈めたセレスタンが、顔を覗き込んでいる。困惑した面持ちだ。
「な、なんでもない」
慌てて首を振り、エレーンは、ぎこちなく笑みを作った。
ワイワイざわざわ、喧騒が体を包み込む。周囲では、ひっきりなしに多くの野戦服が行き来している。──と、さわっ、とお尻に微妙な感触……?
内心( ひえ──っ!? )と絶叫し、エレーンは、とっさに飛び退いた。無我夢中で隣の腕にしがみ付く。そこにいるのは、言わずもがなのセレスタン。だが、彼は、何故だか同時に、ギョッと半歩飛び退(りやが)った。
「……な、なに?」
パチパチ忙しなく瞬いて、こっちがくっ付いた己の腕を引きつった顔で見下ろしている。体勢、引き気味、助けてくれるどころか、心臓の辺りを押さえんばかり。どうした訳だか、かなり、たいそうビビった様子。てか、何気に失礼な反応だ。
( なによお。そんなに驚かなくたっていいでしょー? )
エレーンは、ムッと顔を見た。あんな過激な頭のくせに、実は小心者なのか?
こっちが飛び上がって驚いたのか、痴漢の手は、すぐさま、パッと引っ込んだ。セレスタンが物問いたげな視線を向けてくる。被害を訴えたいのは山々なのだが、しかし、どうにも気恥ずかしくて憚られる。それで結局、
「あ……や、別に何でも」
文句は、ぐぐっ、と飲み込んで、引きつり笑いで首を振った。ここにいるのがファレスなら「不届き者を成敗せよ!」と即刻当り散らすところだが、しかし、あんまり馴染みでもないセレスタンを相手に、
「 痴漢に遭いました 」 と申告するのもどうなのか。彼の方でも、そんなこと言われたって困るだろう。
しかし、当然、エレーンの怒りは収まらない。
「お、遅いわね〜、女男ってば。そんなに混んでいるのかしら〜。( 意訳: もう! なにやってんのよ、あいつってば! )」
内心地団駄踏みながら、( とっとと帰って来い! ) と念を送る。
ファレスは、まだ戻って来ない。エレーンは、苛々沿道を見る。野良猫がいないと、発散出来ずにストレスが溜まる。セレスタンは、のんびり紫煙を吐き出して、心得たようにボチボチ言った。「……まあ、十五分ってとこだろな。急いで頑張って往復して」
「ん?」
十五分?
腑に落ちなげなこちらの様子に気付いたらしく、セレスタンも「……ん?」と振り向いた。
「なんで十五分も?」
エレーンは、( 何故に? )とセレスタンを仰ぐ。算出根拠が不明である。だって、話題の沿道までは、二十メートルくらいしか離れてない。どんなに行列してようが、物品引き渡しに手間取ろうが、精々五、六分が上限だろう。
( ──あ )の形に口を開いて、セレスタンがピクリと停止した。
時を止め、じっとり見つめ合う微妙な両者。急速に立ち込める硬直した空気。
「──悪い」
やがて、パッと目を逸らしたセレスタンが、直立したまま頭だけを下げた。何かを観念したようだ。しかし、
「なんで謝んの?」
エレーンには、何のことやら分からない。パチクリ瞬き、不思議いっぱいで小首を傾げる。「え?」と顔を上げたセレスタンと、唐突に、ばっちり目を合った。だが、
「──あ、ああ。いや、別に!」
セレスタンは、やはり、逃れるように目を逸らす。どうでもいいが、なんで今、顔が変な風に引きつったのだ? セレスタンは、はあ……と溜息で息を抜き、形のよい禿頭をポリポリ人差し指で掻いている。顔が赤い、ような気がする……?
( ぬ? なんなの? )
エレーンは、深く首を捻った。なんだか、よく分からない人だ。なんとなく不気味。だって、
目が合う。 → 目を逸らす。 → どうしてなんだか時々嘆息。
そのパターンの繰り返し。そして、その時々に、こっそり深呼吸とかも挟まるし。
彼の意図不明な言動に、エレーンの疑問はますます深くなるばかり。腕組み、しきりに首を傾げて、エレーンには皆目ちんぷんかんぷん──。
その時だった。
「──ぅおーい! いつまで油売ってんだよー、セレスタンー!」
どこかで聞いたようなダミ声がした。セレスタンが、ふと顔を上げ、ごった返す雑踏を見る。声だけで誰だか分かったようで、肩をすくめて応えを投げた。「……ああ、まあ、ちょっとな」
歯切れの悪い、ばつの悪そうな応答だ。すぐに、薄暗い混雑の向こうから、誰かがブラブラやって来た。こちらに近付いて来るにつれ、かがり火の炎の照り返しに、相手の姿が照らし出される。
「……おー? 奥方様じゃん? お前、どーしたの、これ」
赤い顔でこっちを見るなり、ひょいと背を折り、ひぃーっく、としゃくり上げてセレスタンに訊く。酒瓶下げた、おっちゃんロジェだ。セレスタンは、溜息交じりに目を向けた。「──ん、ああ。今、俺、副長にさ、」
だが、立ち止まったロジェの背中が、構わずどやどや押し退けられる。後続の者がいたらしい。津波の如くに雪崩れ込んできた一同は、「んん……?」とこちらを見やるなり、
「あれー、なんで、こっちにいんのー?」
それは、不思議そうな三つの顔。タンポポ隊の面々だ。
「奥方様―。こんばんわあー!」
長方形顔のあごひげオヤジが、上機嫌で覗き込んでくる。ご多分に漏れず酒臭い。そして、ひょい、とセレスタンの顔を見るなり、「おう、上手いことやったな、セレスタン」
うりゃ、と小突く。にやにや笑いの肘鉄で。当のセレスタンは困惑顔。「……いや、だから、そうじゃなくって、俺は、いきなり副長に」
「どこで拾ったのお? うりゃうりゃっ!」
「──だからっ! 拾ったんじゃなくって! てか、こんなん道端に落ちてるか!」
にやにや笑いが押し退けられて、ひょい、と別顔が現れた。復活したらしいおっちゃんロジェだ。これ迄の流れは一切無視して、「お?」と合点した顔で、こっちを見る。
「もしかして見に来た見に来た? 大将の " ヴォルガ " 」
どうでもいいが、なんで、こんなに楽しげなのだ? 一人でそんな飲んじゃって。いいないいなちょっとムカツク。
「──おい、副長に見つかったら、ぶっ殺されるぞセレスタン」
心配そうな忠告は、生真面目そうな角刈り。顔はやや赤いが、やっぱり、どうしても生真面目そうだ。集中砲火のセレスタンは、大忙し。
「だからっ!? そーじゃなくってっ! 俺はその副長にだな──!」
「あ、副長は〜?──副長―? 副長―?」
構わずロジェがキョロキョロ見回す。コイツは、もうダメっぽい。わななく拳をグッと握って、セレスタンが憤然と顔を上げた。
「ヒトの話を聞けえっ!」
ついに、キレたらしい。しかし、只今陽気な酔っ払いを相手に、そんなこと言っても無駄なのだ。ザンバラ髪を後ろで括った不精そうなダラダラ男が、構わず雑踏を見回した。「──あー又かよ、すーぐいなくなっちまうんだからなー、あの人はー」
無視である。
「まったく気紛れなんだから。連絡回すのも一苦労だぜ」
あごひげ男も、やれやれと同意。そして、上背のある面々にすっかり埋まったエレーンは、一人ぽつねんと蚊帳の外。ふと、それに気付いたらしく、ダラダラ男が、ひょい、と背を折り屈み込んだ。「あー、奥方様もなんか飲むー? それとも食う? 俺、何か持って来てやろうか」
くい、と片手を持ち上げる。等閑(なおざり)だったが、一応気遣い。だが、エレーンは、只今、気が気ではないのだ。
「……あ、……やっ、……う、うん……まあ、そのぉ……」
目をさえ合わせられずに上の空で返答。のぼせ上がった赤面を俯け、指の先をモジモジいじくる。というのも、ドレスを纏った商売女が、ひょい、と横から現れて、例の商売をおっ始めたからだ。しかも、事もあろうに真ん前で。女は、同性の目を気にした風もなく「あらーん、お兄さあん」とか色っぽい本職の品を作り、狙った獲物を藪の暗がりへと引っ張り込むべく、せっせと勧誘に励んでいる。
薄暗い地面を意味なく見つめて、エレーンは、ぷるぷる茹で上がる。際どい格好の女達は、今が書き入れ時とばかりに、せっせと野戦服達を誘惑している。男達の方も男達の方で、あたかも催眠術にでもかかったように、鼻の下伸ばしてヘラヘラ・フラフラついて行く有様。正直、あのムード満点大きなかがり火を見た時は
( すわ! キャンプファイヤーか!? )とウキウキわくわくしたものだったが、蓋を開けてみれば、何のことはない。そんな健全なものでは全くなかった。これでは、柄の悪い飲み会プラスααα──! ではないか。
いつまでも煮え切らないこちらの態度を、ダラダラ男は、しばらく停止で見ていたが、急かすでもなければ訝しむでもなく、軽く肩をすくめただけで話の輪の中へと戻っていった。あんまり覇気のない見かけの通りに、あっさりした性格であるらしい。雑踏を練り歩く彼女らの存在さえも、気にした様子は全くないし──。いや、それは彼に限らず、ガヤガヤ盛り上がっている面々も然りだ。
そう、なんだか不思議な光景だった。しどけなく際どいあの姿を見ても、誰一人として驚くでもなければ囃し立てるでもないのは何故なのだ? チョビ髭どもの手配の首尾にしたって、なんだか、いやに手際が良い。ケネルが開催を宣言してから、まだ幾らも経ってないのに。
ふと、それに気がついた。
──手慣れてる。
彼らは、この手の事に慣れている。
嫌な予感がした。もしや彼らは、事ある毎に、こんなフシダラな宴をしてるんじゃ──?
「……ケネルは、どこ?」
懸念が、思わず口から零れた。彼らが、しょっちゅう、こんな事をしているのだとしたら、
──まさか、ケネルも、ああいう女と!?
胸で両手を握り締め、息を呑んで振り返る。
慌てて周囲を見回した。タンポポ隊の面々は、若干キレ気味のセレスタンを取り囲み、やいのやいのと冷やかしている。彼らの注意は逸れていた。酔っ払いの集団は
" 上手くやったセレスタン " をからかうことに余念がない。
そっと彼らの輪から外れて、エレーンは、足を踏み出した。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》