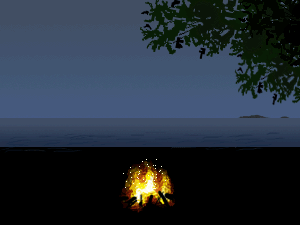
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部3章 6話17
( 前頁 / TOP / 次頁 )
頬が硬い何かにぶつかった。曲がるタイミングを間違えて壁に激突してしまった時のような、目から火花が飛び出しそうな手痛い不意打ち。けれど、それとは違うのは、今は曲がり角になど差し掛かっていないし、後頭部を掴まれて、後ろから強く押し付けられていることだ。
何が起きたか分からない。目の前の壁が僅かに動いて、エレーンは、我に返って振り向いた。突っ込んで来ていたあのバリーが、少し離れた地面の上で、仰向けに後ろ手をついて、呆然と尻もちをついている。何かに弾かれ引っ繰り返ってしまった、とでもいうような風情だ。あの面食らった面持ちは、本人にも訳が分かっていないらしい。
全てが動きを停めていた。喧騒さえも消えている。ただパチパチと燃え爆ぜる篝火だけが炎を赤々と不安定に揺らして、立ちこめる異様な雰囲気を静かに浮かび上がらせている。──いや、動いているのは、それだけじゃない。
銀星瞬く上空で、細長い何かがクルクルと二つ回っていた。それらが落下し、ガラン、ガラン──と続け様に音を立て、地面に跳ねて転がっていく。木刀だ。いや、木刀だった、というべきか。その無残な残骸は、歪(いびつ)にささくれ立った断面を残して、二つに折れてしまっている
。頭上に落ちかかる影があった。夜空を仰げば、誰かの腕が木刀を高く振り抜いている。つき上げられたジャンバーの腕を、肩の方へと辿ってくると、黒い頭髪が現れた。
「すまんな、バリー」
そちらを見やった黒髪が、淡々とそう告げる。バリーが弾かれたように立ち上がった。「あ、──ああ、いえ、隊長」
エレーンは、息を呑んで目を瞠った。そう、──そうだ。顔を背けたあの輪郭、腕を突き上げた体勢を戻して、おもむろに見返す深い黒瞳。あれは、
「──ケネ」
「何してんだ、あんたは!」
振り向き様、開口一番、問答無用で怒鳴られた。ケネルが、いつの間にか、そこにいた。珍しいことに真面目に怒った面持ちだ。服を払って立ち上がったバリーは、大儀そうに背を折って、脚を伸ばして突っ立ったまま、折れた木刀を拾っている。
「──だ、だ、だって──だってえっ! ケネル!」
エレーンは、口篭りつつも指差した。「だって、あいつ卑怯なんだもん! アドが怪我してること知ってるくせに、腕とか平気で叩いちゃってさあ! そんなの全然フェアじゃない! だから、あたしは──!」
ケネルが木刀を持ち替えて、切っ先を下げ、刀柄をグイと突き出した。
「な、なに……?」
エレーンは、ギクリ、とたじろいだ。この行動の意味するところが分らない。ケネルの顔色を上目使いで窺いつつも、内心、怪訝に首を捻る。もしや、これを「持て」というのか? でも、
──なんでよ?
まさか、アドルファスの代わりに戦え、と?──いや、まさか。
さっぱり訳がわからない。ケネルは、顎をしゃくって受け取るよう促してくる。腑に落ちないながらもエレーンは、渋々それに手を伸ばした。その途端、足元がグラリと大きく揺れた。ニュ──ッ、と横から片手が突き出る。大きく分厚い筋張った手だ。飛び上がって見返せば、真横にいかつい蓬髪の無精髭──?
アドルファスだった。座ったままで、右手を、ぬっ、と突き伸ばしている。そのまま木刀を大儀そうに受け取った。彼の物だったらしい。
逞しい体躯の大きな男が目の前にいた。太い左腕は、未だにこちらの背を支えている。木刀を受け取ろうとした際に体が自由になったから、後頭部を押し付けていたのは彼の右手だったらしい。そう、とっさに、あの腕で庇ってくれた。何故だかアドルファスは、逞しい上体を若干後ろに逸らしている。でも、どうして、あんな不自然な体勢で──はっ、とエレーンは、我に返った。いや、そんな事はどうでもいい。モタモタしていたら、ファレスに連れ戻されてしまう。そうだ、のんびり観察している暇はない。ヤツは、すぐにも飛んで来る!
「──あ、あのねっ、アド!」
慌てて口を開いた矢先、出し抜けに二の腕を掴まれた。ぞんざいに引っ張り上げられ、へたり込んでいた腰が浮く。腕を掴んでいたのは、案の定、ケネルだ。
「退いてやれ」
淡々とそう言い、顎をしゃくる。
( んもうっ! なによ! 忙しいのにっ! )
エレーンは、そわそわ気が気じゃない。眦(まなじり)吊り上げ長髪を翻し、いつヤツが飛んで来ることか──。猶予のなさにヤキモキしながら苛々口を開きかけ、はた、とそこに気が付いた。
──脚の上に乗ってると、アドルファスが起きられない。
「わっ!? ご、ごめんっアドっ!」
慌てて上から飛びのいた。アドルファスが脚をのっそり動かした。だが、どうした訳か、依然として地面に座り込んだままだ。
「……も、もしかして、重かった? あ、脚、痛かったとか?」
エレーンは、気を揉んで問いかける。アドルファスは、脱力したように項垂れて、一つ長く息を吐いた。いかつい不精髭の横顔が、僅かに眉をひそめている。どこか痛めてしまったのだろうか、勢いよく突進したから──。けれど、今は時間がない。早くここから連れ出さないと! 上体を屈め、逞しい肩に手を置いて、俯き加減の顔を覗いた。
「か、帰ろう? アド。──ね、一緒に帰ろう? こんな無茶なことは、もうやめて。ね、お願い」
肩を揺すり、逞しい腕を両手で引っ張り、あたふた忙しなく説得する。その時だった。
「──引っ込めえ! クソアマ!」
ギョッ、と心臓が縮み上がった。
唐突な罵倒に肩が震え、屈んだ上体が跳ね起きた。特徴を特定したその声は、紛れもなく自分一人に向いている。静まり返った会場からの、憎々しげな予期せぬ罵声──。
初めの内は、何の音だか分らなかった。地響きのような轟音が、周囲に不気味に立ちこめていた。唖然と周囲を見回せば、取り囲んだ人垣が敵意と非難を向けている。
「ふざけんな! こらァ!」
「ぶっ殺すぞ! てめえっ!」
口汚い罵声がすぐに続いた。夥しくも荒々しい殺気が、円形闘技場を取りまいていた。険悪な怒りが渦を巻き、怒号が飛び交い、様々な声が口々に、吼えるように面詰する。会場全体が激昂していた。烈火の如くいきり立ち、ぐるりを取りまく目を怒らせた顔、顔、顔──。
両手を胸で掻き抱き、エレーンは、オロオロうろたえた。場は紛糾し、騒然としている。罵声と野次が交錯し、会場全体が殺気立っている。本気なのだ。本気で自分をなじっている。本気で自分を咎めている。
( ど、どうしよう…… )
投げ付けられる罵詈雑言。酒が入っているせいか、攻撃の手は容赦ない。今、人垣に戻ったら、たちまち袋叩きに遭いそうだ。だが、あれだけ激昂しているにも拘らず、踏み込んで来る者は、誰一人としてない。この即席闘技場は、人垣の壁で出来ている。柵も、綱も、彼らの前に遮る物は何一つない。にも拘らず、最前列は、定位置を守って踏み止まっている。すぐにも、ここへ雪崩れ込んで来そうなものなのに──。今しがた聞いた注意事項が、恐慌をきたした脳裏を掠めた。"
一たび試合が始まれば── "
" なん人たりとも立ち入れない。 "
彼らにとって、ゲームを律する約束事は、いつ如何なる場合も絶対なのだ。不意に、はっきりと認識した。立ち入り厳禁、
──闘技場は不可侵。
四方から投げ付けられる粗暴で荒削りな疑いようもない敵意。それは、まさしく禁を犯した己自身への非難だった。予期せぬ相手に吊るし上げられ、凶暴な憤りの渦に呑まれて、エレーンは、なす術もなく立ち尽くす。殺伐と猛り狂った人垣を、どう宥めていいのか分からない。頭の中が朦朧として、もう何も考えられない──。
「馬鹿野郎! こんな所に出て来るんじゃねえ!」
一際大きな咆哮が上がった。
エレーンは、息を呑んで凍り付いた。いや、拳を振り上げて激昂していた面々までも、一瞬にして水を打ったように静まり返った。圧倒的なまでの凄まじい気迫、数十人からの怒声の渦を只の一声で凌駕した怒号
──。
地面に脚を投げ出したまま、黒い蓬髪が険しい目を向けていた。息を呑んだ衆人環視の只中で、アドルファスは、膝に手を置き、のっそり大儀そうに立ち上がる。この始末をどうつけるのか、会場の誰もが息を殺して注目していた。アドルファスは、ギロリと目を向け、悠然とこちらに近付いて来る。
( ──お、怒ってる、の? )
ギクリ、と、エレーンは、たじろいだ。
「あ、あのっ! 違う! 違うからっ! あたし邪魔するつもりとかは全然──っ!」
慌てて喘ぐように言い訳する。迫力に気圧され息詰まり、知らず後退った不注意な背が後ろのケネルに突き当たった。助けを求めてオロオロ仰ぐ。ケネルは、普段と変わる事なく淡々と事態を眺めていた。口を挟むつもりはないようだ。いよいよ気配が差し迫り、エレーンは、固唾を飲んで振り向いた。アドルファスは厳しい顔つきだ。すぐに目の前まで歩み寄り、ぬっ、とゴツい手を突き出した。
とっさに首を縮めて居竦まる。観衆が一斉に息を呑む。間を置かず、重たい何かが、ずっしり頭上に落ちてきた。
「──危ねえじゃねえか」
思わぬ穏やかな声がした。少しだけいがらっぽい、普段通りの鷹揚な声。エレーンは、薄目を開けて窺った。頭の上にあるのは、大きく分厚いアドルファスの手。
「ア、アド……?」
エレーンは、一気に気が抜けた。すっぽりと包み込むような手の平が、ぞんざいに頭を撫でている。緊張が解かれた人垣に、ざわめきが徐々に戻ってきた。荒れた意気は削がれている。だが、血気にはやった一時よりも大分下火になりはしたものの、そこには依然として、怒気と不満が拭い難く燻っている。
頭上から手を引き上げて、アドルファスは、会場を見渡した。鋭い双眸を僅かに眇めて算段するような面持ちだ。ケネルに鋭く一瞥をくれ、人垣に向けて顎をしゃくった。「──連れて出ろ」
様子を見ていた背後のケネルが、おもむろに身じろぎ、腕を引く。はっ、と、エレーンは、身構えた。
「──い、行かない! あたし行かないから! だって無茶よ、こんな試合は!」
足を踏ん張り、拒絶を示して首を振り、腕を引くケネルを必死で仰ぐ。はい、そうですか、と簡単に戻る訳にはいかないのだ。怪我人を戦わせるなんて、とんでもない。誰が見たって無謀な話だ。そうだ。こんなこと、いつまでも続けて良い筈がない。エレーンは、顔を振り上げた。
「戻るんだったらアドも一緒に!」
──だって、死んだ人がいる。
「だーい丈夫だよ」
意外にも、のんきな声が遮った。アドルファスが苦笑いで右腕をゆっくり回している。
「なあに、これっぽっち、なんでもねえやな。早く帰んな、お嬢ちゃん」
からかうようにそう言って、顎をしゃくって再び促す。ケネルは、構わず歩き出した。「気は済んだな? さ、行くぞ」
「え!? い、嫌だってばっ!?」
とっさに片手を突き伸ばし、アドルファスのシャツの腹を、むんず、と掴んだ。その手を素早くたぐり寄せ、逞しい首に手を掛ける。掴んだ腕はそのままにケネルが歩いたものだから、両方の腕が伸びきって、「大」の字になってピンと張る。逆方向に歩きかけていたアドルファスが、「ん?」と振り向き、足を止めた。唖然と立ち尽くすその顔が心持ち迷惑げに見えるのは、たぶん何かの間違いだ。
意図せず、のっぴきならない状況に追い込まれ、エレーンは、左右の男をあたふた見やる。会場のあちこちから失笑が漏れた。エレーンは、むむう……と赤っ恥の赤面で項垂れる。面目ない。他人様に笑われてしまった。どうやら見世物になってしまったらしい。こんなあられもない失態は、乙女としては不本意であるが、この手はどうあっても離せない。やむなし。
ケネルがふと足を止めた。怪訝そうに振り向いて、ギョッと顔を強張らせる。膠着状態に陥っていた救いようのないこの危機を、ようやく発見した模様。だが、すぐに、いつもの面倒臭げな顔になり、アドルファスの太い首からしがみ付く手を引き剥がし、暴れる腕を引っ掴む。再び歩き出したケネルを持てる全力で引き戻し、エレーンは、憤然と抗議した。
「だ、だめだってばっ! アドも連れて帰んないとっ! だってケネル、アドは腕が!」
「──おいおい、そう悲愴な顔をしてくれるなよ」
アドルファスが苦笑いしていた。「それじゃあ、俺が、まるっきり弱ええみてえじゃねえか」
情けなさそうにそう言って、逞しい腕をゆっくりと組む。
「よしてくれ。他人に哀れみをかけられるほど、俺は耄碌(もうろく)してねえぞ。──おう、こっちが済んだら、あんたの顔を見に行くからよ、一足先にテントの中で休んでな」
「──でも、アドっ!」
「" ヴォルガ " は、女子供が見るような代物じゃねえよ」
素気ない、だが、厳然とした口調だ。アドルファスは、算段するように無精髭を擦り、ああ、と気付いた様子で付け足した。「それに、ほれ。あんた、もう眠いだろ? 近頃、めっきり早寝だからな 」
「……なんで、そんなこと知ってるの?」
エレーンは、呆気に取られて見返した。まじまじと見られて、はっ、と不手際に気付いたらしい。アドルファスが慌てた様子で目を逸らす。その時だった。
「ほーら、チャッチャッとお退きになってん? 良い子はおネムの時間よん?」
一瞬立ちこめた静寂の後、ドッと爆笑が湧き起こった。唖然と辺りを見回せば、人垣がゲラゲラ笑っている。揶揄の上がった方向を眺めて、アドルファスが苦笑いした。「──あのハゲ、中々機転が利くじゃねえかよ」
笑いざわめく会場を見渡し、元いた沿道へと不精髭の顎をしゃくる。「早く出ろ、今の内だ」
「ああ」
ケネルが強く腕を引いた。とっさに足を踏ん張るが、ケネルは、全く構わない。結果、二本の轍を地面に残して、ずるずる無様に引きずられる。必死でその手に抗いながら、エレーンは、涼しい顔を睨み付けた。
「やだっ! 帰んないっ! アドと一緒でなきゃ帰んないぃっ!──んもう! 帰んないってばあっ!──アドーっ!」
拘束を振り解くべく、手足を振り回して本気で暴れる。あんなにも荒立っていた人垣は、平坦な落ち着きを取り戻していた。今はもう、どんなにジタバタもがいても、大して関心を示さない。どうやら、決死の救出行は、取るに足らぬ余興とみなされ、軽く受け流されてしまったらしい。肝心のアドルファスも蓬髪の後ろ頭をやれやれと掻いて、さっさと背を向けてしまったし。そして、
「おう! 調達班、仕切り直しだ! 換えの得物を用意しろ!」
吠えるように野太い銅鑼声を張り上げた。のんびり眺めていた一角が、はっ、と見るからに我に返った。バタバタと俄かに騒がしくなる。あの辺りに陣取っているのが例の部隊であるらしい。
「──さあてとバリー、再開しようぜ」
不精髭の横顔が、不敵な笑いでバリーを見た。
「揉んでやるから、覚悟しとけよ」
沿道では、ファレスが最前列で待ち構えていた。案の定、今にも咬みつかんばかりに柳眉を吊り上げ、両手を腰に仁王立ちしている。
ケネルは、出発地点へと向かっていた。腕を引っ張られて歩きつつ、結局連れ戻されたエレーンは、未練たらたら、肩越しに様子を振り返る。当のアドルファスは、うーん、と、のんきに伸びなんかしていた。
「──おい、副長!」
人垣が近付くなり、ケネルは、憮然と呼ばわった。「しっかり見ていろ。危なかしくて、しょうがない」
珍しく不機嫌だ。てぐすね引いて待ち構えていたファレスは、予定外に叱り飛ばされ、たじろいだ。
「──悪りぃ。ちょっと目を離したその隙に。中には入んねえよう、念入りに釘は刺しておいたんだが、」
そして、申し開きを一通り終えると、ギロリ、と鋭く振り向いた。「──こんの身のほど知らずのジャジャ馬があっ!」
一喝と同時に、頭を平手で掴まれた。上からグリグリ地面にめり込む程に沈められる。
「ナメくさった真似しやがって! 俺の話をなんにも聞いてなかったな!? 次やったら、ただじゃおかねえからなっ!」
更には耳たぶ引っ張られ、思う存分叱責される。言葉の意味が聞き取れないほどの大音量で。キン──と痛くなった左の耳を擦りつつ、エレーンは、口を尖らせて「だってえっ!」と会場を指差した。
「だって、あいつがアドのことをー!」
「" あいつが "じゃねえだろっ! まだ懲りねえのかアホンダラが!」
「──でもおっ!」
「イチイチイチイチ口答えすんじゃねえ!──来い! 見てられねえなら引っ込んでろ!」
怒り心頭に達したらしく、ファレスがぞんざいに腕を取る。たいそうな剣幕だ。ファレスに引き渡そうというのだろう、後ろのケネルが身じろいで、逆側の腕の拘束が緩んだ。エレーンは、チラと盗み見る。つまり、これは、
──脱出のチャンスだっ!
「痛たあいぃっ! 痛いってばあっ!」
すかさず暴れて、ここぞとばかりに全力で抗議。力任せに引っ張ったファレスが、ギクリと怯んで手を緩めた。
「──あ、ああ。悪り、」
今だ! 脱兎の如くに果敢にダーッシュ!
だが、地面を蹴ったその途端、又も首根っこ掴まれた。そろり、と肩越しに窺えば、
「まったく、油断も隙もないな、あんたは」
ケネルが溜息をついていた。むむ、やるな? これを阻止してみせるとは。
わりと反射神経がいいらしい。隣では、まんまと引っ掛かった野良猫が、握った拳をぷるぷる震わせ、頭から湯気を立てている。やばい。案の定、ツカツカ踏み出し、ゲンコを高く振り上げた。
「──こんのクソアマ〜っ!? 言ってる傍からチョロチョロと〜!」
「もういい、ファレス。俺がこのまま連れて行く」
ケネルが呆れた声で遮った。おおナイス、ケネル。とっても助かる。そーだ、暴力反対。絶対反対。平和に解決しようじゃないか!
「え?」
ケネルをとっさに盾にしていたエレーンは、「あれ?」と瞬き、目を返した。ケネルがいきなり両脇の下を掴んだからだ。
なに? と訝る暇もなく爪先がふっと浮き上がった。体がグラリと傾いて、目の前の首筋にしがみ付く。そして、はっ、と気が付けば、又もケネルの腕の上。左の腕に座っている。しまった、
( 逃げられくなった──!?)
エレーンは、愕然と見返した。ケネルは、いつもとなんら変わらぬ涼しい顔。いとも簡単に担ぎ上げられている。なんということ、ケネルのタヌキに先手を打たれた──!? いや、そんな事より何よりも、
「も、戻るっ! あたし、あっちに戻るからっ!──だってアドがっ!」
助けに行くのだ!
「──ねえっ! あんなの駄目よ! どう見たって、あれは卑怯すぎるでしょ! ねえ! 聞いてる? アドは怪我してるのよ!? なのに、あいつってば、そんなの全然お構いなしで!──ねえ、ケネル──ケネルってばっ!」
腕の上だが、ジタバタ暴れる、子供抱きの体勢が、情けないことこの上ない。ケネルは、あっさり抗議を無視した。
「副長、待機だ。すぐに戻る」
通り過ぎ様、ファレスに向けて指示を出し、次いで、腕組みで見ていた傍らのバパに、端的な口調で断りを入れた。「テントを借りる」
バパは、肩をすくめて「了解、隊長」と短く応じ、近くの部下に何事か指示して、 暗い林へと走らせる。静まり返った暗林に向けて、ケネルが足を踏み出した。伴い、人垣が左右に速やかに退く。エレーンは、やきもき振り向いた。
「……で、でも、アドが!? アドが〜!?」
引っ抱えられた肩越しに出来る限り身を乗り出して、エレーンは、片手を突き伸ばす。アドルファスの所に戻りたい。ケネルの肩を両手で揺さぶり、髪の毛を掴んで引っ張って、精一杯の抵抗を試みる。けれど、どんなに頑張って暴れても、ケネルは、もう目もくれない。何をしても無駄だった。足が地にさえ付いてない。会場のある沿道を外れて、ケネルは、木立の中へと踏み込んで行く。
歩くに連れて、人垣の隙間の揺れる視界で、アドルファスの蓬髪が遠ざかった。もう、こちらを見もしない。換えの木刀が届くのを待っているのだろうか、バリーと何事か談笑しながら、手持ち無沙汰そうに歩いている。向こうを向いたその刹那、不精髭のその頬に、照れ臭そうな苦笑いが束の間浮かんだのが見えた気がした。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》