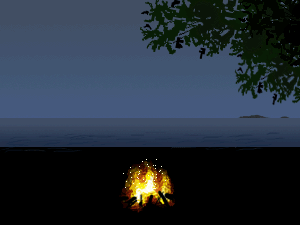
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部3章 6話18
( 前頁 / TOP / 次頁 )
ケネルに逆らう者は、いなかった。ケネルが足を踏み出した途端に速やかに道を開けた周囲の者の機敏さや、試合に割り込んだケネルに対して文句一つ言うでもなかった人垣の反応は言うに及ばす、日頃小煩いファレスまでもが、不機嫌な目を向けられた途端、少したじろいだようだった。皆がケネルを恐れている、肌に感じてそれが分かった。けれど、何がそんなに恐いのか、エレーンには、さっぱり分からない。確かに彼はぶっきらぼうではあるけれど、声を荒げたりせず静かだし、いつでもどこでも淡々としていて、性格的には穏和な方だとさえ思う。少なくとも争い事は好まない、そんな気がする。実際、ケネルが何かを無理強いする場面など、想像さえ出来ない。
けれど、周囲の者達の反応は、暗い夜道に群れ集ったあの大勢の男達を率いているのは名実共に彼なのだ、という紛れもない現実を認識させるに十分だった。そのケネルが一度やると言ったからには、
"どうあっても " やることになるのだろう。ケネルを止めるようファレスに捻じ込んだ時「無駄だ」とにべもなく突っぱねられた返答が、なんとはなしに飲み込めた気がする。けれど──。
「や、やっぱダメ……あんなのダメよ……!」
逃走防止にと担ぎ上げられた肩の上、エレーンは、どうにも思い切れずに唇を噛んでいた。頑張って目を凝らしても、アドルファスの姿は既に豆粒ほどの大きさだ。いや、それさえ生い茂る木立に邪魔されて、すぐに見えなくなってしまった。
見つめ続ける視界の先で、会場の喧騒が遠ざかる。エレーンは、焦燥に駆られて振り向いた。
「──あー! もーダメ! 我慢出来ないっ! やっぱ戻る! あたし戻るっ!」
「駄目だ」
前を見たまま、ケネルは一蹴。むぅ、と膨れて見返した。
「だって、アドは腕が──!」
「駄目だ」
「だって、ケネ──!」
「駄目だ」
歯牙にもかけずに、ケネルは却下。言下に無愛想にあしらわれる。なんという投げやり、なんという手抜き、なんという捻りのない返事なのだ。ついでに言えば、なんで、そんなに、せっかちなのだ? 堪え続けた癇癪が、これを境に爆発した。
「だって、あれじゃあ、リンチじゃない!」
「リンチじゃない」
「リンチよっ! だって──!」
「リンチじゃない。誰も、手出しはしていない」
「──そっ、それはそうだけどっ! でもっ!」
語法の誤りを平然と突かれて、とっさに口篭って反撃に詰まる。ケネルは、抗議を聞き入れない。けんもほろろで取り付く島もない。いや、ケネルに限らず誰もがだ。当のアドルファスでさえ例外ではなかった。まったく揃いも揃ってヤツらは頑固だ。
ケネルは、人一人分の体重を左腕のみで支えつつ、無脈略に伸びる若枝を右手で無造作に掻き分けて、膝まで伸びた下草に一定の速さで踏み込んで行く。後ろに乗り出しずり落ちた体を元の位置まで揺すり上げ、ほらみろ、と言わんばかりに、あてつけがましく溜息をついた。「──だから、先に帰れと言ったろう。"
ヴォルガ " の見物は、あんたには無理だ」
白けたような、辟易したような横顔だ。
「そっ、そっ、そんなんじゃないもんっ! ただアドが──!」
「アドルファスなら大丈夫だ」
ケネルは、言い分を素気なく遮り、ぶっきらぼうに太鼓判を押し「あんたさえ、いなければな」と無礼な条件をボソリと付け足す。
この当てこすりには、カチンときた。
「ほんとぉーにぃぃー?」
エレーンは、不審の眼差しで、とくと念押し。だが、ケネルは、
「本当に」
いけしゃあしゃあと、あっさり返答。いやに簡単に答え(やがっ)たので、ジトリと睨んで続けて駄目押し。
「絶対請け負うぅー?」
「絶対請け負う」
又も素気なく、ケネルは即答。何を言っても、問いと同じ言葉を用いて、淡々と必殺オウム返し。やる気のなさと怠慢さとが応答の仕方に隠しようもなく滲み出ている。前を向いたままの横顔が怒っているようにも感じられ、つられてトゲトゲしてしまう。エレーンは、ぶんむくれて顔を見た。
「ねー、もしかして、又なんか怒ってるでしょー!」
「怒ってる」
「嘘よ! 絶対怒ってるもん!」
「怒ってる」
「嘘よウソウソっ! あたし、ちゃあんと分かるもん! こういう時って、ケネルは絶対怒ってるもん! だって、あたしが何を言っても、さっきから──!」
はた、と、エレーンは、気が付いた。そう、さっきから肯定してやしなかったか? 内心で焦って念押しした。「──お、怒ってる、の? ケネル」
ケネルは、前を見たまま、淡々と応えた。
「ああ、怒ってる。当然だろ。中には入るな、と、ファレスが再三言った筈だな」
けれど、そう言うわりには、子供に言って聞かせるような淡々とした口調だ。もっとも、旗色が悪いという事実には何ら変わりがあるでもないので、用心しいしい、上目使いでブチブチ見た。
「だ、だってさー、──だって、あの時はさあ──!」
緊急事態だったのだ。
仕方がなかったのだ。急いでいたから。だって、アドルファスが転んで、あの卑怯者のヤツが──!
「" ヴォルガ " は、是非の審判の場だ。その結果は、あんたらの国での裁定にも等しい」
「でも、今、アドは──!」
「討ち手の好不調は様々だ」
呆れたように嘆息し、ケネルが間近で振り向いた。
「勝負事は水物だからな。運のあるなしも引っ包め、討ち手が抱える個人的な事情は、全て天が誂えた環境だ。勝敗は自力で勝ち取るものだが、そういう意味では、結果は神意と言っていい。" ヴォルガ " には互いの矜持を賭けている。討ち手は極めて真剣だ。それを──どうして、そんなに邪魔しようとするんだ」
「──だ、だってえ、」
遠ざかりつつある会場を、不安な思いで、じっと見つめる。そう、だからこそ、その矜持に殉じてしまいやしないかと心配になるのだ。だって、
──死んだ人がいる。
込み上げてきた苛立ちを、エレーンは、必死で押し殺す。そうだ。もう、たくさんだ。
" あんなこと " は。
言い知れぬ切なさが胸にザワザワ涌いてきて、眉をひそめて目を逸らす。けれど、ケネルは、逃げ道を塞ぐように深い黒瞳で問うてくる。再三邪魔したその理由を。エレーンは、唇を噛みしめ、項垂れた。こんなふうに見つめられると、だだっ子になった気分にさせられる。自分がとても詮無いことで拗ねて膨れているような──。視線で先を促され、渋々ながら口を開いた。「──だって、──あたしのせいだもんアドが腕を痛めたの。右の腕も左の腕も、どっちもあたしが──」
「そんな事を気にしていたのか」
ケネルが呆れたように口を挟んだ。あまりの無神経さに、とっさに心が反発する。
「だって! 危ないって女男が言ってたもん! 前にアレやって死んじゃった人がいる、って! ケネルも知ってるんでしょーこの話!」
人けなく暗い林道を会場に向かって歩いた際に、それを告げたファレスの言葉が不安を煽って蘇る。
『 過去に三人ばかり、くたばったヤツがいる 』
ケネルは、前を向いたまま、野草を踏み分け歩いている。エレーンは、応答を待って顔を見た。けれど、ケネルは、口をつぐんだままだ。
奇妙な間が空いていた。日頃率直なケネルにして珍しいことだ。下草を掻いていた右の手が拳を握っていることが、何とはなしに妙だと思う。ついでに確認しただけなのに、予期せず言いっ放しになってしまい、エレーンは、間近な横顔を怪訝に覗いて訊き直す。「ねー、知ってるんでしょ? この話」
ケネルは、ずり落ちた体を揺すり上げ、
「──さあな」
素気ない口調で、それだけ言った。
「なによ、それえ……」
エレーンは、膨れっ面でケネルを見る。散々待たされた挙句に、意味不明な怠惰な返事だ。けれど、それはそれとして、あの話を思い出したら、急に不安がせり上がってきた。もそもそ身じろぎ、ケネルの肩に身を乗り出して、後にした会場に目を凝らす。
「とにかくねー。あたしのせいで、アドが危ない目に遭うなんて嫌だもん。アドに何かあったら嫌だもん。だから、あたしは──」
既に遠く離れてしまって、視界は夜の木立一色。暗いばかりで何も見えない。歓声も叫び声も聞こえない。首筋に掴まった肩越しで、親指の爪をそわそわ噛んだ。「……ねー、本当に平気? 本当にアド、大丈夫?」
「大丈夫だ」
今度は、ケネルは、即答した。そして、素気なく付け足した。「アドルファスも、あんたにそう言ったろう」
夜に染まった木立の中で、踏みしだかれた下草が規則正しく鳴っていた。蒼暗く沈む木立の中を、ケネルは、淡々と歩いている。いつものように。
ケネルの口から言質を取り付け、気分が少し落ち着いた。いや、少しじゃない、大分だ。
不思議なほどに安堵していた。ケネルが請け負うと言うのなら、或いはアドルファスは大丈夫かも知れない──根拠はなくても信じられた。あれほど吹き荒れた焦燥が、綺麗に溶かされ消えていく。ケネルが言うなら大丈夫。そう、ケネルが断言したことは、何故か不思議と信じられる。
日焼けした温かい首筋に潜り込む。冷たい頬に掠った拍子に、伸びかけた髭がザラリと擦れて痛かったけれど、そんなことは構わなかった。すぐ近くにあるケネルの気配。ケネルがいれば大丈夫。ケネルがこの手を払いのけないのは知っている。そう、ずっと、ずっと、
ずっと、こうして欲しかった──。
規則的な足音と揺れ、何より確かな温もりが、疲れた体に心地良い。そう、今日は色々なことがありすぎて、なんだか、とても疲れてしまった──。
どこか遠くで、声がした。
指示を与える落ち着いた声。キビキビ答える別の声──。
うたた寝をしていたのは、どれぐらいの間のことだったろうか。いつの間にか、心地良い揺れが止まっていた。ぼんやりと目を開ければ、幻想的な蒼林に夜霧がうっすらと立ち込めている。漏れ降る月光のみの薄暗い中、前に立った野戦服が二人、真面目な顔で頷いて、暗林の奥へと機敏な足取りで駆けて行く。駆け去る背中を見届けて、ケネルが身じろいで背を屈めた。
ぬくぬくと密着していたケネルとの間に隙間が出来て、夜気がひんやりと入り込む。ケネルが肩から下ろそうとしているらしいのだ。起きぬけの頭が事態を理解出来ずに混乱した。心地良い居場所を取り上げられて、焦りと反発が込み上げる。どうして、そんな理不尽な真似をするのだ。内心でうろたえ、ケネルを見た。
「中に寝袋の予備が置いてある」
「──え?」
ケネルは、木立の先を眺めていた。暗く湿った夜林の地面によろめく足で降り立てば、静かに林立する木立に紛れて、大きく頑丈なテントが見える。
「眠けりゃ、広げて寝てていい。大丈夫だ、誰も来ない。周囲に歩哨も立ててある」
「ね、眠くなんかないってば!」
エレーンは、たじろいで言い返した。夜間の森林の澄んだ冷気が、凍えそうなほどに肌寒い。ありていに言えば、離れるのが嫌だ。だが、ケネルの応えは素気ない。
「そうか。それなら少し頭を冷やせ」
テントの入口までツカツカ歩いて、シートを片手でめくり上げ、中に入るよう動作で促す。エレーンは、困惑して見返した。「ケネルも、一緒……?」
「俺は戻る。勝手に出るなよ、分かったな」
抗う間もなく腕を取られて、入口から中へと押しやられる。この中に閉じ込めようとしている──そう認識したその刹那、鋭敏になった神経が、目前の危機を察知した。
──置いていかれる。又!?
深い亀裂の奥底から、ザワザワと這い上がってくる影があった。それは忘れた筈の戦慄だった。音も光も届かない淀んだ沼の深い地底に、一人引きずり込まれるような恐怖心。立ち竦んだ足がどうしようもなく震えて、エレーンは、慄然と振り仰いだ。
「行かないで! 一人にしないで!」
背を向けた上着を無我夢中で引っ掴む。意図せず堤防を打破したケネルが、立ち去りかけた足を止め、ふと肩越しに振り向いた。
「すぐに戻る。向こうが済み次第、迎えに来る」
「──いやよ! だって! だってケネル!」
この問題は、切実だった。他のどんな事よりも。どんな言質もあてにはならない。何故なら「すぐに戻る」と出かけた両親は、
──二度と戻って来なかった。
幼いあの日、訃報がもたらされたあの時以来、世界はすっかり様相を替えた。それまで当たり前だと思っていた退屈で平穏な明るい陽射しは、白々と下り降る空虚な日差しに様変わり、温かい団欒の窓の外に、たった一人で放り出された。焦燥さえも突き抜けた空虚で惨めな諦観が、ジワリと胸に込み上げて、エレーンは、細く息をつく。
……いつでも、そうだ。
いつも、いつも、いつも、いつも、散々騒いで、笑顔を振り向け、みんな 行ってしまうのだ。薄暗く冷たい闇の中、自分一人を残したままで。
どんなに日々を重ねても、それはきっと同じこと。何かの拍子にガラガラ崩れて、その都度一からやり直し。それまでの幸福は幻のように泡と消え、気がつくと、何もない振り出しに戻って、ドロドロした倦怠の中、暗い水底で一人膝を抱えて蹲っている。
胸を切り裂く残骸は、強い色彩を放って胸にある。すぐに戻ると出かけた親が二度と戻って来なかったことや、迎えに来た母親と友達が帰って行った後、一人で残された公園の夕陽がいやに赤くて胸が詰まったことや、妹も同然のあのアディーが寒い朝に一人ぼっちで自分を置いて逝ってしまったことや、かつては何十人もの使用人を使い信用と敬愛を集めた祖父が枯れ木のように痩せ細り窓硝子の割れた寒い部屋で誰にも看取られることなく亡くなっていたことや、明るい陽の当たる緑の庭で子供を抱き上げたダドリーの幸せそうな笑顔を見てしまったことや、その彼が喧嘩したまま失踪してしまったことや──そんなこんなの雑多で生々しい出来事が一度にいっぺんに押し寄せてきて、ザワザワと歯痒くもどかしい。それは、口の細いボトルに詰まった大量の水のようだった。悲しくて、苦しくて、すぐにも全部を吐き出したくて、逆さまにして強く振っても、ほんの僅かずつしか出てこない。たった一つしかない壜の出口は、それには如何にも小さ過ぎる。
「いや……行かないで……だって……だって……!」
切迫していた。混乱していた。言葉が上手く出てこない。どれから切り出していいのか分らずに、胸が詰まって、ひどく苦しい。
「──何を泣いているんだ」
面食らったように、ケネルが言った。両手で胴を捕えられ、少し驚いたような面持ちだ。
「だ、だって、……だって父さんが、……だって、ダドも……帰っ……なくて……なのに、ケネルが……!」
訴える声が上擦り、震える。手の甲で目を擦り、半ば魘されたように切れ切れの言葉ばかりを訴えた。子供じみたダダをこねているとは思ったけれど、口をつぐむのが恐かった。取り残されるのが恐かった。この手を離せば、すぐにでも、あの"影"に追いつかれ、奈落に引きずり込まれてしまうだろう。どこまで逃げても追いかけてくる圧倒的な底なしの恐怖──。
それは隠し続けてきた負い目だった。誰にも攻められる事のないように、丹念に、慎重に、隠し続けた、どうにもならないアキレス腱。幸せな者には、どんなに説明しても分からない。広い世界の只中に置き去りにされるあの恐怖は。こんなにも大勢の人がいるのに、どこにも拠り所のない空虚さは。"持っている"者は、往々にして、本当の意味でのその価値を知らない。それでもケネルにだけは分かって欲しくて、精一杯に訴える。ケネルは、溜息をついて首を振った。「落ち着いて話せ。何を言っているのか分らない」
弾かれたように怒鳴り返した。「──だってケネルがっ!」
「落ち着け」
「落ち着いてるわよ!」
ケネルの声は、いつもと同じように、ゆったりとして落ち着いていて、けれど、その冷静さが許せない。肩越しに会場方面を一瞥し、ケネルは、困惑しきりの面持ちだ。
「どうしたというんだ、いきなり」
後から後から涙が零れて頬を伝った。ケネルは、向こうの会場を気にしている。そちらに関心が向いている。身じろいだケネルに反応し、衝動に駆られて縋りついた。
「──いやっ! 置いてかないで! ここにいて!」
ケネルが難儀したように見下ろした。「……何が、そんなに気に入らないんだ」
何か言おうと口を開きかけ、溜息混じりで口をつぐむ。肩越しに会場を振り向いた横顔は、何を考えているのか分らない。子供のようにわあわあ泣いて、肩を震わせ、しゃくり上げた。迷惑だろうと分かっている。けれど、自分で自分が止められない。自分自身の立ち位置が自分で支えていられない。
ケネルは、何かを迷っているように一つ深く溜息をつくと、じっと目を閉じ、又、開けた。このまま戻ろうかどうしようか逡巡しているようにも見える。胴に強くしがみ付かれて、しばらく持て余したように見ていたが、ふと何かに気付いた様子で体を少し傾けて、右手でズボンのポケットを漁った。ゴソゴソ中を探っている。やがて「……ああ、あった」と顔を上げ、手を握ったままで抜き出した。
向き直り、左手を伸ばして、ケネルがこちらの手首を掴み、クルリと手の平を上向きにする。ケネルに向けて手を差し出している格好だ。何をしているのだと見ていると、握ったままの自分の右手をもってきて、その上でゆっくりと五指を開いた。
「……これ?」
手の平に載ったそれを認めて、エレーンは、訳が分からず見返した。日頃の彼の仏頂面からは想像し難い代物だ。自分の手の平を唖然と見つめ、ケネルの顔に目を戻す。ケネルは、困ったような、哀れむような面持ちだ。
「──ずいぶん痩せたな」
「え?」
言うなり、不意に手が伸びた。後ろ頭を無造作に掴んで、一歩踏み出しケネルが近付く。顔を傾け、上体を屈めた。左頬に柔らかな感触──。
エレーンは、息を飲んで目を見開く。一つ瞬いたその途端、涙が頬を滑り落ちた。
「大丈夫だ。どこにも行かない」
呆気に取られて、ケネルを仰ぐ。頭が軽く叩かれた。
「だが、結果を見届けるのが俺の務めだからな。──すぐに戻る。それまで大人しくしていろよ」
そのまま手の平を強く押し付け、ケネルは、反動を付けるようにして背を向けた。
ケネルの見慣れたジャンバーの背が、草木を無造作に掻き分けて、今来た道を戻って行く。それを放心したまま見送って、エレーンは、のろのろ左の手を持ち上げた。ケネルの唇が触れた頬を、ゆっくり指先で触ってみる。感触は、もうほとんど残ってない。
「……どういう、つもりよ」
少し震えた独り言が、他人の声のようによそよそしく響いた。頭がひどく混乱している。安穏としていた全てのバランスが失われ、気分がふわふわと心許ない。落ち着いた、というよりは、気が抜けた、といった方が現状に近い。
どこかで、ふくろうが鳴いていた。夜霧立ち込める蒼林で、下草が踏みしだかれて鳴っていた。右手をそっと開いてみる。包装の端が少しくたびれて丸まっていた。随分と長くポケットに入っていたらしい。手の平の上に載っているのは、白い薄紙に包まれた飴玉が一つ
。
どこか、ぼうっとしながらも、のろのろテントに振り向いて、約束通りに入口を潜る。そこには、音のない薄闇が閑散と広がっていた。ひんやりしている。誰もいない。壁の上部の四角い窓から、月光が音もなく降り注ぎ、床に影を落としている。仄暗い室内の様子が、月明りで見分けられた。これが短髪の首長の日常生活──丸めた寝袋が幾つかあって、彼の所持品であるらしい大振りで頑丈そうなザックと共に、左の壁に寄せられている。雑多な荷物、壁に無造作に吊られたタオル、折り詰めの残骸、床に落ちているアルミのコップ。大雑把で手慣れた生活の息遣いが薄闇の底に沈んでいる。ガランと広い空間に、闇がひっそりと漂っている。
見知らぬ場所に置き去りにされて、急に心細くなってきた。気分がそわそわ落ち着かない。寂しさがヒシヒシと込み上げて、発作的に踵を返して、入口シートを慌てて掴む。今なら、ケネルに追いつける筈だ。まだ遠くには行ってない。この一枚向こうにケネルがいる──!
後を追おうと踏み出して、ピクリと足が勝手に止まった。エレーンは、呆然と足元を見下ろす。
「行かれ、ない──?」
薄墨を刷いたような影の中、ぼんやり沈んだ自分の靴の爪先が見えた。それ以上は進めない。体が越境することを拒んでいるのだ。そこにあるのは、目には見えない境界線。ケネルに「出るな」と言われている。迎えに来るまで、ここから出るな、と。
のろのろ入口に背を向けた。無人の室内は閑散としていた。外光遮るテントの壁が、家具のない平板な床に濃く影を作っている。入口でぼんやり立ち尽くし、背を屈め、ブーツの靴紐に手を伸ばす。脱いだ靴を脇に寄せ、ぶかぶかの靴下で降り立てば、夜の床はひんやりしていた。
つい先程のケネルの行為を、頭の中で反芻しながら、冷たい床を踏みしめる。体を傾けズボンのポケットを漁るケネル。やたらとポケットがたくさん付いた暗緑色のケネルのズボン。ケネルが持ち歩いていたらしい白い薄紙に包まれた飴玉、そして──。ふと、右隅の壁で目を止めた。今、何かが動いた気がする。
光の届かぬテントの片隅、深くて黒い暗がりの中に、息を殺して目を凝らす。辛うじて見分けられる輪郭があった。壁沿いに床を這い、こんもり盛り上がった黒い影──。
正体を見分けて、ギクリ、と、エレーンは、戦慄した。寝袋や毛布が積んであるものとばかりに思っていたが、" それ " は収納してある寝袋より、もっと、ずっと遥かに大きい。もしや、あの騒ぎで酔い潰れ、勝手に入り込んでいたのだろうか。知らぬ間に両手を握って、エレーンは、固唾を飲んで後ずさった。
──誰か、いる!?
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》