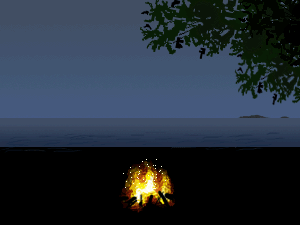
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部3章 6話19
( 前頁 / TOP / 次頁 )
色濃い影の中、それは、ぼんやりと浮かんでいた。指の長い大きな手が、背を向けた肩を掴むようにして抱き締めている。白いTシャツの広い背中。手足を縮めた裸足の足裏。呻き声が聞こえた。獣があげるような唸り声。切羽詰った苦しげな呻き。
長身痩躯の白い背が、壁の隅に転がっていた。胎児のように身を丸め、両手で我が身を抱いている。ただ酔っ払って寝ている、というような呑気な風情では、まるでない。荒い息をつきながら、ぐったり床に落ちているのは、柔らかそうな薄茶の頭髪。あれは──。
「ノッポ、君……?」
瞠目して息を飲み、エレーンは、おろおろ近付いた。背中側に膝をつき、背けた顔を恐る恐る覗けば、ウォードは、歯を食いしばり、瞼を硬く苦しげに閉じて、脂汗をかいている。驚き、うろたえ、上側の腕に、そっと手を置く。「……どうして、こんな、」
ピクリ、と腕が身じろいだ。右の肩を掴まれた──と認識したその直後、凄まじい痛みが肩に走った。あまりの痛みに息を詰め、ようやく相手を見返せば、いつの間にか起き上がっていたウォードから長袖の腕が伸びている。振り向き様に肩を掴んだものらしい。背後の窓からの逆光の中、威嚇の眼が爛々と光っていた。躊躇も情も、そこにはない。対象を正確に捉え射竦める捕食獣の獰猛な眼──。
「痛いっ!──放してノッポ君──!」
力が、緩んだ。こちらの肩を捕えたままで、息を詰めて停止している。しばらくして、怪訝そうに首を傾げた。
「……なんで、いるのー?」
いつものように飄々と訊くが、全力疾走の後のように、尋ねる声は途切れ途切れで発音するのもやっと、という風情だ。
「な、なんで、って言われても、あの〜……」
不審の色をありありと感じて、エレーンは、しどもど口篭った。まさか、悪さして摘み出された挙句に閉じ込められました──とは、情けなくて言えない。ウォードは、眩しそうに目を細め、顔を少し傾けて注意深く聞いている。肩で息つくその様は、瀕死の獣を思わせる。
「やー、あの──なんて言ったらいいのか、その〜」
辛うじて停止していたその影が、ガクリと突然くず折れた。ギョッ、と、エレーンは、取り付いた。
「──だ、大丈夫っ!? しっかりしてノッポ君! き、傷は浅いぞっ!?」
顔色失い、無人の周囲をおろおろ見回す。とっさに触れた硬い肩が、夜間の寒さに冷え切っていた。こんな肌寒いテントの中で、綿シャツ一枚で転がっていたのだろうか。誰に気付かれることもなく──。
仰臥した丸首Tシャツの白い腹が、荒く速く波打っていた。精根尽き果てたというように、ウォードは、顔を歪めて、ぐったり床に転がっている。手を翳すように額に置いた彼の指が、薄暗闇に、いやに長く、白く見える。予期せぬ事態に動転しつつも、腕を恐々揺すってみると、ウォードがうっすら目を開けた。焦点を無理に合わせるようにして目を眇め、眉をひそめて、ほんの僅か首を振り、訳が分からないといった顔。そして、再び目を閉じた。
「く、苦しいの? どこか、痛い……?」
横たわる大きな体を前にして、エレーンは、成す術もなくうろたえる。ウォードは、額に脂汗を浮かべて、口をきくのも億劫そうだ。いや、
「……悪かったねー。……オレ、行かなきゃいけない、と、思ったんだけどさー……」
唐突に詫びを入れた。必死で堪えた切れ切れの掠れ声。エレーンは、困惑した。彼と待ち合わせた覚えはない。けれど、本人は気に病んでいる。
「い、いいって! それより、どしたの? こんなに汗かいて苦しそうに──」
思い当たる節はさっぱりないが、曖昧に濁して返事をしておく。そんな事より異変が気になる。この有様は尋常ではない。冷たい床に寝転がったまま、ウォードは、息も絶え絶えに喘いでいる。酔っ払った誰かと喧嘩でも、と訝るが、彼のゆったりと大振りな長袖Tシャツに汚れはないし、顔や手足にも外傷等はなさそうだ。ならば、患部は見えない場所か? お腹が痛いのだろうか。それとも頭? それとも何か又別の──?
「──いつから、いたの? 一人で来たの? こんな暗い所で、どうして一人で」
途方に暮れて、おろおろ訊く。けれど、事情を彼に尋ねても、的外れな答えで要領を得ないし、こんな見知らぬテントの中じゃ、薬の類いがどこにあるかも分からない。天井を仰いだウォードの口が、だしぬけに小さく嘆息した。「……なんで、泣いたのー?」
「……え?」
「顔―」
ギクリ、と頬を手で隠す。泣きじゃくって擦りつけた顔が、斑(まだら)模様になっているらしい。しかし言えない、おん年十五の少年に、ケネルに置いていかれるのが寂しくて、わんわんしがみ付いて泣きました、とは──。傍から見れば身勝手極まりない先の醜態を思い出し、エレーンは、どんより項垂れる。だが、あんまり思い出したくない気恥ずかしい鬱にも、ウォードは、構わず畳みかける。
「何かされたー?……誰ー?」
"誰"と問われて、とっさにケネルを連想するが、それは事実と大いに異なる。正確に言えば「ケネルに泣かされた」訳ではなく、戸惑うケネルを前にして、こっちが勝手に大泣きしたのだ。身じろぐ気配に目をやれば、ウォードが大儀そうに肘を突き、顔をしかめて起き上がろうとしている。
「あ!? ノッポ君、起きない方が──!?」
慌てて肩をなだめるが、ウォードは、構わず右肘を突き、なんとか横臥の体勢をとった。
長い薄茶の前髪の下から、硝子の瞳が切迫した光を底に湛えて、じっと顔を見据えていた。深く透き通った薄茶の瞳は、真摯な色を湛えている。誤魔化しを許さぬ真っ直ぐな瞳。この年齢特有の壊れそうな繊細さと、力ある者が隠し持つ奔放な横暴さとが雑居した眼──。
「こ、これは、そのぉ〜……」
エレーンは、しどもど戸惑った。愚痴や冗談が通じるような和やかな雰囲気では全くない。これでは実質、詰問に等しい。全く予期せぬ真剣さだ。こちらの返答如何では、すぐさま殴り込みに行きそうな──。ケインやザイと対峙した昼の場面を思い起こせば、今でも薄ら寒い怖気が走る。重く淀んだ雰囲気に、得体の知れぬ危険を感じる。
「や、──ホント別になんでもないことなんだけど──ちょっとその、色々と手違いがあって──」
務めて普通の調子になるよう返事を濁した。実のところ、本件の下手人はザイだのバリーだの取り巻きだのだが、うっかり名など挙げようものなら、物騒な事件になりかねない。現に外では、一言名前が挙がったせいで大騒動になっている。面子や威信に重きを置く彼ら野戦服の間では、制裁だの報復だの敵討ちだのと物騒な攻防が日々行われているようなのだ。さっきの調子でこの彼にまで、報復云々などと言い出されては大変だ。いや、ウォードは何も言わないだろう。自分一人で勝手に決めて、自分一人で行動に移し、そして、たぶん誰にも言わない。
ウォードは、半身を起こしたままで、大儀そうに聞いている。いつものように突飛なことを言い出すでもなく、珍しく、大人しく聞いている。だが、いくらも経たぬ間に、支えの肘がガクリと崩れた。
「──ノッポ君っ!?」
うめいて仰け反ったウォードを見て、エレーンは、慌てて取り付いた。こちら向きに横臥して自分の肩先を掴んだ彼は、荒く息を喘がせて、しきりに呼吸を整えている。体が大分辛いらしい。エレーンは、膝立ちになった肩越しに、薄暗い出入り口を振り返る。「ま、待っててノッポ君! 今、誰か呼んでくるから!」
確か、歩哨がいるとか言っていた──。
出入り口へと縋る思いで立ち上がる。途端、手首が掴まれた。
「……いいー」
床に頭を落としたままで、ウォードが首を振っていた。エレーンは、唖然と絶句した。もどかしさが込み上げる。こんな時にまで、見栄を張ろうというのか──。
「なに言ってるの! そんなに辛そうにしているくせに!」
「あいつら、面白がって蹴るからさー」
「え?」
返す言葉を失って、苦しげに呻く彼を見る。確かに、彼らは品行方正とは言い難いが──。はっ、と、とある可能性が頭に浮かんだ。
「……もしかしてノッポ君、苛められているの?」
昼に見ている限りでは、そんな気配は全くないが、実は子供だからと侮って、不平不満の捌け口に──? 揶揄して笑う野戦服に寄って集って足蹴にされる彼の悲惨な有様が、ふとリアルに頭に過ぎって、怒りがむかむか込み上げた。──冗談じゃない。
( そーよ! 冗談じゃないわよ、あたしのノッポ君に! )
不穏に眦(まなじり)吊り上げる。近頃めっきり " お気に入り " である。いや、そうでなくても、そういう陰湿なのは許せない。( ささ、正直に言ってごらんなさいっ! )と有無を言わさず、ずずい、と膝を進めると、ウォードは、眉をひそめて口をつぐんだ。そして、何故だか白けたように嘆息し、
「……そーゆーんじゃ、ないけどさー」
心外そうな面持ちだ。ならば " 悪ふざけ " の範疇ということか。彼らの手荒い認定基準はさっぱり理解出来ないが。
「来たって、何も出来ないしー」
「で、でもねノッポ君。他にも誰かいた方が、心強いとか、何かとあるでしょ? だから、ね」
荷が重い、というのが本音だ。
「いいよー、邪魔だし。それに、あいつらにかまけて、オレが弱れば──」
唐突に、ウォードが " 自分の言葉 " で話を始める。
「攻めてくるしー」
瞠目して見返した。
「だ、誰? あの人達? あの人達が攻めて来るの?」
──やっぱり、苛めか!? 野郎ども!
安心させるように、エレーンは、大きく頷いた。「だったら、あたし、なんとかするから! ケネルに言って、そんなの、すぐにやめさせ──!」
「 " 世界 " 」
唖然と顔を見返した。
「セ、セカイ……?」
だが、本人は、言うだけ言って、疲れたように目を閉じてしまった。エレーンは、もう一度「セカイ……」と呪文のように繰り返し、面食らって彼を見る。「でも、──でもねノッポ君。やっぱ、誰か呼んだ方が、」
薄闇に沈んだ出入り口へ、そわそわやきもき腰を浮かせる。ウォードがうっすら目を開けて、片手を力なく持ち上げた。はっ、と気付いて、慌てて手を取ろうと身を屈める。だが、彼の手は、それを無視して素通りした。
左の腕を掴まれた、と認識したその直後、体が傾き、肘を強かに打ちつけた。その間、ウォードは、片手を伸ばして、こちらの腰を引き寄せる。強い力で引きずられ、驚愕して見返せば、寝転がったまま這い寄ったウォードが腹にしがみ付いていた。
「──ちょっと! ノッポくんっ!?」
相手の苦境は一瞬忘れて ( それとこれとは話が別よっ! )と"お気に入り"の髪を無下に引っ張る。いくら十五歳でも、どうなのだソレ──!?
( ふざけんなよ!? )と威嚇しつつも、焦ってアチコチ見回した。両手でしがみ付く幅広の肩を、力の限りに押し退ける。これがふてぶてしい野良猫のヤツならば、デコピンしてでも黙らせるトコだが、どこか繊細そうな青少年が相手では、そういう訳には、さすがにいかない。だが、がむしゃらにしがみ付くウォードの力は、途方もなく強い。
「……悪いんだけどー、」
とっさに身を捩った今しがた、強かに打ちつけた左の肘がジンジン痛い。彼が張り付いた腰から下は、身じろぎさえもままならない。ウォードは、頓着しなかった。
「もう少し、ここに、いてくれるー?」
( この期に及んで、なんの話だー!? )と成敗直前で見返して、エレーンは、はた、と気がついた。" 心細い " のだろうか、もしかして。ウォードは何をするというでもなく、両手でただただしがみ付いているだけだ。それ以上の進展はない。力だけを比べれば、こちらより余程強いのだろうに。
髭のないスベスベした頬。めくれ上がったズボンの裾からツルンと白い踝(くるぶし)が見えた。伸び盛りの若枝を思わせる長くしなやかな少年の足。今も尚休むことなく作り続けられているのだろう、すくすく育つ真新しい足。男というより " 男の子 " だ。図体ばかり大きくても。そこにあるのは、育ち盛りの子供の足。そう、寂しいのだろうか、ここに " 一人で取り残される " ことが。
「……ノッポ君」
腕が必死にしがみ付いていた。ケネルを前に泣いて喚いた今しがたの余韻が、ざわざわ胸に押し寄せた。潰れそうなほどに胸が痛む。理由は何故だか分からない。けれど、正確に捕捉した確信はあった。彼が抱く不安な心情、彼の恐れとざわめきが不意に身の内に流れ込み、寄る辺ない心が共鳴する。そう、それは、よく知る形をしたものだ。覚えがあった、この渇きには。
気付いた時には、ずい、と体を乗り出していた。
「わ、わかった! あたし、ノッポ君とここにいる! 絶対一人にしないから!」
敵視も一転、安心させるべく、うんうん頷き、全面的に誓いを立てる。共に戦う所存である。けれど、彼の反応はチグハグで、
「……大丈夫だよー、」
両手でしがみ付いた薄茶の髪から、くぐもった宣言がボソリと漏れた。
「潰さない」
決然と呟く。相手が目の前に存在しないかのような率直さで。その硬い声音は決意めいた悲壮ささえ伴っている。即席保護者を自負するエレーンは、反応叶わず絶句した。
( か、変わった人だ―…… )
全く応答になってない。大抵の受け答えには普通に自信があるのだが、( そういう応え方もあるのかー…… )と頭の中は真っ白だ。ウォードは「生まれたての、鳥の卵……ホーリーよりも、脆いから……」などと妙な呪文を唱えている。でも
" ホーリー "って馬の名前とかじゃなかったか。──まあいいか、向こうの試合が終わったら、ケネルもここにやって来る。
たじろいで見下ろす視線の先には、柔らかそうな薄茶の髪、長袖シャツの白い背中、首元の伸びた丸首Tシャツ──。目を閉じたウォードは、眉をひそめて気難しい表情だ。膝の上に頭を乗せて、じっとしている。その頭を撫でてみる。何をされているのか気付いているだろうに、嫌がるでもなく、振り払うでもなく、じっと目を閉じ、動かない。不思議な気がした。気紛れな風のようなこの彼が、大人しく体を休めている。肩で荒く息をつき、弱った姿を曝しながらも、それでも安心しているように見えた。手強い天敵から逃げ回った挙句に安全な居場所をやっと見つけたかのような。それとも、この無防備さは、例え攻撃を受けようと、捻じ伏せられる自信があるからか。
ふと、肩が冷え切っていたことを思い出し、とりあえず体を暖めなければ、と思い付いた。アドルファスから借りた分厚く大きな上着を脱いで、幅広い肩に着せ掛ける。ウォードが鋭く息を詰めた。
「ご、ごめんっ!? 痛かった!?」
悲鳴混じりで、自分が飛び退く。「──苦しいのっ? どっか痛いっ?」
心臓をドキドキ言わせつつ、しがみ付いた肩をおろおろ撫でる。ウォードは、激痛を堪えているようで、苦しげに歯を食いしばっている。痛みの出方には波があるらしく、ピークを迎えると、息を継ぐにも難儀する。どうしたら、いいのだろう、こういう時は──。己の無力さに苛立って、エレーンは、親指の爪を噛み締める。何か自分にも出来ることは──。はっ、と顔を振り上げた。
「──い、い、い、」
人差し指を突き出して、ぱっと片手を振り上げる。ウォードが、むっくり、顔だけ起こした。
「痛いの痛いの飛んでいけー!」
硝子のような綺麗な瞳が、こちらの顔をじっと見る。
へたっ、と無言で突っ伏した。
( ──やっぱ、だめかー!? )
今のナシ! と引きつり笑いで即刻退散。ならば、と彼の前髪はね退けて、額をむんずと鷲掴む。
「ねねねねねね熱でもあるのかしらー!?」
もう泣きたい。因みに、熱も大してないようだ。こうなると、何故こうまで苦しんでいるのか見当もつかない。
「──どうしたら、」
こんなに酷い有様なのに、人を呼ぶのは嫌だと言う。強行すれば、人を呼びに行っている内に、どこかへいなくなってしまうだろう。ウォードは、更にぐったりし、力尽きたように肩で呼吸を繰り返している。こんなに痛がっているのに、何も出来ない。気が急く。歯がゆい。いても立ってもいられない。やはり、誰か呼んで来た方が──。
「……せなか―」
「え?」
ぶっきらぼうな声がした。はっとして見返せば、ウォードがむずかるように腹に顔を擦りつけてくる。白くて長い指先が寝巻きをシッカと握り締めている。混乱した頭がようやく事態を把握した。
「──あ、背中?」
彼の肩を抱え込むようにして、広い背中に手を伸ばす。
「ノッポ君、背中が痛いのねっ!? わかった任して! 任しといてっ!」
無言でしがみ付く広い背を、懸命に擦る。しゃかりきに擦る。問うてからかなりの間があったが、今の「せなか―」は先程の問いへの答えだったようだ。しがみ付いた袖口が肘の上までめくれ上がって、彼の滑らかな腕が露出している。
「──あれ?」
意識に何かが引っ掛かった。何かが変だ。違和感がある。それに気付いて、エレーンは、ぽかん、と見返した。
──治ってる。
彼は腕を怪我してた筈だ。ケインと揉めて皆の所へ引き上げる時、腕から血が流れていて、気になって気になって仕方がなかった。なのに、今は跡形もない。
( ……さ、さっすが違うわね、若い子は )
エレーンは、引きつり笑いで、うーむ、と唸った。なにせ花の十代だ。成長盛り伸び盛り、損なった肉体の再生力が違う。ああ、そういや自分も、野草で手とか切ったっけ──。何となくつられて、自分もモソモソ右手を見る。「さっすが、あたしなんかとは回復力ってもんが違うわ──え?」
先回りして己自身に言い訳し、エレーンは、ぱちくり瞬いた。
「……ない?」
確か、昼に切ったのに。
腑に落ちない思いで( ……どこだっけ? 左手だっけ? )とパーにした両手を表、裏と見直して、エレーンは、何故に? と口を開けた。傷がない。どこにも。
しばし、不思議いっぱいで、まじまじと見やり、パッと頬に手を置いた。
「いっや〜ん! あたしってば若いぃっ!」
キャッキャッと一人で照れまくる。"少年"の仲間に予期せず入れて、たいそう嬉しい。そんな場合ではないのだが。
「……なんか、ラクー」
「え?」
一人ウキウキ小躍りしていたエレーンは、膝からの声に我に返った。「あ!──そ、そおっ?」
慌てて、満面の笑みを作る。
「それは良かったわ! うん良かったっ!」
柔らかな髪に手を伸ばし、母のような優しい気持ちで、ゆっくりと慈悲深く撫でてあげる。
「人の手にはねー、体を癒す力があるのー。だから、治療をすることを " 手当て " っていうのよー」
気分が良い。そこはかとなく。ここぞとばかりに、おん年十五の少年に、由来を説明してあげる。
「……へえー」
関心なさげな反応で、ウォードが顔を擦りつけた。猫が甘える仕草に少し似ている。
「なあんちゃってねー。本当は、この話、アディーから教えてもらったんだー」
「……誰?」
顔さえ上げずに、ウォードは、怪訝そうに訊き返す。
「ああ、アディーっていうのは、前に勤めていたラトキエのお屋敷で、あたしが世話を担当してた娘で、あ、重い病気だったから。……よくこうして背中をさすってあげたっけ。食べちゃいたいくらいに可愛くて、細くって、小さくって、妹みたいで、でも、なんか母さんみたいな、あったかいところもあって、」
「──あー、」
ウォードが合点した声で割り込んだ。「あの、おでこのおかーさんのことかー」
「お、おでこの、おかーさん?」
エレーンは、絶句で固まった。彼の言葉は、時々理解を飛び超える。じれったそうに、ウォードが言った。「だから、いたでしょー? エレーンがいたお屋敷に」
──いたっけ? そんなの。
背中をすりすり擦りつつ、エレーンは、ふーむ、と上目使いで思案する。よく、わからない。
「おでこでー、目がでっかくてー、ちっちゃい子供がいてー、アドに斬られそうになってー、でも、エレーンが代わりにアドに斬られてー」
「サビーネのこと?」
ようやく該当人物に思い当たった。だが、何故にいきなり、サビーネの名前が出てくるのだ? てか、こんなやり取り、前にもしたことあるような……? いや、けれど、そもそも全く別人の話なのだ。エレーンは、困惑して首を振った。
「ううん、違うわ。アディーは、二年も前に亡くなっているもの」
この目の前で逝ったのだ。危篤を知らされ、駆けつけた別棟で。春も浅い寒い朝、ひっそり冷たくなっていた。たくさんの友が詰めていたのに、昼も夜も連日離れに詰めていて、なのに、あの寒い朝に限っては、誰も起きてはいなかった。だから、あの娘は誰に看取られることもなく──
「でも、同じ人だしー」
飄々とした断言が、過去に浸りかけた思考に割り込む。けれど、彼の言う「同じ人」の意味が分からない。確かに、似ている、とは思ったが──。
そう、あの二人は、とても、よく似ている。大きく澄んだあの目だろうか。ほっそり小柄な体型だろうか。いや、外見ではない、雰囲気だ。彼女らが纏うあの
" 質 " だ。無論、二人は全くの別人。"同じ人"だなんて、ありえない。馬耳東風で、ウォードは言う。
「そっかー。"ラトキエの病人"かー。──あー、なるほどねー。だからアド、あのおねーさんのこと斬ろうとしたのかー」
「え?」
ギクリ、と頬が強張った。
「──な、なに? どういうこと? "だから"っていうのは、どういう意味?」
「アドの子供、そいつに殺されちゃったからさー」
呼吸が止まった。何を言っているのか、理解出来ない。アディーは誰も殺してなどいない。細くて非力な病人に、そんなことが出来る筈もない。そもそも、そんな過去があったなら、あんなに無垢に笑えはしない。もちろん、サビーネだって、それは同じだ。
「なるほどねー。だからアドのこと呼んだのかー」
「──え? よ、呼んだ、って、」
いったい、何を言っているのだ。
「だから、アドを呼んだの、あのおねーさんの方だからさー」
絶句した。理解出来ない言葉で、彼は話す。けれど、この上なく正直に。そう、不思議とそれは分かっていた。彼は " 本当の事だけ "
言っている。嘘というものを、ウォードはつかない。自分を曲げてまで嘘をつくという行為自体に、そもそも価値を認めていない。
「どーしても行く気―? トラビアに」
不意に切り込まれて、鳥肌が立った。何を考えているのか分からぬ瞳が、じっと射竦めるように見つめていた。
「行くの、やめればー?」
「……え」
「あの領主たぶん、あっちで死ぬよー?」
背筋がビクリと飛び跳ねた。不吉な忌み語を躊躇なく使う。わざわざこちらを傷付ける為に使っているような悪意にさえ聞こえて、思わず顔を見返してしまう。
こちらを見据える硝子の瞳が、強い輝きを放っていた。反抗的な、というよりは、獲物を追い詰めるような猛々しくも冷淡な色だ。不機嫌そうに断言し、ウォードは、やはり、意地悪く続けた。「要塞の階段を登りつめた所で、矢で胸を射抜かれてさ──」
「やめて!」
エレーンは、強く遮った。その名を聞くのは突然過ぎて、心の準備が出来ていない。こちらの状況を気遣ってか誰もその話はしないから、出し抜けの衝撃が無防備な心を尚のこと抉る。
──あのなあ。そのまま餓死するつもりかよ?
あの声が蘇った。
目を見開いて、息を飲む。いったい、何度聞いたろう、呆れたようなあの言葉。懐かしいあの声を。
硬く閉じ込めた筈の封印が、するする、みるみる解かれていく。どこかの悪戯小僧のような得意げなあの顔が蘇る。いつも何かを企んでいそうな抜け目なさを湛えた瞳。両手を腰に大袈裟に溜息をついた癖っ毛の彼の呆れた顔。それでいて、手負いの猫を諭すかのような慎重で真剣な彼の眼差し。
──大丈夫だって! こう見えても、飯作りは上手いぜ俺。ほら、うちの爺(じい)と婆や、もう結構な年だからさー。その分俺が頑張んないとな。
彼は、まだ幼い頃に、身の回りの世話をする使用人を二人だけ連れ、故郷のノースカレリアを飛び出していた。領家の所有する商都の邸で、仲良く三人で暮らしていた。止める間もなく記憶の奔流が溢れ出す。
──食ってみなって。騙されたと思ってさ。ほら、一口だけでいいから。
締めきったカーテンを無造作に開けて振り向いた、あの笑顔がいっぱいに広がる。暗く淀んだ寮の部屋、開け放たれた木枠の窓、流れ込んでくる新鮮な風、寮の窓から降り注ぐ、眩しいほどの、いっぱいの光──。
「……ダド、リー」
指先が震えた。呼吸が浅く、苦しくなる。温かく苦しい記憶の濁流、その渦の只中に呑まれてしまいそうになる。けれど、今、ウォードの前で、悲嘆にくれて浸ってしまう訳にはいかない。彼はまだ子供なのだ。慌てて、けれど細心の注意を払って、懐かしい残像を押し退けた。
「──まだ分からないじゃない、そんなこと!」
声が震える。牽制を込めて言ったつもりが、怯んでしまって、自分で期待したほどには強い口調にならなかった。何故、彼が突然そんなことを言い出したのか分からない。得体の知れぬその意図に、逃げ出したい衝動にとっさに駆られる。気弱な心に急かされて、知らず知らず早口になる。
「そ、そうよ、そんなこと誰にも言えないじゃ──」
「でも、たぶん、そうなるよ、」
ウォードは悪意なく、微かな希望をも打ち砕く。
「それ、もう見えてるからさー」
「──やめて! ウォード! 聞きたくない! いい加減なこと言わないで!」
追い払うように首を振り、耳を塞いで、硬く、硬く目を瞑る。ピントのずれた変わった物言い。けれど、それには薄々気付いていた。彼の言葉は、いつだって正しい。恐ろしいほど的確に、物事の核心を射抜いてしまう。無造作に、恐らくは無意識に。そして、今日は、いやに意地悪に。心がピリピリ警戒していた。涙さえも溢れてこない。それは不思議なことだった。切迫の度合いを比べれば、目前に迫ったこちらの方は、さっき思い出した過去の事柄の比ではないのに。ケネルにしがみ付いたあの時は、あんなにたくさん泣けたのに──。そうか、と思った。今更だ。
──気が緩んでいないと、人は、泣けない。
無神経な彼を煩わしく思い、いっそ背を向けてしまいたかったが、出来なかった。膝の上にウォードがいるからというよりは、体が硬直して動けないのだ。
「──オレは、」
ウォードの鋭い瞳から、追い詰めるような色が消えた。「……でもオレ、嫌だったからさー、エレーンが、そういうので泣くとこ見るのは」
困ったように目を逸らした。
「──ごめん」
簡単な一言だったが、精一杯の謝罪のようだった。けれど、心の中が掻き乱されて、どう答えていいのか分からない。
沈黙が降りた。
長く、重苦しい沈黙だった。窓明りのみの薄暗いテントに、時が音もなく降り積もる。ウォードは、口をつぐんだままで、何かを考えているようだ。だが、何を考えているものか、心は、やはり窺い知れない。
夏虫の声だけが、いやに聞こえる。エレーンは、唇を噛んで、じっとしていた。拳を握って堪えていても、体が勝手に震えてしまう。心が硬く凍て付いていた。無意識の鋭い刃で又傷付けられるかも知れない、その恐怖でビクビクする。警戒していた。十五の子供を。彼が紡ぎ出す次の言葉を。そう、そんな事を言うものだから、すっかり、はっきりと思い出してしまった。あの声、あの髪、笑い方。試すように覗き込む、悪戯っぽい瞳のことも──。
「──オレさー、黄色い花が好きなんだー」
唐突な言葉が静寂を破った。途方に暮れたようなその声に、はっ、と視線を膝へと戻す。ウォードが取ってつけたように先を続けた。「祭の時、母さんにもらってさ、すごく綺麗だと思ったからさー」
懸命に選んだらしい独り言めいた後講釈。無理に引っ張り出してきたのだろう虚ろな声が、どこか余所余所しく、ぎこちなく響く。視線を逸らした弱り果てたような横顔。今しがたの意地の悪さが嘘のような、おどおどした様子が伝わってくる。エレーンは、怪訝に見返した。もしや、気遣っているのだろうか、この彼が。他人の事には構わない傍若無人なこの彼が──?
戸惑いながらも返事をした。「……そ、そっかー。そんなに綺麗だったんだー。あ、どういう花?」
早くあの話題から離れたい。あれは嫌なのだ。聞きたくない。
「くすぐったい感じのヤツー」
「……ふ、ふーん」
自信たっぷり即答されたが、イメージがさっぱり湧いてこない。"くすぐったい"ってなんなのだ? まったく彼は変わっている。内心困惑してやり過ごし、差し障りのない話題に切り替えた。「──あ、ねえ、ノッポ君のお母さんって、どんな人? 今、どこで暮らしているの?」
口をつぐんで、ウォードは、少し考えた。そして、しばし沈黙した後に、ポツリと無感慨に呟いた。
「いなくなったー」
「……え?」
どういう意味だろう、" いなくなった " というのは──。どぎまぎ窺い、ギクリ、と顔が強張った。
初めて、彼の本当の顔を見た気がする。張り詰めた緊張と漂う不安。怯え震える途方に暮れた子供の顔──。もしや、失踪したとか、そういうことか?
内心うろたえ、けれど、さりげなさを装って話を替えた。「そ、そっか!──あ、それでタンポポなんだー。ほら、前にノッポ君、あたしに持って来てくれたじゃない」
けれど、ウォードは、「──そーじゃなくってー」と面倒そうに訂正する。
「あの時は黄色、あれしか近くになかったからさー。もっと、ふわふわしたヤツでー、丸くて小さいポンポンが、枝の先にいっぱい付いててさー」
「あ、もしかして、ミモザのこと?」
カナリア・イエローのふわふわの綿毛。確か、あの地方には、豊穣祭の折にミモザを配る和やかな風習があった筈だ。もらったミモザを片手に眺め、母親に手を引かれて歩く小さな男の子の姿が思い浮かんで微笑ましい。彼も幸福な子供時代の記憶を持っていたのだ、と内心安堵の息をつく。ウォードは、素気なく首を振った。
「……さあねー」
名前に興味はないらしい。しがみ付いた腹にむずかるように潜り込む。こちらの機嫌を確かめて、一応安心したようだ。体を苛む苦痛から逃れて、もう疲れてしまったのかも知れない。
それきり、会話が唐突に途切れた。ウォードは、ぐったりうつ伏せている。寝た振りをして耳をそばだてているのか、本当に眠ってしまっているのか、よく分からない。
急に一人きりで取り残されて、立ち込める闇が重みを増した。静けさが肩に圧し掛かってくる。密度の高い真っ暗で深い穴の底に、すっぽり嵌ってしまったような閉塞感。息苦しさを不意に覚えて、四角いメッシュの窓を仰げば、暗い星空が広がっている。何かが光った。自分の寝巻きの胸元だ。
ペンダントの翠石だった。お守りにしている翠石の欠片。月光を反射して、それがキラキラ光っている。何かを切実に訴えかけようとするかのような鮮やかで強い石の煌き──。その輝きに魅入られて、手の平に包んで握り締める。
ドクン、と何かが息づいた。
警戒する間も、身構える間もなかった。刹那、強烈なビジョンが視覚に直接飛び込んでくる。見たこともない風景だ。それは、目の前の現実を一切無視して、見開いた視界いっぱいに、ひどく鮮明に広がった。
閑散とした、夜の砂漠だ。
全ての輪郭がくっきりしていて、荒涼として、もの寂しい。何処だろう、ここは──。
血のように赤い大きな月と、底のない常夜の空、どこまでもどこまでも果てなく続く黄色い砂丘に、真紅の美しい巨大な蝶。ポツンと、そこにウォードがいた。見渡す限り、誰もいない。何の音もない。彼一人だけだ。
乾いた荒野に、広大な砂漠に、一人でじっと佇んでいた。指の長い手の平を広げ、何もない自分の手を途方に暮れたように眺めている。それは、何処までも一人ぼっちの光景だった。彼の頭上には赤く美しい巨大な蝶が、ひらひら、ふわふわ舞っている。不思議と分かった。あれは彼のお母さんだ。彼のことが心配で、よそへ飛んでいくことが出来ずにいるのだ。彼の方は、あの蝶が母親だとは気付いていない。それでも気になって気になって仕方がない。ここで動くものは、それしかないから。けれど、腕を伸ばして、長くて黒い蝶の脚をあの手で掴んでしまったら、巨大で美しい真紅の蝶は、たちまち灰色に凝固して、端からパラパラ崩れ去ってしまうだろう。
重厚な地鳴りが低く聞こえた。地底の暗がりで頭をもたげ深層で兆した奔流は、呻き、蠢き、波打ち、淀み、波状に打ち寄せ、緩やかな起伏で大きくうねって全ての音を押し流し、瞬時に膨れ上がっていく。
無音の世界に、耳をつんざかんばかりのけたたましい叫喚が噴き出した。入り混じった幾つもの叫び。男の声、女の声、子供の声、老人のしゃがれた甲高い声。声は膨張し、木霊していた。無数の声が吼えるように何かを叫び、飛瀑のような轟音が猛々しい奔流となって世界全てを呑み込んでいく。何を言っているのかは分からない。けれど、一斉に発声を始めたそれらの声は、同じ言葉を叫んでいる。それは怒りのように聞こえた。嘆きのようにも聞こえる。悲しみのようにも祈りのようにも聞こえる
。絹を裂くような悲鳴が上がった。蝶の脚を、ついに掴んでしまったのだ。
蝶がポロポロ崩れて死んでしまうと、赤い月がどろりと崩れて溶け出した。粘性の高いその赤が暗い天井を満遍なく覆い尽くし、地表に向かい、ねっとり滴り落ちていく。あたかも透明な水槽を満たす赤いペンキであるかのように。見る者の視界を覆うその赤は、みるみる全てを呑み込んでいく。彼は、足元に押し寄せる粘性の高い赤い波に呑まれて、腹まで浸かり、首まで浸かり、酸素を求めて仰向いた顔の真横の耳まで浸かり、もがき、溺れ、窒息していく。逃げ場など、初めから何処にもない。やがて、動きを止めた溺れた体が底の方へと沈んでいき、コツン、と底に突き当たったら、この世界は終わるのだ──。
「……な、なに?」
はっと唐突に我に返り、エレーンは、ドギマギうろたえた。又、うたた寝でもしていたのだろうか。いや、眠ってなどいない。確かに、はっきり目覚めていた。今のは、いったい何だろう。まぼろし? 錯覚? けれど、まぼろしにしては生々しく、錯覚にしては、いやにリアルだ。いや、これは、
──" セカイ " ?
ウォードが言っていた、これが " セカイ "? 何故、あんなものが見えたのかは分からない。けれど、唐突に理解した。あの場こそが彼が度々口にした、あの
" セカイ "──彼が存する、もう一つの世界だ。
胸に滑り込んできた残照は、強く鮮やかに焼きついた。呆然と視線を膝に下げると、静かな寝息が聞こえていた。眠ってしまったようだった。胴にしがみ付く長い腕、強く折り曲げた長い脚、Tシャツに包まれた広い肩。大きな体を胎児のように屈めて、小さくなってしがみ付いている。腹にうつ伏せた顔は、見えなかった。長い睫毛も、吹き出物一つない綺麗な頬も。彼の薄茶の髪だけが、むずかるように腹に押し当てられている。どうして、あんな所へ行ってしまったの? どうして、一人ぼっちで立っていたの?
どうして、あそこには " お母さん " しか、いないの?
エレーンは、手を伸ばして、柔らかな髪をゆっくりと撫でた。何故、自分が泣いているのか分からない。けれど、彼が哀れで、不憫で、切なくて──。膝の上で目を閉じたウォードは、小さく寝息を立てている。我がままを言う少年の顔だった。不安そうに見上げた顔は、怯えた少年の顔だった。
「……まだ、本当に、子供なんだ」
安らいだ寝顔に、溜息が落ちる。深く暗い孤独の底に、彼の "砂漠" が広がっている。静かな、けれど、決定的な、受け入れざるを得ない確信があった。あの蝶の正体を、彼が言い当ててしまったら、あの世界は崩壊する──。
ふと、それを思った。どうして、彼の世界には、" お母さん " しか、いないんだろう?
四角い窓から夜空に瞬く星々が見えた。柔らかな髪を、ゆっくりと撫でる。心身共に憔悴していた。圧し掛かる世界の重みが、肩に直接覆い被さってくる。少し風が出てきたようで、テントの布地がバタバタ騒いだ。暗闇に目を凝らし、息を殺して、殺伐とした響きを聞いた。夜の匂いがする。
風の加減だろうか。歓声が遠く微かに聞こえた。まだ、あの二人は戦っているのだろうか。そういえば、あの後、アドルファスはどうしたろう……?
頭が割れそうな耳鳴りがした。
呼吸が浅く、息苦しい。動悸が激しく、金縛りに遭ったように、体が全く動かない。
『 ──何をしておる 』
視界に、ビジョンが飛び込んだ。
真紅の口が小さく嘲笑う。愛(いとお)しむように、哀れむように。
警戒に息を詰め、エレーンは、目だけで周囲を窺う。どこだろう、ここは──?
テントの中では、なさそうだった。恐らく、どこかの部屋の中。全く知らない空間にいる。辺りは随分薄暗く、何が在るのか分からない。
『 どうした。何をそんなに躊躇する 』
声が問う。鈴を転がすような凛とした声。
静かなようでいて、逆らうことを許さぬ揺るぎない口調で。
『 お前ならば、容易いであろう? 脆弱な女の一人や二人、容易く斬れる、そうではないのか? 罪なき多くの民草を、その手は斬ってきたのだろう? 』
薄暗がりに、天女のような純白の衣装が現れた。
肩から零れる長い髪。スッと背筋を伸ばした子供のように華奢な体。誘い、諭す、紅のさされた小さな口。広い額、傷一つない抜けるように白い肌。自信に溢れた大きな瞳。あれは──
……アディー?
いや、サビーネ、だろうか。美しく高貴な輪郭が揺らぎ、二人の顔にユラユラとぶれる。
──いや、違う。全然違う別人だ。大人しいあの二人が、あんな高飛車な口をきく筈がない。
なのに、どうして、彼女らの面影が、ああも重なって見えてしまうのか。
『 何をしておる。それで私を斬れ、と言うに 』
挑発するようそう命じ、気高い天女は、両手を広げる。目の前にいる相手に向けて。
部屋の中に、誰かいた。男のようだ。突き伸ばした左手で、壁に相手を押し付けている。刀剣を握る節くれ立った右手、横顔の半分を覆い隠す長い直毛、柳眉をひそめ、苦々しげに睨み付ける鋭い双眸。あれは、
( ──女男? )
対峙しているのは、あのファレスだ。何故、彼がいるのか分からない。ファレスに肩を掴まれて、壁に押し付けられているのは天女じゃない、サビーネだ。怯えた顔でファレスを見ている。ファレスには天女の姿は見えていないようだ。無論、声も聞こえてはいまい。けれど、強烈な意思だけは、全身で感じ取っている。目の前のサビーネを睨み付けたまま、天女の誘惑と闘っている。だが、ファレスの握った刀剣は、その意に反してジリジリ徐々に持ち上がっていく。見えない力に吊り上げられていくように。
ファレスと天女の攻防は、嫌な緊張を孕んで、しばらく続いた。だが、静かで熾烈なせめぎ合いの末、やがて、ファレスは、見えない鎖を引き千切り、天女の強制を振り切った。捕えたサビーネを突き放し、夕暮れの部屋を憮然と出て行く。
翻ったファレスの長髪がぶれて、視界が不意に大きく歪む。
……これは、夢?
誰が見ている、夢の中? だって、自分は、眠ってなど、いない。
どうして、こんなものが見えるのだろう。恐ろしい予感に、身が竦む。けれど、目を背けることは許されず、金縛りに遭ったように動けない。
気高い天女は、物憂げな口調で呟いた。
『 壊れた殻など足手纏い、こんなものに囚われて、長く苦しむなど飽き飽きじゃ。早よう、ここから解き放て 』
我がままな童(わらべ)のような、拗ねたような命令。
『 お前なら、上手に出来るであろう? 』
頭上に剣を振り上げて、アドルファスが必死で抗っていた。
けれど、相手がこの天女では、容易く操られてしまうだろう。いや、初めから無理なのだ。気高い天女に抗える者など、そう多くはいないのだから。
彼の精神は、ファレスより、弱い。
『 さあ、屈強なる民草よ 』
ファレスを逃した気高い天女が、甘い声で「斬れ」と命じる。堪えきれずに、アドルファスの剣がジリジリと動いて上がっていく。
ついに強制に負けた切っ先が、サビーネ目掛けて振り抜かれた。
サビーネが硬く瞼を閉じる。 刹那、足が吸い込まれるように床を蹴った。だって " アディー " が斬られてしまう。父も母も失って、けれどアディーは、あたしのアディーだけは、
絶対、連れて行かせない──!
背中が熱く焼きついた。
呼吸が浅く、速くなる。興醒めしたように一瞥し、天女の赤い唇が緩やかに歪んだ。怜悧な瞳に忌々しげな色が増す。
『 ──おのれ民草。余計なことを 』
長くしなやかな髪を払って、気高い天女は、大気に溶け入るように踵を返した。
全てを焼き尽くす灼熱が、体をジワジワと侵食する。体の自由を奪う痛みが、ジンワリ全身に広がって行く。
……あれは、誰?
サビーネ? それとも、あのアディー?
違う。サビーネじゃない。アディーじゃない。そう、あれは誰でもない。
" ツクヨミ "
これは 《 月読 ─つくよみ─ 》 の膨大なる記憶の一片。ならば、これは、
── " 極楽鳥 " が、見てる夢。
一瞬、全てを理解した。
けれど、次の一瞬には、手にした全てを失っていた。
重たい闇が圧し掛かり、体を起こしていられない。激しく磨耗し擦り切れた意識が、暗い闇へと吸い込まれていった。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》