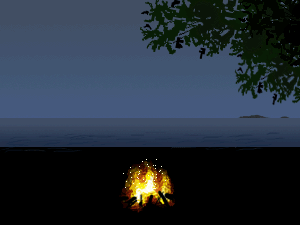
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部3章 6話20
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「──又か」
月明りに照らし出された薄暗い室内を見渡して、ケネルは、小さく嘆息した。両側面のメッシュ窓から蒼い月光が差し込んで、室内を白々と照らしている。取り乱したあの様子では、戻った途端に飛び掛られるものと覚悟していたのに。
蛻(もぬけ)の殻だ。ガランとしたテントの中は、人っ子一人いない。テントの中は真っ暗だった。確かに、中に入って行くところを見届けたのだが──。途方に暮れて頭を掻き、閑散とした室内を入り口に立ったまま見回して、捜索の目を向かいにやる。
「今度は、どこへ行った。裏から出たのか」
首長が使う大型テントは、中央の間仕切りで二つの部屋に区切られており、両側面に出入り口がある。向かいの出口に向かおうとして、ケネルは、ふと足を止めた。奥の間の右手隅に、異様な小山が出来ている。寝袋の山だ。どれも解かれて広げられている。あんなものは、さっきはなかったように思う。よくよく見れば、壁際に寄せてあるザックの口も開いていて、収納物が上から乱雑にはみ出ている。
( 物盗り、か )
ケネルは、静かに踏み込んだ。室内が荒らされていた。いや、窃盗だけというならまだしも、彼女も一緒に連れ去られたらしい。外には歩哨がいた筈だが──。短い舌打ちで、すぐに盗賊の足取りを追う。寝袋の山を通過しようとして、ふと足を止めた。
何かの気配があの下にある。腰の護身刀を引き抜いて、ケネルは、静かに身構えた。息を殺して慎重に近付き、上に掛かった寝袋を指の先で摘み上げ、微かな気配に目を凝らす。めくり上げていくにつれ、その下の暗がりがソロリソロリと露わになる。予期せぬものをそこに認めて、ケネルは、拍子抜けして一人ごちた。
「……こんな所に隠れていたのか」
捜していた黒髪が、小さく寝息を立てていた。広げた寝袋を床に敷き、体の上には何枚も掛けて、手足を縮め、こちら向きに横臥している。荒らされた部屋を見回して、ケネルは、一人苦笑いした。どうやら、このお姫様が置いていかれた腹いせに、テントの持ち主の所持品に八つ当たりをしたようなのだ。そして、拗ねて隠れて不貞寝を決め込んでいたらしい。見れば、頬の下には枕代わりと思しき綿シャツまである。勝手にザックから持ち出したらしい。
刃を腰の鞘へと戻して、持ち上げていた寝袋を、傍らの床に静かに下ろす。脚をゆっくり折り曲げて、起こさぬようにしゃがみ込んだ。凡そ布団になりそうな物を、手当たり次第に掻き集めてきたような感がある。その幾重にも重なる寝袋の山に、すっかり埋もれてしまっている。よくよく見れば、さっき着ていた上着までご丁寧に掛けてある。そうまで寒いような気候ではないが──?
不審に思い、片手を伸ばして、彼女の額に当ててみる。発熱している様子はない。むしろ、赤く火照ったその寝顔は、暑くて寝苦しそうにさえ見える。
「……そんなに欲張るからだ」
もう一度、苦笑いして、寝袋の山をどけてやる。本来、寝袋など一枚あれば十分だ。上着を無造作に脇に退け、ケネルは、ふと首を傾げた。それは、どこか奇妙な光景だった。そんなに寒いというのなら、何故、着ていた上着をわざわざ脱いで、上から掛け直したりしたのだろう。
どこか不自然な行動に腑に落ちないものを感じはしたが、ケネルは、拘るでもなく目を戻した。彼女の力ない右腕を取る。小指の付け根が切れていた筈だ。腕の裏にもあざがあった。確か左の手の甲にも──。
ファレスが寝床に張り付いていたから森で一度見たきりだが、それらについては把握していた。ゲルを空けた僅かな隙に掻き消えるなどとは予想だにせず、何の治療もしていない。腕を裏まで返して傷の具合を手早く調べる。だが、賊に襲われたあの時に、確かに見つけたそれらの傷は、やはり、どこにも見当たらない。切ったのは高々数時間前のこと、まだ半日も経たぬというのに。
「──どうなっているんだろうな、あんたは」
指を伸ばして横顔にかかった髪をどければ、頬の上には、うっすら涙の跡があった。一人で泣いていたらしい。かくれんぼの途中で眠ってしまった子供のようだ。手足を縮めたその様は、さながら
" 大切に隠された宝物" といった風情か。
横臥した細い首から銀のチェーンが零れていた。裂かれた寝巻きの首元に、白い肌が覗いている。忌々しい思いで舌打ちし、肌蹴た襟を引っ張るようにして前を合わせる。疲れ切った寝顔を眺めて、ケネルは、やれやれ、と嘆息した。少しもじっとしていない。チョロチョロどこかへ消えたかと思えば、傷だらけになって帰ってくる。そうかと思えば、真剣勝負の最中に、いきなり、ひょっこり出て来るし。あんなに震えていたくせに──。
片手を伸ばして髪に触れ、髪を撫でかけ、手を止めた。
「まったく、どうかしているな……」
ばつ悪く目を逸らして、頭を掻いた。だが、すぐに気を取り直し、彼女を起こして連れ帰ろうと横臥の肩に手を伸ばす。ふと、それに気が付いた。わざわざ起こして歩かせなくても、今夜はここのまま寝かせればいい。キャンプに置いてきた荷物については、こちらへ運ばせれば済むことだ。
ここを寝床にするのなら、今日の仕事は終了だった。一息ついて、ケネルは、横にしゃがんだままで寝入った顔を眺めやる。
「……今日は、晩飯食い終わるまで保(も)たなかったな」
彼女の体力が目に見えて落ちてきていた。出立当初は宵っ張りだったが、日を追う毎に就寝時間が早くなる。移動中は日がな一日うつらうつらと浅く眠り、ゲルでもいつの間にか眠っている。その都度、向かいの寝床まで運んでいる。そう、腹這いになって盛んに話しかけていたこちらの寝床で。ほったらかされて拗ねて引っ付いていた壁際で。朝食後、膝を抱えて小鳥を見ていた戸口の脇で。だが、今では、夕食が済むまで覚醒状態を保つ事さえ覚束ない。アドルファスは毎晩、様子見に来るし、バパは異変に気付いている。どちらもおくびにも出さないが。そして、そうした事情は副長も同じ。こんな調子で、
「──商都まで、保(も)つか」
彼女の危うげな状態に合わせて、出発を遅らせ移動を早目に切り上げるようにはしているが、先に進めば進むほど、夏の暑さは酷くなる。目的地は大陸の南だ。強行軍の過酷さは、冷涼な北方の比ではない。
嘆息し、天井を仰いだ目の端に、何かが鋭く反射した。不審に思い目をやれば、彼女が身に付けた翠石の欠片だ。彼女は、あれを肌身離さず身に付けている。大切なお守りなのだ、といつも得意げに話している。
白い寝巻きの胸元で、首飾り仕様のその石が、月光に洗われ冴え冴えと輝いていた。己の意思でも持つように。吸い込まれるように手を伸ばし、指先でそれを摘み上げる。目の高さにまで持ち上げて、窓から漏れ降る月光に透かして中身を確かめるように欠片を覗く。今、何かが石の中を過ぎった気がしたのだ。
だが、どんなに目を凝らしても、翠石の中には何もない。熱心に見入っていたことに、ふと気付き、ケネルは、苦笑いして膝先へと目を戻した。見下ろす先には、泣き寝入りした頼りなげな顔。しゃがんだ膝に腕を置き、青白い寝顔をじっと見つめる。
「──領主の女、か」
手の平で転がしていた翠石を指の先で軽く弾いて、寝床の横から立ち上がった。一晩ここを借りる旨、連絡を入れるべくテントの出口へと踵を返す。刹那、月光を浴びた翠石が、目の端で鋭く反射した。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》