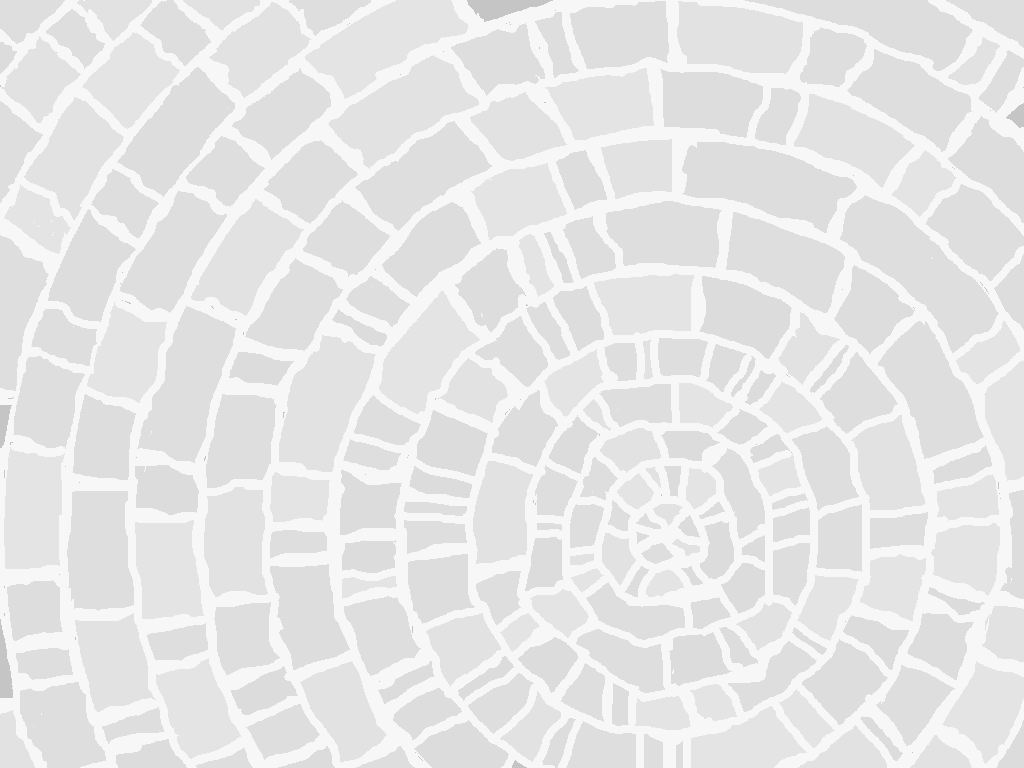
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 3章 12話3
( 前頁 / TOP / 次頁 )
散々色々見た末に、着代えを探しに服屋に入った。白い棚に並んでいるのは、隅を揃えて綺麗に畳んだ色とりどりの四角い綿シャツ。シンプルだけれど可愛い色だ。
( あの娘もこういう可愛い格好すればいいのにさー。なにもあんな一昔前に流行った野暮ったいワンピースとか着なくたってー )
そうしたら、もっと垢抜けるのに、とエレーンは他人事ながら嘆息する。いつも挑みかかってくる気の強いあの顔を思い出したのだ。まったくクリスの気が知れない。もっとも、服のセンスは人それぞれ、お飾りゴテゴテの乙女チックな服が好きと言うなら、無理をしてまで止めはしないが──。やれやれと服を戻しかけ、ふと、手を止めた。手の中のそれを改めて見つめる。だって彼女は、こういう店で買い物をする事ができるのだろうか。
雑貨屋で受けた無礼な仕打ちが脳裏にまざまざと蘇った。あの時ハジが来なければ、今頃どうなっていただろう。理不尽に追い払われて泣き寝入りするしかなかったろう。羊飼いの身形を見ただけで、店主はたちまち売り渋った。詰め所に身柄を突き出そうとさえした。どれだけ腹立たしかったか。どれだけ悲しかったか。どれだけ心が傷ついたか。
「──そう、か。だから、クリスはあんなに」
今更気づいて、息が止まる思いだった。"あの服"の持ち主の屈辱と憤懣が凍えた心にひしひし迫る。彼女の置かれた境遇が、彼女の送る日常が、切実に、鮮烈に理解できた。
きっと、クリスはあんな風に貶められてきたのだろう。苦情を言っても、どうにもならない。売買は売り買い双方の意思が揃って、そこで初めて成立する。一方が売らぬと言うのなら、即ちそれを買う事は出来ない。お金はあっても、売ってはくれない。欲しい物が、すぐそこにあるのに。
道端で容易く買える小物も、クリスには手が届かない。希望の品を当然の如くに持つ者を、どれほど妬ましく思うだろう。だから、こちらと顔を合わせる度に、あんなにも過剰に突っかかってきたのだ。あの流行遅れのワンピースにしても在庫処分か何かの機会にようやく手に入れたに違いない。それでも懸命に着飾って、できる限り張り合って、他人に馬鹿にはされたくないから──。
「……ひどい」
込み上げた涙を、唇を噛み締め何とか堪えた。悪びれもしないあの態度では、あの雑貨屋一人が特別に陰険なのではないだろう。あれと類似の出来事は、恐らく日常的に起きている。だからこそ、ハジは言ったのだ。「あんたの格好に問題がある」と。
猛然と腹が立ってきた。誰に対して、何に対して憤っていいいのか分からない。強いて探せば、さもしく下らない縄張り意識だろうか。いや、そんな漠然としたものでなく、今、具体的にぶつけるべき先が一つある。
「──ファレス、行くわよ」
知らず、押し殺した声が出た。
「行くって、どこへ」
買い物袋を肩から引っ下げ、手持ち無沙汰に歩いていたファレスが、見向きもせずにぞんざいに訊いた。ズボンのポケットに突っ込んだ腕を、エレーンはもどかしく引っ掴む。
「さっきの店よ!」
……ああ? とファレスが怪訝そうに振り向いた。腕を引っ張り、強引に道を取って返す。行き先は雑貨屋、万引き扱いしたあの店だ。
先程同様、店の硝子戸は開け放ってあった。憤怒を抱えて到着し、一歩足を踏み入れた途端、「いらっしゃ〜い」と愛想の良い声がかかる。あの無礼な太っちょ店主だ。エレーンは親父の前までつかつか進み、片手をぐいと突き出した。
「ほら、身分証よ! 見るんでしょ!」
いそいそ出てきた吊りズボンの親父が、面食らった顔で足を止める。エレーンは憤然と詰め寄った。
「ほら、見たいんでしょ! さっさと見なさいよ! さあ!」
恰幅の良い吊りズボンの腹に、その手をぐいぐい押し付ける。親父は戸惑ったように眦(まなじり)を下げ、当惑顔でたじろいだ。「……あ、いえ、あの……なんでいきなり、そんな物をわたしに?」
助けを求めるように、どぎまぎ周囲を見回している。事情がさっぱり飲み込めないらしい。一歩進めば、一歩引く。もう既に逃げ腰で、隅の柱に縋りつかんばかりだ。先程の傲慢な態度から一変、気弱そうなこの様子。さては、さっき怒鳴りつけた相手と気づいていないな? 紛うことなき物証を、エレーンは目の前に突きつけた。
「つべこべ言わずに見なさいよ! あんたが見せろって言ったんでしょうが!」
親父はぱちくり瞬いて、銀のハートのネックレスを見た。客の顔をまじまじ見返す。一瞬後、「──あっ!」と驚愕の顔で瞠目した。太い五指をぶんぶん振る。「い、いえ! 滅相もない! もう結構ですから!」
「ねー。ここって、そんなご大層な店なわけえ? てか何様〜?」
ふんっ、と鼻息荒く見返して、エレーンは「どーしたのよ、なんとか言ってみなさいよ、えー?」と顎をしゃくって責め立てる。泡食う親父を冷ややかに睨んで、両手を腰に押し当てた。
「さっきの態度、マジむかつくー。マジですんごくありえな〜い! この店でどんな目に遭ったか、あたし、みんなに言い触らしちゃおうかなあ〜」
「……そ、それだけは、なにとぞ平にご勘弁を!」
店の評判を持ち出され、親父は色を失った。あたふた体を窮屈そうに折って、悲鳴を上げんばかりの狼狽振り。エレーンは憮然と見下ろした。客の優位を笠に着て居丈高に責めている自覚はあった。でも、気の毒だなんて思わない。こいつは人として間違っている。やり込められて当然の事をしたのだ。そうだ。こいつがしたのと同じ理屈で、やられたから、やり返したまでだ。
泥棒呼ばわりした無礼な親父は、吊りズボンの膝に額を擦り付け、ぺこぺこ頭を下げている。うろたえる姿に溜飲が下がった。屈服させて面目躍如。これまで排斥されてきたクリス達の仇をも、併せて取ってやったような清々した気分だ。──ふと、とある疑問が脳裡を過ぎった。もしも、あの場に自分がいたなら、追い払われようとしている《
遊民 》の女を助けてやろうとしただろうか。
苦々しい結論に眉をひそめる。その答えは、すぐに出た。恐らくは何もしなかった。係わり合いになることを恐れ、見て見ぬ振りを決め込んだ。ならば、経営者の立場であったなら、この親父と同じ事をしたかも知れない。今はたまたま客の立場にいただけ、この立ち位置はそれだけの差だ。丸い体を窮屈そうに屈めて、親父はぺこぺこ平謝りしている。目の前のこの姿は心のありようの写し鏡、自分の姿そのものだ。自分だって、所詮はこの男と同類なのだ──。虚しさが込み上げ、目を逸らした。
「……いいわよ、分かれば」
そもそも、店主一人をやりこめたところで、一体何がどうなるというのだ。この場で素直に改心し、クリスが次に買い物に来た時、無下に扱われる事がなくなるとでもいうのか。
苦い敗北に苛まれた。それを信じられるほど無邪気ではない。自分がした事は自己満足に過ぎない。しかも、唾棄すべき弱い者苛め、最悪だ。鬱憤晴らしをした後だけに、自己嫌悪は尚のこと深い。
クリスは確かに生意気だけれど、不器用なだけで悪人ではない。傷付けられたから警戒し、鋭く反応してしまうだけ、誰だって、そうだ。けれど、それでも、文句を言いつつ賊から一緒に逃げてくれた。こちらを案じて、夜更けに様子を見に来てくれた。あんな目に遭うのは忍びない。けれど、彼女の為に何一つできない。
無力感が荒涼と広がる。他人から奥方様とは呼ばれていても、自分には何も正せない。自分は何も返せない。歯がゆく、情けなく、もどかしかった。こんな不公正が目と鼻の先で罷り通っているというのに。
既得権益を盾にした身びいきの偏向は歴然だった。そして、貶められた者達がどれほどの憎悪を押さえ込むのか、我が身を以て知っている。──ふと、賊に応酬すべく踏み出したケネルの厳しい横顔が蘇った。その手に握られた鋭い刃。
もやついていた心が凍てついた。故なく傷付けられた者達は、いつまで黙っているだろうか。
浅く切り刻まれた心の傷から、不気味な何かが滲み出した。彼らは実のところ無力ではない。何より人は報復する生き物だ。そうだ。現に今、自分はここで何をしている? あんな些細な諍いでさえも、あれ程の憤りを感じたのだ。まして長年に亘って抑圧された遺恨なら、どれほどの力で跳ね返るだろうか。至極当たり前の認識が、苦い焦燥が頭をもたげる。こんな事をしていてはいけない。
──こんな国じゃ、いけない。
しつこく頭を下げていた親父が、ようやくおもむろに顔を上げた。目端の動きで、エレーンははっと我に返る。明るい店内に立っていた。穏やかで平凡な日常に。棚に置かれた細々した商品、硝子の器に盛られたビーズ、白い棚、貝殻の風鈴、中央に据えられた流木のオブジェ。陽が暮れ始めた石畳の通りには、人がのんびり歩いている。開け放った引き戸から、夕方の風が吹いてくる。親父は揉み手で愛想笑いを浮かべている。善良そうな丸顔を傾げた。「そういえば、さっき何か言いかけていませんでした?」
「……え?」
エレーンはたじろいで訊き返した。とっさに頭が回らない。親父はしげしげ見つめている。そして、次の言葉は現実に引き戻すに十分だった。
「" あたし、本当は── " なんなんです?」
う゛──とエレーンは固まった。
「……あ、あれね。あたしは……えーっと……あー、」
とっさに明後日の方向に目を逸らし、「えへへ、なんだったっけえー?」とさりげなくじりじり後ずさる。如何にも自分は"奥方様"だが、町中で意味なく濫用は良くない。
親父は興味津々上目使いで窺っている。停止した禿げ頭を不審げに傾げて、じいっ、と返答を待っている。思わぬ方面からの反撃だ。どうしたものか、とたらたら冷や汗で思案して、エレーンは空口笛で目を逸らした。
「……え、えーっと……じ、じ、実はぁ〜」
さあ、どうする。
形勢逆転、進退窮まり頭は真っ白。しかし、苦しい抵抗も最早これまで。この期に及んで逃げ場などない。片頬引きつらせ、誤魔化し笑いで振り向いた。
「ぜ、善良なカレリア市民なのでしたー」
嘘じゃない。つい二ヶ月前まではそうだった。
話に聞き耳を立てていたファレスが「……なんだそれは」と脱力した。どうでも良さげな横顔で続ける。「にしても、おめえ、すげえ執念深けえな」
なによ、薄情者ぉ〜、とエレーンは薄茶の長髪を睨めつける。ファレスは暇そうに店内をぶらぶら歩き回っている。見るからに市民の風体ではなかろうに、親父は何を言うでもない。むしろ、こそこそ距離を置き、目をさえ決して合わせようとしない。物騒な護身刀とか差していて、よっぽど胡散臭いのに。
どうやら人を見るようだ。コソコソへいこらしている親父を( こんの卑怯者! )と睨めつけた。こういう輩はたいそうムカつく。静まった気分が再度沸騰しかけるも、( いや、いかんいかん…… )と首を振り振り己をなだめ、小奇麗な店内に注意を戻す。
それはそれとて、お買い物。何せ今日は、懐がたいそう暖かいのだ。この機を逃して何とする。因みに"懐"はオブジェの向かいにいるのだが──。棚の商品を物色しいしい、何の気なしに声をかけた。「あ、ねえ。ケネルのお土産、何にするぅ……」
尻つぼみになって声が途切れた。口をついたかの人の名に無防備な胸が鷲掴まれる。声に乗せると、思わぬほどに動揺した。言い知れぬ寂しさが押し寄せて、二の腕をさすって目を伏せる。「……何が、いいかな」
ファレスはまるで気づかぬようで、前を見たままぶっきらぼうに応えた。「要らねえだろ、土産なんか。まあ、どうしても買うってんなら食い物だろ、無難に。食っちまえばかさばらねえし、必需品は支給されるしよ」
棚の商品を見ている振りで、エレーンは「……そっか」と俯いた。
開け放った引き戸の硝子に夕陽の赤が反射していた。路上を冷やかす人々も各々の家へ引き上げていく。物寂しい黄昏時は、ただそれだけで人恋しくなる。ケネルの話題は避けていた。それなのに──。
他に気を取られ警戒が緩んだ一瞬の隙に、するり、と懐に入り込んできた。本当は、何をしても、どこにいても付き纏って離れなかった。喉に刺さった小骨のようにずっとチクチク引っかかっていた。森で踵を返した面影が空虚な胸に蘇る。ケネルはクリスを娶るのだろうか。そして、二人の家庭をつくるのだろうか。ケネルとクリスと、その子供で。
夕焼けに染まる平凡な町の、平凡な光景を改めて眺めた。ここには怒声も殴り合いも流血もない。治安を維持する町の警邏と堅牢な建物に守られて、日々は当然の如くに、穏やかに、和やかに過ぎていく。朝がきて、昼がきて、平穏のまどろみの内に一日が暮れる。非力な自分には相応しい、幾重にも守られた安全な場所。これが元いた場所だった。そして、これからも生きていくであろう自分の居場所。恐らくは、ずっとそうなのだ。
「……のどかでいいよね。こういうの」
ひどい虚しさが込み上げて、エレーンはそっと嘆息した。「──あーあ。あんたとどっか行っちゃおうかなあ」
ファレスからの返事はなかった。怪訝に思い、見返すと、棚を見たまま無言で眉をひそめている。予期せず言いっぱなしになってしまい、気まずくなって目を逸らす。ファレスは先に店を出た。
人の流れは大分引き、石畳が赤く染まっていた。気の早い店は卓の蝋燭に火を灯し、店先を解放した洒落たカフェには、酒のグラスを傾ける客が一組二組出始めている。外に置いた中央の卓で、羽振りの良さげな男二人が、夕方の涼風を浴びて、ゆったり笑って寛いでいる。
夕暮れの町を無言で歩いた。ファレスは柳眉をひそめて口をつぐんだままだ。エレーンは話しかけようとして口を閉じた。黙り込んだ端正な顔は、何者をも冷たく拒絶し寄せ付けない。しばらく気まずく歩いた後に、ファレスは低い声でようやく言った。「──正気かよ」
「な、何が?」
「──だから、さっきの」
もどかしげに低く応える。苛ついた様子だ。記憶を辿り、会話が途切れた直前のやりとりを思い出し、エレーンはいささか拍子抜けした。何の気なしの戯言を律儀に考えていたらしい。仏頂面で黙っているから、てっきり機嫌が悪いのかと思っていたのに。
「逃げるか、俺と」
エレーンは面食らって見返した。ぶっきらぼうな鋭い囁き。こちらの顔を見向きもしないが、探りを入れているような密やかな声音。感じが何かいつもと違う。回答の猶予を与えるように、ファレスは口をつぐんで歩いている。しばし唖然と絶句して、エレーンは夕暮れ空を苦笑いで仰いだ。「……できる訳ないでしょー、そんなこと。さっきのあれは冗談よ冗談。言ってみただけ」
靴裏を鳴らして足を止め、ファレスは「──そうか」と嘆息した。買い物袋を肩から引っ下げ、足をぶん投げ歩き出す。慌てて早歩きで追いついて、横から顔を窺うと、ファレスは僅か眉をひそめて、まっすぐ前を眺めている。その唇がためらうように動いた。「──お前、まだ見ているのか」
「……見るって何を?」
「夢だよ夢。前にお前、言ってたろう」
いきなり話題を代えられて、エレーンは「……ゆめ?」と瞬いた。すぐに「──あー、あれね」と思い出し、げんなりして肩をすくめる。
「見てるわよー、相も変わらず。なんか変な、怖い夢ばっかり。いっつも魘されて起きるのよねー。特に"階段"の夢とかさー」
「階段?」
硬い声音で聞き咎め、ファレスは苦々しげに眉をひそめる。「──"あれ"を見たのか」
「緑の苔の石段を、誰かがゆっくり登っていくだけのことなんだけど、なんかもう怖くて怖くて。何であんなに怖いのか、自分でもよくわかんないんだけど」
「そう、か。そこまでか」
ファレスが拍子抜けしたような顔をした。エレーンは「何がそこまでよー?」と首を傾げる。
「……なんでもねえよ」
ファレスは気まずそうに横を向いた。どうも奇妙な反応だ。何かを隠しているような? じぃっと顔を見ていたが、頑として口を割りそうもない。こうなると野良猫は、たいそうしぶとい。エレーンは、やれやれ、と肩をすくめた。
「でも、場面がいつも切れ切れなのよねー。霧の中みたいにぼやけてるから、何やってんだか、よく見えないヤツが多いしさー──あ、でも、今日のヤツは綺麗だったわよー。あのねえ、花火の夢」
自分の言葉に、( そういや今日、花火買ったっけ…… )と上目使いで思い出す。
「花火。──ああ」
ファレスは物思いに耽っているらしく、言葉が普段よりいやに少ない。眉をひそめて、引き続き口をつぐんでいる。あまりに長く黙り込んでいるので、堪りかねて訊いてみた。「もーなによー。花火の夢がどうかしたー?」
ファレスはやはり前を見たまま、心ここにあらずで首を傾げた。「……解せねえんだよな、あの意味が。あれだけ、どことも繋がらねえしよ」
……あれ? とエレーンは足を止めた。こっちの夢に何気に参加してないか? 絶句であんぐり横を見る。「もしかして、あんたも又見たの? 又、あたしとおんなじ夢を!?」
「……どーなってんのよ」とまじまじと見、ふと何かが引っ掛かって見返した。「その"繋がる"ってなに」
はっ、とファレスが我に返った。
「いや、なんでもねえ」
慌てて、きっぱり口をつぐむ。更には、ぷい、と打ち切るようにそっぽを向いた。もう話したくないらしい。
「えー。なにそれ勝手ー。自分から訊いてきたくせにぃー」
我がまま放題な野良猫をむくれて覗いたその途端、頭が上から押し潰された。ファレスが片手で鷲掴み、グリグリ力任せに沈めてくる。
「──ちょ、ちょっとなにっ! あんた、いきなり何してんのー!」
なんのつもりだ!? とじたばた暴れる。しつこい攻撃を涙目で払えば、ファレスは半眼で仁王立ちしていた。クイ、とぞんざいに顎をしゃくる。
「おう、馬取りに行くぞ。あんぽんたん」
言うなり、くるりと踵を返した。肩に買い物袋を引っ下げて、足をぶん投げ歩いて行く。行く手にあるのは黄昏に染まった街道への道。帰ることにしたようだ。
「おう、ここで待ってろ」と言い置いて、ファレスは馬を取りに行った。迷子の如くに詰め所の横にぐりぐり据えられ、立ち番の警邏の訝しげな顔に「……あ、どーも」とヘラヘラ笑ってご挨拶。しかし、只今勤務中の勤勉な警邏は、世間話には応じてくれない。
目抜き通りの入口で、エレーンはぽつねんと取り残された。手持ち無沙汰で街道を眺める。道端で白い花が揺れていた。歩き回って人も疎らな夕間暮れ。街道沿いに軒を連ねる商店が夕陽の赤を浴びている。あの道の先が懐かしい商都に続いているのだ。戸を開け放った店々は、やがて牧歌的な民家に変わり、見晴らしの良い畑になり──。とある姿を見咎めた。
夕陽を浴びた土道に、髪の長い女性が歩いていた。額の横で薄茶の髪をさらりと分け、首元を開けた薄紫のブラウスに、すっきりと白いスラックスをはいている。
すらりと長いその足に、子供がまとわりついていた。男の子のようだ。姿形が見分けにくい夕暮れ時で、しかと確認はできないが、子供の服はぶかぶかで、片足をいく分引いている。もしや、あれは──
「ケイン?」
エレーンは瞬き、目を凝らした。後ろ姿があの子に見えた。だが、自分のキャンプに戻ったケインが、何故、今時分、こんな街道にいるのだろう──ふと、その可能性に気がついた。もしや、彼女が、
「……お母さん?」
ケインは母親に会いたがっていた。それで、いつも泣いていた。まだ、あんなに小さいのだ。無理もない。それで我慢ができなくなって──。だが、一方の女の方は、追い払おうとしているように見受けられるが──
「おう、何してんだ」
ギクリ、とエレーンは飛び上がった。背後からの不審げな呼びかけ。声を慌てて振り向けば、馬の手綱を手にしたファレスが「さっさと来いよ」と顔をしかめて立っている。ファレスは怪訝そうに顔を見て、視線を街道に巡らせた。「どうした、なんかあるのかよ」
「ううんっ! なんでもない! まったく全然なんでもないっ! さ、帰ろ帰ろ! 帰りましょお!」
畳みかけてあたふた否定し、両手を振ってファレスに駆け寄る。胡散臭げなファレスの背中を両手でぐいぐい押しやって、視界を街道から強制転換。ケインはお尋ね者なのだ。あそこにいるのが露見すれば、大変な騒ぎになってしまう。
ファレスは怪訝そうに見ていたが、それほど拘らずに目を逸らした。野良猫の関心は、既に帰り道にあるらしい。密かに安堵しながらも、馬の高い背に乗せてもらう。
青い帳の帰り道、ファレスにしがみ付いて揺られつつ、さりげなく街道を盗み見た。暗く染まった視界の片隅、夕陽に包まれた街道が次第次第に遠ざかる。遠目のことで定かではないが、やはり、あれはケインだった気がした。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》