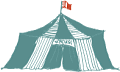
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 4章 2話
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「これは──」と息を呑んだきり、ラッセル伯は面食らったように絶句してしまった。そして「いや、失礼。もっと妖艶な方を想像しておりましたもので」とぎこちなく苦笑いし、それきり口をつぐんでしまった。日頃そつない彼にしては珍しく、ガーデンテーブルに執事が紅茶を運んできてからも、何事か考え込むように、じっと口を開かない。例の「傾国」のイメージと目の前に現れた実物との乖離に、どうやら戸惑っているらしい。
街外れの閑静な館、その最奥にある女主の居室では、テラス戸をいっぱいに開け放ち、その先の緑豊かな庭の芝には、青銅のガーデンテーブルが設えられている。そこに、二人の客が通されていた。庭を背にしたサビーネの右手に、ダドリーの兄であるチェスター候、そして、左にラッセル伯。俯き気味のサビーネの様子を、チェスター候は紅茶を啜りつつ盗み見た。
( ……さて、どうしたものやら )
心中密かに嘆息する。ラッセル伯の求めに応じて引き合わせはしたものの──。
挨拶を済ませ、近況を二三尋ねると、すっかり話題がなくなってしまった。ダドリーが商都へ遊学中、この館と彼女の世話を何くれとなく焼いていたのは活力に富む亡兄の方で、ここにはさっぱり縁がなく、慌しかったここ二年の間も、チェスター候はご無沙汰だった。話題を提供しようにも、彼女は館に籠りきりで共通する知人もなく、親類縁者も朋輩ではない。夜会にも晩餐会にも全く顔を出さないし、流行り物にもまるで疎い。唯一共通する話題といえば、彼女の主ダドリーであろうが、しかし、当人が捕らわれている今この時に、その話題を持ち出すというのは、いささか無神経にも思われた。
なんとも厄介で気詰まりだった。この世慣れぬ振る舞いは、彼女生来のものではあろうが、しかし、この彼女に限って言えば、無理からぬ一面もないではない。男児であれば外に出し、何でもよく見聞きして、でき得る限り見聞を広める。子供が女児であるのなら、でき得る限り外に出さず、世間の風を遮断して育てる──これが貴族階級の躾けである。この地方の女児であれば、教師を雇って家庭内で教育するのが通例だが、盛り場が多く、建物が猥雑に立て込み、良好な環境を確保することが難しい都会などでは、郊外の修道院に送り込み、世間の汚れとは厳密に遮断して厳しい教育を施すと聞く。そうして世に出た令嬢は、右も左もわからぬ「世間知らず」であるのが一般的で、故に社交界デビューを控えた彼女らは、ダンス、着こなし、会話術、様々な場面でのマナーなどについて、専門の家庭教師から猛特訓を受けさせられる。そして、初めの内こそ母親の陰に隠れていたぎこちない令嬢も、夜会や社交を重ねる内に、要領を覚え、駆け引きを覚えて、一人前の貴婦人へとたくましく成長していく。だが、転居後間もなく災難に見舞われ、館深くに篭ってしまったサビーネの場合は、そうした機会がことごとく奪われてしまい、そのまま今日に至る、というやむにやまれぬ事情がある。
気詰まりな空気を察してか、サビーネは居たたまれないというように、じっと俯いてしまっている。隣に目配せしてみるも、ラッセル伯はどうした訳か、あらぬ一点を見つめたきり、何やらずっとうわの空だ。何事にもそつないこの彼にして何やら様子が妙ではあるが、密かに危惧していたような、青年達が豹変したあの騒動の時のような気配はない。
日の当たる庭中で、瑞々しい緑が揺れていた。素焼きの大振りな植木鉢が生垣の隅に寄せられて所狭しと置いてある。派手な花は一つもないが、どれも伸びやかに枝を伸ばし、緑を溢れさせている。無言で座っているのも気詰まりで、正直苦痛でさえあったのだが、しかしまさか、初対面のラッセル伯を残して自分だけ帰る、というのも礼を欠く。
チチチ、と鳥の声がした。使用人が少ない為か、この館は随分と静かだ。気の遠くなりそうなゆったりとした時間。「永遠」という言葉の意味を、ひょんなところで実感する。
「──美しい庭ですね」
体が溶け入りそうな静寂を、落ち着いた声が不意に破った。寡黙に茶を嗜んでいたラッセル伯だ。紅茶の手を膝に置き、庭に視線を巡らせる。「それに、ここは、とても静かだ」
チェスター候は頷いて、おもむろに席を立ち上がった。
「鳥の声がするからか、何やら気分が落ち着きますな」
庭に犇く植木鉢へと、後ろ手にして足を向ける。「これらの世話は、皆、貴女が?」
「ええ。自分で致します」
肩越しに声をかければ、サビーネはか細い声で恐る恐る応える。
「ほう。感心ですな。よく手入れををなさっている」
「ありがとう存じます」
声にほっとしたような響きがあった。褒められて素直に嬉しいらしい。そう、サビーネはとても素直なのだ。彼女にはご婦人方にありがちな、他人を見るような計算高さがない。チェスター候は相好を崩して続けた。「茂り方も旺盛で、どの葉も青く活き活きとしている。どれもは鉢から溢れんばかりだ。このように見事に育てるには、何かコツのようなものはおありかな」
「土の乾き具合を見て、水をやっているだけですわ」
「それでは、肥料や薬剤はどのような物を?」
「いえ、何も」
「──しかし、それでは、虫にやられてしまうだろう。私の所の薔薇などは、少しでも目を離すと、たちまち食われてしまうのだがね」
「いえ。特別なことは本当に何も。コツのようなものがあるとすれば」
サビーネが考えるように小首を傾げた。「お願いすること、くらいでしょうか」
「……お願い?」
「向こうへ行くようお願いすれば、虫達もきちんと聞き分けてくれます。ここでなくても、木立はたくさんありますもの。それに、そうしたことはこの子達も同様ですわ。毎日声をかけてやれば、丈夫に機嫌よく育ってくれます」
サビーネは愛しそうに緑を眺める。チェスター候は怪訝な思いで首を傾げた。彼女の感じが少し変わった気がしたのだ。以前はもっと内気な様子で、物怖じしていたような印象が──
「タイム、セージ、バジル、ラベンダー。これらは皆、ハーブですね」
話にそつなく若い声が割り込む。ほっそりとした脚を青銅の椅子でゆったりと組み、ラッセル伯が庭の一角を眺めていた。「ハーブには虫除けの効果がありますよ」
「──ああ、なるほど。それで虫がつかないのだな」
彼の言葉に合点して、チェスター候はラッセル伯を見る。ラッセル伯は寛いだ様子で庭を眺めた。「その他にも料理に使ったり、茶にして香りを楽しんだりもできます。カモミールなどは不眠に効くと言われますね」
執事に呼ばれ、サビーネが席を外した。ラッセル伯と取り残されて、チェスター候は苦笑交じりに笑いかける。「君に園芸の趣味があるとは知らなかったな。いや、たいしたものだ」
「いえ、滅相もない、私などは」
ラッセル伯もやんわりと苦笑いした。「そうしたものは嗜みませんので」
「それにしては、随分と詳しいようだが?」
ラッセル伯は木漏れ日を仰ぐ。「こちらへのご訪問を昨夜ご承諾頂いてから、今現在この時に至るまで、どれほど暇があったとお思いです? 仮にもご婦人の館を訪問しようというのですよ。多少の下調べは礼儀というものでしょう」
「──なるほど。若者はこまめだな」
何事か執事に言いつけて、サビーネが笑顔で戻ってきた。元の席まで戻って来ると、ラッセル伯は立ち上がり、隣の椅子をさりげなく引いた。「サビーネ様は、この中ではどれがお好きです?」
微笑んで会釈しながら、サビーネは椅子に腰を下ろす。「皆、どれも好きですわ」
「強いて挙げれば?」
「──そう、強いて挙げれば、あれなど好きでしょうか」
視線を向けたその先では、赤い花が揺れている。チェリーセージだ。
吹き抜ける風が心地良く、当初の気詰まりは次第に緩んでほどけていった。緑が一斉に葉を揺らし、清々しい芳香が庭を包んで緩やかに漂う。寛いで庭を散策し、チェスター候は後ろ手にして木漏れ日を仰いだ。「確かに良い香りだが、しかし、草花ばかりの庭というのは、いささか妙味を欠きますな。──おお、よろしければ、私の薔薇をお分けするが」
「……ありがとう存じます。あの、そうした大きな樹のことは、わたくし、あまり存じませんので」
サビーネは笑顔で小首を傾げている。どこか尻込みして見えるのは、臆しているのか、戸惑っているのか。気後れした背を押してやるべく、チェスター候は上機嫌に続けた。「薔薇は良いですぞ。美しく、高貴で、かぐわしい。あれこそ完成された究極の美だ」
「これはミントですか。良い香りだ」
ラッセル伯が花壇の前にしゃがみ込んでいる。いつの間にか席を立っていたらしい。指で軽く葉を擦り、香りを楽しむように目を閉じた。「立派な薔薇を差し上げても、これでは植える場所がないでしょう。大きな樹を植えるなら、代わりに何れかを抜かねばならない。しかし、そうした惨い真似は、お心の優しいサビーネ様にはおできにならない。そうではありませんか」
苦笑いするような柔和な笑みで立ち上がった。「庭師もいないようですし、そうした重労働はか弱いご婦人には酷でしょう。しかし、十分な世話ができないのであれば、せっかくの薔薇が不憫というもの。薔薇という特別な花は、然るべき手間をかけ、然るべき場で咲いていてこそ美しい。チェスター候、貴方の素晴らしい庭園のように」
「……おお、それは確かに」
チェスター候は、ふむ、と頷き、野草で溢れた緑の庭を見回した。「それに、ここに薔薇を植えてしまうと、この柔らかな調和が崩れてしまうか──」
「サビーネ様、夜会にお出でになりませんか」
彼女の座るテーブルへと、ラッセル伯が歩み寄った。サビーネの肩にさりげなく手を置き、にこやかに顔を覗き込む。「どうぞ当家にお出で下さい。なに構えることはありませんよ。私がご一緒しますから」
突然の接近に驚いて、サビーネは座ったまま、逃れるように後ずさった。「──よく考えておきますわ。あの、でも、あてになさらないで。夜会などは控えるようにと旦那さまに」
「それでは音楽会などはいかがでしょう。今は社交のシーズンで、良い楽師がこちらに来ている」
「──あの、でも、わたくしは」
「たまには息抜きも必要ですよ。ここは確かに素晴らしい庭だが、篭ってばかりでは気分が塞いでしまうでしょう」
「……あ、あの」
押しの強い相手に圧され、サビーネはおどおど俯いた。ラッセル伯は「なんでしょう」と悪びれることなくにっこり頷く。サビーネは唇を噛んで困った顔だ。やがて、おずおずと顔を上げた。「それでしたら、わたくし、少し希望があるのですが」
ダン──! と鮮烈な音を立て、床板が強く踏み鳴らされた。強烈な投光を背に浴びて、鍛え上げられたしなやかな肢体が舞い踊る。翻る薄絹、苦悶の表情、宙を掻き取る悩ましげな指先。
「な、なんなのだ、これは……」
薄暗い天幕の中、粗末この上ないベンチの上で、チェスター候は打ち震えていた。指が、体が打ち震え、全身ざわりと総毛立つ。尻の辺りがむずむずした。鼓動が速く、成す術もなく掻き回される。拍子に、調べに圧倒される。叫び出したくなるような魂の高揚。湧きいずる生命の息吹き。流れるように、猛るように、包むように、突き放すように。
街外れの館の庭で、サビーネの申し出た希望を聞いて、ラッセル伯は眉をひそめて面食らった。
『 お祭の興行を見てみたいのです 』
彼女はそう言い、芝居小屋を指定した。
豊穣祭には出し物が集まる。だが、夜毎どこかで夜会が催される貴族にとっては、それらは無縁のものだった。そうした興行を喜ぶのは下級に属する庶民達、つまりは下賎の催しだ。会場は碌な設備もない芝居小屋。布切れで囲われた粗末でいかがわしい天幕で、演者は教養のない浮民ども、そして、品性下劣な演目ばかり──無論チェスター候も、そう信じて疑わなかった。しかと我が目で見るまでは。
音の奔流に押し流され、チェスター候は身じろぎも瞬きも全て忘れて、ステージに釘付けになっていた。こじんまりとまとまった雇われ楽師の演奏などとは比べ物にならぬほど、それは流麗で豊かな楽の音だった。鋭いキレ、迷いのない潔さ、狂おしいまでに心底歌い、その内なる懊悩を洗いざらい絶叫する。彼らはいとも容易く、己が欲するままに表現していた。それの形を正確に。欠くことなく、取り零すことなく。楽師らの行なう修練の枠など、それらはとうに飛び越えている。彼らのそれは本能だ。鋭い牙を剥く野性の本能、いや、生命の躍動そのものだ。
胸の原風景が蘇る。郷愁を掻き立てる横笛の音。流れる弦、軽やかな管、時を刻む厳粛な打楽器、何より素晴らしい人の歌声。おお、そうだ。人の声というものは、どんなに素晴らしい楽器にも勝る!
歌え! いざなえ! その大いなる懐に!
午後の日差しを遮った薄暗い天幕の中、ほぼ満員の観客は静まり返り、息を呑み、ステージに釘付けになっている。今回の主役は人気の役者であるようで、客の入りは上々だ。
「……なんと、素晴らしい」
チェスター候は感極まって嘆息する。型破りなダイナミズム、息を呑むほどに高い跳躍、内に秘めた活力の爆発。振り払われたしなやかな指が、次の流れを呼び覚ます。今まさに、彼の手により与えられし唯一無二のその形。今、生まれしは"喜び"の形。今消え入るは"哀しみ"の形。緩やかに。秘めやかに。豊かに。高らかに。鍛え上げられたしなやかな肢体さえ
"美"につき従う手段だった。彼らは全身で表現していた。怒りを。絶望を。苦悩を。歓喜を。
大いなる調べに呑まれて、成す術もなくさまよい、漂う。なんという至福、なんという哀しみ。これら全てを感受できる、人の感性の偉大さよ。そうだ。神より賜りし、これぞ
──叡智。
チェスター候は席を蹴る。唖然と見つめる聴衆に構わず、一人敢然と立ち上がり、舞台に熱烈な拍手を送った。
「褒めてとらせる! 支配人を呼べ!」
終演後、チェスター候はハンカチを当てて鼻を啜り、会場のスタッフを手招きした。「君、支配人を呼んでくれたまえ」
終幕直後に叫んだのだが、誰にも相手にされなかったので、今度はきっちり指名で言い直す。ぞうきん片手に椅子を整理していた綿シャツの男は、ぽかんと口を開け、首を捻った。「……座長のことすかね」
「おお、では、その座長を」
やがて、客が引けたステージに、汗だくの首にタオルを引っかけた半裸の男が現れた。取り次ぎの男に「あそこです」と指さされ、怪訝そうに目を眇めている。
「おお、君だ!」
つかつかチェスター候は歩み寄った。主役を張った当人だ。半裸の男は胡散臭げに「あ?」と顔をしかめている。感極まって手を取った。
「おお、我が心の友よ!」
ぎょっ、と男が後ずさった。しかし、チェスター候は構わない。
「やはり──なんと美しい青年なのだ。いや、素晴らしかったよ! 君ぃっ!」
ぶんぶん上下に手を揺すり、思うがままに賛美する。今にも頬ずりしそうな勢い。何かが崩壊したようだ。
汗を滴らせた半裸の男は成すがままにされつつも、呆気にとられて固まっている。「……なに泣いてんだ、おっさん」
チェスター候は首を振り、陶酔したように嘆息した。
「まったく素晴らしいステージだった。ああ、なんという奇跡なのだ。怠惰なようでいて寄りかかることなく、一時も安堵してはいられない。最大限に神経を張り詰め、それでいて切なくなる程に繊細だ。輪郭がまるでブレていない。何一つ違わない、それ本来の姿形と!」
ピクリと男が眉をひそめた。
すっと冷ややかに目を眇め、だが、何を言うでもなく、軽い舌打ちで目を逸らす。「……なに言ってんだ」
ふと何かに気付いたようで、ぱちくり瞬き、視線をそらした。「サビーネちゃん?」
「素晴らしかったわ、ローイさま」
チェスター候の少し後ろで、サビーネが瞳を輝かせて会釈した。腕に抱いた溢れんばかりの花束を差し出す。「先日は、お招き頂きありがとう。わたくし、ぜひ拝見したくて、とうとう来てしまいましたわ」
「──あ、ああ。そいつはどうも」
片手でそれを受け取りつつも、ローイは釈然としない顔で二人を見やった。はらはら泣きはらした中年紳士と、にこにこ隣に並んだサビーネ。サビーネはもちろん大歓迎だが、何故にこんなのがくっ付いてきたのか、そこがどうにも腑に落ちない。
もっとも、連れなら他にもいるらしく、客の引けた出口の方に、紳士と同様こんな場には不似合いなモーニングコートの優男がいるのだが、チラチラこちらを盗み見つつも、決して自分からは寄ってこない。ぢーんっ! と鼻をかんでいる珍妙な紳士と関わり合いたくないようだ。
( ……まあ、気持ちはわかる )と見知らぬ優男に同情しつつも、ローイはチェスター候に目を戻した。
しげしげと首を傾げる。「あんたの顔、なんか、どっかで見たような──前に俺と会ったことねえか」
「……君と、かね」
はて、とチェスター候が顔を上げた。
しばし二人、首を傾げる。戦後に散々罵り合った仲の筈だが、殺伐とした混乱状態にあった為、互いを特定できないらしい。サビーネがにこやかに指摘した。「まあ、ローイさま。誰にでもそう仰るのね」
ぎょっとローイが振り向いた。
「いや! 俺はそんなつもりは──!」
あたふた訂正、すっ飛んで行ってサビーネに微笑む。「俺どうだった? かっこ良かった?」
「感動したっ!」
ずい、とチェスター候が間に割り込む。明らかにサビーネに訊いたのであるが。
うむ、と涙目で頷いている、どうもいちいち大仰な紳士に、ローイは迷惑げに眉をひそめる。「……そんな高尚なものじゃありませんや。こちとら、しがないどさ回りでね」
あんたじゃなくてサビーネちゃんに──と紳士の肩越しを覗き込む。ずずい、とチェスター候が視界の中央に移動した。
「援助をさせてもらおう」
ぴた、とローイは動きを止めた。
きょとん、と紳士の顔を見る。チェスター候は胸を張る。「何なりと言ってくれたまえ」
「──まさか、パトロンになるってことか?」
「そう言っているのだが」
チェスター候は鷹揚に頷く。ローイは唖然と絶句した。「……まじかよ。──あっ、いや! そいつはもちろん、ありがたいよ。そりゃもちろん、ありがたいが──」
後ろ頭をぼりぼり掻いて、値踏みするように、ちら、と一瞥。
戸惑い顔で、へいこら揉み手。「……あー、それでそのー……逢瀬はどちらで? いつから伺えばいいすかね」
「安心したまえ。私に男色の趣味はない」
いささか憮然と、チェスター候は顎を出す。なんということを言うのだ君は、といった顔。ほっ、と明らかに安堵して、ローイは胸を撫で下ろした。サビーネの笑顔に変化はないので、訳が分かっていないらしい。ステージの余韻を未だ引きずるチェスター候は、沈痛な面持ちで頭(かぶり)を振る。「しかし、なんと物悲しい筋だてなのだ。いや、神話というものは壮絶だな」
とっさに、ローイは吐き捨てた。「──実話だよ」
「実話、とな」
チェスター候は訝しげに呟く。やはり思わぬ答えであったようで困惑したようなサビーネと唖然と顔を見合わせた。
芝居仕立ての音楽劇は、神の怒りを買った下界の民が住み慣れた大地を追われる、という割合よくあるものだった。もっとも、チェスター候が見つめていたのは、そうした話の上っ面ではなく、底に流れる "魂の形"そのものであったのだが。
怪訝そうな相手の表情を一瞥し、ローイは忌々しげに目を逸らした。「──家を焼かれた事が、あんたにはあるか」
「家を?」
「俺は、ある」
きっぱりと言い捨てて、ローイは大儀そうにあぐらをかいた。首を背中にゆっくり倒し、しばらくじっと黙りこむ。目を眇め、天井の先を眩しそうに見つめた。
「……ただ成す術もなく、燃え落ちる家を見ていたよ。今朝方メシ食った小汚ねえ家を。めらめら燃えて、家が崩れていくんだよ。悪い事なんか何一つ、俺達は何もしていないのに。周囲に大人は何人もいたが、誰も何も言わなかったよ。燃え落ちる家をただ見ていた。家に火を点けた役人どもは、何事もなく戻って行った。あの頃俺はまだガキで、それでも、でかい理不尽を感じてた。──どうしてなんだ。地べたは本来、誰のものでもない筈なのに、なんでこんなひでえこと、他人にされなきゃなんねえんだ。誰かの領土といったって、てめえの物だと言い張って勝手に分捕ったって話じゃねえか。なのに、横取りされぬよう自分らに都合のいい掟まで作って、ちゃっかり力づくで従わせる、それがあんたらの奉る法律ってヤツだ」
汗の光る喉を伸ばしたままで、どこか投げやりに、くすりと笑った。
「でもよ、人間様と威張ったところで、力づくで分捕るだけなら、猿どもの縄張り争いと大差ねえだろ。いや、姑息な点で、まともに競う猿にも劣る。──あんたら、滑稽だよ。所詮あんたらの正体は、弱い者から取り上げて、逆らう奴を捻じ伏せて、それで勝ち誇った猿どもじゃねえか。どれだけてめえが醜いか、その面拝んでみるといい」
肩で大きく息をつき、ローイはゆっくり俯いた。眉をひそめて瞼を閉じ、昂ぶった気を鎮めるように荒い呼吸を整えている。サビーネが困惑顔で歩み出た。座り込んだままの半裸の肩におどおどと、だが、労わるようにそっと手を置く。「……ローイさま」
「──ごめんな。あんたに言ったんじゃない」
ローイは踏ん切りをつけるように息をつき、サビーネの手をやんわりとどけた。首だけを動かして、チェスター候に目を向ける。「悪いが、疲れているんでね。お帰り頂けますか、キリギリスさん」
チェスター侯は面食らった。「──それは、私のことかね」
ローイは膝に手を置いて、大儀そうに立ち上がる。
「あんたの他に誰がいるよ、そんな結構なご身分の方が。人の上に立つ者は、他人の命を預かってんだ。分厚い化粧と絹のドレスで夜毎くるくる舞い踊る前に、あんたはもっと知る必要があるんじゃねえのか」
鋭い視線に射抜かれて、チェスター侯は返事に詰まる。憎々しげにローイは続けた。「援助の話は結構だ。俺達は乞食じゃないんでね」
「──あ、いたいた!」
外光差し込む天幕の切れ目から、男が一人駆け込んできた。革ジャンバーの荒くれた身なり、ここの一座の者ではない。チェスター候を見つけると「散々探し回った」と言い、男は驚くべき話をもたらした。
国軍再来の凶報を。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》