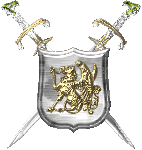
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 4章 interval 〜チェスター候の優雅な一日〜
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「──おお、お帰り」
ワイングラスを軽く持ち上げ、男はにこやかに挨拶した。ナプキンでチョビ髭を正しく拭い、三つ編みビーズの位置を直して、ゆったりまったり寛いだ風情だ。むしろ何故、あの男が当家の食卓で食事をしているのか、いささか解せない。
釣りで話が合った事が、そもそも知り合ったきっかけだった。あの男は趣味良く博識で、時に酒を酌み交わし、時に芸術論を戦わせ、つまるところ、彼とは話が殊の外合った。それにつけても、近頃我が屋敷から物が頻繁になくなるのは、一体どうした訳であろうか。
まあ、そんな些細な事はどうでも良い。
そう、今にして思えば、あぶなかしいとは思っていたのだ。
不慣れな高い靴がいけなかったのかも知れない。姿を見るなり、すぐさま場所を変えるべきだったかも知れない。習いたてのたどたどしい所作も、この災厄の一因かも知れない。しかし、誰が予想しようか。挨拶で腰を屈めた途端、ドレスの端をちょいと摘んで腰を屈めたその途端、後ろに引っくり返ろうとは。
そうだ。前代未聞だ。まさか平地でこけるとは。
長い裾を踏ん付けて、あの阿呆は尻もちをついた。よりにもよって、我が愛しのジュリエンヌの上にだ。あの麗しくも可憐なジュリエンヌを、事もあろうに尻で踏みつけるとは。
繊細なジュリエンヌは天に召された。
胸が張り裂けんばかりに悲嘆に暮れた。あれは珠玉の薔薇だった。いかな宝石にも勝るとも劣らぬ、ただ一輪の可憐なる青薔薇。薔薇には元来青はなく、我ら「青薔薇研究会」が総力を上げて取り組んだ、その研究成果がようやく形となって実を結び、文字通り花開いた奇跡とも言える宝だったのだ。それを、あの馬鹿女が。
ドレスの尻をどけた時には、我がジュリエンヌはぺったんこに伸び広がり、無残にもバラバラになっていた。薔薇なだけに。
がさつ女は顔をしかめて起き上がり「……ん?」と瞬いてそれを見るなり、悪びれもせずににっこり笑った。そして、
「あら、ごめんあそばせ」
あまりのショックに心臓発作を起こしそうになったとも。愕然と放心して見ていると、ふてぶてしい馬鹿女は、むに、と口先を尖らせた。不服そうなその顔には、
( いーじゃないのよ、それくらいケチ! )
ぬぬう、許せん。我が麗しのジュリエンヌを!
だから、ちょっと懲らしめてやったのだ。
公邸に使者が来たというから、自力でなんとかするよう言いつけた。無論、素人の未熟者を一人残して立ち去るほど、私は愚かではない。帰ったフリだ。こっそり戻って扉に張り付き、中の話を窺っていた。すると、なんということだろう。書状受領についての押し問答を続けた挙句に「ダドリーを人質にとった」などと聞き捨てならぬ事を言うではないか。
すぐさま屋敷に取って返したとも。愛する弟ダドリーを、ディールの手から奪還せねば! まずはラトキエに連絡を取り、早急に策を練らなければ。そうだ、すぐに商都へ行くのだ! ぬぬ、待っておれ弟よ! 遅ればせながらこの兄が、今、助けに行くからな!
屋敷の門を潜った途端、ただならぬ異変が私を襲った。具体的には、すぐさまトイレに駆け込んだ。ナイーブでデリケートな神経が「弟の命が風前の灯」などという、とてつもない緊迫状態に耐え切れなかったようなのだ。
以降、ベッドとトイレを激しく往復。その間、例の小娘が面会を求めてきたようなのだが、冗談ではない。便器のない所へなど出られるものか。しかもアポなし、この空前絶後の非常時に会ってやる義理など毛頭ない!
家人に言いつけ、追い返させた。対応に当たった執事の方も「今トイレに篭っているから」とはさすがに口には出せなかったらしく言葉を濁したようではあるが。ともあれ、
今日も激しい戦いだった……。
なにやら頬がやつれた気がする。ああ、心労は身に堪える……。洗った手をハンカチで拭き拭き、トイレのドアをパタリと閉めると、セバスチャンが控えていた。そそ、と近付き、上目使いで恭しく進言する。
「旦那様、一大事でございます」
聞けば、公邸に勤める執事仲間から、何やら聞き込んできたらしい。このセバスチャンは実によく仕えてくれる家族も同然の執事なのだ。そういえば、使者が公邸に来ていたな、と朦朧とした頭の片隅で思い出す。かくかくしかじかセバスチャンは語る。かくして、内容は驚くべきものだった。なんと、あの小娘が──もとい使者と面会した公爵夫人が、勝手に要請を蹴ったのだ。あの不穏な流れでは、意味するところは、
──開戦か!?
卒倒しそうになった。
翌日、同胞から話を聞き、私は耳を疑った。公爵夫人に召集されたのだという。初耳だ。
今、公邸から戻ったところだと不服げに語った紳士が言うには、胡散臭い傭兵から戦に備えるよう指図されたという。この地を収める貴族に対して、なんという無礼。なんという屈辱。むしろ、
何故、私には声をかけない。
どうせ、困って泣き付くだろうと敢えて連絡は取らなかったがしかし、事態はとんでもない方へと突き進んでいた。なんと愚かな。理解に苦しむ。何故にあの小娘は、そうも勝手に突き進むのだ! しかも、ことごとく茨の道へと。
そうだ、何故に教えを乞わない。やむにやまれず確かに居留守も使ったが、こうした場合は三顧の礼を尽くしてでも教えを乞いに来るのが筋というものではないか。
しかし、公邸が他領の使者に、正式に返答してしまったからには最早これまで、致し方ない。
「セバスチャン、あれを」
潔く心を決め、私はおもむろに指示をする。
執事が厳かに捧げ持ってきたは、先祖代々公邸に伝わる婿入り道具。我が偉大なる始祖より受け継がれし由緒ある白銀の鎧だ。
「すまぬ、ダドリー。これが済んだら、すぐに行く!」
重量感溢れるそれを三人がかりでようやく装着、公邸からの出陣要請を厳かに待った。そう、由緒ある騎士というものは、公邸からの要請を受け、然るべく出陣するものなのだ。勝手に気楽には出て行けないのだ。いつでも出られるよう玄関脇の小部屋で待機。士気を鼓舞すべく演説の原稿を清書して、三度の食事もそこでとり──。だが、いつまで経っても、お呼びがかからぬ。そうとなれば、出るにも出られず。
待てど暮らせど、知らせはこない。それでも我慢でじっと待つ。卒倒しそうな暑いさなかに、重たい鎧で蒸し焼きになりそうになりつつも、のぼせた額に氷のうを押し当て、「もう、おやめ下さい」とのセバスチャンの嘆願にも耳を貸さずに。
腹の調子がくるくるおかしい。しかし、鎧の着脱は容易ではない。外はわーわーやっている。窓の外の空が青い。出陣要請は、まだか。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》