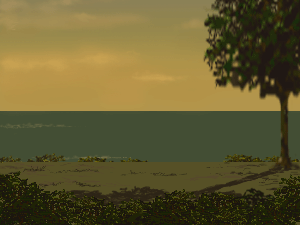
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 5章 3話11
( 前頁 / TOP / 次頁 )
シュッ、と素早い音がして、下に向けた紙筒の先から、明るい火花が噴き出した。鼻をつく火薬の匂い。パチパチ火花の爆ぜる音。宵の浜の暗がりが、ぱっとそこだけ明るくなって、楽しげな嬌声が一気に広がる。
宵の浜は賑わっていた。人だかりがあちこちにでき、仄かで華やかな明かりと共に、わいわいガヤガヤたむろしている。宵の浜にひしめいているのは、この界隈の住民だ。浜一面に広がって、手持ち花火に興じている。
パチパチ弾けて火花が落ちた。エレーンは膝を抱えてしゃがみこみ、隣に立った人影を見上げる。
「その髪、あたしは好きだけどな」
アルノーが面食らったように振り向いて、戸惑い顔で苦笑いした。「そいつはどうも」
「ねー、あたし、けっこう本気で言ったんだけどー」
どうも軽くあしらわれた気がして、エレーンは着流しの袖を引っ張った。「アルノーさん、その頭嫌いって言ってたけど、気にすることなんか全然ないわよ。お日様に透けると綺麗だし、むさ苦しく見えないし、ちょっと商都まで足を伸ばせば、色んな髪の人がいるもん。わざわざ染めたりだとか、脱色したりだとか、あ、前の勤め先のご主人様なんか、真っ赤な頭してたわよ。ま、ちょっと不良だったけど」
「ありがとうございます、嬉しいですよ」
「……ねー。本気にしてないでしょう」
むう、と口を尖らせて、エレーンは裾を払って立ちあがる。雪駄をすって歩きつつ、アルノーは微笑った。「そんなことはないですよ」
ぬぅ、とエレーンは口をつぐんだ。絶対、軽くあしらわれている。足をぶん投げ、ふてて歩いた。次の花火をもらいに行くのだ。
楽しげな人だかりを縫って歩く。子供らに花火をさせながら、大人はうちわで蚊を払い、焼きイカ片手に談笑し、コップ酒を飲み交わしている。子供にねだられた親たちが露店で花火を買い求め、宵闇の暗がりでは、地面に置いた噴き出し花火の導火線に点火する。紙筒が火花を噴水のように吹きあげて、周囲の人だかりで歓声があがる。このささやかな気晴らしを、皆それぞれに楽しんでいるようだ。初めは内輪の遊びだったのだが、今では、ちょっとした夏祭りといった風情だ。
元の場所まで戻ってみると、黒いランニング姿のファレスと、ポタンのない白の綿シャツに着替えたウォードが、気楽亭の女将の向こうで、相も変わらずいがみ合っていた。
突如部屋に現れたウォードは、ひどく疲れた様子だったが、すっかり回復した様子。あの昼寝が効いたのか、階下にある食堂で「おばちゃん、おかわり」とどんぶり飯三杯をもりもり平らげたのが効いたのか、今は楽しそうに遊んでいる。主にファレスを相手にして。
「ウォード! 花火で爆撃すんなっ!」
額に包帯を巻いたファレスは、片足をやや引きずりながら、あたふたウォードから逃げている。まなじり吊りあげ、シッシと手を振るファレスの後を、ウォードが花火をぐるぐる回して、面白がって追い回しているのだ。花火がよほど気に入ったらしい。女将が見かねて声をかけた。「こら、ウォード。火を人に向けるんじゃないよ。危ないだろう」
ウォードが足を止めて振り向いた。
「わかったー」
意外にも素直に花火を持った手をとめる。へえ? とエレーンは目を丸くした。他人の話をまともに聞くとは珍しい。女将は微笑って後ろにまわり、突っ立ったウォードに手を添えた。「花火ってのは、こうやるもんさ」と火花をゆっくり下に向ける。
「ほうら、ごらん。綺麗だろう?」
小柄な女将に寄り添われ、背の高いひょろ長いウォードがじっと大人しくうつむいている。女将と一緒に足元の花火を眺めている。ガラスのように透明な瞳で。無防備な顔だ。仲間に混じっている時は、あんな顔はしないのに。
子供と大人の狭間の顔。まだ何者にもなりきれていない。けれど、それでも何者であるのか「核」の兆しを秘めている──不思議なものだ、とエレーンは思う。ああしていると、ウォードが年相応の少年に見える。女将と二人寄り添う様は、仲の良い親子であるかのようだ。
そう、女将は初めからウォードのことを、彼の年相応に、十五の子供として扱った。長身の見た目に騙されることなく、女性受けする見栄えの良さに惑わされることなく、あの彼の本質を初めから正確に見抜いていた。そうして我が子に接するように、甲斐甲斐しく世話を焼いた。食事の時にも、そして今も。つまり、ウォードは早々と、女将のお気に入りになったようだ。
ちなみに、見てくれだけなら端整なファレスも、ずいぶん女将を気に入った様子で、事あるごとに「なあ女将、なあ女将」とまとわりついていたのだが、その肝心の女将の方は「そんなに元気なら、自分でおやり」といわんばかりに、何気に軽くあしらっていた。熱烈アピールされていたルクイーゼの娘らにはまるで見向きもしなかったくせに、自分がまとわりつく相手には無下に扱われるというのだから、世の中はどうも、うまくいかない。
ウォードに散々虚仮にされ、ファレスは隣のグループの陰にまで逃げていったようだったが、口をへの字にひん曲げて、憮然とした顔つきで戻ってきた。ランニング一丁のその腕を、エレーンは口を尖らせて捕まえた。
「ねー。アレ、どしたのよー。あんたにあげたお揃いのお守り」
ファレスは日頃から装飾品の類いはつけないが、今もランニングの首元は、すっきりしていて何もない。「ほらあ。あたしがお土産であげたやつー」とすかさず抗議をねじ込むと、ウォードを睨む目を返し、たじろいだように立ち止まった。
「……ああ、あれな」
不意を突かれたかのごとくに口ごもり、ファレスは視線をさまよわせ、浮ついた様子で夜空を仰ぐ。口を尖らせ、白状した。
「どっか、いっちまった」
「……はああ?」
くるり、とファレスが踵を返した。捕獲するよりわずかに早く、そそくさ、どこぞへ離れていく。つまるところ、
──もう失くしやがったのか!?
あんぐりエレーンはファレスを見た。確かに、食い物以外は興味を示さないだろうとは思っていたが、よもや本当に捨てちまうとは。あのずぼらなケネルでさえ、まだ首にぶら下げているというのに。
叱責を恐れて逃亡を図ったと思しき当人は、女将と大人しく花火をしているウォードの所へ向かっている。すたすた近づき、着いた途端に、ウォードの腰に蹴りを入れた。
障害物を手荒くどかして、二人の間にぐいぐい割り込む。呆気にとられた女将の前に、ひょい、とファレスは舞い戻り、ふんぞり返って花火を出した。
「女将、こいつにも火ぃつけてくれ」
女将のそばから押しのけられて、むっ、とウォードが振り向いた。すぐさま取って返して、ファレスの尻を蹴り返す。ファレスがたたらを踏んで振り向いた。
「──てめえっ! ウォードっ!」
「そっちが先に蹴ったんだろー!」
陣取り合戦が始まった。やられた分はやり返す。あわよくば多少の色をつけて。どちらも全く容赦ない。エレーンはやれやれと嘆息した。きっと恐らくこいつらは、これと似たようないがみ合いを延々続けていたに違いない。案の定、腕を組んで見ていた女将が、額に手を当て、溜息をついた。
「いい加減におし二人とも。喧嘩するなら、とりあげるよ!」
ぴしゃりと女将に一喝され、どさくさに紛れて蹴られたファレスが、たたらを踏んで振り向いた。
「俺が金払ったんだぞっ!」
女将の取り合いをするファレスとウォードを、アルノーは静かに眺めやり、女将の後ろで影のように佇んでいる。特に何を言うでもないが、本当は面白くないんじゃないかと、ふとそれが気になった。
宵の浜では、手持ち花火の住民が所々でたむろして、それぞれに盛りあがっている。しゃがみ込んだ子供や母親、夕涼みの見物人、飲んだくれた野次馬や、連れ立って見にきた若い娘の二人連れ──クリスがいたら喜ぶだろうな、と、そんなことをぼんやり思った。一人で生きてきたクリスには、こんなに大勢で遊ぶのは、きっと初めてのことだろうから。みやげ物を渡した時の、心底驚いたクリスの横顔が蘇り、エレーンはそっと一人微笑む。どうしていいのか分からずに無為にきょろきょろ見回していた、不安と興奮がない交ぜになった落ち着かない歓喜の顔。
『 わあ! あたし、こんなの初めて! 』
立ち込める火薬の匂い。
暗い浜のあちこちが、明るく楽しげに華やいでいる。賑やかな一団からさりげなく離れて、エレーンはそっと嘆息した。女将の取り合いに気をとられ、こちらには誰も気づかぬようだ。さっきも内緒で離れたのだが、アルノーにばれて迎えに来られてしまった。けれど、今度は大丈夫。
ぶらぶら歩いて、暗い海の波打ち際へと足を向けた。静かにきらめく星々が、黒い天蓋でまたたいている。楽しげな賑わいを背に感じ、夜空を仰いで呟いた。
「……ごめんね、ダド。これで許して」
これが、今できる精一杯。
職人が手がけるような打ち上げ花火を、ダドリーの新しい年齢分、派手に打ち上げるはずだった。こんなちゃちな、手持ちで楽しむ花火ではなく。それが彼との約束だった。
夢の花火が何であるのか、初めの内はわからなかった。夜毎現れるあの夢は、手出しできない遠い空を、突き放されたように眺めている、ただそれだけの夢なのだ。
何度も「夢」を見る内に、ふと、そのことに気がついた。あの夢の光景に「心当たり」があることに。それは以前に交わしたダドリーとの約束だった。それを予告し「夢」が映像を見せている。旅に出る以前から予定に組まれていたことを。
あの約束は守りたい。ダドリーと交わした約束の、辛うじて繋がっている細い絆の「最後」になるかもしれないのだ。だが、それを忠実に実行すれば、夢の「花火」が現実のものとなってしまう。あの「花火」が実現すれば、きっと「階段」も実現する。でも、あの「階段」には近寄りたくない。
恐ろしかった。底のない不吉な未来に、着実に近づいているようで。抗うことさえできぬまま引きずりこまれていくようで。夢で見た「打ち上げ花火」は、たぶん「幕開け」を暗示している。恐ろしいことが起こる予兆を。
それなら「予定」を変えてしまえば、「夢」は実現しないことにならないか。大掛かりな花火は、専門の職人に打ち上げを依頼する必要がある。海岸なり河川なりの水が豊富な広い場所も必要だろう。以後のトラビアまでの道のりで、そうした条件にかなう地域は、レーヌを出れば、そうはない。ならば、レーヌで実行せねば、実現しないことになる。
これは「すり替え」だ。ほんのささやかな抵抗に過ぎない。それは分かっている。けれど「夢」に見つからないよう密かに少しずつ抗えば、きっと結末は変わるはずだ。出発点は同じでも、軌道を途中でずらしてしまえば、来るべき未来の終着点も、自ずと必ず逸れるはず。
未来はきっと変えられる。そうだ、きっと変えられる。何をしようが何をすまいが、同じ未来が到来するなら、悩み、抗い、苦労するのは一体なんの為だというのだ。
波打ち際でしゃがみ込み、寄せては返す足元の波に、指の先を浸けてみた。地平の果てから覆い被さってくるような、黒々とうねる大海を、背中を丸めて眺めやる。
「……これで、おしまい」
エレーンはうつむき、溜息をついた。心を大きく占めていた心配事をやり過ごし、急にふっつり気が抜けてしまった。いささか強引ではあるけれど、これで「花火」は実現しない。だから、もう大丈夫。これで、きっと
──あの「階段」はなくなった。
ふと、エレーンは顔をあげた。何か気配を感じたのだ。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》