



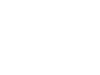
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 5章 3話12
( 前頁 / TOP / 次頁 )
頬に当たる見えない感触。ほんの微かに圧迫感があった。向かいからの海風が、そこだけ薄く固まったような感じ。意識を向ければ、たちまち霧散するほどの、微かで確かな存在感──波打ち際で膝を抱えて、怪訝に視線を巡らせる。
人だかりから離れた波打ち際に、男が一人立っていた。夕闇に紛れた体の向こうで紫煙が薄く立ちのぼり、海からの向かい風に、黒い髪がなびいている。
はっ、とエレーンは息を飲んだ。後頭部の髪の具合、肩から背中にかけての線、深緑の半袖の綿シャツ、ポケットのたくさんついた穿きこんだズボン、あれは──慌てて浜から立ちあがり、両手を振って人影に駆け寄る。
「ケネル!」
海の彼方を眺めていた背が、ふと気づいたように身じろいだ。片足に重心を預けて、気怠そうに目を向ける。「──ああ、あんたか」
「今まで、どこに行ってたの?」
面倒そうに眉をひそめて、ケネルは横を向いて紫煙を吐いた。「アドルファスの所にな」
「ずっと? ずっとアドの所に? もしかして、今戻ったの?」
話によれば、レーヌに帰着し、気楽亭に戻った際に、皆が海岸にいる、と聞いたらしい。元いた場所を振り向くと、昼に出かけたダナンたちや、セレスタンたちの顔が見えた。皆、無精ひげを剃っていて、こざっぱりとしたいつもの顔に戻っている。今しがたまで四人の少人数で遊んでいた女将チームは、今や倍以上の人数だ。セレスタンが咥え煙草で花火をぶらさげ、横ではジョエルがかじった焼き串を横に引き、恰幅のいい赤ら顔のロジェが黒い小瓶をあおっている。誰かが酒を持ってきたらしく、合流した彼らと共に寛いだ様子でたむろしている。上機嫌なロジェに笑いかけられ、女将やアルノーも笑っている。いつの間にやら、あのクロウの顔もある。ふと、風を感じて振り向けば、隣に立っていたケネルがいない。
「──あ! ちょっと待ってよ、ケネル!」
エレーンは慌てて後を追った。ケネルは煙草をふかしつつ、仲間たちの喧騒から離れていく。手にした小瓶をラッパ飲みしながら足を投げ、波打ち際を歩いていく。
やがて、浜に打ち上げられていた流木の一つに、ぶっきらぼうに腰をおろした。疲れているのか、身ごなしが投げやりだ。いつにないケネルの様子に内心いささか戸惑いながらも、エレーンもすかさず隣に座った。途端、肩を引いて顔をしかめる。「──んもー! ケネルってば煙いぃー。煙草はやだって言ってんのに」
「嫌なら寄るな」
ケネルは素っ気なく紫煙を吐いた。むぅ、と更に肩を引きつつ、エレーンは口を尖らせる。この程度の迫害ごときじゃ、無論めげたりしないのだ。
「あ! ねーねー、ケネル。アドの所に行ったとか言って、実はクリスに会いに行ってたりするんじゃないのおー?」
ちょっとばかり面白くない思いで、ちくりと皮肉を仄めかす。ボタンのない綿シャツ一枚の、珍しく身軽な服装のケネルは、座った両膝に腕を置き、うつむいた首を気怠そうに回している。「いや、アドルファスの所だ」
「……そ、そっか」
エレーンはしどもど引き下がった。ケネルの機嫌が何気に悪い。居心地の悪さをひしひし感じて、上目使いでケネルを見た。「もしかして、怒ってる?」
「──そんなことを、なぜ訊くんだ」
かったるそうに問い返されて、エレーンは慌てて付け足した。「あ、だって花火するのは駄目だって、ケネルずっと言ってたし、でも──」
それが事もあろうに、この花火大会だ。いつの間にやら、ご近所さんまで多数参加で。
冷や汗で隣を窺うと、ケネルは「……ああ、そのことか」と呟いて、うつむいた後ろ頭を面倒そうに掻いた。「構わない。ここで騒ぎを起こすほど、連中も馬鹿じゃないだろう」
ケネルの言う"連中"というのは、これまで再三襲ってきたあの賊のことだろう。投げやりな言い方に、いささか呆れてケネルを見た。「なんで、そんなことわかるのよ」
「警邏が出張っている」
どことなく煩わしげに、ケネルはぶっきらぼうに顎でさす。そちらの方向に視線を巡らせ、エレーンは目を丸くした。
「……ほんとだ」
楽しげに憩う人々の周辺、浜の薄暗い隅の方を、制帽を被った男たちが目立たぬように巡回していた。今見えているだけで、ざっと六人。その何れもが制服を着たレーヌの警邏だ。唖然とケネルを振り向いた。「でも、なんで警邏が海岸なんか見回ってんの?」
通常ならば、夜半の海岸にまで警邏はこない。
「レーヌは与太者の巣窟だ。二大派閥が始終縄張りを争っている。人が集まる催しは、連中には恰好の小競り合いの場だ。大抵どちらかの酔った輩が調子に乗って揉め事を起こす。抗争騒ぎは今に始まった話じゃないが、それに住人が巻き込まれたとなれば厄介だ。レーヌは住人の力が強い。その最たる顔ぶれは高級別荘地のお歴々だ」
そうした住民と警邏との間の、特別で繊細な力関係については、地元の店主たちも心得ているから、別荘地との親交を日頃から深め、これと要領よく連係し、或いはこれを利用している云々──淡々とケネルに説明されて、エレーンは目を丸くする。「……よく、そんなこと知ってるわねえ、ケネル」
あたし全然知らなかったわー、と隣の男をつくづく見た。生まれてこの方、レーヌからそう遠くない商都で暮らしてきたけれど──いや、そんな内情を知っているのは、生活に直接関わりのある地元の住人くらいだろう。ましてケネルは、この国に住んでいるわけでもないのに。
「呑気だな」
「……え?」
ケネルが乾いた笑いで苦笑いした。「平和な国だな、カレリアは。何も知らずとも生きていける」
「そっ、そんなことは──!」
むっとして反論しかけ、だが、何も言い返すことができないことに気がついた。それにしても、ケネルにしては珍しい皮肉だ。
ケネルは流木の木肌に後ろ手をつき、向かい風に吹かれている。時折瓶から酒をあおり、煙草をふかして暗い海を眺めている。何を言うでもない。ケネルは日頃から無口だし、特に口をきかなくても、普段であれば気にならない。けれど今は、空気がよどんで重く感じた。ケネルの飲酒にも驚いたが、どこか投げやりな風情といい、今の皮肉な物言いといい、こんな様子は珍しい。
ふと、ケネルが泣いている気がして、横顔を恐る恐る覗いてみた。
ケネルは泣いてはいなかった。その目は静かに、寄せては返す海の唸りを眺めている。何故、そんなふうに思ったのだろう。ケネルが泣いたりするはずはないのに。
窮屈な無言が居心地悪くて、エレーンは夜の浜の賑わいを眺めた。「……誰も呼んだりしないのに、なんで大ごとになってんのかしら」
夜の浜を貸しきって、内輪で遊ぶつもりだったのだ。昼でさえ閑散とした海岸ならば、どうせ誰もいないだろうから。
「ファレスの仕業だろ」
口の端を持ちあげて、事もなげにケネルは笑った。その当人がいる浜の暗がりに視線をやる。「大勢いれば紛れこめるし、警邏がいれば安全だ」
ファレスはウォードをなじりつつ、相変わらず女将を取り合っている。今度はセレスタンらにも冷やかされ、そちらにも食ってかかりながら。エレーンはぽかんとケネルを見た。「それじゃあ、こんなふうにする為に──そんなことまで考えて、花火を買う時、あんなにたくさん?」
「奴は用心深いからな」
確かにファレスは、興味津々集まってきた子供らに、自腹を切った箱積みの花火を惜しげもなくばらまいた。日頃の粗野な性格からは凡そ信じられぬくらいに気前よく。その一方で子供らは、ただで花火がもらえると知るや、嬉々として仲間を連れてきた。やがて、夕涼みしていた者たちが、なんだなんだと花火を手にし、昼には閑古鳥が鳴いていた店の主が、この人だかりを見咎めて、すかさず軽食や飲料を売り始め、そうなると、これを商機と見た身軽な露店が浜に次々移動して、いそいそランタンに火を灯す。人だかりは人を呼び、みるみる野次馬が膨れあがり、今ではこの賑わいだ。
つまりファレスは、昼に花火を大量に買い求めたあの時点で、こうなることを狙っていた、ということか? 今更ながら気がついて、エレーンは唖然と絶句した。その仕組んだところの当人は、女将に耳を引っ張られ、涙目で食ってかかっている。そういえばファレスは、そうした密かな根回しを、いつでも普通にやってのける。だが、その当人は、特別なことをしているとは露ほども思っていないだろう。そう、今にして思えば、泊まるゲルを借りる時にも、食事の手配をする時にも、クリスの服を借りてきた時にも──
「あ! あたし、あの服探さないと!」
はた、と懸案事項を思い出した。
「ほら、今まで着てたクリスの服。だって、あれ、借り物だもん。失くしたなんてクリスに言ったら、あたし、なんて言われるか」
ケネルが苦々しげに紫煙を吐いた。「返さなくていい」
「──あ、でも」
「必要ない!」
ビクリ、とエレーンは首をすくめた。叱責といえるほどの激しさだ。思わぬ剣幕に驚いて、恐る恐る隣を見る。
どさり、と肩に重みがかかった。ぎょっと体を硬直させて、そちらの様子を窺えば、ケネルが横から身を乗り出し、肩の上に覆い被さっている。
「……ケ、ケネルっ?」
重たい体を両手で支えて、エレーンは身構え、戸惑った。顎の下で手首をつかんで、ケネルが肩に伏せている。こんなことは一度もなかった。自分から引っ付くことはあっても、その逆はない。
動転しながら視線を伏せれば、浜に瓶が転がっていた。中身はカラであるようだ。もしやケネルは酔っている? 綿シャツの背中をおろおろさすった。「ど、どしたの?──あ、もしかして気持ち悪い?」
「……疲れたな」
深く息を吐き出して、ぼそり、とケネルが呟いた。ひどく疲れたような声。
ケネルの体温を間近に感じる。気分が何か落ち着かなかった。彼の脆い部分を見せられたようで、弱みを晒されてしまったようで。ケネルに弱音は似合わない。
黒く、広い海原から、波が静かに寄せていた。くり返しくり返し、未来永劫途絶えることなく。何故、自分はこんな海にいるのだろう。
忙しない日常から不意に離れて、ふっと急に気が抜けてしまった。心が空っぽになってしまうと、空いた間隙をすぐさま埋めて"それ"が侵食し始める。閉じ込めておいたあの想いが。
──自分はトラビアに向かっている。
じっと静かにしていると その事実が今更ながら押し寄せた。その重圧に押し潰されそうになってしまう。そう、紛れもない現実だ。いくら目をそむけようと、平気な振りを決め込もうと、自分は今、紛れもなく、あのトラビアに向かっているのだ。ダドリーの最期を見届ける為に。
肩に顔を伏せたまま、ケネルは口を開かない。じっとそのまま動かない。紫煙だけがゆらゆらと、暗い天蓋へ立ちのぼっていく。怖気が背中に押し寄せた。
「……ケネル、助けて」
ダドリーを。
知らぬ間に口を付いた呟きは、けれど、押し殺した声が震えて肝心の言葉が声にならない。うつぶせた顔を軽くすりつけ、ふっ、とケネルが自嘲気味に微笑った。
「俺には、助けられないよ」
驚いてエレーンは振り返る。一瞬、何が起きたか、わからなかった。諦めや卑下はこのケネルにはそぐわない。いや、まだ全てを言っていない。ダドリーの名前を口に出していない。なのにケネルは的確に答えた。話の意図を正確に汲んで。
困惑してケネルを見る。ふっ、と肩が軽くなった。海風を遮る体温が、不意に離れ、すぐに遠のく。ケネルがだしぬけに立ちあがった。
「少し、酔った」
短くなった煙草を投げ捨て、素っ気なく背を向けた。歩き出したその足は、皆がたむろす元の場所へと向かっている。ケネルは彼らの輪まで辿りつき、黒瓶をあおっていたセレスタンに「俺にもくれ」と手を出した。エレーンは困惑して後を追う。ケネルの様子が変だった。ひどく参っているような。そういえば、レーヌの小屋で目覚めてから、ずっと様子が変だったような──?
世界の栓が、抜けたような音がした。
空で太鼓を打ち鳴らすような音。大地を揺るがすような、胸に響く轟音。光源が夜空で炸裂し、宵闇が一瞬にして明るくなる。
「──な、なに? 雷っ?」
両手で耳をとっさに塞いで、エレーンは慌ててしゃがみこんだ。音源は西の方向だ。けれど、おかしい。こんなに晴れているのに落雷が? いや、あれは雷じゃない。
体の芯がすうっと冷えた。空でぱらぱら火花が砕け、地上に向けて降り注ぐ。ファレスが身じろぎ、怪訝そうに空を仰いだ。人々のざわめきが不意にやみ、沈黙は尚、深くなる。
暗い海岸のあちらこちらから、どよめくような歓声があがった。エレーンはのろのろ立ちあがる。空気が薄まりでもしたように、肺にうまく入っていかない。俄かには信じられなかった。だって何故、実現してしまうのだ。夢で見た光景が。あの「打ち上げ花火」の光景が。きちんと回避したはずなのに。
夢の尻尾に振りまわされて、息もできない。水の枝で空を払って、なかったことにしてしまいたい。予感があった。もしも"それ"が実現すれば、他に見た全ての夢も、ことごとく実現してしまう。
花火は、次から次へと打ちあがる。体がわなわな震えだした。わからなかった。何故こんなことが起こるのか。打ち上げ花火の手配など、自分は全くしていない。ならば、街の催しが今夜に偶然重なったのか。だが、そんな話は聞いてない。誰からもどこからも聞いてない。そもそも、催しなどであろうはずがなかった。行事の予定がないからこそ、退屈しきった住民が、こうして集まってきたのではないか。なのに、どうして──
「ザイっすよ」
打ち上げをしている暗がりを、セレスタンが立てた親指で軽く指した。面食らって目を向けると、離れた海岸の暗がりで、赤々と火が焚かれていた。打ち上げ地点がある辺りだ。
浜の男たちが数人で、焚き火を囲ってたむろしていた。手を振ったセレスタンに気がついて、笑って手を振り返している。炎の照り返しに浮かびあがる顔、顔、顔──その中に、見知ったあの横顔を見分けた。あのザイの横顔を。
「快気祝いっすよ」
のんびりとセレスタンは笑った。
「実は、俺らも驚いたんですが、あそこの花火師連中に、ザイが話をつけてきましてね。で、具合のいいことに向こうさんも暇でね。今年は客がさっぱりだってんで、二つ返事で引き受けてくれました。で、どうせなら景気付けに派手にやるかってことで──ああ、ほら、姫さん、ずっと花火やりたがってたでしょ」
「で、でも! なんで、あのキツネがそんなことを」
「──キツネって、もしかして、ザイのことすか」
セレスタンは唖然と見返して「──こいつはいい」と苦笑いした。ザイがいる向こうの焚き火を眺めやり、ちらりと目の端でこちらを窺う。「……気にしてましたよ? ザイの奴。なにせ、姫さん崖から落っことしたの、自分だってんですからねえ」
思わぬ言葉に面食らい、エレーンはやっとのことで訊き返した。「あいつがそう言ってたの? つまり、そのことを気にしてるって」
「まさか」
セレスタンはおかしそうに首を振った。「奴は何も言いませんよ。でも、レーヌに着くまで、ずっとカリカリしていました。もう、おっかねえのなんのって。──ま、いいもん見せてもらいましたがね、ザイのオタついた面なんぞ滅多なことじゃ拝めやしねえし。でもまあ、そっちはともあれ」
ランニングの腕をやおら組み、含み笑いの目を向けた。「仲直り、したんでしょ?」
「……え?」
訳がわからず、エレーンは戸惑う。
「いや、だから──ほら、さっき海岸で。姫さん、奴と話していたでしょ」
二の句が継げずに、エレーンは口を開閉した。さっきのアレは、そんな友好的なものじゃない。向こうが一方的に喋っただけで。セレスタンが腑に落ちなそうに小首を傾げた。「あれ、違うんですか? だったら奴と何してたんです?」
「──う゛」とエレーンは肩を引いた。それがわかれば苦労はない。不思議そうにまじまじ見られ、ちら、と上目使いで顔を見る。「……に、睨めっこ、とか」
「睨めっこ?」
呆気にとられた顔つきで、セレスタンが瞬いた。
「う、ううん! いいの、なんでもない! 花火ありがと、セレスタン」
慌てて手を振り、エレーンは何とか笑みを作った。「どういたしまして」とセレスタンも笑う。上手く笑えた自信はないが、暗がりの中では気づかぬようだ。
「──ああ、そうか」
不意にファレスの声がした。振り向けば、ファレスは目をすがめて顎をなで、華やかな夜空を眺めている。
「こいつ、だったか」
皆がそれぞれの場所で振り向いて、夜空に咲いた華を見ていた。轟音が空を揺るがして、天蓋に光彩が放たれる。いく度も、いく度も、くり返し。
ポーンとあがり、夜空に開く花火の夢。手を伸ばして遠く届かぬ、天空に浮かぶ巨大な華やぎ。全ての終わりを告げる華。
ゆるい海風の闇に紛れて、いくつもの人影が夜空の華を眺めていた。白い華、赤い華、青い華、誰もが各々の場所で手を休め、言葉少なく見入っている。ケネルが、ファレスが、ウォードが、セレスタンが。
息をつめて空を凝視し、エレーンは身じろぎもせずに立っていた。すっ、と一筋、何かが頬をすべり落ちる。
──孵化してしまった。あの夢が。
震える吐息に紛らせて、ようやく"それ"を呟いた。
「……お誕生日、おめでとう、ダド」
黒く広がる海岸の夜空に、花火は次々打ちあがる。
花火はあがり続けている。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》