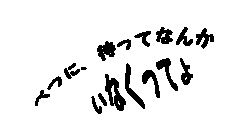
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 5章 interval04 〜お嬢様の憂鬱 3 〜
( 前頁 / TOP / 次頁 )
休憩中の店内で、着流し姿のオーサーと女将が、差しつ差されつ飲んでいた。
その卓から少し離れて、手酌で飲んでいるアルノーの姿。オーサーと女将は夫婦も同然、誰もが認める好い仲だ。
しっぽり飲んでいる二人の間に、にゅっと顔が割り込んだ。
二人をぐいぐい左右に押しのけ、二人の真ん中に女は陣取る。
女は女将に振り返り、にっこり湯飲みを突き出した。
「わたくしもっ!」
いいムードの二人の様子を、向かいで見ていたエルノアである。
実は密かにアルノーに、女将を誘惑するようせっついたが、アルノーにあっさり断られ、己で出向いた次第である。
ガタンと椅子の脚を鳴らして、オーサーが席を立ちあがった。
店の奥へとそそくさ向かう。どうやらエルノアの頭の向こうに、眉一つ動かさぬ女将の、見てはならないものを見てしまったらしい。
歩き出したオーサーに気づいて、エルノアもあたふた席を立つ。
「──わっ、わたくしもっ!」
奥へと向かうオーサーを、エルノアはにこにこ追いかける。
「おじさん、わたくし、あまり早くは歩けなくってよ」
真後ろにピタリ──とくっついているが。
ちなみに、天下のオーサーも、エルノアにかかれば「おじさん」である。
オーサーは廊下をすたすた歩き、角を曲がって、立ち止まった。
薄暗い板戸を前にして、ノブに手をかけ、停止している。
雪駄の着流しで立った背が、溜息まじりに振り向いた。
「なあ、嬢ちゃん。前にも言ったと思うんだが」
「なあに? おじさん」
エルノアはにっこり首をかしげる。
「厠にまでついてくるのは、やめにしねえか」
近くの壁で待つことしばし、板戸の向こうから声がした。
「──まったく、気が知れねえな」
オーサーの声だ。手を洗っているらしい。
「俺なら、ほうっておかねえんだがな。あんたみたいな別嬪を、いつまでも一人でほおっておいたら、他の野郎に取られねえかと気が揉めちまっていけねえや」
エルノアが ん? と顔をあげた。
ふぅ〜むと何やら考えている。
不敵な半眼で、笑みを浮かべた。
「とっても参考になってよ、おじさん」
アルノーは釣竿を肩に、レーヌの海岸を歩いていた。
ため息をついて、連れを見る。
「どこまで、ついてくるんです?」
エルノアは胸で手を握り、アルノーににこにこと宣言する。
「わたくし、つき合ってさしあげても、よろしくってよ」
彼女の言う「つき合う」というのは「いずこかへ連れ立つ」という意味ではない。「恋人になってやる」との意味である。
アルノーはあっさり返答した。
「生憎と、これから仕事でしてね」
ぽかん、とエルノアは放心した。誰かに軽くかわされるなど、これまでただの一度もない。
アルノーは何事もなかったように、船を海へ出そうとしている。
彼には伝わらなかったか、とエルノアは気を取り直して笑顔を向ける。
「わたくしは船のデートでも構わなくってよ」
さあ、ここまではっきりと言えば、間違えようがないであろう。
「部屋付きの船以外は乗れなくってよ」だの「日なたはお肌に悪くってよ」だのとダダをこねまくるエルノアが、ここまで譲歩するには理由があった。別に彼女がアルノーに、恋をしているわけではない。
エルノアの魂胆はこうである。
──こんなことを知ったなら、いかに無関心なあの彼でも、すっ飛んでくるに違いない。
他の男がエルノアに、言い寄っている、と知ったなら。そーよ。おじさん(←オーサーのこと)だって言っていたもの。
つまりはこのアルノーを、当て馬にしようと目論んだのだ。ちなみに、アルノーを選んだのは、ただただ見た目が良いからである。
「聞こえなかった? わたくしは、船でデートでも──」
「すいませんが、一人乗りでして」
十分後、真昼の浜で、ひとり手を振るエルノアがいた。
無敵無敗のエルノア嬢、まんまとアルノーに逃げられる。
アルノーは片手でのれんをよけて、馴染みの店の敷居をまたいだ。
夕暮れ時には珍しく、気楽亭は閑散としている。
がらんとした店内に、斜光が赤く射していた。レーヌの町の喧騒が、遠く絶えまなく聞こえてくる。昼の奇妙な時化のお陰で、町は未だに大騒ぎ、この店も商売あがったりだ。
アルノーはぶらぶら店内を進み、隅の卓を見て、苦笑いした。
「やけ酒飲んで、泣き寝入りですか」
夕焼けに染まった片隅で、茶髪のつむじが突っ伏していた。卓の上に転がっているのは、空になった瓶が数本、底に酒が残ったコップ。
寝入った彼女の斜向かいに、着流し姿のオーサーがいた。店の戸口に背を向けて、一人で酒杯を傾けている。どうやらオーサーはエルノアの、相手をしてやっていたらしい。
女将の姿は店になかった。いつものように奥の板場で、水仕事でもしているのだろう。
アルノーはそのまま奥へと向かった。ひっそりとした帳場に入り、きれいに拭いた天板から、伏せてあった杯と、酒瓶を一本取りあげる。
店の中へ引き返すや、オーサーが顎先でエルノアを指した。「向こうのアジトをぶっ壊したって?」
アルノーはそちらへ足を運ぶ。
「まったく、たいしたもんですよ。知らない老人を助けてやって、手下の仇もきっちりとって、てめえで落とし前をつけるんですから」
なのに──とアルノーは苦笑いした。そう、そんなに勇ましいのに、
「商都がある方角を、じっと見つめていなさって、ずっと、うろついていましてね。街道の端を行ったり来たり。待っていなさるんでしょうねえ、あの人を」
「たく。さっさと迎えにきてやりゃいいものをよ」
くい、とオーサーが酒杯をあおる。
「ま、このところの乱痴気騒ぎだ。商都が忙しいのも分かるがよ」
実は、ラトキエが反撃に転じて、商都の封鎖は解けていた。だが、大陸の端にあるレーヌには、知らせがまだ届いていない。
オーサーが椅子に腕をかけ、「時に、アルノー」と振り向いた。
「おめえ、時化で流されたんだってな。──お前もよくよくついてねえな。遠出をしたその日に限って、時化に当たるってんだから。ま、無事で何よりだがよ」
「お陰さまで」
昼の出来事を思い出し、アルノーは苦笑いした。「ま、妙なもんまで拾ってき
ちまいましたがね」
「妙なもん?」
「──まあ、ちょっと、ありましてね」
アルノーは横を通りすぎ、オーサーの右後ろの卓の上に、酒杯と瓶をコトリと置いた。
オーサーはほとほと困ったように、突っ伏したつむじを眺めている。
右後ろに座ったアルノーを見た。「すまねえが、ちっと頼まれてくれねえか」
アルノーは手酌で酒を注ぐ。「なんです?」
「送ってやって欲しいんだよ。この嬢ちゃんを商都まで。この様子じゃ、てめえからは、意地でも帰らねえだろうしな。軍がまだ詰めていて、中には入れねえかもしれねえが」
アルノーは手酌の手を止めた。
しばし、ためらい、口を開く。「引き受けたいのは山々ですが、あいにく野暮用がありまして」
女将の姿が店奥をよぎり、アルノーを一瞥、くすりと微笑った。いささか意味深な微笑だったが、オーサーに気づいた様子はない。
「そうかい。そんなら仕方がねえな」と、オーサーは酒杯を取りあげる。「なら、後で、連れていくとするか」
「──後で、というと?」
「こっちも、ちょいと野暮用がな。そいつを先に片付けねえことには、二進も三進もいかなくてよ」
アルノーは怪訝に聞き咎めた。「何か、ありましたか」
「アルノー、お前も聞いているだろ。このところ北が騒がしいのは。妙な輩が入り込んで、暴れているようなんだよな」
卓から酒杯を持ちあげて、アルノーは唇に押し当てる。「なんでも、遊民の仕業とか」
「危なかしくってしょうがねえから、どうにかしてくれって泣きつかれてよ。そうまで言われちゃ、ほっとくわけにもいかねえし」
「聞きますね。漁船に拾われた怪我人だの、腕を落とされた盗人だの。例の手配書の連中ですかね」
「気にくわねえな」
オーサーは、くいと酒杯をあおる。
「そういうのは、気にくわねえな俺は。手配書なんざ、あてにはならねえ。だってよ、そういう手配書は、連中の敵が作ったもんだろ。まして、連中にやられているのはジャイルズ側のゴロツキが大半だ。気が荒いってのは確からしいが、片方の言い分ばっかりを、鵜呑みにするのも、どうだかな」
オーサーは手酌で酒を注ぐ。
「どんな悪党にも言い分はある。訳なく他人を、ぶちのめそうなんて輩はいねえよ。大抵は原因がある。重大な根っこの部分がな。だからまずは、そこんところを、じっくり聞こうと思ってよ」
オーサーらしい、とアルノーは思う。
酒杯を口に運びつつ、アルノーは口端で薄く笑う。風当たりの強いオーサーは、偏見と難癖の煩わしさを、嫌というほど知っている。
土壁の古い品書きが、夕陽の赤に染まっていた。
アルノーは酒杯を卓に置く。「兄貴。実は、俺の方の野暮用ってのが──」
「ラルのばかあっ!」
ぎょっ、と二人は動きを止めた。
呆気にとられて、声を見る。卓に突っ伏したエルノアだ。
夕暮れの店に、沈黙が落ちた。
夕焼けに染まった静けさの中、路地を駆け回る音がする。通りのざわめきが遠く聞こえて、動きを止めた店内を、夕風だけが吹き抜ける。
エルノアは目を閉じて、しかめた顔を腕にこすりつけている。
オーサーはしばしそれを見て、「なんだ、寝言かい」と苦笑いした。
「しょうがねえなあ。若い娘が、こんな所で寝ちまって──おう、アルノー。嬢ちゃんを、館に送ってさしあげな。まだ、それほど酔っちゃいねえだろ」
着流しの腕を椅子に置き、それを見ていたアルノーも、微笑って卓に目を戻す。「こいつを片付けたら、行きますよ」
「それなら少し、待っちゃどうだい?」
奥から、女将の声がした。
つまみの載った盆を手にして、女将が奥からぱたぱた出てくる。「今、迎えを呼びにやってるからさ」
オーサーの卓とアルノーの卓に、それぞれつまみの皿を置く。隣の椅子から上着をとって、ルノアの肩にかけてやる。泣き濡れた寝顔に目を細め、栗色の髪をそっと撫でた。「……健気だねえ。いじらしいったら、ありゃしないよ」
開け放った戸口と窓から、涼しい夕風が入ってくる。
年季が入った窓の硝子を、西日が赤く染めあげていた。昼の時化の影響で、町は未だにざわついている。大通りから入ったこの路地まで、不意に怒号が聞こえてくる。医者を呼んでいるらしい。もう日も暮れようというのに、医師たちは駆けずり回っている。
「──ごめんくださいませ」
開け放した戸口の向こうで、女の控えめな声がした。
三人がふと目をやれば、女性が二人立っている。どちらもまだ年若く、どこかおどおどした様子。あの使用人の制服は、ドゴールの館の侍女らしいが。
「あの、当方のお嬢様が、お邪魔していると伺いまして」
店の中を覗いているが、決して中には入ろうとしない。豪邸で働く彼女らは、庶民的な店には不慣れなのだろう。男たちの着流し姿も、気後れしている一因かもしれない。
敷居の外に突っ立った二人に、女将が柔らかく笑顔を向けた。「ああ、夜分に呼びつけて、すみませんねえ」
奥の卓を、目で示す。
虎の穴を覗くがごとく恐々見ていた侍女二人が、そちらに目を向け、瞠目した。
「まあ、まあ、まあ! お嬢様っ!」
なりふり構わず、店に駆けこむ。手前のオーサーの陰になり、姿が見えなかったものらしい。
駆け付けるなり侍女たちは、気遣わしげに顔を覗きこんだ。突っ伏したエルノアの腕を取る。
「さ、お嬢様、参りましょう」
酔いつぶれたエルノアが、顔をしかめて振り払う。
力任せに払われて、酒瓶が床で砕け散った。侍女らは、おろおろするばかり。「お、お嬢様……」
「──あたしばっかり!」
不意に、エルノアの声がした。
動きを止めた侍女らに囲まれ、ぎゅっと握ったエルノアの拳が、空き瓶の転がる卓を叩く。
「いつもいつも、あたしばっかり! なんで、いつも、あたしばっかり──!」
向かいの席のオーサーは、着流しの腕を椅子にもたせて、その様子を眺めている。
アルノーも座った肩越しに、無言でそれを眺めている。
卓に伏したまま、エルノアは続けた。
「いつもいつも、あたしばっかり! あたしばっかり、ラルのこと好きで──!」
ぐすぐす泣いているエルノアに、顔をあげる気配はない。やはり眠っているらしい。
それをかたわらで見ていた女将が、「……可哀相に」と微笑んだ。「よっぽど待っていたんだねえ、迎えに来てくれるのを」
「──ええ。そりゃあ、もう」
侍女たちも苦笑いで、慈しむようにエルノアを見ている。
「毎日、手紙を書いておられました。いえ、手紙は今でも、ですが。ノースカレリアからの帰り道、新しい町に入るごとに。宿のお部屋に入った途端に。ご自分の居場所をあの方に、すぐにお知らせになりたくて。でも、お返事の方はさっぱりで──お忙しい方ですから、仕方のないことですが」
エルノアは真っ赤な顔で突っ伏して、寝顔が眉をひそめている。あの日頃の高慢さは、すっかり成りを潜めている。意識があれば決して言えない、意地っ張りの密かな繰り言。
アルノーが酒盃を置いて、席を立った。
酔い潰れたエルノアの元へと歩く。
「お屋敷まで、お送りしますよ。当分起きねえでしょうから」
侍女二人の手を借りて、エルノアを背中にしょいあげた。
心配そうに見ていた女将の「気をつけて」の声に送られて、アルノーは侍女らと出口へ向かう。
「……ねえ、ラル」
声が小さく呼びかけた。
アルノーが背負ったエルノアの声だ。
その寝言はあいまいで、うまく聞き取れはしなかったが、先の寝言を聞いた者には、その先の言葉は聞かずとも分かった。
『──ねえ、ラル』
ここにいるわ。
わたくしは、ここよ。
ここにいるわ。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》