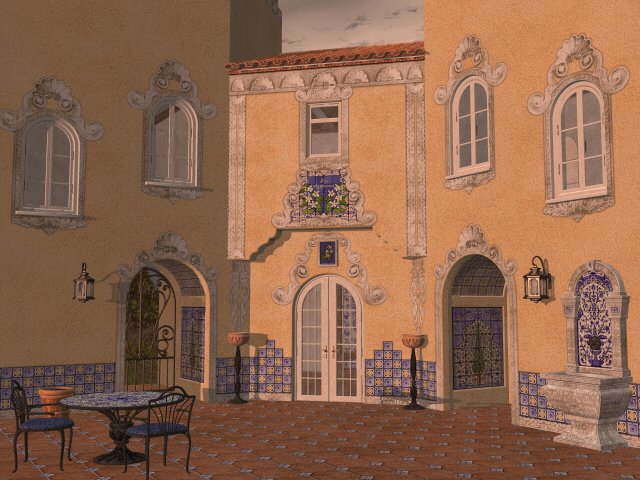
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 9話5
( 前頁 / TOP / 次頁 )
手の平に乗せた小銭を眺めて、エレーンは途方にくれていた。
そこにあるのは財布の中身、今の手持ちの全額だ。一万、一千、三百カレント。
涼しげな噴水の縁石に座り、目抜き通りの中央にある街の象徴の鐘塔をながめた。時刻は既に昼をすぎ、塔の時計の文字盤の針は、もう三時を回ろうとしている。
どこかの店の主だろう、両腕に抱えたミモザに埋もれて、ゆさゆさ歩道を運んでいく。大きなバケツがいたる所に置かれ、中にはどっさりミモザの花が突っ込まれている。祭を知らせる張り紙と看板、道々に様々なオブジェ、そして愉快な顔をした人形たち、黄色い輪のリースが置かれ、通りの両側には準備中の屋台が押し並び、建物と建物の間にはたわわなアーチがかけられる。警邏が街角を巡回する中、皆、飾りつけに余念がない。
街は活気に満ちていた。人足たちがせわしなく行き交い、街中に明るい黄色があふれている。陽の光がこぼれるような、目も覚めるようなレモン色の色彩。
その華やいだ光景に、明日はミモザ祭なのだと気がついた。
ミモザ祭が始まると、街中が明るい太陽の色であふれかえる。国の要たるこの街に、永久の栄華と発展あれ、と祝祭の鐘が打ち鳴らされ、楽隊が組織され、華やかな山車のパレードが街を賑々しく練り歩く。道ばたの観客に向け、山車の上から、菓子の小袋や小さな花束が投げられる。それは「幸せのおすそ分け」
──"あなたの元にも、幸せが訪れますように"
街は浮かれ、いつになく明るい。だが、エレーンは祭を楽しむ気には到底なれず、頬杖をついて嘆息した。
ケネルの部屋を飛び出した後、トラビア行きを実現すべく奔走したが、収穫は無きに等しい。まず、辻馬車の運行状況を街の窓口で確認するも、やはり動いていなかった。辻馬車が使えないなら、ケネルにそう言われたように、馬車を御者ごと貸しきるよりほか手はないが、それには多額の資金がいる。しかも、行く先が戦地というのでは、料金に色をつけない限り、先方も引き受けはしないだろう。だが、手持ちはたったの一万と少し。洒落た宿にでも一泊すれば、それだけで吹っ飛ぶ金額だ。これでは遠く及ばない。
金策に走る必要があった。
だが、手放しで金を貸すような、親身な身内に心辺りがない。ここ商都は故郷だが、両親も祖父も既になく、一人っ子のため縁故もない。親戚は疎遠で付き合いがなく、そもそも彼らは商都に在住していない。行政区画の一角にクレストの公館はあるものの、のこのこ顔を出したりすれば、即座に捕まり、監視下に置かれる。学生時代に仲の良かった友人たちも、既に嫁いで商都にいない。
他に懐があたたかい独身といえば、元同僚のリナたちだが、彼女らの職場・ラトキエ領邸の別棟から逃げ出してきたばかりというのに、その使用人寮のある領邸に再び戻るのはためらわれた。別棟から逃げたことに気づいて、あの黒服が躍起になって捜しているに違いないのだ。今度あの男に見つかれば、どんな目に遭うかわからない。
それで結局、怖気づき、領邸のある行政街区と商業街区を隔てる西門通りを横断する勇気が出せず、建物群の向こうに覗く領邸を囲む木立を眺めて散々うろうろしたあげく、すごすご退散してきたのだった。
頬杖で噴水をながめ、エレーンは小さく嘆息する。啖呵をきって出てきたものの、早々に行き詰まっていた。そして、所持金は依然として
「一万、一千、三百カレント、かあ」
つくづく、嫌というほど思い知った。自分一人ではどれほど無力か。
つまるところ、商都まで辿り着けたのは、ケネルの力添えがあったればこそのことだった。食べるものも寝る場所も移動の手段も何もかも、ケネルが与えてくれていた。自分はのほほんと頼りきりで、ただ運ばれてきたにすぎない。
だが、そのケネルには、トラビアに行く気など全くなかった。「商都まで送り届けるだけ」のつもりでいたから無茶な頼みを聞き入れたのだ。ラトキエの進軍を伝えにきた晩、ノースカレリアの夜更けの部屋で。
自分一人で一体何ができるかといえば──それを考え、うなだれた。
「……一万、一千、三百カレント、かあ」
それが、今の可能性の全てだった。
だが、これで一体どうやって、トラビアまで行こうというのか。大金持ちのおじさんでも身内にいたら良かったのに。ぽん、と気前よく旅費を出してくれるような。
空虚な気分で首を振り、はた、とエレーンは顔をあげた。
「……大金持ちの?」
つぶやき、街並みを振りかえる。
叔父ではないが、心当たりがあった。そう、こんな時こそ、あれほど頼りになる奴もいないではないか!
噴水の縁から立ちあがり、エレーンは街路を駆け出した。
息せき切って通りを駆け抜け、人で賑わう街角を曲がる。
息を切らして走ることしばし、商都の街並みの屋根の上、ひときわ豪奢な三階の館が見えてきた。門に飛びこみ、制止した守衛に取次ぎを頼む。
押し黙った沈黙の中、金色に輝く表札が、おごそかに夏日を浴びていた。そこに刻まれた文字は「ドゴール商会」 この館のエルノア嬢とは浅からぬ交友がある。
ややあって、館の奥から黒服の男がやってきた。白ひげを蓄えた館の執事だ。顔見知りのその彼は、慇懃に礼をして、残念そうに首を振った。
「申し訳ございません。お嬢さまはご不在です」
エレーンは拍子抜けして見返した。
「まだ戻ってないの? レーヌから」
エルノアの方が、先にレーヌを出たはずだ。レーヌで世話になったアルノーから、確かそう聞いていた。
「いえ、お戻りにはなりましたが、今度は王都へお出かけに」
「……お、王都?」
思わぬ行く先に、呆気にとられて執事を見た。
「王都ってあの、王様のいる、あの王都?」
王都は商都の北にある。街路は美しく整備され、壮麗な王宮があると聞いている。だが、詳しいことはわからない。王都は警戒が厳重で、一般人は入れないのだ。それでも、此度の結婚の報告のため国王に謁見する予定もあるにはあったが、ダドリーがディールに捕らわれてしまい、あいにく延期となってしまった。
「エルノアったら、なんでいきなり、そんな所にぃ!」
エレーンはうろたえ、眉をひそめて額を揉んだ。金持ち令嬢の考えることは、まったくもって分からない。いや、商都が閑散としていて退屈だから、王都見物にでも行ったのだろう。どうせ金に物を言わせて、入場許可を取り付けて。それにしたって何も今、そう、よりにもよって今の今、そんな気まぐれを起こさなくてもいいではないか! そんな所へ行かれてしまえば、追いかけることもできはしない。身分こそ「奥方さま」だが、大っぴらにすることなど不可能なのだ。
「もう! 商都が大変な時だっていうのに、一体なにを考えてんのよ!」
執事が気の毒そうにうかがった。
「さあ。私にはわかりかねます」
爪を噛んで苛々歩き、エレーンは顔を振りあげた。
「それで、いつ戻ってくるの?」
真っ白のハンカチを取り出して、執事は額の汗を拭いている。
「相すみません。それについても、私には……」
日程くらいは伝えていけよ! と胸倉つかんでどつきたいところだが、哀れな執事を責めたところで仕方がない。令嬢の突飛な行動は、今に始まった話でもないから、執事としても、さぞや気苦労が絶えないだろう。
出たばかりとのことだから、すぐには戻ってこないと思われた。
だが、そうは言われても立ち去りがたい。金持ちの伝というなら官吏のラルッカも友人だが、彼は他ならぬラトキエ配下で、あのアルベールに近すぎる。ラルッカ当人とは親しくても、今うかつに接近するのは、いかにも無謀な行動だった。そう、やはり、ここは、領邸とはしがらみのないエルノアを頼るべきなのだ。エルノアの生家・ドゴール商会には、いかな領家といえども手は出せない。ここドゴール商会は、商都三大商会の筆頭であり、街の店舗を取り仕切る商都商人会の元締めだ。実勢面では領家と同格ともいえる門閥なのだ。
未練がましくうろうろ歩き、ふと、ひらめいて振り向いた。
「紙と書く物、貸してもらえます?」
通された豪勢な居間で、エレーンは一筆したためた。これまでの経緯を。せっぱ詰まった現状を。取り急ぎ、金を工面して欲しいと。そう、可能な限り早急に。
彼女が帰宅したら渡して欲しい、と執事にくれぐれも言付けて、エレーンは通りを渡って大通りに戻った。
祭で賑わう街に出て、無駄足に肩を落として、にぎやかな街路をとぼとぼ歩く。夕暮れに染まり始めた街並みをながめ、嘆息して腹をさすった。
「……おなか、すいたな」
朝食後にケネルと話し、癇癪を起こして飛び出して以来、何も口に入れていない。財布は持っているものの、所持金はなるべく減らしたくなかった。わずかばかりの小遣いだが、これも今や貴重な資金だ。
街は賑わいで満ちている。明日から始まるミモザ祭に備えて、灯りを煌々とつけた店内では店員が商品を山積みし、飾りつけの丸太を担いで人足たちが通りを行き交う。誰もかれもが忙しそうだ。
エレーンは虚ろな気分で雑踏を歩いた。祭で浮かれるどころではなかった。トラビアに向かうどころか街から出ることさえ覚束ない。リナたちに連絡はとれず、唯一頼りになりそうなエルノアは物見遊山に出かけてしまった。他に親しい友といっても──ふと、街路の石畳から目をあげた。
「……あ、そうだ」
大通りの屋台に、それを見つけて足を向ける。
高く積まれた花束を指さし、小銭を支払い、一束買った。ミモザの花を片手に下げて、荷馬車の行き交う大通りを渡り、建物の間を東に進む。
夕陽に背中を照らされて、狭い路地をしばらく歩くと、やがて、がらんと視界が開けた。敷地の手前に黒い鉄柵。その鉄柵の向こうには、なだらかな丘が広がっている。
未施錠の鉄扉を押し開けて、エレーンは敷地に入りこんだ。丘一面に整然と、白い石板が埋められている。
空を焼くような夕焼けの中、厳かな構内を静かに進んだ。夕陽に照らされた街外れの墓地は、がらんと人けなく閑散としている。敷地の端の、見覚えのある墓標の前で足を止めた。
「ごめんね、アディー。遅くなっちゃって」
ゆっくりと膝を折り、黄色い花束を墓標に置く。
「ほんとは一日早いけど、一緒にお祭のお祝いしようね」
とりあえず、先日助けてもらった礼を言った。あの蒼髪をしりぞけて、自分の身を守ってくれた。もっとも、あれは夢だったかもしれないが。
物言わぬ白い墓石が、ひっそり夕陽を浴びていた。どこかで鳥の耳障りな鳴き声がする。
白い墓標を撫でながら、これまでの出来事を語って聞かせた。
ディールが商都を急襲し、ダドリーが捕虜になったこと。何故かクレストにも使者がきて、開戦してしまったこと。ケネルたちが戦ってくれて、なんとか勝利をおさめたが、たくさんの兵が死んだこと。トラビアに囚われたダドリーに会うべく、はるばる商都までやって来たこと。すぐにもトラビアに行きたいが、「戦場には連れていけない」と言われたこと。
「……戦場」
びくり、とエレーンは体を震わせた。
多くの兵士が刃をまじわす、血に濡れた陰惨な荒野。その戦塵渦まく荒れた大地に、ひとり立ちすくむ自分の姿。「トラビアに行く」ということを、これまで当たり前のように思っていたが、現場に立つのを恐れたことは今までなかった。それは、ケネルが自分のそばにいる、と信じて疑いもしなかったからだ。だが、もしも、それが一人きりなら──いや、今となっては、それこそが現実なのだ。
ここから先、同行者はない。ファレスは常にそばにいたが、彼を頼っても無駄だろう。怪我で動けないという以前に、ファレスは元より、トラビア行きに反対だ。アドルファスも、ザイも、セレスタンも、優しい短髪の首長にしても、首を縦には決して振るまい。彼らはただ命に従い、力を貸してくれたにすぎない。仮に誰かがケネルに無断で付き添ってくれたとしても、彼と二人きりで戦場に立てば、自分の命のみならず、その彼の命をも危険にさらすことになる。
そう、遅まきながら、気がついた。戦場に同行するということは、彼らの命を危険にさらすことに他ならない。何の見返りもないそんな負担を、ケネルが承服するはずもなかった。ケネルは群れの長なのだ。皆の命を預かっている。たとえケネル個人がほだされても、この決定は初めから、個人の意思など介在できない確固たる場所にある。ケネルが群れを放り出し、付き添うことなど、あるはずがない。つまり、
ケネルは、行かない。
厳然たる事実を突きつけられて、エレーンは慄然と硬直した。
一瞬遠のいた物音の向こうで、希望が打ち砕かれる音を聞いた気がした。この期に及んで、まだケネルがなんとかしてくれるのではないか、と心のどこかで期待していたのだ。だが、ケネルが折れて付き添ってくれるなど、あり得ない。むしろ、現状は、もっと悪い。
呆然自失した虚脱の中に、じわりじわりと苦さが広がる。
「……どうして」
愕然と瞠目し、エレーンは唇をかみしめた。どうして、こんなことになるのだろう。
これまでケネルは、身を守る「最強の鎧」だった。それを手に入れたのだと思っていた。なのに、よりにもよって、そのケネルが行く手に立ちはだかろうとは。
今現在の障壁は、他でもない、そのケネルだった。その意に反してトラビア行きを強行するということは、彼と対立することに他ならない。
ケネルの本来の目的は、身柄を診療所に引き渡すこと。今はまだ自由に街を歩けるが、必要とあらば、それなりの措置をとるだろう。目に余る行ないをすれば、行動を強制的に制限し、彼は速やかに監視下に置く。つい先日まで街宿に押し込められていたように。もっとも、そんな手間をかけずとも、出立の手立てを取りあげるだけで、ケネルとしては十分なのだ。事実、彼が手を引いた途端、何もできなくなっている。
もう、誰にも頼れなかった。自分の味方はどこにもいない。ここから先は一人きりだ。
時間は刻々とすぎていく。トラビアは今、どうなっている? アルベールを乗せた馬は、どの辺りまで進んでいる? 既にトラビアに入ったろうか。なのに、頼みの綱のエルノアは、いつ戻るか、わからない。無情な現実に、歯が立たない。
「……ねえ、アディー。あたし、一体どうしたら」
途方に暮れて嘆息し、エレーンは膝にうつぶせた。
顔をゆがめて煙草をくゆらせ、アドルファスは大木の裏から、すがめ見た。
たそがれに染まった西空の下、なだらかな丘は、がらんと広い。まだ、彼女はそこにいた。墓標の前にしゃがんだまま、細いその背は動かない。泉下の客と何事か語らっているようだ。
青芝の上、白い墓標が無数に並ぶ、街外れの墓地だった。ごみごみとした街中とは異なり視界を遮るものがないので、ひっそりとした構内が一望のもとに見渡せる。もっとも門がある入口付近に、巨木が枝を張り出しているので、身を隠す場所には事欠かない。丘の端にあるその墓とは距離が十分あいているので、相手に気取られる気遣いもない。
赤く染まった夏空に、黒い鳥が飛んでいく。夕暮れの墓地に、人けはなかった。短くなった煙草の先を苦い顔で眺めやり、視線を何気なくめぐらせる。ふと、アドルファスは目を止めた。
幹の向こうに誰かいる。敷地の境に立ち並ぶ、三つ先の楡の向こうだ。日も暮れかかった今時分、こんな墓地になんの用だ、と不審な人影に目を凝らし、よく知る顔だと気がついた。
姿を隠したその男は、声を掛けるのをためらっているようだ。無精ひげの頬をゆがめて、困ったもんだとアドルファスは笑う。事情が事情で、出てくる踏ん切りがつかないらしい。彼女の様子が気になって、不覚にも気づいてやれなかったが、いつから、いじましく尾行けていたのか。煙草を捨てて、靴の裏で踏み消した。
「よお、バリー。久しぶりだな」
声をかけると、人影があわてて身じろいだ。
ほんのつかの間ためらったものの、周囲を盗み見、小声で呼びかけ、駆けてくる。
「お、親父っ! 大丈夫なのかよ。しょっ引かれたって、あいつらに聞いて……」
凝視する真摯な顔は、いても立ってもいられぬ様子だ。異民街の本部を訪ねるわけにもいかないから、外出する機会をうかがっていたのか。アドルファスは苦笑い、ばつ悪く視線をめぐらせた。
「おう。見ての通り、ぴんぴんしてるぜ。ケネルの野郎が手ぇ回して、全部ふいにしちまいやがってよ。そんなことより、どうしたバリー。お前、ラデリアじゃねえのかよ。なんでいるんだ、商都なんかに」
先のヴォルガで破れたバリーは、ラデリアの診療所で療養しているはずだった。もっとも、怪我の治療は表向きの理由で、実情は謹慎の命令だ。そのバリーがここにいるのは、つまるところ命令違反だ。やんわりとそれを指摘され、バリーは気まずげに目をそらした。「──悪い、親父。でも、俺は」
「ああ、俺を案じて駆けつけてくれたか。この暑いのにすまなかったな」
「……親父」
変わらぬ相手を確認するように凝視して、バリーは声を詰まらせた。
「本当に、なんともないんだよな? 無理してるってわけじゃないよな?」
不意に顔を伏せ、目をぬぐう。
「無事で、よかった……本当に、よかったっ!」
その頭に手を置いて、アドルファスは腕白坊主にするように、ごつい平手で、ぐりぐりなでた。
「悪かった。悪かったよ。要らぬ心配かけちまってよ。こうしてせっかく来てくれたんだ、飲みにでも行きてえところだが、今はあいにく手が離せなくてな。こんな所ですまねえが、お前もちょっと付き合えや」
アドルファスは大儀そうに膝を折り、張り出した木の根に腰を下ろした。まあ、座れや、と顎で促す。うつむいた目元を腕でぬぐって、バリーも隣に腰を下ろした。
アドルファスは懐を片手で探り、夕暮れの丘に目を戻した。今しがたと変わることなく、彼女はひっそり、うずくまっている。夕陽に染まった墓標の上には、街にあふれる黄色い花束。
「誰の墓だ? あの墓は」
バリーがいぶかしげに問いかけた。紙箱をゆすって一本取り出し、アドルファスはそれを無造作にくわえる。
「さあてな。親御さんのじゃねえのかな。なんでもガキの時分によ、二親とも死んだって話だから」
「二親とも?」
「面倒みてくれたじいさんも、少し前に死んだらしいぜ。今じゃ天涯孤独の身の上だ」
バリーは面くらった顔で見返して、居心地悪げに目をそむけた。「──そんなふうには見えないがな」
「何か、背負っちまってるんだよな、あれは」
西空に紫煙を吐き、アドルファスは思い起こすように目をすがめた。
「だから、あんなに気張っている。誰彼構わず必死で愛想をふりまいている。うなされて、しきりに詫びてたぜ。親父さんを寝言で呼んで。そうとう悔やんでいることがあるらしいな。何があったか知らねえが」
黒い蓬髪を片手で掻いて、紫煙を吐きつつ、ゆるゆる続けた。
「だが、まあ、こう言っちゃなんだがよ、案外よくある話だよな。人ってのは大なり小なり、そんなものを背負っているもんだ」
やんわりと仄めかされ、バリーが頬をこわばらせて目をそらした。横を向いた面持ちは、どこか意固地でかたくななだ。
高木の枝で、黒い鳥が羽繕いをしていた。
ガアガア鳴いて、枝を飛び立つ。一面に広がる白い墓標が、ひっそり夕陽を浴びていた。浮かれた街とは大きく異なる、うら寂しい夕暮れの墓地。訪ねる者も、今はない。
「──なあ、バリーよ」
夕暮れの丘をながめたままで、アドルファスは紫煙を吐いた。
「あの子に力を貸してやっちゃくんねえかなあ。こんな俺に死んだ父ちゃん重ね合わせて、泣き寝入りなんかするんだよ。年端もいかねえガキみてえに、シャツのすそ握っちまって離さねえんだよ。俺の釈放かけ合いに行って、それで領邸でとっ捕まって、それでも俺の顔見て泣くんだよ。無事でよかったって、ぐっちゃぐちゃな顔してよ。あの子は俺の、娘みてえなもんなんだよ」
「──目を覚ませよ、親父。あれは街の女だぞ!」
バリーはたまりかねたように舌打ちした。
「町の奴なんぞ信用ならねえ。奴らは平気で他人を裏切る。てめえの村さえ良かったら、よそがどうなろうが、どうでもいいんだ。飢えようが死のうが、せせら笑って見ているだけだ! なんだかんだ言ったって、どうせ旨い汁吸おうって魂胆なんだよ。出し抜いてやろうって肚なんだよ。連中の言葉なんか真に受けたら──!」
指先で紫煙をくゆらせ、アドルファスは聞いている。憎々しげな罵倒が途切れるのを待ち、ふう、と長く紫煙を吐いた。
「よほど帰りたかったんだな、お前はよ」
バリーの頬が硬直した。たじろいだように目をそらし、歯ぎしりするように言葉を押し出す。
「……もう、いいんだ、そのことは。俺の自業自得なんだから。いや、全部俺のせいだ。だって俺は──あの時、俺は──」
苛立ちまぎれにむしった草を、足元の地面に叩きつける。
「もういい、バリー。済んだことだ」
うなだれた頭に手を置いて、アドルファスはぐりぐり手荒くなでる。
「ガキなら誰でも、一度は手を出す悪戯だ。ただちょっとばかり間が悪かった、それだけだ。避けようなんか、なかったさ。お前はまだ、年端もいかねえガキだったんだ」
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》