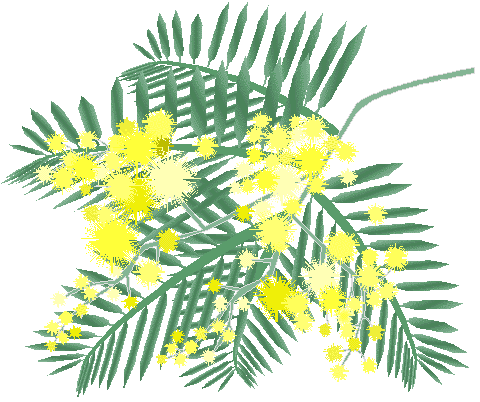
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 9話9
( 前頁 / TOP / 次頁 )
通りをよぎったゆるやかな風に、まばゆい黄色が一斉になびく。
こぼれるような丸い黄色が、夏の日ざしを浴びていた。腕いっぱいにミモザを抱いた、白い帽子に前掛けを締めた、売り子の婦人の晴れやかな笑顔。
時刻は、まだ正午前。
ミモザの山車のパレードは、開国の鐘が打ち鳴らされる二時を過ぎてから始まるため、歩道はまだ、押し合いへし合いの混雑でごった返したりはしていない。だが、人出は例年よりもあるようだった。ディールからのこたびの奇襲で、商都市民の頭上には、未曾有の災難が降りかかった。彼らにとって、開国祝賀のミモザ祭は、不安と鬱屈を吹き飛ばす格好の気晴らしなのだろう。
「──え、ちょっと! なんでドアが開かないわけ?」
店の扉をガタガタ揺すって、エレーンは唖然とノブを見た。
扉のガラスから中を覗けば、店内はまだ薄暗い。つまり、店長が来ていないのだ。ミモザ祭の当日というのに、朝寝坊でもしたのだろうか。もしや、前祝いで飲みすぎて二日酔いで寝てるとか?
「──もう。しょうがないわねえ、店長ってば」
額をつかんで、エレーンはげんなり嘆息した。
「ミモザ祭で稼がなくて、一体いつ稼ぐってのよ。こんな又とない書き入れ時に寝てる場合じゃないっつの」
ならば、開店するまで待つしかない。だが、いつ現れるとも知れぬ店長を待って、この暑い店表にじぃっとひたすら突っ立っているのも、気が遠くなるほど手持ち無沙汰だ。
エレーンはやれやれと首を振り、店の扉に背を向けた。
いくらなんでも、昼までには店もあくだろう。店長もそれまでには起きるはず。そして、寝ぼけまなこで時計を見、青くなって支度して、すっ飛んでくるに違いない。だったら、開店するまで時間をつぶすか。
夏日の当たる歩道に降り、通りに視線をめぐらせた。この歩道を左に行けば、北街区と南街区の境界線「北門通り」がすぐそこだ。一方、向かいの建物の間を抜ければ「目抜き通り」に行き当たる。ちなみに、北門通りの突き当たりには、言わずと知れた北門が、目抜き通りを南下した先には、商都カレリアの正門がある。
特に迷うこともなく、エレーンは通りを横断し、目抜き通りに足を向けた。北門通りは数軒先の近さにあるが、通りの向かいは行政地区と商館街で、大して目ぼしいものはない。実務第一の行政地区など歩いたところで仕方がないし、商館街は高価な品を扱う大商館が軒を連ねる界隈なので、祭とは無縁の通常営業。気軽に店先を冷やかすだけなら、露店ひしめく目抜き通りの方が楽しいし、こちらの通りは山車が通る道筋だから、通りに面した店々もさぞ華やいでいるだろう。
煉瓦の建物の間を抜けて、目抜き通りの歩道に出た。
がやがやざわざわ、街はざわめきに満ちている。通りに面するどの店も、ミモザで飾りつけた軒先に店の品々を山積みにし、気の早い見物客がその店先を冷やかして、陽光あふれる昼の歩道をぶらついている。派手な仮面の紳士もどき。妖精のようなふわふわのドレスでくすくす笑う娘たち。着ぐるみのフードを頭にかぶって走りまわる子供たち。
そのいずれの口元も、ゆったりほころび、寛いでいる。虹色のかつらの赤い丸鼻の道化師が、先のふくれた巨大なブーツで歩行者の間を徘徊し、人波からおどけて顔を出しては、通行人にちょっかいを出して、祭に彩りを添えている。ざわめきにくすぶる、ときめきと熱狂。向かいの窓にさし渡した色鮮やかな旗々が、ゆるい夏風にひるがえる。
昼までの時間をつぶすべく、エレーンは街中をぶらついた。
異民街の建物を出た頃には、十時を既に回っていた。そして、ほどよく込みあう雑踏の中、「ぴんくのリボン」にやってきた。 同僚が溜まり場にしている、先日行った喫茶店だ。
リナの制服を返すから、とファレスには言ってきたけれど、制服の受け渡しに使う場所は、どの店でも良いわけではなかった。そう、あの店でなければならない理由があるのだ。
昨夜、アドルファスに往なされて本部に戻り、自室の枕をひとり抱えて悶々としていたその時に、とあるひらめきが頭をよぎった。
昨日一日奔走したが、結局、金策はままならなかった。頼れるような親類はいないし、友人たちとも連絡がとれない。金持ち令嬢のエルノアも肝心な時に限って不在。無論、馬車を借りる程度の金ならば、クレストの公館に行けば事足りる。だが、のこのこ顔など見せられない。ならば、街の金貸しを利用するより手はないが、それをするには肝心の身元が明かせない──そこまで考えて行きづまり、はた、とそのことに気がついた。
それなら、つまり、身元の保証ができればいいのだ。確かな身元を、先方が知っていさえすれば、それでいい。貸し金を確実に回収できる、領家の夫人であることを。
条件を満たし、容易に接触できる相手が、一人だけ、いた。
「ぴんくのリボン」の店長だ。彼はラトキエ領邸に勤務していた頃からの知り合いだから、信用の点では申し分ない。店長ならば、親身になって助けてくれる。商都で店を経営しているくらいだから、まとまった金も用意できる。
ようやく、道が開けた気がした。
これで、やっと動き出せる。店長に馬車を手配してもらい、数日分の旅費を借りよう。そして、馬車の用意ができるまで、あの店に居させてもらおう。お代は後日の精算で。無論、費用はクレストのツケだ。それに、店に滞在していれば、その内リナがくるかも知れない。
目の前にそびえる高い壁が、がらがら崩れ落ちたようだった。青空がひろがる向こうには、トラビアへの道がひらけている。旅費のことも、移動手段も、もう心配しなくていい。あとはトラビアに向かうだけ。ダドリーのいるトラビアに──。
つ──と頬に涙がこぼれて、エレーンはあわてて頬をぬぐった。
泣くには早い。まだ何も始まっていない。まだ何も終わっていない。早くトラビアに赴いて、ダドリーにそれを知らせないと。
──ラトキエは味方ではない、と。
ダドリーはアルベールに気を許している。よもや、そのアルベールが密かに復讐を企てていようとは夢にも思わないに違いない。アルベールが踏みこめば、ダドリーは無警戒に受け入れてしまう。なんの躊躇もすることなく──。こみあげた感傷を振り切って、エレーンは足早に街角を曲がる。
何かが顔にぶつかった。
「──ごっ、ごめんなさい! あたし、ちょっと考え事してて」
向かいから曲がってきた者と、鉢合わせしてしまったらしい。泣いた顔をあわててぬぐい、向かいの相手に顔をあげる。
「え?」
エレーンはまたたいて動きを止めた。
夏の日ざしをさえぎって、長身の男が立っていた。あの彼と一目でわかる、特徴的な風貌だ。深緑色のランニングに着こんだ革ジャン、そして何より、あの禿頭と黒眼鏡。
「……セレスタン」
出会い頭にぶつかったのは、今朝方別れたばかりのセレスタンだった。彼は無表情に見おろして、周囲に視線をめぐらせている。
「一人、すか?」
「……う、うん。まあ」
エレーンはきまり悪く目をそらした。泣いた顔を見られただろうか。
照れ笑いで、あたふた尋ねる。
「こ、こんな所で会うなんて、奇遇ねセレスタン」
そう、奇遇だ。知り合いとばったり出会うほど、商都の街は狭くない。待ち合わせでもしていない限り、そうあるようなことではない。
セレスタンが小首をかしげて見おろした。
「ちょっと、つきあってもらえませんかね」
「──え? あ、でも、あの」
エレーンはしどもどためらった。
彼の様子が普段と違った。いつもであれば、こちらと顔を合わせた途端、どきまぎ目をそらしたりするのに、今日は全く動じていない。恐いくらいに落ち着き払っている。そう、普段と違う異質な要素を、一言で喩えるなら、獰猛さ、だろうか。
ためらう内にも、セレスタンが一歩踏み出した。
エレーンは気圧されて一歩引く。口元は確かに笑っているが、黒い眼鏡をかけているので、表情が今ひとつわからない。脇をすり抜けるようにして、そろりと足を踏み出した。「あ、でも、あたし、ちょっと予定が──」
視界を戻した目と鼻の先を、革ジャンの腕が素早くふさいだ。
「ちょっと、そこらでお茶しません?」
セレスタンが壁に手を突いて、覆い被さるようにして覗きこんでいた。
相手の思わぬ行動に、エレーンは目を白黒させる。「ふ、二人っきりで?」
「二人きりで」
セレスタンは躊躇なく言い放つ。有無を言わせぬ強い口調だ。
エレーンはうろたえ、上目使いでうかがった。「ね、ねえ、セレスタン? それって、もしかして、つまり、あの──」
言葉に窮して言い淀むが、セレスタンは応えない。相づちさえも打ってくれず、ただ無言で見おろしている。そわそわ周囲を見まわして、エレーンは思い切って顔をあげた。
「デートってこと?」
セレスタンが面くらったように身じろいだ。
困惑したように目をそらし、顔を片手でぬぐっている。やがて、口元に苦笑いを浮かべ、長身をかがめて、うかがった。
「──俺とじゃ、嫌すか?」
気遣うように問いかける。幼子に尋ねるような優しい口調で。
「あっ、ううん! そんなことないけどっ!」
あわてて首を横に振り、エレーンは内心戸惑った。ふっと感じが変わった気がした。強ばっていた空気がゆるみ、ふわり、とほどけたというような。
眼鏡の向こうのまなざしが優しく見つめているのがわかった。ほんのつい今しがたまで、ひりつくような不穏さを全身に漂わせていたのに。彼を傷つけないよう、エレーンはあたふた言い募る。
「あ、だって、セレスタンっていい人だもの。あたし、セレスタンのこと大好きだもの。お茶するくらい問題ないし!」
セレスタンは苦笑いした。背を起こして、行こう、と促す。
馬車が行き交う目抜き通りを、彼と連れだち、横断した。急かして転んだりせぬように、彼は歩調を合わせてくれる。あの長い足でなら、もっと早く渡れるのだろうに。
こんなにも優しいこの彼を、なぜ恐いなどと思ったのだろう。そう、彼の人柄は、この目で見て知っていたはずだ。なのに恐そうに見えてしまう原因は、たぶん、彼がかけている黒眼鏡のせいだ。エレーンはしげしげ顔を見た。
「ねえ、セレスタン。黒い眼鏡とか、やめればいいのに。なんか恐く見えちゃうし。なんで、いっつも、かけてるの?」
ぶらぶらと横を行く、高い位置にある横顔が、ほんのわずか天を仰いだ。
「……お天道様の光がね、俺にはまぶしすぎるんですよ」
ぱちくりエレーンは顔を見た。
「ふうん、セレスタンって、目、弱いんだね」
セレスタンは横顔で苦笑いした。
色とりどりのパラソルが、歩道の両側を埋めていた。
その日陰の屋台では、氷に浸かった飲み物の瓶やら、バナナやらイカ焼きやら揚げ芋やらが所せましと並んでいる。軒から吊るした鮮やかな布が、夏日を透かしてひるがえり、縁台に並ぶ装飾品の金属が、夏の日ざしをきらきら弾く。
さしかかった街角で足を止め、エレーンは困惑して連れを仰いだ。
「ね、ねえ、セレスタン。お茶するんだったら、あっちの通りのお店にしない? この道、なんか薄暗いし、この先行っても、お墓しかないし」
そう、街を東に進んでも、行き当たるのは墓地しかない。
セレスタンは裏道に向かっていた。狭い通路の両側には、うらぶれた酒場が軒を連ね、連れこみ宿の看板が建物の壁を占めている。
思わぬいかがわしげな界隈に、エレーンは視線を泳がせる。「それに、なんか、ちょっと恐い感じもするし」
「大丈夫。怖くないすよ」
路地を眺める横顔で、セレスタンは淡々と応えた。
「俺も一緒にいきますから」
え? とエレーンは戸惑った。何か奇妙な言い方だ。これから、お茶しに行こうというのだ。一緒に行くに決まっている。
沈黙が降りていることに気がついて、エレーンはあわてて言葉を継いだ。
「そ、そうだよね。セレスタンが一緒なら平気だよね。セレスタン、頼り甲斐あるもん!」
「……じゃ、行きましょうか」
セレスタンは困ったように苦笑して、おもむろに片手をさし出した。指の長い、大きな手。
そこにいたのは、以前からよく知るあの彼だった。森で嫌がらせした三バカを叱り飛ばしてかばってくれた、刃をかざした首長の前に立ちふさがり、眠りこんだ少年を身をていして守ってくれた。今朝も、廊下で慰めてくれた。あの優しさは本物だった。
さし出された手をとって、エレーンは笑みを振り向けた。
「うん!」
禿頭の首をわずかかしげて、セレスタンはまぶしそうな顔をした。
華やいだ祭の道ばたで、黄色がふわふわゆれていた。
祭の街をつつみこむ、どこかそわついた雑踏と、街に満ちた静かな興奮。だが、その晴れやかな雑踏から、どこか二人だけ浮いている気がする。
隣の横顔を盗み見て、エレーンは密かに戸惑った。
彼にいざなわれて歩く内、不思議な感覚にとらわれた。雲の上を往くような、地に足がつかないような、儚くも切ない浮遊感。こうしてふたり手をつなぎ、どこまでも歩いていくような。そう、どこまでも、どこまでも、二人きりで──。
果てなく一面にひろがった、ふわふわ黄色いお花畑を、手をつないで歩いていた。
光に埋もれた道なき道を。仲のよい子供らのように。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》