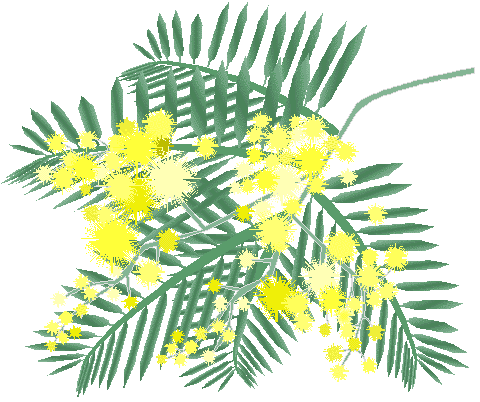
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 9話11
( 前頁 / TOP / 次頁 )
昼前の路地に、人けはなかった。
湿気の多い、むっとするような熱気の中、開店前の飲食店が、そっけない静寂をまとっている。裏口に出されたごみ箱を漁って、野良猫が余所者に顔をあげる。
夏日をさえぎる建物の日陰を、手を引かれて歩いていた。ゆったりと包みこむ、大きくて、乾いた手。
「あ、そうだ!」
するり、と手を引き抜いて、エレーンはあわただしく踵を返した。
「セレスタン、ちょっと、そこで待ってて!」
大通りまで駆け戻り、街角を右に曲がって、祭で賑わう歩道に出る。ばたばた忙しなく用を済ませて、今来た道を駆け戻り、先の街角にさしかかる。
どん、と顔からぶつかった。
向かいから曲がってきた者がいたらしいのだ。ぶつけた顔を涙目でさすり、エレーンは受け止めたくれた相手に顔をあげる。
「……どうしたんです?」
呆気にとられて見おろしていたのは、他ならぬセレスタンだった。ためらいがちに尋ねられ、その腕をすがって、体を起こす。
「──あ、すぐ戻るつもりだったんだけど」
こちらに付き合って、引き返してくれたらしい。ささっと後ろに隠した片手を、エレーンは彼に突きあげる。
「はい、これ! セレスタンに!」
とっさにそれを受けとってしまい、セレスタンは面くらった顔で見返した。「──なんすか、これは」
手の中にあるのは一房のミモザだった。街中にあふれる黄色い花だ。えへへ、とエレーンは得意げに笑う。
「幸せのおすそ分け! あたしからの! ほら、今日、ミモザ祭でしょ!」
あっ、でも、あたし、あんまり好調でもないけどねー……と己が現状を思い出し、言ってしまってから、たじろぎ笑う。そう、新婚の夫に失踪されたり、森で賊に追っかけられたり、なんだかんだとどつかれたり、領邸で捕まって足蹴にされたり──こうしてつらつら思い出してみると、本当にろくな目にあってない。
手にしたミモザを、セレスタンは唖然と見おろした。言葉を探すようにその唇を薄く開け、間を保つように唇を湿らせ、顔をゆがめて目を戻す。
「姫さん……」
ぐい、と体が引きあげられた。
左の肩に、禿頭の重み。爪先が地面から浮きあがっている。
セレスタンが正面から覆い被さり、体がすっぽり、はまっていた。両腕で抱きすくめられている。
大きな体を両手でかかえ、過剰な反応にエレーンは怯んだ。どうしていいのかわからずに、革ジャンの背中をおろおろさする。
「そ、そんなに気に入ってもらえたんだ? よかったわ。そんなに感激してもらえて」
軽口で返してきそうなものだが、セレスタンは強く抱きしめたまま応えない。
「……セレスタン?」
押さえつけられた首をどうにかよじって、エレーンは困惑して横顔を見た。
肩に、禿頭がうつぶせていた。口元がきつく閉じられている。奥歯をかみしめているようだ。何かに耐えているように。
「な、泣いてるの?」
エレーンは驚いて瞠目した。懐の中に囚われたまま、彼の顔をあたふた覗く。
「ど、どして? あたし、なんか悪いことした? ごめん! この花、嫌いだった?」
彼の大きな手の平が、ゆっくり後ろ頭をなでていた。道ばたで抱擁された気恥ずかしさと、彼を泣かした罪悪感とが入り混じり、どうも、ざわざわと居心地悪い。そわそわ視線をめぐらせて、エレーンは遠慮がちに身じろいだ。
「……あ、あの〜、そろそろ放してくれても、いいんだけど……ほら、ここ、いちおう公道だし、人目とかも、あったりするし……」
恐る恐る言ってみるが、聞こえているのかいないのか、セレスタンは動かない。
(こ、困ったな……)
上背のある大きな体に埋もれつつ、エレーンはせめて、のしかかる広い背をさする。「……泣かないで。ねっ、お願いだから、セレスタン」
「あれえ? どこに行ったんだァ?」
ぴくり、とその背がわなないた。
街角から聞こえたダミ声に、反応したようだった。気配が硬く引き締まり、硬直したような彼の腕から、ゆっくり力が抜けていく。
ふっ、と禿頭が肩から離れた。
そのまま押しやるようにしてかばい立ち、セレスタンは肩越しに振りかえる。
視界をふさぐ革ジャンの後ろから、エレーンはそっと盗み見た。向こうの路地の街角から、男が顔を覗かせている。その太い首元に、シャラリと揺れる金鎖──。
「……確か、こっちで見たんだがなあ?」
不思議そうにごちつつ現れたのは、口の周りに丸くひげを生やした中年の男だった。普段の彼とは服装が違うが、その顔に見覚えがある。
あの晩、ヴォルガ開催を知らせにきた、酔っ払いのロジェだった。笑うと、いやに愛嬌がある、なんか陽気なおっちゃんだ。今日は、かわいいクマさん柄の黄色い綿シャツと、渋い緑色のだぼだぼズボンをはいている。常に気の抜けない傭兵という仕事柄か、彼らの仲間は筋肉質で痩せた者が大半だが、そうした中でもあのロジェは、あの太鼓腹の安産体型で抜群の安定感を誇っている。ふと、こちらを振り向いた。
「あー、いたいたァ!」
クマの笑顔が腹いっぱいに横伸びした、でっぱった腹を左右に揺らし、どたどた、そっくり返って駆けてくる。
「ぅおーい! セレスタンんんーっ!」
笑顔で手前に到着するなり、ロジェは口を尖らせた。
「もー。お前、どこ行ってんの。ずっと、俺のことほっぽリ出して。朝から捜していたんだぞ。でも、まあ、そっちはいいや。ちょっと、そこらにフケようぜ。こう暑くちゃ、やってらんねえよ。今日は祭で人も多いし──」
夏の暑さに辟易したように汗をぬぐい、目抜き通りを顎でさす。
セレスタンは応えない。それを気にした風もなく、ぶちぶち一人で喋っていたロジェが、「……ん?」と口をつぐんで、またたいた。
意外にも軽い身ごなしで、ひょい、と肉厚の背をかがめ、セレスタンの後ろを覗きこむ。
「ありゃ、姫さん」
顔を見るなり、ぱちくり、まなこをまたたいた。思わぬものを見つけた、といった顔。
「……ど、どうも」
エレーンは決まり悪く、お愛想笑いした。狭い道ばたでくっ付いていたのは、単なる成り行きだったのだが、隠れていたようで怪しすぎる。ちなみに、ヴォルガがあったあの晩も、ロジェはご機嫌に酔っ払いながらも、焦れたような大声で、セレスタンの名前を呼ばわっていた。つまり、いつも、セレスタンにべったりなのか? てか、この二人
(……どーゆー関係?)
エレーンはじっとりロジェを見る。
ふーむ、とロジェは顎をなで、セレスタンと連れを交互に見た。ふと、人けない路地を一瞥する。
ぽん、と分厚い手の平を、合点したように拳で叩いた。「あー。そーゆー……」
両目を三日月形にして、思わせぶりに、にやりと笑う。なにやら揶揄するような顔?
奇妙な反応をいぶかしみ、エレーンも、なによ? と振り向いた。ロジェのちら見の先を辿れば、ねっとりまたたく、ピンクと紫の宿屋の看板──?
「──ちっ!?」
これ以上ないというほど瞠目し、エレーンはわたわた、前傾姿勢で手を振った。
「ちっ、ちっ、違うわよっ? 違うわよっ? あ、あ、あたし達は、別に、そんなっ!」
ぼっとのぼせて、一気に赤面。
「そそそそんなふしだらなこととか、しようとしてたわけじゃなくって──ね、ねえ? セレスタン? そうよねっ? セレスタンんっ!」
黒眼鏡を直しつつ、セレスタンが軽く片手をあげた。同意のつもりであるらしい。
てか、そこははっきり否定をせんかい!
じれったい思いで密かに彼に合図を送るが、彼はロジェに目を向けてしまった。隣ではらはら拳を握るが、黒眼鏡の横顔は、もうこちらを見向きもしない。
「あっ、じゃ、じゃあねっ! セレスタンっ!」
居たたまれなさが頂点に達し、エレーンはわたわた、引きつり笑いで後ずさった。
「あたし、ちょっと、これから用事がっ! あ、だったら、あたしはこれでってことでっ!」
訊かれもせぬのにあたふた言い立て、くるり、と二人に背を向けた。
目抜き通りを向かいに渡り、脱兎のごとくに退散する。踵を返した肩越しに、すまなそうに頭を掻くロジェの顔がつかの間よぎった。
「悪りィ。邪魔しちまった?」
「……いいさ」
セレスタンが応えたようだった。
ほんの短い返答が、どんな表情を帯びていたのか、とっさのことで追いそびれた。ロジェに返したその声が、笑っていたのか、憮然としていたのか、意気消沈していたか。こっ恥ずかしさが先に立ち、強引に逃げてしまったけれど──。
彼らとは逆方向に通りの人波に紛れつつ、エレーンは肩越しに振り向いた。勝手に予定を反故にして、セレスタンがどんな顔をしているのか気になった。
だが、既に踵を返した後で、ぶらぶらと道を戻る後ろ頭しか、もう見えない。
そわそわ爪先立って目で追いながら、逆方向へとエレーンは歩いた。頭一つ分、人波から突き出た禿頭が、祭の雑踏に呑まれていく。
「にしても、セレスタンってば。なんで、ちゃんと否定してくんないかなあ……」
歩きながら、ぶちぶちぼやく。お陰で、ロジェが誤解した。そうだ。きっと誤解したに違いない。
「はい。あんたはこっち来て」
「──へ?」
声がした、と思ったら、ぐい、と手首を引っぱられた。
左側の街角だ。突如、路地に引っぱりこまれて、あわてて顔を振りあげれば、たるそうに壁にもたれた男が、腕だけこちらに伸ばしている。
二十代半ばの若い男だ。赤いランニングに迷彩パンツ。ぼさぼさの頭髪をうなじで一つにくくっている。伸ばしっぱなしの前髪から見おろす、どことなく、ふてぶてしい顔つき。
あれ? とエレーンは見直した。どうも、どこかで見た顔だ。(……でも、誰だっけ?)とつらつら考え、はた、と突如思い当たる。
「だ、だらだら男?」
なんでいんの? と見返した相手は、セレスタンの仲間の一人だった。いつもたむろしている大勢の一人。顔こそよく見かけるが、特別親しいわけでもない。
まるでまるきり気のない素振りで、男がぶらりと、もたれた壁から背を起こした。
「ま、クリームソーダでも」
「……く、くりーむそーだァ?」
エレーンは呆気にとられて復唱した。誘い文句がクリームソーダって、お前はどこのやんちゃ坊主だ。
ぐい、と男が引っぱった。
「さっ。そこの健全な喫茶店で」
「──え? あ、ちょっと! あたし、行くなんて一言もっ!」
だらだら男は問答無用で、手近な扉を押し開ける。
そして、くるりと振り向いて、ぐいぐい背中を押しこんだ。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》