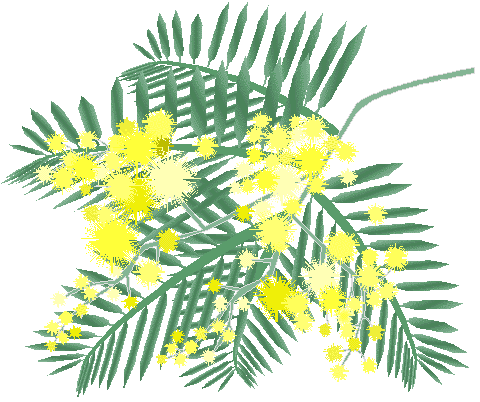
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 9話12
( 前頁 / TOP / 次頁 )
窓の日除けが半分おりて、店内はひんやり、薄暗い。
強烈な夏日がさえぎられ、慣れない視界で一瞥すれば、つややかな板床の店内は、右手に飴色のカウンター、中央に十人がけの丸テーブル、左側には、窓に面したボックス席が三つ。
まだ昼前だからか、客はまばらだ。円卓の向こうの端に、額を寄せ合うカップルが一組、新聞を広げた中年男がカウンターの奥にいる。ポニーテールの店員が、丸テーブルを拭いていた。きれいな若い店員だ。
ふっ、と何かが、ぼさぼさ頭の肩から香った。服についた火薬の匂い?
つかんだその手は放さぬままに、男はぶらぶら左手に進む。窓側のボックス席まで歩いたところで、つかんだ手首をようやく放した。
やれやれというように、ソファーの背もたれに身を投げる。
「あー、なんでも好きなもの頼んでいいから」
ぶちぶち言いつつ引っぱられてきたエレーンは、はた、と男を見返した。
「……なんでも、好きなもの?」
男の向かいにそそくさ座り、卓のメニューをぱたんと開く。
真夏の街中を歩きまわって、喉がからからだったのだ。財布の中身を減らさぬようにと、じぃっと我慢をしてきたが、おごりというなら、話は別だ。日陰の卓が、腕にひんやり。
「あー。言っとくけど」
どれにしようか、じっくり検討していたエレーンは「なに」と邪険に目をあげた。なんでもいいと言ったくせに、食いもの係はだめとか言う気か?
ズボンの尻ポケットを探りつつ、ぶっきらぼうに向かいは言った。
「俺の名前、だらだら男じゃないから」
「──へ?」
面倒そうに続けたところによると、彼の名前は「ジョエル」ということだった。いつもセレスタン達と一緒にいるが、あまり関わってこないので、名前までは覚えてなかった。そう、彼と交した会話といえば、確かヴォルガのあの晩に「何か食うか」と尋ねてくれた、あの時くらいのものだろう。もっとも、彼の方は、五秒で興味が失せたようだが。
というのに、なぜに突如、街角で待ち伏せ?
ひろげたメニューの上端から、ちら、とエレーンは盗み見る。
「ねー。これは何? ナンパなわけ?」
「親切」
「なに言ってんの。ずいぶん強引なナンパじゃない」
「だから言ってんでしょ、親切だって。ひとの親切は素直に受けとくもんでしょが」
ソファーの背もたれに腕をかけ、ジョエルはぐるりと、かったるそうに首をまわす。
「あ、おねーさん。ここ、クリームソーダひとつね。──あんたなに」
一連の動作のついでに、円卓を拭いていた女性の店員を呼び止める。
急に決定を促され、エレーンもあわてて彼女を見た。
「あ、あたしも同じの、お願いしますっ!」
向かいのせっかち男を、むう、と見る。
(……なに、この男はぁ)
優しくない。
てか、どうせなら、ナポリタンとかにすればよかった。
(しくじった……)と内心ぶちぶち悔やみつつ、エレーンは天板に両肘をつく。膨れっ面を両手ではさんで、じぃっ、と向かいを観察した。
ぼさぼさ頭のこの男、物言いがどことなくザイに似ている。一緒に行動していると、口調が似てくるものなのだろうか。もっとも、口数は同じように多くても、つかみどころのないザイとは違い、ジョエルはどことなく冷めている。ザイの口ぶりには計算しているような節があるが、ジョエルの方は思ったことがそのまま口をついて出てくる感じだ。よくいえば率直。悪くいえば無神経。
ジョエルがたるそうに煙草をくわえた。点火しがてら、ぞんざいに尋ねる。
「どっか行くの」
ぎくり、と頬を強ばらせ、エレーンはわたわた引きつり笑った。
「べっ、別にどこにも行かないわよ。なんで、いきなり、そんなこと訊くわけ?」
「それ」と、ジョエルは顎の先で床をさす。
「なによ?」とエレーンも足元を見た。すると、磨きあげられた板床に、ずっと持ち歩いていた袋が二つ。
どきりと高鳴った動揺を押さえ、平静を装い、顔をあげた。「──あー、これは友達の服。借りてたから返そうと思って」
「あー。あの時の特攻服ね」
「とっ──」
あんぐりエレーンは口をあけた。確かに、領邸に突入した際、この制服を着ていたが、そんな形容、初めて聞いた。
むう、と袋を引ったくり、それを抱きしめ、そっぽを向いた。
「失礼ね。この制服、人気あんのよー? 着てくと半額になるお店とか、あるんだから」
「へー。なら、こっちの袋のパンツはなに」
ぎょっと、エレーンは見返した。いつの間にかジョエルが背をかがめ、天板の下のもう一つの袋に、たるそうに腕を伸ばしている。ぴら、とその指がつまみあげているのは──
「な、なに出してんのよっ!」
エレーンはあたふた、イチゴのパンツをひったくる。
「もー! 油断も隙もあったもんじゃないんだからっ!」
不届き男をぎろりと睨み、パンツをタオルでぐるぐる巻いて、袋にぎゅうぎゅう押しこめる。ふと、そこに気がついた。
(……そういえば、セレスタンは訊かなかったな)
袋を二つもさげていたのに、彼は一度も尋ねなかった。どこへ行く、とは一言も。
「あんた、家出すんの」
頭上からの掠れ声に、ぎくり、とエレーンは凍りつく。
たじろぎつつも笑みを貼りつけ、かがんだ背をぎくしゃく起こした。「……な、なんで言うかなあ、いきなり、その、家出とか」
「あるっしょ、パンツが、袋の中に」
ひょい、とジョエルは袋をさす。ぬう、倒置法で来たか。
「これは、その〜……だって、せっかく里帰りしたんだし、だから、友だちの所にでも泊まりに行こうかなあって」
「へー。友だちんとこに。てっきりハゲと駆け落ちかと思った」
「見てたの!?」
卓を叩いて、エレーンは思わず乗り出した。てか、どこから見てた! どのあたりから! セレスタンと連れ立っていたところを目撃されたあのロジェには、要らぬ誤解をされている。ならば、ロジェだけではなかったと──!?
「お待たせしました」
胸ぐらつかみそうな前傾姿勢で、うっ、とエレーンは凍りついた。
ぎくしゃく顔を傾ければ、そこには盆を持った店員が。
意味不明なお愛想笑いで、自分の席にそそくさ戻る。
グラスを二つ、それぞれの卓の前に置き、店員は「ごゆっくり」と踵を返した。
彼女が定位置に戻るまで、ちんまり大人しく着席した。グラスをストローでカラカラ回し、緑色のクリームソーダを、ずずっとすする。変なところでぶった切られて、どうも話を切り出しにくい。
どさり、とジョエルは椅子の背もたれに寄りかかり、ぶっきらぼうに目を向けた。
「あんた、年いくつ。もう二十歳は超えてんの?」
「……はあ? 突然なに。てか、今さらなに」
答えにくいところをさらっと訊かれて、エレーンは憮然と口の先を尖らせる。「てか、ふつう訊くう? 女の人に年齢を。大体ねー。ひとにものを尋ねるなら、まずは自分からっていうのが礼儀でし(ょ)──」
「二十五」
ふっ、とジョエルが紫煙を吐いた。
あっさり答えを放り投げられ、うっ、とエレーンは反論に詰まる。
「で、あんたはいくつ。十八、九?」
畳みかけられ、えーっと……と、そそくさ目をそらす。
小首を傾げて見ていたジョエルが、眉をひそめて口を開いた。
「まさか、俺より年上とか?──まじかよ。なら、もしかして三十超えてる?」
「しっ、失礼ねっ! あたしはまだ二十六っ!」
はっ、とエレーンは口を押さえた。とっさに怒りの拳を握り、白状してしまったが、今のはもしや、引っかけか?
「へー、二十六」
案の定、ジョエルはしげしげ見、ぼさぼさ頭を片手で掻く。
「カレリア人ってのはわっかんね。こんなガキっぽいのが二十六」
己の不覚に額をつかんで沈没していたエレーンは、がばっと顔を振りあげた。
「わ、悪かったわね。どうせ、あたしは童顔よ」
「つか」とジョエルは顎を出す。
「領主が嫁を選ぶなら、相手はふつう十代じゃね?」
「──うっ、うっさいわね。余計なお世話よっ!」
「でも、領家の婚姻ってのは、ガキの量産が目的っしょ。そんな年増でよかったわけ?」
「あたしは家畜じゃないっつの! ぽんぽこ産んどきゃ、それでいいってもんでもないでしょ! 重ね重ね失礼な男ねっ!」
「ともあれ、あんたは二十六」
確認するように言い置くと、ジョエルは片肘ついて乗り出した。
「あんたさ。そんなにホイホイついてっちゃ駄目でしょ。人目のない部屋に連れこまれて、首でも締められたら、どうすんの」
クリームソーダを吹きそうになり、エレーンはわたわた顔をあげる。「セレスタンと駆け落ち」疑惑に戻ったらしい。卓を叩いて乗り出した。
「なっ、なに言ってんの! セレスタンがそんなこと、するわけないでしょっ!」
向かいの席の無表情と、ぬう、と顔をつき合わせる。
「──そりゃそーだ」
意外にも、ジョエルはあっさり引いた。
自分のグラスを片手でとりあげ、大分溶けたクリームごと、クリームソーダを、ぐい、と飲み干す。
「奴に、できるわけがねえ」
とん、とグラスを卓に戻して、ソファーの背もたれに腕を置く。ふい、とその目を窓の外に向けた。
前髪の下の、彼の目が、通りの人波を眺めている。むっつりとした横顔に静かな拒絶を感じとり、エレーンも、むぅ、と口をつぐんだ。急に手持ち無沙汰になってしまい、グラスをストローでカラカラ回す。
店のざわめきが、耳に戻った。
円卓の二人組が席を立ち、楽しげに笑い合いながら、店長のいる帳場に向かう。それが外に出る前に、次の客が来店し、どやどや店に入ってくる。若い男の五人連れ。急にごった返した入口で、黒服の痩せた店長が、客に愛想よく笑みを向ける。「──いらっしゃいませ」
明るい夏日の窓の外を、人々がのんびり行き交っていた。ジョエルはわずか眉をひそめ、無言でそれをながめている。
「ごめんあそばせっ。ちょっと、あたし、お化粧直しに」
ほほ、と笑って、エレーンはそそくさ席を立った。向かい合わせで座っているのに、黙られてしまうと手もち無沙汰だ。きっと奴もケネルみたいに、ずっとなんにも喋らなくても、特別苦痛を感じない人種だ。
窓枠の横木に肘をつき、街の通りをながめていたジョエルが、ふと気づいたように振り向いた。
「──あー。いってらっしゃい、おねーさん。ま、いいか、頃合いだし」
あ? とエレーンは剣呑にすごむ。一体なんの頃合いよっ!
化粧室で適当に時間をつぶし、にぎやかになった店内を歩いて、元の窓際の席へと戻る。
エレーンは唖然と口をあけた。
「……いない?」
窓際の座席は空っぽだった。あいたグラスが、卓にふたつ。
あわてて店内を見まわすが、あの姿はどこにもない。もしや会計をしているのかと、店長がいる帳場を見るが、そこにも奴の姿はない。
ざわり、ざわり、と嫌な寒気にさいなまれ、エレーンは恐る恐る卓を見た。
なめらかな木板の卓に、先と変わらぬ白い伝票。
唖然とエレーンは立ち尽くした。奴が店に引っ張ってきた時、確かに「おごる」とは言わなかったが……。でも、それなら、好きなもの頼め、って当たり前じゃん。てか、
──まんまと、あいつにたかられた!?
「あんのクリームソーダ男ぉっ!」
未会計の伝票を握りしめ、ぎりぎり拳を震わせる。あとはよろしくおねーさん、と、どうでもよさげに言い捨てる奴の横顔が頭に浮かんだ。地団駄踏むが、今となっては後の祭だ。
「んもおおぉっ! あたしは今、貧乏なのにっ!」
しぶしぶ財布の口をあけ、やむなく舌打ちで会計を済ませる。
あのお調子者はどこ行った! と鼻息荒く店を出たが、影も形もありはしない。
エレーンは憤然と歩道を歩いた。もっとも、この心許ない貧乏も、どうせ店長がくるまでの辛抱だ。
ちょっと多めに借りとこう……と密かにセコく算段しながら「ぴんくのリボン」に足を向けた。そろそろ店も開いたろう。
建物の間の日陰を歩いて、先の店先に立ち戻る。その扉を見た途端、エレーンは唖然と絶句した。
「はああ? 休みってなに!」
シンと閉じた店の扉に、先にはなかった、お詫びの張り紙。
「……あー。お隣、しばらく休むってさ」
靴屋を営む隣の店主が、店に戻り際、顎をしゃくった。彼が言うには、店長の妻が急に産気づいたらしいとのこと。
頭の中が真っ白になり、エレーンは愕然と立ち尽くした。汗もしたたる真夏というのに、木枯らしピープー吹きすさぶ気分。予てより「ミモザ祭の時くらいは一緒にいてよね」と笑顔で厳命されていた事情もあって、いそいそ帰郷したらしい。それにしたって、年に一度のミモザ祭だ。店舗にとっては大事な大事な書き入れ時。そんな時に休むか普通!?
「……もう、やだ」
袋が二つ、どさり、どさり、と足元に落ちた。
体中から力が抜けて、店の前でしゃがみこむ。膝をかかえ、途方に暮れてうつ伏せた。
店長にとっては待望の子供だ。我が子の顔など見てしまったら、離れがたくなってしまって、しばらく戻れないに違いない。
せっかく名案がひらめいたのに、頼みの綱も木っ端微塵だ。でも、もう時間がない。店長が商都に帰ってくるのを、悠長に待つような時間はない。
「──仕方ない。行くか」
重たい腰を、エレーンはあげた。こうなったら、行けるところまで行くしかない。一か八か街道に出て、西に向かって、とりあえず歩く。事情を話せば、荷馬車に乗せてくれる人が現れるかもしれない。謝礼はそんなに払えないけれど、なんとか頼みこんで乗せてもらおう。財布の中身はさっきの茶店で更に減り、今現在の所持金は、たったの一万三百カレント──。
「──もう! あのクリームソーダ男ぉ!」
両手の袋をぶんぶん振って、エレーンはぷりぷり歩道を歩く。あいつのせいで、乏しい旅費が更に乏しくなってしまった。トラビアに向かう街道に出るべく、ぶちぶちごちつつ、北門通りに足を向ける。
北門から外に出ると、国境に続く「トラビア街道」が伸びている。
片や、正門から外に出ると、二つの街道が伸びている。一つはロマリア学園都市を経由して漁港レーヌへと続く「レーヌ街道」 もう一つは、北方への玄関口ルクイーゼを経由して件のノースカレリアの街まで続く国内最長の「カレリア街道」
栄えているのは圧倒的に、二つの街道を持つ正門の方で、これから向かう北門は、精彩を欠く印象がある。このトラビア街道の主な役割は、国境と商都を行き来する荷馬車の出入り、そして、この街道の利用者は、街道沿線の住人を除けば、トラビア近郊の鉱夫たちか、もしくは西の軍人くらいだ。他のふたつの街道に比べ、沿道の出店も格段に少ない。終点トラビアは観光地ではないため、観光客が見込めないからだ。更には、北門を出てすぐ森林がひろがる不遇な地形も、ぱっとしない一因かも知れない。
北門通りの馬車道に出ると、昼の時鐘が聞こえてきた。時計塔のある目抜き通りを、エレーンは溜息でながめやる。
「……もう、お昼か」
ひもじくなってきた腹を、思わずさする。やっぱ、ナポリタンとかにしとけばよかった。
「おい。飯の時間だぞ」
ぎょっとエレーンは飛びあがった。
よく知る声が真後ろでしたが、今のはもしや幻聴だろうか。そうだ、奴がこんな所にいるはずがない。そろり、と肩越しに振りかえる。
「……ふぁれす?」
「たく! どこにもいねえと思えばアホタレが! まあだ、こんな所で油を売っていやがって。また飯に遅れるだろうが!」
昼の歩道の真ん中に、ファレスがふんぞり返って立っていた。
包帯の腹に、直に革ジャンを羽織っている。お昼の誘いにきたらしい。いや、そんな悠長なことを言っている場合ではない。
絶句で凝視していたエレーンは、瞠目して指さした。
「なんで、いんのよっ!? あんたがここに! 外出ていいの!?──てか、お腹から血ぃっ!?」
たり、と真っ赤な液体が、腹の包帯ににじみ出ている。
あ? とファレスが己の腹を見おろした。
「屁でもねえよ、こんなもん」
だが、そう言った矢先に、よろ、と肩にもたれかかる。
「……大……丈夫だっ」
頭を両手でかかえこまれ、杖代わりにされたエレーンは、むう……と微妙な顔で立ち尽くした。
(……やせ我慢しちゃって)
顔が引きつっているではないか。ぜえぜえ言ってて鼻息荒いし。
ふんばっているのが辛いらしい。ファレスは忌々しげに舌打ちし、街路樹の木陰に腰を下ろす。「──おう。アレやってくれ、"手当て"って奴」
「ここで!?」
ぎょっとエレーンは見まわした。この天下の往来でか?
だが、座りこんだファレスは、手首をつかんで放さない。睨みあげる額に、したたる汗。
のっぴきならない痛みらしい。
「……もー。なんで外に出てくるわけ? まだ全然無理なくせに」
エレーンはやれやれと嘆息し、ファレスの隣に腰を下ろした。「一人できたの? こんな所まで」
「──たりめえだ。俺はガキじゃねえ」
「ねえ、誰か呼んだ方が」
「……呼ぶな! 大丈夫だっつってんだろ!」
噛みつくファレスを片手でかかえ、肩にうつ伏せた顔を覗いて、包帯の腹にそっと手をおく。
「大丈夫? すんごく痛い?──あ、痛いの痛いのとんでけー!」
即席で、おまじないもしてあげる。
ファレスは、じっとうつ伏せている。肩を滑り落ちた薄茶の髪が、歯を食いしばったその横顔を覆っている。弱音こそ吐かないが、いつものように毒づきもしない。かすかに聞こえる、押さえた荒い息づかい──。
筋肉が硬直し、痛みをこらえているのがわかった。額が汗でびっしょりだ。密かに困惑しながらも、エレーンはゆっくり背中をさする。
目の前の歩道を、人々の足が行きすぎた。
目抜き通りの位置とは異なり祭の主会場から外れているので、北門通りの人波はまばらだ。普段なら、街路樹の根元になど座っていれば、じろじろ通行人に見られるだろうが、今日は祭で馬鹿騒ぎするような者もいるから、その程度のことでは目立たない。
強ばっていた身体から、やがて、こらえていた力が抜けた。
はー……と長く息を吐き、ファレスがぐったり、もたれかかる。
「──おっ、重い重い重いっ!」
あえなく、べちゃ、と押し潰されて、エレーンはあわてて、じたばたあがいた。
だが、奴は細身の割に案外重くて、押しのけようにも動けない。
悪戦苦闘していると、むっくり、重しが身を起こした。
「じゃ、行くか」
ファレスは首をこきこき回して、何事もなかったように立ちあがる。
「も、もう元気になったの!?」
木の根から肩を起こしつつ、エレーンは唖然と顔を仰いだ。五分やそこら、うずくまっていただけで?
ともあれ、服の土ぼこりをあたふた払い、街路樹から立ちあがる。その肩を、ファレスが引っつかんだ。
「とっとと戻って、昼飯食うぞ!」
あの異民街の"本部"に戻る気らしい。
エレーンはあわてて足をふんばる。「──あ、あたしは戻らないから」
「ほれ。とっとと帰るぞ、あんぽんたん!」
「ままま待ってっ! あたしは──て、ひとの話、聞きなさいよっ!」
たまりかねて、顔を振りあげた。
「ファレス、あたし、トラビアに行く!」
「──あァ?」とファレスが、舌打ちして足を止めた。
振りかえって、顔を見て、くるり、と前方に目を戻す。
「さあ、飯だ飯だ!」
「無視すんなっ!?」
「──馬鹿か、てめえは」
眉をひそめた横顔が、苦々しげに舌打ちした。
「あんな危ねえ戦場なんぞに、お前をやれるわけねえだろうが」
はっ、とエレーンは顔をあげた。
「──それって、もしかして」
お目々キラキラで、手を組み、見あげる。
「一緒に行ってくれるの?」
「言葉は正確に聞きとれや」
誰がそんなことを言ったあほんだら! とファレスはまなじりつりあげる。ぞんざいに腕を引っつかんだ。
「馬鹿が! かついででも連れて帰るからなっ!」
「はああ!? 馬鹿はどっちよ! 今のあんたにできるわけないでしょー!」
だが、ファレスは力づくで引っ立てる。ずりずり道を引きずられ、ふんぬ、とエレーンは足をふんばる。
「なにしてんのっ! 力入れたら、又おなか痛くなるわよ? あんた自分の状態わかってんの? たった今までへばってたくせに──て、血ぃっ! お腹から血ぃっ! 無茶しないでよっ!」
ぎょっとエレーンは瞠目し、わたわた腹に指をさす。
「──あっちにいけ! 浮浪児が!」
憎々しげな罵声と共に、水をぶちまける音がした。
ふと、エレーンは目を戻す。楽しい祭に何事だろう。声がしたのは進行方向。
怪訝にそちらに目を凝らすと、歩道が黒く濡れている場所があった。北門よりの、歩道の先だ。
どこかの店主らしき中年の男が、今使ったと思しきバケツを片手に、歩道の片隅を睨んでいた。濡れ鼠になった小さな人影が、そこで、うずくまっている。ひどく痩せた幼い子供だった。その身形から、男の子らしい。
ぺったり額に張りついた髪から、ぼとぼと水をしたたらせ、子供が店主に顔をあげる。その顔に見覚えがあった。
「……ケイン?」
エレーンは驚いて息を飲んだ。なぜ、あの子が商都などにいるのだろう。いや、数日前にも、彼を正門付近で見かけたはずだ。あれは見違いなどではなかったのだ。
あわてて、そちらに駆け出しかけて、はっと足を踏みとどめる。
ケインは賊を殺害し、ケネルたちに追われている。そして、街には、ケネルの仲間がうろついている。騒ぎを起こして人だかりができれば、それを呼び集めてしまいかねない。ケインが彼らと出くわしたら、大変なことになってしまう。──ん? まてよ?
はたと気づいて、エレーンは顔を引きつらせた。とうに、抜きさしならない事態では……?
ごくり、と唾を飲みこんで、真後ろの気配に意識を凝らす。
案の定それは、おどろおどろしく渦まいて、緊張をはらんで淀んでいる。奴も、ケインを見つけたのだ。
そう、今、後ろに、ファレスがいる。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》