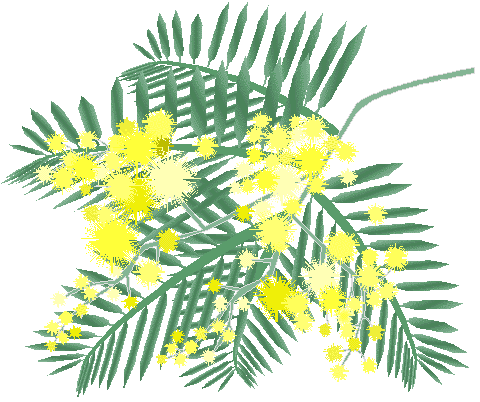
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 9話14
( 前頁 / TOP / 次頁 )
強い海風が吹いていた。
叩きつけるような白いしぶきが黒い岩場に砕け散り、海流がうねり、渦を巻く。
赤い髪の相棒は、強風吹きすさぶ突端にたたずみ、はるか崖下をながめている。その薄い唇の端は、うっすら笑みの形につりあがっている。
吹きすさぶ潮風に銀灰色の長髪をもてあそばれながら、クロイツも鳶色の目を向けた。
切り立った崖下では、海面がバシャバシャ激しく水しぶきをあげていた。叩きあがった周囲の波が、鮮やかな緑に輝いている。
青灰色の背びれがひるがえった。盛大な水しぶきと共に、鋭い歯がびっしり生えた三角の口がせりあがる。
青く輝く海面に、ゆっくり赤が漂った。水面が盛りあがるほどの争奪戦の渦中で、黒い翼が見え隠れしている。とはいえ、鋭いあぎとに食い散らかされているそれは、鴉のそれの大きさではない。
いびつにねじ曲がった白い五指。胴体につながっていたであろう人の腕。そこには衣服らしき布切れがぼろぼろになって張りついている。
獲物が食い散らかされるその様を、赤髪は隠しに手を突っこみ、どこか面白そうに眺めている。
「──殺す必要があったのか?」
クロイツは苦々しげに眉をひそめ、たまりかねて振り向いた。「というより、手駒を始末して不都合はないのか」
赤褐色の双眸は、跳ねまわる海面をながめている。その横顔で、赤髪は応えた。
「留守番も満足にできねえ奴は、使い物になんねーよ。大体クロイツ、俺がそんなものをあてにしたことが一度としてあった?」
「ないな」
クロイツは首を横に振った。「お前は、自分しか信じない」
「だろ? 連中の代えは、いくらでも利くしよ。それに」
赤髪は頓着なく肩をすくめた。
「言うこときかねえ奴は要らねえんだよな」
深手を負って逃げこんできた手兵を、赤髪はあっさり斬り捨てた。そして、哀れな亡骸を、内海に無造作に投げ捨てた。壊れた玩具に興味はないという顔で。
赤髪は身を乗り出して、崖下の海面を覗きこむ。「で、なんで見逃したの? クロイツ」
「何のことだ、見逃した、とは」
「とぼけんなよ。あのバカを刺した女男だ」
赤髪は海面を顎でさす。「お前が情をかけるとは思えねーけどな」
潮風になぶられて、銀髪が高く舞いあがる。
風がごうごう打ち鳴って、衣服の裾がばたついた。無視を決めこむクロイツに、赤髪は肩をすくめる。
「いーけど? 別に。鳥人を見たと騒いだところで、どうせ誰も信じやしねえし、ジェリオと会うことは二度とない」
内海には、獰猛な肉食魚が回遊している。血の匂いを嗅ぎつけたが最後、たちまち餌に群がって、影も形も失くなってしまう。扱いかねる異形の姿を跡形もなく葬り去るには、内海はいかにも都合が良かった。
「それに、ああいう単細胞がいると面白いからな」
荒れる海面を眺めたままで、クロイツは嘆息した。「どうせ、邪魔になれば殺すくせに」
「そりゃ、もちろん」
ぶらりと赤髪が、肩を揺らして振り向いた。
「ま、邪魔にならないこと祈ってる。──さて、トラビアでも見物に行くか。雑用も済んだことだしな」
気楽に歩き出した後に続いて、クロイツも旅装の長い裾をひるがえす。
死神たちは、大陸の西へと足を向けた。
行く手をふさぐ"それ"を見て、ザイは左に進路をそらした。
ざっ、と"それ"も向きを変える。
右に、ザイは進路をそらした。
ざっ、と"それ"も向きを変える。やむなくザイは、左に足を踏み出して──
「鎌風のザイさんっ!」
ザイはたじろいで見まわした。
「……これは、皆さん、おそろいで」
見つけた任務をとりあげられて、北門通りから戻ってすぐのことだった。女声の大合唱と共に、ザザッ──とそれが展開し、たちまち囲いこまれてしまったのだ。
大きなまなこで仰いでいたのは、ふっくらした顔立ちの、子供のように小柄な女たちだった。十人以上いるだろうか、そのいずれもが紺の制服に身をつつんでいる。白い襟のそろいの制服、商都で知らぬ者はないラトキエ領邸のメイドたちだ。
まなこを輝かせて、一人が乗り出す。
「"鎌風のザイ"さんですよね! そうでしょう?」
「ねー、でもさー、なんで鎌風?」
ザイが返事をするより早く、隣のメイドが首をかしげた。
「むしろ、そもそもなに鎌風って」
「あ、あれじゃない? ほらほら!」
あげつらわれて居たたまれないザイ当人を置き去りに、きゃいきゃい勝手に盛り上がり始める。
「寒くなると、手足が切れたりすることあるじゃない。あれのことよ!」
「えっと──つまりなに。あかぎれってこと?」
一同が哀れむように振り向いた。
「……どっから仕入れたんスか、そのネタは」
ザイはうなだれ、額をつかんだ。「つか、ちょっと訊いていいスかね」
「「「 なんなりと 」」」
一同、食い入るように注視する。ザイは頭を掻いて見渡した。
「なんで俺は囲まれてんスかね」
真ん中にいたトンボ眼鏡が、ずい、と前に進み出た。
「話はリナから聞きました。エレーンのこと、あなたが助けてくださったとか。わたしたち感謝してるんです!」
口を真一文字に引き結び、トンボ眼鏡は真面目な顔。肩下のそれを眺め下ろして、ザイは決まり悪げに頭を掻いた。「そいつは語弊がありますよ。なにも俺一人で乗りこんだわけでもねえし──」
「でも、あなたが助けてくださったんでしょう?」
「……ええ。それはまあ、そうですが」
トンボ眼鏡はいぶかしげに見返して、自説を頑として譲らない。どうやら、彼女らの間では、ザイは彼女を与太者からとり戻した英雄、との位置づけらしい。
制服の胸に手を当てて、トンボ眼鏡が真摯に見つめた。
「それで、わたしたち、何かお礼ができないものかと。みんなで相談いたしまして」
「ああ、いいスよ、そんなことは。別にあんた方の為にしたことでもねえん(だし)──」
「それで、お昼休みにお世話させていただこうかと思いまして!」
「……お世話?」
思わぬ申し出に、ザイは面食らって見渡した。「はい」とトンボ眼鏡は大きくうなずく。
「わたしたちメイドの取り柄といえば、それくらいのものですから」
取り囲んだメイドたちが、一斉ににっこり顔を見た。
「「「なんなりとお申し付けください、ご主人様?」」」
「せっかくですが、間に合ってますんで」
ザイはそっけなく踵を返した。
そのまま街路を南下して、煉瓦の街角をいくつか過ぎる。今日は大掛かりな祭ということで、街をぶらつく観光客の姿が目に付いた。親子連れ、老婦人、若い娘らの騒がしい集団、所在なさげに街角でたむろす男たち、普段着の者、仮装した者、思い思いの装いで、談笑しながら行き交っている。
だが、何故かその大半が、目を向けた途端に語らいを取り止め、あるいは、すれ違いざま呆気にとられて突っ立ったあげく、笑って互いをつつき合う。
微妙な空気の立ちこめる中、ザイは黙々と歩き続けた。だが、二区画ほど歩いたところで、ついに肩を落として足を止め、げんなり後ろを振り向いた。
「……なんで、くっついてくるんです?」
周囲の奇妙な反応で薄々気づいてはいたのだが、確認すれば案の定、先のメイドの行列がしずしず後をついてきている。
目を引く制服の大群で。
そう、白襟紺服のラトキエ領邸メイド服。この有名な制服を、商都で知らぬ者はない。
ぱっ、とメイドたちは顔をあげ、にっこり営業用の笑みを向けた。
「「「なんなりとお申し付けください、ご主人様?」」」
「あいにく"ご主人様"はやってねえんで」
まあ、と一同、眉をひそめて後ずさる。隣の仲間を振り向いて、つれないザイをちら見する。
「──おっかしいわねえ」
「殿方はたいてい喜ぶのにね、"ご主人様"ごっこ」
小首をかしげて「ね?」とうなずきあうメイドたち。
「絶対うけると思ったのに。やり方が何かまずいとか?」
「照れてるんじゃない?」「押しが弱いとか?」「変わった性向の持ち主なんじゃない?」
ぽん、と一人が手を打った。
「"ご主人様"じゃなくて"鎌風のザイ"って呼んで欲しいんじゃない?」
な〜るほど、とどよめいて、一斉にザイを振りかえる。
「「「なんなりとお申し付けください、鎌風のザイさん?」」」
……なんか語呂が悪くない? と頬に手を当て無念の舌打ち。
「なにすっとぼけてんだか。頭よわいんスか?」
やれやれと語尾でごち、ザイは困って頭を掻いた。「その名で呼ぶのは、よしてもらえませんかね」
「どうしてですか?」
一同、傷ついたように目をみはる。
「いや、あんた方に呼ばれると、力が抜けるといいますか、むずがゆいといいますか、こっ恥ずかしいといいますか」
「でも、鎌風のザイっていうんじゃ──?」
「別にそれ、名字じゃねえんで。ひと組にして呼ぶ必要は全くねえんで。そんなことより、油売ってていいんスか? 皆さん、領邸のメイドさんでしょう? お仕事の方はどうしたんです?」
「あら。今は昼休みですの」
リーダーらしきトンボ眼鏡が得意満面、説明する。それによると、今日は年に一度のミモザ祭ゆえ特別に外出可、なのだそうだ。
「ちなみに、旦那様も若旦那様もご不在で、時間の方は融通が利くので、ご心配には及びませんわ」
「じゃ、急ぎますんで俺はこれで」
そそくさ、ザイは背を向けた。「はい、ごめんください」と街角に向けて足を踏み出す。
ぐい、と襟首つかまれた。
けほ……とむせて首を押さえて見下ろせば、むんず、とつかんでいたのはトンボ眼鏡。わらわら領邸メイドが取り囲み、極上の笑みを振りあげた。
「なんなりとお申し付けください、ご主人様?」
「お食事になさいますか、ご主人様?」
「肩でもお揉みしますか、ご主人様?」
「それともお休みになりますか、ご主人様?」
「どこで?」
思わず突っ込む鎌風のザイ。
「つか、どうせ揉んでくれるなら、どっちかってえと別の場所の方が──」
「いやあだあっ! ご主人様っ!」
照れ笑いしたトンボ眼鏡に、道の端までぶっとばされる。
思わぬところで、けちょんけちょんにされつつも、ザイは壁にすがって立ちあがった。
はー……と顔をつかんで、うなだれる。これは、ちょっとやそっとでは解放してもらえそうもない。溜息で視線をめぐらせた。「つまり、俺の言うこと、なんでも聞いてくれるんスよね?」
「はい。それはもう」
トンボ眼鏡がほくほくと、揉み手せんばかりに満面の笑み。「なんなりとお申し付けくださいませ、ご主人様」
「なら、離れて歩いてくれません?」
もしくは、そのまま解散してくれてもいい。
「却下ですわ、ご主人様」
トンボ眼鏡は即答した。有無を言わさぬ底なしの笑顔で。ひょい、とザイは顎を出す。
「一応聞きますが、あんた方、完璧に遊んでますよね?」
「滅相もございませんわ、ご主人さ──」
油断した一同の隙を突き、素早く身をひるがえす。
「あ! 逃げたっ!」
「逃げたわよっ!」
はたと気づいた彼女らが、まなじり決して地を蹴った。
スカートの裾をひるがえし、両手を振って追いかける。ザイは追跡を引き離し、そぞろ歩きの街路を駆け抜け、離れた街角に滑りこんだ。
壁から顔を出してうかがえば、二人一組になったメイド服が、抜かりなく視線を投げながら、ざっざっざっ──と足音も高く捜索している。ぴたりとそろった規則正しい走行は、運動選手の日々の鍛錬を見るかのようだ。
ザイは舌打ちで頭を引っ込めた。留意すべき賓客が北門通りにいる以上、遠く離れてしまうのはまずい。
考えようによっては、領邸のこわもて警備員より、よほど手強い相手だった。どれほど警備員が手強かろうが、ぶん殴れば、けりはつく。だが、相手がか弱いメイドとなれば、手荒な真似はご法度だ。迂闊に手を出して万が一にもすっ転ばそうものなら、まなじり決した仲間に囲まれ、四方八方から足蹴にされて私刑にあうこと必定である。となれば、この不自由なおかつ理不尽な状況から脱するには、なんとかやり過ごして逃げきるよりほか方法はない。
「──さてと。メイドさんたちは行っちまいましたかね」
建物の壁に背をつけて、そそそ──とザイは壁伝いに忍び歩く。街角から様子をうかがって、覗いた頭を引っこめた。
二人一組のメイド服が、躍起になって巡回していた。血走らせた目をきょろきょろしている。今しがた通過したメイドたち──いや、似ているが違う。さっきとはどことなく顔だちが違う。
辛抱強く街角にひそみ、気配が行き過ぎるのをザイは待つ。物音が消えたのを確認し、そろりと慎重に顔を出した。
「……すいませんねえ。あんたらが俺を捕まえようなんざ、百年ほど早いスよ」
苦笑いして、利き足を踏みこむ。
ふと、ザイは動きを止めた。いや、前に出そうとした足が、何かに引っかかって止まったのだ。嫌な予感にさいなまれ、そろり、とザイは視線を下げる。
途端、がっくり肩を落とした。
「……眼鏡のセンター、スか」
トンボ眼鏡のメイド服が、両手で足にしがみついていた。にっかと笑ってザイを仰ぐ。
「つ〜かまえたっ! もう逃がしませんよ〜!」
「そんないじわる言っちゃいけませんよあんた」
すっく、とトンボ眼鏡は立ちあがり、呼子を出して口にくわえた。
ピリピリピリ──と街に響きわたる緊急招集。
にわかに靴音がばらばら聞こえ、前後左右の街角から、メイド服が結集した。
低い体勢でおのおの身構え、じりじり包囲網を狭めてくる。感心するほど隙がない。
「「「ご主人様っ!」」」
あっという間に包囲され、ザイは両手を上げて降参した。
のどかに晴れた天を仰ぎ、肩を落としてうなだれる。「……あんた方、ちっこいわりにタフっスね」
「はい! 体力勝負の仕事ですからっ!」
破顔一笑、メイド服は即答した。まなこはらんらん、腕まくり。あのたくましい奥方様の育成土壌が分かった気がする。
その彼女がいるのは北門通り。付近に留まる必要がある以上、彼女らから逃げ果せるのは至難の業というものだった。なにせ、商都は彼女らの庭。この街の隅々、細い路地の裏の裏まで知り尽くしているに違いない。そして、更に悪いことには、敵はお祭り気分で悪乗りしている。集団の権勢を笠に着て。ザイはゆるゆる首を振.る。
「「「 どうなさいました? ご主人様? 」」」
「……もう、ここらで勘弁してもらえませんかねえ。俺の負けでいいいスから。こう見えて、まじで結構いそがしいんスよ」
「「「 では、お手伝いしますわ! ご主人様? 」」」
うなだれた顔を横向けて、ザイは力なく一同を見た。つまりはウォードを捕獲すると?
格闘に長けるあのウォードが、非力な婦女子に捕まるはずもないのだが、挑みかかって捕まえたなら、それはそれで、かなり怖い。
嘆息して顔をあげた。
「なら、何して遊びましょうかね」
腹を決めて腕を組み、一同に視線をめぐらせる。肩下にひしめく大きなまなこが、指示を待って一斉に見つめる。
「「「はい! なんなりと!」」」
「こんな美女に囲まれるなんてのは、めったにない機会ですし。だが、そうかといって、単に大勢で飯食いに行くってのも、ありきたりでつまんねえし」
ひらめいた素振りで顔をあげ、ひょい、と一同を振り向いた。
「なら、鬼ごっこしましょう」
ぱちくりメイド服はまたたいた。狐につままれたような顔。
「で、捕まった人は罰として、鬼の言うこときくってことで。じゃあ、初めは鬼、俺がなります。てことで、俺の希望は、そうスねえ──捕まった人には、さしあたり」
ぴん、とザイは人さし指を立てた。
「祭の余興で裸踊りしてもらうってことで」
はあ!? と一同、口をあけた。
引きつり顔で、ずさっと引く。ザイはにんまり腕まくり。
「十数えたら追っかけますんで。あ、言っときますが、足には自信があるんでナメないように。じゃ、いきますよ? いーちっ!」
「え──えええ!?」
両手を握って一同おろおろ、困惑顔で目配せしている。
「おや。逃げなくていいんスか? にーい!」
ぎょっと顔を強ばらせ、わたわた一斉に走り出す。諸手をあげて、きゃあきゃあ転びそうに駆けていく。
「……さーん?」
誰もいなくなった街路に立ち、ザイは隠しに手を入れた。
逆方向へと、ぶらぶら踏み出す。
「冗談じゃねえ。あんなもん引き連れて歩けるか」
悪目立ちしてしょうがねえ、と一人ごち、ふと、そぞろ歩きの足を止めた。
いぶかしげに振りかえる。街角にひとり、メイド服が立っていた。だが、元気いっぱいのメイド集団とは様子が違う。用でもあるのか、おどおど見ている。その顔に見覚えがあると気がついた。
「ああ、先だってはどうも」
軽く会釈し、ザイは街角に足を向けた。
「お姉さんの方スよね。あ、もしや、今のメイドさんたちに混じってました?」
賓客の友人の領邸メイド──件の双子の姉の方だ。賓客の奪還を企てた際、領邸建造物の配置等々貴重な情報をもたらした。名前はラナ。
ラナはあわてた顔で手を振った。
「いえ、行きつけの店に寄ってから来たので。──あの、すみません、同僚がご迷惑を。ミモザ祭なものだから、みんな、ちょっと、はしゃいじゃったみたいで。それで、わたし、声をかけそびれてしまって」
気まずそうに、もじもじうつむく。大人しい気質の彼女は、気圧されてしまったようだが、メイドたちのばか騒ぎについては、どうやら知っているらしい。ふむ、とザイは向き直る。
「で? 今日はなんのご用でしょ」
ぺこり、とラナは頭を下げた。
「エレーンを助けてくださって、ありがとうございました。でも、わたし、あの時、見当外れなことばかり言ってしまって。せっかく話を聞いてくださったのに」
ああ、とザイは思い出す。領邸に勤める彼女らの手前、例の奥方の身柄については、与太者から奪い返したことになっている。
ラナは手さげの中をごそごそ探る。「それで、あの、お詫びにと思って──お口にあうといいんですけど」
白い包みをさし出した。
「俺に、スか?」
手の平にのせた包みをあけて、ザイは紙袋の中を確かめる。どうやら手作りのクッキーらしい。恐縮しきりで赤面し、ラナは身を縮めている。
「その節は、わたしの早合点でご迷惑をおかけして──あ、でも、わたし、こういうのはあんまり得意じゃなくて」
「へえ、どれ」
ぽい、とザイは一つつまんで口に入れた。
不可解な顔で、ぎこちなく固まる。
「……少し、生焼け、みたいスね」
口から出すわけにもいかないので、半生の物体をにちゃにちゃ咀嚼。
「や、やだ! わたしったら、またっ!」
真っ赤になって、ラナがおろおろ見返した。「ごめんなさい! わたし、こういうのは得意じゃなくて」
「……得意じゃないってのは、こっちの話スか」
やむなく、ザイはたじろぎ笑った。度重なる失態に、ラナは居たたまれない顔で平謝り。「もう、本当に重ね重ねすみませ──!」
くい、とザイが、ラナの手首をつかんだ。
「捕まえた、ってことで」
ぽかん、とラナが顔をあげた。ぬっ、とザイは顎を出す。
「鬼スよ? 俺は。知ってるでしょ? で、あんたをこうして捕まえた。──さあて、何してもらいますかねえ? そういや、あんたには貸しもありましたっけ」
あたふた言い募ろうとしていたラナが「はい?」と停止し、首をかしげた。ちら、とザイは顔を見る。
「俺を覗きで売ったの、あんたでしょ?」
賓客が街宿で待機していた頃、ザイはなぜだか通報されて、警邏にこってり事情聴取されたことがある。
他にそんなことできる人はいませんものねえ、とラナの顔をちら見して、ザイはその手をぐいと引っぱる。「さ、行きましょうか」
「──え?」
至極当然のごとくに引っぱられ、ラナはあたふた見まわした。由々しき事態を視線が捉え、ふんぬと全力で踏み止まる。
行く手の路地に、連れこみ宿の妖しげな看板。
「……冗談よね?」
片頬をひくつかせ、ザイを大真面目にねめつけた。沸々たちこめる青白い怒気。
「もちろんスよ」
ザイはにっこり手を放した。
じいっ、とラナは疑わしげにザイを見る。「本当に冗談?」
「……。ええ。まあ」
今の間はなに? とジト目で腕組み。
ザイは降参の手をあげて、ぶらり、と歩道を振り向いた。
「飯でもどうスか。昼休みでしょ?」
ラナは面食らった顔で見返した。「でも、さっき、忙しいって──」
「いいスよ、どうせ暇なんで。あ、こいつは俺が、後でありがたく頂きますよ」
あぶれば食えなくもねえスからと、祭でにぎわう歩道に踏み出す。
くい、と上着が引っぱられた。
大人しそうなラナの手とは、あからさまに異なるやんちゃぶり──ザイは怪訝に振りかえり、呆気にとられてつぶやいた。
「……あんたですか」
ラナと同じ顔ではあるが、雰囲気はまるきり違う。見覚えのあるその顔が、ぷう、とみるみるふくらんだ。腰に手を当て、びしっと指さす。
「あ! 今、やな顔したでしょ!」
「気のせいですよ」
「嘘よ! 今、チッて舌打ちしたもん! あたしが一緒じゃ、やだってこと?」
「だから気のせいですってば」
ラナの妹リナだった。そのふくれっつらをやり過ごし、はた、とザイはリナを見る。
「あ、さては腹いせですか。あんたでしょ、俺の通り名、愉快なお仲間に言い触らしたのは」
そう、ラトキエ領邸メイド連ご一行様に。
ぷい、とリナはふてくさった顔で横を向いた。「なによ。"副長"に会わせてくんなかったくせにぃ」
「でも、勝手に入りこんだんでしょ?」
生死の境をさまよってファレスが伏せっている間、リナがしつこく探りを入れてきたのだが、ザイは決して取り合わなかった。もっともリナは、根性で館内に潜りこみ、念願の面会を果たしたが。
「あんた、あのトンボ眼鏡に一体なに吹きこんだんです? 目の敵にされましたよ」
ザイは溜息で腕を組んだ。あの馬鹿でかいトンボ眼鏡が夢に出てきて、うなされそうだ。だが、「変ね」とラナは腑に落ちない顔で小首をかしげる。
「オフィーリアは気に入っていたようだけど」
とても、はしゃいでいたもの、と続けてリナを見た。
へえ、あの子が珍しい……と、リナがしげしげ感心するかたわら、ザイは密かに我が身をかかえ、絶句で背筋を凍らせる。ちなみに、あのトンボ眼鏡は「オフィーリア」という名前らしい。
「ああ、ヤサっていや、副長が──」
気を取り直して顔をあげ、ザイは北の馬車道を振りかえる。
「今しがた、北門通りにいましたっけね」
「……え?」とリナが、顔を強ばらせて動きを止めた。
「じゃあ」でもなければ「またね」でもなく、ばたばた、せわしなく踵を返す。両手を振って駆け去るその背が、またたく間に小さくなって──
「あ、リナ、待って!」
ラナが「ではこれで」と一礼した。
止める間もなく駆け出して、リナの背中を追っていく。あっという間に取り残されて、ザイはぽかんと立ち尽くした。
「──なにも一緒に行くこた、ねえじゃねえかよ」
頭を掻いて舌打ちし、もらったクッキーを口に入れる。
「ま、いいか。どうせ食ったばっかだし」
街には黄色い色彩があふれ、明るい熱気に包まれていた。
これから始まるパレードへの期待が、街のそこかしこで、くすぶっている。空は青く、夏空が高い。ザイは生焼けのクッキーをかじりつつ、ぶらぶら見まわりを再開した。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》