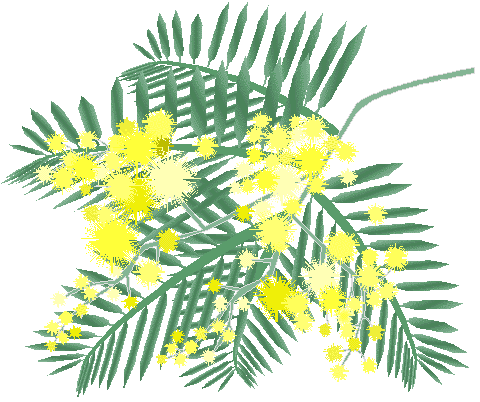
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 9話21
( 前頁 / TOP / 次頁 )
事態の収束を見てとって、往来の人だかりが流れ始めた。
ハジと渋い顔の上官は、荒れた歩道にたたずんで、淡々と交渉を続けている。事切れた二人の遺体は、道の脇に寄せられて、上からシートがかけられている。
「セレスタン、放して。──お礼言ってくる、ラナたちに」
押しやった途端に、足がよろける。
その腕をとっさに支えて、セレスタンが心配そうに顔を覗いた。「歩けますか? 顔が真っ青ですよ。なんなら俺もお供しますが」
「ううん。いいの。大丈夫」
エレーンはゆるゆる首を振る。
「──いや、でも、その様子じゃ」
「いいの。一人で行ける」
少し無理して微笑みを作り、エレーンはその手を押しのけた。踵を返して歩き出す。
セレスタンは二の足を踏んでいるようで、決めかねたようにたたずんでいる。その気遣いと逡巡が、背後の気配から伝わってきたが、振りかえりはしなかった。
ラナたちを見かけた沿道に歩き、彼女らの姿をぼんやり捜す。だが、どうしたわけか見つからない。まだ、それほど経ってないのに。
気だるい頭で首をひねり、エレーンはそっと嘆息した。加勢をしてくれた彼女らが、何も言わずに立ち去るとは思えなかった。だが、どこを探しても見当たらない。
赤い制服が上官に駆け寄り、伺いを立てて一団に戻った。それを受け、衛兵らの一団は、口ひげの上官と現場を保持する数名を残し、通りを西に踵を返した。逮捕すべき被疑者が死亡し、動員目的を失ったため、ひとまず引きあげることにしたのだろう。足を向けた北門には、彼らの詰め所が併設されている。
淡々と進むその様を、見るともなしにぼんやり眺めて、エレーンは抜け殻のように歩き出す。すべて終わった。終わってしまった……
ふと、足元に目をやった。靴先が何かを蹴ったのだ。
ぼんやりそれを見下ろせば、大きく裂けた紙袋だった。中の物が透けそうに薄い、安っぽく素朴な平袋。裏店の駄菓子屋などで飴などを入れて手渡してくれる。
確か、女賊の持ち物だ。だが、みすぼらしいその袋は、女の垢抜けた風体にはそぐわず、それだけが不似合いで、ちぐはぐだった。
踏みしだかれて破れた紙が、なぜだか妙に気になった。少し屈んでうかがうと、大きく裂けた袋の穴から、中の品物が覗いている。みかんくらいの大きさの、何か薄っぺらくて丸い物だった。中央に大きく何かの絵が描かれている。太い線の単純な図柄だ。それは、
──青い龍。
"アルビン"について説明する、あの得意げな顔が脳裏をよぎった。
「……ケイン」
唇をわななかせ、エレーンは路上にへたり込んだ。震える指で、素朴な紙袋を拾いあげる。彼女はきちんと知っていたのだ。我が子が密かに望む物を。
涙があふれて止まらなかった。それを胸に抱きしめて、エレーンは嗚咽を押し殺す。
「──案外、簡単に刺さるものだな」
ざわめきを突き抜け、するり、とその声は耳に入った。
嫌な感じの、潜めた声。泣き濡れた顔をあげ、エレーンは怪訝に振りかえる。
「なあ、初めてだよ俺、人なんか刺したのは」
「俺だって」
彼らが無造作に下げている、抜き身のままの赤いサーベルが目に入った。女賊を刺した衛兵たちだ。帽子の下の顔つきを見れば、三人とも案外若い。周囲をはばかり、さすがに声は押さえつつも、どこか得意げに、興奮気味に話している。
北門へと引きあげる制服の一団に付き従うべく、彼らは足早に追っていた。無罪放免で気がゆるんだか、帽子の下にはうっすら笑みさえ浮かべている。エレーンは吸い寄せられるように立ちあがる。
「にしても、元凶はあの女狐だ。たく。余計なこと言いやがって」
「まったく生意気な女どもだぜ。高々メイドの分際で何様のつもりだ」
「なあ、あれを野放しにするのは、まずくないか? 連中の後ろ盾はラトキエだぜ。あそこの領主は自分の使用人にお優しいからな。今日のこと、告げ口なんかされてみろ。調べが入って、こっぴどい目にあわされるんじゃないか? 俺らと領邸じゃ向こうが上だろ」
「下手すりゃ、免職かよ。──冗談じゃない。俺らは仕事をしただけだぜ」
「……女どもの顔、覚えているか?」
「初めの奴はうっすらと。ああ、説教たれた三番目は、でっかい眼鏡をかけてたな」
「口止めするか? チクられる前に」
「いや、すぐに捜しに行ったんだが、混雑していて見つからなかった」
「たく。逃げ足まで速いのかよ。質の悪い!」
「大丈夫だ。そっちは俺に任せろよ。叔父貴が上にいるからさ」
「──そうか! なら、安泰だな」
頬が熱く、頭がのぼせた。白濁した視界の中で、やれやれと引きあげる一団の姿が、ゆらりゆらりと左右に揺らぐ。
胸でどす黒い感情が渦まいていた。決着がついたのはわかっている。女賊が悪党であることも。予想だにせぬケインの死が、彼らのせいではないことも。けれど、やっぱり、
──許せない。
凝視した視界の中央に、最後尾の衛兵の赤いサーベルがあった。膝が震えて、足に力が入らない。だが、前のめりになり、そり返った石畳でつまずいて度々転びそうになりながらも、あえぐようにエレーンは歩いた。ただ、ただ歩いた。
誰かが何か言ったようだが、耳から入ったその言葉は、何も意味をなさなかった。それは雑音にも等しい、そこに在るだけの音声だった。
往来には、穏やかな喧騒が戻っている。道を行くどの顔も、みな何事もなかったように穏やかだ。彼らは衛兵を糾弾し、証人の務めを果たしたのだ。もう、何の呪縛もない。
わかっていた。わかっている。みんな、全て終わったのだ。人々は適切に事を質し、市民の立場を明示した。ハジはそつなく話を収め、同胞の亡骸をもぎ取った。今さら蒸し返すことはない。謂れのない理不尽はこの世に時として存在する。けれど、それでも──
「……待ってよ」
黙って見ていることだけはできなかった。
いつの間にか北門を抜け、詰め所の前に立っていた。
入口に足をかけていた、赤いサーベルを引っ下げた衛兵らが、雑談をとりやめ、振りかえる。サーベルの血をぬぐうのだろう、詰め所の中の同僚から布きれのようなものを受け取りながら、いずれも怪訝そうな面持ちだ。
胸でどす黒い感情が渦まいた。"上"に泣きつき、揉み消し工作を図るなら、"奥方さま"のこの立場は、それよりよほど上だろう。そう、家紋入りのこの指輪。身の証を立てるには十分だ。肩越しに振り向いた制服の背に、エレーンは手をつき伸ばす。
「このまま逃げるつもりなの? よく見なさいよ! あたしはねえ──」
「──ああ、すいませんねえ」
後ろから男が、ぶつかるようにして駆けこんだ。衛兵につかみかかった指先が、赤い制服の背中をかする。
「いえ、なんでもありません」
駆け込んできた勢いのままに、男が手首をもぎ取っていた。左右の手を後ろから封じ、すかさず両腕で抱えこむ。
「とんだご迷惑をおかけして。どうも、こいつは鼻っ柱が強くってねえ」
怪訝そうな衛兵をあしらい、そつなく男は踵を返す。
「な、なにすんのよっ! あんた、誰よ!」
有無を言わさず男に詰め所から連れ出され、エレーンは振りほどこうと遮二無二もがいた。だが、両手の自由を奪われて身じろぎさえもままならず、どうしても顔を確認できない。だが、この声は知っている。確かにどこかで聞いている。
男は強引に街道を渡り、詰め所の向かいに広がっている森林の縁まで連れ出した。詰め所の前からそのまま離れ、ふと顔をあげ、北門を見る。
「──おいでなすった。早速かよ」
男は視線をめぐらせて、忌々しげに舌打ちしている。いきなりがんじがらめに拘束されて、エレーンには訳が分からない。たまりかねて、わめき散らした。
「なにすんのっ! 放してよっ! あたしは、あの人たちに言いたいことが──!」
「ああ、わかったよ。わかったから、口をふさげ。正直、余裕はねえんだよな」
え? とエレーンは動きを止めた。男の言い草がどこか奇妙だ。
「狙われてんだろ? 奥方さま?」
揶揄する口調で、耳元で言う。
エレーンは身じろぎ、眉をひそめた。一体、これは誰なのか。声は確かに知っている。恐らくケネルたちの仲間の一人だ。だが、どこで聞いたか思い出せない。ザイでもなく、セレスタンでもない、無論、ケネルやファレスでもない。そもそも群れの人数が多すぎて、それぞれ似たような低い声の持ち主だ。それだけの条件で、特定するのは難しい。
「くるぜ」
何が、と問いかえす暇もなく、ぐい、と肩が押し出された。
たたらを踏んだ前方には、街道に面した鬱蒼とした樹海。あるかなきかの獣道に向け、男が強く押しやった。
「走れ!」
後ろ手にした衛兵たちが等間隔に現場を囲い、野次馬の立ち入りを阻止していた。二人の遺体は道端に寄せられ、上からシートをかけられている。
衛兵が被疑者を刺殺するという未曾有の凶変の興奮を引きずり、北門通りは奇妙な昂ぶりに浮き立っていた。人々はそれぞれの場所へと移動しつつも、遺体のシートを遠巻きにして、依然ささやき交わしている。痛ましい表情を浮かべ、歩道の血痕に眉をひそめる者。連れにもたれて目頭を押さえる者。あわてて街角に逃げこむ者。噂を聞きつけ見物に来た者。知り合いに手を振り、歩道の血痕を指さす者。現場を一目見ようと乗り出して衛兵に制止される者。通りにたむろす大勢が、ざわめき、わめき、手を振り、走る──。
人垣の崩れた往来に、彼女が背を向け、歩いて行く。あの友人たちを捜すために。
その背をしばらくながめやり、セレスタンは密かに踏み出した。
混乱した今ならば、容易く彼女を連れ去れる。事態はようやく収束したが、往来は未だ混乱している。素早く当て身を食らわせて、往来の人込みに紛れてしまえば──ざわめく人波を観察し、追跡者の有無を見極める。慎重に歩く肩越しに、彼女の後見人を一瞥し──
思わぬ光景に息を呑み、セレスタンはあわてて地を蹴った。
「副長!」
路上のファレスが長髪をうなだれ、あぐらの膝に突っ伏していた。そのかたわらに滑りこみ、うなだれた肩を引き起こす。
「大丈夫すか、副長っ!」
ファレスはうめいて歯を食いしばり、既に意識が朦朧としていた。額には珠のような脂汗が浮いている。ぐったり力ない体をかかえ、セレスタンは手早く上着を払う。
案の定のありさまに、眉をひそめて首を振った。
「──たく、もう! 無茶するから」
傷から染み出た鮮血で、腹の包帯が濡れそぼっていた。早く本部に運びこみ、手当てをせねば、命さえ危うい。だが──。
舌打ち、視線をめぐらせた。
こちらの足場が変わったことに、ロジェは恐らく勘付いている。
ロジェをかわして彼女を捜し、ようやくここで見つけた時には、既にロジェがかたわらにいた。あたかも牽制するように。いや、あの場にいたのは偶然ではない。彼女の隣に陣取ることで、阻止する意図を示威していたのだ。そもそも、舞い戻った街角から彼女が消えたのも妙だった。街角で別れてさして時間が経ってないのに、どれほど捜しても見つからなかった。
ロジェがつかんだ不信感は、既に伝わったとみるべきだった。つまり、突破すべきはあの特務。これで、残された時間は確実に減った。
彼女を早急に拉致すべく、野次馬の群れに潜んでいた。だが、彼女は女賊の刺殺を目撃し、恐慌をきたして泣き叫び、それを見かねて駆け寄ってしまった。そうする内にも、今度はファレスが立ち戻り、又も連れ出す機会を失った。
こうして発覚した以上、早急に連れ去るべきだった。特務は並みの従卒ではない。片手間にかわせる相手ではなく、いずれも群を抜いて勘が良い。手間取れば、それだけ不利になる。だが、重傷のファレスを置き去りにすれば、出血多量で遠からず死ぬ。
「──どうすればいい!」
顔面蒼白のファレスをかかえ、身動きがとれずにセレスタンは焦れた。
こうして姿をさらしている。これほど目立つ場所にいるのだ。なのに、なぜロジェは出てこない。火急の用で離れたか。彼女のことは副長に任せて。
だが、そもそもこの騒動で、特務が集合しないはずがない。どこかに潜んでいるのなら、副長の危うい様子にも、とうに気づいているはずだ。ならば、なぜ出てこない。騒ぎがあれば、真っ先に駆けつけるザイでさえ、出てくる気配がまるでない。そうする間にも、ようやく間近に戻った彼女が、又も手の内から遠ざかる──彼女が向かった沿道を一瞥、セレスタンは怪訝に見直した。
「……姫さん?」
彼女が、いない。
いや、目を凝らすと、後ろ姿があった。少し向こうの歩道の先だ。詰め所に引きあげる衛兵の後を、ふらふらついて歩いている。友人の元に行ったはずだが、何故あんな所を歩いているのか。
彼女は足元のがれきによろめきながら、頬にだらだら涙を流し、足取りも怪しく歩いている。放心している様子だが、未だ気もそぞろな往来は、誰も注目していない。とっさにセレスタンは腰を浮かせた。彼女を拉致する絶好の機会だ。往来はごった返している。これ以上の好機はあるまい。だが──
セレスタンはじりじりしながら顔をしかめた。手がふさがって身動きがとれない。ぐっと腕に重みがかかり、あわててファレスをかかえ直す。ついに意識を失ったらしい。
遺体にかけられたシートの横で、ハジが衛兵と話していた。あのハジに彼を託して、彼女の後を追うべきか。付近の繁華街のすぐ裏手は、本部のある異民街だ。すぐに応援がくるだろう。いや、その判断は危険にすぎる。付近には、ジャイルズ一派がいるはずだ。あの事件当日のアドルファスの不在証明をさせるべく、レーヌから商都に呼びつけた。なぜか領邸への襲撃容疑で拘束されたようだったが、どうやら釈放されたらしく、沿道にたむろす人垣に紛れて裏切り者の処刑を眺めていた。相手は十人からの大人数だ。ハジ一人では手に余る。ハジの近くには下回りもいるが、ことそうした戦闘においては、鳥師はまるで使い物にならない。そう、次に彼に触れる者が、味方であるとは限らない──
「なぜ、外にいるんですか」
呆れた声に振り向けば、往来の流れに逆らって、美麗な青年が立っていた。
涼やかな瞳が見据えている。さらりとした肩までの髪、少年といっても差し支えないほどに、線の細い小柄な体格。
「本当に言うことを聞かない人ですね。しばらく安静にするように、あれほど念を押したのに」
顔面蒼白のファレスを眺め、クロウはやれやれと歩いてくる。セレスタンは苛々と声をかけた。
「おい、クロウ! ここを頼む!」
クロウは呆れたように顔をしかめ、投げやりに手を広げた。「なにを言っているんですか。わたしに一人で副長を運べと?」
「応援を呼べばいいだろう!」
「事は急を要します。見れば分かるでしょう」
「だが、姫さんが」
「──ああ、あの人なら問題ないですよ」
彼女が進む通りの先に、クロウはうんざりしたように視線を投げた。「他のロムが連れ戻しに行きましたから。毎度毎度のことながら、まったく、あの人はふらふらと」
「……他の?」
思わぬ返事に虚をつかれ、セレスタンは当惑して眉をひそめた。だが、ロムは近隣で待機のはずだ。ならば、特務の誰かだろうか。いや、特務であれば、名前で告げる。無論、隊長や首長をそんなふうに呼ぶ者はない。「他のロム」とクロウは言った。つまり、日頃あまり親しくない同胞だったということだ。だが、ロムは近隣で待機中。街には、誰もいないはず──。
ふっと嫌な胸騒ぎがして、セレスタンはあわてて目を戻す。「誰だ、そいつは」
さあ、とクロウは面倒そうに首をひねった。
「はっきり顔を見たわけではありませんし」
遠くの人波に目を凝らすと、彼女を追う男の背中が、人々の頭の間に垣間見えた。同胞によくある蓬髪で、上背のあるその肩は、なるほど防護服で覆われている。分厚く特殊な件の上着は、敵からの不意打ちに備える為、ロムなら大抵着用している。
隠しに両手を突っ込んだ男は、肩を揺すって後に従い、ちらちら視線をめぐらしている。周囲を警戒するような素振りで。一瞬振り向いた横顔に、セレスタンは眉をひそめた。
「──まさか、あいつじゃ」
男の頬には刀傷があった。見覚えのある、あの傷が。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》