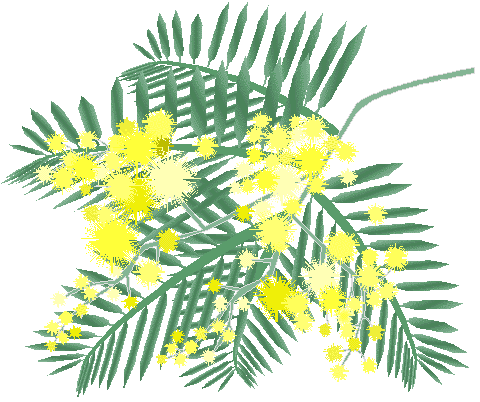
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 9話22
( 前頁 / TOP / 次頁 )
黙りこんで歩いていたラナが、肩をがたがた震わせた。
「──すいません。ちょいと強引でしたかね」
へなへな座り込みそうになり、あわてて腕を引っぱりあげる。ラナを引き起こしてやりながら、ザイは困惑顔でたじろいだ。ラナは目を伏せ、顔をぬぐっている。どうやら泣いているらしい。途方に暮れて視線をめぐらせ、一拍置いて気がついた。
「……今ごろ怖気づいてんですか」
いささか拍子抜けして視線を返し、再び、ぶらぶら足を運ぶ。
「大した度胸だ。中々できませんよ。あの大人数を向こうにまわして、一人で官憲に立てつくなんざ」
そう、彼女は今日の殊勲者だ。彼女の勇気がなかったら、かの女賊は犬死だった。自らもいつ何時、女賊と同じ立場に置かれるやも知れぬ境遇だけに、ひとり矢面に立ったラナの姿は、鮮烈に目に焼きついた。事の真偽を質そうが、なんの見返りもあるまいに。
黒薔薇ローズの刺殺事件を沿道の人垣で見ていたラナは、誰もが口をつぐむ中、対峙の矢面にひとり立ち、衛兵の恣意的な弁明を真正面から覆した。それは向こう見ずとも思えるような訴えで、だが、彼女が放った健気な言葉で閉塞していた流れが変わり、衛兵の目に余る実力行使を、沿道に詰めた目撃者たちが糾弾するまでに至っていた。
ザイはぶらぶら歩きつつ、隣の様子を盗み見る。ラナは口元で両手を握り、びくびく瞳を伏せている。
危なかしい、とザイは思う。かたくなで、変なところで気が強い。肝が太いのか細いのか、わからない。今回は加勢が現れたから良かったようなものの、仮に上潮に乗れなければ、冷淡に取り巻く群衆のただ中、孤立無援で取り残される危うい雲行きを孕んでいた。そうなれば、嘲笑と憐れみの渦の中、むなしく置き去りにされたろう。というのに、隣の娘は、そんな懸念をものともせずに、煽動の口火を切ってのけた。あんなにもか細いあの肩で。
内気なのか、勝気なのか、まったくもってわからない。追随者が現れると踏んでいたのか? だが、領邸使用人の制服だけでは、味方を得るには不十分だ。当主というなら話はまだしも。いや、事の成否や勝算などは、考えもしなかったに違いない。
とはいえ、あれは浅慮ではない。血気にはやった弾みなどではなく、明確な意志に基づく反論だった。女賊に対する憐れみでもない。客に加勢してのことでもない。ただ、違うから違うと言ったのだ。当事者が賊であろうが、衛兵であろうが、そんなことには関係なく。
それは、ザイの中には、かつてなかった価値観だった。大抵のものは認識後、速やかにどこかへやり過ごすが、それは異物として体内に残り、いつまでも微かにくすぶった。溶け込んでいかない不可解な違和感。護衛対象のあの客も突拍子もないことをやらかすが、あの単細胞の反応ならば、予測もきくし、対処もできる。だが、彼女はそうではない。
予測不能は密やかな脅威だった。なんらかの行動を起こすに際し、ザイは要素の全てを予定に織りこむ。筋書きを左右しかねない不明な点は気にかかる。無関係な者ならまだしも、彼女は当該実務の関係者だ。不確定の要素の存在は、なにやら落ち着かない気分にさせる。ぽっかり穿たれた暗黒の領域。次の反応は右か左か、意識がそれに囚われる──ふと、ラナが振り向いた。「……あの、なにか?」
「──ああ、いえ」
視線が不意にかち合って、ザイはどきまぎ目をそらす。
「飯でも食いに行きますか」
え? と面くらったように訊きかえし、ラナがおどおどうかがった。視線を前に向けたまま、ザイはさりげなく理由を続ける。「昼飯まだでしょ? あんたの健闘に敬意を表して、そこらで何かおごりますよ」
「おごってくれるのっ?」
ラナとはまるきり別の方から、嬉々とした声が飛びこんだ。
あ? と思わず頬をひくつかせて振り向けば、双子の片割れリナだった。両手を組んで、お目々きらきら。その横には、同じ体勢のトンボ眼鏡。
「……。ああ、いましたっけねえ、あんた方も」
お前らは帰れよはい解散、と言いたいところをぐっとこらえる。
沿道の人垣が加熱する中、野次馬に紛れて騒動を見物していたザイは、興奮して暴れる双子をひょいと両手で引っかかえ、そそくさ現場を離脱した。路上の女賊に付き添うファレスが、衛兵に歯向かうラナを見て(とっとと退けろ!)と指示をを飛ばしてきたからだ。彼女が衛兵に目をつけられ、こちらとの関係をたぐられれば、先の領邸襲撃の真相が、ひょんなことから明るみに出ないとも限らない。
だが、ラナを保護すべく近づけば、隣には双子の片割れが。つまりは同じ顔であるから、これだけ残してもケチがつく。よって、片割れもやむなく引っかかえ、現場からの離脱を図った次第。
ちなみに撤去すべき保護対象は少し離れてもう一匹いたが、眼鏡はこちらを見咎めるや否や、諸手を広げて突進してきた。そして、唯一空いていた首筋に、両手で勝手にぶらさがった。よってザイは、都合三人の体重を引きずり、ずりずり脱出する羽目と相成った。
トンボ眼鏡が、つつ……とすり寄り、赤らめた満面の笑みで袖を引いた。
「わたくしも頑張りましたのっ!」
己の手柄をアピールしがてら、褒め言葉をさりげなく要求。
感服しきりの顔を作って、ザイは腕組みで首をひねった。「あんたはまた、むつかしい言葉を知ってますねえ」
「売りだから」
こっくりうなずき、言わずもがなと眼鏡は即答。
「……そうスか」
一蹴されてとっさに絶句し、ふと、ザイは見直した。
「おや、眼鏡の端っこに煤のようなものが」
え゛? とオフィーリアはまたたいて、トンボ眼鏡をわたわた外した。
制服のスカートの隠しから、バッとハンカチを振り広げ、焦った顔で拭いている。ザイはよそ見をした振りで、どん、とさりげなくぶつかった。思わず取り落としたその眼鏡を、すかさず靴裏で踏んづける。
「──おっと。とんだご無礼を」
足をどけつつ、白々しく謝罪。
「すいません。誰かに代わりを見繕わせますから」
この大きなトンボ眼鏡は、いささか特徴がありすぎる。やり込められた衛兵が、彼女を特定するに十分だ。
おわっ!?──と見ていたオフィーリアは、んん? とそれを聞き咎め、不満げに顔を振りあげた。「えーっ! ザイさんが見繕ってくれるんじゃなくてえ?」
「いえ、別の奴に」
ザイはきっぱり即座に否定。左右の拳を胸で握って、オフィーリアは駄々をこねるように首を振る。「ザイさんがいい!」
「またまたまた。そんなお戯れを」
ザイは引きつり笑いで、ちょいと手を振る。
「俺は、そういうのはからきしなんで。詳しい奴がいますから、よほど役に立ちますよ。ともあれ店に入っちまいましょう」
不都合な話題はただちに流し、手近な店を適当に指さす。「なんでも好きなもの、おごりますよ。ほら。あんた方の慰労会をしなけりゃ」
「まじでっ?」
リナとオフィーリアが瞳を輝かせて振り向いた。
一も二もなく店頭の品書きに突進する。看板に張りついた二人のたくましい背をながめ、(本部に経費で請求しよう、眼鏡代と一緒に……)とザイは密かに心に誓う。
呆気にとられて取り残されたラナが、口に手をあて振り向いた。
「そういえば、さっきも、そんなようなこと言ってませんでした?」
そんなにお腹すいてたんですか……としげしげ顔を仰いでいる。欠食児童を見るような目で。
無邪気な顔を見おろして、ザイは仕方なく頭を掻いた。
「……ええ。まあ」
繊細なんだか鈍感なんだか、まったく、さっぱりわからない。
皆の集まる一室へと、その男は向かっていた。
上背のある大男だ。縦に長い四角い顔は黒い顎ひげに覆われて、だが、その面持ちはどことなく呑気だ。特務班のレオン、狙った獲物は必ず仕留める隊内きっての射手である。
日中の街から本部に戻り、陽の当たる廊下をぶらぶら歩いて、レオンは部屋の扉を引き開ける。
夏日さしこむ一室には、特務の面々が控えていた。開け放った明るい窓辺で、太鼓腹の中年男がトマトジュースの瓶をあおっている。あのクマ顔のついた黄色いシャツは、力自慢の怪力ロジェだ。その手前には、靴の片足を膝にあげ、道具の加工に熱中している赤ランニング。あのぼさぼさ髪は発破師ジョエル。卓の端に腕組みでもたれ、無表情に見やるは毒薬使いダナン。
一瞥をくれた三人にレオンは視線をめぐらせて、部屋の敷居を無造作にまたいだ。首尾を報告すべく口を開いて、ふと、自分の足元を見る。
びょん、と諸手をあげて飛びのいた。
「な、な、なによっ! なんで、あんた、こんな所にいんのよっ!」
素早く足元をよぎったそれが、レオンを仰いで声をあげた。
「……にゃあ」
一瞥をくれただけで、すたすた前を通過していく。引きつり顔で胸を押さえて、レオンはまなじりつりあげた。
「なによっ! あれはっ!」
甲高い悲鳴で抗議して、人さし指をぶんぶん振る。
ダナンが面倒そうに一瞥し、ご所望の応えを放り投げた。「猫だろ」
「だから! なんで猫がここにいるのか訊いてんのっ!」
「──代理のだってさ」
まともにそちらを見もせずに、工作中のジョエルは言う。「なんでも新しいのを買ったとか──ああ、まかり間違っても射殺さない方がいいっすよ。あんたの方がぶっ殺されるし」
小型の携帯弓セットでキリキリ狙いを定めていたレオンは、すちゃっ……とそれを震える手つきで腰に収める。胸の前で両手を握った。
「どけてどけてどけてえっ!」
ぶんぶん首振り、大絶叫。
ダナンが溜息で身じろいで、しゅっ、と何かを廊下にほうった。
ぴくり、と猫は顔をあげ、それに飛びかかるようにして、廊下の先にすっ飛んでいく。
己の足元に突進され、「んぎゃっ!?」とレオンが踊りあがった。
猫の行方を見送って、ダナンを恐る恐る振りかえる。「……何なげたの?」
「またたび」
毒薬使いはそっけなく応えた。
レオンは戸口に両手で張りつき、廊下の先を探っている。猫が戻ってこないか見ているらしい。
やれやれとロジェは見やって、窓辺からそちらに足を向けた。「でかい図体のくせしてノミの心臓だな。そんな獅子みたいな面なのに」
「つか、そのオネエ言葉どうにかしてよ、気が抜けちまって手元が狂うぜ……」
鼻歌で机に突っ伏したまま、ジョエルはためつすがめつ手元を見る。「──よっしゃ。できた」
「誰にだって、苦手なもんはあるでしょがっ!」
キッと涙目のレオンを見やって、ロジェは真面目な顔で腕を組んだ。「それはそうと、さっきは悪かったな、急に頼んで。副長の方はどんな具合だ?」
「──どんなもこんなも」
レオンは憎々しげにジョエルをねめつけ、気を取り直してロジェの顔を振りかえる。
「絶対安静に決まってるだろ。そもそも、なんで外にいるんだよ、九死に一生を得たばかりだってのに」
理解できないという顔で呆れたようにそう言うと、レオンは顔だけ廊下に出した。
びくびく気配をうかがっている。そうしてしばらく張り付いていたが、やがて、そろりと、爪先を廊下に踏み出した。どうしても猫が気になるらしい。
大きな背中が消えるのを見送り、ロジェはやれやれと嘆息した。
「……何か、嫌な予感がするんだよなあ。頭(かしら)がこんな時だってのに」
彼らを取りまとめる首長のバパは、領邸でこっぴどく痛めつけられ、未だ一室で寝ついている。
ロジェは昼食中のファレスらから離れて、急ぎクロウを呼びに戻った。その際、本部の廊下を通りかかったレオンに、クロウと同行するよう頼みこみ、自分はセレスタンを捜しに街に戻った。様子がただごとではなかったからだ。いやに不穏で殺気立ち、のほほんと気さくな普段の彼とは、明らかに様子が違っていた。
ウォードを捕らえるべく街に出た、ロジェ、ジョエル、ダナンの三人は、毎度のごとくにさぼりを決めこみ、今日も街角でたべっていた。その時に見かけたのだ。セレスタンが賓客を捕まえているのを。
荒事に手慣れた三人は、何かある、とピンときた。密かに追跡すれば案の定、裏道へ裏道へと彼女を連れて行くではないか。
三人はすぐさま、彼女をセレスタンから引き離した。セレスタンをロジェが連れ出し、ジョエルが彼女を確保して、街角のダナンがロジェの首尾を確認するまで、手近な店舗内に隔離した。だが、ロジェがわずか油断した隙に、セレスタンは姿をくらませた。
そこには、はっきりとした感触があった。理由や目的はわからないが、セレスタンは彼女を拉致しようとしている、それだけは間違いなかった。
「なに狙ってんすかね、あのハゲは。いきなり客の後つけ回して」
弄んでいた道具を机に置いて、ジョエルが二人を淡々と見やった。顎をつかんで黙考していたダナンが、それに静かに目を向ける。「駆け落ちとか?」
「姫さんの方は眼中にないだろ」
ロジェが顔をしかめて手を振った。
よしんば、そうであるにせよ、後ろ盾のない遊民は、群れを出ては生きていけない。身元を保証する者がなければ、職さえ得られないのが現状だ。だが、一度群れを飛び出したからには、遊民の社会にも戻れない。安易に出奔したところで、枯れた道ばたで野垂れ死にが落ちだ。
「大体あれは、ご執心の範疇を飛び超えてる」
それは、三人ともすぐに気づいた。あれは獲物を狙う目だ。だが、彼女に恨みはないはずだ。恨みを抱く可能性があるとすれば──それについては心当たりがないでもなかった。背もたれに体重をかけて一本足で椅子をかたむけ、ジョエルはそり返って天井を仰いだ。
「つまり、奴は残党、か」
隊がまだ混沌としていた頃、現隊長にヴォルガで挑み、討たれた頭目が幾人かいた。その手下──つまり、旧勢力の残党は、散り散りに解体され、隊の各所に配されている。つまり、頭目たちの報復をすべく虎視眈々と狙う輩が、今もどこかに存在する。
「できることなら、隊長の寝首を掻きたいわけだ。なら、森で羊飼いめった刺しにしたのも、ハゲの仕業ってことっすか」
浮かせた足をぶらつかせ、信じらんねえ、とジョエルはぼやく。ロジェも太鼓腹で腕を組み、渋るように首をひねった。「だが、相手はセレスタンだぜ。どんな理由があるにせよ、女子供を手にかけるとは、俺にはどうしても思えねえんだがな」
「だが、現に、羊飼いは惨殺された」
そっけなく、ダナンが事実を投げた。切れ長の目端で一瞥する。「どうする?」
「決まってる。ハゲをとっ捕まえて、頭(かしら)の前に引きずり出す」
気楽な口調で言い放ち、ジョエルが背もたれから起きあがった。ロジェは苦虫噛み潰した顔だ。「頭(かしら)に奴を突き出した後は、やっぱ、俺らの仕事になるよな」
特務は別名「処刑隊」とも一部で揶揄され、隊内の粛清を請け負っている。事実、多くの同胞を、彼らは人知れず葬ってきた。
ロジェはやりきれない顔で首を振る。
「まさか仲間が、狩りの標的になるとはな」
「やるっきゃないでしょ。害毒の排除が元より特務の生業すよ」
ジョエルの返事はそっけない。苦虫噛み潰して渋るロジェに、ダナンが静かに目を向けた。「こっちの動きに、奴はもう勘付いているのか?」
「たぶんな」
「早急に客を確保するか」
「いや、必要ないだろう。姫さん担当はあのザイだ。よしんば俺らが突破されても、ちょっとやそっとじゃ出し抜けねえだろ」
窓辺の陽だまりに目をやって、ロジェは虚ろに目を細める。「にしても、セレスタンの奴、一体どこに行っちまったんだか」
「……セレスタン?」
割りこんだ声に振り向けば、レオンが戸口に立っていた。いつの間にか戻っていたらしく、そろりと入り込んだ戸口のふちで、廊下の気配を睨み睨み、室内の三人を肩越しに振り向く。
「奴なら、いたぜ? 副長のそばに」
ぎょっと三人は見返した。
その過剰な反応にたじろいで、レオンはぽりぽり所在なげに頬を掻く。「あ、いや、だって間違いねえよ。俺に副長を押し付けたの、他でもないあいつだからさ。ちょっと遅れて通りに着いたら、あとを頼むって、えらい勢いで行っちまってよ」
「姫さんを追って行ったのか?」
「──姫さん?」
思いもしない問いだったようで、レオンは怪訝そうに眉をひそめた。
「姫さんなんか、いたっけな? なにしろ祭で混んでるわ、副長は虫の息だわ、セレスタンが行っちまって手伝わされたもんだから、クロウもすっげえ機嫌悪いわで、こっちも正直それどころじゃ」
「奴はどこへ向かっていた?」
もどかしげに続けたロジェに、レオンは投げやりに手を広げた。「北門通りを、門の方へ。あのまま外に出たんじゃねえの?」
「街道、かよ」
そり返った椅子をギシギシ揺らし、天井をながめてジョエルはつぶやく。ロジェが思案顔で顎をなでた。「街から出たか。厄介だな」
北門を出て道なりに進めば、トラビア方面への街道に入る。詰め所の方へ左に折れて、外壁沿いの裏道を行けば、商都カレリアの正門に出る。つまり、限定された街中とは違い、彼らの捜索範囲はほぼ無制限に拡大したことになる。
「街道の向かいは森林だが」
静かにやりとりを見ていたダナンが、的確に抜けを指摘する。
「森? そんな所になんの用が?」
じれったそうにロジェは舌打ち。
いささか過敏な反応に、ダナンは小さく肩をすくめた。明らかに二の足を踏んでいる。
室内は、にわかに緊迫した。
どこか刺々しいその空気にレオンもようやく気づいたらしい。腑に落ちない顔で首をひねった。「……なに。何かしたの? あいつ」
「道々話す」
ジョエルはそっなく一蹴し、机にのった小道具を無造作に引っつかんで立ちあがった。
「ここでうだうだ言っても始まらねえよ。奴が相手じゃ猶予もない。どのみち標的はハゲで決まりだ。このこと頭に報告して──」
ロジェを促すように一瞥した。
「早急にハゲを狩りにいく」
各々防護服を引っつかみ、あわただしく部屋を出る。
建物の出口に肩を並べて向かいつつ、ジョエルは前髪の下の目をすがめた。
「──裏切り者、か」
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》