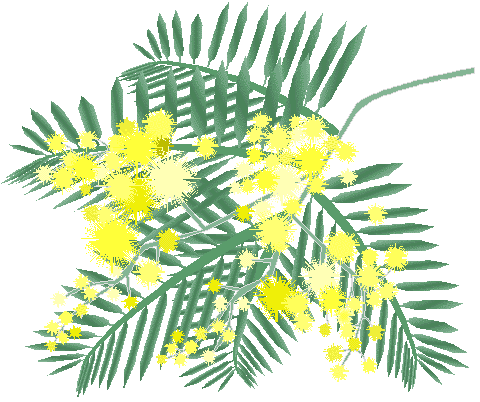
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 10話2
( 前頁 / TOP / 次頁 )
穏やかに晴れた空の高みで、鐘が厳かに鳴っていた。
「──ミモザ祭、か」
一服した目を煙たそうにすがめ、バリーは東の上空を見る。
向かいには、十人からの賊徒の一味が、囲いこむようにして居並んでいた。その中央に、ジャイルズと名乗った頭目がいる。倦んだ目をした四十絡みの痩せぎすの男、黒い蓬髪の前髪の下、飢えた野犬を思わせる獰猛な双眸が光っている。ひとり岩に腰を下ろして、狡猾な目を向けている。
『お前の自由は、あの女と引き換えだ』
客の拉致に向かうのだろう手下の背から目を戻し、頭目ジャイルズはそう言った。客には、第三間道を西の出口に向かうよう指示してある。
商都の南西に広がるこの森には、道幅が比較的広い、出口まで続く道が三つあり、商都北門を基点とし「一」から「三」までの番号が時計まわりに振られている。つまり、内々の地図上の名称は、北門から見て南に出るのが第一間道、南西に出るのが第二間道、そして、西に出るのが第三間道という具合。そして、ここは第一間道と第二間道の中間辺りの山腹だ。
周囲を取りまく手下どもは、疑わしげな面持ちで虎視眈々とうかがっている。胡乱にたむろすその様は、あたかも飢えた野犬のごとく。
いつ飛びかかるとも知れぬ様に、あの時、加勢を乞うていれぱ、楽ができたかもしれないなと、弱気が胸を掠めるが、バリーは苦笑いで払いのけた。あんな子供に助けを乞うなど己の矜持が許さない。そもそも一刻の猶予もない。
向かいの野犬の頭数が、明らかに先より減っていた。ここにいるのは総勢十二。だが、物陰から密かに数えた時には、優に二十人は超えていた。導き出される可能性は一つ。野犬の残り半数は、的を森から逃がさぬように既に狩り出しに向かっている。つまり、一味は二手以上に分かれたと見ていい。追っ手の目を欺くべく、こちらが道を分けたように。
敵を十分に挑発し、おびき寄せたはずだった。だが、あの頭目は抜け目なかった。
つまるところ、野犬の全てが追随したわけではなかった。結果、あの頼りない保護対象は単独での逃走を余儀なくされ、こちらも追いつめられて動けない。
こうなってしまえば、打つ手にさほどの差はなくとも、双方の末路は大違いだった。一味には、なんといっても人手がある。部隊を支える一員として行動してきたバリーには、多勢に無勢をこれほど痛感したことはなかった。
こんな辺鄙な林野にひょっこり、あの男が現れたのは僥倖だった。
ひょろりと背が高い白いシャツ。ガラスのようにきらめく瞳。薄茶の髪の輪郭が日ざしにふわふわ透けている。バパ隊の居候、異端児ウォード。
先日、部隊を脱走し、捜索中と聞いていた男が、何故こんな森にいるのか、その辺りの事情は定かではないが、ともあれ今は、どんな輩でも味方は味方だ。だが、今、抗争でもたつけば、客が一味の手に渡る。そうなれば後々厄介だ。自分の自由は客と引き換え、しばらくこの場を動けない。一刻も早く客の身柄を確保するには──
「客はレーヌだ。第三間道から外に出ろ」
虎視眈々と一味が潜むただ中で、さりげなく符丁を紛れこませた。
レーヌの立地は商都の南方。指示した出口は、商都から見て西の位置。つまり、レーヌに行くなら、実にちぐはぐな指示になる。急を要する話にしては、わざわざ指定した第三間道は、三道の出口で最も遠い。この相違にウォードが気づけば──
不安はあった。「第三間道」の名称は仲間でなければ通じはしないが、相手はわずか十五の子供、即興で機転が利くかどうか。体格こそはいっぱしだが、普段の作戦行動でも頭数から外れている。戦場に於けるウォードはいわば、投入されるだけの兵卒だ。戦場に放てば、ただただ敵を殺戮する。連携とは無縁の単なる駒だ。
果たしてウォードは、無言でこちらの指示を聞き、じっと顔を見返してきた。
「早く行けよ。お前の馬のリーホーちゃんが首を長くして待ってるぜ?」
反応のなさに畳みかけると、ウォードは怪訝そうに視線をめぐらせ、困惑したように首をかしげた。果たして含みに気づいたのかどうか、馬名の誤りには触れることなく、「馬?」とだけ呟いて、おもむろに視線を振り向けた。
「あんたはー?」
予期せぬ誘いに虚をつかれた。
「──一人で行けよ。俺にはまだ、することがあんだよ」
辛うじて返すと、ウォードは無視して訊いてきた。
「それで、あんたは大丈夫ー?」
「──たりめえだ。こんな浅い森なんかで、迷子になんかなんねえよ」
目を合わせていられなかった。
いやに冴えた双眸が、底の知れぬ強い視線が、じっと見つめ返していた。殻を脱ぎ捨てた猛獣が頭をもたげた錯覚に襲われ、ぞくりと背筋が凍りつく。気づいた時には、怖気を振り払い、叫んでいた。
「急げ! 客が危ねえってんだよっ!」
あれは、まさしく成獣の眼だった。明確な意志をもつ、妥協を許さぬ強い瞳。何を考えているのか分からない、いつも、ぼうっとしていたあの子供が。
あやふやだった輪郭が、パシリ──と明確に一致した。
はっ、とバリーは顔をあげた。
思考をさえぎったのは、何かの音だ。よく通る、冴えた音、方角は北東。
穏やかな木立の中、澄んだ空気を貫いて、警笛が空に鳴り響いていた。いや、これは警笛ではない。
指笛だ。
即座にバリーは動きを止めた。
伝達事項を読みとるべく、注意深く意識を凝らす。
──作戦完了。総員集合。
誰が発したものなのか、そっけなくも端的な連絡だった。だが、それは、味方が存在する確かな証。
バリーは苦笑いして顎をなでた。
「──なんだ。いるんじゃねえかよ。ガキの他にも」
発信元は、単独行動のウォードではない。集合をかけたということは、森にいるのは集団だ。だが、部隊は現在、商都近郊で待機のはず。今頃自由に出歩けるのは一部の者に限られる。例えば、長の指示で動く者。特殊な任に当たる者。ならば、あれは、
「特務、ってわけだ」
つぶやき、バリーはにやりと笑った。
「まったく俺はツイている。まさか連中がいたとはな。やっと運が向いてきたぜ」
素早く指を口にくわえた。
間髪容れず、バリーの指笛が響きわたる。
──敵襲。
──じゃじゃ馬が単独で移動中。
──第三間道、中央から西。要、確保。
「なんだ、てめえ! 何していやがる!」
一味は一斉に身構えた。
うろたえた顔で、ねめつける。「さては裏切りやがったな!」
バリーは笑って振り向いた。
「なに言ってやがる。お互い様だろ。用が済めば、俺を始末するつもりでいたろうが。この俺を甘く見るなよ? そんな見え透いた手にうかうか乗るほど、ぼんくらだとでも思ったか」
「だったら、あの女、初めから逃がすつもりで!」
「たりめえだ。確かにあれは、馬鹿で不出来でうるさくて、どうしようもねえ阿呆だが、親父がアレを娘ってんなら、俺にとっちゃ妹なんだよ。──俺はなあ、心に決めてんだよ。てめえの身内を売るような真似は金輪際しねえってな!」
刃を引き抜き、身構えた。勝算は、ある。
第二間道に飛びこめば、本隊が陣取る駐屯地の東に出る。客の確保に要する時間を可能な限りここで稼ぎ、賊を引き付けて逃走し、そのまま駐屯地に凱旋する。いや、突入はせずとも、本隊付近まで誘いこめば、部隊の哨戒が必ずいる。そうなれば形勢逆転、一網打尽という手筈。
バリーは頬をゆがめて不敵に笑う。
「さあ、どこからでも、かかってこいよ。まとめて相手をしてやるぜ!」
早々に急行した衛生班の数人に続き、血相を変えたバリーの配下、険しい顔をした各班の長らが、続々と森に到着していた。それに特務を加えた一団が商都西方の森に散り、敵襲の有無を確認している。
ひっそりたたずむ昼の森は、にわかに活気づいていた。
第三間道の終着点、出口付近のひらけた場所には大型テントが据えつけられ、この拠点の付近には、防護服の隊員が、絶え間なく、せわしなく行き来している。指示を出す者。間道の先に駆けていく者、長に報告に戻る者。
客のテントの番をしがてら、ザイは経過報告を受けていた。先に聞いた指笛は「敵襲」を警告していたが、賊徒発見の報はない。バリーとウォードもいるはずだが、そちらも未だ戻らない。
編みあげ靴の足元で、黄色い蝶が舞っていた。
ぽっかりひらけた緑の林野に、昼の光が当たっている。茶と緑に閉ざされた森。緑したたる苔むした樹幹に、リスが素早く這い登る。
やんわり足を動かして、ザイはまとわりつく蝶を払った。ジョエルをやった本部からも、まだ何の連絡もない。
客は密かに負傷していた、それがどうにも不可解だった。森で賊に斬られたならば、服に破れがないのはおかしい。セレスタンに指摘されるまでもなく、それには一目で気がついた。傷がひらいた、そう思った。だが、上からは何も聞かされていない。近日負った傷にせよ、今しがた、北門通りで見た時には、何事もなくぴんぴんしていた。あの出血は致死量だ。我慢や無理で平静を保てる程度ではない。動こうにも動けない、そのはずだ。一体何がどうなっているのか──思索の糸を断ち切って、ふと、ザイは顔をあげた。
視界の端で、テントが動いた。
腕組みを解き、そちらへ、おもむろに足を向ける。
「よう。どうだ、容態は」
テントから出てきた小奇麗な身成りの若い男が、足を止めて振り向いた。
細い顎、うりざね顔で涼しい目元、頭の高い位置で長い茶髪をくくっている。戦地を駆けるロムというより、舞台が似合いそうな優男だ。バードから転属した新入りミック。衛生班に属している。クレスト領主のトラビア行で同行したため、彼とはいささか面識がある。
ぶらりとミックは向きなおり、お手上げというように肩をすくめた。
「ダメっすね。むしろ、くたばらないのが不思議なくらいすよ。今、"上"がついてます」
"上"というのは、衛生班の古参だろう。
地面に張ったテントの布地が、夏陽に白々と照らされていた。梢の払われた辺りはひらけ、明るく、のどやかに静まっている。
ザイは苦々しくテントを眺め、懐に突っ込みかけた手を止めた。かたわらのミックを振りかえる。
「そういや、カルロの旦那はどうした」
カルロは衛生班の班長だが、駐屯地に駆け込んだ時には、姿がなかった。それでやむなく、勝手に班員を連れ出してきたのだ。
不在の指摘が非難めいて聞こえたか、ミックはばつ悪そうに頭をかいた。「──ああ、なんかいないんすよね、このところ」
「へえ。"ずっと"ってことか?」
煙草をくわえかけた手を止めて、ザイは面食らった顔でつぶやいた。ここカレリアは開戦国、しかも、当事者の一方であるラトキエ領家の膝元に、武装した部隊を近接させている。班を仕切る長というなら、神経をすり減らしていて然るべき時だろうに。
「あれで頭でも打ったんじゃねえだろうな」
「で、ふらふら、どっかを徘徊してると?──よしてくださいよ」
衛生班の班長カルロは、ウォードが野営地を脱走した晩、たまたまテントの横を通りかかって、ウォードの番を押しつけられた。そして、テントから勝手に出て行くウォードに吹っ飛ばされて気絶した、という事情がある。
ミックは嫌そうに顔をゆがめた。「班長はぴんぴんしてましたよ」
「だよな。あれしきのことで、どうにかなる、なんてこたァねえか」
ザイは釈然としない顔つきで、煙草の先に点火した。商都のある東方に、何気なく視線をめぐらせる。「なら、頭(かしら)がヤサを空けてるのをいいことに、どっかで羽でも伸ばしてんのかね」
「俺らも実は困ってるんすよね。どこに行ったか誰も聞いていないんで」
「こんな時に放っぽり出して、しょうがねえなあの人も。俺だって、話通さなきゃなんねえのによ」
他班の部下を借りるなら、まずは長に了解を得るのが筋である。
「でも、丁度よかったじゃないっすか」
「なんで」
「できれば会いたくなかったでしょ?」
ザイは忌々しげに舌打ちし、ふい、と視線をよそにそらした。
「そんなこたねえよ。ちょっと反りが合わねえってだけだ」
事実ザイは、カルロが苦手だ。衛生班を取りまとめる長には、普段から近寄りたがらない。一日の大半を共にする同じ隊の隊員ならば、そうした場面は大抵の者が目にしている。
苦虫噛み潰した横顔を、ミックはやれやれと眺めていたが、ああ、と合点したように目を向けた。
「そういや、なんか似てますもんね、胡散くさそうなところとか」
「──なんで言うかね、本人に」
「裏で頭(かしら)苛めてるって、もっぱらの噂ですよ?」
んなわけねえだろ、と小さく吐き捨て、ザイは溜息まじりに振りかえる。「正直なことで結構だ。だが、時と場合によっちゃ美徳じゃねえぞ」
「ザイさんが言っても説得力がないっすね」
確かに、歯に衣着せぬザイの言は、大抵の隊員は知っている。とはいえ、恐いものなしの無遠慮は若さゆえの特権だ。ザイは苦笑いした。
「俺んとこ来るか、正直者」
ミックが顔を引きつらせて身を引いた。「……悪の道に引っぱりこもうってんですか?」
「人聞きが悪いな。大体、悪だの善だのは見方によるだろ」
「なんで、急にそんなことを?」
ミックは及び腰の上目使いで、恐々顔色をうかがっている。
「──近々空きが、出そうなんだよな」
まぶしそうに目をすがめ、ザイは夏の空を仰いだ。
そこには、果てのない天蓋があった。真昼の太陽がぎらついて、薄青の空と白い雲、ただそれだけが広がっている。
鳥が梢を叩く音。仲間のものだろう遠い声。どこかで密かに草の鳴る音──
ふと、ザイは我に返った。
ミックが怪訝そうに立っている。しばし、風に吹かれていたらしい。軽く嘆息、煙草をくわえた。「──お前の特技は面白そうだ。ほら、ザルトの辺りでやって見せたろ、"赤狼の遠吠え"って奴。ああいうのが一人、いてもいい」
ミックは元獣使いだ。ロムに転属する前は、様々な動物を扱っていた。
「毎日、怪我人の世話だけじゃ、お前も辛気臭くて退屈だろ。念願のロムになったのに」
よほどの力量がない限り、転属は通常認められない。稼業の下地がないからだ。ロムは生死に関わる荒仕事、所属している隊員は、相応の修練を積んでいる。
もっともミックの場合には、上役となった短髪の首長の「面白そうじゃねえか」の一言で決定したという噂だが。そう、たぶん言ったに違いない。『まあ、いいじゃねえかよ、様子を見ようぜ。こいつは俺が引き取るぜ』
「そうすね。でもまあ、俺は──」
ミックはそわついた様子で言葉を濁し、後ろ頭をもじもじ掻いた。
「どっちかっていうと、副長のそばの方が」
一瞬、話が飲み込めず、はたとザイは思い出した。ミックがロムに移籍を希望した動機、ならびに特徴的な性向を。そういえば、このミックについて、特務の面々が無駄話をしていた。副長にこっぴどく振られたとかなんとか──
くるりとミックを振り向いた。
「今の話はナシってことで」
「はあ? なんでまた急に」
問答無用の撤回に、ミックはぽかんと訊き返す。ザイは切りあげるように手を振った。「大事な部下を、そうそう食われちゃたまんねえよ」
「言っときますけど、タイプじゃないすよ?ザイさんたちは」
男はほら、美しくなくっちゃ、とミックは大真面目で指を振る。"あのつれない副長のように"
いささか呆れて拝聴し、ザイは背後の樹幹にもたれた。動きのない件のテントを、持て余したようにながめやる。「へえ。そいつはありがたい。にしても、あっちはどうしたもんだかな」
中は恐らく修羅場だろうが、物音一つ聞こえてこない。ミックも同様に目を向けて、渋い顔で腕を組んだ。「傷はふさぎましたが、いつまでもつか。つか、何者なんすか、あの女」
「何者ってのは? クレスト領家の奥方だろ」
「いや、そういうことじゃなくってね。──なんか変すよ、あの女。だって怪我のすぐ上に、なんだって包帯巻いちまうんだか」
「──どういう意味だ?」
「だから、処置してないんすよ。包帯まで巻いたのに、肝心の傷は放ったらかしって、そんなことをしますかね」
喫煙の手をふと止めて、ザイは唖然と見返した。
「つまり、縫合していなかったってのか? なら、怪我の程度が浅かったとか」
「いや、ばっさり骨までいってますって。即死じゃないのが不思議なくらいすよ」
「それで、何もしていない?」
ミックは深々と嘆息し、腕組みで投げやりに首を振った。
「いっそ死んじまえれば楽なんだろうけど。──なんて言ったらいいんすかね、そっちに行きかけちゃ、あわててこっちに引き返してくるって感じで。ああなると、いっそ不憫って話すね」
「……死に切れねえってことか」
死にかけると回復する──ザイはいぶかしげに口を閉じ、思案顔で顎をなでた。
「まあ、回復力が高いってのは、ここじゃ、さほど珍しくもねえがな。隊長もそういう体質らしいし、副長なんか、領邸で刺されて間もねえってのに、外で客とじゃれてたぜ」
「……又すか?」
ミックが露骨に顔をゆがめた。
「あの二人、なんか、いつも一緒すね。副長も、仕事で嫌々しょうがなくとはいえ」
ちっ。役得だなあの女……と面白くなさげにぶちぶちごちる。ザイはぽっかり紫煙を吐いた。「まったく、仲がいいってのか、過保護ってのか」
そういや、二人はいつも一緒だ。あの女嫌いの副長が、ずっと客をなで回している──
「……伝染ったのかね」
なんすか? と見返したミックと目が合い、ザイはゆるゆる首を振る。
「んなわけねえか」
首の後ろをとんとん叩く。
「……疲れてんのかね、俺も」
ミックがそわそわ道の先をながめた。「──そんなことより、まだですかね、副長は」
「本部に知らせは、やっている。隊長も副長も、その内くんだろ」
「でも、そうなると、まずいすよねえ?」
「なにが」
「だって、とうに手遅れですよ。あの人、領家からの預かり物でしょ。それを、目の前でむざむざ死なせたとあっちゃ」
あ? とザイは動きを止めた。
絶句でテントを振りかえる。何故かそうした可能性を丸々排除していたが、確かに彼らが知ったなら──。
樹幹にげんなり頭を預けて、ザイは空に紫煙を吐いた。
「……こりゃ、夜逃げの支度でもしますかね」
廊下で行き会った蓬髪の首長は、その知らせを聞くやいなや、血相変えて駆け出した。だが、代理の居室も隊長の部屋もがらんと薄暗く静まりかえり、二人の不在を告げている。
商都に急ぎ舞い戻ったジョエルは、異民街にある本部の廊下を長の部屋へと急いでいた。
一段飛ばしで階段をのぼり、件の扉に手をかける。
「よう、どうした。そんなにあわてて」
不意の声に振り向けば、そこにいたのはコルザだった。白髪の入り混じった頭とひげ、引き締まった頬、いかめしい双眸。バパ隊最年長のこの男は、首長の参謀役というところ、首長の留守中、代わって隊を預かっている。今日は定時報告にでも来たのだろう。
コルザは急いた様子をまじまじながめ、顎の先で扉をさした。「ああ、頭(かしら)なら、いねえぞ」
「──そうすか」
虚をつかれ、ジョエルはノブから手を離した。
脱力して上体を折り、汗ばんだ手を両膝におく。今朝まで伏せっていたあの首長は、体がようやく楽になり、さっそく遊びに出たらしい。
走りづめらしいその様を、コルザはつくづく眺めやった。
「いつもふてぶてしい発破師が、そうまでおたつくとは、よくよくのことだな」
伏せたジョエルの頭をつかんで、そのまま、ぐりぐり平手でなでる。「──ああっ、もう! ガキじゃないんすからっ」と頭を振りあげたジョエルの顔に、にっと笑って片目をつむった。
「ほれ、坊主。話してみろよ、聞いてやるから」
気を悪くした風もなく、ジョエルは真面目に目を向けた。
「実は今、北門出た先の"西の森"で──」
コルザが隊員を子供扱いするのは、今に始まったことではない。むしろ、自隊の隊員ことごとく、己の息子と思っている節さえある。そして、当の隊員らにしても、このいかめしい眼をした往年の戦士を父のように慕っている。短髪の首長がああも気楽でいられるのは、威厳と親しみを兼ね備えた、彼の存在が殊の外大きい。
コルザは眉をひそめて報告を聞き、白髪の混じった顎をなでた。「──へえ、そいつは大ごとだな」
「じゃ、外捜してきますんで。俺はこれで失礼します」
一礼し、ジョエルはせわしなく踵を返した。見る間に、その背は廊下を曲がり、階段の先に、姿が消える。
階段を駆け下りる靴音が、のどかに静まった館内に響いた。
無人の階段の踊り場で、コルザはそれを見送ってしまうと、踊り場の先にある向かいの廊下に足を向けた。
「だとさ。どうする?」
コルザが声をかけた先──木箱が積まれた向こう側、廊下に置かれた長椅子に、男が足を組んで寝そべっていた。日向ぼっこしていたのは中年の男、額や手足には、まだ新しい包帯が巻かれている。
「──やれやれ。又、お姫様かよ」
体の痛みに顔をしかめて、バパが寝そべった体を引き起こした。包帯の巻かれた短髪をうなだれ、思案するようにうなじを叩く。「……まったく寿命が縮むねえ」
「死にかけたのは何度目だ? 二度目、いや、三度目か。野営地の時と、レーヌに漂着した時と。だが、斬られたってんじゃ話が違うな。なんとか助かりゃいいんだが」
コルザは深刻な顔で腕を組む。「それにしても"今"とはな。なんで悪いことってのは重なるのかね」
まったくだ、と嘆息し、バパは大儀そうに立ちあがった。
「悪いな、コルザ。そっちは頼む」
ござの上に座りこむ露店商に入り混じり、ケネルは路地裏の石壁にもたれていた。
昼の街角から顔を出し、通りの気配をそっと探って、辟易したように背を戻す。
「──まったく、いつにも増してしつこいな」
足元にすり寄る野良猫に気づいて、目の高さに抱きあげた。
猫の顔を真正面からじっと見て、「お前、腹へってないか?」と話しかける。
「俺もなんか、腹減ったよ」
にゃあ、と鳴いたその猫を、あぐらの膝に抱えこみ、よしよしと頭をなでてやる。「……なんか食いもん、なかったかな」と上着の隠しをごそごそ探った。
わいわいがやがや、街人行きかう昼下がり。
猫が膝で、にゃあ、と鳴いた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》