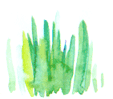
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 11話2
( 前頁 / TOP / 次頁 )
どういたしまして、とおどけて笑い、セレスタンはマッチを吹き消した。
「なんで、お前がここにいるんだ?」
静かな建物の裏口を、セレスタンは振り返る。「留守番、仰せつかっちまいましてね、ここの色男の先生に。で、表の店で寝ていたら、裏で戸が開いたんで、ひょっとして隊長が起きたかな、と」
「お前もここまで同行したのか? だが、特務は森で、テントを撤収していたはずだが」
「──ああ、昨日は俺、別行動でしてね」
セレスタンは苦笑いし、北門のある西の方角を振り返る。
「街に戻ろうと思ったら、向こうの首長があわてて馬走らせてくとこ見たもんで。なにかな〜と思いましてね。そうしたら皆さんおそろいで。──で、どんな様子すか、姫さんは」
「熟睡中だ。ぴんぴんしてる。ふとんに絡まって格闘している最中だ」
「……へえ? 確か死にかけてましたよね?」
ぽかん、とセレスタンは口をあけ、不可解そうに小首をかしげる。
「あの医者、評判通りの腕らしいな」とケネルは紫煙を吐きながら、後ろで首をかしげている禿頭の顔に目をあげた。「ちょっと出てくる。念のため、しばらくここを頼めるか」
「了解、隊長。店主も戻る頃合ですし」
肩先から覗き込み、セレスタンはいたずらっぽく片眉をあげた。「隊長が留守の間に、姫さんに襲いかかったら、どうします?」
きょとん、とケネルは瞬いた。
呆れた顔で、つくづく見返す。「お前に強姦できるわけがないだろう」
ふっ、とセレスタンは困ったように微笑った。
「──お見通し、ってことっすか」
拳を顎に当て、くつくつ笑っている。
呆気にとられてケネルは見やり、いささか憮然と付け足した。「それに、廊下でアドルファスが寝ている。わめき声のかけらでも、叩っ殺されるから、そう思え」
「……さいですか」
ひくり、と頬を引きつらせ、セレスタンは降参の両手をあげた。「了解、隊長。肝に銘じておきますよ」
「それはそうとセレスタン、つかぬことを訊くが」
いく分そわつきながら話をかえて ケネルは顎をつき出した。
「俺を運んだのはお前だよな?なっ?」
「なんだってそんなに必死なんです?」
セレスタンは小首をかしげ、あーなるほど、と禿頭を掻いた。合点顔で背を起こし、裏庭に視線をめぐらせて、やれやれと腕を組む。
「そんなに嫌すか。調達屋の馬は」
「まさかそんなはずがないだろう」
ケネルは即答。棒読みで。口が裂けても言えない立場だ。
へら、とセレスタンは己をさした。
「安心していいっすよ。俺すから、運んだのは。ええ、ここまで、きっちりと。だって、大切な隊長すもんね」
……んん? と固まったケネルをしり目に、セレスタンは背もたれに腕を置き、ずい、とケネルに身を乗り出す。
「隊長、俺はね。あんたのことが大好きですよ」
げほっ、とケネルは咳きこんだ。
──な、なんだ、いきなり、とゲホゲホしながら、後ずさりつつ、ひるんで見あげる。
「冗談だよな?」
「まじっすよ?」
後ずさった分だけ肩を進めて、セレスタンは情けない顔で小首をかしげる。「ええー? 隊長は嫌いすかー? 俺のこと」
しどもど、ケネルは目をそらした。「──悪いが、俺には男色の趣味は」
「はい?」
本日二度目の、どよん、とよどむ微妙な空気。
転げ落ちそうにのけぞったケネル。ぱちくり瞬き固まったセレスタン。しばし、無言で見つめ合い──ぽりぽりセレスタンが禿頭を掻いた。
乗りかかった背を起こし、そそくさ裏口に踵を返す。
「んじゃ、姫さんとこ行ってきまさ。店の戸締りしてきますわ」
隊長はどうぞ、ごゆっくり〜、とぷらぷら背中で手を振って、裏口の戸を開け、入っていく。鼻歌まじりで。
唖然とその背を見送りながら、ケネルはどぎまぎ首をかしげた。
(……今、絶対、遊ばれたよな?)
今のは一体なんなのだ? そもそも、セレスタンが「大好き」なのはファレスの方ではなかったか? やり返せないのをいいことに、死に損ないのファレスをかかえて頭をなでくりまわしていたし。そもそも、どういう心境の変化だ。そう、あのチャラい
丸眼鏡は。
しかも、黄色。
明らかに浮ついている。
気味が悪いほど上機嫌だ。だが、それでいて妙に真剣で、必ずしも冗談とばかりも言い切れないのが微妙なところ……。
呆然と絶句したその肩に、じりじり日ざしが照りつけた。
晴れわたった青空、真夏の日ざし──ああ、とそれに気がついて、襟首をつまんでパタパタしつつ、ケネルは空を仰ぎやる。
「……夏場にハゲはきついよな」
さえぎる髪が皆無だから、強い日ざしが脳天を直撃。
暑さにやられたか、と釈然としないながらもつぶやいて、ケネルはこきこき首をまわす。
もっとも、セレスタンはファレスの機転で九死に一生を得たことがある。つまりは命の恩人だ。その彼が甦生したなら、多少過剰に喜んでも無理からぬところと言っていい。特殊な性向は、たぶんあるまい。そうだ、あの時ファレスにしたように頭をなでくりまわしそうな勢いだったし。あの親しげな笑顔の中にいやに切なげなものを感じたが、どこか慈しむような今の視線は、昨日、森で例の新入りから向けられた、ねっとり悩ましげな目つきとは違う。ならば、今のは額面通り──
「……俺、あんがい慕われてんのかな?」
ぽりぽり、ケネルは頬を掻く。
なんとなく釈然としないが、首をかしげつつ身を戻した。背もたれに両腕をもたせかけ、脱力しながら一服する。
ふんわり、風が頬をなでた。
じりじり肩を焼く夏の日ざし。ぼんやり見やった屋根の上には、澄んだ青空を背景に、入道雲が輝いている。
指の先で紫煙をくゆらせ、ケネルは長く息を吐いた。
「……着いたな」
商都カレリア、闇医師の診療所にいた。この行程の終点に。
あとは彼女の回復を待ち、商都の北区画に居を構えるクレスト公邸に引き渡す。それで全てが終了だった。昨日、瀕死に陥った時には、最早これまでと覚悟もしたが、なんとかここまでたどり着いた。そう、辛くも彼女は助かった。
「──夢の石、か」
煙草をはさんだ自分の利き手を、得体の知れぬもののように眺めやる。
この手は確かに、あの時、奇石を発動した。だが、そうした力は、彼女にはない。
だが、彼女でないというのなら、ファレスが生還したのは何故なのか。
その答えは、とうに出ていた。
決まっている。ファレスは自力で生還したのだ。なぜなら奇石は、あの日、北カレリアで彼女が負傷して以降、常に稼動していたからだ。
背中の傷は、凍結された状態だった。どんな痛打も受け付けず、縫合してさえ元に戻る。つまり、彼女は四六時中、常にその気を帯びていた。その滞留した気を流用し、ファレスは己を修復していた。だからこそファレスだけは、何度でも死地から生還する。崖から海に叩き込まれ、全身を激しく打ちつけても、時化の激流をかいくぐり、沖合の孤島に打ち上げられても満身創痍で生き残り、腹を刺され致命傷を負って尚、瀕死の縁から生還した。
そうした奇石の効用にファレスが気づいたきっかけは、あの晩に治した腹痛だろう。彼女の差し入れのサンドイッチで腹を壊したあの晩に。
あの時ファレスは、「手当て」と称して彼女が触れた手の平から、彼女の体に滞留していた奇石の気を奪いとり、己の腹を修復したのだ。それは恐らく偶然の産物、意図せぬ僥倖だったろう。呻吟する苦痛の中、無我夢中で
"それ" をつかんだ。
そうして、ファレスは見つけてしまった。どんなに優れた薬にも勝る、すこぶる有用な鉱脈を。あの奇石の真価に触れ、本能が感じとったに違いない。これは使える、と。
そして、本能は味をしめた。生傷の絶えぬ傭兵稼業では、そうした装置は利用価値がすこぶる高い。偶然見つけたその「技」を、体が速やかに取り込んだのは、むしろ当然の成り行きだったろう。そう、紙が水を吸いあげるがごとくに。
やがて、何度もくり返す内に、彼女の体がほんの一部でも触れさえすれば、奇石の力を作動できるようになった。本人はいたって無自覚に、そして、まったく無意識の内に。
そもそもファレスは、赤の他人に大人しく癒されてやるような、やわで女々しい男ではない。有益な要素は自力でぶん取る、そうして今日まで生きてきた男だ。彼女に癒してもらうどころか、むしろ、彼女を修復していたのも、あるいはファレスだったかも知れない。そう、恐らくは無意識の内に。
だが、なぜ、そんなことが可能なのか。
奇石の力をファレスとケネルは行使でき、あの彼女には行使できない。これらが示す共通項は何か。彼我の間を隔てるもの、二人は持つが彼女は持たない決定的な違いは何か。
結論は出ていた。
" 血 " だ。
常人のそれとは異なる血が、二人の体には流れている。
ファレスを見舞った宿屋の主に、正体を突きつけられたはずだった。「世の理の外にある者──禁忌の者」の末裔であると。
それは、およそ、こんな話だ。
かつて、北カレリアの森にいた「青い髪の民族」は、自らを「翅鳥」と総称し、「ここは本来居るべき土地ではない」と、かの亭主セヴィランに語った。世の秩序を損ねぬために、土地の者とは関わらないのだと。
だが、厳しく戒めてきたにもかかわらず、翅鳥と現地の異性との間に、事もあろうに「禁忌の子」が誕生してしまった。いわゆる「二つの世界の合いの子」が。そして、「禁忌の子」は案の定、親の能力を凌駕する恐るべき力を持っていた。出現を恐れられていた通りに。
「──そうか、だから、あの男は」
凝視の視線をふと逸らし、ケネルは腹立たしげに舌打ちした。
ようやく、そこに気がついたのだ。ケネルの父が、彼女の奇石を狙う理由に。
彼はいわゆる「禁忌の子」、桁外れの存在だ。ケネルに行使可能な奇石なら、作動できて然るべき、むしろ、あの彼の方が、よほど楽々と扱うだろう。
もっとも、奇石を欲する動機は、ろくなものではなかろうが。
世俗的な物欲など、あの男には既にない。そもそも奇石に頼らずとも、自力でなんでも調達できる。なにせ、投げた視線の一瞥で、相手の意識を奪える男だ。金も名誉も今更だ。
あの男が欲しいのは、強行しても手に入らぬもの──つまるところ、人の「心」だ。
そう、その魂胆は読めていた。つれない息子をなつかせたい、あわよくば、思い通りに動かしたい、大方そんなところだろう。だが、そうは問屋がおろさない。
かつて、無視を決め込んでいたあの父は、「戦神」の名を獲得すると、手のひら返したようにすり寄ってきたが、迎合する気はケネルにはなかった。あの男に誠意はない。多忙を理由に見殺しにされた母の例をひくまでもなく、気が向けば猫かわいがりし、飽きれば捨てる、勝手な男だ。
あの男は恐らく、あの時気づいてしまったのだろう。奇石のもつ絶大な力に。戦時下のノースカレリア、彼女が櫓(やぐら)に立った時、噂の奇石を面白半分に発動して。
そういえば、当時、街で妙な騒動があった。それによって敗色が一変、攻めに転じる契機ともなった。十中八九あの男の仕業だ。当時ケネルは街におらず、何が起きたか見てはいないが、彼が奇石を行使したなら、さぞ壮絶な異変が起きたろう。なにせ、その行使者は、常人には及びもつかぬ「禁忌の子」だというのだから。
二世界の狭間に産み落とされた、この「合いの子」の存在を、世界は予定しておらず、「予定された規格」の中に、彼らの振幅は収まらない。それほどの力だ。そして「禁忌の子」の能力は、その血脈の子孫にも、発露の程度の差こそあれ、密かに受け継がれているはずだ。
あの父とケネルとファレス、そして、あの彼女との違いは、まさにその一点にある。彼らにあって彼女にはないもの、つまり、共通項は「翅鳥の血」だ。そう、
──奇石「夢の石」は「翅鳥の血」に反応する。
だが、それでも疑問は残る。
それならば、彼女の背中を凍結していたのは誰なのか。
ケネルではない。ファレスでもない。無論、あの父でもないだろう。ならば、考え得る可能性はひとつだ。
「──もう一人、いる、か」
晴れた夏空を、ケネルは見つめる。
あのクロウの報告によれば、傷は意外にも浅かった。背中の傷の深さは丁度、刃が入ったその直後。察するに、アドルファスの刃は振り抜かれておらず、傷口はその状態で固まっていた。それが突如、昨日の森で、振り切られた。つまり、その行使者は、患部の時を止めていた、ということになる。
だが、あの奇石を行使するには、要求に見合った力量が要る。実際に奇石を行使したケネルは、それを肌で知っている。
ケネルは、傷の修復を命じただけで、ただの一度の奇石の行使で、意識が混濁するほどの消耗をきたした。まして「時を止める」など論外だ。継続的に稼動するには膨大な精力が要るだろう。
だが、現実に、背中の傷は凍結された状態だった。つまり、彼女が負傷して以降、奇石は継続的に稼動していた。発動した状態を一月近くも維持するなど、並大抵の力ではない。むしろ、ヒトの領域ではない。いわば、この世の者ではない。
結局、ケネルにできたのは、現状維持に留まった。
彼女を生死の境に留めおく、それだけのことで、もてる体力を使い果たした。まして、傷の消去など及びもつかない。だからこそ自力での救命を断念し、要求をかくのごとく変更したのだ。
──治せる者を連れてこい、と。
坑道に現れたのは、あの男だった。
かねてより手配していた噂の闇医師。そして、背を向け患者に向かった医師は、彼女を死の縁から引き戻した。奇石に要求した文言通りに。
もっとも、どんな治療が施されたのか、ケネルは見届けることはできなかった。監視のために居残ったものの、彼女の治療が始まった頃には、意識を手放しかけていたからだ。だから、あの光景は、せっぱ詰まった願望が見せた、夢まぼろしであったかもしれない。
それは、この世のものとは到底思えぬ、まばゆくも奇妙な光景だった。
彼女にかがんだ闇医師の背から、鮮やかな緑焔が立ちのぼったように見えた。体全体をつつんだ揺らぎが、まばゆい白光となって噴きあがったかのように──
建物の中から、物音がした。
バタン、と扉が開く音──店の方の戸締りを済ませ、セレスタンが個室に着いたのだろう。
「──そろそろ、行くか」
煙草を足元に投げ捨てて、吸い殻を踏み消し、立ちあがる。
体の凝りをほぐして軽く伸びをし、セレスタンが入っていった建物の裏口をながめやる。裏庭に降りそそぐ、夏の日ざしがうららかだ。
"日常"に戻ってきていた。
ついに駄目かと観念したのに、一夜あければ、ここにいた。行程の目的地、闇医師の診療所に。
北カレリアから商都まで、本来ならば四、五日の行程。長くても十日かかるかどうか、当初はそう踏んでいた。ところが、いざ出立すれば、客が体調を崩したり、賊の襲撃を受けたりと予期せぬ不都合が頻発し、思わぬ難儀な行程となった。そして、ついには崖から転落したと聞かされて、客の死亡も覚悟した。というのに、結局こうしてたどり着いてしまった。あたかも予定調和であるかのように。
「──いや」
ケネルは苦笑いで首を振る。
そうではない。転機は、あの夢の石だ。時間切れの坑道で、追いつめられて自棄になり、奇石に苛立ちをぶつけなければ、今この時の平穏はなかった。奇石が発動しなければ、今見ている風景も大分違っていたはずだ。そもそも、こうして見ている景色自体あったかどうか、はなはだ怪しい。
そうだ。夢の石が転換点だ。
行使者の要求に沿うように、奇石が未来を都合して、あの闇医師を連れてきた──
知らぬ間につめた息を吐き、ケネルは後ろ頭を掻いて、建物の屋根を仰ぎやる。
「──もう、どうでもいいことか」
それもこれも済んだ話だ。ここが終点。この先は、ない。
軽い溜息で、歩き出す。
つまり、これで自由放免。あの彼女のキイキイ声がもう聞けなくなるかと思えば、いささか寂しい気もするが、これでもう後腐れなく──
ぴくり、とケネルは足をとめた。
「……後腐れなく?」
顔から血の気がザッと引き、口をあけて愕然と固まる。そう、そういえば、奇石を発動する前に、とんでもないことを口走りはしなかったか──
「……。今さら、どうにもならない、よな」
どんより、ケネルは頭をかかえた。泥酔した翌朝に、ベッドの隣で眠りこむ見知らぬ男に遭遇し、頭をかかえる婦女子のように。
あの時は、後がないと覚悟した。だから、後先考えず、思いつくままに口にしたのだ。だが、いくら自暴自棄になったとはいえ──
それは、不可思議な強制力をもつのだという。
予定された軌道をねじ曲げ、その内容に沿うように、未来を歪めていくような。当人や周囲の努力の有無に関わらず。
呆然と見下ろした視線の先には、昨日と変わらぬ我が手がある。
ケネルは途方にくれて嘆息した。
「……誓いを、立てちまった」
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》