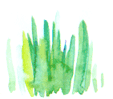
■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 11話5
( 前頁 / TOP / 次頁 )
ぼんやり霞んだもやの中に、あの黒い蓬髪が見えた。
半袖の綿シャツが張り付いた、見覚えのあるたくましい背、蓬髪のかかるいかつい横顔──
そう、あれはアドルファスだ。戸口で誰かと話している。相手が誰かは陰に隠れて分からないが、例の上着を着ているから、部下からの報告を受けているのだろう。無精ひげをしごきつつ、じっと話を聞いている。いつにもまして厳しい顔つき。
頬に憔悴の影があった。
一気に十歳ほど老けこんでしまったような。一体何があったというのか。嫌な事件でも起きたのだろうか。
難しい顔で黙りこんだ首長は、やがて、部下の頭に手を置き、薄暗い戸口を出て行った──。
ゆるい風を頬に感じて、次に薄目をあけた時には、明るい窓辺が写りこんだ。
くりっとした茶色い瞳が、遠い夏空を睨んでいた。
だが、ほんの少し眉をしかめた、どこかうつろなその視線は、心ここに在らずの風情だ。
くりっとした大きなまなこ、短く刈った茶髪の丸刈り、襟足の一房だけが少し長い。窓枠に寄りかかった半袖の肩に、陽射しが白く当たっている。
彼は窓に腰かけて、ぼんやり空を仰いでいた。
綿の半袖から小麦色の腕が伸び、放り出したその手は腿の上。ゆるく開いた手の平で、スズメが二匹、せわしなくパン屑を突いている。だが、彼の意識は彼方をさまよい、それにも気づいてないようだ。手首には古びた紐が、ゆるく結わえつけられている。あの紐は確か、まじないだとか、願掛けだとか、お守りだとか、そうした類いではなかったか。
シャツの裾は出したまま、床から浮いた靴先を頓着なく垂らした様は、小柄な体格とも相まって、反抗期の少年を思わせる。手の届かない遠い空に、どんな思いを馳せているのだろう。ぼんやり仰いだ透明な瞳で。まるで無防備な素の顔で。
あの言葉がよみがえった。
森で聞いた昔話。身を切るような彼の告白──。そうか、見ているのは"思い出"だ。あの窓辺の彼もまた、かけがえのない家族を失ったのだ。いたずら盛りのあの頃に。取り返しのつかない過ちで──
ふと、横顔が振り向いた。
「──起きたか」
とん、と窓辺から飛びおりて、つかつか寝台に歩いてくる。
ぱっちりとしたドングリまなこと髪のない丸い輪郭、丸いパーツ同士の取り合わせは、どこか猫の顔を思わせる。
あやふやな夢の余韻が吹き飛んで、エレーンはあたふた上掛けのシーツを引っかぶった。
「な、なんで、いんのっ? あんたがここにっ?」
あァ? とこちらをすがめ見たのは、三バカの一人、イガグリだった。名前はボリス。
そういや、あの三バカとは商都の門前で別れたきり、今日の今日まで完璧に忘れ果てていた。それが、なにゆえ、今になってやってきたのか。
商都までの同行を無理強いし、あげく無断でトンズラした己の仕打ちを思い出し、エレーンは冷や汗たらたら青くなる。つまり、奴は
──あの時の文句を言いにきたのか?
ボリスはたるそうに足を止め、ドングリまなこですがめ見た。
「俺がいちゃ、悪いかよ」
ぱちくり、エレーンはまたたいた。意外にも穏やかな反応だ。
どつかれそうな気配がないのを、遠巻きに念入りに確認し、そろそろシーツから顔を出す。「てか、ここどこ?」
「ああ、気絶してたから知らねえか」
ボリスは壁にもたれて腕を組む。「五番街の診療所、ま、表向きは斡旋屋だけどな」
「なんで、あたしがそんな所に?」
エレーンはそろそろ布団に正座。そういや、いつの間にか寝巻き姿だ。旅で着ていたふわふわの白。
「昨日、こっちに運び込まれたんだよ。なんでも傷がひらいたとかなんとか」
ふーん? ともそもそ背中に手をやる。なんか、ちょっと、かゆい気がする。いや、背中は確か、森で斬られたのではなかったか? そうだ、てっきり死んだと思った。けれど、背中はちくちくするだけで、死ぬほど痛いわけでもない。なら、あの激痛は夢だったとか?
まさか。
釈然としない思いで、首をかしげる。意識した途端むずがゆくなった背中を、何気にぽりぽり掻きながら、壁のボリスに目を戻す。「あ、ねえ……あの、ケネルは?」
くい、とボリスは親指を立てた。
「隊長なら、呼び出しがきて本部に戻った」
「う゛っ──あ、じゃ、じゃあファレスは?」
「いなかったぞ、副長なんか」
「──あっ──あっそう……」
そっけなく返されて、エレーンはばつ悪く引きつり笑った。なによ、案外薄情じゃん。診療所に運び込まれるくらい重体なのに。お陰で気まずく二人っきり。
もっとも、身の置き場のない手持ち無沙汰は、敵も同じであるようで、ボリスは無闇にガンくれながら、目つきの悪い不良のごとくに、うろうろ部屋を歩きまわっている。
枕元のそれをちらちら見やって、エレーンは手慰みにとりあげた。
目覚めた枕元に、なぜか置いてあった黄色い房。そう、浮かんでは消えた意識の端で、この黄色がゆれていた。ふわふわ、ゆらゆら明るい黄色。なぜ、こんなミモザの花が、枕元にあるのだろう。昨日の祭の名残りだろうか。つまりは "幸せのおすそ分け" ? でも、それなら一体誰からの? まさか、あのイガグリじゃ──?
「……ねー。もしかして、これ、あたしにくれたりするー?」
まさかとは思うが、一応訊いた。念のため。
あァ? とドングリまなこが振りかえる。
「そこにあったぞ。初めから」
やっぱ、そーよねー、あるわけないしぃ、とエレーンは所在なげにミモザをまわす。奴が贈り主であるわけがない。むしろ、
(なんでいるわけ? イガグリが?)
起きた途端に、謎で一杯。
そわそわ居心地悪く首をかしげて、むぎゅうぅ、と枕を抱きしめる。ふと、思い出して顔をあげた。
「あっ、ね、ねえ? さっき、あたしの熱はかってくれた?」
手のぬくもりを感じたのだ。額をおおう手の平の。
壁のシミにまでガンくれていたボリスが、眉をしかめて振り向いた。
「しらねえぞ、そんなの」
言うなり、何かをためらうように視線を外し、思い余ったように目を戻す。「──なあ、おい。もう気にすんなよ、ガキのことは」
ぽかん、とエレーンは見返した。
なによ急に、と見ていると、ボリスはもどかしげに舌打ちする。「北門通りで、昨日ガキが死んだろうがよ」
「──それって、もしかしてケインのこと? てか、なんであんたが、ケインのこと知ってんの?」
ボリスはそわついた顔で肩を揺すり、頭を掻いて舌打ちした。「いや、あのガキのことで気に病んでるから、慰めてやれってバリーがよ」
「バリー?」
思わぬ名前が飛び出して、エレーンはぱちくり瞬いた。
「なんで、あの人がそんなことを? てか、ちゃんと逃げられたんだ、あっちの道で。あ、ねえ、今どこ? あの人」
「──なんでだよ」
実に心底嫌そうな顔で、かったるそうにボリスはすごむ。
寝巻きの膝を、エレーンはかかえた。「昨日、あの人、あたしに色々言ってくれてさー。それで、あたし、気が軽くなった、みたいな? だから、やっぱ一応、お礼とか? 言っとかなきゃなんないでしょう人として。てか、今どこ」
ボリスは鬱陶しげに舌打ちし、茶髪の丸刈りをガリガリ掻いた。「今は詰め所だ、大通りの。ブルーノとジェスキーがそばについてる」
あー、あれね、あいつらね、とエレーンは上目使いで思い出す。「金魚のフンのあの二人かー……」
「誰がフンだ誰がっ!」
がなる相手を完全無視して、ひょい、とエレーンは振りかえる。
「そうすると、あの人、怪我とかしたの? てか、詰め所ってなんで詰め所にいんの? あ、ひょっとして捕まったとか!? えええー! でもあれは、こっちのせいじゃないんだけどー。ゴロツキが勝手にあたしのこと追いかけてきてだから森まで逃げる羽目になっちゃって迷惑してんのむしろこっちてかそれってあの人大丈夫っ?」
「うぜえなっ! てめえは!」
ふるふる肩を震わせていたボリスが、ついにぶち切れ、咆哮した。
「色々質問すんじゃねえ! つか、なんでそんなに元気はつらつしてんだよっ!」
「あっ、ねーねー、その前にぃ! ひとつ言っとくこと、あんだけどー」
「──なんだよ」
気勢を削がれて、ぐっと詰まり、ボリスが前のめりで停止した。
寝巻きの膝をもそもそかかえて、エレーンは口をとがらせる。「襲わないでよ?」
「誰が襲うか妹を!」
「……いもーと?」
ぽかん、とエレーンはまたたいた。ふくれっつらで、ボリスを見る。
「なに勝手に兄妹関係成立されてくれちゃってんの?」
「しょうがねえだろ! バリーがお前を妹ってんなら、俺らにとっても、そうなるんだよっ!」
「……は? あの人が?」
ドングリまなこを吊りあげて、びしっ、とボリスは指をさす。
「今日から、お前は妹分だ。口答えは許さねえからな! いいな! てめえ! わかったな!」
「てか、あんた、たぶん年下よね?」
ひょい、とエレーンは顎を出した。「ちなみにいくつ? 十八、九?」
きのう引っ掛けられたのと、おんなじ手で訊いてやる。
ボリスが真っ赤になって地団駄を踏んだ。
「馬鹿にすんな! 俺は今年二十五だっ!」
「あ、やっぱ、いっこ下だぁ?」
ふふん? とエレーンは余裕の笑み。案の定、簡単にボリスが釣れた。見かけ通りだが、なんてちょろい。
「……お前、十代じゃねえのかよ」
ぽかん、とボリスは聞き返す。
はっと我に返って、がなり立てた。
「こういうのに年の上下は関係ねえんだっ!」
「あっそ〜お? なら、あたしも言っちゃうけどさー」
くいとエレーンは顎を出し、人さし指をぶんぶん振った。
「もー。助けにくんのおっそーいっ! かよわい妹の危機なのにぃ」
「知るわけねえだろっ!? てめえが勝手に消えたんだろうがっ!」
がなるボリスを完全無視して、くるり、とエレーンは背を向けた。
ふーむ、と上目使いで顎をなでる。奴が二十五ということは、あの姑息なクリームソーダ男、ジョエルの奴と同い年──いやいや、奴の方が断然大人だ。イガグリと違って上背あるのもまああるが、いいように手玉にとられて、クリームソーダたかられたし。むしろ、堂に入ったふてぶてしさは絶対年上だと思っていた。いや、むしろ、イガグリなら、
(ノッポ君のが頼り甲斐ある……)
驚愕の事実に、うーむ、とうなる。そう、あの十五歳の少年の方が、イガグリよりも、よっぽど大人だ。ウォードはつかみどころがないけれど、ひょろりと大きいウォードと違ってボリスがチビなのもあるけれど、体格が問題なのでは多分ない。決定的に敵わない何かが、あのウォードには確かにある。それに比べて、イガグリは……
深い溜息で額をつかんで、エレーンはゆるゆる首を振る。
(……残念)
なんか、もう、色々と。
兄貴面がむしろ痛い。
相手にされないイガグリが、がるがる後ろで睨んでいるが、エレーンは無視して値踏みを継続。ファレスのいつもの「がるがる」は、こんな生易しいものではない。
ボリスが舌打ちして背を向けた。
がなっても効果がないと悟ったらしい。今度は、卓でがさごそしている。て、なんの音だ?
「あーっ! ちょっとお!」
ふと振り向いたエレーンは、驚愕して見咎めた。
びしっと奴に指をさす。
「なに勝手に開けてんの! あたしのじゃないのそれえっ!」
うるさそうに眉をひそめて、ボリスがたるそうに振り向いた。
「いーじゃねえかよ。腹減ってんだからよ。生なら早く食った方がいいだろ」
解いた菓子折りのリボンの先が、風に乗って、くるくる回った。
一分後、寝台に広げた菓子折りに、二人は顔を突っこんでいた。
紙箱の中に入っていたのは、菓子の相場など知らないケネルが、手もみの店主に言われるがままに、買わされてきた高級生菓子。二人で箱を覗きこみ、あーでもないこーでもない、と、もふもふ、わしわし菓子を取り合い、しばし昼下がりのお茶タイム。
エレーンは指のクリームを舐める。
「つまりなに? アドがあたしのこと娘って言ったから、妹ってことになっちゃったわけ?」
「ま、要するに、そういうこったな」
あ、お兄ちゃんお茶ねん! と命じられるがままに己が淹れた茶を飲みつつも、早くも二つ目にいくボリス。エレーンも両手の菓子をもぐもぐ。
「でも、アドのこと、親父だとかなんとか言うわりに、アドにひどいことしてたじゃん」
「あ? するわけねえだろ、そんなこと」
「やったでしょー? ヴォルガっていうやつ」
むう、とふくれてボリスを見た。「あの人、あの時、アドのこと本気でやっつけようとしてたもん」
うん。あれは絶対マジだった、と腕組みで当時を振りかえる。
指のクリームを舐めながら、ボリスは次を箱の中に漁る。「親父もそろそろ、いい年だからな」
「アドはそんなに年寄りじゃないでしょー?」
「それに肩を壊してる。バリーに潰されるくらいなら、さっさと引退した方がいい」
「ちょっとお。なにそれ。そういう言い方ってないんじゃないのー? アドに一体なんの恨みが──!」
「命に関わる」
菓子を口に入れる手を止めて、エレーンはぽかんと口をつぐんだ。
「──あのなあ。俺らは命の取り合いしてんだぞ」
手づかみの菓子の崩れた残りを ボリスは口に放りこむ。「弱った体で戦場に出てみろ。ぶん殴られるだけじゃ済まねえ、殺される」
びくりと頬を強ばらせ、エレーンは絶句でボリスを見た。ボリスは頓着なく菓子をほおばる
「勲章なんだよ、名のある奴の首級ってのは。隙あらば、猫も杓子も狩りにくる。怪我してようが腹痛だろうが、そんなの一切関係ねえ。敵は一時だって待っちゃくれねえ。腕が落ちたら、それきりだ。一度でもヘマした日には、そいつにその先の未来は、ねえ」
殺伐とした話に眉をひそめて、エレーンはぶちぶち目をそらす。「──で、でも、アドは勝ったもん」
「ああ、楽勝だったな、あの時は。だが」
大きなまなこを鋭くすがめて、ボリスはきっぱりと言い切った。
「親父はもう、引き時だ」
思わぬ話に困惑し、エレーンは目を泳がせる。「で、でも、アドは……アドは、まだ……」
心は反発していたが、打ち消す言葉が見つからなかった。
そうか、だから、と心は勝手に腑に落ちた。だって現に、あの晩、肩を、
──壊している。
領邸に押し入ったあの晩に、勢いのついた軍刀を、無理に途中で止めたから。だが、身体に故障があったとて、戦場に立たないわけにはいかない。部隊を率いる長ならば。
荒くれた戦場がありありと浮かび、愕然と停止した脳裏の隅で、むっと緑がむせ返った。
追っ手たちから逃げた森。膝をかかえた大穴の隣で、辛い過去を明かしてくれた、あのさばさばとした彼の横顔。
胸が苦く締め付けられて、不意に切なく、苦しくなる。彼の健気で密かな祈りを、だが、試合の観衆は誰ひとり、知らなかったに違いない。首長に挑んだ彼の真意を。
手負いの首長に成り代わり、天下をとりたかったわけじゃない。
あの森のヴォルガの試合で、首長に牙を剥いたのは、あんなにも躍起になって彼が木刀を振りかぶったのは、どうしても勝ちたかったから。首長を無理にも引退させて、命を守りたかったから。この世の中に二人といない、自分の大切な人だから。
たとえ、卑怯者と呼ばれても。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》