( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
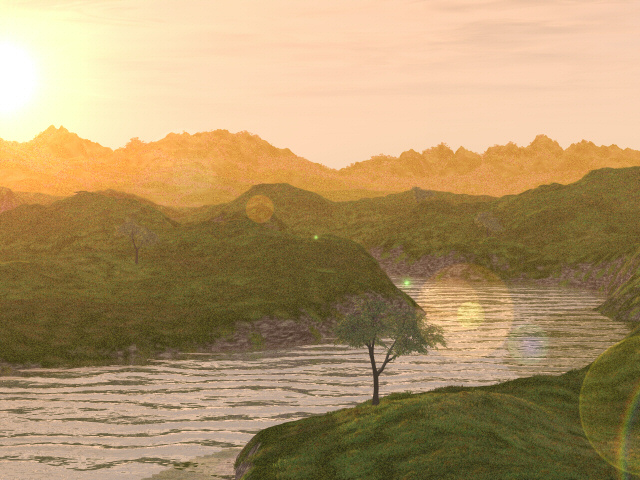
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部 opening2
( 前頁 / TOP / 次頁 )
木陰に四肢を投げ出して、ぷい、とタテガミがそっぽを向いた。
ウォードはその前にしゃがみこみ、のんびりそれをなだめている。だが、ウォードの愛馬ホーリーは、ふてくさって寝そべり、見向きもしない。
「──しょうがないなー」
ついにウォードは業を煮やして、かがんだ膝に手を置いた。
溜息まじりに立ちあがる。
「なら、いいよー」
無造作に肩を返して、荒れ野へ向かって歩き出した。「行くよー、エレーン」
「え? え、行くって──ね、ねえ、ちょっと、ノッポ君っ!」
エレーンはおろおろ後を追った。すっかり拗ねたホーリーと、ひょろりと長いウォードの背中を困惑しきりであたふた見る。「ね、ねえ、ノッポ君? でも、ホーリーがいないと、この先はちょっと──」
てか、歩いて行くのか? トラビアまで。
カノ山の荒い岩肌が、枯れ野の左に見えていた。今、ウォードが向かっているのは、西へと続くトラビア街道。ここは、その北に広がる立ち枯れた荒野だ。
待ちくたびれたホーリーは、ごろりと馬体を横たえたまま、依然としておかんむり。その様子を盗み見て、エレーンはぶちぶち文句を垂れた。
(でも、遅くなったの、別にあたしのせいとかじゃ〜……)
こっちのせい、だと思っているようなのだ。でも、そんなの濡れ衣もいいところ……
はた、と気づいて、またたいた。
(……そっか)
ほりほり頬を掻きながら、そそくさ木陰から目をそらす。それは紛うことなき己のせいだ。だって、診療所から脱出した後、
お墓参りしてたし。
ともあれ、ずいぶんなエコ贔屓だ。そばにいるのがウォードなら、別に噛もうとしないのに。なのに、こっちが近づくと、とたんに口の端もちあげて、ガンガン威嚇するのはどういう訳だ。むしろ、やきもち焼いてる勢いだ。そう、なぜかホーリーに、ライバル視されてるような気が──
はた、と閃き、木陰を見た。もしかして、ホーリーって、
(……女の子?)
あぜんと何かが氷解する。
そうだ、そうに違いない。ホーリーは寝そべったまま頭だけもちあげ、ふくれっつらでウォードを見ている。あの「もう、絶対に動かないもんんんっ!」的だだっ子のような意固地さは、妙にすんなり納得できる。うむ。幼少のみぎりより今現在に至るまで、何度あの手を使ってきたか。
ただいま絶賛ストライキ中のホーリーは、睨みながらも尻尾をバサバサ、(ほら、こっち見ろ! ほら! ほらっ!)とウォードの気を引いている。だが、秋波を送られているウォードの方は……
(……うっわ)
エレーンは溜息まじりに額をつかむ。
すんごい、つれない。
ウォードはぶらぶらと草地を出、気にしたふうもなく歩いていく。
「ね、ねえ、ノッポ君?」
たまりかね、おろおろウォードに足を向けた。「やっぱ置いてっちゃ、かわいそうでしょ。ちょっと今は、拗ねちゃってるだけだって。ね? ホーリーも一緒に──」
『──どこ行った、コラ!?』
びくり、とエレーンは飛びあがった。
あわてて、きょろきょろ辺りを見まわす。「……え……え?」
……ファレス?
間違いない。嫌ってほど聞いたあの声だ。でも、こんな所にいるはずがない。でも、今、確かに耳元で……?
あたりは一面、立ち枯れた荒れ野だ。膝丈の草地がある程度で、人が隠れられるような立ち木はない。そもそもファレスは、いつまでも隠れてられる奴じゃない。とっくにここまで飛んできて、ゲンコの一発も食らわしていること必定だ。
しきりに首をかしげて、振りかえる。「ねーねー、ノッポ君、今、何か──」
はた、と気づけば、ウォードがいない。
見れば、彼ははるか先。ほんのちょっと立ち尽くしていた間に。
エレーンはあたふた駆け寄った。「ね、ねーねー。今、あたしになんか言った?」
「何をー?」
ひょろりと背の高いウォードの背中が、ぶらぶら草地を歩いていく。
「……。そ、そーよねえ?」
その背について歩きつつ、エレーンは腕組みで首をかしげる。なぜだろう。いないはずのファレスの怒声が、はっきり耳元で聞こえたのは。
(……。どっかで怒ってんのかしらあいつ)
世の中って、不思議がいっぱい。
「あんた、よく泣くねー」
「……え?」
エレーンは面食らって振り向いた。
隠しに手を突っ込んで、ウォードは振り向きもせずに歩いていく。
「目がまっかー」
エレーンはあわてて目元をこすった。「……そ、そう?」
五番街の診療所を出、北門から商都を出る前に、町外れの墓地に寄っていた。アディーが眠るあの墓地だ。だが、会いに行った相手は、アディーではない。
バリーに、どうしても謝りたかった。彼に訊いてみたかった。なぜ、こんなことになったのか。
場所は聞いていなかったが、バリーの墓はすぐに分かった。ひっそり打ち沈んだ夜闇の中、そこだけこんもりと盛りあがっていたから。昼にボリスらが供えたのだろう真新しい花束で。
硬い墓石に膝をつき、エレーンは長いこと泣きじゃくった。その間ウォードは、ずっと無言でそばにいた。だが、夜仕事の街明かりがまたたき始めたのを目にするや、問答無用で担ぎあげ、夜更けの墓地から連れ出した。
狭く薄暗い路地から路地へと、ウォードは早足に伝い歩いた。その首にずっと、エレーンはしがみついて泣いていた。
気づいた時には、空が白み始めていて、ウォードは明け方の人けない街道を歩いていた。バリーのことに気をとられ、それどころではなかったが、墓地から夜の街を抜け、この荒れ地に到着するまで、ずっと負ぶってくれていたらしい。
その並ならぬ彼の苦労に、今になって思いあたる。
エレーンは気まずくうつむいた。「ご、ごめん。あたし、重かったよね……」
「あんたは軽いよー」
前からの無頓着な声に、気負った様子は感じられない。
立ち枯れた野草を靴先で掻き分け、ウォードはぶらぶら、無造作に足を運んでいる。その横顔で、ぼそりと言った。「でも、仇はとったから」
え? とエレーンは顔をあげた。
「それって、やくざ者と喧嘩したってこと?──あ、そっか。あの後、部隊のみんながきて」
「オレひとりー」
「──じゃ、じゃあ、一人であんな大勢と」
事態を悟って息をのんだ。「あ、危ないでしょう! 怪我でもしたら、どうするの」
「そうやって」
後ろ頭を背中に倒して、ウォードは途方に暮れたように空を仰いだ。「あんたが泣くと思ったからさー」
とっさにエレーンは言葉につまった。
戸惑い、視線を泳がせる。「そ、そりゃあ、あの人たちはひどいことしたけど──でも──」
ふと、エレーンは口をつぐんだ。そういや昨夜、嫌な噂を聞かなかったか?
そう、診療所でたむろしていた物騒な男たちが言っていた。あの後、森で抗争があり、ゴロツキが大勢死んだのだと。二十を超える数だったと。おそらくバリーを殺したゴロツキだ。そして、ウォードもやはり、あの森にいた……?
「行くの、やめればー?」
ぶっきらぼうに割りこまれ、はっ、とエレーンは我に返った。
今の問いの脈略を急いでたぐり寄せていると、どうでもよさげに、ウォードは続けた。
「トラビア」
あわてて彼の隣に並び、高い位置にある横顔をうかがう。「あっ──やっぱ、やだ? トラビアに行くのは」
「できればねー」
「──そ、そっか。……そうだよね」
予想だにせぬ展開だった。
「……そっか。やっぱり恐いよね、あっちは戦争中だもん」
辛うじて返事をしながらも、エレーンはひどく戸惑った。
強制できるようなことではなかった。現在、目的地トラビアは、武装した軍が対峙する最も危険な場所なのだ。だが、彼に拒まれては手立てがない。
恐る恐るうかがった。「……あの〜……そうしたら、手前のザルトまででもいいんだけど」
「エレーン。オレさー」
ウォードは溜息まじりにうつむいた。
「やっぱり、あんたに言わなくちゃなんないんだけどー」
え゛っ? とエレーンは眉根を寄せた。今の言葉、前にも聞いたことがあるような……?
ふっと、あれが脳裏をよぎって、む、むぅ……とエレーンは顔をしかめる。じっとり汗が手ににじむ。そう、あれだ。みんみん蝉鳴くロマリアの丘……。
額をつかんで、うなだれた。
(また、アレかー!?)
「エレーン、オレ、あんたのことを──」
案の定、ウォードは切り出した。前回と寸分たがわぬ言いまわしで。
たじろぎつつも、エレーンはどぎまぎ先を促す。「う、うん。なあに? ノッポ君」
ウォードが怯んだように口をつぐんだ。
狼狽して、目をそらす。
(……やっぱりかー)
前と同じパターンだ。四角四面に切り出して、同じ所で詰まってしまう。そして、じぃっと見つめ合い、延々続く息づまる沈黙。そうして、初めからやり直し。延々それのくり返し。でも、
エレーンはぐったり(ウォードに気づかれないよう)うなだれた。
(なんで、今、始めちゃうかな〜……)
こんな所で。
彼が何を言いたいか、そりゃあ、見当はついている。伊達に年ばっか食ってるわけじゃないのだ。だが、まさかこちらが指摘して台なしにするわけにはいかないではないか。彼の一世一代の告白を。
荒れ野を覆う石砂利が、歩くたびに音を立てた。
遠い西の荒れ地の果てに、山の稜線がうっすらと見える。見渡す限り、人家はない。海風で野草も育たないのか、辺り一面立ち枯れて、殺伐とした風景だ。
唸りをあげる海風と、台詞の練習であるかのようなぎこちない呟きを聞きながら、夏日に照らされた荒れ野を歩いた。やむなく、ひたすら忍耐で、悶々、うずうず、先を待つ。ああ、これで何度目か……。
「エレーン、オレ、あんたのことを──」
突如、ウォードの肩が傾いだ。
いや、痺れを切らして、ぶっ飛ばしたわけでは断じてない。無造作におろした彼の腕が、ぐい、と後ろに引っ張られたのだ。
はた、と我に返って振りかえる。
「……ホーリー?」
あぜんとエレーンは呟いた。
いつの間にか、大きな馬体が迫っていた。そう、ウォードの腕をくわえていたのは、他ならぬあのホーリーではないか。ぜえぜえ顔を引きつらせ、四肢をふんばって立っている。そのつぶらな瞳の真剣なこと。つまり、彼を
(追っかけてきたのか……)
不覚にも、じぃぃーん、と胸が熱くなる。おお、ホーリー。乙女の意地を見せたのか。別の女に告白ろうとした薄情この上ないこの彼に「待った!」をかけて阻止しようとは。なんといういじらしさ。その切ない胸の内、とても他人事とは思えない。そうだ。がんばれホーリー。
馬と人だが、異種間がなんだ!
「行ってくれるのー?」
ウォードはまるで頓着なく、ホーリーの耳の後ろを撫でている。
その何事もないいつもの顔を、エレーンはあぜんと盗み見た。ホーリーがこうして追ってくるのを、もしやウォードは知っていて、つれない態度をとっていたのか? いや、あれは絶対、確信犯だ。
(……。ノッポ君ってば)
なにやら虚ろで微妙な気分。いじましいホーリーが、何やら不憫に見えてくる。
そろそろ近づき、ぎこちなくホーリーに笑いかけた。「あ、あの、ありがとね、ホー──」
ぎろり、とホーリーが目を剥いた。
だが、それでも渋々頭は垂れた。はっきり、それとわかる「渋々」さ加減で。
「……。あ、ありがとー……」
居心地悪く引きつり笑う。それでも、ウォードの頼みは拒めない、ということか。世の中って無情だ。
ウォードの手に助けられ、馬の高い背にまたがった。すぐに、ウォードも真後ろに乗りこむ。
ゆっくり、ホーリーは歩き出す。茶色のタテガミの細長い顔を、そっとエレーンは盗み見た。
(ごめんね、ホーリー。トラビアに着いたら、返すから)
あなたの大事なこの彼を。
そう、彼とは、そこまでだ。
現地手前で、彼を帰そう。あの短髪の首長の元に。トラビアは今、戦争中だ。こんな危ない騒乱に、子供を巻き込むわけにはいかない。彼は一見大人に見えるが、まだ十五の子供なのだ。
覚悟は、既にできていた。真新しい墓石の上に、ひざまずいたあの時に。
もう、誰ひとり失ってはならない。
後はひとりで歩いて行くのだ。自分の足で、歩いて行くのだ。たとえ、我が身を投げ打つことになろうとも。物ごとは左右の秤。何かを欲せば、見合うだけの対価が要る。何ひとつ失うことなく利益だけを得ようなど、考えてみれば、虫のいい話だ。
ふと、エレーンはまたたいた。
なにか感じが、いつもと違う。いぶかしい思いで見まわして、ようやくそれに気がついた。
ウォードが体を支えている。
指の長い大きな手が、肩を支えてくれていた。当たり前のような無造作な手つきで。ほんの数日前までは、ウォードは頓着しなかった。他人のことは他人のこと、不注意で何が起きようが、我関せずという態度だった。だから、彼の馬に乗る時には、必死でしがみついていなければならなかった。なのに──。
そういえば、と思い出す。
ここまで来るのも、彼が負ぶってくれていた。決して短くはなかろう道のりを。文句も言わずに墓参りに付き添い、墓石にしがみついた手を引き剥がし、だだをこねる子を諌めるようにして──。
成長している。
はっきりと、それがわかった。彼は、ここ数日で成長していた。どんどん、どんどん成長している。その速さに、鮮やかさに、傍が怖気づいてしまうほどに。
(もう、任せて大丈夫なんだ……)
手をゆるめても、もう、落ちない。
そう頭を掠めた途端、急に気が抜けてしまった。
ウォードの肩に頭を預け、耳を胸に押しつける。どくん、どくん、と胸が力強く脈打っている。規則正しい、くっきりとした鼓動──。
ぼんやりそれを聞いていたら、猛烈な睡魔に襲われた。そういえば夜通し泣いていて、昨夜は一睡もしていない。
せめて今は、少し眠ろう。トラビアに着くまでの短い一とき。「その時」がくるまでの束の間の時間。ここは、あたたかくて心地いい──
綿シャツの肩に顔をすりつけ、エレーンはゆっくり瞼を閉じる。
長い、長い、夢をみた。
☆ おまけSS ☆
( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
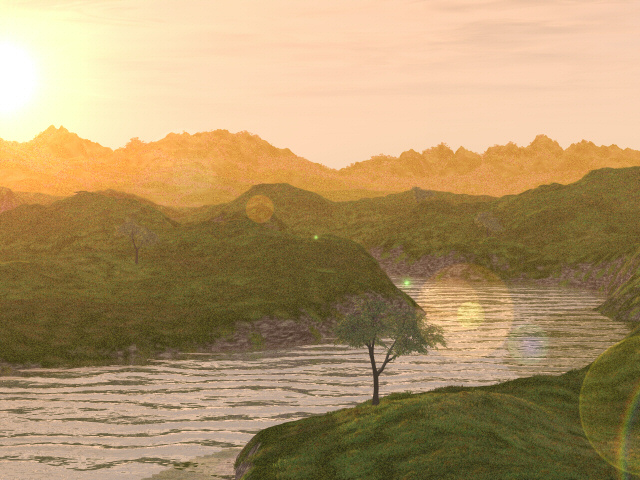
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》![]()