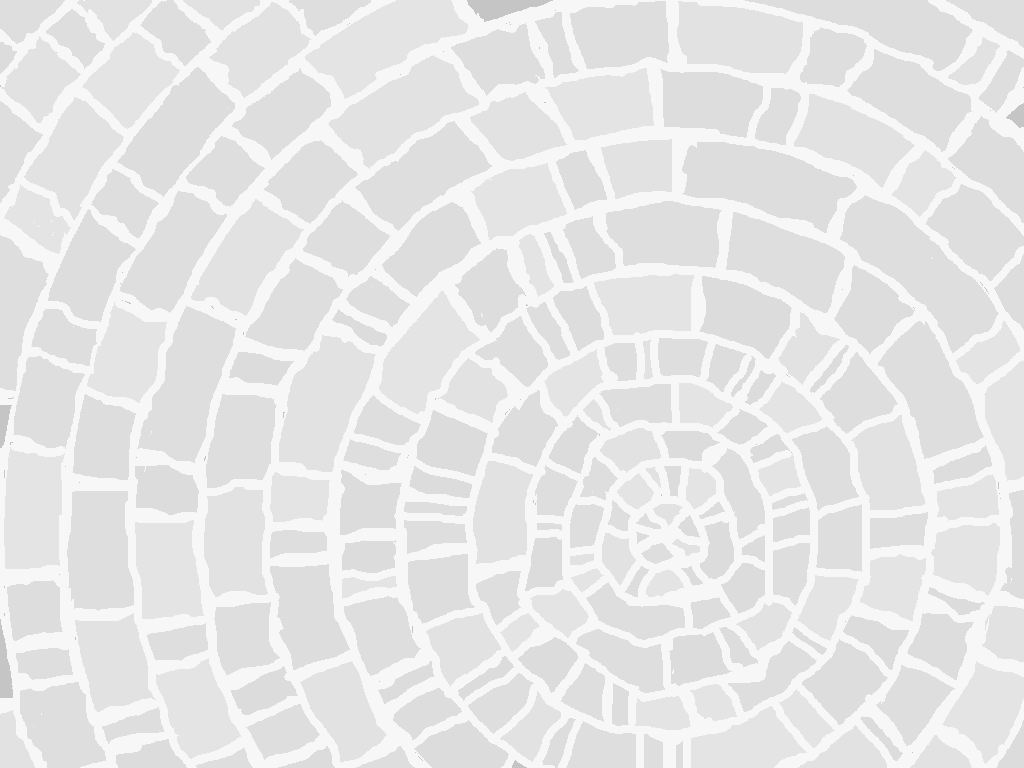
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章19
( 前頁 / TOP / 次頁 )
大勢の声と足音が、ばたばた横を行きすぎた。
一団の足音が遠ざかる。捕えた男は動かない。ならば、一味の者ではない? けれど、それなら、この人は──刹那、忙しなく疑問がよぎる。だが、すぐに気がついた。それどころではないことに。
ぐにゃり、と時間がゆがむ感覚。
突かれたように、鼓動が跳ねた。
足が竦む。不安がうごめく。視界がぼやけ、焦点が遠のく。息が
──吸えない。
間近な気配が、息を呑んだ。
「やべ!──おい、息しろ息っ!」
肩をつかまれ、揺さぶられた。平手が軽く背中を叩く。
ぽん、と栓が抜けたように息が通った。
あわてて息を吸い、そして、吐く。忙しなく呼吸を整える。
「──くそ。又かよ」
外套の男のなじる声。どこかで聞き覚えがあるような?
顔をしかめて胸を押しやり、エレーンは怪訝に振り仰ぐ。
使いこんだザックを肩にかけ、くびれた綿シャツを着こんでいる。こざっばりと短い頭髪の、どこにでもいる中年の男だ。いや、あの右眉の古い傷は──
面食らって、またたいた。
「お、おじさん……?」
あの夏、長らく逗留した、ノースカレリアの街道の宿「どくろ亭」の主ではないか。
「いやあ、旅装にしといて正解だったよ」
外套をつまんで、にっ、と笑う。
「服屋にはしつこく勧められたが、これじゃ、ちょっと大袈裟かなって実は思ってたんだよな」
すばらしく美味しい料理を出す、崩壊寸前のボロ宿の主。名前は確かセヴィランとか。
今曲がってきた町角を、背を押されるがまま又戻る。「え? え? なんでここに」
「話は後だ。早く中へ」
セヴィランが視線を走らせて、壁の扉を押し開けた。
体を隙間に滑りこませる。
視界が、薄く煙っていた。
押し開いた扉の向こうで、卓にともったランプが八つ、店の暗がりに浮かんでいる。その半数に、酒を酌み交わす男たちの姿。
入って右手は、酒瓶の壁にカウンター。店の奥に階段があるなら、二階は大抵、客室の造り。
酒場だった。ホールに気だるく立ちこめる、何事もない低いざわめき──。
馴染みのある光景に、ほっとエレーンは息をつく。いきなり戸口に押し込まれた時には、どこへ連れこまれたかと、ひるんだが──。空き卓を見つけ、やれやれと歩く。
腕を、引っぱり戻された。
ばさり、と外套で押し包まれる。けれど、もう店内だ。エレーンは戸惑い、おろおろ仰ぐ。「お、おじさ……?」
「ちょっと口を閉じていてくれ」
声をひそめて素早くたしなめ、セヴィランは壁に背を張りつけている。今入ってきた戸口の横で。
口をつぐむと、外の物音が耳に届いた。ばたばた駆けまわる大勢の足音。閉じた扉の向こう側。
バン──と叩きつけるようにして扉があいた。
扉が間近に飛んできて、とっさにセヴィランにしがみつく。
密かに腕で扉を受け止め、彼は一言も発しない。外套で頭まで包まれた耳に、どかどか荒い足音が響く。
「親父! 女が来なかったか!」
「──女だ?」
男の声がうんざりと応じた。「見ての通りだ。いやしねえよ、そんなものは」
「おい、二階だ! 部屋ん中探せ!」
たちまち数人が動く音。ばたばた階段を駆けあがる音。
荒い物音が、天井から聞こえた。戸を乱暴に開け閉てする音。宿泊客がいたのだろう、男の罵声。非難を含む驚きの──。
物音はそれからしばらく続き、ばたばた足音が駆け降りた。大勢の気配が徐々に近づく。「おう、親父。邪魔したな」
「まったくだよ、ガキどもが。営業妨害するんじゃないよ。次は通報するからな」
「へっ! ゴチャゴチャうっせえんだよ!」
「くたばりぞこないが! ぶっ殺すぞ!」
毒を吐き捨て、どやどや脇を通過した。
悪態と気配が離れていく。
十分遠ざかったのを確認し、セヴィランが綿シャツの腕を伸ばした。
やれやれと扉を閉め、カウンターの店主に笑いかける。「悪い、ジフ。助かったよ」
「なんのこれしき。お安い御用だ」
拭いていたグラスに、はあっ、と息を吹きかけて、初老の店主は澄ました顔。「あれで連中も気が済んだろ」
あぜんと、エレーンは背後を仰いだ。「おじさんの知ってる人? あ、てことは、同業者……」
「ああ。今夜はここで世話になる」
「でも、そしたら商売敵ってことなんじゃ? なにもわざわざ、そういう所に──」
はた、とエレーンは口を押さえた。カウンターの店主に気がついたのだ。ちらちらそちらを盗み見て、言い訳がましくあわあわ仰ぐ。「やっ、べ、別にあたしはそんな意味で言──」
「どうせなら、恩を売っておく」
面食らってまたたくと、セヴィランは苦笑い。
「だからさ、共存共栄の精神って奴だよ。こんな旅先じゃ、意地を張っても仕方ないだろ? せいぜい友人に儲けてもらうさ。それに何かと融通が利くし、情報交換も兼ねられる。だろ?」
卓について飲んでいる客は、ちらと見やっただけだった。今の騒ぎは見ていたはずだが、誰もが見て見ない振り。与太者になど関わらないし、まして、誰も協力しない。
「ともあれ、これで一安心だ。ここへは、もう来ないだろ」
一番近い空き卓へ、セヴィランはやれやれと足を運ぶ。
肩のザックを板床に下ろし、外套を脱いで、椅子にかけた。隣の椅子の背を、つかんで引く。「まあ、こんな所で立ち話もなんだ。積もる話は食いながらでも──」
「ごはんっ!?」
エレーンは目を丸くして飛びついた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》