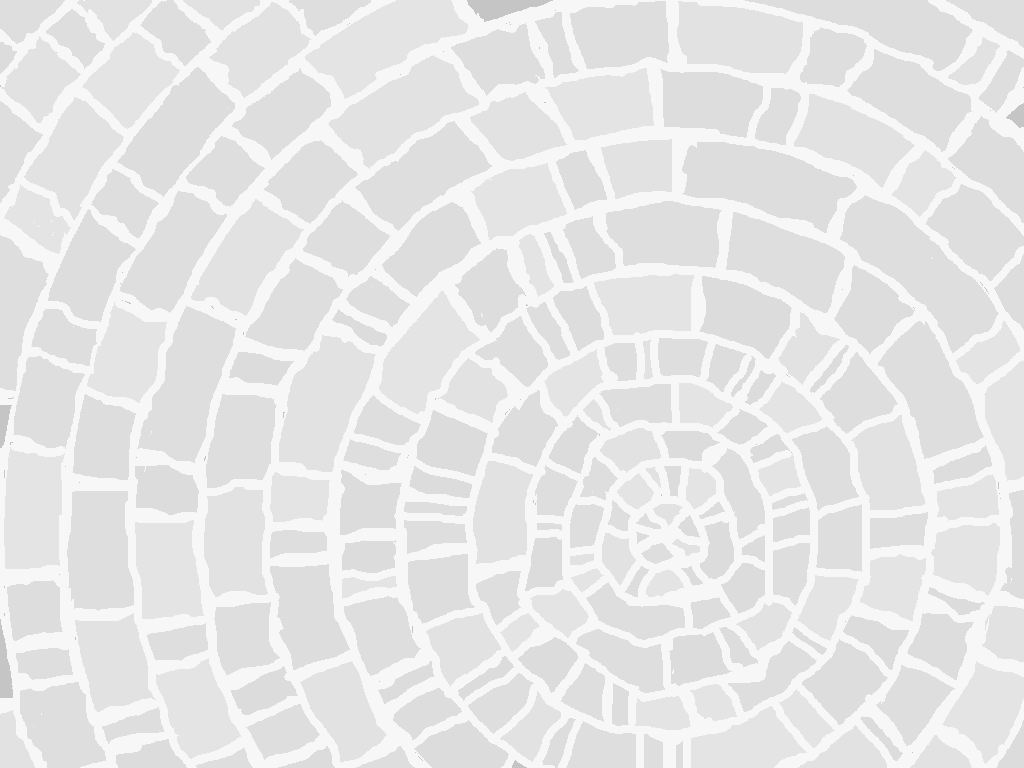
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章20
( 前頁 / TOP / 次頁 )
あっけにとられた頬杖で、セヴィランがあぜんと眺めていた。
「あんた、よく食うなあ……」
食事中の自分の皿にスプーンの先をつけたまま、どこか惚れ惚れとした顔つきだ。
右手に骨付き肉、左手にパンと、エレーンはるんるん満面の笑み。
「だあって、お腹すいちゃってぇー──あ、もしかして、食べすぎってこと?」
「いや、いいよ、好きなだけ食ってくれて。飯を残さず食う奴は好きだ。だが、そんなに食って、腹の方は大丈夫か?」
「ぜんぜん平気っ! お構いなくぅ〜!」
目の前の卓には、パン屑だけが散らばった籠と、完食した皿が三枚、すでに四枚目の鶏に取りかかっている。
こんな大盤振る舞いが何故にできたかといったらば、連れが口を滑らせたからだ。「勘定はもつ」と。
あの出会い頭の出来事を、彼は気にしているようだった。ずっとそわそわし通しで、事あるごとに気遣ってくれる。「気分はどうだ?」「もう苦しくないか?」「どこか痛いところはないか?」
ぶつかった拍子に息が詰まっただけなのに。むろん、ご飯はありがたく頂戴するが。
息も継がずに食い漁り、四枚目の皿を積みあげて、ふぃ〜、とご機嫌で腹を叩いた。「でも、なんで、おじさん、あんな所に?」
「連れと落ち合うことになっていて、ここに向かって歩いていた。で、その道で、あんたを見かけた」
店の戸口を親指でさし、セヴィランは片肘ついて酒を啜る。「だが、追っ手はあの人数だろ。まともに遣りあってちゃ骨が折れる。それで町角まで取って返して、あんたが来るのを待っていたわけだ」
そして、外套で包んで隠してくれた。追っ手が行ってしまうまで。
「でも、なんでわかったの? あたしが角を曲がるって。直進したかも知れないのに」
「曲がったさ」
へ? とエレーンは面食らって見返す。思いがけないぶっきらぼうな口振り。日ごろの温和さとはそぐわない──。
ふと、セヴィランが目をあげた。
まじまじ見つめる視線に気づいて、ばつ悪そうに目をそらす。「──勘がいいんだ、昔から」
そういえば、とエレーンは思う。そう、さっきもそうだった。店に入った直後にも、いきなり戸口に張りついた。本人にも自覚はあるようだが、ずいぶん勘が良いようだ。とはいえ扉は閉じていたから、遠くを駆ける足音に、気づくとなると至難の業だが──
どこか釈然としないながらも、ふうん、とエレーンはナプキンを取り、口元についた油を拭く。「それで、こっちには仕入れかなんかで? でも、商都は過ぎたけど」
「……ずっと、会いたかった奴がいてな」
手の平で包んだグラスの中を、セヴィランは遠い瞳でながめている。
「戦後、ノースカレリアであいつを見かけて、生きていたと確信した。あいつの消息を追う内に、こんな所まで来ちまった──ああ、つまりは人捜しってことだな。あんたの方こそ、なぜ、ここに? 領邸をあけちまって大丈夫なのか?」
「そ、それが──」
彼に事情を話したものか、エレーンはとっさにまごついた。「トラビアへ行く」と言ったなら、やはり、戻るよう言うだろうか。
皆が自分に戻れと言う。昼に出会ったザイやセレスタン、ケネルやファレス、そして、三バカ。いや、取り立て屋やゴロツキでさえ。むしろ、賛成する者など一人もいない。
もじもじ卓で指をいじくり、迷った末に上目使いで見た。
「じ、実はあの後、色々あって……」
隠し立ては失礼な気がした。彼には世話になっている。ノースカレリアでも。たった今も。その上、ここの勘定まで。まあ、小言くらいはあるにせよ、連れ戻しはしないだろう。人捜しの途中のようだし。
手のグラスをゆっくり揺らして、セヴィランは無言で聞いている。
あらかた事情を聞き終わり、眉をしかめて息をついた。「──そうか。一人でトラビアになあ」
ぽかん、とエレーンは口を開けた。「止めないんだ?」
「──生き別れってのは辛いからな」
ぐい、とセヴィランはグラスをあおる。
「ここで無理にあんたを帰して、それっきりってことにでもなれば、俺には責任がとれないよ、あんたが舐める辛酸に」
どこかやりきれない、苦々しげな口振り。──深入りするのを避けるべく、エレーンはあわてて話を替える。「そ、それであの、あたし、おじさんに訊きたいことあって」
ながめていたグラスの底から、ふと、セヴィランが目を向けた。
えへへ、とエレーンは指先どうしをくっつける。「じ、実はちょっと困ってて。うんと安い宿、おじさん知らない?」
「宿?」
「──実は、あんまりお金なくて──おじさん、そういうの詳しそうだし。だから」
「安いところも、あるにはあるが」
顔をしかめ、往生したように頭を掻いた。「だが、あんたみたいな若い娘を、一人でやるのは、ちょっとなあ」
「あ、あたしだったら大丈夫! 部屋きれいでなくても構わないし。く、黒虫さえ出なければっ……!」
「虫より先に心配することがあるだろう」
セヴィランはやはり渋い顔。椅子の背に深々ともたれ、考え込んでしまった様子。
エレーンは手を打ち合わせ、卓に額をこすりつける。「ね、お願い! このとおーりっ! 一生のお願い! ね?」
「変にとらないでもらいたいんだが」
慎重な口ぶりで、セヴィランが見た。
「よければ、俺と一緒にくるかい?」
ぽかん、とエレーンは口をあける。「お、おじさんと?」
「どうも、あんたは心配だ。旅費も持たずに出てきたり」
「──う゛っ……だ、だから、それには色々あって……」
「飯と宿代は俺がもつ。さいわい方向も同じようだし。──ああ、そろそろ連れが来るから、二人きりってわけじゃない。どうだい?」
降ってわいた急な話に、エレーンは口をパクつかせる。「あの、あたし的には、うんと、すんごく助かるんだけど、でも、こっちで勝手に決めちゃったら、おじさんの連れって人が──」
「当分、四の五の言わせないさ」
「……へ?」
なんぞ貸しでもあったりするのか?
「それに、ここまできたら渡りに船だ。ノースカレリアの開戦には、俺も一枚かんでいるし」
そういえば、と思い出した。ディールからの使者を追い返し、天幕群に出向いたあの時、一度は追い払われた統領代理に、引き合わせてくれたのがこの人だった。
「結局俺は、なんの役にも立てなかったからな。ま、ここで会ったのも何かの縁だろ。それに、あんたには埋め合わせをしないと」
「埋め合わせ?」
……て、なんの? と首をかしげ、あ、と思い当たって手を振った。
「やっだー、おじさん! さっきのアレなら、気にしないでいいってば! 大体おじさんのせいでもないし」
「いや、本当に危なかったんだ」
セヴィランは一蹴、探るような真顔で見つめている。ずいぶん気にしているらしい。
「で、でも、勝手にあたしが喉つまらせただけ──」
「悪かったな」
顔をしかめ、疲れたように瞼を揉んだ。「滅多にないんだが、あんなことは。ああいう荒事は近頃ないから、過敏に反応しちまったようで──。あんた、本当に大丈夫か」
言われて腕を上げ下げし、エレーンはきょろきょろ再点検。「……や。別に。なんともない、と思うけど」
現に、こうしてピンピンしている。笑って、エレーンは手を振った。
「やー。おじさん。気にしなくて大丈夫──」
かくり、とその肘が卓から落ちた。
「……え?」
うつ伏せた背中に、ずしん、と"重み"が覆いかぶさる。
はたと悟って、ぅげ!? とエレーンは顔をゆがめた。
(う、嘘っ!? 又!? てか、まじで勘弁こんな時にっ! おじさんに誤解されちゃうじゃないよっ!?)
「どうした」
驚いて、セヴィランが席を立った。「どうした。やっばり、具合が悪いか」
「……あ……や、そういうことじゃ、ないんだけどっ……」
けれど、ちょっと説明しがたい。
あの奇妙な感覚だった。大気がねじれているような。うねりの中に投げこまれ、ぐにぐに揉まれているような。
両手で卓をしっかとつかみ、ぐぬぬ……と重圧を押し戻す。どうにかこうにか顔をあげ、エレーンは困惑しきりで引きつり笑い。
「な、何がどうなってんだか自分でも──実は最近、変な感じになることあって──あ、でも、大丈夫みたい。引いてきた」
セヴィランが顔を強ばらせ、卓をまわってやってきた。「横になった方がいい。すぐに二階に部屋をとるから」
「あ、あたしなら、もう平気。なんか治ったみたいだし」
「そうしてくれ! 頼むから」
強い語気に、エレーンはひるんだ。
「……あ……うん……あ、はい」
がたん、と椅子の足を鳴らして、素直に席から立ちあがる。
「じゃあ、お言葉に甘えて休ませてもらうね。今日はなんか逃げてばっかで、知らない内に疲れてたみたいで」
制服の袋も、忘れずつかむ。
歩き出したセヴィランについて、店の奥にある階段へ向かった。
途中、店主のいるカウンターに立ち寄り、二部屋分の鍵を受けとる。
「部屋は奥がいいだろう? 俺たちは隣の部屋だから」
古い階段を二階へあがると、暗がりに八つほど扉が見えた。廊下をはさんで、左右に扉が四つずつ。
ランプの灯った薄暗い廊下を進む。
左壁三つ目の扉で足を止め、セヴィランが鍵を手渡した。「何かあれば、呼んでくれ。夜中でも俺は構わないから」
「あ、うん。ありがと。そうさせてもらうね」
袋をかかえ、更に先へと、薄暗い廊下をエレーンは歩く。平気というのは本当だった。気を使ったわけではない。彼が飛んできた途端、なぜだか異変も吹っ飛んだのだ。突風で炎が消えたように。相手が動いた拍子に、というなら、やはり金縛りのようなものなのだろうか──。足が、不意に歩みを止めた。
ざわり、と悪寒が背筋をなでる。
ピシ──と耳元で空気が鳴る。鼓動が少し速くなる。
(な、なに、これ……)
気持ちが騒ぐ。何かの予兆を伝えるように。だが、原因はわからない。ふと、エレーンは胸元を見る。
「……あれ? なんだろ」
じんわり、胸元が温かい。それに、ブラウスの下が、なにか明るい。
薄い綿の生地を透かして、うっすら緑が息づいている。
「……お守り?」
淡い光を放っているのは、どうやら首飾りであるらしい。ダドリーの書斎から持ち出した「夢の石」のにせものの翠石。廊下のランプに反射して? いや、翠石が
明滅している?
「どうした?」
鍵をあけていたセヴィランが、怪訝そうに振り向いていた。
「──あ、ううん! お休みなさい」
あわててそちらに笑い返して、首をひねりつつ、歩き出す。
「……。なんだろ、これ」
石のことが気になるが、今は両手がふさがっている。右手に鍵、左手には制服の袋。ひとまず荷物を下ろしてからと、もらった鍵で施錠を外し、ノブをまわして扉を開く。
キィ……とかすかに扉が軋んだ。
しん、と暗い板張りの床。灯かりのない闇の中、向かいの窓から、月明かり──
背を、叩きつけられた。
すさまじい風圧を感じた刹那、壁まで跳ね飛ばされていた。もしや突風──いや、木窓はぴったり閉じていた。通常、空室は施錠してある。いや、そんなことより──
拡散する意識に抗い、必死で思考をめぐらせる。今、垣間みえた扉の向こうで、妙なものが視界を掠めた。
足だった。
不明瞭な"黒"の中、足が一本、浮いていた。
そして、男物のズボンと靴が、暗がりの境をまたぎこした。
何もない、闇の虚空を。
※ あまりにも久々の登場なので (^0^;
【参照頁 〜 セヴィランて誰 〜】
第1部 2章1話1(&エレーン)
第1部 interval「闇の中」
第1部 3章3話4(&エレーン)
第2部5章9話10(&ケネ・ファ)
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》