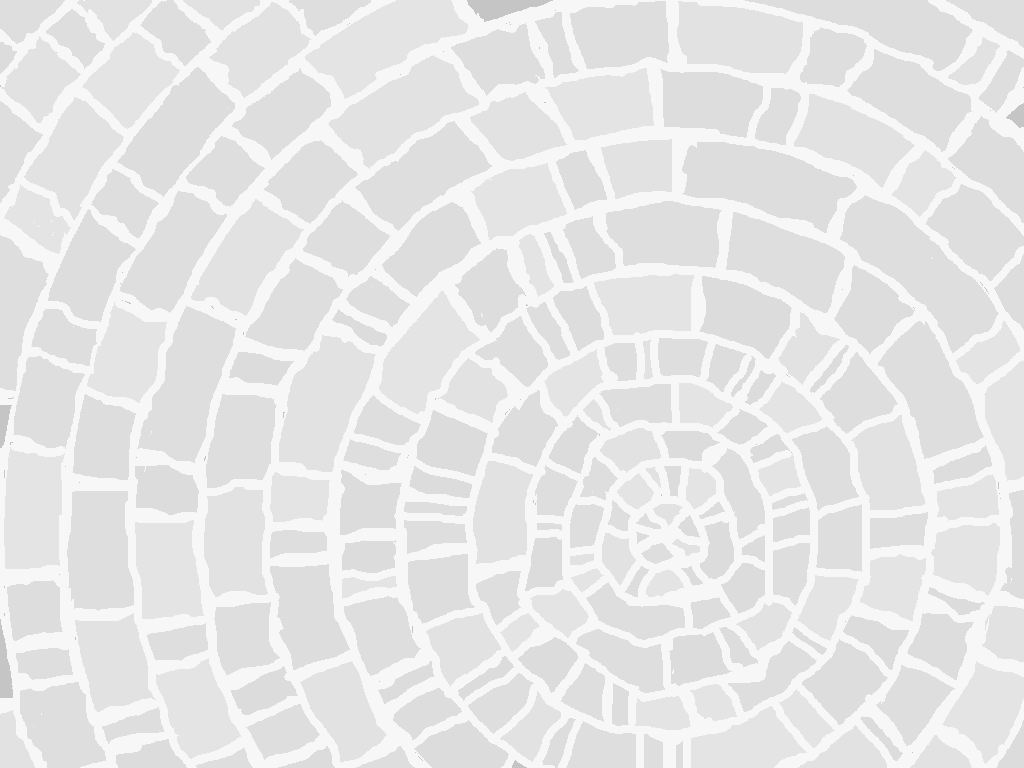
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章21
( 前頁 / TOP / 次頁 )
廊下の物音に驚いて、セヴィランは部屋を飛び出した。
薄暗い廊下の隅を見て、くずおれた彼女に息を呑む。
「どうした!」
駆け寄り、呆気にとられて見おろした。気を失っている。何が起きた。今しがた別れてから、さほど経っていないというのに。
見たところ出血はなく、外傷などはないようだ。今の派手な物音は、壁に叩きつけられでもしたのか。だが、一度で気を失うほどとは尋常ではない。
気配に気づき、反射的に振り向いた。
開いたままの扉の先、灯かりのない暗がりに、男が一人立っている。
「なんだ、お前は。どこから入った」
まだ若い。二十代半ばというところか。身の軽そうな小柄な体格。利発な少年を思わせる顔つき。淡々と見やった怜悧な目には、なんの感情もうかがえない。
けれど、おかしい。ここに人など、いるはずがない。
廊下の両側は客室で、どの部屋も鍵がかかっている。仮にどこかに潜んでいたのだとしても、扉が開く音はなかった。彼女の部屋は突き当たりで、つまりは階段から最も遠い。男が室内で待ち受けるためには、先に入室する必要があるが、彼女と廊下を歩いた時には、追い抜く者などいなかった。つまり、侵入路はどこにもない。
セヴィランは怪訝に向き直り、不審な男へ躊躇なく踏み出す。「お前、一体──」
階下からの音に、足を止めた。
とん、とん、とん……と気だるそうな木板の軋み。誰かが来る。階段をあがって。事と次第によっては締めあげてやろうかと思ったが──
「なんだよセヴィ、大声あげて」
聞き慣れた声がした。
階段を上りきり、廊下の先から歩いてくる。乏しい壁灯かりが照らし出す、すらりとした長身の人影。手入れの行き届いた長い髪。目鼻の整った端正な顔だち。白絹の肩に手をおいて、大儀そうに首をまわしている。
「着いたばかりだぞ。勘弁してくれ、揉め事なんて」
面倒そうにぼやいたのは、落ち合う予定だったデジデリオ──気絶した彼女が彼を見れば "統領代理"と言ったろう。かの北カレリアでの戦闘時、天幕群の指令棟で、遊民たちを束ねていたから。ぶらぶらデジデリオは歩み寄り、こちらを見て顔をしかめる。
すばやく見返し、当惑気味に眉をひそめた。
「なあ、セヴィ。なんていうか、その……お前、何か違わない──?」
ためらいがちな言葉半ばで、気づいたように室内を一瞥。
「──ぅわっ!?」
廊下の端まで飛びのいた。
見開いた凝視のその先は、無言でたたずむ室内の人影。
まごつき、視線を泳がせる。狼狽したように唇がわななく。「な、なんで、ここに……」
すぐさま階段へ取って返した。
「お、おい、デジデリオ。いきなりどこへ──」
だが、何も耳に入らぬようで、ばたばた階段を下りていく。
戸惑い、セヴィランは呆気にとられた。尻尾を巻いて逃げ出した? 斜に構えて物事を見る、傲岸不遜なあの男が? 室内にいる不審者を知っているような素振りだったが──。ひらめき、男を見返した。
「そうか。お前がユージンか」
男は怪訝そうに目をすがめ、この状況を咀嚼するようにつぶやく。
「"セヴィ"──北カレリアの"セヴィラン"か」
「どういうことだ」
セヴィランは苦々しく彼女を見る。「何をした、俺の連れに」
「俺は何も」
事もなげにユージンは返し、いぶかしげに彼女を見やった。
「どうやら、運悪く居合わせたらしいな」
セヴィランは顔をしかめて短髪を掻く。
「──瞬間移動かよ、たまげたな」
諸条件を勘案すれは、適当な事由はそれしかない。半ば呆れて相手を見る。「話には聞いていたが。いつも、こんなに派手なのか」
「いや。人を巻きこんだことはない」
感嘆にも困惑にもさして興味はないらしく、ユージンは淡々とやり過ごす。それよりも、と言いたげに、窺うようにすがめ見た。
「なるほど。あんたが"死神"か」
「──あ? なんだよ、やぶから棒に」
セヴィランは顔をしかめる。
「何を勘違いしたんだか知らないが、そいつは俺じゃない、知り合いだ。俺もそいつに会いたくて、こんな所まで出て来たんだ」
「それが本当なら、ご苦労なことだな」
「どうして、俺が嘘をつく?」
「ならば訊くが、そのためにわざわざ出向いたと? 北方から延々南下し、大陸の最果てトラビアまで」
「トラビア?」
ふと、セヴィランは聞き咎めた。
「一体なんの冗談だ。お前はここがトラビアだとでも言うつもりか?」
ユージンが怪訝そうに見返した。真意を推し量るようにすがめ見る。
「──おいおい。まじかよ、参ったね」
やれやれとセヴィランは頭を掻いた。
「着地点を誤ったらしいな。この街はノアニールだよ。商都の西方、トラビア街道沿いの地方都市さ」
「ノアニール……」
口の中で地名を復唱、ユージンはやはり釈然としない顔。
「疑うなら外へ出て、そこらの標識でも見てこいよ。──それにしても物好きだな。今時分トラビアとは。お前だって知ってんだろ、向こうは今、抗戦中だぜ」
「近ごろ不審だろう、トラビアの動きが」
投げやりな調子でユージンは返し、眉をひそめて周囲を見やった。
「こうする間にも、次第次第に強くなる。あんただって感じるだろう、この大気の荒ぶりを。トラビアからの獰猛な波動を」
「──ああ、いや。俺は」
セヴィランは気まずく目をそらした。「言ったろう、人を捜しに来ただけだ」
そうか、と拍子抜けしたように口をつぐみ、ユージンは溜息で仕切り直した。
「それで少し様子を見にな。あの地で何が起きているのか。誰が何をしているのか。ところがトラビアを飛び越して、こんな見当外れな場所へ。しかも、宿とは。どうなっている」
往生したように腕を組む。
「まったく訳がわからない。何かに引っ張られたように進路が歪んで──」
ふと、目をあげ、腕を解いた。
振り向き、つかつか戸口へ歩く。
真顔の相手の勢いに押され、セヴィランはたじろぎ、身構える。「な、なんだよ。やろうってのか」
すっ、とユージンが通過した。
押しのけるようにして廊下へ出、壁にもたれた彼女の前で、ゆっくり慎重に膝を折る。
怪訝にセヴィランは目で追った。ユージンは背を向け、床の彼女をながめている。瞼を閉じた顔を見て、慎重に視線を胸元へ下げ、板張りの床に落ちていた、力ない左手をとりあげる。何かを見つけようとするように。
「──今さら罪悪感でもないだろう」
たまりかねて皮肉をほうるも、ユージンの方は見向きもしない。そむけた背中で問いかけた。「連れだと言ったな」
「あ?──ああ。そうなるか。今しがた、そういう話になったから」
面食らいつつもセヴィランはうなずき、部屋の戸口に肩でもたれる。
「知り合いでな、この娘は俺の。だが、危なかしくて見ちゃおれん。旅費はないわ、連れはいないわ、与太者には集られるわ。ただでさえ女の一人旅は物騒だってのに」
「手を引いてくれないか」
「──なに?」
彼女の前から立ちあがり、ユージンがおもむろに振り向いた。
「俺に譲ってくれないか」
じっと真顔で直視する。
唐突な申し出に面食らい、セヴィランは苦笑いで目をそらす。「──生憎だったな。亭主もちだよ」
「それが?」
「──。おいおい、勘弁してくれよ」
舌打ちで話を打ち切り、彼女に向かい、歩き出す。
「どいてくれ。この娘を寝かせてやらないと。遊び相手なら、よそを当たれよ。選り取りみどりだろ、お前なら」
片手でユージンを押しのけて、かがんで、床の腕をとった。彼女の脇に肩を入れ、力ない体をひきずりあげる。
ユージンが腕組みで壁にもたれた。
「気づいていないようだから、あんたに教えておいてやる」
目を向け、軽く顎でさす。
「あんた、化けの皮が剥がれかかっているぜ?」
「──今度はなんだ。さ、早く消えてくれ。この子が目を覚ます前に。今のはこっちで揉み消しておいてやるから」
ぐったり力ない彼女の爪先を引きずって、セヴィランは室内に運び入れた。
顔をしかめた彼女に気づいて、セヴィランは安堵の笑みを浮かべた。
「目が覚めたか。どこか痛むところはないか?」
枕の上で目を開けた彼女が、ぼんやり視線をめぐらせる。
その目が顔を捉えた途端、たちまち眉根をいぶかしげに寄せた。「……ど、どちらさま?」
「うん?──どうした、俺だよ。セヴィランだよ」
思わぬ事態に、セヴィランはあわてた。さては、打ち所でも悪かったか?
「……はあ? あんた、何言ってるの?」
寝台の敷布に肘をつき、彼女が肩を引き起こした。
あからさまに警戒した面持ちで、じりじり背もたれに後ずさる。「変なこと言うと、人を呼ぶわよ」
「ど、どうしたんだ、一体……」
「こっち来ないでっ!」
盾にするように枕を抱いて、彼女がまなじり吊りあげた。
「な、なあにが "セヴィランだよ〜" よ! セヴィランさんは、もっとずぅっとおじさんよっ!」
あぜん、とセヴィランは絶句した。彼女が何を言っているのか、まるで、さっぱり理解できない。なすすべもなく視線を泳がせ、ふと、手の甲で目が止まった。シミ一つない、なめらかな肌──
「……え」
ぎくり、と硬直、思考が停止。彼女の言葉が脳裏をよぎる。
《 セヴィランさんは、もっとずぅっとおじさんよ! 》
にわかに顔から血の気が引き、とっさにあわあわ手を振った。「あ──あ──いや、違う。違うんだ、俺は」
「"俺は"〜?」
彼女は顔をゆがめて警戒もあらわ。嫌な汗が背を伝う。
──まずい。
このままでは人を呼ばれてしまう。これではまさに不審者だ。ここの店主は旧知の仲だが、そのよく知る彼でさえ、疑いの眼差しを向けてくること請け合いだ。
「──そ、そうっ! 俺は、あの人の甥っ子だよ!」
きょとん、と彼女がまたたいた。胡散臭そうに眉根を寄せる。「えー? でもー。今、自分のことセヴィランってー」
「お、同じ名前なんだ偶然にも! なんでも急用ができたとかで、それで俺が呼びつけられて」
「急用〜? おじさんが〜? そんなこと言ってなかったけどぉ〜?」
疑わしげな視線に耐えかね、そそっ、とセヴィランは目をそらす。
何が起きたか察しがついた。
原因については不明だが、この際起こり得る可能性は一つ。
──呪が解けた。
あの日かけた「夢の石」への願が。つまり、当時の姿形に戻っている──?
唐突に絶望を突きつけられて、セヴィランは額をつかんで天井を仰ぐ。だって、どう足掻いても、他人には説明のしようがないのだ。
彼女は無言で眺めまわしている。すでに全身汗びっしょり。苦し紛れが口をついたが、そんな取ってつけような出任せは、さすがに通用しなかったらしい。こうなれば、早く逃げた方が得策かもしれない。通報されて引っ立てられる前に。
「──そう言われれば」
そろり、と出した足を踏みしめ、ふと、声を振り向いた。
彼女が唇に指をあて、思案げに小首をかしげている。
まじまじ彼女が目を向けた。「おじさんと顔、よく似てるし」
「し、親類だからね……」
すかさず合いの手、引きつり笑い。
不思議そうな面持ちでしきりに首をひねっているが、ちらちら彼女は盗み見ている。腑に落ちなさそうな様子だが、渋々納得はしたらしい。全面的に信用したというわけでもないが、そうかといって否定する決め手も見つからない、というところか。
「だ、大丈夫」
笑って、セヴィランは胸を叩く。
「あんたの面倒は俺がみるから。そう言い付かってきたからさ」
抱きついていた枕から、ちら、と彼女が目を向けた。「一緒に行ってくれるの? おじさんの代わりに?」
「そっ、そうだよ!」
「宿もご飯代も出してくれるの?」
「もちろん出すさ」
「──じゃあ」
わずかに乗り出し、ちら、と彼女は上目使い。
「替えの服とかお化粧品とか、あ、それからお土産代も?」
「……そんなこと言ったか?」
顔と顔をつき合わせ、思わず見合わせた視線の先で、ぱちくり彼女がまたたいた。
「あっ、いや! おじさんがっ!」
あわててセヴィランは片手を振る。「おじさん、そんなこと、あんたに言ってた?」
「……」
彼女は無言。またも不審げ。ささやかな歩み寄りも、どこへやら。
「い、いいよ。わかった……」
無言の冷ややかな圧力に負け、やむなくセヴィランは引きつり笑った。「出すよ、もちろん」
釈然としないが。
ふうん、と彼女が、盾にしていた枕をようやく下ろした。
だが、口を尖らせた顔つきは依然 (どうしよっかなー? 大丈夫かなー? けど、そもそも、この人誰よー?) と行きつ戻りつしている様子。
生きた心地もしないセヴィランが、なすすべもなく突っ立っていると、何かを決めたようにまたたいた。それとわかる外向けの顔で、にんまり彼女が笑いかける。
「じゃあ、しばらくお世話になりますぅ〜。これからよろしくぅ! セヴィラ……」
小首をかしげたまま、言葉が途切れる。
「な、なにっ? どうかした?」
今度はなんだ!?
「……や。なんかさー」
ぽりぽり彼女が、所在なげに頭を掻いた。
「だって、なんか悪くない? なんていうの? 気が引けるっていうか。だっておじさん、優しくて親切で格好よくて、よく見ると、けっこう顔いいし」
虚をつかれ、そわそわセヴィランは目をそらす。
「──ああ、いや、それほどでも」
「なんで、あんたが照れるのよ?」
はあ? と彼女が実に嫌そうに顔をゆがめる。
とにかくねー、と口を尖らせ、言い聞かせるように目を据えた。
「おじさんはあたしのヒーローなの! 颯爽とあたしのこと助けてくれて、悪い奴から守ってくれて、ご飯とかもおごってくれて、それを呼び捨てにするなんて」
「きっ、きっ、気にすんなよ、そんなこと」
予期せず盛大に持ちあげられて、セヴィランはどぎまぎ赤面で手を振る。「あ、なんなら俺のことはセヴィって呼べよ。みんな大抵そう呼ぶからさ」
言われて目をあげ、口真似をするように彼女がなぞった。
「せびー?」
「……。うん。いいよそれで」
幼児か己は。
「けど、おじさんもおじさんよね〜」
溜息まじりに枕を抱きしめ、彼女は顔をすりつける。「それならそうと言っといてくれても。だって、びっくりしちゃうじゃない。いきなり知らない人とかさー」
「……。い、色々事情があったんだと思うよ? どうにものっぴきならない理由が……」
もはや全身汗びっしょり。遠いまなざしで壁のシミを見つめる。急に思い出すから始末が悪い。
「それで」
彼女がおもむろに目をあげた。「それで、だあれ? そっちの人は」
「セヴィの連れだよ」
ぎょっ、と飛びあがって振り向いた。
「──なっ!?」
片頬引きつらせて、セヴィランは固まる。彼女に微笑みかけている。利発な少年を思わせる顔が。
「僕はユージン。よろしく、エレーン」
にっこり快活に笑った顔を、わなわな絶句で睨めつけた。
(──お、お、お前っ!?──お前っ! ユージンっ! いつからそこにっ!)
ユージンは横目で涼しい顔。
(いいのか? 秘密バラすけど)
ぐっと詰まったその肩を、親しい友のように笑って抱いた。
「な、セヴィ?」
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》