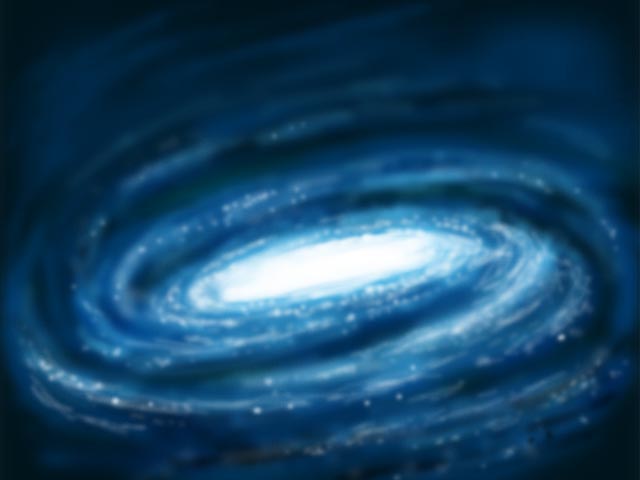
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章23
( 前頁 / TOP / 次頁 )
闇が、茫洋と広がっていた。
不確かで、不明瞭な、無音の"黒"が。
果てなく "黒"がただよっている。
動くものは何もない。ただ "黒"がただよっている。
いや、目を凝らせば、そこここで、まばらに光がまたたいていた。
あまりに微かな銀の光。ぱっと生まれ、すっと消える。チリ……と焦げたように闇に消え入る。
闇にちらばる無数の瞬き。それは生命そのものだ。今、生まれ、そして死んだ。光がまたたくその一瞬──まばたきをすれば見逃していたろうその刹那、今、一人が生涯を終えた。
無限に広がる虚空の闇で、意識だけが浮いていた。
前も後ろも、上も下もない。過去も、未来も、ここにはない。時の流れさえ、ここにはない。永久のただ中で漂っている。
恐怖も、焦りも何もない。ただ茫洋と広がる闇、無心でそれに浸っていたら、すべてのありようが自然と分かった。すべての事柄に理由はなく、なんの意味もないことが。生とは虚空の一部であり、同時に、虚空そのものだから。
これまでの日々の移ろいはまやかし。街も、空も、人の顔も。それらは網膜が創りあげた虚像。"世界"を写した膜を剥げば、そこには、常にこの闇がある。生きとし生けるもの全てに通じる──。
そして、同時にこの闇は、誰もが身の内に持っている。瞼を閉じれば、そこにある。すべてのものはここから来、やがては散って、戻り還る。それが永々とくり返される。闇が呼吸をするがごとく、その気の流れが個々の生。
音も光もない無のただ中、一点で芽生えたその核が、広く四方に飛散して、大気を創り、大地を創り、水を創り、命を創った。そして、今を迎えている。つまりは皆、同じもの──。
本当は、誰もが知っていることだ。
けれど、生を享けてしばらくすると、やがては薄れ、虚ろになる。実世界で生き抜くための情報の雪崩に押し出されて。
世に生まれ出た直後から、覚えるべき必須事項は山のようにある。母の顔。父の顔。敵。味方。泣き方。笑い方。二本の足で立つ方法。周囲に則した言語を解し、意思の疎通を図る方法──。
忘れたとて、支障はないのだ。自分が何者であるかなど。
己の生の本質など、当たり前すぎるほど当たり前のことだから。
ちか……ちか……ちか……と、かなたで銀がまたたいていた。
遠く、遠く、かすかにきらめく、三つの銀の小さな光。あるか無きかのくすくす笑い。笑いさざめく子供の声?
唐突に気がついた。耳を圧する静けさの中、この闇を占めるほどの、巨大な塊がうずくまっている。いや、闇そのものというべきか。いや、この猛禽の名は
──ポイニクス。
なぜ、そんな名を知っているのか。
なんだろう "ポイニクス"というのは。
遠いかなたで、闇がゆらぐ。
"黒"を波立たせ、影がよぎった。
影としか呼びようがない。それには色も形もない。それでも「在る」とわかるのは、周囲の闇が押しのけられて揺らぐから。けれど、ここには属さないから、輪郭を表わす線がないのだ。存在だけがあるその影が、ふっと現れ、ふっと消え入る──
すとん、と何やら腑に落ちた。
胸の底に押しこめた、ずっと、もやついていたことが。
あんな風にして、あの子も会いに来ていたのか。商都で亡くなった、あのケインも。
距離の概念のないこの虚空に、世界の裂け目から入り込み、別の異なる裂け目へ抜けて。延々と続く道を縮め、異なる二つの地点をつないで。
ぽつん、と光が現れた。
瞬きではない、確かな光だ。それが徐々に近づいてくる。
いや、あれは光ではない。
人だ。人の形をしている。
それは白っぽい人影だった。ゆっくり、たゆたうように近づいてくる。線が細く、髪が長い。女の人、だろうか。
人影が白く見えたのは、彼女の上着のせいだった。馴染みのある衣服ではなく、胸の前を合わせただけの、ボタンのない風変わりな衣服。そう、レーヌの漁師の"キモノ"のような。そして、爪先を覆う緋色のスカート──いや、あれはズボンだろうか。それにしては幅も裾もずいぶん広い。
ふわ、ふわ、ふわ、と闇の中、浮遊するように近づいてくる。地表のない虚空の闇を。
《 屈しては、だめ 》
凛と、彼女の声が響いた。
光源などないはずなのに、はっきり顔が見分けられる。
その顔に見覚えがあった。以前どこかで会っている。だから彼女を知っている。そう、たしか、彼女は"ツクヨミ" あれはノッポの彼といた頃だろうか。
……いや、果たして、本当にそうだったか。
彼女に関する記憶を辿れば、彼の顔がしきりと浮かぶが、二人が一緒にいるところを見たような記憶がどこにもない。ならば、なぜ、彼の顔が浮かぶのか。
《 屈しては、だめ 》
"ツクヨミ"が近づいてくる。
じっと見つめ、形の良い眉をひそめて。
《 屈しては、だめ。行ってはだめよ 》
どこへ「行くな」と言っているのか──ふと、あることに気がついて、怪訝に彼女を見返した。
細い眉を生真面目にひそめて、すがるように見つめるこの顔。そう、だって、この顔は──
《 行ってはだめよ 》
だって、この、目の前にいる娘は
《 行かないで。エレーンさん 》
……アディー?
「……う゛―……変な夢みたー……」
遅い朝の光が射しこむ、ひと気ない酒場の片隅で、エレーンは首をぐるんぐるん回す。まだ、どこかすっきりしない。起床してから結構たつのに。
何とはなしに嘆息し、卓の牛乳に手を伸ばす。
「……アディーの夢、かあ」
また、夢に彼女が出てきた。
なにか不思議な夢だった。やたらと壮大で安らかな、すべてがすっかり腑に落ちたような。感じていたのは全能感──いや、自分もその一部だった。
まだ頭がぼうっとして、夢の雰囲気に捉われている。頭の一部が麻痺したように。そのくせ夢の内容は、ぼやけて忘れてしまっている。夢に脈略など大抵ないが。
やんわりとまとわりつく夢の余韻を払うべく、ぐびり、と冷たい牛乳を飲み、焼きたての棒パンに、苺のジャムを塗りたくる。今日はパンで朝食だ。
ゆうべ連れになったあのセビーも朝ご飯に誘ったが、彼はまだ寝ていたいようで、結局部屋から出てこなかった。だから一人で階下に降りて、通りでパンを買ってきたのだ。宿の一階は酒場だが、朝は営業していない。
もぐもぐパンを咀嚼して、普段の元気を取り戻す。今日からは知らない人と一緒なのだから、ダラダラしてはいられないのだ。
面倒みるって言ったそばから、おじさんどっかに消えるとか、不貞寝したいところだが、寝てても先には進めないから、考えるのは止めにする。このまま旅を続ければ、どっかで会うかもしんないし。
どうも怪しいセビーについても思うところは色々あるし、なんか挙動不審だし、連れなら断然おじさんの方が良かったが、こうなった以上は致し方ない。そうだ、贅沢は敵だ。宿代、払ってくれるんなら良し。うん。これはこれで良し!
それにしても、なんの因果で、おじさんの甥っ子と行く羽目に? おじさんが連れというならまだしも、更にその甥っ子じゃ、そこらの他人と変わらない──
ふと、昨日の一件が頭をかすめ、むに、と口を尖らせた。
「──なあによ、また別の女とぉー」
あのケネルが街中を、知らない女性と歩いていた。親密そうに笑いながら。
ジャムの瓶を引っつかみ、スプーンを突っ込み、ぐるぐる回す。あの腹立たしい遭遇についてはなるべく考えないようにしていたが、ふとした拍子に顔を出す。あわただしい出来事や思考が不意に途切れた時。ふっと気が抜けた物事の合間。
はあ、と嘆息でうなだれて、卓をかかえて、くったり伸びた。
卓に伸ばした腕の先、握った瓶をながめやり、腕に顔をこすりつける。
「……きれいな、人だったな」
自分でも驚くほどに、心がダメージを受けていた。目鼻立ちの整った、浅黒い肌の異国人。いや、それ自体は不思議ではない。ケネルの居場所は、本来、隣国、カレリアにいる方が特例なのだ。隣の国に彼女がいても、別におかしな話ではない。ケネルを追って、ここまで会いに来たのだろうか。いや、案外ただの知り合いということも──
顔をしかめて、嘆息した。いや、心のどこかで分かっている。それだけではないことは。あの彼女はケネルにとって、特別な存在なのだということが。だって、あんな顔見たことない。あんなにくすぐったそうに笑った顔など。
「──むぅ。なによ、浮気者ぉっ!」
むくっと卓から起きあがり、ばりばりパンを噛み千切った。
縁から五本ほどパンが突き出た、茶色い紙袋を引っかかえる。極貧節約生活に甘んじてきたが、セビーのおごりだ構うこたない。セビーの分も買ってきたから、パンなら、まだまだいっぱいあるし──
次のパンを取ろうとして、ふと、やけ食いの目をあげた。誰かの視線を感じたのだ。
怪訝に視線を巡らせば、逆光になった窓辺に人影。戸惑い、エレーンは首をひねる。
(へ、変だな? ここ、誰もいなかったのに)
この席に着いてから、まだ扉は開いてないから、二階から降りてきた宿泊客? いや、階段を降りる音も聞かなかったような。
ガタリ、と椅子の音がした。
逆光の中で席を立ち、彼がゆっくり歩いてくる。光の中から踏み出して、徐々にその顔が露わになる。小柄な体格。冴えた相貌。淡々とした落ち着いた所作。
「あっ、おっはよー」
椅子の背をつかんで身をよじり、エレーンは彼に笑いかけた。誰かと思えば、あのセビーの連れではないか。いや、彼が言った「セヴィ」というのは、急用で消えたおじさんの方か?
「一緒に食べるー? ユージンくん も!」
あぜん、とユージンが立ち止まった。なぜか、度肝を抜かれたような顔つきだが。
「なに? どしたの? お腹すいてない?」
「──あ、いや、そうじゃなくて」
固まっていたユージンが、困惑したように笑みをつくった。「そういう呼ばれ方は、あまりしないものだから」
「でもー。いきなり呼び捨てにするっていうのもー」 ←他の選択肢はない
「たぶん、君より、大分年上だと思うけどね」
え? と彼を見返した。
「またまたまたあ!」
エレーンは笑って片手を振る。「どう見たって同い年でしょ、いいとこ。別によくない? ユージンくんで」
「……。うん。いいよそれで」
何か気持ちの持って行き場がなさそうな顔で、ユージンはうつろに微笑う。
気を取り直した様子で歩き出し、向かいの椅子に手をかけた。
「ここ、座っていい?」
「どうぞどうぞ。一人でつまんないなーって思ってたとこ」
椅子の背を引き、ユージンが卓の向かいに座る。「昨日はゆっくり話もできなくて。あいつがせっかちに追い出すから」
「それで一人でどうしたの? セビーだったら、いないけど」
「いや、君に興味がある」
ユージンが卓に腕を置き、ずいと身を乗り出した。「ねえ、話があるんだけどな」
「ん、なに?」
エレーンはもぐもぐ、首を傾げる。
ユージンが顔を寄せ、ささやいた。
「僕と行こうよ、あんな奴は置いてさ」
「……んん?」
つまり、二人きりで行こうってお誘いか!?──いや待て。セビーがいないと、ご飯代とか宿代とかが!
「色々言っていたようだけど、あいつ、下心あると思うよ?」
「と、友達のこと、そんなふうに言うのは、ちょっとどうかと思うなあ……」
冷や汗たらたら、たじろぎ笑う。
「友達?」
ふと、ユージンが聞き咎めた。
「そんなこと誰が言った?」
「……え?」
だったら、なんで、ここにいるのだ?
「僕が君を守ってあげるよ」
「……えっ? えっ? えっ?」
手でも握りそうな勢いだ。エレーンはわたわた後ずさる。「ちょ、ちょっ──ちょっと待ってちょっと」
「なにしてんだ!」
怒声の一喝がとどろいた。
店の奥を振り向けば、階段の途中で足を止め、セビーが真顔で立っていた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》