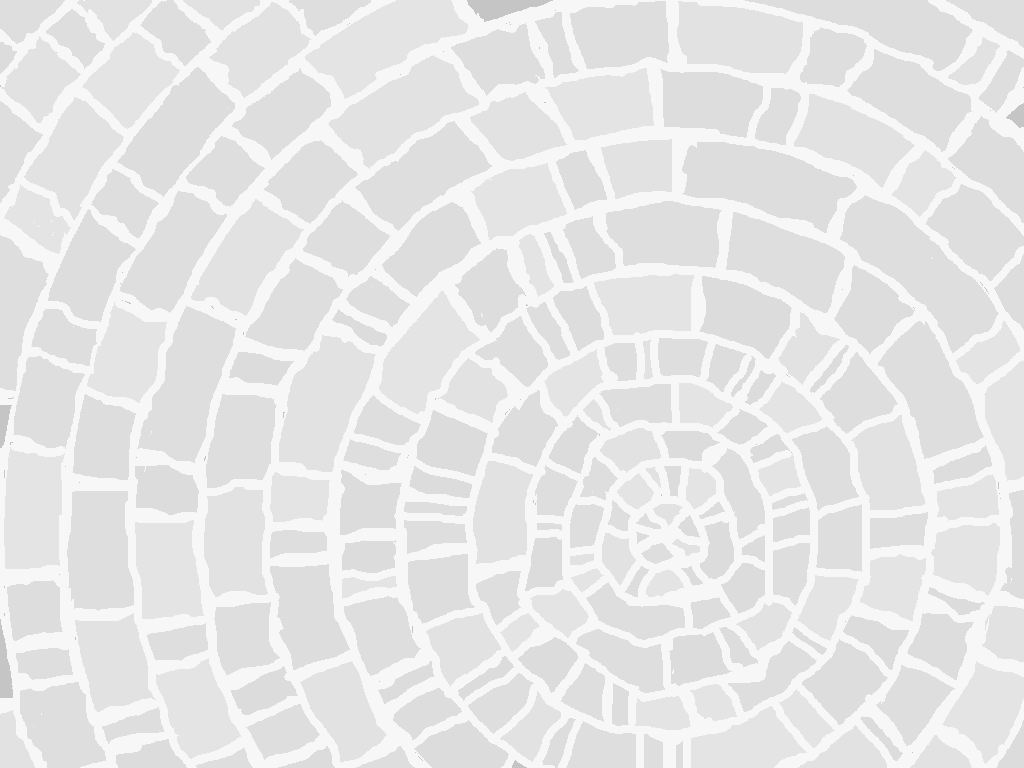
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章26
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「ねえ、どっちがいいかなあ?」
にんまり彼女が振りかえり、両手のそれを、顔の高さに持ちあげる。
「赤いリュックと、青いリュックぅ〜!」
「……どっちでもいいよ」
セビーはげんなり嘆息した。「大きさは同じなんだろ? なら、入る量も同じだし」
つまりは単なる色違いだ。入れ物の機能に遜色はない。
「セビー、適当に言ってるでしょおぉー!」
「──そっ、そんなことないって!」
ぶんむくれられて、あわてて振り向く。「じゃ、赤な。かわいい奴がいいんだろ?」
「ええー? 赤ぁ?」
青いリュックを彼女はもちあげ、名残惜しげにぶちぶち見やる。
「……そっかなー。青もいい感じだと思うけどなぁ〜。赤は、ほら、なんていうの? いかにも女の子ですぅ、って感じで」
「じゃ、青で決まりだな。なら、勘定済ませてく──」
「えええー? 青ぉ?」
なぜだか異議が噴出する。
赤いリュックをもちあげて、彼女はまじまじ再び検分。
「でも、こっちも捨てがたくない? だって、かわいさで言ったら、やっぱ赤でしょ。あ、だってだって、どーせ買うなら、かわいい方が──」
「……」
セビーはたそがれて突っ立った。この同じやりとりを、一体何度くり返しただろうか。
徒労感に襲われて、街路樹の日陰へ、げっそり踏み出す。「……なら、決まったら呼んでくれる?」
ぐい、と腕が引き戻された。
「もおぉぉー! セビー、真面目にやってよー」
ぷりぷり彼女になじられて、溜息で渋々振りかえる。「──んじゃ、こっちな? 女の子だから赤い奴」
「それそれそれぇ!」
彼女が顔をゆがめて指を振った。
「その"女の子だから赤"とかって、なんかすんごく安易じゃない?」
セビーは(勘弁してくれ……)とうなだれた。それなら一体どうせよというのだ。
そそくさ踏み出し、店から離れた。
「なら、好きなのをじっくり選んでくれ。俺にはそういうの、わからないからさ」
あっ、と気づいた彼女の手から、ひょい、と飛んで辛くも逃れ、ぶらぶら街路樹へ足を向ける。
眉をしかめて、町角を一瞥。
「──おい、なんの冗談だ」
牽制した先──町角で、人影が二つ後ずさった。
ばたばた路地を逃げていく。
セビーはやれやれとながめやった。「ゴロツキの残りかよ。どうなってんだか」
「ねーねー、セビー?」
くい、とシャツを引っぱられた。
又きたか……とうなだれて悟り、引きつり笑顔で振りかえる。「あっ、んじゃ、青の方で──」
「よかったのかなあ、ユージンくん置いてきちゃって」
彼女は視線をめぐらせて、まだ来ぬユージンを捜している。
「ねえ、やっぱ、わかんないんじゃない? だって、あそこからこんなに遠くちゃ」
セビーは眉をしかめて手を振った。「いいの! あいつのことは、ほっとけよ」
「なんかさー」
彼女がまじまじと顔を見た。
「セビーって、お父さんみたいだよねー」
……へ? と瞬き、彼女を見る。
「だって、すぐ、ユージンくんのこと追っ払おうとするし──なんていうの? "うちの娘に近づくなー!" みたいな?」
あんぐり絶句で己をさした。
「……お、おとーさん?」
今の話など忘れたかのように、彼女はすでに選定作業に戻っている。ああでもない、こうでもない、と両手を真剣に見比べて。それだけでは飽き足らず、店の中にまで入っていく。
「お父さん、か」
取り残された店先に立ち、セビーは苦笑いで彼女を見やった。
「──まあ、あんな感じか、娘がいれば」
女房との間に子があれば。
年齢的には、あれくらい──二十歳を超えるか超えないかくらいだ。店の品を物色する、いかにも身軽そうな娘の背中。ただ今、年頃真っ盛り。ビビが彼女に肩入れするのは、権力者に取り入ろうなどという、さもしい性根からではない。
セビーは小さく嘆息する。
子供好きなあのビビが、子宝に恵まれなかった原因が、自分にあるのは明らかだった。本来あるべき己の姿を、無理に歪めた自分の方に。
「やあ。探しちゃったよ」
通りからかかった快活な声。
(……なに言ってやがる)とセビーは舌打ち。
「あ、ユージンくんっ!」
声を聞きつけ、彼女が店から飛び出してきた。
店の前までユージンは歩き、あわてる彼女に笑いかける。「ずいぶん遠くまで来たんだね」
「ごめんね。この辺りの方が、お店が多いってセビーが」
「危うく見失うところだったな」
「そうなることを期待したんだがな」
セビーは白け顔で目を背ける。
ユージンが困った笑いで眉尻をさげた。「冗談がうまいね、彼は」
「もおぉー! どうして、そういう意地悪いうかな、セビーは!」
彼女がふくれて振り向いた。
「仲良くしてよ。友達でしょー?」
くるり、とユージンを振りかえる。
「ねえ、どっちがいいと思う? ユージンくんは」
両手にさげしは、赤いリュックと青のリュック。
左右をユージンは交互に見、彼女の顔に目を戻した。
「赤の方が、君には似合うよ」
ぱちくり彼女は瞬いて、赤のリュックを、じいっと凝視。「……そ、そっかな」
顔を赤らめて笑いかえす。
「なら、これにしよっかなあ〜!」
え゛え゛──とセビーは見返した。
(即決かよ!?)
こっちの時には、あんなに散々ごねたくせに。
なんとはなしにムカついて、ユージンの顔を、じとりと睨む。
むぎゅ、と何かが押し付けられた。
……なんだよ、と視線を下ろせば、胸の辺りに赤いリュック。
その値札をぶちぶち見、ぎょっとセビーは二度見した。
「さ、三万二千カレント!?」
思いがけない高額商品。そりゃあ、真面目に検討もする。
そこらの吊るしを、ささっと適当に引ったくった。「こ、こっちのにしない?」
「やっだあ〜。そんな地味な奴」
「……あのな。袋一つで三万カレントって尋常じゃないだろ」
思わず諭す。大真面目に。
「好きなの選べって言ったじゃない」
「それにしたって限度があるだろ」
「僕がもつよ」
ユージンが笑って割りこんだ。
「お近づきの印ってことで」
身をよじって札入れを出し、店の奥へと声をかける。
「これ下さい」
にわかに目を見開いた彼女が (ちょっとちょっと今の見たあっ?) と腕をバンバン引っ叩く。
「はい、いらっしゃい」と声がして、店主と思しき中年の女性が奥から出てきた。
鞄と代金を受け取って、愛想のよい笑みを、彼女に向ける。
「そうそう。手作りのお守りがあるんだけど。ウサギとか、キツネとか、ヒツジとか。よかったら、選んでいってちょうだいな」
「うわー! いいんですかあ? どれにしようかなあ?」
満面の笑みで彼女は飛びつき、いそいそ店に入っていく。
その背を見送り、ユージンがかったるそうに横目で見た。
「勘が鈍ったんじゃないの? "おじさん稼業"が長すぎて」
セビーは苦々しく舌打ちした。「そんなことより、取りこぼしたろ、ゴロツキを」
「もれなく飛ばしたはずだけど」
「──おい。飛ばしたってのは、どういう意味だ」
「聞かない方がいいんじゃないの?」
ユージンはそっけなく肩をすくめる。「もっとも、行き先は知らないが」
「さっきも言ったが、トラビアになら、一人で行けよ」
セビーは嘆息して向き直った。
「ひとっ飛びだろ、お前なら。何もこの暑い中、俺らに付き合うことはない」
ちら、とユージンが目を向けた。
「惚れた、と言ったら?」
セビーは白けて、顔をしかめる。「もう少し、ましな嘘をつけ。そんな訳があるかよ、きのうの今日だぜ」
「一目惚れってのがあるだろう?」
「狙いはなんだ」
「あんたこそ」
間髪容れずに言い返し、ユージンが平然と目を向けた。
「そっちこそ揉めるんじゃないか? あんた、女房がいるんだろ」
面倒そうに腕を組み、揶揄するように目を向ける。「あんたの女房、穏やかじゃないだろ、自分の亭主が若い女と」
憮然とセビーは鼻を鳴らした。「──そんなんじゃない」
「どうだか」
「──あの子は客だよ。うちの宿の上得意だ」
ふと、セビーは口をつぐんだ。
自分の言葉に、視線が揺れる。本当にそれだけだろうか。
確かに彼女は宿の客だが、同じ "あの夏" の客だとしても、これが他の客ならば、果たして、ここまでしたろうか。
自覚はあった。
この町で彼女に会ってから、好意の度合いが上がっている。むしろ、興味の度合いというべきか。そして、それは隣の男も同じ。だから、奪い合いが起きている。彼女の何が、そんなにも他人を惹きつけるのか──
胡散臭そうに目をすがめ、ユージンは出方をうかがっている。
明らかに、真に受けていない顔つきだ。だが、腹の探り合いをしたところで、この男が相手では埒があかない。
「──それはそうと」
やむなく話を切り替えた。
町並みの向こう、西の尾根を、苦々しく眺めやる。
「俺にもやっと、わかったぜ。お前が何を言っていたのか」
暗澹たる思いでつぶやいた。「──あんなものが目覚めたら」
「食われて、世界は終わるだろうね」
そっけなくユージンは言い捨てて、疎ましげに顔をしかめる。
「完全に目が覚めたらしいな。──やはり、潰しておくべきだったよ、昨夜の内に。今さら言っても、手遅れだけど」
「ああ、まったく手遅れだな」
セビーは苦々しくつぶやいて、西の尾根に目をすがめた。
「でかい竜が見えやがる」
袋物屋の店の中、エレーンは、むむう、と口の先をとがらせた。
「さあ、どれでも、好きなのを選んでちょうだい」
帳場の上に、おばさんが広げた"お守り"は六種。
ウサギとキツネ、ヒツジとネズミ。それからクマと、あろうことかタヌキ──。
「……ぬ、ぬう」
ぷい、とタヌキから目を背け、ウサギ達をエレーンは一巡。
けれど、なぜだか、また戻る。
とぼけたタヌキを取りあげて、むに、と口をとがらせた。
「──ふんだ。なあによ、浮気者!」
ぽいっと投げ捨て、ピンクのウサギを、むんず、とつかむ。
にんまり、おばさんに振り向いた。
「おばさん、これね! これにするぅっ!」
ウサギの紐を、鼻歌でリュックにくくりつけ、店先で待っている連れの元へと駆け戻る。
「おまたせっ!」
ふと、二人が振り向いた。
な、なに……? とエレーンは、たじろいで見返す。気のせいだろうか。今なにか、難しい顔をしていたような?
「──行くか」とセビーが、通りに目を向け、踏み出した。
ユージンも、おもむろに横に並ぶ。「行くのはいいけど、移動手段はどうする? 馬ってわけにはいかないよね」
ちら、と横目で (女の子がいるし) と仄めかす。
二人を追いかけ、セビーの隣にわたわた並ぶと、セビーはひと気ない街並みに、ぐるりと視線をめぐらせた。「片っ端から店を当たるか。一軒くらい、荷を運ぶ馬車があるだろう」
「どうかな。難しいかも知れないよ? 商都へ行くというならまだしも、僕らの行く先は西だから」
「なら、俺らが探すのは、ザルト方面行きってことか──」
「あ、やっぱ、ちょっと待って?」
交通手段の検討に入った二人の話をそわそわ遮り、えへへ、とエレーンは交互に見た。
「ごめん。すぐ戻るから!」
言うなり、店へと踵を返す。
怪訝そうな二人を置いて、先の店へと駆け戻り、ややあって、店を出た。
二人の元へと駆け戻る。
「ごっめ〜ん! お待たせお待たせっ!」
通りの左にいたユージンが、心配そうに顔を覗いた。「どうしたの? おなかでも痛い?」
「うっ、ううん! 平気! 大丈夫!──あの、ちょっと忘れ物しちゃって」
エレーンは笑って息を弾ませ、ぶんぶん首を横に振る。
「さっ、行きましょ行きましょ!」
呆気にとられて立っているセビーとユージンの間に割り込み、むんずと二人の腕をとる。
通りを歩き出しながら、ちら、と肩のリュックを見た。
取り替えてきた、お守りのタヌキを。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》