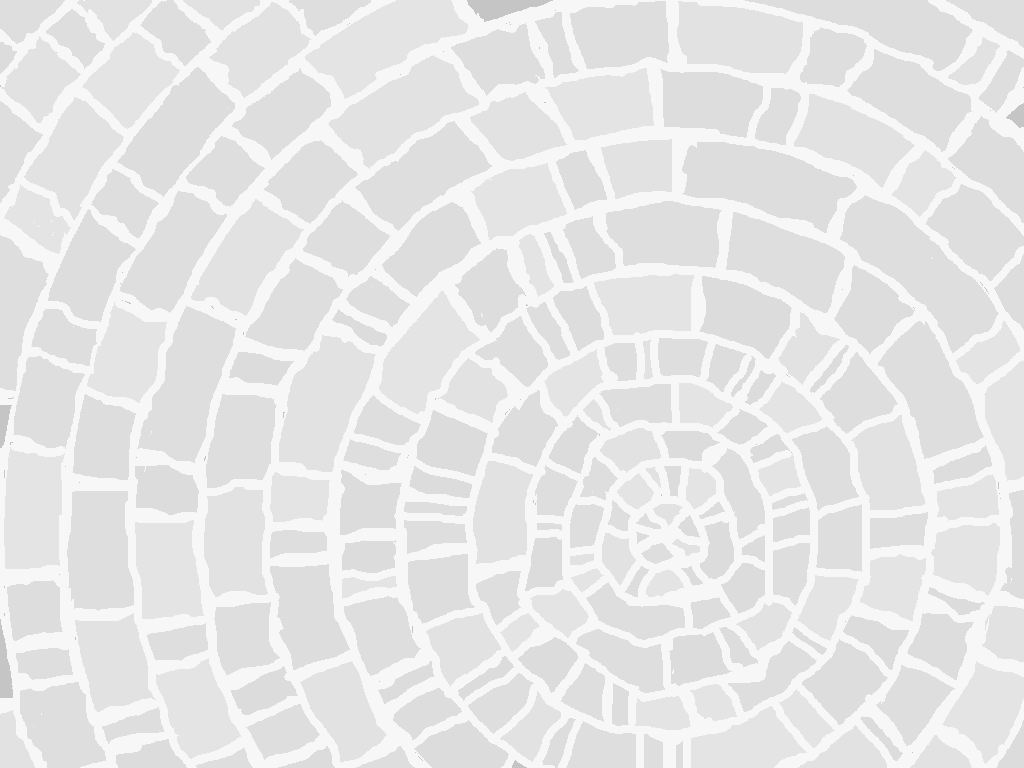
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章27
( 前頁 / TOP / 次頁 )
ゆるい癖のある薄色の頭髪。
そして、同じく茶色い瞳。ふとした拍子に、鮮緑を帯びる不思議な瞳──
頬杖で見やった向かいの席には、腕組みでふんぞり返ったしかめっ面。セビーの苦々しげな視線の先には、口元にうっすら笑みさえ浮かべた、落ち着き払ったユージンの顔。
甘物屋の円卓で、エレーンはげんなり頭をかかえる。
「んもう〜。どうして仲良くできないかなあ〜……」
二人はじっとり、飽きもせず睨みあっている。今回のきっかけは些細なこと、もう覚えてさえ、いないくらいの──。
わんわん耳に充満する真夏の日中のセミしぐれの中、エレーンはぐったり卓に突っ伏す。溜息まじりに指を伸ばして、グラスについた水滴をいじった。
(やっぱ、三人ってのが問題なのよね〜……)
なまじ三人いるもんだから、常に一人余ってしまい、仲間の取り合いが勃発するのだ。いっそ連れがもう一人増えて、四人になれば解決するのに。急用で出立したおじさんが、ひょっこり戻ってこないだろうか……わりあい真剣にそう願う。ちなみに、仲裁できれば誰でも可。
人影まばらな、昼のほの暗い店の中。
開け放った木窓の外は、まぶしい夏日と蝉しぐれ。天井にくっついた木の羽根が、くるくる惰性で回っている。馬車を求めて訪ね歩いたのは、さして長い時間ではないが、凪いだような日照りの熱気に、あっさりへこたれ、逃げ込んだのだ。
「ねー。注文しちゃおうよー。ケーキとかジュースとか充実してるみたいだしー」
そうとも。だから駄々をこね、渋るセビーをぐいぐい店に押し込んだのだ。
頬杖ついたユージンが、ちら、と横目でセビーを見た。「ごちそうさま」
「誰が貴様におごると言った?」
間髪容れずにセビーは一蹴、憎々しげに顔をしかめる。
気怠そうに首を回して、ユージンは白けた一瞥をくれる。「なんなら、もつけど? ここの勘定」
「いいっ! 払うから! 余計な真似すんなっ!」
ふっと哀れむようにユージンが笑った。「無理するなよ」
「──なんだとおっ!」
バアン──! と両手で卓を叩いて、セビーが椅子を蹴って立ちあがる。
「お前は一切、手を出すなっ!」
ぶんぶん指振り、いがみ合い勃発。
「ちょ!?──ちょっとセビー!?」
エレーンはあわててセビーのシャツを引っ張り戻す。「ちょっとちょっと! わかってる!? ここ、お店の中なんだからねっ?」
なんとか着席させようと、両手で胴にへばりつくが、セビーはがるがる食いつきそうな顔つきだ。ちなみにユージンはどうかといえば、毎度のことながら涼しい顔。もっとも彼は、常に何気に挑発的だが。
二人は朝からこの調子。この先もきっと、こうだろう。ずーっと、ずーっと、この調子──。
(……。もー、勝手にやってよね〜)
自棄になって匙を投げ、エレーンは脱力して突っ伏した。
ひんやり冷たい天板に、ぺったり頬をくっ付ける。
(もおぉー。なんで、すぐに張り合うかなあ……)
しかも、びっくりするほど些細な理由で。
意地だの矜持だのメンツだの、どうして、男どもはこうなのか。部隊にいた時も、そうだった。特にファレスとあのウォードが。
『 どうせ食うなら、飯を食え! 』
よく知る声が不意に轟き、ぎょっとしてエレーンは頬を浮かせる。
とっさに、わたわた見回した。
(げ、幻聴……?)
顔をゆがめて、首を傾げる。けれど、奴なら、確かに顔をしかめるだろう。この手の喫茶店の品書きを見たら。そうして、絶対こう言うのだ。
『 こんなものばっか食ってんじゃねえぞ。腹の足しにもならねえだろうが 』
ずきん、と胸に痛みが走った。
再び、もそもそ腕に突っ伏す。ぐりぐり顔を腕にすりつけ、はあ、と溜息で夏空を仰いだ。
「……どしたかな、ファレス」
目と鼻の先にいたのに、結局、顔を見られなかった……
「大丈夫?」
声に気付いて、振り向いた。
片腕をついて卓に乗り出し、ユージンが心配そうに覗いている。
「具合でも悪い?」
「──あっ、ううん。なんでもない!」
エレーンはわたわた、愛想笑いで起きあがった。
「ぜんぜん平気、大丈夫! ちょっと暑くて、バテちゃって」
そう、とユージンは言いながら、まだ眉をひそめている。気遣わしげな真剣な面持ち。
「……ごめん。別に、なんともないから」
いささか気まずくなってしまい、エレーンはそそくさ目をそらす。セビーは苛ついてばかりだが、ユージンは神経質なほど体調を気にする。とはいえ、その気遣いには、友人のそれのような親密さはない。もっと冷静で職業的な観察──たとえば、医者が患者を診るような。それでそんなことを連想したのか、クロウに似ている──そんなふうに思う。確かに、どちらも小柄で端正、中性的な雰囲気だけれど。つまりは、ぱっと見が似ているのか──。
まだ納得していないのか、ユージンはちらちら様子を見ている。
殊更な愛想笑いで、エレーンはそそくさメニューを取った。「さ、さあて! なんにしよっかな〜」
ぱたん、と厚紙のメニューを開く。
(……うわぉ!?)
思わず二度見し、顔面崩壊。
色とりどりの品書きには、イラストのケーキが盛りだくさん。くいくい、隣を引っぱった。「ねーねー、セビーはどれ食べるぅ〜?」
「──俺はいいよ、飲み物で」
セビーは窓に目を向けて、日中の通りをながめている。まるで興味のなさそうな横顔。
「そんなこと言わないで食べようよー。せっかくこんなお洒落なお店に入ったんだしー」
「いいって、俺は。これっぽっちの一切れに五百カレントも払えるか。粉も卵も、いくらでもないのに」
ぽかん、とエレーンは見返した。「……もしかして、セビーって、お菓子の類い作れちゃう人?」
「この程度、楽勝だよ」
「……へええ〜」
まじまじセビーの顔を見る。人って本当に見かけによらない。どこから見ても、ひょろりと今風のお兄ちゃんなのに。
あっ、と気づいて見返した。「──そっか。おじさん?」
「え、なに?」
「だから、お店を手伝っていたとか? おじさんのケーキ美味しいもんね」
急用で出立したあのおじさん──どくろ亭の店主の料理は、どれもこれも絶品なのだが、実はデザートも達人の域だ。所在地が田舎で人通りがないが。
ぎくり、とセビーが逆毛を立てた。
どこかぎくしゃくと振りかえり、ちら、と見やって、目をそらす。「う、うん。まあね、そんなところ」
「……。なによ。なんかあるの?」
「べ、別に?」
著しく不自然な、ぎこちない微笑い。声が甲高く裏返っている。
「──変なセビー」
セビーは時々怪しくなる。
なぜかそそくさ縮こまったセビーを、眉根を寄せてじろじろ見、エレーンは気を取り直してメニューを見る。
組んだ手の甲頬に押し当て、鼻歌でメニューにかぶりついた。
「えっとー。どれにしよっかな〜っ? 苺のケーキにレモンパイでしょ? あっ、チョコのケーキも捨て難いよね? あっ、それとバナナのタルト!──うっくぅ〜! やーん、迷っちゃうぅぅ〜!──あ、なにこれすんごい豪華!? あたし、この盛り合わせとかにしちゃおっかな〜?」
「あっ! 俺も俺もっ!」
ガタタ──と椅子がせわしなく鳴った。
……え、何事? と振り向けば、前のめりでユージンが挙手。
椅子でこそこそ背を丸めていたセビーが「……へ?」と面食らって振り向いた。
呆気にとられて二度瞬き、ユージンを指さし、ぷっ、と吹き出す。
「"俺も俺も"って、お前よぉ!? 普段はあんなにふてぶてしいくせにっ!」
腹をかかえて、ひーひー笑う。「く、クリームどっさりの盛り合わせなんて、大の男がよく食うな!」
「──い、いいだろ、別に」
顔を赤らめ、ユージンが着席。「……そんなの、人の好き好きだろ」
「別に、悪いなんて言ってないって。けど、さっきの顔ったら! お前、超ノリノリ(で──)」
「むー。けど、問題は、クリームの奴も捨て難いってことよねー」
ぱらり、ぱらり、とメニューをめくり、エレーンはぶつぶつ、大真面目に検討。
「でも、やっぱ、今日はチョコの気分かなあ〜?」
前後の脈略ぶった切り、ふい、とユージンに振りかえる。
「ねえねえ、ユージンくんはクリーム系にしない? あたしはチョコ系の盛り合わせでいくから。そしたら二人で半分こって良くない?」
ぽかん、とユージンが見返した。
返事のない相手に焦れて、首を傾げてエレーンは念押し。「え、なに? 盛り合わせでしょ? ユージンくんも」
「そう、だけど……」
「あ、もしかして全部食べたい? うーん。そしたら仕方ないけど──」
「──いや、そうじゃなくて」
困惑の呪縛が解けたように、ユージンがもどかしげに割りこんだ。
だが、視線がかち合ったとたん、ためらうように視線を揺らす。
すくいあげるようにして、うかがった。「……嘲笑わないんだ?」
「なんで?」
ぱちくりエレーンは瞬いた。むしろ同志は大歓迎だ。二人で注文して分け合えば、種類が二倍になるではないか。
ユージンは宙に視線を浮かせ、戸惑ったように口を開け閉め、卓に置いた片手を握る。
「……へ?」
エレーンはたじろぎ、どぎまぎ仰いだ。頭の上に、ユージンの手?
「……な、なになに? 急になに?」
放心したような顔つきで、ユージンはぽんぽん、手のひらで頭を叩いている。何かの加減でも見るように。いい子、いい子、となでるように。
卓にうつむき、打ち震え、もう一方の手を、ぐぐぐっ──と握った。「……くうぅ〜」
「え゛──」
ビビってエレーンは後ずさる。「……ななななんか付いてる? あたしの頭に?」
てか、なんだ、今の奇妙なうめきは!?
蝉がみんみん合唱する中、どんより微妙な沈黙がただよう。
ユージンが目を閉じ、くすり、と笑った。
「……ん。なんでもない」
ゆるり、とひとつ首を振り、笑みを残して、頭の手を引く。
胸をかかえるようにして両腕をつき、くすくす笑いながら顔をあげた。
「いいね、分けるの。半分こしよう」
「……へ?」
エレーンは呆然とまたたいて、片方の頬をひくつかせた。
こちらを見やったユージンは、すっかり、いつもの冴えた顔つき。落ち着いた佇まいを取り戻した模様。てか、今の奇態はなんだったのだ?
あぜんと成り行きを見ていたセビーを、ちら、とユージンが勝ち誇って一瞥。
「あんたはいいんだよね? 仲間はずれで」
すっかり見下した半眼に、ぐっ、とセビーは返事に詰まる。「──て、てめえ、ユージ(ン──)」
「ど、どっちがい〜いっ? ユージンくんは!?」
またも不穏な雲行きに、エレーンは大急ぎで割って入る。
「チョコの方? クリームの方? あたしはどっちかっていうとチョコの気分で──あっ、でも、桃とかオレンジとかの果物系も結構よくない?」
「おっ。いいね」
ユージンが椅子をガタガタ引きずり、見るからにうずうず真横に移動。
頭を寄せて、メニューを覗く。「なら、ケーキはそれぞれ頼んで、果物の盛り合わせ、別にとっちゃう?」
「あっ。そしたらケーキ、ひと口ちょうだい?」
「いいよ。そっちのも、ひと口ね」
「あっ! ねえねえ! そしたら思い切って、こっちのいっちゃう? この特盛りスーパーデラックスっ!」
だが、言い放った矢先に、うーむ、と失速。「……けど、ちょっと無理かなあ。五人前って書いてあるし」
「軽い」
うむ、とユージンが事もなげにうなずく。「俺、べつに全然いけるし」
「まじでまじで!? なら、いっちゃういっちゃう? これ、まじでっ!」
堅固な仲間意識が急速に芽生え、にんまり顔を見合わせる。
(……ユージンくんて)
ほくほく広げたメニューの影で、エレーンはたじろいで横を見た。
(こんな活き活きした人だっけ……?)
ユージンは瞳を輝かせ、注文の品を検討している。落ち着き払った雰囲気から一転、絶対に譲れないこだわりを持つ、男の子のような利かなそうな顔つき。
……んん、あれ? と気がついた。初めて「彼」を見た気がする。確かにいつでも、彼は卒なく微笑っていたが、
初めて、本当に笑った気がした。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》