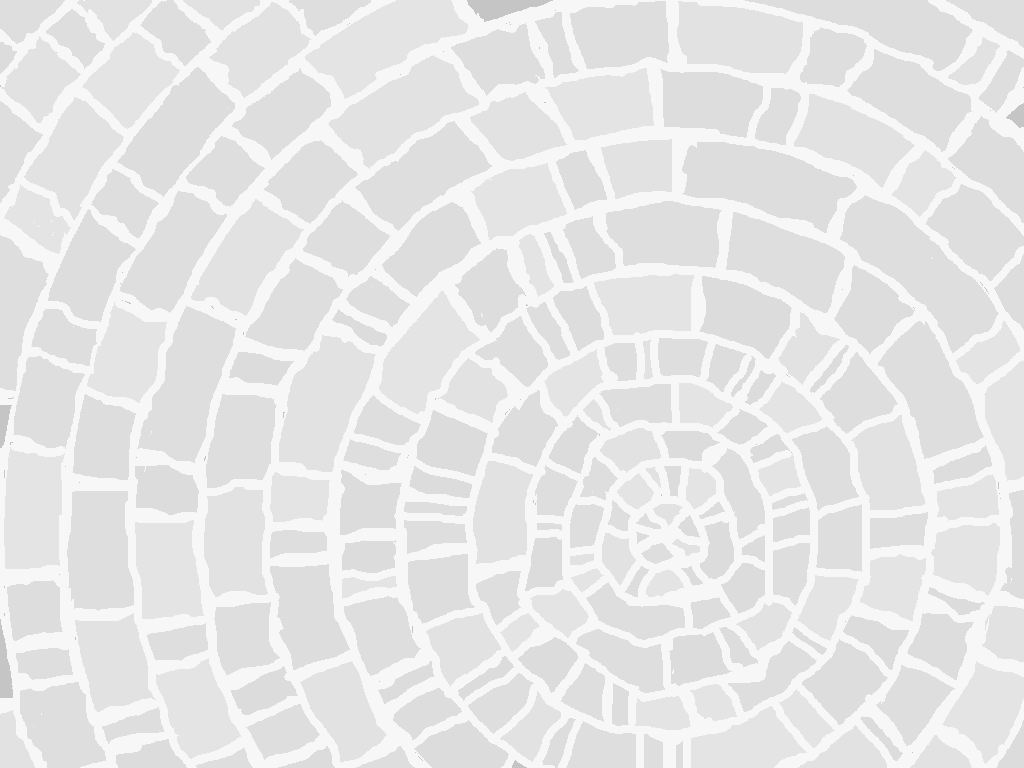
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章28
( 前頁 / TOP / 次頁 )
濃い陰の射す昼の通りを、ファレスは一人ぶらついていた。
しきりに首をひねっては、己の利き手をにぎにぎしながら。
得体の知れないものでも見るように、その手をファレスはいぶかしげに見おろす。「……あー。足りねえ」
なにか、柔らか成分が。
喩えるならば、そう、あれだ。あのあんぽんたん的ぷにぷに感。
とはいえ、いくら手軽とはいえ、宿の女将に抱きつくのはまずい。あれも相当ぷにぷしてるが、それはまた別の話だ。
ちなみにそうした用途なら、まさに娼家がうってつけだが、土地鑑のないカレリアで、まして、人家に紛れた闇営業など、案内がいなけりゃ辿りつけない。よって、自力で調達すべく、道行く女に声をかけてみたのだが──。
ぶらぶら道を行きながら、ファレスはつくづく首を傾げる。
「……問題はねえよな?」
あの商都の放蕩者、ラトキエ縁戚"赤頭"からも、高等技法の訓示を受けた。確かに奴にはダシにもされたが、一度の仕事で二を仕留める、あの腕前は本物だ。
だが、とはいえ、現状は……
本日の成績、無勝三敗。つまり、結果は惨憺たるもの。どいつもこいつも一言で、キッと鋭く睨みつけ、大股で彼方へ歩み去る。仕事のさなかや急ぐ時など別段用のない時は、うじゃうじゃ湧いて出るくせに。
振り向いた時には、異変はないのだ。変わったところは取り立ててない。むしろ、好感触といっていい。あわてた様子で笑みをつくり、顔を赤らめ、はにかむ素振り、とここまでは普段通りだ。
なのに、なぜだか、こっちが一言発した途端、まなじり吊りあげ、豹変する。ただの一人の例外もなく。
あの張り倒さんばかりの剣幕は、一体何が原因なのか。別に何をしたでもない。指一本触れてない。何度仔細に点検しても、なんの瑕疵も見当たらない。
本日これまで三度ばかり踏んだ手順を(どこが間違っている?)と反芻する。いつぞや阿呆に「口をつぐめ」などと言われたが、相手が苛つく余計なことなど一言たりとも言ってない。むしろ、話は要点のみ。この上なく簡潔だ。まずは獲物を捕捉して、速やかに近づき、笑顔で一言。
『 そこらに一発シケこまねえ? 』
なにが悪い。
ひゅるるん……といやに生ぬるい風が、石畳をさらって往きすぎた。
閑散とした町の通りは、がらん、と陰の中に静まっている。殊更に無関係を主張するかのように。
「……ま、後にするか」
ファレスは舌打ち、用事を片付けるべく、進行方向を変えた。
いささか面倒にもなってきたし、堂々巡りで埒があかない。大体、真昼の町中など、セミがみんみんやかましいだけで、女など早々歩いちゃいない。
開け放った戸口をくぐり、店奥に視線をめぐらせる。
「おう。いるか、肉屋」
肉塊の吊られた店の奥から、いらっしゃい、と声がした。
ややあってその本人、長靴履きの初老の店主が、濡れた石床に姿を現す。
「──あんた!?」
目を丸くして二度見した。
幽霊でも見るかのように、困惑気味に盗み見る。「……もう、出歩いていいのかい?」
「おう。その節は世話になったな」
先日、通りで倒れていたところを、宿まで連れ戻ってくれた親切な肉屋だ。
おそるおそるという態で、肉屋が下からうかがった。「きのう、行き倒れたばかりなのになあ」
「行き倒れじゃねえ」
即座にきっぱり、ファレスは訂正。ちょっと腹がひらいて死にそうになっただけだ。
で、と肉屋は怪訝そうにすがめ見る。「今日はなんだい。まさか、あんたが肉を買うってんじゃないんだろ?」
「おう。ババアの代理だ。今日の仕入れ分を取りにきた」
「どうかしたかい? みっちゃんが」
「……。それが、腰をやっちまったらしくてよ」
一瞬ファレスは返事を詰まらせ、きれいに片付いた作業台にもたれる。"みっちゃん"というのが、あの女将の名前らしい。
たちまち顔を曇らせた肉屋に話の先を促され、経緯をかいつまんで説明する。
今しがた、いつものように、台所で大量の芋を剥き、席を外して戻ってみると、女将が勝手口でうずくまっていた。当然、どうしたのかと声をかければ、あわてて振り向いた女将が突進、一緒にこけて押しつぶされたという次第。
そして、のしかかった肉塊の下から、やっとの思いで這い出した頃、女将が真顔で言うことには、
「……ぎっくり腰?」
「それが、客が三組いてよ」
ファレスはやれやれと顔をしかめる。「飯だのなんだの、世話があんのに、肝心のババアが寝込んじまった始末でよ。この先どうやってしのぐんだか。──たく。いい年したあんなババアが、一人で切り盛りしようってのが、そもそも話に無理があんだよ」
腕を組んで聞いていた肉屋が、溜息まじりに首を振った。「……あの倅がいりゃあなあ」
ファレスは苦虫かみつぶす。「──死んだ奴のことを言っても始まらねえだろ」
ぽかん、と肉屋が振り向いた。
「生きてるぞ? テル坊は」
「……あ?」
ぱちくりファレスも肉屋を見返す。
聞けば、女将の一人息子テル坊は「女将と喧嘩して飛び出して以来、トラビア近郊の親戚の家に立てこもっている」のだという。
「十年前に、みっちゃんが亭主を亡くしてからこっち、あそこは親一人子一人でねえ。けど、あんな小さかったテル坊も、もう、あんたと同じくらい(か──)」
「なんで、引きずり戻さねえ!?」
まなじり吊りあげ、ファレスはがなる。
肉屋はあいまいに笑って、頬を掻いた。「……うーん。まあ、そう言われてもなあ。意地っ張りでなあ、二人とも」
「意地とかそういう問題かよ!? いい年した大の男が、何をちんたら甘ったれていやがる! 年とったババアが一人で切り盛りしてるってのに!──つか、おっさん、いやに詳しいな?」
よそ様の家庭の事情に。
「みっちゃんとは昔馴染みだからね」
「──。ま、そんなわけだからよ。ババアが今、動けねえんだよ」
呼び名が出るたび一々もやもや引っかかるが、ファレスはとりあえず話を戻す。
「それで代わりに来たってわけだ。こっちにも晩飯の都合があるからよ。にしたって、ちょっと声をかけたくらいで、あのビビりようはねえよな実際。そういや、あの時、外に誰かいたような?」
不覚にも女将に押しつぶされたその直後、勝手口から立ち去った人影を見たような気がするのだ。こそこそ逃げるようにして。大きな麻の袋を持って。
はっと肉屋が、だぶついた頬をこわばらせた。「……そいつはもしや、白い上っ張りじゃなかったかい? ほら、こう、ごま塩頭の、色男の!」
「──言われてみれば、そんな頭のジジイだったような」
ファレスはつらつら、首を傾げて天井を見やる。「そういや、飯屋みたいな白い上っ張り──」
「抜け駆けしやがって! タツの野郎!」
ぎょっとファレスは振り向いた。「……あ? タツ?」
「裏通りの飯屋だよ!」
肉屋は憎々しげな形相で、わなわな拳を握っている。「あの野郎、みっちゃんにちょっかい出しやがって!」
「……。つまり何か? あのババアを取り合ってんのか?」
更にその上、切々と語った肉屋の口から、衝撃の事実が発覚した。
あんぐりファレスは口をあける。
「ババアの元恋人? おっさんが?」
だが、二人がまだ若かりし頃、女将が事故で記憶を喪失。
丁度その頃、女将に良い縁談がある事を知った若き日の肉屋は、女将に恋人と明かすことなく、自ら身を引いたのだという。以降、ずっと近くで見守りながら、密かに思いを寄せている。自らは独り身を貫いたままで。
「──健気っていうかよ」
ファレスは舌打ち、いささかげんなりと頭を掻く。「それで我慢してたってか。そんな白髪のジジイになるまで」
はあ、と嘆息、目を向けた。
「たく。なにをモタモタやってんだ。生きてる内にあと何度、あのツラ拝めるか分かんねえんだぞ、あんなとうの立ったババアだけどよ」
「"あんな"とか言うな」
むっと肉屋が口の先を尖らせる。
構わずファレスは、溜息まじりに腕を組む。「たく。黙って見てたとか、馬鹿じゃねえのか。欲しけりゃ欲しいと言やァいいだろ」
息を呑んで、口をつぐんだ。
眉をひそめて考えをめぐらせ、鋭く真顔で振りかえる。
「一番近い馬商はどこだ」
肉屋は面食らった顔で顎を引き、店の戸口を振りかえる。「──あ、ああ。サムの店がテオール通りの先にあるが──急になんだい。あんた、馬でも買うのかい」
「ああ、これから、すぐに出立する」
「──す、すぐに?」
あっけにとられて肉屋は瞬き、困惑顔で店奥を見た。「けど、そうしたら、みっちゃんとこの届け物は──」
「そんくらい、てめえで届けろや。配達も仕事の内だろうが」
「けど、なんだって、また急に」
「肉屋。人生で一等大事なこと、何だかわかるか」
ぽかん、と肉屋が瞬いた。「……じ、人生?」
顔をしかめて、ファレスは舌打ち。
「飯だよ飯! そんなこともわかんねえのかよ。人生で一等大事なのは飯だ」
眉根を寄せて固まった肉屋が、そろり、と下から顔色をうかがう。「……で、それが?」
「──たく! だからよ! いいか、肉屋」
ずい、とファレスは向き直った。
「飯ってのは大勢で食えば、それだけで大抵旨めえんだよ。それが腐ったサンドイッチでも」
「腐った……?」
承服しがたく絶句の肉屋。
「どうせ食うなら、その方がよっぽど得だって話だ。──ま、阿呆は百人分くっ喋るから、 あれ一人いりゃ十分だ」
一人で納得、うむ、とうなずき、ファレスはすたすた出口へ向かう。
はた、と肉屋が我に返った。「あ、ちょっと、あんた──」
「ついでにバカ息子、引っぱって来てやる」
店の戸口をくぐりつつ、ファレスは肩越しに言葉をほうった。
「そういうことだから、ババアに言っとけ」
夏日に凪いだ石畳の通りを、ファレスはせかせか馬商へ向かった。
ちら、と宿の方向を見る。
「ガキがいるなら、女将はよし」
ザイに馬を没収され、部下とも連絡不能となれば、移動手段は自力で手配するしかない。だが──
虚空に向けた上目使いで、ファレスはほりほり頬を掻く。
「……勘定は、ハジにでもつけておくか」
馬は、所持金で買えるほど、かわいらしい商品ではない。よって、請求書の宛先は、商都《 異民街 》バルサモ商会。
陽は強く輝いて、陰が濃く落ちていた。
敷きつめられた石畳が、白く夏日に焼かれている。暑い盛りに出歩く者もないようで、どこもかしこもひっそりしている。閑散とした往く手を見据え、ファレスは苛々と舌打ちする。
「──たく。何をモタモタしてたんだか」
阿呆の元へ乗り込めば、大方ウォードがごねるだろうが、力づくでぶん取ってやる。阿呆がいないと、
「──俺は、だめだ」
片頬をしかめて、足を止めた。
手が、傷のある脇腹を押さえる。
路地に入って、ぶつかるようにして壁にもたれ、肩で擦って、へたり込んだ。
額にびっしりと汗を浮かべ、脇腹を押さえて片足を投げる。
「──ち! 薬が切れやがった」
肩で荒く息をつき、身をよじって、隠しの奥の包みを探る。「──こんなもの、阿呆がいりゃ、一発なのによ」
体の回復は元より早いが、治癒力が更に跳ね上がる。驚異的に。
ようやく包みから煙草を取り出し、一本くわえ、震える指で点火する。
一服深く吸い込んで、空に向けて、ゆっくりと吐いた。
眉をしかめて額を揉み、じっと壁際にうずくまる。
石畳に落とした布の包みを、感慨なくファレスは眺めた。市販の煙草とは別にしてある、黒い巻紙の煙草の束──激痛を和らげ、正気を保つべく持ち歩いている、いわゆる麻薬だ。
前線に赴く傭兵ならば、大抵の者は持ち歩いている。前線で敵と斬り合う恐怖と、負傷の苦痛を和らげるために。この稼業特有の必需品ともいえる薬物は、隠れ里で生産され、一部が裏市場で流通している。
大まかにわけて、等級は四つ。銘柄は軽い方から、レスト、リゲル、ホーリー──奇遇にもウォードの愛馬と同じ名だ。
レストはたしなむ程度のお遊び用で、外向け用の高価なリゲルが、これとほぼ同程度。そして、最も強力で毒性の強いのがヘブン。ちなみに威力が強いほど、体への負担は大きく、依存性が増す。
軽い薬では効かないために、ファレスはホーリーを常備していた。商都を出てから、なぜか鎮痛剤が効かないために、やむなく使用に踏み切ったが、ここ数日、それさえ効かなくなりつつある。
朦朧とし始めた頭を振って、ファレスは眉をしかめて舌打ちする。
「──早く、阿呆を捕まえねえと」
苦痛が高じて動けなくなり、最強のヘブンに手を出す前に。
麻薬で廃人になる前に。
異様な空の色に気づいて、ぼんやりファレスは視線を向ける。
目を閉じ、舌打ちで首を振った。「──畜生。幻覚かよ」
西の尾根に居すわる曇が、
「……赤い竜に、見えやがる」
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》