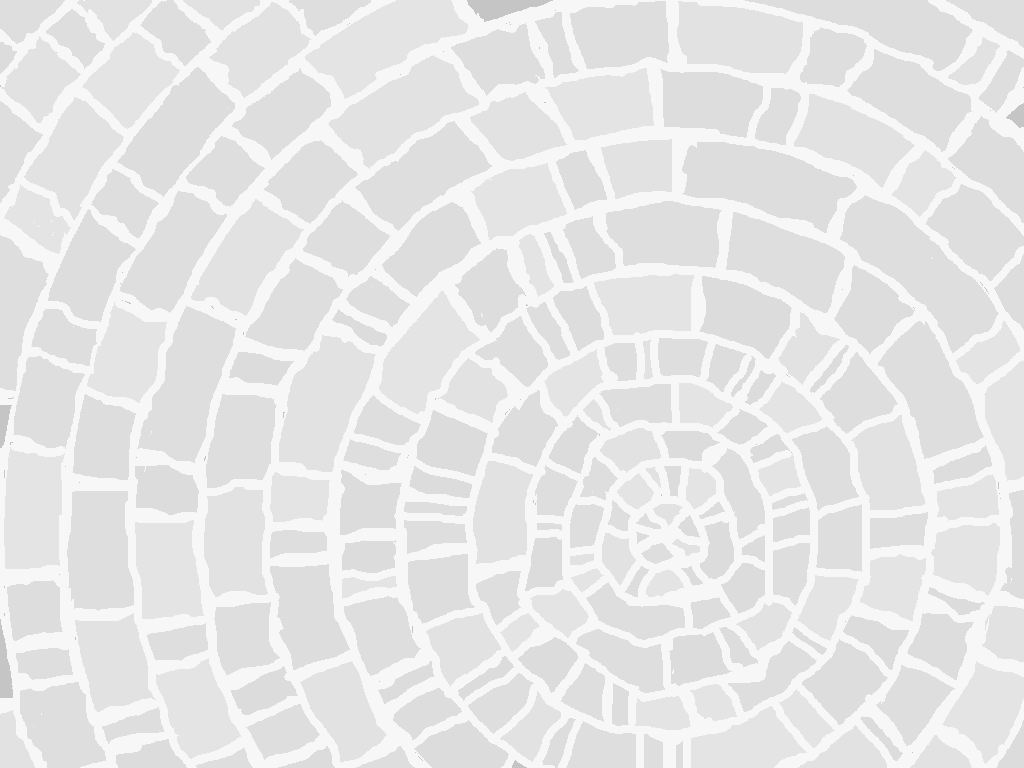
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章29
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「──なんだって?」
言伝を持ってきた店員の背を、セビーはあぜんと見送った。
ぶっきらぼうに肩を戻して、窓辺の席で渋面を作る。「なんで勝手に出て行くかね」
真昼の店内はほの暗く、甘物屋に人影はまばらだ。用足しに行くと席を立った彼女が、出て行ったのであろう木枠の出口を、顔をしかめてながめやる。店員がもってきた言伝はこうだ。
── ちょっと買い物に行ってくるね〜。
「たく。若い娘の考えることはわからん」
とんとん指で卓を叩いて、セビーはやきもき嘆息する。「また絡まれたら、どうすんだ。無謀ってのか考えなしってのか、こっちの方が肝が冷えるぜ。言ってくれれば、一緒に行ってやるものを」
向かいの席でユージンが、気のない頬杖で、ちらと見た。「あんたが一緒じゃ、買いにくい物もあるんじゃないの?」
「なんだよ、買いにくい物って」
「女の子だよ?」
呆れたように横目で見やる。「察しろよ。おじさん」
ぐっと詰まって、セビーは顔をしかめて頭を掻く。「──悪かったな。どうせ、俺はおじさんだよ」
せめて舌打ちで応酬し、がたん、と席を立ちあがった。
口をつけていたカップの縁から、ちら、とユージンが目をあげる。「行くの?」
「妙な輩がうろついている。誰かさんが 取りこぼしてくれたお陰でな」
「言ったろう、あらかた排除したって」
「一匹残ってりゃ十分なんだよ!」
「なら、俺はここにいるよ。入れ違いになった時、誰もいないと、まずいしね」
「勝手にしろ」
せかせか店をつっきって、セビーは帳場付近の出口へ向かう。
ふと、足を止め、振り向いた。
つかつか倍速で引き返し、窓辺の円卓に両手をつく。「……おい」
「なに」
「お前、ばかに素直だな」
「そう?」
ユージンは澄ましてカップをすする。
「もし、あの子が、俺より先に戻っても──」
疑わしげにジロジロ見、セビーは胡乱にすがめ見た。
「 さらうなよ? 」
あはは、とユージンは邪気なく笑う。
「信用ないなあ。まるで抜け駆けでもしたみたいに」
「 常 習 犯 だろ!」
卓を叩いて、セビーは一喝。
「しれっと流しやがってこの野郎。気づかないとでも思ったか。今朝、宿で何をしていた! 隙あらば、さらおうとしやがって」
「いやだなあ。妙な言いがかりはやめてくれる?」
「そういや、十八番だよな、その手のことは」
「──なんだよ、藪から棒に」
ユージンは苦虫かみつぶす。「妙な話を持ち出すなよ」
「事実だろうが。え? 何百人いるんだ? お前んとこのガキどもは」
面倒そうにユージンは嘆息。「さあね。数えたこともない。養えるんだから、いいだろう。そもそも、あんたには関係ないし。──なんで、そんなにムキになるのさ。あの娘はただの客なんだろう?」
「──色々あんだよ、事情ってもんが」
「あんた、あの娘に何したの」
予期せず鋭く突っ返され、セビーは虚をつかれて返事に詰まった。
「ふうん。後ろ暗いことがありそうじゃない」
頬杖で探るユージンから、苦々しく目をそらす。「お前には関係ない。そんなことより──いいか、もう一度、言っておくぞ」
気を取り直して振り向いた。
「うちの娘に手を出すな!」
ぽかん、とユージンが見返した。
呆気にとられて口を開け、憚るように顔をゆがめる。「……隠し子?」
「──そうじゃない!」
「だって、今、娘って」
「だから、それは──」
もどかしげにセビーは舌打ち。「だから、"みたいなもの"って意味だろうが。汲めよ流れを」
「やっぱり隠し子……」
「だからっ! ひと夏、店に友達といたから、毎日、世話をしてたんだよ! 朝から晩まで飯を作って! また妙な真似をしてみやがれ。今度は容赦しないからな!」
ユージンはカップを卓に置く。
椅子の背もたれに身を投げて、怜悧な目を振り向けた。
「本気で俺とやるとでも?」
セビーも真顔で腕を組む。
「返答次第だ」
「互角だと思うよ?」
そっけなくユージンは言い置いて、一段声を低くする。「分かっているだろ、共倒れがオチだ。そうなればお互い、無傷じゃ済まない」
「だったらどうした」
「自信がある、というわけだ」
窓の外の町なみは、強い日射に凪いでいる。
蝉の音ひろがる暑い盛りで、人の姿は相変わらずない。からん、とグラスで氷が鳴る。
「──なんて顔をしてるのさ」
くすり、とユージンが頬をゆるめた。
さばさばと身じろいで、椅子の背もたれに腕をかける。「どこから声を出してるんだよ。早くハゲるよ? おじさん」
「余計なお世話だ! 今、ここで、以後、手を出さないと約束しろ!」
手を伸ばし、ユージンは微笑ってカップをとる。「決まっているだろ。そんなの、もちろん──」
不敵に笑って見返した。
「保証はしない」
昼の街路を歩きつつ、エレーンはきょろきょろ、閑散とした町なみを見まわした。
「そう。確か、この辺り……」
時計塔のある中央通りから、左に二つ、通りを入った──。あの時は日が暮れかけていて、今とは様子が違うけれど、大きな青旗が掲げられた、町角の商館に見覚えがある。
白っぽい石畳。黒い鉄の街路灯。三車線ある舗装した馬車道。確かにゆうべ、ケネルはここを歩いていた。
「──んもう。どこへ行ったのよ」
リュックにつけたお守りの、タヌキのとぼけたその顔に、ぶちぶち口を尖らせる。
「外、けっこう暑っついんだから〜。もー。早く出てきてよー」
はた、と気づいて、またたいた。
「……ちっ、違うわよ?」
無人の路上でわたわた手を振り、とくとタヌキに言い聞かせる。
「このタヌキに取り替えたのは、単にこの子が気に入ったからで、ケネルの代わりにしようとか、そういう意味じゃないんだからねっ? ケネルのこと探してるのも──そ、そう! だって、あの時の返事をしないと!」
『 俺とくるか 』
ぎくり、と赤面で硬直した。
はたと二秒後、我に返って、周囲の視線をあわてて確認。
幸い誰にも見咎められず、胸をなで下ろして歩き出した。あの光景がぶり返し、顔がほてり、胸が高鳴る。夏日にさらされた時計塔の屋上。ばたばた風に打ち鳴る旗。顔を覗くケネルの瞳──。
「……。だけど、どうしよう」
はあ、とエレーンはうなだれた。それを思うと、怖気づく。まだ、あやふやな所をさまよっているから。だって、ケネルと一緒に行く? それとも、やっぱり一緒には行けない? 次にケネルに会ったなら、彼にどう応えれば──
自分には夫がいる。自分の連れ合いはダドリーなのだ。国王の許可こそ下りていないが、立場は一応、既婚者だ。
確かに、先に裏切ったのはダドリーの方だ。妾の存在を隠していたし、それどころか子供までいた。軽率で身勝手な彼の保身が、密かに描いていたささやかな夢も、明るい未来も目茶苦茶にした。彼は空っぽの階級だけを与え、本来収まるべきだった柔らかな居場所を奪ったのだ。
それでも無断で彼を裏切り、意趣返しするのは何か違う。釈然としないし、やっぱり筋が通らない。仮に「行く」と決めたとしても、それならダドリーにそう告げて、きちんと区切りをつけないと。けれど、それには、今は時期が悪すぎる。
ダドリーは今も戦の渦中だ。自分の不用意な言葉のせいで。
あの時、余計なことさえ言わなければ、彼は戦地になど飛び込まなかったし、苦境に立たされることもなかった。けれど、今なら、まだ何とかできるかもしれない。
自分にならば、できることがあるはずだった。
ラトキエを率いるアルベール様とは、今は簡単には会えないだろうが、公爵夫人の立場なら、向こうも無下には断れまい。なんとかして彼と会うのだ。そして、進軍を止めるのだ。
可能性はあるはずだった。彼が知らない当時の事実を伝えることさえできたなら。その芽をつんで見て見ぬ振りで、ダドリーを見捨てて行くなどできない。けれど、今は──
リュックについたお守りのタヌキが、とぼけた顔で見返していた。
ぎゅっ、とその手に力がこもる。けれど、今は、
──ケネルに会いたい。
深呼吸して、目を閉じた。
意識を凝らして、大気を探る。あの感じが、どこかにないか。ぴん、と糸が張りつめたような、一方向に引っぱられるようなあの感じ……
蝉の音が、耳に届いた。
この街の様子を思い浮かべる。ひと気ない街路。路上のかげろう。一筋、汗がこめかみを伝う。
「……だめか〜」
つめていた息を吐き出して、エレーンはゆるく首を振った。いない。たぶん。この辺りには。
それらしい気配は、どこにもなかった。なんの取っ掛かりもつかめない。瞼を閉ざした薄闇が、茫洋と取りとめもなく広がるばかりで。もしや、もう出立ってしまった? ゆうべ連れ立っていたあの女と……
むくむく光景がよみがえり、むっ、と眉が吊りあがった。
ゆうべの姿が頭をよぎる。連れ立って歩く 楽しげな 顔──。
「なっ、なによ! デレデレしちゃってさあっ!」
むかむか憤怒がこみあげて、タヌキに口を尖らせる。
「なによ、ケネルの浮気者。まだ返事もしてないのに、もう、あんな別の女と!──いいもん、ケネルがその気なら、あたしにだってセビーがいるもんっ!」
ぽい、とタヌキを打ち捨てた。ずんずん、ふくれっ面で歩き出す。
「ユージンくんだって、いるんだからっ」
そうだ。そろそろ戻らないと。あんまり遅いと、きっとセビーが心配する。おじさんに後を任されて、やたら使命感に燃えているから。それに、二人だけで残しておけば、また喧嘩するに決まってる。
車道をわたり、路地を過ぎ、見覚えのある町角に出た。
昼のひと気ない歩道を戻り、甘物屋への道に差しかかる。店先へ続くゆるい坂道。何とはなしに上げた視界に、ふと、それを見咎めた。
「──セビー?」
上り坂の街路樹の向こうに、背中を向けて立っている。あんな所で佇んで、煙草でもふかしているのだろうか。
「や、やっぱ、捜しに来ちゃったかなあ〜」
思わずにんまり頬がゆるみ、るんるん鼻歌で足を向けた。
迎えに来なくたって戻るのにぃ〜、と満更でもない照れ笑いで、人影の背中にほくほく近づく。「せびいぃ……」
口をつぐんで足を止めた。
ささっ、とあわてて町角に引っ込む。
左隣の町角へと歩き、今の坂道をそそくさ迂回。誰か、いた。彼の向こうに。白っぽい、小柄な夏服の。
柔らかそうな長い髪──女の子だ。髪のかかる華奢な肩。彼を見あげて、楽しそうに笑っていた。その奥にも、もう一人。街路樹にもたれて彼女らを見おろし セビーもやはり楽しげな笑顔で。
一つ隣の坂道を、呆然としながら、てくてくのぼる。むに、と口を尖らせた。
「……な、なあによ。セビーってば、あんな所で」
気を抜いた、優しげな横顔だった。あんな顔こっちにはしないくせに。そりゃ、なんか自分のもんみたいに思っていたけど、よくよく考えれば他人だし、何をしようがセビーの勝手だ。とはいえ、ここに異性がいるのに、自分の方はまるっと無視で、別の女の子といちゃついてるとか、軽んじられているようで釈然としない。
なによぉ、と肩越しに毒づいて、ぷい、と道の先に目を戻した。
「いーわよ。あたしにはユージンくんがいるもん」
街路樹の青葉がゆれる、甘物屋の白い壁。迂回したお陰で裏手に出てしまったが、こっちの道なら、さっきまでいた窓辺の席が見えるはず。
そろそろ店に近づきながら(どこにいるかな? ユージンくんは〜)と鼻歌の薄笑いで店内をうかがう。
顔をゆがめて固まった。
そろり、と一つ手前の街路樹まで戻り、左右の手足を同時に出して、ぎくしゃくそのまま引きかえす。
「……そ、そっか」
ゆるい坂を降りながら、そわつく頬をぽりぽり掻いた。「そっか。そうよね。そういうこともあるわよね……」
さっきの窓辺に──窓際の席にユージンはいた。
一人で、背を向けて座っていた。そして、円卓の前には女子が三人。きゃいきゃい彼を囲んでいた。顔を赤らめて楽しげに。
店を出てから、まだいくらも経ってないのに、セビーもユージンくんも、あっという間に……
今見た光景を反芻しながら、エレーンはあぜんとつぶやいた。
「も、もてるんだ、二人とも……」
なんというのか漠然と焦った。そう、よその女子からしてみれば、彼らはそういう対象なのだ。あの二人といる時は、不思議と考えもしなかったけれど。いや、彼女らが惹かれる理由は分かる。
あの二人は、確かに目を引く。他より気配が濃いというのか、何かいやに存在感があるのだ。顔だって悪くない。服のセンスも悪くない。ああして取り囲まれるのも無理はない──。
途方に暮れてしまったような、ふさいだ気分に襲われて、エレーンは軽く息をついた。「……いーわよ、だったら一人で行くもん」
今度は本当に買い物に。
後ろ手にして、ぶらぶら歩く。
「やっぱ、一人になっちゃうかあ……」
がらん、と街は静まっている。
買い物客がいないから、軒を並べる店々も開店休業の状態だ。舗装した白っぽい石畳。夏の強い照り返し。空が、青い。
ふと、足を止め、見返した。
たった今、路地の先を、よく知る男が通過した気がしたのだ。
そして直後に、鬼気迫る 形相の女。つまり、男の方が追われている?
「でも、今の、あの人って……」
あれ? と眉をしかめて首を傾げた。けれど、なぜ、ここにいるのだ? 商都から遠いこんな街に。そう、存分に不良を主張する、あのど派手な赤い頭は──
昼に凪いだ路地の先を、ぽかん、とエレーンは見返した。
「……レノさま?」
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》