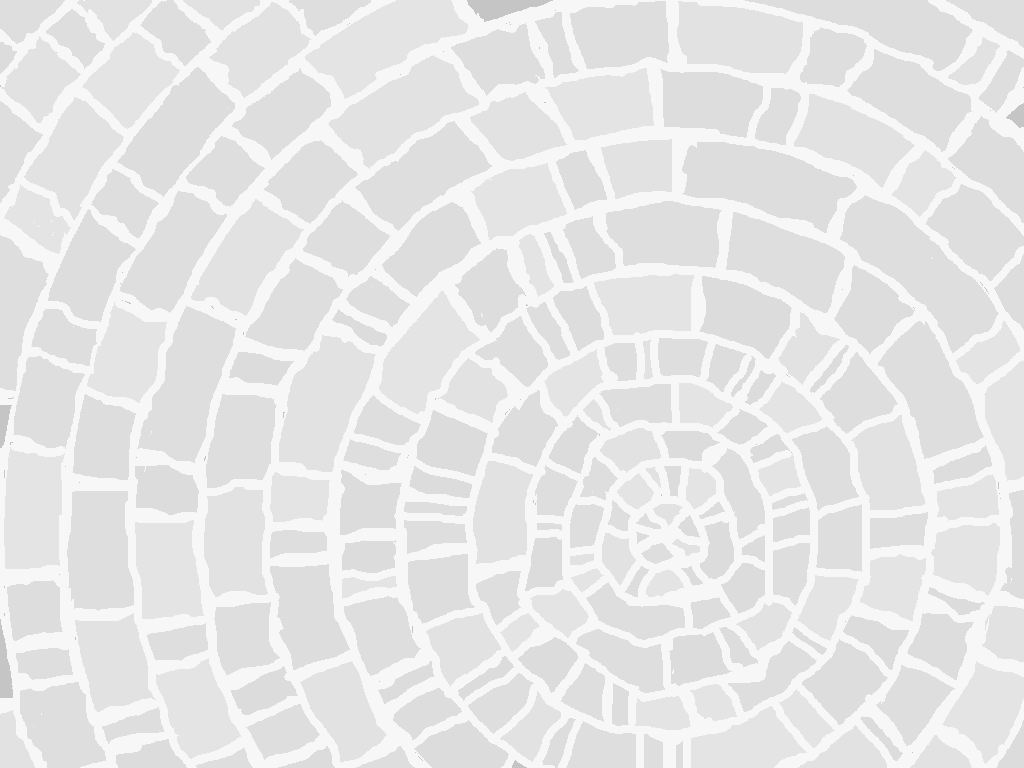
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章33
( 前頁 / TOP / 次頁 )
死神のようだ──
そんなことを、ふと思った。
陰の中にいるからだろうか、男がいる一角だけ、どんより大気が澱んでいる。
まだぼんやり霞がかった朦朧とした視界の中で、いやに骨ばった男のその手が、また酒瓶を取りあげる。
奥の壁の木窓から、夏日が鈍く射していた。
男は光を避けるかのように、左壁の暗がりに埋もれ、一人で酒を飲んでいる。年恰好は四十絡み、いや、五十年配といったところか。艶のない黒い蓬髪、土気色のこけた頬、赤銅色の痩せぎすの胸、そして、顔色がひどく悪い。
──病気、だろうか。
そんな印象を、ふと抱いた。
どこか荒んだ風貌のせいか、死神のようだと思ったが、あの顔色の悪さはむしろ、死神に取りつかれた対象という方がしっくりくる。
肩の痛みに顔をしかめて、エレーンは板張りの床に手をついた。
顔をあげ、怪訝に視線をめぐらせる。
酒場にいるようだった。
時の中に沈んだような廃墟を思わせる木造の店内、間隔をあけて円卓が四つ。夕刻からの営業に備えて昼は休んでいるのだろう、がらんとして、ほの暗い。
窓は奥の壁に一つきり。向かって右手に階段があり、左手には飴色のカウンター、壁には酒瓶が並んでいる。身をよじって振り向けば、夏日を四角く切り取って、戸口があけ放たれている。
その脇で男が五人、所在なげにたむろしていた。与太者ふうの風体だ。
なぜ、自分がここにいるのか、その顔を見て思い出した。
逃げ込んでしまった袋小路で、与太者の一味に追いつめられ、やむなく同行を決めた直後、ボリスが与太者につかみかかったのだ。いや、ボリスだけではない。続いてブルーノとジェスキーも。
見る間に乱闘が再開され、あわてて制止しようとした。その矢先、突き飛ばされて壁にぶつかり、それきり意識がなくなった。
そして、ふと目覚めたら、見も知らない酒場の床に、こうして無下に転がされていた。
どこかに強くぶつけたか、頭の後ろがズキズキ痛む。ここは一体どこなのか。あの街路の袋小路から、どちらへ、どれぐらい移動したのか。あれからどれくらい経ったのか。
一味におとなしく従って、根城までの道順を覚えておくつもりでいた。なのに、不覚にも気絶して、その間に運ばれてしまった。ボリスたちはどうなったのか。ジェスキーの目は大丈夫だったろうか。あの後、自分はどんなふうに──
ぎくり、と頬が強ばった。
あわてて衣服を点検する。すでに骨身に染みている。あの傭兵団での体験で。
男ばかりの武力集団では、女性は特殊な標的なのだ。むろん、ケネルを初めとする一部の者には全幅の信頼を置いているし、隊員も部隊の定めに従う。けれど、常に全員がそうであるとは限らない。まして、他人を拉致する邪な輩が、紳士であるとは思えない。いや、傭兵のような技量はなくても、対外的な制約もなく、律する体系が何もない分、一味の方がむしろ危険だ。
意識が途切れた「空白の時間」が気にかかる。
相手は野放図な無法者だ。ファレスにも散々、考えの甘さを注意された──。
固唾をのんだ息を吐き、肩からゆっくり力を抜いた。
へなへな床にへたりこみ、ほっと小さく息をつく。
(ぶ、無事……)
ブラウスのボタンはかかっている。裂け目や破れも、見たところない。体に異変は感じられない。どことなく腑に落ちないが。
そう、意外だった。野犬のような無法の輩が、女性を根城に連れ込んだからには、即刻襲いかかっても、おかしくはない。
だが、手荒な扱いは受けていない。いや、床に放り出されていただけで十分手荒といえるだろうが。とはいえ、まだ、少なくとも、深刻な事態には至っていない。それは確かだ。
いかにも危うい、こんな状況での幸運に、いささか拍子抜けしながらも、気を取り直して身の回りを見る。
(……どうしよう)
チリ、と焦燥が胸を焼き、眉をしかめて唇をかんだ。
持ち歩いているポシェットがなかった。買ってもらった赤いリュックも。少し前に詰め替えた、借り物の制服が脳裏をよぎる。
(あたし、リナになんて言ったら……)
何を置いてもあれだけは、手元に置くつもりでいたのに。
荷物まで運んでくれるほど親切ではなかった与太者たちは、相も変わらずたむろしている。扉の脇に突っ立ったままで。
ふと、その光景に違和感を覚える。なぜ、誰も座らないのだろう。
この暑さではばてるだろうし、座席ならば十分ある。奥ではああして飲んでいる者さえいるというのに──
そうか、と目を見開いた。
あの男は立場が違う。あれこそ一味の頭目なのだ。
だから無事でいられたのかと、にわかに理由が腑に落ちた。手下が頭目をさしおいて、獲物に手を出すわけにはいかない。けれど、当の頭目は、一人でああして飲んでいるばかりで、幸い関心を示さない。
つまりは奥の男こそ、この一連の騒動の首謀者。馬群で大陸を南下中、何度も部隊を襲撃した、悪名高い
海賊ジャイルズ。
「──こっち来な、姉ちゃん」
しゃがれた声に振り向いた。
奥の卓で座席にもたれ、ジャイルズが気だるそうに目を向けている。
(きた……!)
へたりこんだ板床で、エレーンはすくみ上って目をそらす。
戸口でたむろす手下の一人が、面倒そうに顎をしゃくった。
早く行けと促している。むしろ逃げ出したいところだったが、観念して立ちあがった。
店の唯一の逃げ道は、手下たちにふさがれている。拒んでぐずぐずしていたところで、どうせ手下がやってきて、引っ立てられるに決まっている。
胸で握った手の中に、薬指の指輪をそっと隠して、警戒しながら卓へと近づく。
グラスをあおるジャイルズは、酔っているのか捨て鉢な仕草。それでいて濁ったその目は、狡猾に何かを狙っている。
「女だてらに大した度胸だ」
喉でくつくつ、ジャイルズが笑った。要求通り同行した旨、手下から聞き及んでいるのだろう。骨ばった指先で、持ち上げたグラスをジャイルズは揺らす。
「警戒厳重な領邸から、宝を盗み出してくるってんだからよ」
面食らって見返した。「……え?」
思いがけない言葉に戸惑う。いや、これと似たようなことを、前にも誰かに言われなかったか?
「お前が持っていたとはな」
顔をゆがめてジャイルズは、苦々しく舌打ちする。「虚仮にしやがって、あの野郎。あんな野っ原くんだりで、水浴びさせた挙句によ。だが」
じゃらり、と指からチェーンを垂らす。
「俺の勝ちだ」
銀の細いチェーンの先で、きらり、とあの翠玉がかがやく。
目をみはって、手を伸ばした。「──あたしの!?」
「おっと」
すばやくジャイルズが手を引いた。
「これはもう、俺のもんだ」
にやにや笑って身をよじり、左の尻の隠しにねじ込む。
ふと、エレーンは見咎めた。今の動作に違和感を覚える。そう、なぜ首にかけない?
何とはなしに向かいの首を見、ああ、とすぐに合点した。別の鎖がすでにあるから──
ぎくりと息をのみ、目をそらした。
得体の知れぬ動揺が、ざわりと胸にこみあげる。黒々とした怖気と焦燥。なぜ、気持ちがざわめくのか、自分でもよくわからない。ただ、禍々しさを強く感じる。
「どんなにすごい宝かと思えば」
ジャイルズは、動揺に気づいたふうもない。
「なんのこたァねえ、贋物じゃねえかよ」
はっとしてエレーンは我に返った。
「だったら返して! それでもあたしには、大事なお守りなんだから!」
それに、いずれは元の場所に、領邸の執務室に返さねばならない。
「知らねえなあ、そんなこたァ」
興味なさげにジャイルズは言い捨て、口端をゆがめて薄く笑った。
「贋物だろうがなんだろうが、手に入れたからには俺のもんだ。もう、誰にも渡しはしねえ。なにせ苦労させられたからな、こいつには。──しかし、なにが夢の石だ、笑わせてくれる。うんともすんとも言わねえじゃねえかよ。ま、こいつが駄目でも、次の手は打ってあるがな」
含みありげに一瞥され、ぎくり、とエレーンは後ずさる。「な、なによ……」
「人魚の肉ってのを知っているか」
「……え?」
不意をつかれて返事につまり、あっけにとられて、しげしげとうかがう。「人魚ってあの、おとぎ話なんかに出てくる、あの──?」
「肉を食らうと、不死身になる」
「それが?」
言わんとするところがわからない。
「無愛想なあの兄ちゃん──傭兵どもの隊長だよ。食ったらしいじゃねえか、その肉を」
「……ケネルが?」
内容以前に、思いがけない名前だ。
「つまりはこうだ。不死身の奴の肉を食らえば、食った奴も不死身になる」
一拍おいて、相手の意図に気がついた。
「──あ! だから、あんなに」
あんなにしつこく付きまとったのか。
「あの優男の兄ちゃんは、あれで逃げ足が速くてよ。奴に言うことを聞かせるには、何か弱みを握らねえとな」
ジャイルズが目をすがめ、にやにや笑う。
「……あたし?」
意味するところをにわかに悟り、はっとエレーンは目をみはった。
「だから、あんなにあたしのことを追いかけて──でも、ここにいるって、どうして知って──」
「ま、どこにでも、いらァな」
ジャイルズの口の端が、にやり、と皮肉な形にゆがむ。
「裏切り者ってのは」
虚をつかれて口をつぐんだ。
胸がざわめき、不安がよぎる。この場合、裏切り者とは「内通者」をさすのだろう。つまり、こちらの動向を、逐一流している者がいる。あの見知った顔の中に。
一体誰のことなのか。この現在地を知っていて、なおかつ賊と面識のある──。だが、商都の診療所を飛び出して、トラビアへ向かっている現状を知る者は限られる。
このところ関わった数人の顔が思い浮かんだ。
ケネル、ではないだろう。ファレスというのも、ありえない。ならば、まさかノッポの彼──いや、それはないだろう。確かにウォードは子供だが、賊に情報を提供するほど無邪気でもなければ迂闊でもない。そもそも彼が駆け引きなどに興味を示すとは思えない。ならば、商都を出てから会った人?
何人かに会っている。前の町バルドールでは、青鳥を連れたクロウに会ったし、この街に来てからも、どくろ亭のおじさんだとか、セビーだとかユージンくんに──この中の誰かが実は、裏で賊と通じていた……?
ガタン──と椅子の足を鳴らして、ジャイルズが席を立ちあがった。
卓の向かいから手を伸ばし、こちらの腕を引っつかむ。「あとは、優男が来るのを待つだけだ」
とっさにエレーンは睨み返す。「ケネルは──」
「来るさ」
揶揄する口調で大仰にさえぎり、ジャイルズは不敵に口端をゆがめる。
「必ずな」
エレーンは詰まって唇を噛んだ。そう、ジャイルズの言う通り、この事態を知ったなら、どこにいようが、ケネルは
──来る。
おい、とジャイルズが振り向いて、戸口の手下に呼びかけた。
「上へ行く。見張ってろ」
にやにやと思わせぶりに、手下が下卑た笑いを返す。
「ごゆっくり」
容赦なく腕を引っ張られ、エレーンはたたらを踏んで店を突っ切る。
引きずりあげられるようにして階段をあがり、二階の床にもつれ出た。
この酒場の建物の造りも二階は客室であるようで、窓のない板張りの壁には、ランプが薄暗く灯っている。
廊下の両側に扉は四つ、その内の一つが開いていた。
向かって左手の突き当りだ。隣の扉との間隔から、ここで一番広い部屋とわかる。一番上等な部屋を陣取り、寝起きしていたものらしい。
そして、そこへ連れ込もうとしている。
(じょ、冗談じゃないわよっ!?)
なけなしの力を振り絞り、エレーンは足を踏ん張った。
(誰がこんなおっさんと!)
ふっと胸に影がさした。
わずかばかり時間を稼いだところで、助けが来るあてはなかった。乱闘になったボリスらは、すでに伸びる寸前だったし、まして、連れ込まれた酒場の場所など、あの三人が知る由もない。
そう、自分のいる場所を、誰も知らない。
連れのセビーも、ユージンくんも。いや、当の自分でさえも。何かの拍子に逃げ出すことができたとしても、自力では戻り方がわからない。わずか二日ばかりの滞在では、何とか居場所の見当がつくのはこの街の中心部、目抜き通り近辺の大まかな位置関係を押さえるくらいが精々だ。
腕をつかんだままジャイルズは進み、肩先で扉を押しやった。
力の限り抵抗するが、構うことなく踏みこんでいく。
向かいの窓で、ゆるくカーテンが揺れていた。
開いた窓の向こうには、青い夏空と街並みの屋根。床に酒瓶が転がっている。壁際の卓には水差しとグラス、そして、ひらいた何かの紙片。年季の入ったくすんだザックが、壁に無造作に寄せてある。
全力で足を踏ん張るも、ずるずる容易く引きずられ、寝台の上へ突き飛ばされた。
寝乱れたシーツの上に顔から突っ込んだエレーンは、あわてて手を突き、振りかえる。
「優男が来るまで、精々楽しませてもらうとするか」
我が身を抱いて、寝台の背もたれに後ずさった。
シャツのボタンをむしりとるように外したジャイルズが、それを無造作に脱ぎ捨てて、値踏みの視線で近づいてくる。黒い蓬髪、倦んだ双眸、赤銅色の硬そうな胸。そして、首からさげた鎖の先には、異様にかがやく黒い石──
「それって……」
とっさにつぶやきが口からこぼれた。
ジャイルズは怪訝そうに足を止め、自分の胸元に目を落とす。
「──これか」
ふん、と軽く鼻を鳴らして、鎖についた石をいじった。
「こいつも戦利品、黒耀石って奴だ。いつだったか、誰だかから分捕ったもんだが、ここにあっても問題はねえ。なにせもう、前の持ち主はいねえからな」
「……え」
ぎくり、とエレーンはこわばった。つまり、殺して強奪した、ということか。
「俺はなんだって手に入れる。どんな手を使ってでもな。ちなみに、さっきの人魚の肉だが」
ギシ──と片膝で寝台に乗り、にやりとジャイルズは唇をあげる。
「なんでも心臓の近くが効くらしいぜ」
とっさに逃げたが、腕をとられた。
そのまま寝台に押しつけて、あっという間にのしかかる。
木板の天井を仰いだ視界に、ばさりと蓬髪が割り込んだ。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》