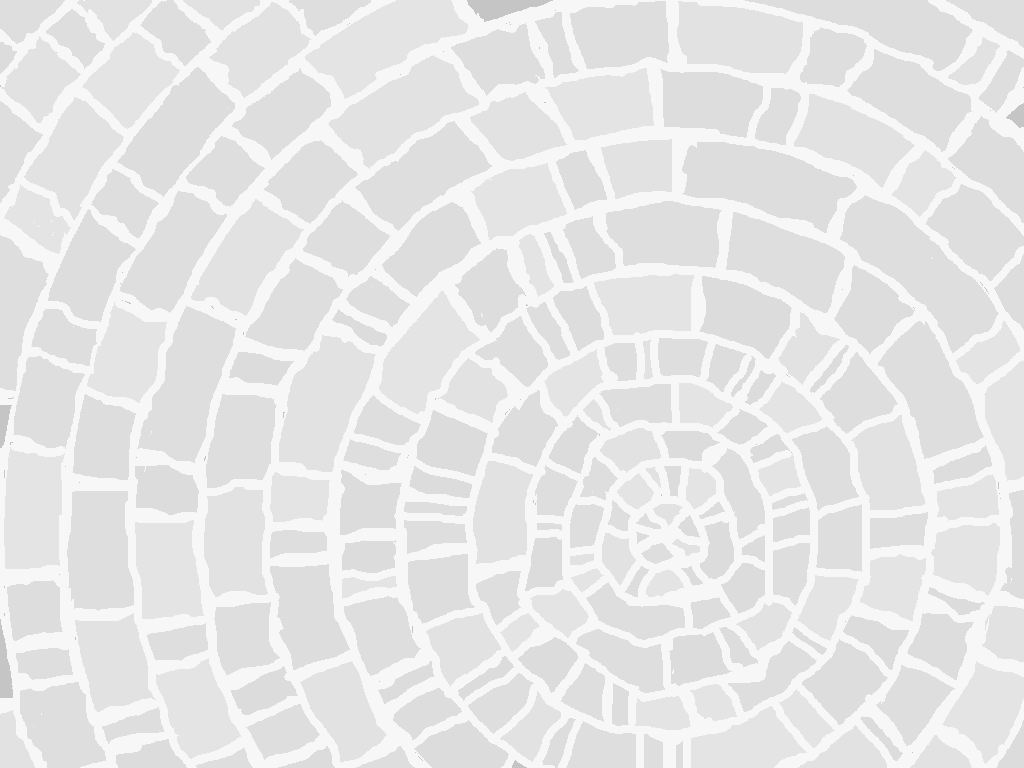
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章34
( 前頁 / TOP / 次頁 )
うめいて、蓬髪がのけぞった。
奥歯を食いしばっていたエレーンは、薄目をあけて、右手を伸ばす。
自分の上に馬乗りになった、ジャイルズの体を押しのけた。
寝台の背柱にくくられた左手首の縄を解き、転げ落ちるようにして床に降りる。
あの黒い蓬髪が、喉をかきむしって、うめいていた。
肩から、床に転げ落ちる。
エレーンはそろそろ近づいて、身を折って横臥した蓬髪の様子をおそるおそる覗く。
「え──」
ぎくり、と息を飲みこんだ。あの、蓬髪の隙間の黒斑は、まさか──
はっ、とそれに気がついて、蓬髪の腰に手を伸ばした。
すばやく手の中に引ったくり、自分の隠しにそれを突っこむ。床に手を突き、たたらを踏むようにして立ちあがり、壁にかかった大きな姿見の前を通過、扉から廊下に走り出た。
「に、逃げないと──!」
今のうちに。
人けない廊下の中ほどに、階下に続く階段が見えた。手すりを目指して一心に走る。もたつく足で一段、二段、と段を降り──
「おい。何してんだ」
ぎくり、とすくんで踏みとどまった。
階下で姿を見咎めたのは、喫煙しながら通りかかった、あのジャイルズの手下だった。店の戸口でたむろしていた数人も、今は卓について寛いだ様子。
手近な卓の灰皿に、手下が煙草をすりつけた。
胡散くさげにすがめ見て、たちまち階段をあがってくる。
「あっ……えっと……その……」
ごまかし笑いで後ずさった腕をつかまれ、階段を引きずりあげられた。
ずるずる廊下を引き戻される。「たく。油断も隙もあったもんじゃねえ」
開いた扉へ手下は歩き、部屋との境の戸口をくぐる。
「失礼します、ジャイルズさん。この女、階段の上に──」
その背が怪訝そうに固まった。
「……ジャイルズさん?」
つかんだ腕はそのままに、つかつか室内へ踏みこんでいく。寝台のかたわらの床の上、壁の大きな姿見の前には、身を折って倒れた黒い蓬髪。
「い、い、今ね──っ!」
エレーンはあわあわ顔をあげる。「今呼びに行こうと思ってたとこで──あ、けど、その前に会っちゃって。だから……」
からからに乾いた口で、とっさに手下に言い訳し、ちら、と上目づかいで様子をうかがう。
倒れた蓬髪を見やったたまま、立ち尽くした背中は動かない。エレーンはびくびく首をすくめた。絶対こっちが何かしたと思ってる──!
ぐい、と手下が、舌打ちで腕を引っ張った。
部屋の奥、窓の方へと、力任せに突き飛ばされる。
壁に手をついて激突を防ぎ、あわててエレーンは振りかえる。
床で身を折った蓬髪の横に、手下がかがんで膝をついた。
倒れた蓬髪の脇に手を入れ、自分の肩へ担ぎあげる。
「──ほら、寝るなら、ふとんで寝てくださいよ」
ジャイルズの体を寝台におろし、溜息まじりで見おろした。顔を横向けた蓬髪の下、ジャイルズは瞼を閉じている。
「しょうがねえな、ジャイルズさんも」
やれやれと手下が頭をかいた。「あんなに毎日、浴びるように飲んだら、潰れねえ方がどうかしてるぜ」
ぎろり、と肩越しに振り向いた。
「で、お前はどこへ行くんだコラ」
「……えっ?」
壁の端をそろそろと、出口に向かっていたエレーンは、引きつり笑いで振り向いた。
「逃げようなんざ、ふてえアマだ」
ギリ──と縄で縛りあげられ、背に回された両手首が痛い。
床にうつぶせに押さえつけられ、エレーンはうめいて顔をしかめる。「──い、痛いってばっ! もっと優しくぅ〜!」
「そうはいくか、盗賊が」
……え? と手下の顔を見た。
「盗賊? あたしが!? なんで盗賊っ?」
あぜんと口あけ、しばし呆然。ふと考えて、顔をあげて申告。
「あ、いいですそれで盗賊で」
「──何をごちゃごちゃ言っていやがる」
顔をしかめて手下は舌打ち、肩を乱暴に突き飛ばした。
硬い床に頬をぶつけ、エレーンは涙目で顔をしかめる。けど、泥棒だろうが何だろうが、正体がバレるより、はるかにマシだ。クレスト領家、正夫人の身分が。
どんどんどん──! と激しい物音が飛びこんだ。
びくり、とエレーンは凍りつく。
「……な、なに、あの音」
力任せに叩く音。叩いているのは壁──いや、扉板だろうか。
音が聞こえる廊下の方へと、手下が忌々しげに目をやった。
「静かにしやがれ! ぶっ殺すぞジジイ!」
耳をほじって、顔をしかめる。「たく。うるさくって、しょうがねえ。なんできちんと縛っておかねえ。手ぇ抜きやがって、あの連中」
エレーンは怪訝に眉をひそめた。この口ぶり──もしや、他にも監禁された人がいる? 運悪く居合わせた客だろうか。いや、必ず店にいる人物で、まだ見てない者がいる。
はっと気づいて顔をあげた。「と、閉じ込めてるの!? このお店の持ち主を? なんで、そんなひどいこと──」
「他人の心配、お前がしている場合かよ」
う゛っ……とエレーンは口をつぐんだ。そういや自分も立場は同じ。いや、自分の方が断然悪い。巻き込まれただけならば、用さえ済めば解放されるが、こっちはまさに当事者だ。しかも、敵は海賊ジャイルズ。階下には、悪そうな与太者がゴロゴロ──
「……ね、ねえ? もし、よかったら」
そわつきながらも、ちら、とうかがう。「し、下にいる人たちには内緒で、ちょっと、あたしと──」
「冗談じゃねえ」
え゛っ──と片頬がひくついた。
間髪容れずに一蹴され、ぎこちない笑顔で、しばし呆然。誘惑して油断させ、隙を見て逃げ出そうと思っていたのに……。いや、断るにしたって、アレはない。迷う振りくらい、してくれたっていいではないか。てか、皆まで言わせず
即答で却下!?
木っ端みじんで、虚空を漂う。
「妙な考え、起こさねえ方が身のためだぜ」
手下が苦い顔で腕を組んだ。
「前に、ジャイルズさんの気に入りの女と、よろしくやってた奴がいてよ。その後そいつ、どうなったと思う」
「……さあ。乗りこまれちゃって修羅場とか」
「串刺しだ」
「え?」
「やってる最中、そいつの後ろから、ぶすりとな。その相手の女ごと」
「──。は?」
息をのんで、しばし固まる。
「ええ!?──え゛え゛え゛え゛っ!?」
言葉がようやく像を結び、あわあわ手下を見返した。浮気を見つけたぐらいのことで!?
「捕虜は基本ぶっ殺す。酒の肴に拷問してな。通りすがりの野郎でも、ぶった斬るからな、あの人は。略奪、火付けは日常茶飯事、ほんのつい先だっても、沿岸の島の集落が、一つ壊滅したばかりだぜ」
ごくり、とエレーンは唾をのんだ。予想以上に凶悪な輩だ。てか、確か海賊稼業から
──足を洗ったんじゃなかったのかー!?
「よ、よ、よく、そんな怖い人と、一緒にいるわね、あんたたち」
「そりゃ、気前がいいからな、あの人は。それで誰がおっ死のうが、俺たちには関係ねえしよ」
奪った財貨を景気よく振る舞い、気炎を揚げる姿が思い浮かぶ。
「ジャイルズさんの好物、知ってるか」
え……とエレーンは面食らった。それで機嫌をとれ、とでも言うつもりか?
「え、えっと──お酒がすごく好きそうだから、焼き鳥とか裂きイカとか……あ、スルメ?」
にやり、と手下が口端をあげた。
「心臓だよ、人間のな」
天窓から射す光の中で、ゆっくり埃が動いていた。
片隅の壁に、掃除のモップ。そして、バケツやぞうきんなどの掃除用具。ふとんやシーツが木棚に畳まれ、店の備品なのだろう、花瓶や灰皿や細々とした物が積んである。
エレーンはうめいて顔をしかめた。暑さで頭が朦朧とする。
手足を縛られた不自由な体で苦労して身をよじり、部屋中央の日なたから、壁側の日陰へ移動する。
手下が放り込んでいったのは、隣室の物置部屋だった。
手足を縛って転がした上、ご丁寧に鍵までかけていった。扉に鍵などかけずとも、これほど大仰に、ぐるぐる巻きに縛っておけば、ろくに動けやしないのに。監禁された宿の店主が騒いだことが災いし、扱いが厳重になったらしい。
部屋の中は暑かった。窓のない物置で、そよとも風が吹かない上に、明かりとりの天窓があるから、日射だけが降り注ぐ。暑い盛りの日中に。
ジャイルズに連れ込まれた部屋の方が、まだましというものだった。部屋は広くて埃っぽくないし、何より窓から風が入る。もっとも、手下の口ぶりでは、ジャイルズの部屋に置いておけば、寝首を掻きかねないとでも思ったらしい。この"やり手の盗賊"が。
ただただ部屋が暑かった。軽く口をあけ、あえぐように呼吸をしていた。
ぼうっと意識が混濁していく。のぼせている自覚はあった。せめて、天窓から風が入れば、少しは体も楽だったろうに。
浅い呼吸を繰り返す脳裏に、隣室での出来事がよみがえる。
ふと、エレーンは眉をひそめた。
「あの人、まさか──」
いや、見間違えるはずがない。毎日のように、アディーのそばについていたのだ。
見覚えがあった。あのうなじの黒斑に。
床に身を折った赤銅色の背中。あのジャイルズの様を見て、手下は"酔い潰れた"と思ったらしいが、乱れた蓬髪に垣間見えたあれは──
すとん、とすべてが腑に落ちた。
あのジャイルズの言動が。ああも夢の石に固執した理由が。「人魚の肉」などという迷信に、それほどまでに憑かれた理由が。
だから、浴びるように酒を飲んだ。体を蝕む激痛を、なんとしても紛らわせるために。
あの血色の悪さを思い出すまでもない。かなりの際どいところまで進行している。そう、あれは紛れもなく──
「……黒障病」
アディーが患った稀有な奇病だ。手下が気づかなくても無理はない。
それにしても、あれは何だったのか。
部屋に連れ込まれてあの後すぐに、片手を背柱にくくられた。
寝台で乗りかかったジャイルズは、舌なめずりせんばかりの薄笑いで、首に刃を押しつけた。
手下が語った先のジャイルズの日常は、大袈裟などではなかったのだろう。人肉を食す、というのも、あながち脅しではなかったのかもしれない。蓬髪の向こうで見おろした瞳が、にわかに残忍な色を帯びた。
服の襟を無造作につかまれ、最早これまで、と覚悟したその時──
どくん──と大気が息づいた。
急速に日暮れていくように、辺りがにわかに禍々しさを帯び、室内の大気がビリビリと震えた。見えない何かが寝台の周囲を取り囲み、ぐるぐる渦を巻き始め──
澱み、めらめらと立ち込めた気。透明な火焔が立ちのぼったような。
目には見えない何者かが、咆哮をあげたようだった。
怒りに触れた──そんな言葉が思い浮かんだ。理由も脈略もわからない。猛り狂ったこの相手が、そもそも何者であるのかも。
膝立ちで喉を掻きむしり、ジャイルズがうめいて、のけぞっていた──。
あれは、いつのこと、だったろう。
しばらく前か、今なのか、ほんの数秒前なのか、うつろに漂う虚海の端で、ゴトリ、と硬い"音"を聞いた。
彼方でそれを捉えながらも、暑くて意識の焦点が合わない。何か物を動かしたような、異質な感じがしたのだが、注意を向けていられない。
……まあ、いいか、と投げやりに思った。どうせ、さっきの与太者が、物でも取りに来たのだろう。
ふわり、と何かが頬をなでた。
空気の動き……これは、かぜ?
そう、風だ。
あるはずもない存在を、ようやくそれと認識し、怪訝に思って瞼をあけた。
ぼんやり霞んだ視界には、なんら変わることのない横向きの光景。閉じた扉。モップにバケツ。ふとんやシーツが木棚に畳まれ、花瓶や灰皿や雑多な物が積んである──
ゴトン──と何かが落下した。
とっさに向けた視界の端、日射の板床に、何かある。
注意を向け、目を凝らした。なんだろう、あれは。手のひらにのるほどの大きさだ。日差しに銀が輝いている。そう、あれは──
「……果物、ナイフ?」
鞘のない、抜き身のナイフだ。だが、ほんのつい今しがたまで、何も落ちてはいなかった。なぜ、そんな物がここにある──
思考を中断、体をひねった。
ナイフに向けて、肩で這う。
手足を縛られた不自由な体で苦労して反転し、背中の指でナイフを探る。
柄をとり、いくえにも巻かれた手首の縄に、ナイフの刃をあてがった。
縄の外側を刃先でこする。慎重に作業を続けつつ、ふと、エレーンは首を傾げた。以前にもこれと、同じことをしなかったか?
あの時もやはり、こうした刃物で、手首の拘束を断ち切った。監禁されていた、あのラトキエの別棟で──
ぶつり、と唐突に手応えがあった。
手首を動かして縄をゆるめ、縄の中から両手を抜く。切れた縄を取り払い、足首の拘束も断ち切った。よろめく足で戸口へ向かい、扉にとりつき、ノブを回す。
眉をしかめて、唇をかんだ。
開かない。鍵がかかったまま──。壁へと歩き、棚にのって身をよじった。天井の窓を押しあげる。
指先は辛うじて届いたが、天井の窓は動かない。
精一杯背伸びをしても、それより上には押しやれない。そもそも、天窓から脱出するには、体をそこまで持ちあげなければならない。もっと高さが必要だ。
棚から降りて、壁に視線を走らせた。
掃除のモップにバケツやぞうきん。ふとんやシーツに、花瓶や灰皿。ハシゴや椅子など足場になりそうな物はない。
落胆しつつも、壁からモップを取りあげた。
もう一度棚にのり、モップの先で天井の窓枠を押しあげる。
つっかえ棒をかませて通気口を確保し、棚から降りてモップを戻した。壁にいわゆる窓はない。この部屋の開口部は、あの天窓一つきり──。
元いた日陰の壁まで戻り、脱力してへたり込む。
とっさに、まぶしさに目をそらした。
肩を戻して、顔をしかめる。後ろの壁が、まだらに白い。陽射しが、壁で揺らいでいる。あんなもの、さっきまでなかったのに……
そうか、と気づいて天窓を見た。窓の角度が変わったからだ。外からの日差しを、あの窓が反射している。とはいえ、よそへ行こうにも、他には備品が置いてあるので、寄りかかれるような壁はない。
きらきら、きらきら、陽射しが揺れる。
溜息まじりに壁に背を向け、いささか投げやりに寄りかかる。
もたれた肩が、ずぶり、と沈んだ。 ※
ほんのつかの間、視界がブレた。
ぐるん、と後方一回転。尻を落として、ぺたり、と床にへたりこむ。
呆然とうつむいた視界には、自分の膝と板張りの床──。
胸が、騒いだ。
なぜだろう、ざわついている。気持ちが掻き乱されている。
涙が頬を伝って落ちる。何が何だかわからない。なぜ、こんなにも動揺している……?
自分の反応と感情に後ろ髪を引かれたが、今はもっと不可解な出来事があったはずだ。
全身にまとわりつく、胸を締め付けられるような想いを振り払い、気を取り直して目をあげる。
ぽかん、とエレーンは見直した。
一瞬、訳が分からない。向かいの"それ"を凝視する。
「……ここって」
視界の様相が一変していた。
あの寝台が、目の前にある。背中にあるなめらかな壁は、あの部屋の姿見の鏡面──。
物置部屋と壁一枚を隔てた、あのジャイルズの部屋にいた。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》