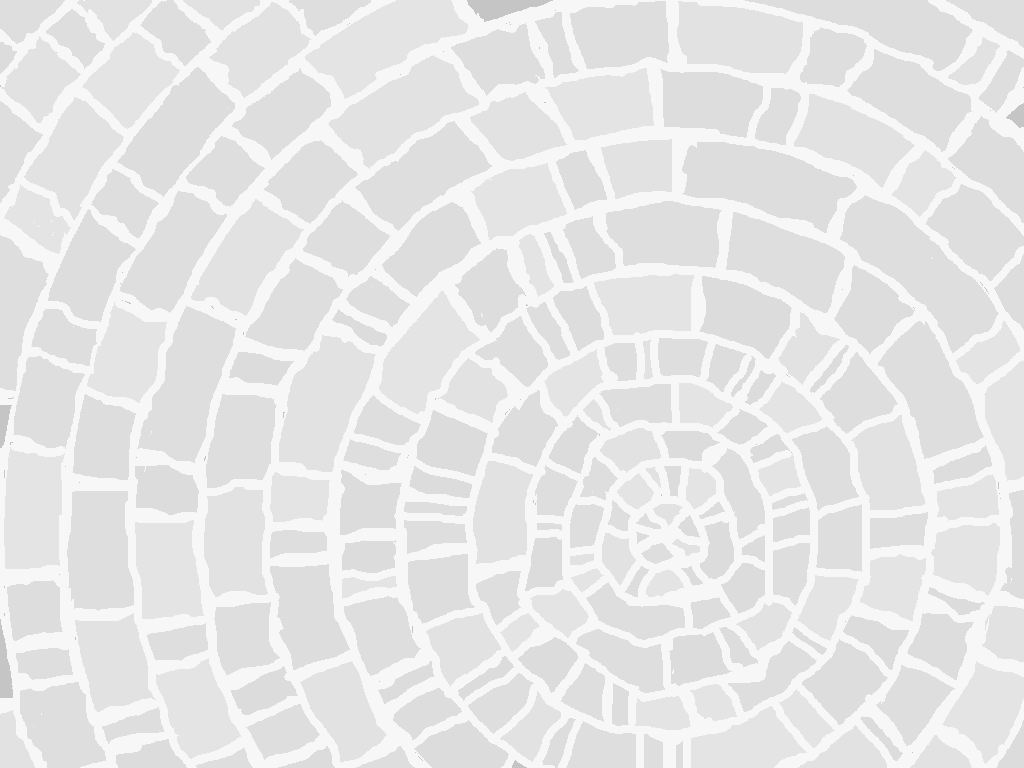
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章35
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「カラクリだろ」
事もなげにボリスが言った。
ぽかん、としてエレーンは、どんぐり眼の横顔を見返す。「……なに、からくりって」
「だから、その姿見が "隠し扉"って寸法なんだよ。よくあるだろ、偉い人の部屋とかに」
……よく、あるか?
「でも、そこ、普通のお店なんだけどー」
「けど、宿で一番いい部屋だろ? 上等の部屋にはつきもんだって。急に踏み込まれても逃げられるようによ。だからそこだけ物が置いてなかったろ」
「……そっ、そう言われれば、そうだけどー」
じれったそうに畳みかけられ、エレーンは足元の小石を蹴る。お説一々ごもっとも。でも、どうも納得しがたい。
「あっ、でもでもぉー」
あっ、そうだ、と顔をあげた。
「それだけじゃなくって、なんでかナイフが、ごとん、ってぇー」
「──あー、それな」
ボリスは面倒そうに頭をかく。「気づかなかっただけだろ、そっちは」
「えー。絶対なんにもなかったしー」
「だから、棚から落ちたんだって。大暴れした振動で」
「えええー!? 普通、ナイフなんか置いてあるー? なんか、そんな都合よく」
「あるだろ。 物置 なら」
「……そっ」
一発で沈められた。
「そっ、それは、そーなんだけどぉー……」
やっぱり、どうも納得いかない。
夏日きらめく川沿いの道を、エレーンは三バカと歩いていた。名前でいえば、ボリス、ジェスキー、ブルーノの三人組。
壁に寄りかかったと思ったら、ぐるんと一回転して元の部屋にいた──あの奇妙な体験をした後、エレーンはあわてて出口に走った。誰も見てないこの隙に、とっとと脱走するためだ。
とはいえ、階下には手下がわんさか、正面突破はまず無理だ、それは骨身にしみて学習した。なので、扉の前で思い止まり、窓の方へと取って返した。
手すりに取りついて見おろした窓が、一階店舗入り口の、真上に位置していたのが幸いした。
雨避けの屋根を三歩爆走、破れかぶれの助走をつけて、手近な街路樹に飛びついた。
顔を引きつらせて伝い降り、着地と同時に通りを爆走、死にもの狂いで走り出た道で、三バカと遭遇した次第。
ちなみにその時三バカは、並んで噴水に頭を突っ込み、腫れた顔を冷やしていた。ぼろ雑巾のごとくしなだれかかって。
通りの中ほどにある噴水からは、景観整備のためなのか、小奇麗な水路が伸びていた。
黒眼帯のジェスキーが言うには、この水路沿いに歩いていけば「青い旗の商館」のある、あの通りに出るらしい。そこまで戻れば、しめたもの。セビーらの居場所はすぐそこだ。
並木の青い樹梢の下、水面がきらきら夏日に光る。
流れはゆるく、深さもない。せいぜい幼い子供らが、水遊びする程度の浅い川だ。
肩にうららかな木漏れ日を浴びて、川沿いの遊歩道をてくてく歩く。
「てか、なんでまだ、うろついてるかなー。そんなヨレヨレで、ボロボロのくせにぃ」
「──あのな」
むっと口を尖らせて、ボリスがちらと横目で見た。「あの時お前が言ったんじゃねえかよ。耳打ちしたろ、"助けに来て"って」
「──だからー」
げんなり嘆息、イラッとエレーンは拳を握る。
「なんで、おまわりさん 呼ばないかな!?」
相手は町のごろつきなのだ。こうした輩の取り締まりは、おまわりさんの管轄だ。
ぱちくり三人が瞬いた。
そうか、と顔を見合わせている。思いつきもしなかったらしい。
「──ああ。そういや、お前に渡す物が」
ボリスが肩の布袋をとって、手を突っ込み、ごそごそ取り出す。「──ほらよ」
「あたしのリュックぅ!?」
目を丸くして引ったくった。なんと、失くしたと思ったあのリュックではないか!? 三万二千カレントたぬき付き! セビーにねだって買ってもらった──いや、お勘定したのはユージン君だが──。てか、自分のザックとは別にして、ズタ袋に隠していたが、肩にかけるの、そんなに嫌か 失敬な。
ぼうっと見ていたブルーノが、なにやら俄かにあわただしくなった。
大きな図体の背中から、やはりゴソゴソ出してくる。「お、俺はコレ……」
「あたしのポシェットぉ!?」
全財産の入った財布入り。わたわた片手で引ったくる。
「──いや、あん時、俺よ」
言い訳するように口を尖らせ、ボリスがもそもそ頭を掻いた。
「どうあっても渡しちゃいけねえ、と思ってよ」
む? とエレーンは眉根を寄せた。
リュックとポシェット両手で抱きしめ、胡乱な視線で牽制する。「あ、あげないわよ?」
「──袋じゃねえよっ!?」
「だって、渡しちゃいけねえって」
「"お前を" だろうが! なんで袋だ!?」
爪先立って怒鳴りつけ、はた、とボリスが我に返った。
ぼっと耳まで赤らんだ頬を、ぱっ、とかたわらの川へと背ける。「けど、気づいたら、なんでかそれが──」
手元に残っていたらしい。必死でしがみついた腕の代わりに。
きまり悪げな二人の顔を、あぜんとエレーンは交互に見た。このリュックもポシェットも、てっきり手下が盗ったとばかり──。いや、相手は与太者。目をつけなかったわけがない。奪おうとはしたが、諦めたのだ。蹴っても殴っても離さなかったから。
ということは、つまりはなんだ? 所持品紛失の一件は、つまり、
──こいつらだったのか 犯人 はー!?
しばし、呆然と脱力する。
いや、しかし、なんにせよ、荷物が無事だったのはありがたいが……。
「……あ。そうだ」
ふと、エレーンも思い出し、自分のズボンのポケットを探った。
ごそごそ取り出し、首にかける。
胸元で、きらきら陽射しを弾いた。あのお守りの翠玉が。あのジャイルズが倒れた直後、あわてて取り返した夢の石(のニセモノ)
これで万事元通り。さあ、早く戻らねば。セビーたちが自分のことを捜し始める頃合だ。きっと、戻りが遅いのを心配して──
「……。セビー?」
ふと、再会シーンが頭に浮かんだ。そういや、この三バカをなんと紹介したものか。あんなにちゃんとしたユージン君でさえ、セビーはきっちり受けつけないのに、まして、この三人を連れて行ったら……。いや、受けつけないどころか対面直後に、
「……。大乱闘かな」
頭いたい……と額をつかんでうなだれる。なにせ、この三人は、誰かれ構わずガン飛ばすような連中なのだ。町の与太者にはぺこぺこ媚びるが。
急に気分がどんよりしつつも、行く手の歩道に再び踏み出す。
ふと瞬き、振り向いた。
「ガンタ──んん、ジェスキー。もしかして、目、痛いの?」
うつむいて眼帯を触り、ジェスキーが首をひねっている。「ああ、いや、痛くはねえけど──なんてえのか変な感じで──あ、いや、なんともない。大丈夫だ」
「……本当に?」
疑わしげに確認し、思い切っておずおず尋ねる。「あの、その目、仕事で怪我して?」
「いや、俺らは前線には出ねえから」
……え? とエレーンは面食らった。思いがけない返答だ。
「俺らの仕事は、親父の近くで──いや、首長の身辺警護だからさ」
ジェスキーによれば、彼が視力を失ったのは、生まれ故郷が襲撃された、まさにあの日のことだったという。アドルファスの部隊から襲撃を受けた──
当時、子供だったジェスキーは、部隊を見て驚いて逃げ、あわてて転んで頭をぶつけた。そして、視力を失った。
とはいえ眼球は無事だったので、本来、眼帯などは要らないのだが、子供らを保護したアドルファスが、付けているように言いつけたのだという。
「だから俺らは、前線へ送られずに済んでんだ」
ジェスキーは自嘲気味に含みを持たせる。
「……そっか」
エレーンは複雑な思いで合点した。それはささやかな免罪符。部下の反発をねじ伏せて、無理にも承服させるための。それが首長アドルファスなりの配慮ということなのだろう。未来も居場所も奪ってしまった、罪のない子らに対する──。
雇い主の計略に乗せられた首長の心中を慮り、やりきれない気分で翠玉をいじる。
ふと、怪訝に目を戻した。
石が、ほんのり温かい。強い夏日のせいだろうか。
「……あれ?」
ぱちくり見返し、目をこすった。今のは目の錯覚だろうか。
ちょろっ、と刹那、緑が揺らいだ。
透き通った焔が燃え立つように。何かの残り火であるかのように──
指の先が、細かく震える。
どこかで持ち続けていた違和感の、横顔が不意に浮かびあがる。
淡い幻影が胸をかすめた。
閉じ込められた物置から元の部屋へと転がり出た、一瞬に圧縮された幾つもの情景。けれど、それには色がない。それどころか輪郭もない。
それらが一体なんだったのか、いくら考えても思い出せない。見つめれば見つめるほど、闇の彼方へ遠のいていく。
そんなものは、ない。
本来、影も形もないのだから。けれど、確かに存在する。
じりじりと歯がゆかった。もどかしさが胸を焼く。
なぜ、すべて消え失せた──
「お前、」
不意に、声が耳に飛びこむ。
咎めるような男の声音。いや、いぶかしさが勝るだろうか。呼びかけたのは三バカではない。歩道の向かいにいる誰か──ふと、エレーンは目をあげる。
あわあわ、地面にうつむいた。だが、時すでに遅かったようだ。
「なんで、お前がそこにいる!?」
驚愕の怒声が飛んできた。
やさぐれた身なりの見たような顔が、歩道の行く手に立っていた。片手にさげた紙袋の縁から、棒パンの先がのぞいている。
忘れもしないあの男。縄で手足を縛りあげ、物置に放りこんだあの手下だ。
手下はあっけにとられた様子で、食い入るようにまじまじと見、酒場の方角と見比べる。「ば、ばかな……閉じ込めてきたばかりだぞ? その足で飯買いに出て──こんな所を歩いているはずが──」
そろり、とエレーンは足を引き、引きつり笑いで後ずさる。「ひ、人違いじゃ?」
「さっきと同じメンツじゃねえかよ!」
固まっていた三バカ共々、飛びあがって逆走した。
「待ちやがれ!?」
パンの袋をぶん投げて、すぐさま手下も追ってくる。
いく度もでたらめに角を曲がった。細い路地へと闇雲に入る。両手を振って逃げながら、エレーンはやきもき振りかえる。「──んもうっ! なにやってんの! 早く早くっ!」
「ま、待てよ……っ!」
だが、すでに三人は、肩で息をついている。
逃げ足(だけ)は速い三バカだが、殴られ、蹴られ、駆けずり回り、完全にばてている様子。常日頃から不摂生な、与太者相手だから、いいようなものの──。
真昼の町は、ひっそりしていた。
炎天下をぶらつく物好きは元より、路地へと続く街角に、仲間らしき人影もない。捕り物終了の連絡がいき、解散した後なのだろう。そして、おそらく今ごろは、アジトの酒場に集合している。だが、全てがそうではなかったらしい。
乱れた足音と怒号を聞きつけ、路地から追手が合流した。一人、ややあって又一人──そして、路地でたむろす輩が気づいて、一気に五人にふくれあがる。
「──このままじゃ、増える一方だ」
歯を食いしばった横顔の、どんぐり眼が行く手を睨む。
「これじゃ、いつか追いつかれる。どうにか撒いて隠れねえと……っ!」
顔を振りあげ、顎で左の町角をさす。
「次、曲がるぞ!」
「──え゛?」
とっさに顔がこわばった。このセリフ、前にもどこかで聞いた気が……?
なにか悪い予感がする。いや、悪い予感しか、むしろ、しない!
だが、事態は切迫。待ったなし!
止める間もなく、わらわら突進。塀沿いに路地へとなだれ込む。
愕然と、エレーンは目をみはった。
「──んもう! またあ!?」
いくらも行かぬ間に急停止。
行く手は、塀で行き止まり。よじ登れそうな街路樹もない。
引きつったボリスを、地団太でなじる。「もう! なんで言うかな曲がるとかあっ!?」
「ほんとスよねえ。なんで、わざわざ曲がるんスかねえ」
「……。へ?」
眉根を寄せて固まった。
どこかで聞いた声がした。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》