※ 8/27(土)9:00頃を境に「web拍手」が繋がらなくなっていたようです。
もし、頂いていたらすみません。
同日23;10に修正しました。
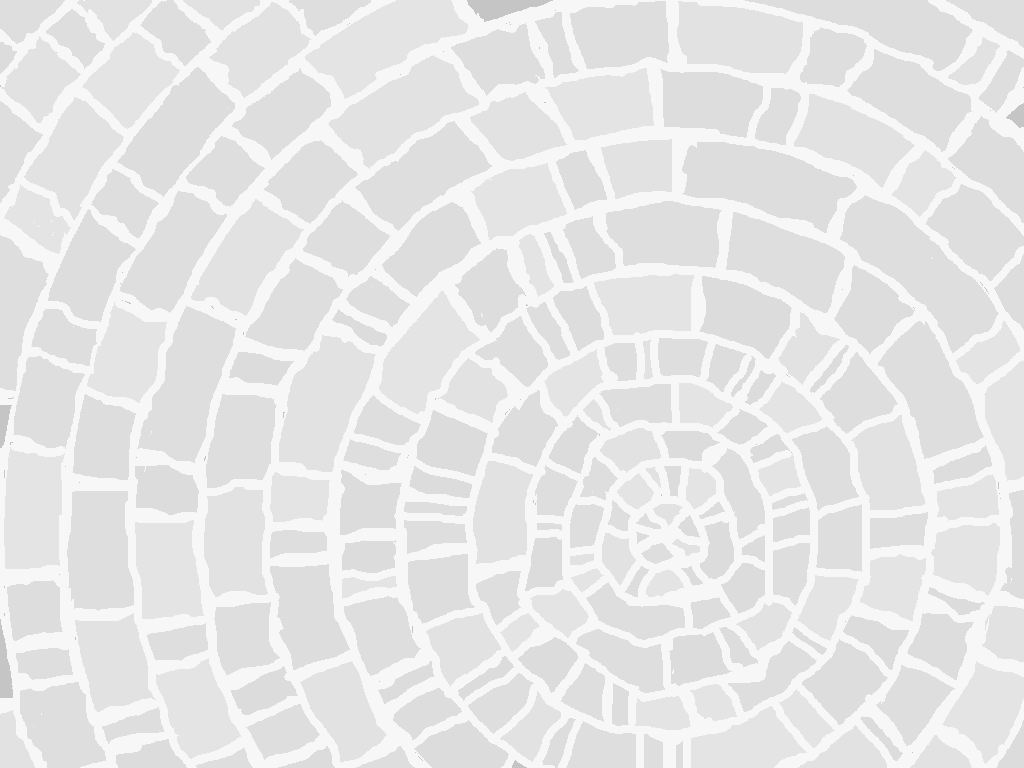
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章36
( 前頁 / TOP / 次頁 )
エレーンはきょろきょろ、三方の塀に相手を探す。
とはいえ、ここは脇道一つない袋小路。行く手は石塀で行き止まり、後を追って駆け込んできた後ろの五人の与太者を除けば、人が入りこむ余地などない。ならば、声は一体どこから……
ふと、足元で視線が止まった。
地面に、影が落ちていた。自分のものでも、連れのものでもない。地面の色を線で隔てる「建物の影」から伸びている。つまり、塀に、
──人がいる?
左を仰いだ視界の先で、ひらりと靴が、塀の足場を蹴りやった。
それは造作もなく着地して、三バカとの間に割って入る。
怪訝に見やった三バカが、ずさっと後退、引きつった。
「「「 特務!? 」」」
そう、こんな所にいるはずがないが、昨日とはまるで衣服が違うが、特徴的なあの禿頭と、さらりと薄茶のこの髪は──。すぐ目の前のシャツの背を、あっけにとられてエレーンは仰ぐ。「ザ──」
「ぶん殴られる覚悟、できてますよね」
じろり、とザイが一瞥をくれた。
──う゛っ、とエレーンはたじろいで、上目使いの引きつり笑い。
もじもじ、そわそわ、両手の人差し指をくっつける。「で、でもぉー、あれはしょうがないっていうかー。不可抗力っていうかー」
「不可抗力。なんスか、そりゃ」
けんもほろろにザイは一蹴。ぶっ飛ばしこそせぬものの、静かに深く怒っている……
「──あっ、あっとセレスタンっ?」
すがる思いで、名を呼んだ。
組んだ両手を頬に押しつけ、にーっこり禿頭に笑いかける。「そういう格好もめっちゃ似あうぅセレスタン!──あっと、ええっと、もちろんザイもぉー」
ぬっとザイが顎を出した。
「誤魔化せると思います?」
「──う゛っ。──ご、誤魔化すだとか、やーねー、なんでそんなことぉ〜」
「積もる話は後ってことで」
へらへらおべっかを短く制し、セレスタンが向かいを親指でさす。
「先客がしびれ切らしてる」
険しい顔つきの手下五人が、路地の出口をふさいでいた。
二人の飛び入りにたじろいだ様子で、じろじろ、いぶかしげにすがめ見ている。
「──おうおうおう!」
ついに、苛立たしげに一人が吠えた。
「なんだなんだ、てめえらは!」
闖入者の出現に気を呑まれはしたものの、二人はどこにでもいる平服姿、取るに足りないと踏んだのだろう。
走りづめの与太者は、額の汗をぬぐいつつ、忌々しげに睨んでいる。
勢いを増した険悪さに、三バカが弾かれたように身構える。一触即発の胡乱さだ。エレーンはおろおろ顔をゆがめる。
不穏な光景が、脳裏をよぎった。前の町の薄暗い路地で、無様に転がる与太者の姿。それを手荒に引き起こすあの二人の──
とっさに、ザイの服をつかんでいた。
「……喧嘩、するの?」
ザイが面食らった顔をした。
つかのま躊躇したその肩を叩いて、禿頭の横顔が前へ出る。
「姫さん、よろしく」
すっと行きすぎた肩に気づいて、エレーンはあわてて目で追った。「だ、だめ、セレ──!」
「はい。見えないー」
ぐるり、と肩が反転した。
たたらを踏んで、エレーンは固まる。「……はっ?」
肩を引き回されたと思ったら、ぱっと視界をふさがれた。そして、背中にくっつく真後ろの気配……?
「な、なになになにっ!?」
事態を把握し、わたわた恐慌。
「おや。どーしたんスかねー。なんにも見えなくなっちまったスねー」
「……あ゛?」
「おやおや。いきなり真っ暗っスねー。一体どうしたもんスかねー」
……いや、あんたの仕業じゃん。この目隠し。
耳元の絶え間ないおちゃらけの合間に、ドカッ! バキッ! ドゴン!──などなど不穏な物音が漏れ聞こえる。男の短いうめき声も。
ものの十数秒で静まった。
ザイの目隠しを払いのけ、あわてて現場を振りかえる。
あぜん、とエレーンは突っ立った。
「……こ、これ、もしかして、セレスタンがやったの? セレスタン一人で!?」
三バカはあんぐり口をあけ、絶句の態で突っ立っているから、多分それで合っている。
先の五人が、そこにいた。
地面に突っ伏し、塀にもたれて、皆ことごとく気絶している。
そんな中、一人だけ立った禿頭は、そっぽを向いてカラ口笛。「どうしたんすかね。バテたんすかね。ほら、今日も暑いから」
「……」
そんなわけあるか。
誤魔化し笑いでセレスタンは移動し、視界をさりげなく背で隠す。「あー、それより何すか、不可抗力って」
「……えっ?」
エレーンは追及を呑みこんだ。
(不可抗力?)と言葉を反芻、はた、と脈略を思い出す。事ここに至った経緯を。そう、前の町バルドールに、二人を置き去りにしたその事実を。
「あっ、あのね? 違うからねセレスタンっ!?」
沸々怒りをたぎらせたザイの横顔を思い出し、あたふた顔を振りあげた。
「あたし、逃げようとか、そんなつもりじゃ!? でも、借金とりが追っかけてきて、馬車に隠れたら動いちゃって、降りようとしたんだけど降りられなくて、それで気がついたら、ここにいて──」
「ま、そいつは後でじっくりと」
ぽん、とザイが肩を叩いた。
釈明の途中で割りこまれ、むっとエレーンは振りかえる。
「信じてないでしょ」
「信じてますとも」
間髪容れずに返したところが、白々しいほど嘘くさい。
「もう! だから違うんだってば! 本当にお店に借金取りがー」
「それより、とっとと離れましょ。警邏が来ても面倒だ」
壁の隅っこで放心し、固まっていた三バカが、はたと顔を振りあげた。
わたわた駆け出し、なぜだか突進、べしっ──と石塀に突き飛ばされる。
ぶつけた壁から顔をあげ、エレーンは涙目で振り向いた。
「んもう! なによっ! なにすん、の……っ?」
思いがけない光景に、ひくりと頬が引きつった。
「な、なにやってんの?」
あのボリスとジェスキーが、突っ立ったザイにしがみついていた。
その横でブルーノも、後ろからセレスタンに抱きついている。一体何がどうなっているやら。てか、
…… そんなに好きか? この二人が?
怯み、たじろぎ、エレーンは固まる。微妙な境地で、思考が停止。
それは抱きつかれた当人も同じのようで、ザイもセレスタンも、なすすべもなく突っ立っている……
はた、と二秒後、我に返った。いや待てまさか、ありえない。そんなことがあるわけない。なにせ三バカは部隊の人とは、まんべんなく仲が悪い。その唯一の例外がかの 調達屋 というんだから、ひねくれ具合は推して知るべし。けれど、だったら、こうして抱きつく理由はなんだ?
ふっとひらめき、顔がゆがんだ。そう、奇態の理由など、一つしかあるまい。さては、こいつら、この時とばかりに、
──日ごろの鬱憤を晴らす気かー!?
「ちょ、ちょっと!? よしなさいよ、いがぐりっ!」
あわててボリスに取りついた。
「よしなさいっ! よしなさいってば!」
ふっかける相手、間違ってるから!
さっき、他ならぬ自分らをけちょんけちょんにしてった手下を、やっつけちゃった相手だぞ!? それもザイの方は不参加で。
ぐぬぬと歯を食いしばり、ボリスの腕をがむしゃらに引っ張る。「なにやってんの!? そっちは味方──」
「味方じゃねえ!」
虚をつかれて見返した。
「……な、なに言ってんの? そりゃ仲良くないかもしんないけども、けど、おんなじ部隊にいるんじゃない。それに今は緊急時で──ほ、ほら、なんていうの? 相対的なくくりで言えば、今はみんな味方ってことに──」
「いつまで寝ぼけてんだ! 味方じゃねえだろ!」
叱りつけるように、ボリスが怒鳴った。
「よく見ろ! 連れ戻しに来たんだろうが、こいつらは!」
ぎくり、とザイの顔を見た。
ザイが無言で見返した。特に何を言うでもない。あわてるでも否定するでもない。セレスタンも無言で見ている。確かに実際、その通りではあるけれど……。呆然としつつも、おろおろ見やる。「あ、でも、だけど、あたしは──」
「行け!」
しびれを切らして、ボリスが怒鳴った。
「ばかっ! なにしてんだ! 早く行け!」
鋭く視線を振り向ける。
「行くんだろ! トラビアっ!」
はっとエレーンは息をのんだ。
ジェスキーと二人がかりでザイに取りつき、ボリスは通りへ顎を振る。
「いいから行け! 俺らに構うな! こいつらに捕まったら、逃げられねえぞっ!」
ボリスと出口をおろおろ見比べ、エレーンは唇をかみしめる。
「う、うん……」
一同を見つめて、後ずさった。
肩越しに振りかえり振りかえり、おずおず通りへ歩き出す。
「──あ、ちょっとタンマっ!」
くるりと反転、駆け戻り、地を蹴り、セレスタンに飛びついた。
もぐりこんだ首元で頬ずり。
「──ごめん──ごめんね、セレスタン」
ぎゅっと抱きついた腕を放して、ためらい、隣へ足を向ける。
無言で見おろしたその首に、思い切ってしがみついた。
さらりと長めの髪先の、その耳元にもぐりこむ。
ザイは振り向きもせず、微動だにしない。その頬に唇で触れ、とん、と背伸びの踵を戻す。
ひくり、と一同凍りつくも構わず、脱兎のごとく逃げ出した。
顔に落ちかかる前髪の向こうで、何かを咀嚼するようにその目が瞬く。
何か、耳打ちされたようだったが──。辟易としたように眉をひそめて、ザイが軽く息を吐いた。「──いつまでそうして引っ付いてんだ」
はっ、とボリスは我に返った。
舌打ちで手をどけられて、三人同時に飛びすさる。
相手の身じろぎにあわてて駆け出し、三人横並びで出口をふさいだ。
「こ、ここは通さねえっ!」
小首をかしげるように、ザイが見た。
「いい度胸してるじゃねえかよ」
抑揚のないその声には、蔑みさえも含まれていない。ただ押し殺した苛立ちが伝わる。片足に軽く重心を預けて、セレスタンも無言でながめている。じりじりするような胸騒ぎに駆られて、ボリスは奥歯をかみしめる。
相対した膝が震えた。
何をされたわけでもないのに、向かいに二人並び立っただけで、足が竦み、気を呑まれる。あの彼女に接する時には、幼い子供でもあやすように、信じがたいほど穏やかだったが、さすがに甘い顔はしないらしい。
剣呑な気をみなぎらせ、ぎろりとザイが目を向けた。
「どけ!」
「──どかねえっ!」
死に物狂いで、ボリスは返す。
「脅したって、どかねえぞっ! 絶対連れて行かせねえ! 力になると決めたんだ!」
両手を広げ、汗ばんだ耳に、めまいのように蝉の音が満ちる。
特務二人は無言で見ている。顔にはなんの表情もない。言い返すでもなく、構えるでもなく。
いや、行動に移れば、特務は速い。
ほんの一瞬──そう、動いたと思った時には、やられている、そういう噂だ。
造作もなく五人を下したセレスタンのあの手際は、まだ目に焼き付いている。顔色一つ変えるでもなく。淡々と手足を繰り出して。赤子の手でもひねるように。あんなに苦労した与太者を。いや、二人の素性を思い起こせば、むしろ、それも当然か。
ああしたロムは物心つく頃から、何百何千と格闘訓練を積んでいる。
人体の急所を熟知して、関心はすでに相手を倒せるかどうかではない。その内容、その出来だ。いかに手際よく片づけるか──。
彼らに課される訓練は、一歩間違えば、命さえ落としかねない過酷さだ。それをよく知るあの首長は、保護した子供を近づけなかった。町のひ弱な子供では、脱落すると踏んだのだろう。そうでなくてもロムは市民より、身体能力が総じて高い。
その分、子供たちの護身術は、首長が手ずから身につけさせた。緊急時の対処法、敵からの逃げ方を念入りに。そうした配慮に不服を抱いた、あのバリー一人を除いて。
そう、傭兵になるべく教育された、特殊な環境で育ったロムなど、軍人でもない与太者風情が、太刀打ちできる相手ではない。まして相手は特務の精鋭、その双璧をなすこの二人だ。
格闘に有利な長い手足、禿頭、長身のセレスタン。そして、速さで知られる鎌風のザイ。
かのレッド・ピアスの親衛「特務」 中でもとりわけこの二人は、上から一、二を争う逸材だ。運悪く出くわした敵兵は、あわてて陣に逃げ戻るという。
与太者が次々繰り出す拳は、一度たりとも掠らなかった。
それほどセレスタンは速かった。そのくせ攻撃は的確で、一撃で全員が地を這った。いや、あの男にとってはあの程度、準備運動にもならなかったろう。
おかしな言い方になってしまうが、のびのび手足を繰り出しているようだった。軽く突き伸ばした拳の先に、敵が自ら当たりにいっているような。つまり、それだけ読みが正確だったということだ。
軽やかな足さばきで、いやにゆっくり手足を動かし、慎重に手加減しているのが傍目にもわかる、そうした動き。
ザイの実力もそれと互角、いや、立場が上だというのなら、それ以上ということだ。
並みいる傭兵の配下の中で、誰より多く武勲をあげ、二人は現在の位置にいる──言ってしまえば、どれだけの命を奪ってきたのか。あの気違いじみた戦場で。
そんな手合いと対峙している。他ならぬ自分たちが、
──今。
喉が、からからに干上がった。真昼の暑さで、頭がのぼせる。
「……しょ、正直いえば、」
すくんだ足を叱咤して、ボリスはなんとか、向かいを睨んで踏みとどまる。
「正直いえば、お前らは怖ええよ。俺らなんかじゃ敵わねえよ。足元にも寄れねえよっ! けどっ! だけどよっ!」
破れかぶれで怒鳴りつけた。
「それでも、あいつと約束したんだ! あいつと──バリーと約束したっ! だから、どうあっても、ここはどかねえ!」
耳の端が、脈打つのを感じた。
突き当りの塀を背にして、特務は無言で佇んでいる。
二人の姿から目は逸らさず、ごくり、とボリスは唾を飲む。街の人波に紛れるために、目立たない平服を着ているが、得物は今も隠し持っているだろう。すぐにも使える状態で。
膝ががくがく震え出した。
のぼせた頭に怖気がよぎる。今、自分は、とんでもない間違いを、しでかしたのではあるまいか──。
流れた汗が目に入り、並び立った二人がぼやける。視界の右が身じろいだ。
身構える間もなく、ぱっとザイが両手をあげる。
「降参」
ひとつ、ボリスは瞬いた。「──え」
流れる汗で、頬がひりつく。なんのことだか、わからない。隣のジェスキーとブルーノも、反応しがたく固まっている。
「負けたぜ、お前らには」
ザイが気負いなく言葉をほうった。
連れを促し、歩き出す。「行こうぜ、セレスタン」
セレスタンも後に続く。通りへ続く出口へと、かったるそうに引きあげていく。
「バリーのことは気の毒だった」
耳に滑りこんだ落ち着いた声音に、え……とボリスは硬直する。
あわててザイを振り向いた刹那、脇を二人が通過した。
「──お、おい、待てよ!」
足を止め、ザイが肩越しに振りかえる。その無表情を、すがめ見た。
「あっ、あっ、ありがとなっ!」
「何が」
「──助けてくれたろ、俺らのことも」
すばやく二人が視線を交わした。
セレスタンが禿頭をかしげ、軽く肩をすくめてみせる。「どういたしまして」
それを肩越しに見ていたザイが、肩を返して歩き出す。「気にすんな。お前らはついでだ」
夏日まぶしい街路の通りへ、ぶらぶら二人、たるそうに出ていく。
息をのんで立ち尽くした耳に、充満するような蝉の音が戻った。
じりじり夏日が照りつける。
「……か、勝った?」
かすれた、間抜けな声が出た。
のろのろ互いに顔を見る。三人それぞれ己を指した。
「「「 俺らが、特務に? 」」」
絶句で、大きく目をみはる。
膝から力が抜け落ちて、三人そろってへたりこんだ。
どっと噴き出た額の汗を、引きつり笑いでボリスはぬぐう。「ああああ案外、話の分かる連中じゃねえかよっ」
どんな怪物かと思っていたら。
ガタイのいい背中をそらし、ブルーノが後ろ手をついて足を投げた。
細く息を吐きながら、ボリスもあぐらで座りこむ。指の先が震えている。投げた手足がわなないている。ふと、隣に目を向けた。
「……どうした? ジェスキー」
同じく地面に足を投げたジェスキーが、うつむき、後頭部を触っている。「──たく。一体何がどうなってんだか」
左の目に当ててある、眼帯を外そうとしているらしい。
「お、おい。お前、まじで大丈夫かよ……」
肘鉄を決めてしまったブルーノが、心配顔で覗きこむ。「そういや、さっきも、変な感じって」
眼帯を外したジェスキーは、目頭を押さえ、しきりに首をひねっている。焦ってボリスは眉をひそめた。「……痛むのか、目」
「あ、いや、そういうんじゃないんだが──むず痒いっていうか、鬱陶しいっていうか、こんなこと一度もなかったのに。つか、感覚自体、今まで全然──」
顔をしかめて首を振り、あぐらをかいた靴を見る。
振りかかった髪の下、呆然としたように動きを止めた。
「……な、なあ。お前ら、どう思う? いや、俺も、まさかとは思ったんだが──俺さ。俺の目」
のろのろと顔をあげ、困惑顔で見返した。
「見えるんだよ、俺の左目」
( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
※ 8/27(土)9:00頃を境に「web拍手」が繋がらなくなっていたようです。
もし、頂いていたらすみません。
同日23;10に修正しました。
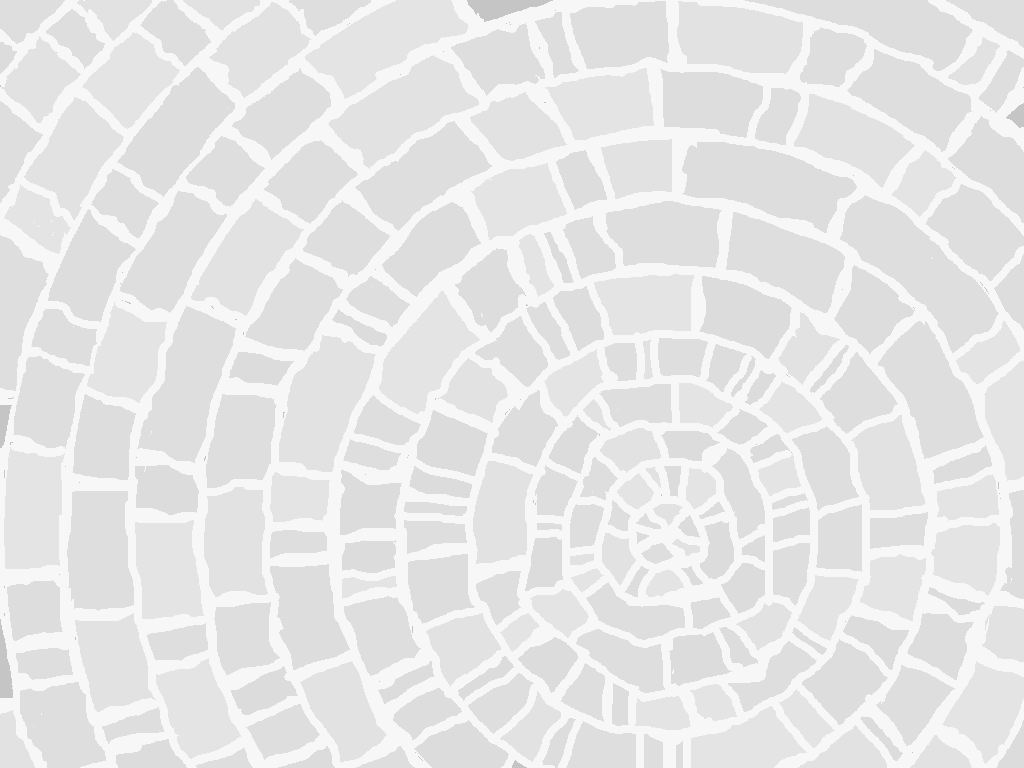
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》