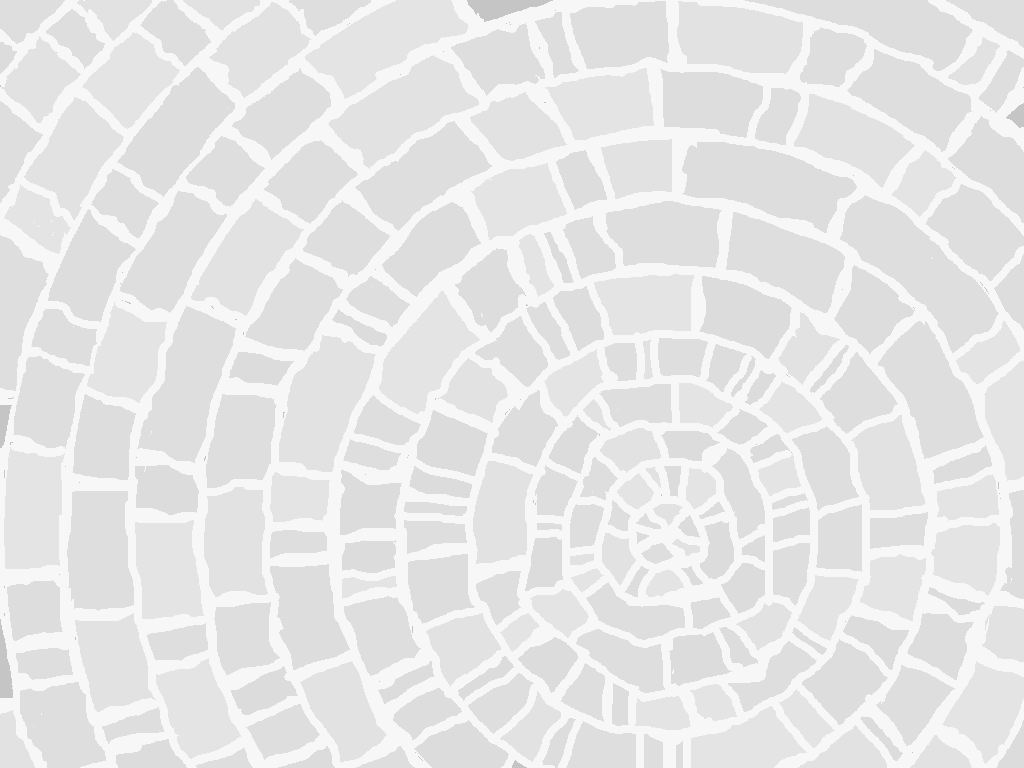
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章37
( 前頁 / TOP / 次頁 )
路地の角を曲がった途端、二人は同時に地を蹴った。
「──付き合ってられるか」
軽く走る横顔でごち、ザイは捜索の視線を走らせる。
赤の鞄を背負った姿は、すでにどこにも見当たらない。街路がゆるく湾曲し、建物の壁で見通しがきかない。
通りに面した軒先で、木箱に盛られた赤い果実が、凪いだ夏日を浴びていた。
影が色濃く落ちている。まだ暑い日中のこと、街の端のこの界隈に通行人の姿はなく、街路はひっそりと静まっている。
多少足が速かろうが、町育ちの堅気の娘だ。まだ、そう遠くへは行っていない──行きすぎる路地を覗きつつ、ふと、ザイは苦笑いする。「──なるほどな」
手持ちの金がなくなって泣きついてきた顔を思えば、逃げ出した理由が解せなかったが、これでようやく腑に落ちた。
『 でも、借金とりが追っかけてきて、馬車に隠れたら動いちゃって── 』
「で、姫さん、なんだって?」
だしぬけに声をかけられて、面食らって振り向いた。
左を走るセレスタンが、黄色い眼鏡の向こうで促す。客が逃げ際に抱きついた時の、耳打ちのことを言っているらしい。
「──ああ、別に」
「隠すようなことなわけ?」
からかいまじりの催促に、ザイは苦虫かみつぶす。「別に大したことじゃねえ。──たく。まんまと足止めしやがってよ」
あの不意打ちに虚をつかれ、あの場の全員が固まった。もっとも、その当人には、そんな意図などなかったろうが。
ちょうど一日前の今時分、腰を落ち着けたばかりの居酒屋で、彼女が姿を消したと悟り、二人は街路へ飛び出した。
向かった先に心当たりがあった。それは、客の後をつけ狙う町の与太者を叩きのめし、店へと戻る道すがら、耳に入った会話の切れ端。
人もまばらな昼の通りで、脇をすれ違って行ったのは、旅慣れたふうの二人組だった。男同士の二人連れ。初めに注意を引いたのは、一人が無造作にさげていた袋。それは実によく似ていた。北から馬群で南下中、客が持ち歩いていたあの袋と。
そして、セレスタンも覚えていた。闇医師シュウの診療所で、たむろしていた数人の男。その中の二人だと。客から聞いた話では、診療所の取り立てにあったという。
右側を歩く小太りが、忌々しげに闊歩しながら、連れの眼鏡に確認していた。
『 なら、あの女が向かったのは、グッドール商会ってことになるか 』
急きょグッドール商会の所在地を調べ、トラビア街道要衝の街、ノアニールに乗りこんだ。だが、店の付近で一昼夜見張るも、客は姿を現わさない。
やむなく移動を考えた矢先、街の外れで騒ぎがあった。
街路を走る与太者を尾行け、直ちに現場へ急行した。与太者を排除し、客の身柄をようやく確保。だが、アドルファス隊 の二班に阻まれて、結局まんまと逃げられた。
「分かれ道だな」
路地の先に慎重に目をやり、セレスタンがつぶやいた。
行く手で大きく、道が二手に分かれている。
左の道は、この街の中心部、目抜き通りへ続く道。右は西方、あの水路へ続く道。客がやってきた方角だ。道行く人影は、相変わらず、ない。二股の分岐がぐんぐん近づく。
「満更でもないくせに」
思わず、禿頭を振り向いた。「……あ?」
「右はよろしく」
別れ間際に笑みを投げ、禿頭は道なりに駆けていく。
あぜんと、ザイは見送った。
「……本気かよ、あのハゲ」
絶句で、人けない街路を走る。
「──あの隊長と張り合う気かよ。いや、その前に」
副長がいるか……と微妙な気分で空を仰ぐ。むしろ、誰より鉄壁の守り……。
道なりに角を曲がった途端、日常の物音に紛れて鳴っていた、かすかな水音が大きくなる。
路地から行く手に戻した視界に、光のきらめきが飛びこんだ。
木陰の涼しげな遊歩道。右から左へ流れゆく水面が、夏日を弾いてまぶしく光る。道は水路で突き当り。走り出、視線を走らせて、水路の下流、遊歩道の左で目を止める。
「な──!?」
思わず、それを見直した。
思いがけない光景に、あぜんと一瞬、思考が止まる。
わっせ、わっせ、と赤い鞄が駆けていた。小柄な肩で、黒髪を揺らして。強い夏日に溶けこみそうに──。
いかにも、客を発見した。
だが、想定したより、はるかに遠い。
「──馬鹿な」
目の前の現実が合致せず、立ち尽くした頭が混乱をきたす。
不意に記憶が呼び覚まされた。前にもやはり、似たような不覚をとらなかったか。
あの忘れもしない転落事故だ。客が崖から滑落した。そして、その事故の直前、森で副長に追い抜かれた──。だが、副長は別格だ。あの飛び抜けた身体能力の高さは、いっそ異質の部類に入る。この前を往くことのできる数少ない一握りの相手だ。
そう、あんな所にいるなど、ありえない。距離が開きすぎている。あの副長と同じ血が流れている、というならともかく。
──いや、とザイは、苦々しく首を振る。心当たりがないでもない。アドルファス隊 の二班の連中だ。
可能なかぎり短時間でやり過ごしたつもりでいたが、思う以上に時間がかかっていたのかもしれない。ともあれ、今は早く客を連れ戻さねば。
気を取り直し、後を追う。
つかのま脳裏をよぎった顔が──亡き友との約束を持ち出した、あの必死などんぐり眼が消え去ろうとしたその刹那、ふわり、と耳打ちがよみがえった。
『 ありがとザイ。迎えに来てくれて 』
ぎり、とザイは奥歯を噛んだ。
行く手の"赤"に目を据える。
「──やれるかよ、戦地なんかに」
ひときわ強く、地を蹴った。
ひっそりと人けない、水面きらめく遊歩道。明るく穏やかな光に満ちた、安寧そのものの日常の風景。これこそ客のいるべき場所だ。
治領のノースカレリアが他領から奇襲を受けた折り、戦に巻き込まれたはずだったが、さしものあの隊長も、客に見せはしなかったろう。あの戦場の惨たらしさを。ばたばた人が死んでゆく血にまみれた救いのなさを。
この先の手数を省くため、相手に気づかれぬよう距離をつめた。
ここで気づかれ、逃げ回られれば、また、どんな横やりが入るか知れたものではない。
小柄な肩の赤い鞄、前を走る標的を見つめる。ふと、ザイは眉をひそめた。
……速度があがった?
急に足を速めた原因は──。思案し、すぐに思い当たる。
つまり、目的地が定まったのだ。客の行く手に目をやれば、案の定、遠くに人影がある。
「──知り合い、か?」
遠目だが、見ない顔だ。身なりは今風、若い男だ。髪は短く、背は高い。水面きらめく遊歩道で、何かを探すように見回している。客が接近していることに、幸い、まだ気づいていない。
追跡の足を、ザイは速めた。
客がこうして逃げている以上、一たび男と合流すれば、話がよけい厄介になる。あの客一人なら、いかようにも言い包められるが、問題なのは男の方だ。近づくにつれ大きくなる男の姿に意識を向ける。
ぎくりと、とっさに目をそらした。
胸のざわめきをいぶかしみ、眉をひそめて相手を見返す。
「……同業か?」
それも、かなりの腕前だ。
遠目からでも、それはわかった。隠しようのない覇気がある。
隙のない身のこなし。力の抜けた日常というのに、さりげなく片足を引いている。つまり、左右どちらにも動ける。おそらく無意識の習慣だろうが、むしろ、無意識だからこそ、ふとした拍子ににじみ出る。こちらに気づくその前に、客の身柄を確保せねば。
話がこじれるその前に。
客を見据えて、足を踏みこむ。
視界が揺らぎ、靴裏が浮く。
──標的まで、あと少し。
それに気をとられ、気づくのが遅れた。
強い圧に引き戻されたその矢先、ザバン──と激しく水しぶきがあがった。
浅い水底に、手をついた。
むくり、とザイは身を起こし、ぷるる……と犬のように首を振る。
髪からしたたる水滴の中、呆然と見まわし、目を止めた。
先行する客との間に、男がいつの間にか歩いている。さらりと長めの茶色の頭髪。身の軽そうな小柄な背。肩には旅仕様の新しいザック。
「……さしずめ、良家のボンボンってとこか」
さりげなさを装ってはいるが、身なりに金がかかっている。接近の気配がなかったが、そこの並木から飛び出してきたのか。もっとも、ぶつかった当人は、気づかないのか見向きもしないが。
この日照りで、人けはない。ならば、人違いの余地はない。今の犯人は間違いなく──
「──あのガキ、ふざけやがって!」
水を蹴立てて、立ちあがった。
頭からずぶ濡れで、苛立ちに任せて足を踏み出す。
ぐい、と肩を引き戻された。
「町で騒ぎを起こすんじゃねえよ」
耳元でささやいたその声に、一瞬、全身に緊張が走る。
のんびりしているようでいて、有無を言わさぬ落ち着いた口調。そう、妙に張りのあるこの声は──
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》