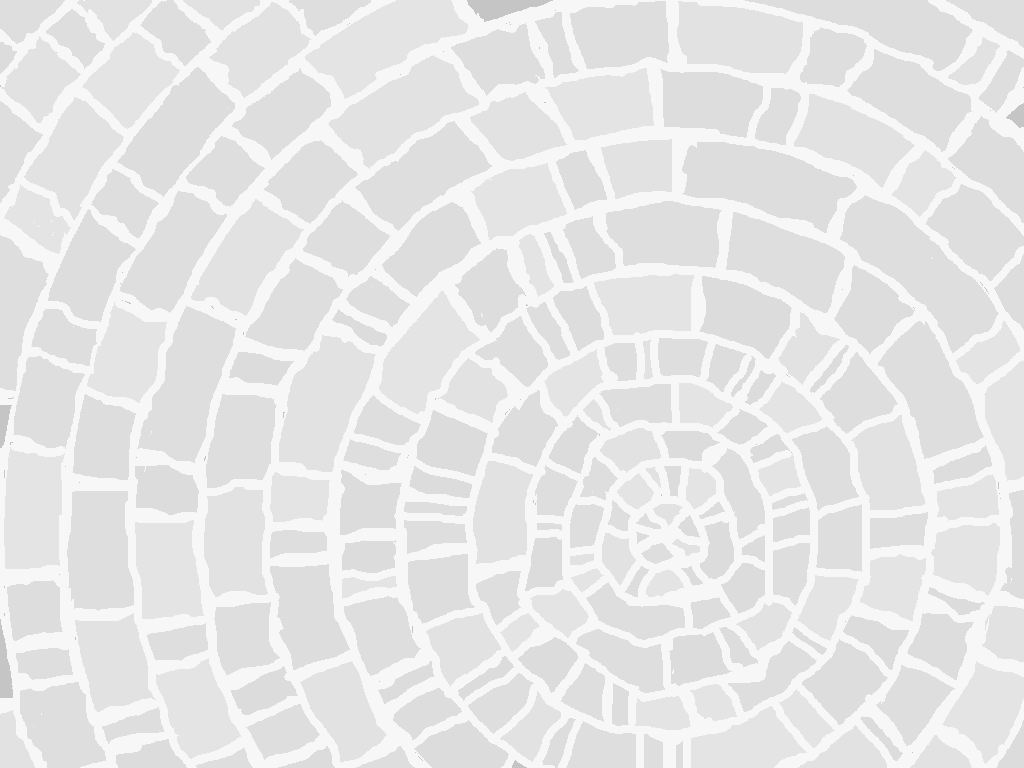
※ 爵位の序列を、作者が勘違いしていたため、
「子爵」→「伯爵」に訂正いたしました。すみません(^0^;
13:58 2016/09/27
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章39
( 前頁 / TOP / 次頁 )
破れた幌から射した夏日が、荷台の隅を照らしていた。
がらんと物のない床板には、ザックが三つと、風よけの外套。
店の裏手で停まったきりの、荷馬車の幌を、蝉の音が包む。馬車の持ち主は戻らない。
日陰一つない街道を、一人で馬車を駆ってきたセビーは、荷台の前の御者台で、くーかー口をあけてうたた寝している。
路地にザイらを置き去りにして、連れの元へと戻ってみると、ささやかな吉報が待っていた。
与太者たちから逃げ回っている間、セビーがおじさんの友人から──ゆうべの宿の主から、隣町に返す荷馬車を、代わりに運ぶ話をとりつけてきたのだ。
西へと馬車が進む間、エレーンは連れのユージンと荷台で揺られていたのだが、いつの間にか居眠りしていた。
その間ずっと、一人で幌に寄りかかっていたのだろうユージンは、到着を知らせたセビーと目配せ、町を見てくる、と出て行った。そして、まだ戻らない。店の所在地は知っているはずだが、荷台の連れに寝られてしまい、ずっと退屈していたのかもしれない。
宿の主から預かった馬車を、店の裏手に停めていた。
目的地に着いたとはいえ、持ち主に確かに引き渡さねば、馬車のそばを離れられない。
「……どうしたかなあ、みんな」
一人きりの幌の下、エレーンは膝に突っ伏した。「……ごめんね、セレスタン」
それに、ザイも。
あの路地に残してきた二人の顔が目に浮かぶ。
懸命に逃がそうとしてくれたボリスたちには悪いけれど、本音をいえば、あの二人といたかった。
知らない街路でセレスタンを見た時、どれほどほっとしたことか。思わず飛びついたあの時の、やっと家路を見つけたような得も言われぬ安堵感。
ザイも迎えに来てくれた。上っ面だけであしらうザイが、本気で身を案じてくれた。
ボリスに急かされ、とっさに逃げたが、戻って覗いたザイの目に、忌々しげな色はなかった。その目は静かで、あの鋭い反応はなかった。だから、きっと大丈夫だと思った。彼との距離を、もう少し詰めても。
誰かが置き忘れた新聞の端が、荷台の隅で、風にめくれる。
夏の匂い。湿った手触り。地面でちらつくまだらな木漏れ日。昼下がりの町は静かだ。
手を伸ばし、板床に放り出してあった赤いリュックを引き寄せた。
手のひらにのせた布製のタヌキの、とぼけた顔を、じぃ……と見つめる。
ぴん、と顔を指で弾いて、はあ~……と溜息でうなだれた。
「会いたかったな……」
夜の街で見かけたケネルと。
床にぐりぐりマルを書き、じたばた足をばたつかせる。
「あ゛あ゛あ゛ やっぱあの時、会っとくんだったーっ!」
でも……と支障を思い出し、顔をゆがめて動きを止めた。そう、ケネルに会うこと、それ自体はいい。でも、それだけでは済まない問題が──
とんとん指で床板を叩き、思いあぐねて天井に嘆息。
「……けど、あの女がなあ……」
ケネルのそばにいた知らない女。浅黒い肌をした、目鼻立ちの整った──。あの彼女が誰なのか、ケネルとの関係はわからない。けれど、たぶん同郷で、たぶん近しい間柄。だって、彼女と話すケネルの笑顔は、いつになく親しげで──。いや、ケネルとどうにかして会ったにせよ、真っ向から対面したら、例の返事はどうするのだ。持ち越したままの、あの時の──
『 俺とくるか 』
うっ、と赤面で硬直した。
あの時計塔の光景がよみがえり、ぶんぶん首を横に振る。本気になっては、だめなのだ。深刻な領域に踏み込んではいけない。みんなのことが好きでもいい。それと同じ意味合いで、ケネルのことが好きでもいい。でも、それ以上はご法度だ。
だって手が届かない。歴とした連れ合いがいる。そんな不実は許されない。世間的にも自分的にも。平気で言ってくるあたり、ケネルは気にしてないようだけど。
ケネルが誰とどうしようが、文句の言える立場じゃない。でも、彼女に優しいケネルを見たら、きっとケネルをぶっ飛ばす──
「……う゛う゛う゛~っ!」
頭の中がぐるぐる回って、悶々と頭を掻きむしる。そんなものは、ないはずだ。二人の仲を邪魔してまで、ケネルに会いにいく理由など──
はた、と膝を打って目をあげた。
「そ、そうよっ! あるじゃない、理由なら!」
あの昼の陰気な酒場。倦んだような目をした男。そうだ、ケネルに知らせねば!
──ケネル自身が狙われていると。
あの凶暴な海賊あがりは、まだ海賊をやめてない。密かに略奪を繰り返しているのだ。当局の目が届かない、大陸から離れた群島あたりで。
不治の病に苛まれ、期限が迫ったあの男は、藁にもすがる思いで固執する。「人魚の肉」などという迷信に。今こうしている間にも、大勢の手下を招集し、虎視眈々と狙っているのだ。ただ一つ、ケネルの心臓それだけを。だから──
「だだだだからいいよねっ? ケネルと会ってもっ!」
己で己にこくこくうなずき、はた、と前のめりで我に返った。
しおしお脱力、うなだれる。
「──口実、だよね」
そんなのは。
たとえケネルに伝えたところで、果たしてどれほどの助けになるか。
彼らは本職の傭兵で、つまり戦闘にかけては専門家で、相手が凶暴な海賊とはいえ、だらだら日暮らす与太者などとは技術も経験も桁違いなのだ。あれほど優しいセレスタンでさえ、五人の手下を難なく下した。ましてそれが隊長の実力を持つケネルなら……
「……。だよね」
抱えこんだ膝に嘆息した。
うつぶせた肩に、背に、暑気が気だるくのしかかる。
がらんと物のない幌の中、蝉の音だけが遠く聞こえる。右の手のひらを強く握った。口実でも何でもいい。それでも、どうしてもケネルに会いたい。知らない女が横にいても。だって、どうしても、
──ケネルに会いたい。
意識が、不意に引き戻された。
さわり、と空気が動いた気がする。とはいえ、ここは馬車の中。雨避けの幌に囲まれている。首をかしげて目をあける。
「──わっ!?」
ぎょっと壁まで後ずさった。
至近距離に、誰かの顔面。
ぴたり、と背中で幌に張りつく。
「……ゆゆゆゆゆーじんくん?」
にっこりユージンが笑みを作った。「ごめん。起こしちゃったみたいだね」
「なっ、なになになにっ? なんか用っ?」
あわあわ恐慌、肩を引く。一体そこでなにしてんの!? てか、あなたは一体
──いつから、そこにー!?
目と鼻の先でしゃがみ込み、じっと顔を見つめていた。
不思議なものでも見るように、熱心に観察するような面持ちで。他人のつむじを観察しても、さして面白いとも思えないが、なんぞ謎の趣味でもあるのか?
膝の頬杖をユージンが外し、すっと右手をさし伸ばした。
頬にひんやり、何かの感触。
とっさに押さえて、首をすくめ、引き抜かれた彼の手から、頬のそれをエレーンは受けとる。
ぽかん、とユージンの顔を見た。「……これ」
「こういうのも好きかと思って」
利発そうな相好を崩して、にっこりユージンは頬杖で笑う。手のひらにのっていたのは、涼やかな色の氷菓子。
「……え……もしかして、買いに行ってくれてたの?」
それが彼だけ一足先に、街道で馬車を降りた理由?
「良さそうな屋台も見つけたよ。今から一緒に行ってみない?」
「う、うん、いいねっ! でも、お店の人が戻ってなくて、セビーがまだ動けないから──」
「いいじゃない、あいつのことは」
ユージンは笑顔で、だが、問答無用でぶった切る。「あっちはほっといて、僕らだけで行こうよ」
「でも、断りもなく出かけたら──」
「あいつ、甘い物食べないし、誘うだけ無駄ってもんだよ」
「あ、でも、またセビー怒ると思──」
「疲れてぐっすり寝てるのに、わざわざ起こすこともない。ね?」
「……そっ」
なぜに、そんなに断固排除したがるのだ?
「で、でもね? ユージンく──」
「豪華五段重ねフルーツ・パフェ・デラックス」
「……へ?」
ほとんど喋らせてもらえない、ごり押しの勢いに気圧されて、ぱくつかせるばかりだった口が一瞬閉じた。
神々しいまでのその様をうっかり想像した間隙を突いて、ユージンは着実に畳みかける。
「ちょっと試してみたくない?」
にっこり笑顔で、誘いをねじ込む。
むしろ自信のない顔など見たことがない。
「──あっ──だっ、だけど、そのっ」
お愛想笑いでエレーンは逃げ腰。「セビーがいないと、そういう高そうなのは、あたし、ちょっと──」
「おごるよ?」
「……まじで?」
ぱっとエレーンは振り向いた。
至近距離の真顔で見つめる。
「まじで」
釣りあげられるようにして膝を立てた。
とたん、そわそわ気もそぞろ、馬車の荷台に座った尻を、ぎこちない笑いで、ぱたぱた払う。「す、すぐに戻れば大丈夫かも……」
「そうそう、そうだよ。それに来るよ、あいつも、どうせ」
エレーンはうつろにたじろぎ笑った。「ゆ、ゆーじんくん……」
邪険だね。
そして、たまに腹黒いくらいに強引だ。
少し町を見てくる旨、セビー宛で紙にしたため、馬車の荷台に残しておいた。
先に荷台から飛び降りたユージンの肩につかまって、エレーンもまたぐようにして地上に降り立つ。
裏手の路地をユージンは出、上機嫌で歩いていく。目抜き通りへ行くらしい。
(ユージンくんって本当に──)
賢そうな顔してるよね~、と横から顔をつくづく盗み見、エレーンはいそいそ氷菓子を頬張る。「ん──あ、これ、おいしい!」
「ね、中々いけるでしょ」
「うん、おいしい! すんごくおいしい! ああ、なんか生き返るぅ~!」
ユージンがはにかむように微笑んだ。
「よかった。君に喜んでもらえて」
……あれ? とエレーンは眉根を寄せた。
「あ……えっと……う、うん……」
ほりほり指で頬を掻く。あれ? なんだ、この感じ……
晴れ渡った空に伸びをして、彼はすがすがしく笑っている。「こんな暑い盛りだよ。お茶でも飲んで休憩しなくちゃ」
「そ、そだね……」
気のせいかな……と密かに首をかしげつつ、エレーンは引きつり笑いで汗を拭く。
ぶらぶら道を行きながら、町で見つけたのだという甘物屋について、ユージンは笑って話している。
ふと、気づいたように振り向いた。
「そういえば、大丈夫だった?」
心配そうに顔を覗く。「目つきの悪いチンピラに、追われていたようだけど」
そういえば、とエレーンは、遅ればせながら思い出した。まだ事情を話していない。あのザイたちを振り切って、戻った後は気忙しくて──
預かる荷馬車を受け取りに行って、あの後すぐに街を出た。街から街道に出たとたん、街中逃げ回った疲れもあってか、不覚にも荷台で眠りこけてしまった。この同乗者を置いてけぼりにして。
「あ、うん。そうなの、実は──」
店へと向かう道すがら、事の顛末をユージンに話した。とはいえ、三バカとザイたちのことは、こちらの素性にも関わるし、諸々の事情でさりげなく伏せたが。
ユージンたちのいた甘物屋を出、通りで買い物していたら、町の与太者に絡まれたこと。そのまま酒場に連れこまれたこと。そこには海賊あがりの親分がいて、一人で酒を飲んでいて──
「誰だって?」
何気なく出した頭目の名に、ユージンが顕著に反応した。
「あ──えっと、確かジャイルズとかって名前で」
「ジャイルズ……」
ふとユージンは眉をひそめ、利発そうな顔を曇らせた。
苦々しげに目をすがめ、こぶしを顎に押しあてる。「──海賊になったのか」
顔を振りあげ、振り向いた。
「出よう。町を」
だしぬけに手首をつかみ、つかつか早足で歩き出す。
引っ張られて歩かされ、エレーンはあたふた彼を見る。「き、急にそんなこと言われてもっ!?──ちょ、ちょっと待ってよ、まだセビーが──」
「いいから、あいつのことは」
「……や。さすがに、そういうわけには~」
しどもどエレーンは引きつり笑い。いくら仲が悪いからって、ここに一人で置き去りにする気か?
急いた様子にたじろいで、彼の横顔をそろりとうかがう。「……ね、ねえ、ユージンくん?」
「なに」
「あの、もしかして知ってるの? あたしが会った海賊のこと」
「なぜ」
「あ、だって──さっき、なんか、そんな言い方──」
足早に歩く横顔は、行く手を見たまま振り向かない。
現れた町角を、左に曲がる。凪いだような夏日の下、白壁が続く、人けない道。
手首をしっかりつかんだままで、ユージンは手を放さない。どんどん遠ざかる荷馬車を気にして、エレーンはおろおろ振りかえる。「どうして急に、こんなこと──」
「……どうして、だって?」
ユージンの足が歩みを止めた。
「君は──」
たまりかねたように、背中でつぶやく。
初めて彼が、苛立ったように目を向けた。
「わかっているの? 君は自分が何者なのか」
「……え」
ユージンが大きく踏み出した。
それに押し戻されるようにして、エレーンは壁へと後ずさる。
とん、とユージンが壁に手をつき、壁に肩を押しつけた。
小柄とはいえ、やはり彼の方が上背がある。覆いかぶさる頭上の顔に、エレーンはあわあわ目をみはる。「……ゆ、ゆーじん、くんっ?」
「口を閉じて」
真顔の瞳が、間近に迫る。
「目を閉じて」
ごくり、とエレーンは唾をのむ。まさか、これって、もしや、
……キスか!?
だが、あまりに急な展開に、目をつぶるどころか、更に目をみはってしまう。
固まった相手に焦れたように、向かいの肩がおもむろに迫った。
その唇が言葉を紡ぐ。
《 Fit via vī. 》
ぞくり、と全身総毛立った。
聞こえてきたつぶやきは、聞いたことのない言語。体中の血液が吸い出され、端から霧散するような──。
体が硬直、足がすくんだ。
ぽっかり口をあけた暗黒に、背中から倒れこむような恐怖感。
あたかも流砂に呑まれるような、抗いがたく壮絶な勢い。指一本動かせないが、せめて意識で流れに抗う。
伏せたまつ毛を彼があげ、片手をついた壁を見た。
「……なぜ」
壁に手応えがありすぎるのを、いぶかるような面持ちだ。
覆いかぶさった彼の陰から、呆気にとられてエレーンは仰ぐ。
「な、なに? 今の言葉……」
なにかの、呪文、だったみたいな……?
こぶしにした手を口に当て、ユージンは眉をひそめている。考えを巡らせているように。
目をあげ、ぐい、と手首をつかんだ。
「出よう」
「──え?」
「町を出る。行くよ」
その手を引っ張り、問答無用で歩き出す。
たたらを踏んで、エレーンは踏ん張る。「えっ? えっ? 今すぐ!? 行くってどこへ!?」
「遠くへ」
「な、なんでいきなり!?」
「ノアニールに近すぎる。連中の拠点から離れないと」
「な、なら、どうしても行くなら、セビーにも言っ──」
「あいつはいい」
「でも、あたし、お金なくて、セビーがいないと──」
「君の面倒くらい、俺がみる!」
「何やってんの?」
苛立って振り向いたユージンが、男の声に動きを止めた。
彼の向こう側で見えないが、道の先に誰かいる。
「こんな所で痴話ゲンカ?」
そちらに背中を向けたまま、ユージンは意識を凝らしている。重ねて声をかけてきた相手が誰か推し量るように。
エレーンも奇妙なことに気がついた。今の声に聞き覚えがあるのだ。どこかで聞いたことがある。深みがあるようでいて、軽い響きの独特の声音。
相手がいる道の先へと、ユージンは眉をひそめて振りかえる。「──君か」
「ご機嫌いかが。オベール伯爵」
白壁の続く道の先に、男が一人立っていた。
小首をかしげた薄い唇が笑っている。シャツのボタンを二つあけた、大きな花柄の派手な綿シャツ。細身の背格好。ゆるい癖のある赤い髪──
「え?」
思わずごしごし目をこすり、エレーンは面食らって見返した。
「……レノさま?」
( 前頁 / TOP / 次頁 ) web拍手
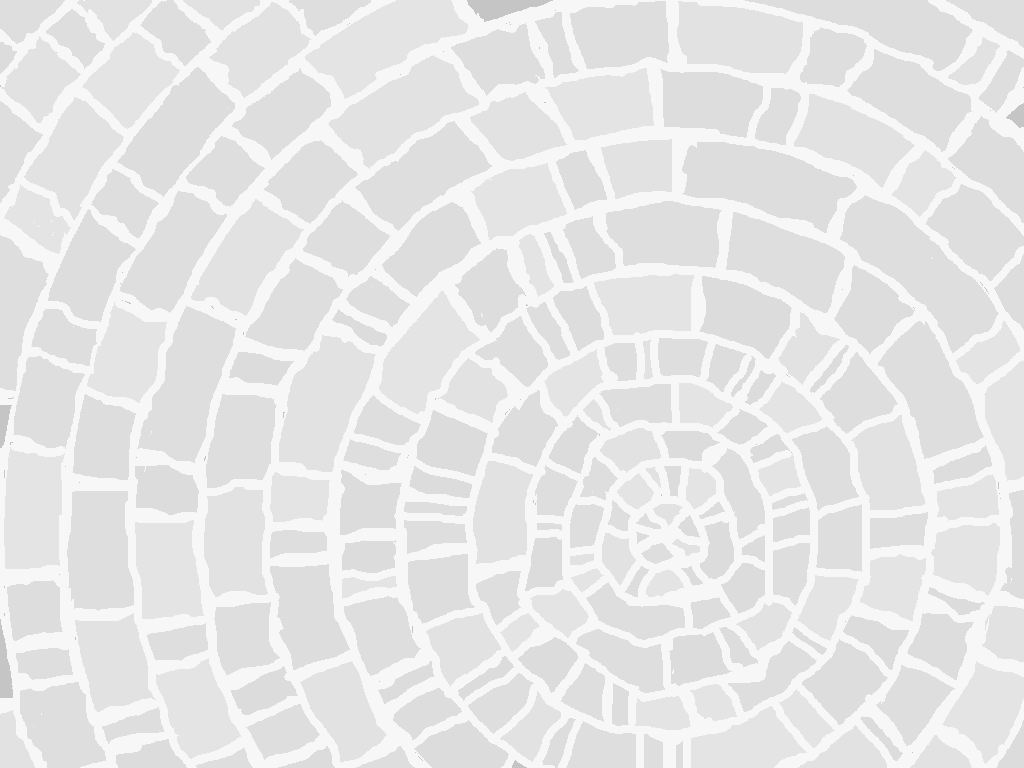
※ 爵位の序列を、作者が勘違いしていたため、
「子爵」→「伯爵」に訂正いたしました。すみません(^0^;
13:58 2016/09/27
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》