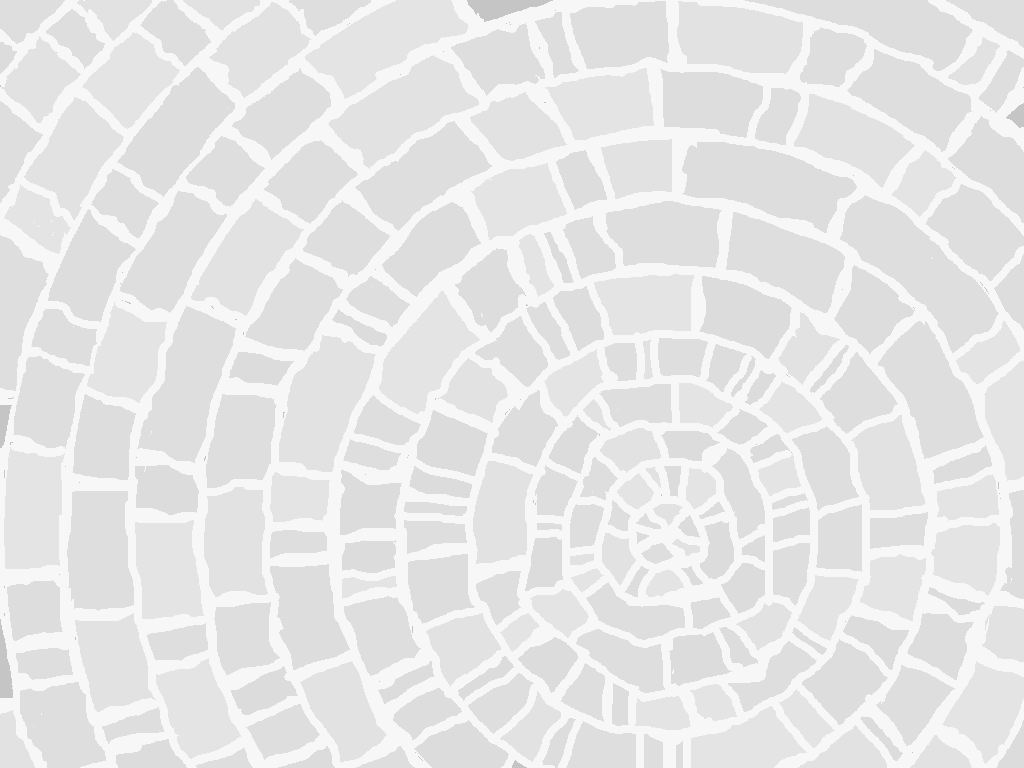
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章54
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「ちょっと、どいて」
とん──とレノが脇をすり抜け、荷台の上に飛び乗った。
彼女の前でしゃがみこみ、力ない体を抱き起こす。
「なに、お前、いつまで寝てんの」
しゃがみ込んだその膝へ、無造作に彼女を引きずりあげる。
むずかる赤子をあやすかのように、肩を軽くゆすっている。
荷台の外で立ちつくし、セヴィランは思わず目をそらした。
もう、息をしていない。
呼んで起きるようなものではない。言ってもレノには分からないだろうが──。
彼女がついに事切れたのを、肌に感じて理解していた。
命のともし火が消えたのを。あんなにも牙を剥いていた、彼女が放った緑焔は、すでに跡形もなく消滅している。
悪夢を見ているようだった。
しん、と彼女が横たわっていた。白襟、紺服の制服で。レノにふざけて着せられた、冗談のようなメイド服姿で。
柄シャツの背からはみ出た手足が、されるがままにぶらぶら揺れる。まるで壊れた人形のように──
「……よせ」
たまりかねて呼びかけた。
「もうよせ。その子を放してやれ」
何もかもが、もう遅い。
「──ほら、オカッパ、目を開けろ」
レノの背は振り向かない。わからないなりにも懸命に、まだ彼女を起こそうとしている。相手を無視していたぶるような、子供のように残酷なその手で──
たまらず、とっさにその肩をつかんだ。
「よせと言っている! 聞こえないのか!」
引き戻された肩越しに、レノが冷ややかに一瞥をくれた。
「離せ」
ぎくり、と手の筋が硬直した。
思いがけない殺気にあてられ、戸惑い、のろのろ手を放す。
宙に浮いた手のひらを握り、表情のないその顔を見た。
「……その子はもう、動かないだろう?」
腹の底まで冷え込んだ、重い溜息で言葉を紡ぐ。
「いくらあんたがその子を呼んでも、そうしていくら揺すっても、その子はもう起きないんだよ。もう、目はあけないんだよ。だってな……だって、その子はもう──」
「なに。死んだとでも言うつもり?」
言葉を失い、唇をかんだ。
そうだ、とは言えなかった。彼は仲間を亡くしたばかりだ。大事にしていた病気の娘を。酷というものだった。その傷も癒えぬ間に、その上それを告げるのは、この仲間の彼女まで、失ったのだと告げるのは。
言葉を選んで逡巡し、やっとのことで言い聞かせた。
「……もう、終わったんだよ」
ぷい、とレノが顔を背けた。
彼女の体をかかえ直して、膝の顔を覗きこむ。
「ほら、オカッパ。バールに着いたぞ。とっとと起きろよ。いつまでお前、待たせるつもり?」
呼びかけ、軽く頬を叩く。
「西にあるラズール通りの、"ルゼロ"まで行ってきて。買ってくるのは黒の上下、一番仕立てのいい奴な」
どう見ても異常事態だ。普通の状態でないことは、見てすぐにわかったろうに。
目を閉じ、奥歯を食いしばった。無邪気にすがるそんな姿を、もう見ていられない──
はっと息を呑んで、目を開けた。
不意に気配が変わった気がして、とっさに荷台を振りかえる。
しゃがんだレノの膝の上、彼女のまつげがかすかに震えた。
ぼんやり、瞼が開かれる。
「……レノ、さま」
愕然と凝視したその前で、レノは「……なんだよ」と顔をしかめる。「着替えろっつったの、お前だろ」
「ドーナツ、食べたい」
「……。なにお前」
口を尖らせたレノの腕に、くたり、と彼女の頭が落ちた。
さわり、と頭をなでられた。
軽く触れてみただけの、そんな感じの、しなやかな手のひら──
瞼の向こうが、いやに明るい──不意に覚えたまぶしさに、セヴィランは顔をしかめて目をこすった。
突っ伏した卓から肩を起こして、くわ、とあくびで首を振る。
「……やべ。寝ちまってたか」
何度か瞼をしばたいて、顔をしかめて視線をめぐらす。「何時だよ、今……」
ほの暗く静まった昼の居酒屋の店内には、時計も人影も見当たらない。彼女を部屋に運び込み、階下に降りて、食事をしたまでは覚えているが──。
泥のように眠っていたらしい。
長らく卓を占領し、眠りこけていたにもかかわらず、放り出されることもなく、こうして居座っていられたのは、店が混み合う昼時から、大分外れていたからだろう。二階に部屋をとった客でもあるし。
枕にしていた頭の重みでしびれた腕を振りやって「このところ、ろくに寝てないからな……」と、うなじのあたりをとんとん叩く。
開け放った窓の外には、午後の夏空が広がっていた。
石造りの古い町並み。なだらかに続く石畳。まだ日が高いから、街路を歩く人影はまばらだ。のどかな町の昼下がり──。
ふと、セヴィランは眉をしかめた。
卓からグラスを取りあげて、ぬるくなった水を一気にあおる。グラスに唇をつけたまま、卓の木目をすがめ見た。
「……どうなってんだ」
つぶさに見ていたはずだった。
だが、何が起きたか、わからなかった。彼女が息を吹き返したあの時。そう、確かに事切れていたのに。
奇跡が起きた?
──馬鹿な、と舌打ちで一蹴し、安易な考えを振り払う。そんなおとぎ話があるわけない。それより、気になるモノを見た。あれは一体何だったのか。あの時、ちょろっと目の端をかすめた──。
あたかも人目から逃れるように。不意に人に出くわしたネズミが、姿を隠すような素早さで。
萌黄にかがやく、ほのかな焔が。
見咎めたその刹那、それはすぐに霧散して、すうっと大気に消え入った。あんなものが生じたからには、何か原因があったはず。──もしや、彼女が自分で自分を? 理由はよくわからないが、彼女には妙な力があるのだ。現にファレスを癒していたし。
──いや、彼女は倒れていたのだ。そんな力を奮うのは無理だ。だが、彼女でなければ、誰だというのだ。一体誰にそんな真似が──
卓のグラスを凝視する。
思案の眉を、ふと、ひそめた。まさか──
「……ファレス、か?」
彼女と共に倒れこんだ拍子に、人知れず意識を取り戻していたら? そして、倒れた彼女を見つけ──
溜息まじりに首を振った。「──いや、違うな」
確かにファレスも特殊な血脈を継いではいるが、そうした系譜の末裔だ。系譜の起首のユージンでさえ──時空を自在に移動する途轍もない術者でさえも、《 あわい 》に落ちたあの彼女を引き戻すこともできなかった。まして生還させるなど、末裔にできる芸当ではない。だが、そうなると、一体誰が──。
彼女ではなく、ファレスでもない。最有力のユージンも、馬車を離れた後だった。だが、誰かが何かをしたはずだ。そうでなければ説明がつかない。あの萌黄のかがやきの。もう一人、誰かいたはずだ。そうした力を奮える者が──
はっと目を見開いた。
握りしめたグラスを離し、その手を開いて、まじまじと見やる。系譜の起首というのなら、もう一人、ここにいるではないか。
「……俺が?」
愕然とセヴィランはつぶやいた。灯台もと暗しとは、このことだ。身に覚えは全くないが、資質というなら十分にある。まだ勘は戻っていないが、いや、戻っていないからこそ、身の内の力を制御できず、無意識のうちに力を放って──?
複雑な思いで我が手をながめ、窓からの陽にかざしてみる。
膜一枚隔てた向こうは、別の地平だとユージンは言った。隣接する時空のはざまに、生死の境《 あわい 》があるとも。ならば、その気になりさえすれば、感じ取ることができるだろうか。
目を閉じ、努めて意識を凝らす。
大気の中に、気配を探る。二つの世界を隔てる壁。目には見えない時空の境──
「……言ってくれればよかったのに」
ぎょっとセヴィランは目をあけた。
あたふた手を引っ込めて、踊りあがって人影を仰ぐ。どこか癖のあるこの声は──
なぜか同志を見るような目つきで、レノが憐れむように見おろしていた。溜息まじりに腕を組む。「前の通りを左に入って、二区画先の三軒目」
「……え?」
「だから、手頃な店だって」
ひょうたんの形を両手でなぞり、まさぐってたろ? と、ちらと見る。「エアー彼女」
「──俺は欲求不満じゃないっ!?」
「じゃ何」
う゛──と詰まって固まった。理由はあるが、とても言えない。
「……。二区画先の、三軒目、な」
敗北感でいっぱいだ。肩身の狭さに身を縮め、すごすご椅子に腰を下ろす。
恨みがましくレノを見た。「まったくあんたは、いつも急だな。しかも、きまって間の悪い時に──て、おい?」
はた、と気づいて向き直った。
「そういや、あんた、馬車はどうした!?」
そうだ、なぜ、レノがいる!? 馬車の番はどうしたのだ!?
ああ、それね、という顔で、レノが事もなげに窓を見やった。「ん。ファレス、起きたから」
「つまり、一人で置いてきたのか!? 何かあったら、どうするんだ! 強盗にでもやられたら!」
「知ってる? あいつ傭兵よ?」
……あ、とつまって思い出した。あの端正な顔立ちにそぐわぬ、そうした勇ましい生業だったと。
「あの手の野蛮な連中って、喧嘩関係は得意なんじゃないの? ただでさえ目つき悪くて鋭いから、町の与太者風情なら、あいつなら余裕で──」
「追い返す、か。だが、あんなに弱っていたら」
「どうせ、すぐに馬車戻るし」
「……。まあ、そういうことだったら」
溜息まじりに背中を戻し、椅子の背もたれに腕を置く。「着替えてきたのか」
レノは柄シャツから一変し、黒の上下を着こんでいる。
「だって、あいつ、うるせーんだもん」
そういえば彼女に、身なりで文句を言われていたが──。つまり、長袖を着て暑くなるより、小言を言われる方が嫌なようだ。
「それにしても極端だな。急に黒の上下ってのも。ずい分まともな成りじゃないか」
柄シャツを着ていた男にして、意外にも簡素な装いだ。白いシャツもよくある無地。金満家の衣服のような華やかさの欠けらもない。もっとも生地は良いようだが。
「ん、一番飾りのない奴。びらびらしたボウタイだの、紐だの肩章だの趣味じゃない」
「なら、なんでさっきまで、あんな格好──?」
「あれは女にもらった奴」
ちょっと涼しかったから、と悪びれるでもなく、こくりとうなずく。
……そうか、とセヴィランはたじろぎ笑い、レノがぶら下げた袋をさした。「で、それは?」
「──たく」
レノもうんざり紙袋を見やる。「主人をパシリにするとか聞いたことねーよ」
顔見たとたん飯の催促とかなんなのあいつ、とぶちぶちごちる。
思わず、セヴィランは苦笑した。
「いいご主人さまだな」
レノが苦虫かみつぶして肩をすくめた。「今回は特別。復活祝い」
しかめた顔は不本意そうだが、それでも店まで、わざわざ足を運んだらしい。彼女がつぶやいたドーナツを買いに。
「……正しかったな、あんたは」
しみじみレノの顔を見る。取り乱した甲斐あって、彼女は意識を取り戻した。ずっと彼が言い張っていた通りに。
「なに急に」
怪訝そうにレノは瞬き、階段の先の天井を見やった。「で、どうしてる? アレ」
「ああ、部屋で休ませてはいるが」
「見てねーの? 様子」
レノが呆れ顔で肩を返した。
ぶらぶら店奥へ歩いていく。──て、いや、まて。
「うわっ!? あんた、どこへ行く気だ!?」
ぎょっとセヴィランは腰を浮かせた。足を向けたその先には、二階へ続く古い階段。
「どこって、そんなの決まってんだろ」
「おっ、女の子が寝てるんだぞ!?」
「だからなに。別に邪魔はしねえって」
「……。本当か?」
思わず疑惑の目を向けた。馬車で揺り起こしたあの調子で、すぐ又ちょっかいを出しそうだが……
「あっ、いや違う! 邪魔とかそういうことを言ってるんじゃなくて!」
「ぶっ倒れてたら、まずいだろ」
うっ、と不覚にも口ごもった。「そ、それは、まあ、そうなんだろうが──だが、女の子の部屋を覗くのは──」
「来るだろ? あんたも」
え? と思わず見返した。
レノは頓着なく歩いていく。
つかの間ためらい、だが、鍵をつかんで立ちあがった。
連れの背に、そそくさ続く。「よ、様子を見たら、すぐ出るからな?」
振り向きざま、レノが「はい」と押しつけた。
当然のごとく受け取らされて、セヴィランは怪訝に我が手を見る。なぜに手渡す、紙袋なんかを。そう、さっきの──
ドーナツの。
一気に脱力、理由を悟った。こちらも勘定に入れていた理由を。つまりは従者、
──荷物持ちか。
ほの暗く、人けないホールを、ぶらぶら赤い髪が歩いている。すっかりこちらに背を向けて。
既視感を覚えた。何か不思議な光景だった。今、あの彼と二人でいる。二年前、宿を貸し切ったあの客と──。
これも感傷の類だろうか。何か気分が落ち着かない。足元がふわふわ覚束ない、奇妙な感覚にとらわれる。急に目の前が色あせたような、視界の光景が古びたような、「あの夏」が間断なく、まだ続いているような──。
「……遠ざけないんだな、俺のことは」
ためらいながらも訊いていた。
歩く背中で、レノは応える。「なんで?」
「いや、だって、ユージンの時には──」
あんなにこっぴどく撃退するのに。
さっきもここへ、彼女を一人で運んだが、何も言わずにレノは許した。
「だって味方だろ? あんたは俺の」
面食らって瞬いた。
そんな言葉を、よもや、レノの口から聞くとは。
カツン、カツン──と靴音が響く。
赤い髪の黒い背が、古い階段の木板を軋ませ、気だるげに階段をのぼっていく。一つ段をのぼるにつれ、一階ホールの見晴らしが良くなる。
ほの暗い日陰にひっそり沈む、無人の卓と無数の椅子。
営業を終えた昼さがり。天井の片隅で、光が揺らぐ。気だるく、ほの暗い、たゆたうような静かな時間。
「……どこも、こんなもんだよな」
予てよりよく知る、よく似た風情に、知らぬ間につぶやきが漏れていた。ノースカレリアで営む宿の、階下の店の様子が重なる。昼時をすぎて営業を終えた、がらんとした佇まい──。
不意の感慨が呼び水になったか、まだそれほど古くない、かすれた記憶が呼び覚まされた。
壁の隅の陽射しのゆらぎが、昼さがりの静けさが、あの夏の記憶と重なる。毎日部屋まで食事を運んだ、穏やかで脆いあの日々と。
宿の二階の突き当りの角部屋。
いつも、扉の向こうには、寝台の脇に据えた椅子に、だらしなくもたれたこの客の姿。膝で雑誌を無造作に広げて。連れが寝込んで仕方なく、という顔で。
連れてきた娘が臥せってからは、どこへも遊びに行かなくなった。三度の食事は部屋でとり、どれほどの行楽日和でも、決して部屋から出なかった。引きこもった身を案じ、病人の面倒はみるからと、幾度か気晴らしを勧めたが、応じることはついぞなかった。
『 いい。ダリい。めんどくさい 』
えずく音は聞こえていたのに、部屋は常に片付いていた。
清掃さえも締め出して、部屋には誰も入れなかった。彼がながめる誌面の隅には、いつも同じ絵柄の挿絵──。
はっとして立ち止まった背に、時を超えて、察知が追いつく。
悪びれもせずに他人で遊ぶ、飄然と構えたこの彼が、かけがえのないものを失ったのだと。
あの時それが、永久に損なわれてしまったのだと──。
「何が起きたかと思ったぜ」
階段を上りきって、部屋に向かい、レノは何事もない顔つきだ。
「初めの二発はでっかくて、最近では、あのねじれ」
怪訝にレノの顔を見た。「な、なにが?」
「間隔は不規則で、徐々に規模がでかくなる。初めは北のノースカレリア。次はレーヌ。商都、カノ山」
「だから、一体なんの話を──」
レノは背中で嘆息する。「あんた、鈍すぎ」
取っ手に手を置いた肩越しに、笑いを含んだ目を向けた。
「そろそろ気づいていい頃だぜ?」
ざわり、と心が動いたその時、レノが怪訝そうに取っ手を見た。
扉をひらいて、室内を一瞥、肩を返して走り出す。
「あんた、一体、どこ見てたの!」
元の階段まで駆け戻り、ただちに階下へ下りていく。
突如なじられて置き去りにされ、あぜんとセヴィランは見送った。
怪訝に扉を振りかえり、取っ手を押して、室内を覗く。
ぬるい風が頬をなでた。
換気であけた向かいの窓が、まだ、そのままになっている。
陽の射しこむ明るい室内。隅に置かれた寝台も、先と変わらず静まりかえって──
「……な!?」
絶句で、愕然と目をみはった。
寝乱れた白いシーツが、ひっそり陽射しを浴びていた。壁の、無人の寝台が。
自信に満ちたあの顔がよぎった。様子を見に一旦戻ると、少し前に馬車を離れた──
「──やられた!」
そんな言葉を、なぜ信じてしまったのか。
開けた扉もそのままに、すぐさま廊下へ飛び出した。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》