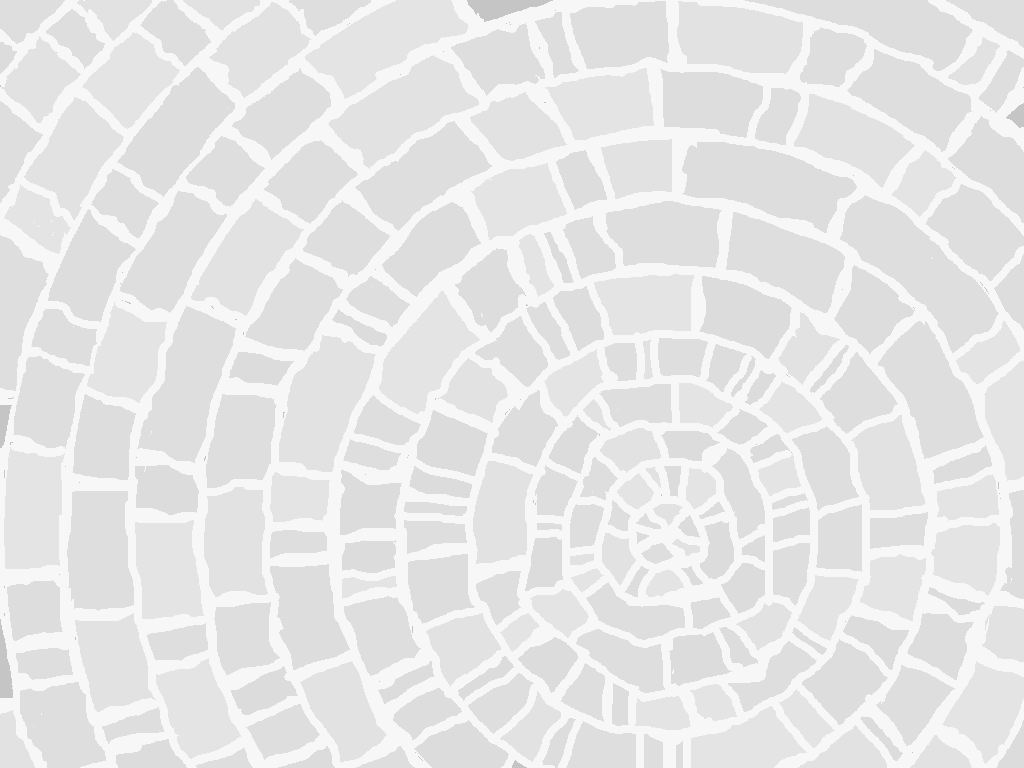
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章55
( 前頁 / TOP / 次頁 )
昼下がりの町は閑散としていた。
とはいえ、通りの人影が皆無というわけでもない。
時おり見かける人目を気にして、速度があがりすぎないよう気をつけながら、セヴィランは小走りに路地を駆けた。その内心で舌打ちする。まさか、目と鼻の先でさらわれようとは!
部屋は、もぬけの殻だった。
張りつめていた気が不意にゆるんだ、間隙をついた出来事だった。終日の警戒をも掻いくぐり、あっさり姿をくらませた。いかなる場所へも抜けられるあの能力を以てすれば、すでに連れ去った可能性が大だ。一縷の望みがあるとすれば──
街道へ続く出口を目指した。
あの疲弊した様子では、異能の酷使で消耗した体力の回復が追いつかず、まだ異能は使えないかもしれない。彼女を自力で移動するなら、必要になるのはありふれた手段、ここまで運んできた
──あの馬車だ。
走り続けた左の視界に、長年風雨にさらされた風情の、赤い屋根が見えてきた。
馬を預かる掘っ立て小屋だ。木柵で囲った脇の敷き地に、荷馬車が列をなしている。町の出入り口に設えられた移動手段の有料預かり所──。じれったい思いで馬小屋を通過し、ようやく街道に走り出る。
「馬車は──!」
振りかぶるようにして振り向いた。
夏雲うかぶ空の下、乾いた白っぽい街道が、なだらかに西へと伸びている。はるか先まで見渡せる、のどかにひらけた田園風景。川のせせらぎが聞こえる左は、夏草生い茂る傾斜の先に、水面きらめく先の川。右手は町の外周を覆う鬱蒼とした雑木林、脇の路肩で荷車が、青い夏草に埋もれている。出入り口から少し離して道端に停めたあの馬車は──
「……やられた!」
苦虫かみつぶして首を振った。
無駄と知りつつ、のろのろそちらへ足を向ける。馬車を駆ってユージンは、道なりに西へ進んだか。それとも追手の裏をかき、逆行したということも──
「──くそっ! これでどうしろってんだ」
影も形も、すでにない。
腹立たしさを持てあまし、短髪の頭を掻きむしる。なぜ、呑気に居眠りなどしていた。彼女が奇跡的に目を覚まし、ようやく危機を脱したというのに。
油断したとしか言いようがなかった。一瞬たりとも警戒を緩めるべきではなかった。相手はあのユージンなのだ。彼女をさらうと公言して憚らなかった──。だが、今となっては、すべてが遅い。
やるせない苛立ちを盛大な溜息で吐き出して、空に響いたその音を仰いだ。
「……三時か」
時鐘だった。目抜き通りの時計塔の。日暮れまで猶予はあるが、昼の街道は閑散として、どちらへ行ったか見当もつかない。目撃者を見つけようにも、この暑い盛りでは、見渡すかぎり人影もない。ただただ夏日が降りそそぐ、のどかに開けた街道に、途方に暮れて立ち尽くす。
「あれ? 馬車は?」
怪訝に、声を聞き咎めた。単なる往来の挨拶にしては──?
振り向きざま、相手の胸倉を引っつかんだ。「──てめえ! どの面さげて戻ってきた!」
「え、なに……」
「とぼけるな! まんまと出し抜かれた間抜けな面を、嘲笑いにきたというわけか!」
「──あんた、一体何を言って」
「なにが"馬車は"だ! 白々しい!」
「落ち着けよ!」
一喝で、ユージンが睨めつけた。
思わぬ剣幕に面食らい、吊るしあげた手がゆるむ。「……お前じゃ、ないのか?」
「だから、なんの話だよ!」
腹立たしげに振り払い、ユージンは乱れた衣服を整える。「相手がレノじゃ難儀だろうから、早目に切りあげてやったのに、いきなり罵倒って、どういう了見?」
口調こそ抑えたものだが、ふつふつ苛立ちが募るのがわかった。当座しのぎの誤魔化しではなく、本気で心底怒っている──?
遅まきながら、セヴィランはあわてた。「──あ、いや、停めた馬車がなくなっていたから、てっきり、お前の仕業かと──」
「だったらなんで、ここにいるのさ。あんたを冷やかしに戻るほど、暇人にでも見えるわけ?」
静かに怒りをたぎらせたまま、ゆらり、とユージンが目をあげた。
「説明、してくれるんだろうね」
有無を言わさぬ半眼に気押され、経緯をかいつまんで話して聞かせた。ユージンが町へと去ったあの後、レノと話していたことを。そして、
「彼女が倒れた?」
ユージンが面食らったように絶句した。
すぐには反応できない様子で、戸惑いがちに目をそらす。「……なんで、今ごろ」
「今ごろ?」
すかさず、セヴィランは詰め寄った。
「やっぱり何かしてやがったな! おい! 今の"今ごろ"ってのはなんだっ!」
ふと、ユージンが目をあげた。
ぱっと、そっけなく横を向く。「別に」
「今のは明らかに怪しいだろうがっ!? てめえ、ユージン! 俺のこの目が節穴だとでも──!」
「なんでもないよ、うるさいな。ちょっと口をついただけだろ」
煙たそうに顔をしかめて、腕を組んで目を戻す。「そんなことより問題は、消えた馬車の行方だろ。あんた、倒れた彼女を置いて、どこで油を売っていたのさ」
「──だから」
顔をしかめて頭を掻き、馬車の消えた道端を見やる。「たく。人の話は最後まで聞けよ。お前がいなくなったあの後に、ちょっと不思議なことがあったんだよ」
「不思議なこと?」
「ああ」
舌打ちまじりに説明する。
何かを叩きつけでもしたような激しい物音に驚いて、馬車の背後に駆け寄ると、彼女が荷台に倒れていたこと。《 あわい 》の揺らぎは消滅し、彼女の呼吸が止まっていたこと。
ところが、奇妙なことが起きた。
ぴくりとも動かなくなっていた彼女が、何事もなく目を覚ましたのだ。無遠慮に荷台に乗りこんだレノに、容赦なく揺すられている内に。
「つまり、蘇生したっていうの?」
呆れた顔つきで要点を指摘し、ユージンがげんなり嘆息した。「ちょっと体を揺すったくらいで?」
「──あ、いや、それがその、」
そそくさセヴィランは目をそらした。いささかきまり悪く頭を掻く。「どうも、俺、らしいんだよな、原因は……」
ユージンは胡散臭げに目をすがめ、図りかねるといった顔。
仕方がないので、経緯を詳しく説明した。実は自分が、何らかの力を放ったらしいと。
話を咀嚼するように瞬いて、ユージンは疑わしげな目を向けた。「それ、本当にあんたがやったの?」
「俺でなけりゃ誰だっていうんだ。そりゃ、自分でも驚いているが。だが、現に」
「そんな真似、俺にだって無理だと思うけど?」
「──だからだな。たぶん俺には潜在的に、そういう力が具わっていてだな。それがあの状況に驚いて──」
「開花したってわけ? 才能が?」
揶揄するように強調し、ユージンは白けたように目を背けた。「いくらなんでも無理があるだろ。そもそも蘇生なんて不可能だ。限られた生命の理に反する。大体あんたも、覚醒したばかりで、そんな大技──俺に勝てもしないのに」
「──おい。あんまり見くびるなよ?」
カチンときて見返した。
「これでも昔は天下無双だったんだからな。どんな荒くれ野郎でも一睨みで倒したもんだぜ。傭兵で一稼ぎしに行った時にも、そりゃ、もっぱらの評判で。技量の幅を広げようとか、力の限界に挑もうだとか、当時は思いつきもしなかったが、途轍もない才能が眠っていたって不思議じゃない。それが今回ふとした拍子に、開花したからって別段ありえない話ってわけでも──」
はた、と気づいて、いささか気まずく目を戻した。
「……なんだよ、どうかしたのか」
ユージンが口をつぐんだまま、いつの間にか眉をひそめている。
「──ちょっとね。気になることを思い出して」
ほんのつかのま、記憶を追うように視線を外し、改めて怜悧な目を向ける。
「あんたには言ってなかったけど、妙な気配を感じたんだ 《 あわい 》 に入る直前に」
「──他にも誰か、いたってことか? だが、誰にでも入れる場所でもないだろ」
「ああ、もちろん。だが、するり、とあの時、続いて何かが入りこんだ気がして。あっという間に消えたから、人かどうかまではわからないが──。あんたに自覚はないようだし、万一彼女が仮死状態なら、あるいはそいつが、と思ってね」
薄気味悪さに眉をひそめ、だが、なんと返していいやらわからず、落ち着かない気分で頬を掻いた。「いや、──そんな気配はなかったと思うが。あの子が荷台で蘇生した時には」
こちらの反応に注意を凝らし、じっと聞いていたユージンは、釈然としない顔でつぶやいた。「……そう」
それ以上の追及を取りやめるように、一つゆるく首を振る。「なら、たぶん気のせいだろう。それで彼女は?」
元の話題に引き戻され、ああ、と鼻白んで、軽く身じろぐ。
腕を組み、道の先の町をながめた。「まさか、あんな女の子を床に転がしておくわけにもいかないし、ひとまず宿に運んだんだが。馬車の番はあの人に任せて」
……なんだ、と言わんばかりの顔つきで、ユージンが拍子抜けしたように見返した。「だったらレノだろ、犯人は。どうせ、いつもの気まぐれで、勝手に馬車を動かしたんだ。連れの俺たちに断りもなく」
「いや、そうじゃないんだ。あの人じゃない」
「なにかばってんだよ」
「──俺は、別に、かばってなんか」
顔をしかめて嘆息し、ユージンがやれやれと腕を組んだ。
「誑しなんだよ、あのレノは。誰もが、あいつに好意を抱く。だが、ひどいやり方で、必ず裏切る。もしやと思ったが案の定だ。あんたまで取り込まれるとはな」
「──おい!? そんなんじゃないからな!?」
「まんまと手懐けられちゃって」
「だから、あの人のはずがないんだ! 今しがたまで、俺と宿にいたんだからな、あの子が部屋から消えたと知るまで──」
「消えた? 彼女が?」
ユージンが目をみはって振り向いた。
「──なぜ、それを早く言わない!」
もどかしげに舌打ちし、即座に身をひるがえす。
駆け出した背に、あわてて続いた。「だって、お前の仕業じゃないんだろ? だったら、そんなに気を揉む必要は──」
「大ありだよ! 彼女を狙っているのはジャイルズだ!」
「……え、誰だって?」
「だから! レーヌの海賊だよっ! まったくこれだから呑気な親父はっ!」
「悪かったなー。おっさんでぇ」
「とにかく急ごう! うろついていたのは奴の手下だ。拉致した報告が入るまで、ノアニールのアジトにいるはずだ」
「なら、こっちにいるのは下っ端ってことか。だったら話は簡単だ。雑魚をつぶして、あの子を分捕ってくればいい。ノアニールがアジトなら、こっちに出向くまで大分間がある」
町へと駆けつつ、ユージンが顔を曇らせた。「……そう上手くいけばいいが」
「なんだよ、めずらしく弱気だな」
賢そうな横顔が、苦々しく眉をひそめた。
「──あんたはジャイルズを知らないからだ」
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》