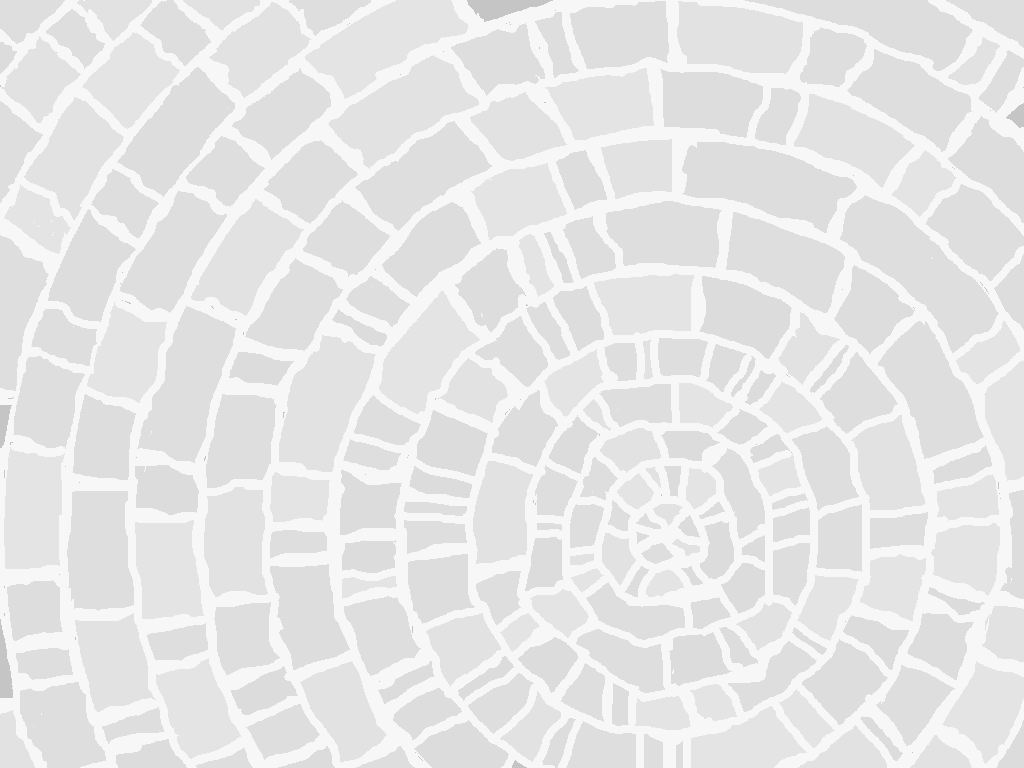
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部2章56
( 前頁 / TOP / 次頁 )
町の入り口を駆け抜けて、目抜き通りを左に折れた。
古びた簡素な店が居ならぶ申しわけ程度の繁華街に入り、手近な飯屋の扉を開く。
午後の陽射しに白んだ店内、がらんとほの暗いホールには、だが、客の姿は見当たらない。
帳場にいた店主を呼んで、部屋をとった客の中に女連れがいないか尋ねるも、捗々しい成果は得られない。目をしばたいて聞いていた眼鏡の奥のつぶらな瞳は、何かの嘘をついてるようでも、誰かに脅されたようでもない。
礼を言って通りに出、今度は手分けして店を当たった。
古びて鄙びたどの店も、店内は似たり寄ったりだ。書き入れ時の飯時を大分まわった今時分、昼の営業は終了している。
一足先に通りに出、連れの報告を待っていると、最後の店の扉を押しあけ、ユージンがゆっくり外に出てきた。
「どうだった」
首を振ってそれに応え、ユージンは肩越しに店を見る。「……どうなってるんだ。これまではあんなに、鬱陶しいほどうろついていたのに」
与太者がたむろす店はなかった。引っ張りこまれた女の姿を目撃した者もない。どの店も閑散と鄙びて、怪しい気配のかけらもない。
「──連中の仕業じゃないってことか」
ふっと肩の力を抜き、ユージンは途方に暮れたように首を振る。「それならそれで一安心だが、だったら彼女は、一体どこへ──」
ふと、目を見開いて、あぜんと通りを見まわした。今気がついた、というに。
よろり、と膝に手を置いて、へたり込みそうに脱力した。「なんだよ。こんなに近くにあったんじゃないか……」
「何が」
「……。目抜き通りの突き当りの……役場を東に入った場所まで、体を休めに行ったんだ……」
「なんで、そんな遠くの宿まで?」
疲れていたんじゃなかったのか?
役場までは、かなりある。目抜き通りを道なりに進み、中央の時計塔を通り過ぎ──要は一番奥まった場所だ。
「だが、役場の東に店なんかあったか?」
町の全景を思い浮かべて、セヴィランは首をかしげる。目抜き通りの両側と、一部の小さな商店を除けば、東は民家が大半だが。
「……ああ、すっかり騙された」
疲れに拍車がかかったか、ユージンはうなだれ、首を振る。「やっぱり、あれは甥っ子の家か」
「甥っ子って誰の」
「町を入ってすぐの所の、馬小屋でたむろしていた老人に、近い宿を尋ねたんだ。疲れていたから手っ取り早く。そうしたら、その内の一人が、そこまで案内してやると」
そして、はるばる役場まで歩き、民家の一室に連れこまれた。そして、料金をふんだくられた──。
「よく引っかかるな、そんな手に」
セヴィランは呆れて肩をすくめた。「途中で気づかなかったのかよ。お前にしては間が抜けてるな」
「──疲れていれば、こんな事だってあるよ」
恨みがましくユージンは見、やつれた渋面で歩き出す。「そういや、レノは?」
「ああ、あの子が部屋から消えたと知るや、あわてて飛び出して、それっきり。ああいう人でも、あわてることがあるんだな」
ふっと会話が、そこで途切れた。
沈黙に耐えかね、セヴィランは気まずく頭を掻く。「あ、いや……なんか、あの人、何をするんでも迷いってもんがないからさ……」
言わずもがなの言い訳をし、昼の通りをぶらぶら歩く。
足を止め、ふと、肩越しに振り向いた。
「なんだ。どうした」
夏日に乾いた土道に、ユージンが立ち止まっている。
「──そうだよ。やっぱり何かがおかしい」
思案するように眉をひそめ、拳を唇に押し当てた。
「彼女の姿が消えたからって、レノがそんなことを気にするか? 誰も彼女に近づけないよう事あるごとに邪魔したり、彼女が荷台にこもったら、自分も荷台で寝泊まりまでして」
「──そいつは確かに、不都合な事この上ないよな、お前には」
「変なのは、それだけじゃない」
チクリと刺すも無視して斥け、ユージンは記憶の糸をたぐっている。
「会議の招集を後回しにしてまで、なぜ、彼女に会いにきた? わざわざ幾つも別の町を覗いて、居場所を捜し出してまで。事もあろうにその理由が "彼女が自分を呼んでいたから"?──は! まるで理由になってない。他人がどこで何をしようが、気にするような奴じゃないだろ」
「だから、友達なんだよ、あの二人は」
「そんな可愛らしいごっこ遊びを、真に受けるような奴だとでも? むしろ、彼女が消えたと知って、そんなにあわてる理由は何」
射貫くように見据えられ、頭を掻いて口ごもった。「それは、あれだ……だから、心配だったんだろ、あの子のことが……」
拳の指で唇を叩き、ユージンは思考を追い求める。「……どうも一々引っかかる。あいつの言動、なにかが妙だ」
「まあ、確かに、ちょっと変わった人だけどよ」
連れの真剣な面持ちにつられ、つらつら思考をめぐらせる。
ふと、思い当たって目をあげた。「──そういや、あの人、妙なことを言ってたな」
目で促したユージンに、足を踏みかえ、向き直る。
「あの子がいなくなったゴタゴタで、すっかり忘れていたんだが──」
居眠りから覚めた後の、レノとのやりとりをそのまま伝えた。いや、要約などできるはずもない。心の奥底でくすぶっていた、なんとも不可思議なあの言葉を。
『 何が起きたかと思ったぜ、
初めの二発はでっかくて、最近では、あのねじれ 』
『 間隔は不規則で、徐々に規模がでかくなる。初めは北のノースカレリア。次はレーヌ。商都、カノ山 ──』
はっとユージンが目をみはった。
「──やられた!」
面食らって、セヴィランはまたたく。「……なんだよ、急に」
「気がつかないのか!」
苛立たしげに舌打ちし、憤懣やるかたない息を吐く。
「一番初めがノースカレリアだ。そしてレーヌ。商都、カノ山──わからないか。どれも異変の発現場所だ。レノがそれを知っていたなら、つまりは、あいつも、」
冷ややかに鋭い一瞥をくれた。
「同類だ」
怜悧な瞳が、射るように見つめる。
呆気にとられ、戸惑いつつも、ようやく返した。
「……は、なに言ってんだ、お前」
「レノは初めから知っていたんだ。各地で起きた異変のことも。この俺たちの正体も。その上でおちょくっていた。なるほど、それなら説明がつく。ああ、そうだよ! そういうことか!」
「お、おい、ちょっと待て。ちょっとお前、落ち着けって」
続く言葉をつかのま失い、困り果てて頬を掻いた。
「そんなことが、あるわけないだろ。──あのなあ、ユージン。言いたかないが、特殊なんだぞ、俺たちは。俺たちみたいな異分子が、そこらにいてたまるかよ」
出生自体が禁忌の事柄。いわば、この身は、相容れない二つの世界の軋轢そのものと言っていい。
「そもそも、あの人は荷台にいたぜ。火事場みたいな焔を浴びても、何食わぬ平気な顔で。あんな真似が俺たちにできるか?」
「焔の方が避けていたとしたら?」
「──は。──たく、何を言って」
「思い出せ、セヴィ。あの時、焔は、確かにレノを避けていただろ。つまり、あいつには手出しができない。だとすれば、レノの方がより上位、俺たちにすれば」
真顔で、真っ向から目を据えた。
「とてつもなく格上だということだ」
凪いだ町の土道に、午後の夏日が照りつけた。
路地に落ちた、影が濃い。こめかみを伝い、汗がしたたる。
息をつめ、絶句していた。レノが騙し、翻弄していた──?
にわかには信じがたいことだった。確かに案じていたではないか、荷台で倒れた彼女の身を。膝の上に抱えあげ、無心に呼びかけるあの様は、芝居などでは決してなかった。
上辺の付き合いのユージンよりも、彼を知っている自負がある。
毎日のように顔を合わせ、家族のように暮らしたのだ。彼の素顔を知っている。あの二年前の繊細な──素知らぬ振りをしながらも祈るような横顔を思えば、そんなことは信じられない。現に、つい今しがたまで、その当人と会っていた──。
昼時をすぎて営業を終えた、昼さがりの人けない飯屋。
古い階段の木板を軋ませ、あの客の黒い背が、気だるげに階段をのぼっていく。階下のホールは、ほの暗く陰に沈んでいる。
たゆたうような静かな午後。無人の卓と無数の椅子。天井の片隅で、光が揺らぐ。色あせた情景が重なって、その境があいまいになる。「あの夏」が間断なく、まだ続いているような──
はっ、と息を飲んで目をあげた。
今になって思い当たった。あの時、違和感を覚えた理由に。距離感が元に戻ったからだ。彼が客として宿泊していた、二年前のあの当時に。
原因は、彼の立ち位置の変化、つまり、レノは見抜いたのだ。「あの宿にいた親父」だと。毎日のように顔を合わせ、言葉を交わした当人だと。
当時とはまるで異なる若返った容姿というのに、それでも難なく看破した。それを確信した上で、反応を見るように仄めかし──
くすり、と笑った一瞥が、愉しげな瞳が脳裏をよぎる。
『 そろそろ気づいていい頃だぜ? 』
信じられない心持ちで、しばし、呆然と立ち尽くす。
「……いや、まて」
ぎくり、とセヴィランは息をつめた。
うなだれ、平手で顔をつかむ。
「……やべえ。まじかよ……ファレスがまずい……」
ふと目をあげたその先で、ユージンが怪訝そうにながめている。
「あの人が俺に言ったんだよ。怪物になる前に始末する、とかなんとか──あ、いや、その時は、てっきり冗談だとばかり。だって、まさか思わないだろ、高々麻薬くらいのことで」
拳を唇に押し当てて、ユージンは眉をひそめている。
「──それさ」
慎重に言い置いて、探るように目を向けた。「それ、本当にファレスのこと?」
「どういう意味だ」
「あんたが言った通りだよ。高々麻薬くらいのことで、あいつはわざわざ動かない。もっと重大な、早急に対処すべき事でもなければ──」
怜悧な顔を間近で見据え、ごくり、とセヴィランは唾をのむ。「──つまり?」
「もう、あんたにも分かっているんじゃないの? 彼女の力と西の竜。あの焔が見えていたなら、レノも見ていたはずなんだ。竜が彼女に呼応するのを。彼女の力が爆発的に、刻々と増大するさまを」
不意の暴走を危ぶむほどに。彼女の行く末を危惧するほどに。
誰よりも近くで。誰よりもつぶさに。
昼の町壁に視線を投げて、思考の先に目をすがめる。
「ラトキエは今、ディールを潰しにかかっている。国土の三分割を覆し、勢力図を塗り替えるなら、今をおいて他にない。ここが命運を賭けた分岐点、千載一遇の局面だ。だが、尋常でない未曽有の脅威が、その前途を塞いでいたら──」
ちら、と冷ややかに一瞥をくれた。
「行く手を阻む邪魔者を、あのラトキエが許すと思う?」
息を飲み、セヴィランは愕然と目をみはる。「……なら、始末する相手ってのは」
「もう、行くよ」
焦れて地を蹴ったその背を見送り、言葉を失い、立ち尽くした。そう、確かにこのままでは、彼女は呑まれ、喰いつくされる。あの焔に取り込まれたら……
ぞくり、と背筋が凍りつく。
ぴたり──と"黒"が、輪郭に馴染んだ。あたかも彼の一部のように。あの背にまとった黒の上下が。
そう、あれが元の姿だ。
そっけないほどに無造作な衣服。金糸も肩章も必要ない。己を誇示する装飾など、彼には一切必要ない。その視線が捉えたその先、言葉を浴びせたその先に、佇んでいるのが彼女だったとしたら──
そうだ。レノはなんと言った。
" 怪物になる前に 始末しねーと "
彼を中央に据えた途端、据わりの悪いくすぶりが、あっさり一点に収束し、淀みが一気に氷解する。
「──と、止めないと!」
転げるようにして地を蹴った。
全力で街路を走り出す。なんとしてでも止めないと! いや、実力の知れない格上と、やり合うなど自殺行為だ。彼女を見つける方がはるかに容易い。必ず先に見つけ出すのだ。ただならぬ力が膨れあがり、制御不能に陥る前に。
あわただしく出て行った忌々しげな横顔が、町壁を舐める視界をかすめる。すでに狙いを定めたからには、もう、どれほども猶予はない。早くしないと、彼女が
危ない!
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》