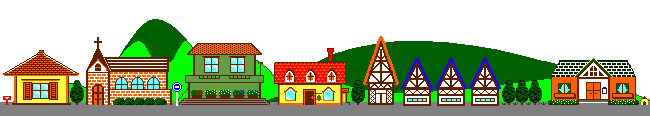
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部3章20
( 前頁 / TOP / 次頁 )
適当に戸枠をノックして、オットーは片手で覆布をどける。
もう片方の左手は、あいにく盆でふさがっているから。
つややかな黒塗りの盆の上には、達筆な表書きの封書が一通。
バスラ近郊の天幕の中、書類を積んだ机の向こうで、上司は今日も書き物をしている。
「失礼しまーす」
オットーは机に歩み寄り、盆ごと封書を上司に差し出す。
「上席徴税官殿、お手紙ですよ」
はっと上司が顔をあげ、引っつかむようにして封書をとった。「──来たか」
ただちに開封、便箋を取り出す。
食い入るように手紙を見ているラルッカ=ロワイエその人の家は、国の中枢"商都"を治めるラトキエ門閥、高位の家柄。そして、ラルッカ当人も、その身は次子でありながら一族の出世頭に躍り出た、押しも押されもせぬ切れ者だ。
両手でつかんだ文面を、やきもき目で追う白皙の顔を、ちらとオットーはうかがった。
「どこのご令嬢なんですかー?」
すごい食いつきっぷりっすね、と言外ににじませ尋ねると、ふと、ラルッカが目をあげた。
あからさまに眉根を寄せた「お前まだいたのか」という顔で。
「ご苦労、オットー。下がっていい」
「……はーい」
シッシ、とぞんざいに手を振られ、オットーは口を尖らせて出口に戻った。
近頃、上司の行動が怪しい。
妙にピリピリ気を張って、軽口・雑言・小突き合いはおろか、すぐにどっかへ追っ払おうとする。手紙を取り次いだその後は特に。
「ちぇっ、つまんねーの」と肩越しに舌打ち、和やかな雑談は職場の雰囲気を円満にするのに、と天幕を払って敷居をまたぐ。
くい、と襟首を引っ張っられた。
「なんだって?」
ずい、と顔を寄せてきたのは、戸脇で退室を待ち構えていたロルフ。
個人を見分ける目印にしている緑の服の向こうには、赤服カルルの顔もある。
割り当て「青」のオットーは、自分と同じ背格好、そっくりな顔の三つ子の同僚に、肩をすくめて首を振る。
「だめ。全然。けんもほろろ。内緒で何やってんだか」
くりんと大きな瞳を曇らせ、赤服カルルがすねたように顔をしかめた。「もう、司令官殿ったら。僕たちには教えてくれてもいいのにー」
「"上席徴税官"だよ、カルル。"司令官"はもう終わりだ」
緑のロルフがそつなくたしなめ、上司の肩書を訂正する。今でもカルルは上司のことを、一切の悪気なく「司令官」と呼ぶし、にこにこ呼ばわれた本人も実は満更でもなさそうなのだが、さすがに職場で「司令官」はまずい。本物もいるし組織のどっかに。
戸口におりた白い覆布が、うららかな夏陽を浴びていた。
純白の天幕が立ち並ぶ、昼さがりの駐留地。そこかしこで掲げられた、黄金旗がひるがえる。その旗章は《 天駆ける馬 》──首都カレリアを統括する、ここラトキエ領家の家紋だ。
「……なんだよ、目の色変えちゃって」
あっさり締め出されたオットーは、地面の石ころを軽く蹴る。「そんなことしてる場合じゃないだろ」
このところ上司ラルッカは、いたく文通にご執心。こうして遠征先にまで、日に一度は文が届く。だが、相手が誰なのか、絶対教えてくれないのだ。
「ディールとの戦も大詰めだってのに」
天幕に向かって悪態をつくと、ロルフが緑服の肩をすくめた。「今度はラルッカ様も本気だってことさ」
「エルノアさんの時だって本気だったよっ」
すかさずカルルが、むきになって口を尖らす。
「──まったく、なんで破談になんか」
はあ、とオットーは嘆息し、ガリガリ頭を掻きやった。「ドゴール財閥の令嬢なら、下手な貴族より金持ちなのにな」
カルルも残念そうに唇を掻く。「ぼく、あの人好きだったのになあ〜」
「お前しょっちゅう、菓子やら何やらもらってたもんな」
「ね、どこの使いか訊いてみようよ、あの人に」
茶々を入れるもあっさり無視して、カルルは横に指をさす。
三人並んだその向こうで、平服姿の男が一人、天幕にもたれて喫煙していた。
件の文を届けるために、いつもああして控えているのだ。ドゴール家の令嬢と破談になる少し前から。
「無駄だよ、カルル」
無礼な人差し指を片手で下げさせ、ロルフが男をすがめ見た。
「ラルッカ様が口を割らなきゃ、あいつだって言いやしないさ」
ファレスは親父に代金を払い、一抱えもある茶色の紙袋を受けとった。
「おう。ありがとよ」
縁まで菓子を満載した紙袋を両手でかかえて、ホクホクしながら街路を歩く。これで当面、戯具の類いには困らない。道中ピーピーわめいたら、女子供のあの口に突っ込んでやろうと決めている。この先トラムに着くまでは、店はおろか町もない。
大きな袋で圧迫された脇腹の傷に意識が向き、ふと、ファレスは首をかしげる。
「そういや、治りが妙に速えな」
あれ以来だ。いつぞやの晩に路地で倒れ、馬車で目覚めたあの時以来。
脇腹はすっかり回復していた。
あんなに長引いたのが嘘のように。いや、むしろこの頃は、前にも増して治りが速い。こんな快調はかつてない。だが、急変した原因が、まるで一向に見当たらない。切っても、すぐにふさがる感じが、なぜか日に日に強くなる。
ふと、気づいて、足を止めた。
何かの気配。生き物だ。すぐ目の前に何かいる。
視界を遮る袋をどけて、怪訝に向かいを見おろせば、腹の高さに子供のつむじ。
凛とした瞳で見あげている。
肩で切りそろえた頭髪の、七歳に満たない男の子供。町の子供とは言い難い、奇妙な身形にきれいな面ざし。いや、芝居小屋で見るような、ふわりと白い装束は──。
見た顔だと首をひねる。だが、どこで見たのか思い出せない。
歯がゆい思いで記憶を辿ると、冷ややかな声音が脳裏をよぎった。
『 愚かな 』
はっと弾かれ、男児を見た。
「お前、確かあの晩の。ザルトの門前市にいた──」
いや、とファレスは口をつぐむ。この子供と会ったのは、夜市の雑踏が初めてなどではない。
北から馬群で南下中、キャンプ付近の草原でも、蓬髪の首長アドルファスと何事もなく歩いていた。
降雨の名残りのぬかるんだ草原、その只中の高枝に、だしぬけに姿を現した。土塊一つない真っ新な草履で。
ありふれた日常の景色の端に、さりげなく写り込むその姿。
染みも皺もない白装束。肩で切りそろえた真っ黒な頭髪。芝居小屋の役者のごとき、古風で奇妙な言い回し──あれらは、すべてこの子供だ。なぜ、今まで結びつかなかった。なぜ、すっかり忘れていた。こうも際立った存在を。
「すでに集り始めておるわ」
「──あ?」
凛と澄んだ男児の瞳が、晴れた西の尾根を見る。
「"爪"の始動を感知して、あの禁忌の者たちが」
──禁忌?
聞き咎め、ファレスは眉をひそめる。前にも聞いた言葉だが。
そのくすぶりを読んだ風情で、子供が大儀そうに口を開いた。
「人であって人でない、法外な力を持つヒトの類いよ。本来不可侵であるべき二界の、狭間に芽生えし慮外の命。その軋轢に在って尚、すり潰されずに勝ち残った魂。あれらは埒外。界主でさえも干渉できぬ。なにせ、あれらは、世の理の外にある」
次々常識が覆され、自分の足場が崩れ去るような不安──背筋を這った怖気をはねのけ、ファレスは胡乱にねめつける。
「──なんだって、俺の前に現れやがる」
「"爪"が"石"を呼んでおる」
いささか筋違いと思える方向から、白装束は素っ気なく応えた。
面食らった相手に構うことなく、話の先を滔々と続ける。
先刻の北方での発動で覚醒した竜爪が、かの"石"を呼んでいる。己が身に取り込まんがために。かつて、荒国にしたように。
だが、"石"が岩塊に行き着いて、かの荒竜に取り込まれたが最期、時はたちどころに巻き戻り、地平は砕け、ことごとく無に帰す。
この事象は破綻して、慶寿の世は終焉を迎える。
「未来は所持者の判断如何。つまりはそちの、働き如何ということじゃ」
二の句も告げずに見やった脳裏で、肩までの髪をひるがえし、あの彼女が振りかえる。
はっとファレスは目をあげた。
「つまり、俺に、阿呆を止めろ、ということか?」
はた、とまたたき、見回した。
きょろきょろ視線をめぐらせて、町角を見、路地を見て、そのまた隣の町角を見る。
「……いねえ?」
凪いだ昼の夏日の中、無人の街路が広がっていた。
姿かたちが掻き消えている。人など初めからいなかったように。
ぎこちなく首をかしげて、眉をひそめて路面を見る。
そこはかとない覚束なさを、ファレスは舌打ちで振り払い、気を取り直して歩き出す。「──台詞の稽古かってんだ」
だが、いくらも行かない内に「──いや」とつぶやき、首をかしげた。
「そういやアレも、似たようなことを」
ゆうべの出来事を思い出す。連れが寝静まったあの深夜の。
窓から射しこむ月あかりに、ほのかに輝くその姿。
《 我と組まぬか 》 と月読が言った。
片膝立てたあぐらで座り、緋色にきらめく目をすがめて。
《 ひとつ取引をしようではないか。用さえ済めば、そやつはお前にくれてやる 》
知らぬ間に足を止め、ファレスは眉をひそめていた。
規制線に至った途端、妙な輩が立て続く。持ちかけてくる要求は、つまるところ、いずこも同じ。
──客の西への接近を、なんとしてでも食い止めよ。
紙袋を背負い上げて、両手でかかえて歩き出す。
「どいつもこいつも、ピーチクパーチク」
各人各様、西に不都合があるようだが、むしろ客当人でさえ、無縁の他国へ渡るなど不本意極まりないだろうが、商都方面へ逃亡すれば、早晩必ず手詰まりになる。そもそも、
「アレは俺のだ。指図は受けねえ」
能天気なあの阿呆は、微塵もわかっちゃいないだろう。命綱の部隊を去れば、こっちの損害は甚大だと。
だが、わかってほしいとは思わない。俺は客をよく知っている──。
ふと、ファレスは眉根を寄せた。 あれは、どういう意味だったのか。
《 まったく。お前が不甲斐ないばかりに、要らぬ約束をさせられたわ 》
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》