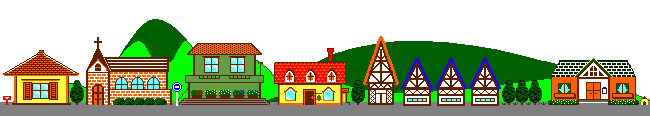
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部3章21
( 前頁 / TOP / 次頁 )
まったくもって釈然としない。
なぜ、突然、地図屋が客に 「規制線を越えろ」 などと言い出したのか。
的確すぎるそんな助言を。
規制線の向こうなら、確かに易々とは手が出せない。たとえ潜入に慣れている、あの特務であろうとも──
ぶらぶら歩く足を止め、ギイはくわえ煙草で額をつかむ。
「──俺か」
知恵をつけたのは。
そう、おそらく、あの時だ。副長の出奔先を言い当てた、理由を訊かれたあの時の──
『 このカレリアの国土の中で、トラムにある武装部隊が、唯一進めねえ場所がある 』
答えは"トラビア"
"規制線"は、その応用。
踏み板をきしませて階段をあがり、登り切った床を、廊下へ曲がる。
静まり返った宿舎の二階、夕方の気配がかすかに漂う、ほの暗い壁の廊下を進む。
大部屋の前で足を止め、煙草を靴裏で踏みつけた。
「よ。起きたかい」
念のため、室内に一声かけてから、からり、と戸を引き開ける。
藺草の敷物が敷かれた室内、がらんと物のない向かいの左に、窓辺に腰かけ、喫煙している、丸首シャツの禿頭の背。
手前の部屋中央には、気だるそうにあぐらをかいた、薄茶の頭髪のうつむいた肩。
「どうだい。少しは休めたか」
「──お蔭さまで」
寝起きらしいかすれた声で、ザイが煙草に手を伸ばす。「戻りましたか、あの客は」
「そろそろじゃねえかな。馬の足なら」
頬が少しこけただろうか。窓辺にいるセレスタンと同じく、シャツ一枚の無防備な姿。顔に振りかかる前髪の下、一本抜いた煙草をくわえる。「戦況は?」
「把握してるさ」
「──そいつは抜かりのねえことで。政府の高官でも抱き込みましたか」
火を点け、気だるそうに一服する。
「ここはヤサだぜ。交代で仮眠しなくてもよ」
窓辺で紫煙をくゆらせる、セレスタンの手の煙草は短い。
「悪気はねえんで、ご容赦を。なにもそっちを信用しねえ訳じゃない」
「なに。用心深いのはいいことさ」
ギイは苦笑いで靴を脱ぐ。珍しいこともあるものだ。特務の寝起きなど初めて見た。道なき道を不休で急行したとはいえ、タフで知られるこの二人が。
式台を踏んで部屋にあがり、ギイは脇の壁にもたれる。
「しかし、客には恐れ入る。自ら死地へ赴こうってんだからよ」
顔にふりかかる髪の向こうで、ザイが苦笑いするように口角をあげた。「──そいつはちょっと、大袈裟すぎやしませんか」
「そうでもねえさ。言葉の通りだ。あの客の目的は、ラトキエ総領アルベールとの面会、トラビアで捕虜になっている領主の助命嘆願だ。だが、当の総領の方は、クレスト領主にただならぬ恨みがある」
「──恨み?」
二人が怪訝そうに見交わした。ギイはおもむろに腕を組む。
「話は二年前にさかのぼる。ラトキエ総領アルベールは、大病を患う娼婦を請け出し、屋敷の別棟に住まわせていた。客が"アディー"と呼んでいる、二十歳そこそこの若い娘だ」
当時、アディーは黒障病の末期、医師からの余命宣告は一年余りという重篤さだ。
当然ながらアルベールは、何かと彼女に目をかけた。いや"夢中になった"が正確か。なにせ絶世の美女って話だからな。それに、悪ガキどもが手を出した。
ラトキエの縁戚とつるんでいた、冷や飯食いの貴族の子弟だ。元は娼婦だってんで、手軽に遊ぼうとしたんだろう。
ま、質の悪いお遊び自体は、アディーが骨折したのに驚いて、お開きになったらしいんだが、火の粉が降りかかったアディーの方は、骨折だけでは済まなかった。
その晩、危篤に陥って、慎重の上にも慎重を重ねてなだめすかしていた病状が、それで一気に悪化した。そして、その翌春には、あっさりこの世を去っちまった。宣告された余命より、半年も早い春先に。
「──そいつは大した悲劇スね」
その言葉とは裏腹な、付き合い程度のザイの返答。まあ、保護した客の周辺事情だ。調べはついているのだろう。
「そう言わずに、まあ聞けよ。話の肝はここからだ。葬儀に列席した一人の女医が、総領息子にこう告げたらしい」
「間に合わなくて残念だった」と。治療薬の完成まで、
あと一歩だったのに。
皮肉な苦笑を一服に紛らせ、ザイがゆるりと首を振った。「患者も滅多にいねえのに?」
「この名前に聞き覚えはねえか、オーレリー=クレマン」
「クレマン?」
ザイは思案を巡らすように、前髪の下の目を細める。「まさか、例の──」
同じく眉をひそめていた、窓辺のセレスタンと素早く見交わす。
そう、聞き覚えがあるはずだ。"商都の医者"で "女"で "クレマン"──黒障病に罹患した、首長アドルファスの娘を使って生体実験を行なった、無慈悲で悪辣な仇敵の名に。
「なら、あの女医が媚びていたのは──」
「ラトキエ総領アルベール。ま、新薬開発云々ってのは、援助を引き出すための方便だろうぜ。そんな話は聞かねえし、女史にとってラトキエは、手放すには惜しい金蔓だ」
しがない駆け出しの町医者から上流階級御用達にまで功成り名遂げたきっかけは、ラトキエ総領の援助と口添え。この誼を失えば、たちまち仕事を干されかねない。
「──さぞや悔やんだでしょうねえ、総領息子は」
畳面に目を投げて、ザイは気だるげに紫煙を吐く。
「もし、薬が間に合っていれば。もし、そいつを与えていれば。あと少しでも猶予があれば」
そうしたら、アディーは間に合ったかもしれない。
その後の開発が順調ならば、完治も夢ではなかったかもしれない。
なんとか細々と生き長らえて、その先には薔薇色の、二人の未来が広がっていたかもしれない。失われた猶予がありさえすれば──
あの時、悪化しなければ。宣告通りの余命であれば。あの貴族のごく潰しどもが、くだらない遊びを始めなければ。
──あんな事さえ、なかったら。
「事件を起こした悪ガキこそが、当時、領家の冷や飯食い、クレスト領家の三男坊だ。つまりは現クレスト当主、ディールの拠点トラビアにいる、ダドリー=クレストその人さ」
窓辺の手すりで、紫煙がくゆる。
セレスタンが目を向けている。一切口を挟むことなく。
ふと、ギイは首をかしげた。あんなに無口だったろうか。べらべら喋る方でもないが、それにしてももう少し、愛想があった気がするが。
かすかに伝わるザラついた気配。
気が立っている。二人とも。何をそんなに苛ついている? さすがにザイはおくびにも出さずに、そつなく話を合わせているが──
「たく」
そのザイがやれやれと、呆れたように舌打ちした。「骨のある奴かと思いきや、なんのこたねえ、甘ちゃんじゃねえかよ」
「──ところが、そうでもねえんだよな」
ギイは制して、肩をすくめる。
「ディールの砦に立てこもっているのは、他ならぬダドリー=クレストだからな」
二人が面食らったように振り向いた。
うかがうように唇を舐め、眉をひそめてザイが見る。「領主は捕虜にとられたはずじゃ? そもそも、あのトラビアには、ディールの当主がいるでしょうに」
「病没したらしいぜ、春先に」
二人が虚をつかれたように眉をひそめた。諜報に長けた特務でも、さすがにこれは想定外らしい。
「それ以降の政務は万事、秘書官が取り仕切っていたらしい。領主の死亡は周到に伏せてな」
「春先ってえと、ラトキエに仕掛ける前ですが」
「そういうことだ。つまり、喧嘩を売ったのは、てめえの野心に突き動かされた秘書官だったというわけさ。だが、ラトキエの逆襲で包囲され、そいつは姿をくらました。で、間抜けにもそこに飛びこんで領民共々取り残されたクレスト領主ダドリーが、踏ん張る羽目になっちまったわけだ。ラトキエの蹂躙を防ぐためにな」
「だったら、その旨説得すれば、総攻撃の回避は可能では? そりゃ主都を急襲されたラトキエにすれば、腹の虫が収まらねえところでしょうが」
「ところがだ。そうは問屋が卸さねえのさ。もっともディールの矢面が、ダドリー=クレストだってのは、アルベールも百も承知だがな」
「──承知の上で、囲んでるってんで?」
あっけにとられて口をつぐみ、訝しげにザイがうかがう。「なんで、そんなに詳しいんで?」
「把握していると言ったろう」
ぐるりと首をギイはまわす。「一報があってな、別の筋から。特務到着の知らせが来る前に」
「──もしや、今のは機密ってんじゃ? 拙かねえスか、俺ら風情に漏らしちまって」
「いいさ。部下をぶん殴らねえでくれたからな」
一瞬ザイは返事に詰まり、脱力したようにうなだれた。
「……俺らを何だと思ってんスか」
窓辺で紫煙をくゆらせて、セレスタンは沈黙を守っている。やはり口を挟まない。
「なら、ついでに訊いちまいますが、一報した相手ってのは?」
「いるだろ、別行動をとってる奴が」
ザイは思案を巡らせるように視線を外し、事情が呑みこめたように目をあげた。「──ああ、あの赤髪の、」
「砕王の部隊の、班長カーシュさ」
アドルファス隊一班を仕切る、剛腕で知られる斬り込み隊長。
クレスト領主に同行し、トラビア門前の待ち伏せで部隊が壊走した後も、あえて領主と居残った──。
「めっきり見ねえと思ったら。そういや、あの人、今どこに?」
「なんでもウェズメルに着いたとか」
「ウェズメルってぇと同盟の? 隣国の東の国境沿いスか。あんな山麓に何の用が」
「ディールの領主をかくまってる」
「たった今、死んだ、と言いやしませんでしたかね」
「言ったな、確かに。だからこそ、逃がす必要があるんじゃねえかよ」
ザイが怪訝そうに口をつぐんだ。
すぐに、ふと目をあげる。「──ああ、つまりはそういうことで。跡取りってわけですか。だが、ディールの領主に嫡男はいない。なら、そいつは隠し子で、跡目を継ぐにはまだ幼い」
「さすがに利口だな、特務の長は。たとえ秘書官の仕業だろうが、国盗りは国盗り、誰かが責任をとらなきゃ収まらねえ。国家転覆を企てた以上 "ディールの領主"は死罪だろうぜ。だが、何も知らねえ跡取りを差し出すわけにもいかねえってんで、カーシュに託して国外へ逃がした。ダドリー=クレストの采配でな」
ま、跡取りの話はこの際いいか、と頭を掻いて仕切り直す。
「要は、ラトキエの総領は、仇敵ディールを背負って立つのがダドリー=クレストだと知っている。もちろん奴が新婚で、政略婚でもねえってこともな。そういう相手を脅すなら、最も効果的な方法は?」
「あの客を盾にする」
「ご名答。そうなりゃ、ダドリーには手も足も出ねえ。総領息子の言いなりだ。憎い仇のその首を虎視眈々と狙っていたラトキエ総領アルベールにしてみりゃ、こいつはまさに無類の僥倖。政敵ディールを軍門に下らせ、憎い仇に制裁を加える、格好の好機というわけだ」
ふと、ギイは目をやった。
「どうかしたか、セレスタン」
何かの匂いを嗅ぐように、セレスタンがいぶかしげに外を見ている。
黒眼鏡の横顔が、意識を凝らすようにしてつぶやいた。「風が、やんだ」
「風?」
とっさに計りかねて目を向けた先、遠くの川面で乱反射する光──。言われてみれば、確かにそうだ。常に吹いていた風がない。
「──まずいな」
意味するところに思い当たり、ギイは小さく舌打ちする。「始まる」
「どういうことで?」
眉をひそめてザイが見た。「もしや、ラトキエの攻撃のことスか。だが、風と何の関係が」
予定が狂って頭を掻きやり、ギイは溜息で背を戻す。
「篭城した相手には、兵糧攻めが定石だが、あのディールの古城には、水も食料もふんだんにある。一方、補給を万全にするには、ただでさえ骨が折れる。となれば、攻撃側は、一刻も早くケリをつけたい。竜巻が消えればラトキエは、直接攻撃に移行する」
「だが、トラビアはいわば要塞ですが」
「正面突破はまず無理だ。坑道掘りも右に同じ。なら、街を囲む防壁を、渡し板で乗り越える。もしくは壁を破壊する」
「つまりは投擲──攻城兵器を投入すると?」
「他に手立てがねえからな。ラトキエが攻略に先立って、ディールの門番や守備兵を買収していりゃ話は別だが、無断でディールに囲まれちまって、そんなに暇じゃなかったろうしよ」
「しかし、高々非戦国の一都市に、そんなに大がかりな攻城兵器がありますかね」
「言えてるな。だが、これは知ってるか。ここカレリアの国軍は、元よりラトキエの管轄だと。だったら、昔の戦の名残りの設計図くらいは見つけたんじゃねえか? 暇なら腐るほどあったんだからよ」
もっとも、実際に組み立てる段となれば、資材と工兵が必要だが。
「要塞の壁に板を渡して、兵を中に乗り込ませるなら、攻城櫓が必要だが、こいつの設置には時間を要する。しかも、防壁以上の高さなら、包囲した現場で組み立てにゃならない。だが、トラビア手前の平原は、」
「近年稀に見る悪天候」
床の灰皿を引き寄せて、長くなった灰をザイは落とす。「なるほど、それでラトキエも、街壁を睨んで包囲したまま、手をこまねいてたってわけですか」
「いかにもあの強風こそが、戦を長引かせた原因だ。だが、寝込みを襲った転覆劇も、寝首を掻けずに終幕だな。どれほど城に蓄えがあろうが、ディールはもう手も足も出ねえ。粘っても援軍はねえからな」
「皮肉なもんスね。少し前にはてめえの方が、ラトキエを包囲してたってのに──」
言いかけた口をふとつぐみ、ザイが怪訝そうに顔をあげた。
「そういや、なんでラトキエは、攻勢に転じることができたんですかね」
「そこだよ」
ギイは真顔で目を返す。
「そいつが今度の戦の肝だ。少し前にはてめえらだって、身動き取れなかったはずなのによ──」
ふと、口をつぐんで、耳を澄ました。
特務の二人も、すでに聞き耳を立てている。足音だった。階段を上がり、廊下を歩き、誰かが部屋にやってくる。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》