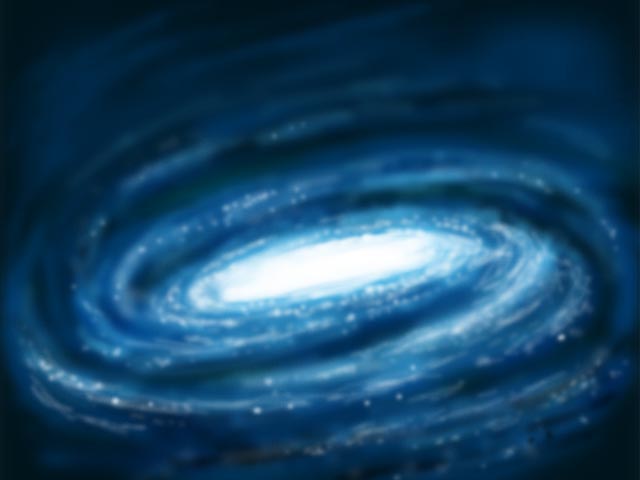
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部3章37
( 前頁 / TOP / 次頁 )
ラトキエ領家の敷地の片隅、木立に囲まれた別棟で、アディーはひっそりと養生していた。
街の高級娼館から、レノさまに気まぐれに引き取られて以来。
伴い、こちらの仕事の持ち場も、母屋から別棟へと転属になった。
アディーはいつもおどおどと、何かに怯えているような極めて大人しい娘だったが、例の事件をきっかけに、あのダドリーとラルッカが、アディーの別棟に入り浸るようになった。次いで、レノさまに熱をあげていた財閥令嬢エルノアも。
それにアディーの主レノさまを加えた六人で、お茶会を開くのが日課になった。
毎日定刻、同じ顔触れで馴染みになって、いつしか異なる身分を越えて、親密な友人同士になっていた。いや、互いが互いの家族以上の、かけがえのない存在に。
だが、周囲を無自覚に惹きつけたアディーは、患者数が極めて少ない黒障病を患って、二年前の寒い春、祈りもむなしく亡くなった。そのはずだった。それなのに──
思考停止に陥って茫然と突っ立った肩下に、アディーが構わず、ぎゅっと抱きつく。
「夢みたいっ! またエレーンさんと会えるなんてっ!」
満面の笑みでスリスリされ、ぎょっと怯んで後ずさる。「ど、どしたのアディー!? あんたが他人に引っ付くとか……」
彼女は決してそういう気安いキャラではない。
アディーが不服そうに顔を見あげた。
「エレーンさん、わかってる? 時は流れて、戻ってこないの。今はこうして一緒にいるけど、この一瞬一瞬にも、どんどん時は過ぎ去って、二度と戻りはしないのよ」
へ? とエレーンは面食らった。
「たまたまこうして会えたけど、またエレーンさんと会えるなんて、わたし、夢にも思わなかったわ」
「……あっ、はい」
気まずく、もそもそ居住まいを正す。
「あんなにみんなと一緒にいたのに一度も言ってなかったから、それでとっても後悔したから、だから今、言っておくね」
破顔一笑、アディーが見つめた。
「あなたのこと、大好きよ」
「……。てか、なんで、そんなにちっこいわけ?」
じっと見つめる真摯な瞳に「うん。それはわかったけども〜」と了解した旨こっくりうなずき、もやもやの原因をようやくぶつけた。
だって、この子はどう見ても、十歳前後のまるっきり"少女"だ。
こちらの肩にも届かぬ背丈。成長途上の細い手足に、子供特有の華奢な骨格。だが、生前、アディーは二十歳前後。
なるほど彼女は子供のような愛らしい顔立ちをしていたし、そこらの路地の悪ガキより、よっぽど素直な性格だったが、けれど、断じて子供じゃない。それに、そもそも、
(……こんなに無邪気だったっけ?)
眉根を寄せて、絶句でたじろぐ。
いつも、おどおど微笑んでいて、間違ってもはしゃいだりしない、まして、説教たれるようなタイプじゃなかった。もっとも時折、妙に生真面目で抜けている、楽天家の顔が覗くことはあったが──そこまで考え、ふと、現状に思いが及んだ。
(そっか。もう、亡くなったから……)
それで柵から解き放たれて、彼女をくるんでいた"怯えの表皮"が剥がれ落ちたということか。つまり、こっちが本来の姿──。
メイド服の鳩尾にすりすり顔をこすりつけていたアディーが、きょとんと我が身を振り返った。
「あっ。わたし縮んでる?」
今さら不具合に気づいたらしく、あれ? と瞬き、首をかしげる。「あ、でも、細かいことはいいじゃない。ちゃんと "わたし"ってわかったでしょう?」
「……。あんたってさ。実はけっこう テキトー よね」
あっさり笑ってやり過ごされて、エレーンは、むぅ、と眉根を寄せる。やっぱり、のびのび、お気楽になってる。もっとずぅっと大人しい、繊細な"お嬢様"とばかり思っていたのに。だから、あのレノさまでさえ──とっかえひっかえ彼女を変える節操のない遊び人でさえ、アディーの別棟に入れたタンスを、ふわっふわの白い服で満タンにしたのではなかったか。まあ、確かに着せたくなるよなふりふりレース。こんなお人形さんみたいに可愛いけれぱ──。
かつての主人の気まぐれの理由を、二年も経った今になってしみじみ合点していると、ぱっとアディーが身を離した。
早く、早く、と手を引っ張る。
「それより早くここから出ないと。ぐずぐずしてたら、エレーンさん溶けちゃう」
「──溶け!?」
ぎょっと引きつって、エレーンはわたわた。「な、ならっ! 出ないとっ! 早くっ!」
「だから、わたし急いでるでしょう? 大丈夫よ、エレーンさん。あの人ならたぶん、出口を知ってる」
「あの人って?」
ふふっと悪戯っぽくアディーが笑う。
「ちょっとかっこいい男の人よ」
──。おお?
「ねねっ。それって、もしかしてケネ──!」
「金髪で巻き毛の」
「……。きっ?」
誰。
アディーは唇に指をあて、彼を思い出すように小首をかしげる。
「知ってると思うのよねー、あの人なら帰り道。あなたのこと捜してたようだし」
だから誰。
「エレーンさん安心して。彼がいれば、出られるから」
その「金髪巻き毛」とやらはどうにも正体不明だが、自信ありげに請け負われたから、ひとまず胸をなでおろす。「よ、よかったあ〜。じゃ、その金髪の巻き毛を、捜せばいいのね、あたしたち。もー、帰れなかったら、どうしようかと……」
はた、と別件を思い出し、あわてて右手の闇をさした。「あ、脱出するなら、あっちの人も!」
「……あっちの人?」
大きな瞳で瞬いて、アディーが驚いたように振り向いた。
「他にも誰か、人がいるの?」
ケネルをさした方向に、眉をしかめて目を凝らす。小首をかしげて見返した。
「どこ? 誰もいないけど」
「やっ。そんな。またまたまたあっ」
エレーンは笑って、ちょいと手を振る。
「そこにいるでしょー、ケネルと子供が。だって、あたし、ついさっき──」
冗談やめてよーと振りかえり、あんぐり口をあけて突っ立った。
──どこ行ったー!?
目を見開いて、あわあわ見まわす。綺麗さっぱり消えている。あの白装束の子供ごと。
「な、な、なんでぇー?」
隠れられる場所なんか一切ないのに。
目を皿にして、きょろきょろ見た。地団太踏んで指をさす。「いや、絶対そこにいたって! なんで、急に消えちゃうわけえ?」
「留まっているものなんて、一つもないのよ、エレーンさん」
……え゛? とたじろいで振り向いた途端、アディーの細い手が手首をつかんだ。
「早く行かなきゃ、さっきの人もいなくなっちゃう」
つかんだ手首を引っ張って、アディーはせかせか歩き出す。「その人は、後で捜してみるから。ここは複雑に入り組んでいるし」
「ところで、なんで、あんたは自由に動けるわけ?」
ずんずん歩く横顔で、事もなげにアディーは応える。
「だって、わたしは思念だもの。ほら、わたし、お屋敷の離れで死んじゃったでしょ?」
けっこう重い話をさらっと流し、焦れたような口ぶりで続ける。
「そんなことより、早くあの人を捜さないと。エレーンさん覚えてないでしょう、どこからここに入ってきたか」
「……や。どこって言われても〜」
むしろ、どこに目印が?
見渡すかぎり一面の闇で、行楽歓迎の道しるべはおろか、昼定食の献立が書かれた看板一つ見当たらない。夜の空を征くがごとくに同じ色合いが果てしなく続き、進んでいるのか曲がっているのか、さっきとどう違うのか、まるでさっぱり見当がつかない。
「ねえ、出られる所って、他にはないの?」
「ないこともないんだけど、入った場所からきちんと出ないと、とんでもない所に出ちゃうから」
「例えば?」
「そうね、原始の森だとか。たぶん虫とか獣しかいない」
「むっ……?」
うっかり密林を思い浮かべた脳裏に、あの黒虫がカサカサよぎり、ぞわりと身震い、総毛立つ。同居は避けたい絶対に。二の腕さすって、えへらと笑った。
「ね、ねえ。今さら訊くのもなんだけど、そもそも、ここって、どこなわけ?」
"出口を知る男の人"を捜索する横顔で、アディーはやはりそわそわ応える。
「ここは 《あわい》 生命の台座。生命が還り、孵る場所。古くなった肉体を粉より細かく分解して、バラバラになった素材を集めて、新しい命を創る場所なの。だから、本来、生きている人が来られる所じゃないんだけど」
「でも、あたし、ここにいるけど?」
「エレーンさんは異例中の異例よ。この 《あわい》 に入れる人は、ものすごく限られているもの」
溜息をつくように言葉を切り、虚空を見やって「それは」と続ける。
三つの境域のいずれかと、かつて契約を交わした "国主"
世の理の外にある、どんな制約も受けない人たち。
そして、その役割柄、状況次第で便宜的に、"国主" に仕える縁の者と、そこから派生した血縁者。
初めの二つは極めて特殊で、世界に数人しかいないのだという。
だから、おそらく、"国主" に仕える縁の者の「血縁」に含まれるだろうとアディーは言う。
「でもー、両親は商都の出だし、うちの家系も平凡な──」
「血筋に具わったものでなければ、どこかで変質したんでしょうね。実際あなたの体には 《あわい》 の気が息づいているもの」
「──またまたっなにそれ。あわいの気とか〜」
「あなたが異物とみなされず、攻撃されずに済んでいるのは、《あわい》 があなたを見つけてないから。でも、それにも限度があるわ。正当な資質をもたない人が、いつまでも、こんな所をうろついていたら──」
「うろついていたら?」
手を引っ張って歩きつつ、言いにくそうに溜息をつく。
「体の端から組織が離れて、次の命の材料になるわ」
エレーンは怯んで己を指さす。「そ、そんな所に、なんで、あたしがっ」
「望んだのはあなたでしょう?」
ちら、とアディーが横目で見た。
「助けようって思わなかった? 誰かのこと」
とっさに返事に詰まった胸に、ずきん、と鈍い痛みが走った。
あの顔が薄くよぎる。ふわりと長い前髪の下、うつむき気味のきれいな横顔。よく知っている相手のはずだ。けれど、誰だかわからない。
焦ってそれに目を凝らすが、そのそばから姿が薄れる。
何を見ようとしていたのかさえ、やがて、すっかりうやむやになり、しばし、呆然と虚無に漂う。
「……でも、」
ひとつエレーンは瞬いて、ふと自分の腕を見た。「でも、あたし、まだ、いるし」
「まだ無事でいられるのは、条件が揃っているからよ。あなたは今 "契約の石"と、資質を偶然持ち合わせている。だから、」
あっ、と小さくつぶやいて、びくり、とアディーが足を止めた。
硬直して立ちつくし、目をみはって凝視している。
ぶつかりそうになったエレーンも「なに急にー」とぶちぶち文句、行く手の闇へと目を向ける。
ぞろり、と何かが横切った。
黒い闇になお黒い、長く尾を引く巨大な影。長い胴は蛇のようだが、それにしてはあまりに巨大で、短い足も生えている。あれは一体──
「……や。こっちに来ないで」
声を震わせたつぶやきで、アディーの足が後ずさった。
驚いて目を戻せば、強ばった顔で目を据えている。どうしたのだろう。
──怯えている?
でも、何に、一体そんなに──ふわり、と髪がひるがえった。
ぱっ、と姿が掻き消える。
「……え?」
エレーンは顔をしかめて目をこすった。忽然と消えた。目の前で。
あわててきょろきょろ見回すが、姿はすでに、どこにもない。
壮大な宙空にぽつねんと、呆然として立ちすくむ。
「まさか、置き去り……?」
絶海の孤島にいるような心細さに襲われる。そろりと周囲を見まわした。
「……も、戻ってくる気は、あるのよね?」
引きつり笑顔で己を励まし、「やだもー、ちょっとぉー。どーしよ、あたしー……」と、肩を落として目を戻す。
「わっ!?」
ぎょっと思わず飛びのいた。
ふっと闇が揺らめいたと思ったら、紅を引いた女の顔が、すぐ目の前にあったからだ。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》