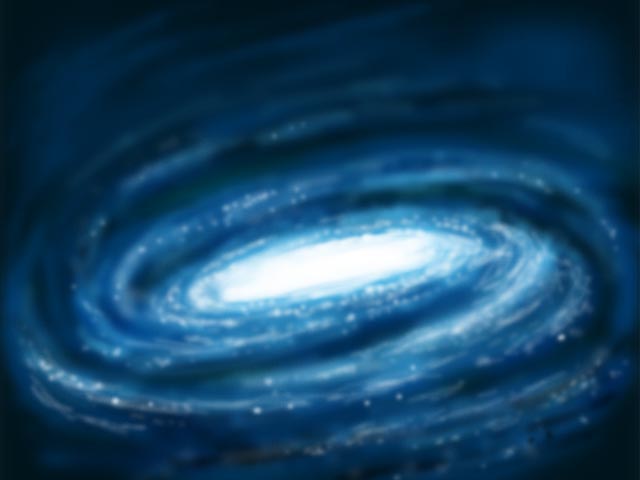
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部3章40
( 前頁 / TOP / 次頁 )
「人魚を食せば、不死身になる」
そんな辺境伝説を聞きつけて、特殊な体質であるらしいケネルの肉を狙っていた。
だが、本職の傭兵には歯が立たず、非力なこちらを人質にして、ケネルを脅そうとつけ狙っていた輩だ。おそらく不治の病・黒障病を、快癒したい一心で。でも──
蓬髪の剣呑な顔を見据えて、ごくり、とエレーンは唾を呑む。
──こんな所まで追いかけてくるとか!?
臍まではだけたシャツの下、赤銅色の痩せぎすの胸で、ギラリ、と不穏に何かが光った。あれは──
じり、と踏み出した蓬髪に気づいて、エレーンはわたわた三歩飛びのく。異様な輝きを放っているのは、確か、戦利品の黒耀石。かつて他人から分捕ったとかいう──。
何はともあれ、長居は無用だ。
ちら、と背後をうかがった。幸いケネルも、どこかにいる。あんなに体が溶けかかっていれば、ちょっと走れば振り切れる。一刻も早く離れようと、くるりと背を向け、地を蹴って──
ばさり、と衝撃が背中を襲った。
そのまま前方に投げ出される。
(……え?)
既視感があった。この衝撃。
息が詰まるこの感じ。肩口から背にかけての、灼けつくような凄まじい痛み。
倒れこんだ先で、恐慌をきたした。
呼吸もままならない激痛に、奥歯をきつく食いしばって耐える。
無慈悲な敵から、ほんの少しでも遠ざかるべく、力の入らない爪先を蹴りやり、辛うじて届く肩先に、震える指を伸ばして押さえる。
その肩を、すかさずジャイルズが踏みつけた。
「おっと。どこへ行こうってんだ、姉ちゃんよォ。会ったばかりだってのに。また消えられちゃ困るんだよ。物置に閉じこめたはずなのに、いつの間にかいなくなりやがって。しかし、思いもしなかったぜ、まさか、こんな抜け道があったとはな」
カカと笑って、勝ち誇って見まわす。「だが、それならお前は知ってるな。出口がどこにあるのかを」
ぐい、と靴裏で踏みにじる。思わず、エレーンは悲鳴をあげる。
「まだだ。まだ、くたばるんじゃねえぞ。きっちり答えてもらわねえとな。さあ、吐け、出口はどこだ」
傷をえぐられる壮絶な痛みに、死に物狂いで靴をつかんだ。
だが、必死に耐えるその間にも、動揺の波紋が、ざわざわ広がる。
(どう、して……)
同じ場所を、また斬られた。
首長に斬られたあの時と。傷の軌跡をなぞったように、寸分違わぬ同じ場所を。
どうあっても動かない "事実"である、というように。
刃を振るのが誰であろうが、斬られることそれ自体は、決定事項というように。
(……あたし、)
胸に冷たく、無残な予感が迫り上がる。
……死ぬの?
誰に看取られることもなく。
それは密かに恐れてきたことではなかったか。
窓ガラスの端が割れ、寒風吹き込む冬の部屋。一人逝ったあの祖父の、侘しい死を知らされて以来。
最も恐れることではなかったか。自分がかつて祖父にした、心無い仕打ちのしっぺ返し。
自分もいつか、あの祖父と、同じ目に遭わされることを。
助けは来ない。
逃げて、隠れて、自らケネルを遠ざけた。
さっきの子供も、あのアディーも、死に瀕したこの現場を、広大な 《 あわい 》 の一点を、探し当てることなどできないだろう。ならば、やはり、自分は一人でこんな所で──。
今にも絶え入りそうに煮えたぎった脳裏に、皮肉の影がつとよぎる。
── ならば、いっそ手間がない。
こと死に関しては、これほどふさわしい場所もあるまい。命が還る再生の場所。一つの命の終着点──。
『 お前も存外、殊勝ではないか 』
声が、まざまざと蘇った。あでやかな黒髪の冷ややかな声が。
『 己が命を返上しに、自ら 《 あわい 》 へ赴こうとは 』
命を砕き、再生する場へ。
汗が、こめかみを滴り落ちた。
浅い吐息だけが耳に届く。
絶望的な結論を、女の声が裏付けていた。
その意味を、不意に知る。
自分の知らない心の奥底、封じてきた自分の意図を。
自分はずっと、これを回避し続けていたのだということを。
それでも結局、こうして 《 あわい 》 に捕らわれた。
あらかじめ決まっていた定めのように。ならば、やはり、これが最期の──
死が目前に迫っていた。
くっきり姿を現していた。
黒々とした胡乱な霧が、どこからともなく現れて、周囲を取り巻き始めていた。
逃れられない 運命のように。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》