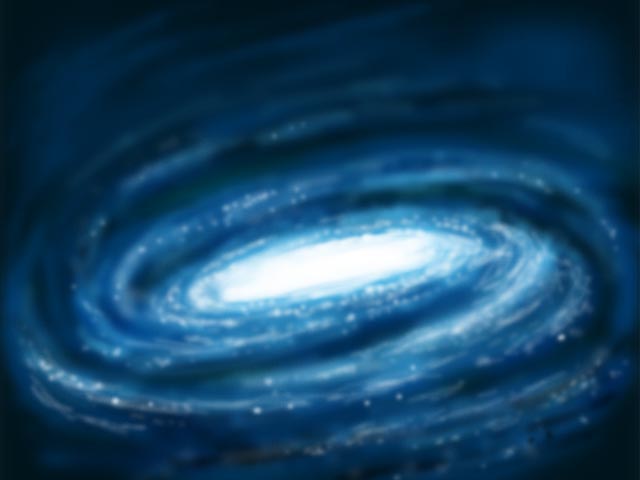
■ CROSS ROAD ディール急襲 第3部3章41
( 前頁 / TOP / 次頁 )
弱々しく悲鳴をあげ、うわごとのようにエレーンは名を呼ぶ。
「ケ、ネル……」
──来て。
うつろになった意識の海で、辛うじて思い描けるのは、もはや彼の顔だけだ。
ジャイルズは声を上ずらせ、狂喜した目を見開いて笑う。
「なんだ、もう降参かァ?」
愉悦に瞳をぎらつかせ、今や完全に興奮している。不思議と気に留める様子はない。今も自身を損ない続け、ぽろぽろ剥がれる精気には。
「どうした。さっさと出口を吐けや」
容赦なく肩を踏みつけて、ぐいぐい靴裏で踏みにじる。激痛に全身を硬直させ、なすすべもなくエレーンはあえぐ。
ふっ、と甚振っていた重みが消えた。
地面に頬をすりつけた、うつ伏せの頭上に、気配が飛びこむ。
ジャイルズに取って代わったその手が、体をゆすり、引きあげた。
「おい! あんた、しっかりしろ!」
この声は……
なんとかこじ開けた瞼の先に、思いがけないその顔を認め、エレーンは怪訝に目を凝らす。ずっと遠くへ歩いて行った。だから、彼を追っていた、なのに──
「……どうして、ここが」
「わからないはずがないだろう。あれだけ強く発光すれば」
怪我人を扱い慣れた手で、ケネルは慎重にうつ伏せに戻す。
「あんたの背中だ。気づいてないのか」
一面広がる闇の中、一点、強い輝きを放った。それを目指して戻ってみれば、この襲撃に出くわした。ちなみに、今この時も、大きく斬られた背中を包んで、萌黄の波がひるがえっている──ケネルの説明を聞きながら、瞼がだんだん重くなる。
「しっかりしろ。あんたは助かる」
片膝ついて覗きこむ彼のシャツを握りしめ、エレーンは(……同じ?)とぼんやり思う。そう、だって、さっきから、同じ流れを繰り返している。
あの夜の領邸広間と。
駆け付けたケネルに励まされる、この状況と今の言葉。そして、同じ軌跡で斬られた背中。あの時は死ぬかと思ったが、意外なことに軽傷で済んで、翌日には、歩いて街道へ行けた──。
痛みが一段和らいだ気がした。
だったら、今度もやり過ごせる。あの時には全快したのだ。今も状況はあの晩と同じで、だから──
「あのふざけた化け物も、中々乙なことをするじゃねえかよ」
射しこんだ一筋の光明を、タガが外れたような哄笑が破った。
尻もちをついたジャイルズだった。こちらを指さし、笑っている。おかしくておかしくて堪らないとでもいうように。顔に降りかかる蓬髪の向こうで、ギラリとその目が不穏に光る。
「"人魚の肉"の兄ちゃんと引き合わせてくれるってんだからよ。まったく人生、何が起こるか、わかりゃしねえ。こんな所に送り込まれて、命運尽きたかと観念すりゃあ、"肉"がのこのこ、てめえの方から出てくるってんだからな。ま、これも運命ってもんだ」
見入った瞳をギラつかせ、這いつくばって近づいてくる。起きあがろうと手をつくが、すぐに、ぐしゃりとくずおれる。どうやら足腰が立たないらしい。
その様は──痩せさらばえた四本の手足は、蜘蛛の肢を思わせた。
精気は今も流出を続け、ひどく動きにくそうに見えるが、それでもジャイルズは浮かれた様子で、崩れかけた体をいそいそ引きずる。
「ついに、ついに、この時が来たか! これでやっと、俺は不死身だ!」
本人に気づいた様子はないが、腕が奇妙な方向に、ねじ曲がってしまっている。
常軌を逸した不気味さに、ケネルが眉をひそめて立ちあがった。
その顔を見据えたジャイルズが、口角泡を飛ばして掴みかかる。
「俺のだ! その肉、俺に寄越せえっ!」
突進した肩が弾かれた。
後ろに高くのけぞった体が、ぐしゃり、とあっけなく地に落ちる。
見れば、賊とこちらとの間に、白く輝く銀の線?
《 やっぱり、ここだ。ここだった 》
鈴を振るような声がした。
白銀の線の左の端だ。小さな人影が立っている。
細い手足に薄い胸。まつ毛の長い素直な顔立ち。覚えがある。あの少年。けれど、なぜ、あの子がここに──。かすむ視界に目を凝らし、エレーンはぼんやり首をかしげる。
「……ヨハン?」
華奢な肩の少年は、全身ほの白く輝いている。
《 印が光ったから、来てみたんだ 》
ぽつんと佇む足元から、うずくまったジャイルズの後ろへ向かい、白銀の線が伸びていく。
右の手前へ跳ね返り、今しがたジャイルズを弾き飛ばした線の先端と交わり、閉じる。
三角形を形成し、軌跡が強く輝いた。その完成を示すように。
その三つの頂点が、輝きを増して盛り上がった。
手前の左の頂きには、すでにヨハンが立っている。他の二点の光塊も、それぞれ子供の輪郭を象る。エレーンは目をみはって、身を起こす。
「どうして、あの子たちが……」
それは意外な顔だった。どちらの子にも見覚えがある。
うずまったジャイルズの向こうにいるのは、遊牧民のキャンプで会った「プリシラ」という女の子だ。ケネルにとても懐いていた。
手前の線の右手には、ケインやヨハンと一緒にいた、同じ仲間のわんぱく坊主。キャンプの人たちの呼び名は「ダイ」
三つの頂点に立っている三人の幼い子供たちは、線の内側に囚われたジャイルズを無言で眺めている。あの少女は盲目だったが、紫に輝くきれいな瞳で、彼女もじっと見つめている。むしろ、結界で捕らえた獲物の動きを封じようとでもいうように。
取り囲まれたジャイルズが、たじろいだ様子で見まわした。「──な、なんだ、てめえら。何をした!」
《 迎えにきたんだ。君のこと 》
「お呼びじゃねえよ、ガキなんざ」
《 だったら、どうして、つけてるの? 》
苛立って吐き捨てたジャイルズの、はだけた胸元をヨハンは指す。そこには、胸にさげた黒曜石。
《 それがあると、苦しいでしょう? 体も痛くなっちゃうし 》
「──仕方ねえだろ。とれねえんだからよ。しけた漁師から分捕って、首にかけたら、このザマよ」
《 初めから決まっていたんだね、君がここへ来ることは 》
何の感情も浮かべない瞳で、ヨハンは抑揚なくジャイルズを見る。
《 その漁師に会ったのも。"竜の爪"をとりあげて、君が首にかけたのも。隊長のことを追いかけて 《あわい》 に入り込んだのも。だって、それがなかったら、ここでは体を保てない 》
「さっきから何をごちゃごちゃと!」
ジャイルズは苛々と舌打ちし、光の結界を指さした。
「こいつをどけて、さっさと出せ! さもないと、てめえら、皆殺しにするぞ!」
《 どうして、そんなひどいことを言うの? ぼくら、君を待っていたのに 》
ダイもプリシラも近くにいるが、二人ともどこか虚ろな目をして、一言も言葉を発さない。胡乱にすごむ凶賊に、ヨハンは怯える様子もない。
《 もう、君は出られないよ。《あわい》に選ばれ、招かれたんだ。だって、ぼくたち、三人そろってしまったから。ぼくらに欠けたピースがないと、君がいないと── 》
──完全になれない。
頂点に佇む三人が、一斉にジャイルズへ手を伸ばした。
あわててジャイルズが後ずさる。「よ、寄るなっ、化け物! 来るんじゃねえ!」
《 ぼくらにちょうだい、"悪い心"を 》
にわかに白銀が輝きを増した。
三角形の結界が、頂点に立つ三人とともに、内に向けて狭まり始める。
さしもの凶賊ジャイルズも、徐々に迫りくる光の檻に、異様な恐怖を感じたらしい。動きの鈍った体を引きずり、逃げ惑うようにして立ちあがる。そうする間にも精気の粒子は、しゅう、しゅう湯気のように噴出し、その全身を覆っていく。
中央に立ったジャイルズに、三人の子供がいよいよ迫る。
逃げ場を失くしたジャイルズの、引きつった顔をヨハンは見あげ、おもむろに手を差し伸べる。
《 さあ。一緒に 《 あわい 》 へ還ろう 》
手を止め、薄い眉を曇らせた。想定外、という顔つきで。
確かに異変が起きていた。湯気の中の黒塊に。その姿が縮んでいくのだ。手足の長い輪郭が縮み、みるみるそれに収束する。
憎々しげな不信の目をした、邪悪な子供が立ち現れた。
「だって──だって、あいつらが!」
ヨハンを睨むその顔が、激情に駆られ、歪んでいく。
「寄ってたかって犯人にしたんだ! ぼくはなんにもしてないのに! 大人も先生もあいつらも、本当は全部知ってたくせに! あの本当の犯人は、
大人しい目をした善良な子供が、わんわん泣いてへたり込んだ。善良を装う者たちの悪意に、その後の人生まで狂わされ。
心の殻に閉じこもり、膝をかかえたその肩に、ヨハンが静かに寄り添った。
《 なら、行かなくっちゃね。復讐しに 》
両手で硬く抱えこんだ膝から、呆けたようにジャイルズが仰ぐ。
《 やっつけに行こう、そいつらを。もう、みんな死んでたら、そいつの子供や孫たちを。そんな悪い連中は、ぼくらの世界に必要ない 》
言葉を失い、エレーンは見入った。
善悪が逆転した瞬間に。
因果の生まれる瞬間に。
過激な会話に立ち会って、だが、いさめる言葉が出てこない。ヨハンの言い分は真っ当だ。無実の相手を脅かせば、やり返されて当たり前。たとえ個人の生涯の枠には、収まりきらない報復であっても。
ジャイルズの胸の黒曜石に、ヨハンはおもむろに目を向ける。
《 とってあげる。苦しいよね? 》
小さなジャイルズは、こくり、とうなずき、素直にヨハンに首を垂れる。
《 "竜の爪"は、どんどん生気を吸い取るから 》
ヨハンはそう言い、向かいのダイに目を向けた。
《 お願い 》
ダイは無言でうなずいて、手首から先のない、左の腕で空を切る。
ボン──とそこに、巨大な手が現れた。
節くれだった男の手、手首で途切れた左手が。
その"手"をダイは操って、徐々に小さく変えていき、うなじの鎖に"指"を伸ばす。
だが、上手くつかめない。
やむなく、その"手"を引きあげた。
たちまち元の大きさに戻り、再び宙に浮いた"手"を、思案するように眺めやり、次々形状を変えていく。小さく柔らかな鼠の手、水かき付きの蛙の手、先端の丸い狐の手、平たい鋤のようなモグラの手、熊の鋭い黒い爪──手あたり次第の試みが、青鳥の鉤爪になった時、ダイはおもむろに変化を止めた。
うなじの鎖へ移動させ、鉤爪の先をひっかける。
プツン、と軽い音がして、ジャイルズのうなじの鎖が切れた。
狭まっていた結界が、刹那、一点に収縮した。
"竜の爪"を弾き飛ばし、ジャイルズと三人を呑み込んで。
直後、爆発的に点が膨張、おびただしい閃光を放つ。
ケネルの身長ほどの直径に、巨大化した球の内部で、どろどろ何かが流動している。
カッ──とまぶしく視界が光った。
周囲が一面、乳白色に輝いて、やがて、橙に染めあがる。
一面ひらけた彼方まで、大地の起伏ができていた。絶句で仰いだ宙空に、薄紅と橙の中間のような、薔薇色の天蓋が広がっている。
はっとエレーンは息を呑んだ。天蓋がある、ということは。地面がある、ということは──。
ざわり、と胸に焦燥がよぎる。《あわい》が閉じた。
──出られない。
ぽっかり浮いた巨大な球は、激しく光を放っている。
それは再び収縮を始め、人の手のひらに載るほどの、つるりとした珠になった。水晶玉のような珠の内に、萌黄の炎を揺らめかせ。
混じり合い、うごめく対流に、ピッ──と縦に筋が入った。
内部が二つに分裂する。
それにも横に筋が入り、内部が四つに分裂し、みるみる八つに分裂していく。それは更に分裂を続け、ぶくぶく内部で泡立っている。
多数の泡を内部にかかえて、ぐつぐつ息づく珠の中、ぐるり、と動く尾が見えた。
頭でっかちで尾がついた、オタマジャクシのような形のモノが、ぐるぐる内部で回っている。その活発な動きに伴い、透明度がぐんぐん増して、殻が薄くなっていく。
ついに殻を突き破り、ぬめり、と飛び跳ねるようにして現れた。
己の尾を追いかけて、オタマジャクシがぐるりと回る。
だが、周回の外へと飛び出した姿は、すでにオタマジャクシのそれではない。大気に切りこむ長い嘴、滑空すべく広げた翼──
薔薇色の天蓋に弧を描き、天蓋を突き破って、姿を消す。
どくん、と 《 あわい 》 が息づいた。
あたり一面、どくん、どくん、と、確かな鼓動を刻み始める。
主が出て行った 《 あわい 》 の虚洞が。
エレーンは愕然と立ちあがった。
天蓋に開いた穴の端が、ぽろぽろ剥がれて落ちてくる。ぐらぐら足場が揺れ動き、方々に亀裂が入り始める。
あたりが崩落を始めていた。
不穏に轟音がとどろいて、地面が砕け、奈落の底へ落ちていく。
成すすべもなく見守る間にも、近くの地面に亀裂が入った。
悲鳴を上げて飛びのくも、辛うじて立てる四辺を残して、周囲の足場が崩れ去る。
あっという間に、ケネルと二人、取り残された。だが、この頼りない命綱でさえ、崩れ去るのは時間の問題。
「い、いよいよかな〜。あたしたち」
あたり一面薔薇色にかがやく、瓦解を始めた滅びの景色を、引きつり笑いでエレーンは見まわす。「もう、これで終わり、とか」
「大丈夫だ。あんたは助かる」
肩を抱きよせたケネルの顔に、ぎこちなく笑みを向ける。
「そっ、そーよね、なんとかなるわよねー。これまでだって、なんとかなったし──あっ、無事に帰れたら、そしたら、どっかで祝杯あげない?」
「……そうだな」
「あたし、いい店知ってるから! あのね、"サムの店"っていうのが商都にあって」
本当は、リナたちとだべっていた 《 ぴんくのリボン 》 が馴染みだが、産気づいた女将の実家へ店主が飛んでいったから、店はしばらく休みだろう。でも、近所にもう一軒いい店がある。
やせ我慢に付き合って「そうだな」とケネルは苦笑う。
「いつか、すっかり片がついたら、"サムの店"で祝杯をあげよう」
茶番の虚しさがこみあげて、エレーンは微笑み、首を振る。「……な〜んてね。ありがと、ケネル。合わせてくれて」
「そんなんじゃない」
「──いいって。もう」
「そうじゃない」
「だから、もういいってば」
溜息でケネルを振り仰ぐ。「もう。なんでいつも、そう頑固に──」
唇が、軽く触れ合った。
ごく間近のその顔に、ぽかんとエレーンは口をあける。今のは軽い悪戯だろうか。でも、そんな悪戯は、このケネルにはそぐわない。
(……ど、どうしちゃったの? 今日のケネルは)
今やガラガラ、あらゆる起伏が崩落し、至るところが流動していた。
どくん、どくん、と鼓動が天蓋に響き渡る。
ケネルは目をそらさない。
間近なその目を見つめ返して、エレーンは静かに目を閉じる。もう、どこにも、
──逃げ場がない。
まさに終末を迎えていた。
滅亡の壮観に呑まれていた。世界が滅ぶかたわらで、
二人の唇が、自然と近づく。
オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》