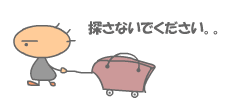「……まあ、雲っていや、雲なんだが」
窓の手すりに腕を置き、ファレスは腑に落ちない顔で首をひねった。
「どうも何か、あるような気がしてならねえんだよな。何かこう、馬鹿でかいもんが」
窓の外の、緑の山なみ、あの西の尾根の上に。
じぃ……っと疑い深く目を凝らす。
「……お?……なんだ、ありゃ」
純白にかがやく真夏の雲が、ぼんやり形をとり始める。
うぐっ、と引きつり、腹をかばった。
辟易と舌打ちで眉をしかめる。「──畜生。ずきずき疼きやがる」
商都で刺された腹の痛みが、不思議と次第にひどくなる。
「まったく何がどうなってんだ。たまに、妙な具合になるしよ」
こんな奇怪な体験は初めてだ。右から左から、上から下から、突き上げを食らうような圧迫感。全身ぐにぐに激流に揉まれるような嫌なうねり。だが、怪我を除けば体調は万全、高熱にうなされているわけでもない。そもそも腹は、負傷であって病ではないから、処置さえ済めば、回復に向かうはずなのに。
「どうだい、具合は」
ふと、声に振り向けば、戸口に女将が立っていた。
どすどす体を左右に揺らし、タオルをかかえて入ってくる。
「馬はどこだ。俺の馬は」
女将はそのまま壁際へ歩き、どさりとタオルを棚に置く。「馬? はて。預かってないねえ」
「……預かって、ねえ?」
不可解な答えに、ファレスはあんぐり口をあけた。いや、確かに馬でこの町まで来た。というのに、これまで乗ってきた馬がいない? そんな馬鹿なことがあるだろうか。馬は勝手に帰りはしない。
いや、まて。
しれっとした顔が脳裏をよぎった。陰謀の匂いをにわかに嗅ぎつけ、ファレスは頬をわななかせる。
「──あいつら、馬を引きあげやがった!?」
あのハゲとキツネの仕業だ。そう「馬がいねえ事件」の真相は一つ。腐っても特務、抜かりない。足止めするなら、後続の手段まできっちり潰す。
と、それはともあれ問題はこの先。西へ行くなら、馬は必須だ。
だが、新たに調達しようにも、こんな半端な規模の町では、部隊の関係者はまずいない。部隊と行動を異にする予測不能な調達班なら、あるいは何がしかの獲物を漁ってうろついているかも知れないが、今ごろどこぞの床下で聞き耳を立てているやも知れぬ輩など、見つけ出すのも至難の業だ。このまま街道を西に進んで、中継地点ノアニールまで行き着けば、区域を担当する鳥師がいるが。
(──どうする)
進むか。戻るか。
この位置ならば、商都の方がまだ近い。だが、商都で調達して出直すとなると、それだけで大幅に時間を食う。ただでさえ出遅れている。これ以上無為に費やすわけには──
「へえ、シャレたものをしてるじゃないか」
西日の寝台に腰かけて、女将が手首を覗きこんだ。「ミサンガかい。なんの願をかけてるんだい?」
「──そんなんじゃねえ」
顔をしかめて舌打ちし、ファレスは寝台に背を投げる。「好きでこんなもん巻いてんじゃねえ。気がついたら、あったんだよ。取っ払って捨てようとすると、なんでか腹が痛みやがるし」
街路で激痛に見舞われた、あまりのタイミングの良さを不審に思い、あの後何度か試してみたが、その拍子に激痛に襲われ、情けなく突っ伏す羽目になった。──はたと合点し、顔をゆがめて、紐を見る。
「……ぜってえ、仕掛けがありやがる」
誰だ。呪いをかけたのは。
「そう悪し様に言うもんじゃないよ」
ひょいと女将が、笑って手首の紐を覗いた。「似合ってるじゃないか、中々あんたに」
憮然とファレスは腕を引く。「そんなことより、服を返せ」
「──服。ああ、あんたのあれね。さてと、どこへやったかねえ」
「"どこへやったかねえ"って、どこへやった!?」
女将は思案げに窓をながめて、そうそう、とうなずき、目を戻した。「そういや、洗い直したんだっけね。ミケがじゃれて泥だらけにしちまってさ」
「……みけ〜っ!?」
皮ひん剥いて楽器にしてやる!?
「まあ、いいじゃないのさ。着るもんはあるだろ」
「着てられっかよ!? こんなピラピラ!?」
純白ふりふりのネグリジェだ。ピンクのリボンが愛くるしい。
「さっさと返せよ。俺はもう出立つんだからよ!」
「何をそんなにあわててるんだか」
女将が呆れた顔つきで、両手を腰に押し当てた。「怪我人は養生するもんだよ」
「のんびりなんかしてられっか! 俺がいねえと、満足に飯も食いやがらねえんだ、あの阿呆のあんぽんたんは!」
「あんぽんたんってなんだい? 新種の飴かい?」
「──飴じゃねえっ! とにかく俺は行くからなっ!」
寝台のかたわらに立っていた女将を、苛立ちまかせに押しのける。
よろり、とその肩がのけぞった。
ぎょっとファレスは目をみはり、たたらを踏んだ肉厚の背中に、あたふた辛くも滑りこむ。
間一髪で膝をつき、むぎゅうぅぅ〜と押しつぶされそうになりつつも、ふるふる両手で押しあげた。「──なっ、なっ、なんで、もっと踏ん張らねえっ!?」
んもう、なんだよ〜、自分が押したくせしてさ、と、女将はごちつつ立ちあがる。
その手をようやく押し戻し、ふと、ファレスは目を止めた。
戸惑いがちに目をそらし、もそもそ寝台に腰をおろす。思いがけない、呆気なさ。
(──そういや、結構な年なんだよな)
額に数筋、白髪の横顔。
ふと、あの光景がよぎった。
気配に身構え、薄目を開けると、ふくよかなあの手が、ふとんを腹にかけ直している。一度きりのことではない。気づけば、いつでも。何度も何度も部屋に来て──
ちり一つない古い板床。
掃除の行き届いた小奇麗な部屋。畳んで積まれた清潔なタオル。食事の量も十分で──確かに客室が三つきりの、ごく小さな宿ではあるが。
「一人で切り盛りしてるのか? 倅に手伝わせりゃいいじゃねえかよ」
この宿の女将には確か息子がいたはずだが、未だに顔を見ていない。いつも、女将一人きり。他には誰も見かけない。
女将は微笑し、投げやりな色を頬に浮かべた。「とうの昔に死んじまったよ」
「──そうか」
とっさにファレスは口ごもり、ばつ悪く窓へ目をそらす。
穏やかに静まった西日の部屋で、女将が身じろぐ気配がする。「……似合うかねえ。あたしにも」
「──あ?」
ぎくり、と身構えるも、反応が遅れた。
もじもじ女将が顔を赤らめ、紐の端をつまんで引っ張る。
「ちょっと、あたしも、してみようかね」
ぎょっ、と目を剥いて振りかえり、あわててファレスは腕を引く。
「──ま、まてっ!? 取るんじゃねええええっ!?」
しゅるり、と手首の紐がほどけた。
「ぐおおおおおっ!?」
腹をかかえて突っ伏した。
怒涛のごとく押し寄せる激痛。
「ばっ、ババア〜……」
苦悶の涙目で顔をゆがめて、ぱちくり見やった女将を見る。
「……だから、やだって……言ってんじゃねえかよ……」
開け放った西の窓から、うららかな陽が射していた。
どんな猛者でも震えあがる向かうところ敵なしの副長ファレス、思わぬ相手に一敗を喫す。